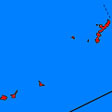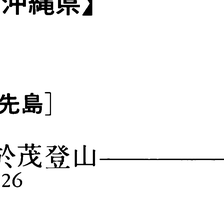精選版 日本国語大辞典 「沖縄」の意味・読み・例文・類語
おき‐なわ ‥なは【沖縄】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「沖縄」の意味・わかりやすい解説
沖縄[県] (おきなわ)
基本情報
面積=2276.15km2(全国44位)
人口(2010)=139万2818人(全国30位)
人口密度(2010)=611.9人/km2(全国9位)
市町村(2011.10)=11市11町19村
県庁所在地=那覇市(人口=31万5954人)
県花=デイコ
県木=リュウキュウマツ
県鳥=ノグチゲラ
日本の最南西に位置し,沖縄島(本島)ほか160の島々からなる島嶼(とうしよ)県で,そのうち40島が有人島,他は無人島である。明治以前の沖縄は琉球国という小独立国で,特に中国からは冊封を受け,臣の礼をつくして貿易を守り,その文物を輸入した。1609年(慶長14)薩摩藩に征服されてからのちも中国との通交は持続し,日中両属の形が続いた。明治政府は琉球と中国との関係を断絶させ,いわゆる琉球処分によって1872年(明治5)琉球国を琉球藩とし,79年藩を廃して沖縄県を設置した。こうして沖縄県は,明治・大正・昭和の県政時代を経て,第2次世界大戦の終了まで存続した。戦後,沖縄県はアメリカ軍の統治下に置かれ,27年間におよぶアメリカの統治後,1972年5月15日,日本への復帰が実現した。なお2000年に〈琉球王国のグスク及び関連遺跡群〉が世界文化遺産に登録されている。
先史時代の沖縄
琉球諸島で現在知られている最古の人類は,那覇市山下町出土の山下洞人で,炭素14法の年代によると約3万2000年前にさかのぼり,具志頭村発見の港川人とともに東アジアにおける確実な洪積世人類として重要な意義をもつといわれる。利器としての確実な石器は未発見だが,鹿角骨を利用した製品は若干検出されている。しかし,シカの長管骨などを利用した,いわゆる叉状骨器はシカ同士による咬傷痕であって,人工品ではないという見解もある。
新石器時代文化は沖縄諸島と先島諸島とでは起源を異にする。沖縄諸島は早・前・中・後の4期に編年される。早期は縄文時代の中期までを一括するが,将来は細分が必要であろう。前期は縄文後期,中期は同じく晩期にほぼ比定される。早期中ごろまでは九州の土器文化の延長にあるが,早期後葉に九州の文化圏から離脱したものと思われ,前期の段階では沖縄独自の土器文化を展開させた。ところで,弥生文化が沖縄に及んだかどうかはまだわかっていない。しかし近年,弥生土器,板状鉄斧,ガラス小玉,箱式石棺墓,炭化米など弥生関係の資料は増加しており,またすぐ北の奄美諸島では弥生前・中期文化の定着したことが確認され,沖縄諸島への波及も十分考えられる。弥生期以降に対比される石器時代終末期の文化が後期で,10世紀ころまで存続する。その次は〈ぐすく〉時代で,〈ぐすく〉の性格についてはいまだ定説がなく,初期のものについては支配者居城説,葬所説,高地性集落説などがある。終末は15世紀ころといわれる。
南の先島諸島の土器文化は南方起源といわれているが,系譜の確認は今後の課題である。南端の八重山では先史~歴史時代を4期に編年する。第1・2期が先史時代で,打製・磨製石器文化で始まる。第2期に土器出現,炭素14法によると約3000年前である。第3期は外耳土器の時代で〈ぐすく〉時代に対比され,第4期はパナリ焼の時期である。宮古列島はすべて新しく,八重山の第3期以降の遺跡である。
執筆者:高宮 廣衞
風土と産業
沖縄県の自然は本土と大きく相違し,亜熱帯風土の特色を有している。県域は,九州南端から台湾にいたる海域に飛石のように連なる南西諸島のうち,北部の薩南諸島(大隅諸島,奄美諸島)を除いた琉球諸島,すなわち沖縄諸島,先島諸島(八重山列島,宮古列島),尖閣諸島と琉球海溝をへだてて大東諸島などの島々から構成される。琉球弧(琉球諸島)の地体構造は,次のように分けられる(1965,小西健二)。琉球地背斜区(沖縄島,宮古島,石垣島,西表(いりおもて)島の脊梁山地)の新第三系の基盤岩類は,東シナ海側から太平洋側に向かって,(1)石垣帯(古生代のトムル層と琉球火山帯が重なる),(2)本部(もとぶ)帯(古生代の本部層,与那嶺層),(3)国頭(くにがみ)帯(中生代の名護層,嘉陽層),(4)島尻帯(第三紀層)が,古いものから新しいものへと雁行状に配列する。そのうち沖縄県の面積の過半を占め,県の政治,経済,文化の中心をなす沖縄島は北東から南西にのびる細長い島で,北端の辺戸(へど)岬から南端の荒崎までおよそ120kmである。沖縄島の石川・仲泊地峡を境に,以北は山岳の多い地域で,島軸の脊梁山地は標高300~500mの山地が島状に連続し,そのまわりに台地(海岸段丘)が広く発達する。最高点の与那覇岳(503m)から南下するにつれて高さを減じ,山地南端の読谷山(よみたんざん)岳(236m)に達する。地峡以南の中・南部地域は第三紀層島尻層の泥岩を基盤に,上部を琉球石灰岩が被覆し,丘陵・低地の波浪状の地形やカルスト台地の地形などの特徴がある。また海岸は裾礁,堡礁などサンゴ礁地形がみられ,サンゴ礁独特の青い海,白い砂浜,強烈な陽光はいかにも南国的である。
亜熱帯海洋性気候に属する沖縄県は東アジア季節風の影響を受けるが,全体としては長い夏と短い冬型の季節が特徴で,四季の変化は明確でなく,降雪はまったくない。5月下旬から6月下旬の梅雨期に最も雨が多く,夏には台風が数回襲来する。台風はしばしば猛烈な暴風雨を伴い,農作物などに大被害を与えることがある。また多くの離島からなるため,古くから離島苦(島チャビ)をかかえて,つねに自活の道を歩まねばならなかった。この島嶼性,離島性と本土を遠く離れた隔絶的な環境は,沖縄の地域性に大きな影響をおよぼし,独自の歴史・文化を生み出す要因となった。
第2次大戦前は農業県で,産業構造上農牧業の占める比重は高く,農家率は73%(1940)を占めていたが,戦後はアメリカ軍基地の恒久化に伴って農業の地位と特色が変容した。復帰後かなりの経済成長率を示し,1人当りの県民所得は1986年に全国平均の75.7%にまで格差が縮まったが,その後は低下し,94年には全国平均の71%となっている。沖縄県の総生産の割合(1994)を産業別にみると,第1次産業3%,第2次産業21%,第3次産業76%で,全国と比較すると第3次産業に特化している。94年の農業粗生産額の総額は1009億円で,その構成は,耕種部門ではサトウキビ19%,野菜17%,花卉16%,果実4%,葉タバコ4%,いも2%,米1%,その他2%,畜産部門では豚16%,肉用牛8%,鶏6%,乳用牛5%,その他畜産1%となっている。耕種と畜産の比率は65:35で,耕種農業を主として畜産を加味した経営となっている。原料農産物に比べて,米・いもはわずかに18億円に過ぎず,稲作はまったく不振である。全体として,基幹作物であるサトウキビから花卉や畜産への転換が図られている。
沖縄の糖業は1623年(元和9)儀間真常が製糖を試み,その成功以来のことである。およそ350年余の歴史的背景をもつ糖業の沖縄経済上に占める地位は高いものがある。戦前は移出額の65%内外が砂糖で,また戦後の1953年の総輸出額の36%が砂糖であった。しだいにその比重は低下傾向にある。戦前の砂糖生産は分蜜糖(ざらめ糖)に比べて含蜜糖(黒糖)が29:71の割合(1938年期)で多かった。戦後は農家はサトウキビ栽培だけを行い,県全体で101万3000t(1995),全国の62%を産し,製糖は工場で行うという分離方式をとっているため,分蜜糖が圧倒的に多く,95%を占めている。県下の大型工場11社では分蜜糖,小型工場7社では含蜜糖を生産している。その他昭和初期に栽培が始められたパイナップルは戦後沖縄の復興産業と位置づけられ,おもに沖縄北部と石垣島で栽培が盛んであったが,年々減少している。これに代わり急激に生産量を増加してきた花卉は,主として沖縄島各地で盛んに行われるようになってきた。また,肉用牛を中心とする畜産も盛んになってきた。伝統的な特産品工業の泡盛,紅型(びんがた),陶器,漆器などは首里,那覇に生産地がある。南風原(はえばる)町の絣,大宜味(おおぎみ)村の芭蕉布,久米島のつむぎ,宮古・八重山の上布などは特産品である。
27年間にわたるアメリカ統治の影響は,沖縄の政治,経済,社会など各面におよんでいる。1950年ころから始まったアメリカ軍の基地恒久化に伴って,莫大な予算を投じて築きあげた軍事基地の存在は,直接・間接に沖縄経済に結びついている。96年のアメリカ軍基地面積は2万4306haで,全県の10.7%を占めている。とくに沖縄島北部,中部,それに伊江島において広大な面積を占めている。〈沖縄に基地があるのではなく,基地の中に沖縄がある〉と誇張されるように,軍事基地の存在は,基地と政治,基地と経済,基地と生活というように,基地の周辺地域に大きな影響をおよぼしている。したがって基地密度の高い沖縄島中・南部の基地周辺地域に,顕著な地域的変容がみられる。那覇市の過密化や,中部の都市化が進み,石川市(1945),宜野湾市(1962),具志川市(1968),浦添市(1970),沖縄市(1974)が成立した(2005年合併により石川,具志川両市はうるま市となる)。これらの都市は程度の差こそあれ,いずれも基地の存在と無関係ではなく,卸売業,小売業,サービス業などを中心とした消費的性格の強い基地的都市を出現させている。沖縄島には戦前,那覇から与那原(よなばる),嘉手納,糸満,那覇港へ沖縄県営鉄道(1914創業,全延長48.03km)が通じていたが,沖縄戦で破壊された。以後全国で唯一,鉄道をもたない県となり,自動車交通の発達が著しいが,交通渋滞など交通問題は深刻化している。その対策として,道路の立体化などの整備を進める一方,2003年沖縄都市モノレールの那覇空港~首里間が開通。沖縄自動車道は1975年に名護市の許田インターチェンジと石川市(現,うるま市)の石川インターチェンジの間が国道329号沖縄自動車道として開通。87年石川インターチェンジから那覇インターチェンジまでが開通し,高速自動車国道に編入された。沖縄島を中心に他の主要な島々へは海上交通が発達するが,航空路も発達していて,那覇空港(1933開設)から宮古,石垣,粟国,南大東,久米などの各島へは航空路が通じる。また東京,大阪,神戸,福岡,鹿児島などへは定期航路,東京,名古屋,大阪,福岡,鹿児島などへは定期航空路が通じる。香港,台北,ソウルなどへの国際線の定期航空路もある。
沖縄島北部,中南部,先島
ここでは沖縄県域のうち自然や人文環境の相違により,石川地峡を境にして沖縄島の北部と中南部,それに先島の3地域について述べる。
(1)沖縄島北部 名護市と国頭郡の範囲で,山岳地形をなすことから山原(やんばる)の呼称がある。緑の山地を背景にしたサンゴ礁の海岸は美しく,恩納(おんな)から辺戸岬までの海岸は沖縄海岸国定公園に指定された。また海洋博記念公園をはじめ真栄田(まえだ)岬,万座毛(まんざもう),辺戸岬,海水浴場のあるビーチなど,名勝地,行楽地が多い。名護市は北部の中心都市である。
(2)沖縄島中南部 石川地峡以南の範囲で,県人口の80%がこの地域に集中しており,都市地域を形成している。那覇市は表玄関として歴史的に栄え,1881年首里にかわって県庁所在地となり,名実ともに沖縄県の主都となった。これに比べて歴史都市の首里は首里城跡(史)付近に県立芸術大学,守礼門(県史跡),園比屋武御嶽(そのひやんうたき)石門(重要文化財),玉陵(たまうどん)(史)などの集まる閑静な文教住宅地に変わった。南部の糸満市は漁業の町として知られ,沖縄戦最後の激戦地となった摩文仁(まぶに)岳一帯は沖縄戦跡国定公園となっている。
(3)先島 宮古島市,石垣市,宮古郡,八重山郡の範囲である。宮古列島は宮古島など八つの島嶼からなる。宮古島は全島琉球石灰岩で被覆され,平たんな地形で,太平山(島)とも呼ばれた。サトウキビ単一栽培の砂糖の島であったが,復帰後から園芸農業が盛んになった。宮古漁民の南方漁場への進出は目覚ましい。宮古上布,サンゴの加工は特産。宮古島の旧平良(ひらら)市が中心都市である。八重山列島は石垣島,西表島など19の島嶼からなる。石垣島は,中央部に沖縄県で最も高い於茂登(おもと)山(526m)がそびえ,山々が連なる。山地に続く緩斜面の台地,沃野は広く未開地もあり,人口密度は低い。かつてはマラリア地帯もあったが,今はない。八重山は詩の国,歌の国といわれ,島々には古謡があり,民謡も豊富で,伝統的な祭り行事を保存している。西表(いりおもて)島は沖縄県第2の面積をもつ島であるが,全般的に山がちで低地が乏しく,熱帯・亜熱帯の原生林が繁茂し,秘境を残している。イリオモテヤマネコ,カンムリワシ,セマルハコガメなど国指定の天然記念物がある。西表島と周辺海域は西表国立公園(2007年石垣島などとともに西表石垣国立公園となる)に指定されている。
執筆者:田里 友哲
近代の歴史
人頭税廃止運動
ここでは琉球処分(1872-81)以後について述べる。それ以前については〈琉球〉の項を参照されたい。
明治前期における琉球処分の政治過程は,明治政権の中央集権体制の完成を期す連続的な事業であった。それが10年という期間にわたっていることは,国内の政治状況が流動的であり,日清の国際環境が緊張していたことに大きく規定されている。琉球処分の直後から,明治政府は清国の国内の通商権と引換えに宮古・八重山を割譲するという内容の秘密外交交渉(改約分島交渉)を進めていた。初期明治政権が日本民族の独立確保を重要な課題として,欧米諸国に対等に伍そうとする外交政策は,国権を確立しその伸張をはかることにあった。それゆえに,条約改正の先鞭として開始した改約分島交渉は,内容的に琉球処分における統合を否定するものであった。この交渉は〈琉球分割条約〉まで構想したが,その後,清国はロシアとの対立抗争を解消することに成功したので,必ずしも日本との対立を解決せねばならぬという緊急性を失い,分割条約案は流産することになる。また明治政府は,沖縄県を設置しても,すべての諸制度を統合化,一体化する施策をとらなかった。むしろ沖縄の旧支配層を懐柔し,脱清行為を鎮めるために,旧慣を存置する政策がとられた。そのため土地制度,租税制度,地方制度などの改革は大きく遅れることとなる。と同時に当時の日本政府は,自由民権運動の高揚の対応に全力を注ぎ,沖縄に深く関わるだけの余力をもっていなかった。
日本政府の旧慣存置の政策によって,沖縄社会はその発展を抑制された。当時の農民は巨額の負債を背負いこんで疲弊しきっており,まったく返済のあてもなかった。《上杉県令巡回日誌》(1881-82)は農民の貧困と悲惨な現実にふれ,県政改革を模索しはじめている。上杉茂憲は県庁役人の人員整理・縮小による財政再建をはかり政府に建白したが,政府は拒否して上杉改革案を葬り去った。先島の農民の場合は,もっと緊迫していた。それは人頭税制に直接的に苦しめられていたからである。琉球政府の収入を一定ならしめるためとも,他の地への移住を禁止するためにともいわれている人頭税は宮古・八重山で典型的に見られ,反布で上納されていた。宮古の人頭税撤廃に立ち上がった農民を支援したのは,製糖指導員城間(ぐすくま)正安と新潟県人中村十作である。2人は人頭税の納期に縊死や身投げが続発するのをみて農民に同情し,運動に尽力することになった。農民は宮古島役所長に対し人頭税の廃止を要求したが,役所長および県当局は要求を認めようとはしなかった。農民は政府との直接交渉を決意し,平良真牛,西里蒲を代表に選んで上京させた。1893年11月に〈沖縄県宮古島島費軽減及島政改革請願書〉を提出し,翌年には内務省に県政改革建議書を提出した。この運動を契機に政府の旧慣存置の政策の再検討が行われ,人頭税は1903年沖縄県土地整理法の施行によって廃止された。
沖縄自由民権
明治10年代の自由民権運動の基本綱領は,国会開設(国家構想),地租軽減,条約改正であった。明治30年代の謝花(じやはな)昇とその同志によって推進された県政改革運動は,特に〈沖縄の自由民権運動〉と位置づけられ,評価されてきた。謝花昇の運動と本土の自由民権とは,当然のことながら内容,質的に差違がある。後者が国会開設をめぐって抗争していることに対し,前者は形式的には開設された国会に代表者を参加させるという要望をしている。これは歴史的落差の顕著な例であろう。当時の沖縄県知事は鹿児島出身の奈良原繁で,彼は士族の救済対策として杣山(そまやま)の開墾事業に着手し,尚家一族や鹿児島商人,上級官僚らに開墾を許可した。開墾事務にたずさわっていた謝花は開墾予定地を視察し,農民の反対の声に接して奈良原知事と対立する。入会地の一方的払下げは,農民の生活を根底から破壊するのも同然であった。謝花は上京し,〈杣山慣行取調書及び其官民有利陳述書〉を議会に提出した。また田中正造,星亨,高木正年らの協力を得て奈良原の暴政を指摘し,その更迭を訴えた。謝花らの運動原理の中には,沖縄のかかえる課題を,市民的自由という政治参加の方式を通じて地域住民の意思を広く国会の場に反映させ,国民的課題として解決をはかることこそが重要であるとの立場があった。したがって,参政権の必要性は最も重大な政治課題になりえたのである。謝花は同志とともに沖縄俱楽部という政治・学習結社を作り,政治宣伝のために機関誌《沖縄時論》(1899-1902)を創刊した。しかし奈良原ら反対派の激しい攻撃で運動は挫折して同志は離散し,謝花もついには発狂した。県民が参政権を獲得して形式的に国政に代表を送ったのは,帝国議会が開設されて22年目の1912年であり,それも宮古・八重山を除く差別的な制度であった。
奈良原県政の1899年から1903年にかけて,〈土地整理〉が実施された。これは沖縄社会の一大変革で,古琉球以来つづいた地割制度が廃止され,土地の私的所有権が認められた。かくして村落共同体社会の秩序は,上から資本制的社会に改変させられていった。土地整理の意義は,土地の私的所有権が確定したことで,租税が間切(まぎり)や村に課されていたのが,所有者個人に課されるようになる。したがって行政全般が本土と一体となり,諸制度(徴兵,選挙)の実施が可能となった。それ以後政府は,県庁や公教育機関を通じて国策の浸透をはかり,より一層の本土との一体化を積極的に推進した。これに迎合する風潮も見られたが,啓蒙思想家伊波普猷(いはふゆう)のように,沖縄の歴史的地域的個性を主張して,政府の一方的な政策に抵抗したものもいた。この文化運動はのちに沖縄学と称され,大きく発展した。今日の沖縄研究の基礎は,この時に構築されたものである。
ソテツ地獄
明治・大正の沖縄で,唯一の換金作物は黒糖であり,その生産と価格は沖縄経済全体に大きな影響を与えていた。60万人ほどの人口のほとんどが農業生産に従事しており,農業経営の規模も1戸当り平均耕地面積が約7反,5反未満農家が全体の半数以上を占めていた。しかも農家戸数全体の6割以上がサトウキビ栽培に従事する零細農業県で,高い租税の支払にはサトウキビ作以外に換金作物を見いだすことができなかった。またサトウキビ作面積の増大は自給食糧であるサツマイモの栽培面積を縮小させ,同時に水田をも畑に変えていき,主食糧を他に依存する形態をとるようになる。この生産構造は第1次大戦後の不景気をまともに受けて,県民の生活を恐慌の中におとしいれた。1920年黒糖は那覇相場で10斤につき24円であったが,翌年には12円台と大暴落し,26年には9円台に落ちこみ,以後8~9円台を低迷した。もともと貧困な県民生活はこの恐慌によりいっそう窮迫し,三度の食事のうち1回は,野生のソテツの実や幹を食べたという。しかしソテツには有毒成分サイカシンが含まれているので製法を誤ると中毒し,そのために死者がでるというありさまだった。それはまさにソテツ地獄と呼ばれる状況であった。そこで貧農だけでなく中農層の子弟も身売りに出された。
沖縄県の海外移民は,〈謝花民権〉の挫折後に始まり,しだいに激増した。1907年の対米移民禁止後ハワイへの移民は減少した。不況の時代に入って多くの人が,北アメリカ,南アメリカ,フィリピン,南洋諸島に出かけた(特に農村地域からの流出が大きい)。実際には,不況で農村の〈口べらし〉のために移民となり,故郷をはなれた人たちではあったが,彼らは苦労して稼ぎためた金を実家に送った。不況の県下に有効な救済策もなく,海外からの送金は県経済を大きく支えていた。移民に出ない者は,安い労働力として県外に流出していった。
戦時体制下の沖縄
第1次大戦終了後の恐慌と不況の影響を受けた沖縄社会の疲弊ぶりは,実に深刻であった。その救済対策としてにわかに浮上した沖縄県振興計画(1932)は,産業基盤の整備・拡充を基本的な柱とし,産業各分野における生産力の増強をはかるというものであった。しかし振興計画策がようやく軌道にのりはじめたころに,戦時体制へと没入していくことになる。この間の沖縄社会の動向を象徴的に示す史料に沖縄連隊区司令部の報告書《沖縄防備対策》(1934)がある。報告書は国防の観点から,沖縄社会の性格をこう分析している。(1)憂いの最大は県民の事大思想である。(2)依頼心が強く他力本願である。(3)一般に惰弱の気風がある。(4)古来任俠の伝統がなく,団結,犠牲の美風に乏しい。(5)武装の点でほとんど無力である。青年訓練所,在郷軍人においてすら銃器を有せず,有事の際の郷土防衛はきわめて困難。以上の軍の対沖縄観には,沖縄に対する不信と偏見,差別意識が表出している。こうした認識を基盤にして具体的な施策が政府と軍の指導の下で,国防教育,愛国運動として精力的に展開されていくことになった。これは沖縄県民を自発的・自主的に戦争体制に協力させ,ひいては動員および調達していくことを目的としていた。政府は1937年〈国民的思想動員運動〉を策定し,さらに〈国民精神総動員計画実施要綱〉を発表した。〈挙国一致,尽忠報国,堅忍持久〉のスローガンのもとに,言論,思想の弾圧,国民統制の強化がはかられ,しだいに県民生活の細部に干渉し,物理的強制力を発動していった(国民精神総動員運動)。特に標準語使用,方言撲滅の運動は,方言の使用をスパイ行為とみなし,戦争中には軍の指令でスパイ嫌疑として虐殺している。地方文化を無視した防諜取締りのきびしい一面である。また38年4月には国家総動員法が公布され,同法にもとづいて〈長期持久戦時体制の確立〉をはかるため,(1)物価統制,(2)消費節約,(3)輸出振興,(4)廃品回収,(5)貯蓄徹底,(6)生活簡素化などの方策が掲げられ,〈沖縄県振興計画〉ももはや例外を許されなくなった(国家総動員)。
太平洋戦争開戦を画期として,戦時色は沖縄県下をぬりつぶし,大政翼賛会が決定した〈必勝生活訓〉が県民のスローガンになっていく。(1)強くあれ,必勝の信念をもって職域を守れ,(2)家庭も戦陣,生活を挙げて御奉公の誠をつくせ,(3)国土防衛は協力一致,隣組の力で持場を固めよ,(4)流言に惑うな,当局の指示を信頼して行動せよ,(5)国運を賭しての戦だ,沈着平静最後までがんばれ,と。新聞も一県一紙の方針のもとに,1940年《琉球新報》《沖縄朝日新聞》《沖縄日報》の3紙が統合して《沖縄新報》のみとなった。検閲もきびしく,自主性は失われ,政府や軍部の代弁機関となった新聞からは,真実を聞かされることはまったくなくなってしまった。情報回路は上意下達の回覧板にゆだねられ,民衆を相互に監視する隣組組織が強められた。民衆の意識は戦争に協力する画一的な様相をますますこくしていった。このような状況下で45年3月,太平洋戦争最後の戦闘であり,日本国内で唯一の地上戦である沖縄戦が沖縄島ならびに周辺諸島で展開された。
→沖縄戦
日本復帰運動
数ヵ月間にわたる日米両軍の戦闘の結果,約20万人の死者を出し,焦土と化した戦後沖縄の出発は,すでに苦難を背負っていた。戦災で生活基盤のすべてを徹底的に破壊された住民は各地の収容所に幽閉され,居住地に帰ることすら禁止された(1945年10月29日以降原住地への帰村は許されたが,原住地がアメリカ軍に接収されたままいまだに帰れない住民もいる)。戦場となった農耕地も軍事施設としてアメリカ軍に囲いこまれた。中華人民共和国の成立(1949)後,アメリカ軍の土地政策は土地接収の方向に転換した。朝鮮戦争の勃発でアメリカ軍は沖縄基地の重要性を認識し,基地機能を集中化した。そして1952年4月28日の対日平和条約の発効によって,法的にも沖縄は日本より分断され,沖縄基地はアメリカ軍における極東の軍事的かなめ石となった。アメリカによる統治は当初,陸・海軍の軍政府(米軍政府)によってなされていたが,1950年12月5日の〈琉球列島米国民政府に関する指令〉で,アメリカ政府の出先機関である米国民政府United States Civil Administration of the Ryukyu Islands(略称USCAR)が設置された。この結果,沖縄の統治は司法,立法,行政の全般にわたって,琉球列島米国民政長官の指揮下で行われた。また52年4月1日には,米国民政府布告〈琉球政府の設立〉に基づいて,沖縄住民側の中央政府としての琉球政府Government of the Ryukyu Islandsが,米国民政府のもとに設立された。その機構は,行政主席官房,行政主席情報局,総務局,警察局など1房13局81課3委員会(人事委員会,中央選挙委員会,中央教育委員会)よりなっていた(同年9月,奄美,宮古,八重山に各々地方庁が置かれた)。琉球政府は〈琉球における政治の全権を行うことができる〉との権限をもってはいたが,あくまでも米国民政府の指揮下においてであった。しかし三権分立,司法権の行使など,国家的作用もある程度認められていた。
対日講和の構想が明らかにされるころから,沖縄では日本復帰運動の組織的活動が開始される。1951年4月,沖縄社会大衆党(社大党,1950年10月結党),沖縄人民党(人民党,1947年7月結党)を中心に〈日本復帰促進期成会〉が初の超党派的復帰運動体として結成された。50年代の沖縄の民衆運動は軍用地問題をめぐる島ぐるみ闘争に象徴されるが,その爆発的契機となったのは,56年6月のプライス勧告である。アメリカ軍の土地強制接収に対抗するため,琉球立法院は(1)一括払い反対,(2)適正補償,(3)損害賠償,(4)新規収集反対の四原則を決議していたが,勧告はこれを否定するものであった。運動組織は強化され,四者協議会(琉球政府,立法院,市町村長会,軍用土地連合会により1954年4月に結成)による,島ぐるみの土地闘争は爆発的高揚を示した。四者協の闘争方針や四原則をささえた思想の根底には,生活権の擁護(デモクラシー),領土主権の防衛(ナショナリズム)が流れており,土地闘争で提起された課題は復帰運動に引きつがれる。復帰運動は三つの要素からなっており,(1)異民族支配からの脱却(復帰),(2)民主主義の確立(人権と自治),(3)戦争反対,平和の擁護(反戦・平和)である。これは沖縄民衆の占領支配に対する権利要求の集約的表現となっている。60年4月28日,沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)が結成され,運動の母体となり,復帰協に参加した各種の団体は対日講和条約の発効した4月28日を〈屈辱の日〉として,この日を中心に統一と団結のスローガンの下に統一戦線的性格を堅持し,運動を深化させていった。
復帰運動の理念は日本国憲法の民主主義と平和主義の精神を異民族支配下の特殊政治状況の中で実現化するところにあり,それは復帰協に結集する沖縄民衆の闘争の蓄積によって支えられていた。68年には屋良朝苗を初の公選主席に当選させるほどに運動は高揚し,72年5月15日の施政権返還というかたちで,日米両政府間における沖縄返還が歴史的事実となったのである。しかし,その時点でアメリカ軍基地の存続が認められ,一部自衛隊の使用に供されて,軍事基地の問題は未解決のまま残されたために,沖縄戦を思いおこし,戦争への危機感をうえつけている(この点を歴史的に第三の琉球処分と評価する視点もある)。一方,異民族支配下の政治風土である住民自治の制約,基本的人権の抑圧などは大きく変貌をとげた。復帰実現は沖縄県民に多くの夢を与えたが,その反面,本土との系列化の進行,急激な開発による自然破壊をもたらした。しかし,県民に日本国民としての精神的な余裕を与えた点は大きな変化であろう。
返還・復帰後の沖縄
沖縄の人々は,日本国憲法の下での人権も,参政権も,米軍基地の存在も〈本土並みに〉保障されることを祈願して,〈島ぐるみの〉祖国復帰運動をくりひろげ,1972年に復帰を実現させ,国政に参加することができたが,日本・アメリカ両政府の沖縄政策は,日米軍事協力の強化を目的にした沖縄返還でしかなかったことが,復帰後にますますはっきりしてきたといえよう。復帰後の沖縄県知事は,革新・保守から屋良朝苗(1972-76),平良幸市(1976-78),西銘順治(1978-90),大田昌秀(1990-98),稲嶺惠一(1998-2006)等が選出されて行政を担当し,政府とわたりあってきた。
1972年の本土復帰当時,沖縄の米軍基地は287km2,87施設であったが,四半世紀後の96年には243km2,47施設である(2001年には237.53km2,38施設)。日本全土の米軍基地314km2の実に4分の3を沖縄が占め,しかも沖縄本島に集中しており,本島面積の約18%に及ぶ。基地の存在の〈本土並み〉縮小という切実な願いは,完全に裏切られた。
日本政府は,アメリカ合衆国との間で日米安全保障条約を結んでおり,その目的はアメリカと日本との相互の安全とアジアの平和維持だとされている。この条約によって日本はアメリカに基地を提供する約束をしたのであるが,沖縄の米軍基地は,日本の安全を守るためにアメリカに提供しているのだから大幅に縮小することはできないと,日本政府は主張しつづけてきた。
沖縄の人々の反発を抑えるために,政府は復帰後に軍用地使用料を6倍に引き上げ,基地所在市町村には基地周辺整備事業費を交付してきた。また,復帰の年の12月から政府は3次にわたり沖縄振興計画を実施し,沖縄と本土の格差是正をはかり,自立的な発展の基盤をつくるべく港湾,空港,道路,下水道,学校校舎等の整備を行った。しかし,それら沖縄の人々への〈懐柔策〉ともとれる政策は,沖縄の経済を公共投資依存型の構造を強める方向に押しやってきた。
本土では米軍基地の9割が国有地であるが,沖縄では基地面積の7割弱を民有地が占める。沖縄の人々の多くは,これ以上自分たちの土地を基地に提供することはできないと,拒否する立場をとっており,とくに〈反戦地主〉たちはその前面に立っている。1990年に革新系の大田知事が登場し,基地の整理・縮小を掲げて日米の政府と交渉を進めてきたが,その間95年9月に起きた米兵による少女暴行事件は沖縄県民の怒りを爆発させ,基地縮小の要求が拡大した。95年11月に日米政府は〈沖縄基地特別行動委員会(SACO)〉を設置して基地の整理・統合計画を検討し,96年12月には普天間など一部の基地返還に伴う代替へリポート建設などの報告を出した。また96年9月〈基地の整理・縮小,日米地位協定の見直し〉に関する県民投票では投票率約6割のうち,賛成が9割近くを占めた。次いで97年には,同年5月で契約期限切れとなる嘉手納など12施設の扱いをめぐり,政府は沖縄県の意向を押し切って〈駐留軍用地特別措置法〉を改正し,暫定使用を可能とした。
政府は,安保体制に協力する沖縄に対して,その引替え条件に地域振興策としての国際都市構想の実現を約しているが,その実態は明確でなく,沖縄の人々の支持を取り付けているとはいいがたい。97年末,代替へリポート建設をめぐり沖縄本島北部の名護市で行われた住民投票で,地元世論を二分したうえで反対派が上回った事態は象徴的であろう。基地問題の解決を地方交付金の空中散布的な配分方式,大型予算の投入等で図る政府の態度は,かつてのアメリカ軍政といかほどの差異があるであろうか。
こうした新しい状況の中で,戦後沖縄に重くのしかかってきた日米安全保障条約体制を見直す運動(人権,平和,自立)が高揚してくるが,その背景に〈安保再定義〉論議があることはいうまでもない。また他方では,平和憲法を持つ国家への期待がうすれていくなかで,沖縄では,かつて〈一国家を形成していた琉球王国〉の歴史を想起し,アジアに開かれた沖縄を志向する動きも見られる。
執筆者:我部 政男
民俗
沖縄の民俗は地理・歴史的背景が本土とかなり異なるため独特のものがあり,おおざっぱに沖縄島とその周辺,宮古島とその周辺,八重山地区に大別される。全般に仏教の影響が少なく血忌が重視されないことや,清明祭や火の神などに中国的要素が色濃く認められることのほか,琉球王府の政策によって各種の規制が加えられ,その独自性を強めたことも考慮すべきである。一方で,日本の古語,古俗を残すと思われる民俗が見いだされ,沖縄は〈古代日本の鏡〉ともいわれている。
衣食住
琉球に木綿が伝来したのは17世紀初めで急速に普及したが,それまでは今日夏だけに用いられる芭蕉布が一般住民の通年の衣料であった。身分的服装規定が16世紀にはじまり明治中期ころまで残存しており,一般には紅型,藍型(えーがた)はじみなものが礼装に許されるのみで,平織に限られていた。縞柄,模様も身分,性,年齢によって規定され,身分の低いものは高いものより,男は女より,老人は若いものより細かくなっていた。ハレの衣服は祝儀で黒地,不祝儀で白地で,女性は祝儀に色ものも用いた。食物は,現在は米中心だが,近年まで主食としては通年収穫可能なサツマイモ,副食としては豚肉,ヤギ肉を用いる点に特徴がある。豚は魔物を追い払うと考えられていることから,驚いてマブイ(霊魂)が落ちたと思われる時には,豚小屋に行って供物して拝むこともある。正月準備に正月豚といって豚を殺し,塩漬けにして赤肉から順次調理して食べるほか,清明祭や葬式,年忌にも豚肉を用いる。調理法は煮たり,いためることが発達し,焼くことはほとんどなく,魚の調理法はあまり発達していない。住居は,周囲をサンゴ礁で築いた石垣で囲まれ,一般に南向きに建てられ,主屋は4部屋ある。南面東側を一番座と呼び神をまつる祭壇が設けられ,南面西側を二番座と呼び仏壇がおかれており,死に関する儀礼が行われるほか,日常の社交の場となる。主屋の西側に台所があり,主婦が管掌する火の神がまつられる。これは炉を象徴する三つの石を神体とし,分家の際にはこの灰を分け,主婦が死亡すると石をとりかえる風があった。家族レベルの儀礼は屋敷の南東部で行われ,便所と豚小屋は北西隅におかれることが多い。
→琉球料理
信仰
15世紀以降,沖縄では国王の宗教政策によって神女組織がつくられ,〈聞得大君(きこえおおぎみ)〉と称する国王の姉妹または王妃が,最高の女祭司官として頂点に立ち,その下に大アムシラレという女祭司が3人いて全地域のノロ(祝女)を統轄させた。〈聞得大君〉は高級神女三十三君の上位に位する大君であり,聞補君(ちふじん)ともあてられ,名高い意でキコエを冠するという。また国王のオナリ神として,その霊力をもって国王の安泰と国の隆昌を保障するものであったとされ,国家泰平,航海安全,五穀豊穣,稲麦の穂祭,干ばつの祈願などがなされた。オナリ神信仰は,兄弟に対して姉妹が霊的に優位にたつというもので,国家から村落レベルに至る神女組織をささえる信仰の一つであった。久米島にあって〈聞得大君〉に直属し,同島のノロを統轄していた神官は〈君南風(チンベー)〉と呼び,八重山のオヤケ・アカハチの反乱征伐(尚真王24年,1500年)に功ありとして恩賞に君南風御殿を授かったことで知られ,三十三君の一つである。国王および〈聞得大君〉と深い関係をもつ久高(くたか)島は開闢(かいびやく)伝説でも名高く,知念(ちねん),玉城(たまぐすく)とともにカミグニとされた。南城市の旧知念村久手堅にある斎場御嶽(さいふあうたき)は開闢降臨の地とされ,久高島への遥拝所でもあり,聞得大君の〈御新下(おあらおり)〉という就任儀礼では参籠が行われた。聞得大君はトヨムセダカコとも呼ばれる。セジは霊力を意味し,村落レベルの神女でもその適格者はセジ高い女でなければならないという。セジを身につけ,これを国王に奉り,兄弟をまもり,またこれで仇敵を呪詛することもした。
村落レベルの祭祀をつかさどるノロは,王国の神女組織の末端を担っていた。ノロ以上の神官は国王から辞令を受け,特別に土地を給せられ,賦役も免除されていた。彼女らは官人でその職責は世襲であるが,その継承にあたっては種々の違いが認められる。ノロは〈ノロ殿内(どんち)〉に住んで,担当の祭祀管轄区域内の祈願儀礼を行い,御嶽(おたけ)/(うたき)や拝所でオモロをうたい,オタカベ(お崇べ)を唱えた。オタカベは祭礼のよき日と神の出自をたたえた神への祈願の言葉をいう。各村落の御嶽は村の守護神としてノロの執行する祭祀や共同祭祀の中心となる。御嶽は小高い丘に森をなしているものが多く,いずれも名前をもち,神話伝説も伝えられている。各村落には御嶽のほかに〈拝所(うがんじよ)〉と呼ばれる聖地があり,祭りの時にここでも儀礼が行われる。御嶽の中には神アシアゲという神殿があるが,これはノロ殿内や村の草分けの家の近くにあることもある。祭礼の日にはここに神が降臨し人々の祝福をうけ,その前の広場では神遊び,オモロ,臼太鼓などが行われる。こうした信仰生活を律してきた王国から村落に至るヒエラルヒー的な神女組織は17世紀の薩摩の侵入以後,さまざまな社会変化や旧体制への圧迫によって,明治期以降国レベルでは崩壊し村落祭祀の執行者としての地位はかなり形骸化した。
沖縄的信仰の基盤はシャマニズムの中に位置づけることができる。霊的職能者とされるユタはモノシリともいわれ,〈門中〉と不可分のタブーの判断や運勢,病気祈禱などを行う。歴史的には庶民を惑わすものとして取締りをうけてきたことが,ユタの存在を隠微なものにしてしまったことも考えられる。ユタが霊的能力を備えるとされる現象をカミダーリ(憑依(ひようい)現象)といい,これを経ることがユタたる一つの特徴である。系譜関係の当否の判断をはじめとして近親の死者との橋わたしをするので,〈生きた祖先崇拝の維持者〉であり,〈神意診断役〉ともいえよう。ユタは全琉球に分布するが,沖縄島の中部に偏在し,位牌祭祀に関して男系をたどる継承を推進するため,女性の立場から社会問題化している一方,その存在はますます隆盛をきわめている。
社会
琉球王国末期の百姓地は村の共有であって,一定年限ごとに持地の割替えを行った。先祖が占有した土地を住民に均分に分割相続させ,耕地は共同作業で耕作し収穫物は平等に分配した。これが制度化されたのが地割制度で,1899-1903年の土地整理まで続いた。
親族関係を特徴づける用語にはウェーカ,ハラウジ,門中,チュチョーデーなどがある。門中は男系系譜をたどり,長男を優先するのが特徴で,沖縄島中南部でこの観念が強い。息子のない場合には,たとえ娘がいても婚出させ,自分の男系系譜内から養子を組み入れることにしている。庶民の間ではこれに抵触する〈他系混淆(たちーまじくい)〉〈兄弟重合(ちよーでーかさばい)〉〈嫡子押込(ちやつちうしくみ)〉〈女先祖(いなぐがんす)〉などの言葉があるが,これらはユタの活動によるところが大きい。ハラウジは男女双系にわたって血縁をたどり,個人を中心におおむね従兄弟姉妹までを含む関係を指している。沖縄島北部,久米島,本部(もとぶ)半島,先島の一部に分布し,日常的な互助共同や通過儀礼において機能する。地縁集団は〈組〉と呼ばれ,労働力交換を指すユイの仲間を構成することが多い。
通過儀礼
出産は裏座に〈地炉(じろ)〉を作って,その脇で行い,夏でも産後は火をたいて暖めていた。えな(胞衣)は火の神がまつってある台所裏手の雨だれの下に埋めたが,近所の婦人や子供たちに大声で笑ってもらい,生児が健康に育つよう祈った。命名までの間,子供の性の反対に男児は〈大女〉,女児は〈大男〉と呼んだ。農村の結婚は男女の交際が自由でモーアシビ(毛遊び)で結ばれることも多かった。他村落との通婚は少なく,その場合は女方の村落の青年へ〈馬手間(うまでま)〉という酒または酒代を出さねばならなかった。嫁の引移りにあたって,仏壇と火の神を拝み,男方では台所から入ってその火の神を拝んでから披露宴をした。婚約成立の時点で男方で行う親類へのひろめを〈門中開き〉といった。沖縄では自分の干支が来るごとに正月に年祝を行う風習がある。すなわち13,25,37,49,61,73,85,97歳を祝うが,とくに13歳の祝は実家での最後の祝いとして成年式の意味もかねて女子のある家では盛大に行った。このほか,88歳の祝いは〈トカキ祝〉と称し,8月8日に大だらいに米を盛り斗搔(とかき)をさしておいて参会者にそれを配った。また97歳の祝いは〈カジマヤー祝〉という。
墓ははじめは天然の洞穴を利用していたが,やがて横穴を掘るようになり,のちに平地に築造するようになった。本格的な墓の築造は13世紀末の〈ヨウドレ〉(国王の墳墓)にはじまるとされ,先祖崇拝の厚い沖縄では立派な墓が多いが,墓の形としては,〈亀甲墓〉と〈破風墓〉の二つがよく知られている。亀甲墓は亀の甲の形に似ていることにその名が由来し,築造は堅固である。破風墓は人家に似せてつくられている。埋葬後3年程度たつと遺骨を洗い清める〈洗骨〉が行われ,骨壺に入れて墓に納める。これにより子孫は先祖に対する義務を果たしたとされる。
年中行事
沖縄の気候は本土とかなり異なるため,作物の収穫時期が早く,同じ行事でも本土とは日時がずれることが多く,また琉球王府の政策によって行事の日時が統一されたと思われるものもある。年中行事はほとんど旧暦で行われ,同じ沖縄でも沖縄島と先島(宮古・八重山)地方とでは行事の名称や内容にかなりちがいがみられる。農耕に関連するおもな行事には,2~3月の麦の収穫祭,5~6月のアワや稲の収穫祭,11月のいもの収穫祭のほか,4月のアブシバレー(畦払い)という害虫駆除の儀礼や,立冬ころの〈種取り〉という稲の播種祭などがある。沖縄では年末に豚をころし,正月は餅をつかずに豚で祝った。沖縄島では元旦に若水をくみ,神棚,仏壇,かまどに若水をあげ,家族はその水で〈お水撫で〉をする。若水はスディミズともいわれ,生命を新しくする水という意味がある。マブイ込めやはしかの時にも水をつけた指先で額をなでる行為を行う。先島では夏季のシチ(節)にこの水をくむが,これは正月よりも稲やアワの収穫祭のほうが1年の折り目としてより重要視されていたためであろう。盆行事も沖縄島では本土と同じように行われるが,仏教の影響が少ない先島では盆を行わない所もある。
3月3日には〈浜下(はまおり)〉という一種のみそぎが行われ,蓬餅(よもぎもち)を作って先祖に供したり,親戚知人などに配る。また3月の清明節には墓前で清明祭(シーミー)という盛大な先祖祭が行われる。5月4日には,おもに糸満漁民の村でハーリー(爬竜)と呼ばれる船競漕が行われる。4月のアブシバレーにハーリーを行う所もある。6月には六月ウマチー(祭)といって稲の大祭が行われ,村によってはこのとき沖縄相撲や綱引きなどを行う。八重山各地では6月にプールと呼ばれる稲やアワの収穫祭が行われ,西表島古見など4ヵ所ではこの祭りに豊穣をもたらす仮面仮装神であるアカマタ・クロマタが登場する。沖縄島北部の沿岸では7月20日以後の亥の日または6月中の亥の日に〈海神(うんじやみ)祭〉が行われる。これは海神を迎えまつって海の幸を祈る祭りである。また7月の盆の前後の亥の日には豊作豊猟の予祝祭である〈シヌグ祭〉が行われ,海神祭と隔年で交互に行っている所が多い。7月7日には墓掃除や洗骨がなされ,盆を行う所ではその準備が始まる。盆には,遊び念仏,盆踊とも呼ばれるエイサーが沖縄島中部で盛んに行われる。7月15日の晩に精霊送りをすますと,村の男女はエイサーを踊りながら各戸をまわって酒を求めた。10月1日には〈竈(かまど)回り〉といって,火の神をまつったかまどを掃除し,村の頭役が見まわった。沖縄島などでは10月は〈アキハテ(飽き果て)十月〉といってほとんど祭りらしい行事はないが,宮古の伊良部島佐良浜では〈ユークイ(世乞)〉という豊年祈願祭が行われ,神女たちを中心に村の婦人たちがみな参加し,各拝所を踊りながら健康と豊漁を祈願して歩く。冬至には各家で〈冬至雑炊〉というサトイモ入りの雑炊を作って火の神や仏壇に供えるが,沖縄島北部の村々ではいもの収穫祭が行われる。12月8日には〈鬼餅(むーちー)〉といってビロウの葉に包んだ餅を作り,年の数だけ食べる。この行事には鉄の入った餅で人食い鬼を退治したという伝説が伴っている。年末にはカイルガマという悪魔払いの儀礼が行われる。また12月24日には,かまどの火の神が昇天し,正月の初旬に下界に戻ってくるといわれている。このほかに時期は不定だが,〈井泉詣(かーめー)〉といって井泉を拝み,水への感謝と健康祈願をする行事や,門中ごとに沖縄島北部の東方霊地を巡拝する〈東(あがり)回り〉や北山への〈今帰仁(なきじん)拝み〉といった行事もある。玉城村百名(ひやくな)の海岸にある〈受水走水(うきんじゆはいんじゆ)〉は東回りの第1の霊地で,この水でアマミキョ(始祖神)がはじめて稲作を行ったといわれている。
執筆者:饒平名 健爾
琉装
現在は沖縄でもおおかたの人々の衣生活は洋服である。しかし本土における和服同様に,沖縄でも伝統的な衣服が日常生活にも使用されており,沖縄特有の衣装姿(琉装(りゆうそう))は本土の和服姿とほぼ同じくらいの比率で見受けられる。和服の長着(ながぎ)(小袖,単(ひとえ),帷子(かたびら))に相当する琉装の衣服は〈衣(ちん)〉で,これは本土の小袖や単や帷子が男女,階級,地域に関係なく,伝統的に基本衣服として使用されてきたと同様,沖縄でも男女,階級に関係なく,ほとんどの地域で着用されてきた。形態は本土の小袖の類と一見したところほとんど同形である。ただ,袖が平袖(広袖)で,袖口は袖下の縫目の位置まで大きく開いており,袖付下に襠(まち)が入っている。これは本土以上に高温多湿の土地柄から,袖口をいっぱいに開けて少しでも風通しのよい衣服にした形であり,袖付下の襠は腕の動きを楽にし,また補強のために付けられた布である。単仕立てとあわせ仕立てとがあり,季節に合わせて着用する。この沖縄の伝統的かつ各階級共通衣服の〈衣〉も,基本的な形態は変わらないながら,士族以上と庶民とでは袖丈など多少長さが異なるなどの違いはあった。また地質,色柄,模様,着装法に至っては,王家,士族,庶民の階級別にかなり厳しいきまりがあった。たとえば,庶民は芭蕉布の場合上等品の煮綛(にーがしー)は着られない。柄も庶民は絣模様は禁じられているが縞はよい。紅型・藍型の模様染は士族以上のもので,それもその中での身分によって模様の大きさ(大きい柄ほど身分が高く,一幅に一つの模様がある一玉柄は王家専用,二玉,三玉は士族用)や色(金(黄)が最高,次いで赤,水色,茶色の順の地色)にきまりがあるなどである。また沖縄衣装のきれ地は,芭蕉布,苧麻(ちよま)布,木綿が主で,上流者の間に絹や桐板(とんびやん)が時に用いられた。
衣服の着装法は,庶民の場合,男子はふんどしの上に〈衣〉を着て,織帯(幅が10cm前後のミンサー帯)を締め,女子も腰布の上に〈衣〉を着て,織帯を締めるだけの簡単なものが基準であった。しかし士族以上は相当厳格に姿容を整えていたようで,古くは中国の属国であったところから上流階級の衣服は中国系であり,近世以降薩摩藩の統治下になってからも士族以上の正装は男女ともに中国系の濃厚なものであった。したがって近世以降明治にいたるまでの沖縄上流者の服装は,本土風が入ったとはいうものの男子はほとんど中国系の服装,女子は多分に本土風が取り入れられた服装という様相であった。明治になってから上流階級の男子は本土同様急速に洋服化するが,女子は近世以降に入った本土風が明治になったからといってそれ以上は入らなかったようである。ただ,夏季の女子のくつろぎ着としての着装法押衣(うしんちー)が,しだいに士族婦女子の一般的な夏季服装になってきたことが注目される。もともと押衣は,ごく内々の非常にくつろいだ時の服装である。士族以上の女性は常に下着としての袴をつけているが,押衣の時はふくらはぎくらいまでの丈の四布袴(よのばかま)で,その袴の腰の位置に小帯(ミンサー帯)を締める。その上から〈衣〉を着て,合わせた上前(うわまえ)の右腰部分を,下袴に締めてある小帯に,上から押し込むようにして挟み込む着装法である。1920年代ころまでは士族の女性は家居の場合でも威儀を正した服装で,夏季も〈衣〉の上に帯を締め,その上から田無(たなし)という絽地花織(花倉織)の夏季用打掛を着ていたという。明治時代の沖縄の絵画や大正時代から現代にいたる沖縄の写真資料にしばしば〈衣〉の前の打合せが左前(左衽(さじん))になっているのがあるが,中国の服装文化と日本の服装文化とのなんらかの影響が,現代にこういう現象となって残されているのだと思われる。
執筆者:神谷 榮子
美術工芸
資源の乏しい沖縄では,古くから中国,日本,朝鮮,南方の諸外国との交易によって文化を摂取しながら,亜熱帯特有の気候風土の中で独自の美術工芸をつくり育てた。それらを歴史的にながめると,1609年(慶長14)の薩摩藩の琉球征服以前と以後でその性格を異にしているといえる。慶長以前は海外貿易による豊かな財源を背景に,石造建築や彫刻を中心とする大規模な建造物群がつくられたのに対し,慶長以後は薩摩の支配の下,対外交易権を奪われて財源が困窮し,小規模の工芸品制作が行われた。慶長以後は琉球王府に〈貝摺奉行所〉や〈瓦奉行所〉が設置され,漆器や染織,陶器などの工芸品を王府が保護育成したため,工芸技術が一段と進歩した。それらの多くはかつて王家や士族用のものであったが,伝統技術は今も継承されている。
絵画
記録にのこる最古の絵画は察度(さつと)王(1395没)の肖像画(16世紀末)といわれるが,今では不明である。その後,尚円王以来歴代国王の肖像画が極彩色で描かれているが,いずれも画家の名は判明しない。王府時代の画家では欽可聖(きんかせい)(城間(ぐすくま)清豊,1614-44)が天才自了(じりよう)と呼ばれ,中国の陳元輔や日本の狩野安信らに推称されたという。17~18世紀には呉師虔(ごしけん)(山口宗季)とその弟子殷元良(いんげんりよう)(座間味庸昌)を生んだ。このころはおもに中国の技法を学びながら琉球独特の絵画を生み出し,琉球絵画が最も栄えた時期である。その後尚元瑚(小橋川朝安,1748-1841),呉著温(屋慶名政賀),慎思九(泉川寛永)らが輩出したが,総体として絵画は工芸ほどには振るわなかった。それは,絵画が工芸に従属し,絵師は工芸の下絵などで働いたからである。琉球絵画は日本にはあまり影響を与えず,殷元良や呉著温などは日本の画法を取り入れて《雪中雉子の図》や《雪中山水図》を描いている。
建築
沖縄の建造物は第2次大戦でことごとく灰燼(かいじん)に帰した。戦前における沖縄の代表的な建築物には,首里城内の守礼門,歓会門,瑞泉門,白銀門,正殿,首里円覚寺内の総門,左・右掖門,三門,仏殿,竜淵殿,鐘楼,獅子窟,那覇崇元寺内の総門,正廟,首里の園比屋武(そのひやん)御嶽,弁ヶ嶽,末吉宮,那覇の沖宮(おきのみや)などがあった。これらは大半が琉球の黄金時代といわれた尚真王(1477-1526)時代,あるいはそれ以前の創建になるものである。これらの建造物には唐様,天竺様,和様と種々の様式が認められ,中でも多くの城や石橋は技術的・造形的に優れたものであった。石造建築には石を切る鉄器をはじめ種々の高度の技術が必要であり,それを可能にしたのは尚真時代の経済的繁栄であったといえる。高度な石彫技術を示す遺品には15世紀の第一尚氏王統時代の世持橋の勾欄の羽目がある。砂岩に魚貝や海波模様が力強く彫り込まれているのは,海外貿易に挑んだ当時の人々の精神の現れとも見られる。また尚真時代の円覚寺放生池石橋の勾欄羽目や玉陵の屋根獅子などには珍しいセン緑岩が使用され,中国の石工との合作による琉球石造彫刻中の最高のものである。しかし慶長以後は薩摩産の花コウ岩による日本式雪見灯籠や三重塔灯籠のような優美なものにかわった。
木彫は沖縄に良質の木材が少なかったため,石彫に比べて劣っているが,円覚寺竜淵殿鳳凰板戸透彫や欄間竜彫刻,総門の仁王像などが作られ,また梅帯華(田名宗経,1798-1863)の《竜頭観音像》や《十六羅漢浮彫椰子合子》などが残っている。
陶芸
沖縄最古の瓦は中部の浦添(うらそえ)城跡から出土したおよそ13世紀初期の高麗瓦である。記録では15世紀中期に中国人が南部の国場で瓦を初めて焼いたとある。15世紀初期の陶器は南方系の素焼が多く,中部の知花(ちばな)や読谷(よみたん)村の喜名,北部の古我知(こがち)でおもに酒がめや水がめがつくられた。16世紀初期には喜名や知花の窯が王府によって那覇の壺屋に移された。そして17世紀初期に王府は薩摩から高麗人陶工張献功(一六),一官,三官らを招聘(しようへい)して朝鮮式陶法を伝授させ,さらに17世紀中期には陶工平田典通を中国に派遣して赤絵の技法を習得させた。18世紀初期には仲宗根喜元が初めて白土を陶土に使用し,さらに仲村渠致元(なかんだかりちげん)も薩摩で陶法を学び大型製陶に成功した。このように沖縄の陶器には南方系,中国系,朝鮮系,日本系があり,これらはいずれも壺屋で制作された。そして現在も魔よけの屋根獅子や置物の獅子,抱瓶(だちびん),碗,皿,壺などが,灰釉,飴釉,黒釉,呉須などを用いて焼かれ,魚文に代表される大らかな文様を施した温かみのある陶器が作られている。なお新城(あらぐすく)島(現,竹富町)で19世紀中ごろまで作られたパナリ焼は土器で,製法は古く中国人が伝えたともいわれる。つる草やタブノキの粘液を土に混ぜてこね,手で成形してカタツムリや貝肉の粘液を塗り,露天で焼いた。パナリ焼についての古謡も伝えられ,素朴で美しいフォルムが今日も喜ばれている。
漆器
古い記録に1429年に明より漆を買いに来たとあるので,このころには沖縄でも漆を使用していたと思われる。また,北部今帰仁(なきじん)の百按司(ももじやな)墓内の朱塗りの木製厨子や首里円覚寺扁額の漆絵などからみても,そのころすでに漆芸が相当発達していたと思われる。漆芸の技法はおもに日本から学び,ろくろの技術も1629年(寛永6)に日本の漆工が沖縄に漂着し,那覇の若狭町で塗物と一緒に伝えたという。その後王府は漆工芸に最も力を注ぎ,中国の技法も取り入れて,沖縄の夜光貝を使用して作った螺鈿(らでん)(青貝摺)や中国の堆朱(ついしゆ)の技法を応用した琉球漆器独特の堆錦(ついきん)が生み出された。また明治以降は木地に特産のデイゴが用いられ,木肌の粗いデイゴへの下地塗りにキリ油や泥岩に豚血(とんけつ)を混ぜる豚血下地が行われ,廉価で堅牢なため今日も伝承されている。そのほかにも彫りの線が太く重厚な沈金や漆絵などがある。これらの漆器はいずれも王府によって日本や中国へ献上あるいは輸出された。
染色
沖縄の代表的な染色工芸である紅型(びんがた)染は,近世初頭に南方の更紗や日本の友禅染の影響を受けて発達した。もっぱら王家や上流士族の間で使用され,制作も王府の監督のもとに首里の特定の紺屋,城間,知念,沢 (たくし)家で行われ,世襲であった。型紙を用いる型付には藍型(えーがた)もあり,藍型は琉球藍一色で染め,紅型は多色で染めたものをいう。型付に対して,手がきによる筒引(つつびき)の技法も行われる。これは筒袋からのり(糊)を出しながら描く糊引法で,おもにふろしきや舞台幕に用いられた。色彩は植物染料のほかに顔料や動物性の醒臙脂などを使用し,生地は,芭蕉布,苧麻,羽二重などもあるが,主として綿布を用いる。
(たくし)家で行われ,世襲であった。型紙を用いる型付には藍型(えーがた)もあり,藍型は琉球藍一色で染め,紅型は多色で染めたものをいう。型付に対して,手がきによる筒引(つつびき)の技法も行われる。これは筒袋からのり(糊)を出しながら描く糊引法で,おもにふろしきや舞台幕に用いられた。色彩は植物染料のほかに顔料や動物性の醒臙脂などを使用し,生地は,芭蕉布,苧麻,羽二重などもあるが,主として綿布を用いる。
織物
古くは一般に芭蕉布や苧麻が織られ,上流階級には木綿や絹が使用された。絹は14世紀に中国から,木綿は17世紀初めに薩摩から伝えられた。これらの織物は草木で糸を染めて織った。機織は古くはもっぱら地機で,後に高機の手機織を使用した。織物の種類は平織や絽織,綾織,ロートン織,浮織その他たいへん多い。王府時代は芭蕉布の最上品や麻の首里上布,絹織物の高級品は首里で最も盛んに織られた。高級品は王族や上流階級しか着用が許されなかったからである。一方,宮古上布や八重山上布,久米島紬,読谷花織,大宜味村の喜如嘉(きじよか)や今帰仁村の芭蕉布など,地域によって特色ある織物もつくられた。織柄には絣,縞,格子などがある。特に絣の技法は15世紀ころ南方から伝えられ,独特の清楚な琉球絣を完成し,さらにこれは日本本土の絣にも影響を与えた。
執筆者:外間 正幸
文学
沖縄文学は,奄美諸島(現,鹿児島県),沖縄諸島,宮古列島,八重山列島にまたがる地域で生まれた文学の総称で,古代文学と近代文学の二つに分けることができる。古代文学とは,沖縄が歴史的出発(3世紀ころ~6世紀ころ)をしてから,19世紀後半ころまでの間に琉球方言で表現された文学を指し,近代文学とは19世紀後半以後,主として日本的標準語で書かれた文学を指す。古代文学と近代文学の間には,歴史の変革に伴う文学の〈場〉の構造的な変質と,文学意識,および意識の媒体となる言語のあらたまり(琉球語→日本語)が明らかであり,それらをもって区別の基準とする。
→琉球語
古代文学
古代文学の内容は,その形態と発想の側面から呪禱文学,叙事文学,抒情文学,劇文学の四つに分けられる。呪禱,叙事,抒情の三つは,そのほとんどが唱えものか謡いもの,あるいは歌謡として韻文的に口承されてきたものであり,劇文学も韻律を伴ったせりふに,音楽,舞踊が組み合わされたもので韻文的である。このようにそのほとんどが韻文で構成されており,散文形式のものはかろうじて狂言などに見られる程度で,呪禱,叙事性を基層にした呪詞,歌謡中心の文学であることと,その言語が,ほとんど島ごとに異なった姿をみせていることが大きな特徴である。したがって,それらをそのまま日本文学の中に包みこむことはむずかしい。ただ,両者は言語も文化も源を同じくするものであり,文学の形態,発想そのものも本質的には同質で,日本文学の古形,あるいは独自に変成したとみられるものである。日本文学の歴史には痕跡しかとどめない原始的過程を暗示するものとして注目したい。
(1)呪禱文学 呪禱文学は言霊信仰に基づいた呪言によって唱えたり謡われたりするもので,奄美のクチ(口),タハブェ(崇(たか)べ),オモリ,マジニョイ(まじない),沖縄のミセセル,オタカベ(お崇べ),ヌダティグトゥ(宣立言),ティルクグチ(照るく口),ティルル(照るる),マジナイグトゥ(まじない言),宮古のニガリ(願い),マジナイグトゥ(まじない言),タービ(崇べ),ピャーシ(拍子),フサ(草),ニーリ,八重山のカンフチ(神口),ニガイフチ(願い口),カザリフチ(飾り口),ジンムヌ(まじない言)などがある。例を沖縄諸島にとれば,ここに伝わる呪詞・呪言のうち,もっとも古いと思われているものはミセセルとオタカベである。オタカベは,神を崇べ,神に対する宣立(のだて)のための祝詞(のりと)であることは,その内容と機能から明らかである。超人間的な力をもつ神にすがり,五穀豊穣の予祝をしようとする願望が,神祭りにおけるオタカベとなって発達したのである。島々の呪詞・呪言には多くの呼称があり,地域的な偏差と内容の変遷または重なりなどをもっているため,それぞれの呼称に対応した内容の区別をすることはきわめてむずかしい。中には,神々の呪縛と呪禱的な心意を離れ,集落の歴史や人事(ひとごと)を語る叙事歌的内容に変わっているものもある。ただそれらのすべてに共通することは,人と神との間をむすぶ呪詞としての機能をもっていることである。
(2)叙事文学 奄美のナガレ歌,八月踊歌,ユングトゥ,沖縄のクェーナ,ウムイ,オモロ,宮古の長アーグ,クイチャーアーグ,八重山のアヨー,ジラバ,ユンタ,ユングトゥなどがある。叙事文学もまた,歴史的変遷の中で呼称に応じた区別をしにくくなったものが多い。さらに呪禱と叙事と抒情との区別もしがたいほど内容の重複の見られるものすらある。それらの大部分は農耕儀礼にかかわりが深く,神々の呪縛の中に初源的な生命を育て,呪禱的心意や叙事性を含みこんだまま,共同体の生活の場に大きく広がっていったものである。沖縄のクェーナは,村落共同体の繁栄や幸福への願いを,対語・対句をつらね,連続・進行的に述べていく典型的な叙事的歌謡である。アマウェーダーと呼ばれるクェーナをみると,稲作のための整地から種まき,稲の生育,刈入れまでの過程を,順序よくていねいに謡いこむことによって,予祝すると同時に作業手順を正確に伝承していったことがうかがえる。このように,稲作その他の生産過程を表現することが,そのまま豊穣につながっていくのだという言霊信仰があり,それを基盤にしてクェーナ的古謡が生まれてきたようである。こういうクェーナ的古謡の形態と発想は,奄美,沖縄,宮古,八重山などの南島古謡に共通な基本的性格であるといえる。沖縄のウムイはクェーナを基盤にしながら,オモロという新しい歌形を生みだす母体になったものである。《おもろさうし》は16世紀から17世紀にかけて琉球王府が島々の古謡を採録したもので,沖縄の古代社会を研究するための大事な手がかりである。ウムイとオモロは本来同じものであるが,地方のウムイが中央で整理され,歌形をととのえていったものがオモロである。
(3)抒情文学 奄美の島歌(しまうた),沖縄の琉歌,宮古のクイチャー,トーガニ,シュンカニ,八重山の節歌(ふしうた),トゥバラーマ,スンカニなどがある。島歌,琉歌,節歌などは総括的な呼称で,それぞれの中でまた長歌形と短歌形に分けることができる。いずれも,もとは単に〈うた〉と呼ばれたものであるが,沖縄の〈うた〉が琉歌といわれるようになったのは,日本の和歌が,漢詩(からうた)に対して和歌(やまとうた)と称して区別されるようになったのと同じ事情であり,地域的変容と特性をもっている。琉歌は〈短歌形式〉〈長歌形式〉に二分し,前者は〈短歌〉〈仲風(なかふう)〉に,後者は〈長歌〉〈つらね〉〈木遣り〉〈口説(くどき)〉に分けることができる。短歌は8・8・8・6の4句30音から成る定型の短い文学形式で,普通に〈琉歌〉というときにはこれを指す。仲風は7・5・8・6の4句26音,もしくは5・5・8・6の4句24音から成る定型の短歌である。長歌は8・8・8・8と八音を連続し,末句を六音でしめくくる形式の歌である。八音の連続性が〈短歌〉より長いことが特徴であるが,長いといっても〈短歌〉に比べてという程度で,さらに長い〈長歌〉は別のジャンルの〈つらね〉に近くなってくる。八音を連ねて末句を六音でしめくくるのは,〈長歌〉〈つらね〉ともに同じであり,その点〈短歌〉も例外でない。木遣りは,建築用材を山からおろして引いていく時に歌われる労働歌である。口説は,七五音の連続を基調にし,いわゆる和文調の歌である。和語も取り入れられているし,読みも和風に読むのが正しい。もともと薩摩役人たちをもてなす宴席で歌われたという。
(4)劇文学 奄美の諸鈍芝居(しよどんしばや),狂言,沖縄の組踊(くみおどり),狂言,人形芝居,歌劇,宮古・八重山の組踊,狂言などが伝わっている。組踊は,沖縄の言語,文学,芸能をもって総合的に構成された独自の楽劇である。島々に伝わる伝説,説話を軸とし,古語を積極的に取り入れながら沖縄的な八八調の音律に調え,舞踊もまた古くから伝わる〈こねり〉〈しぬぐ〉などの祭式舞踊を組み合わせている。沖縄,宮古,八重山に伝わる狂言はそれぞれ独自であり,風土に根ざした〈笑いの文学〉である。人形芝居は,人形を操って各地を門付したもので,大和からの渡来であるという。歌劇は沖縄独特の歌舞劇である。せりふを琉歌の節(ふし)に合わせて掛けあいで歌い,しぐさや踊りをまじえながら劇を進めていくという形をとる。組踊がとかく王府や士族階層のもつ道徳律にしばられがちであったのに比べ,歌劇は庶民の生活の場にある喜びや悲しみをたくみにくみあげている。
近代文学
沖縄の文学は呪禱から叙事,抒情へと独自な形で数百年も続いてきた。しかし明治初年,幕藩体制の崩壊による日本の国家統一,近代化の過程で,沖縄もまた日本的体制の中にくみこまれることになったため,政治,経済,文化の諸面にわたって大きな変動がおこった。文学も例外ではなかった。まず言葉の面で日本的標準語が沖縄語の上にかぶさったため,沖縄語によるよりは標準語を使ったほうが,より広い場に通用し,多くの支持を得るようになった。文学環境のこのような変革を,沖縄における古代文学と近代文学のくぎりにすることができる。言語のみならず,社会の変動に伴う文学意識の変化も,はっきりとした様相を呈してくる。しかし,沖縄の島々を本土の体制の中にくみいれようとする上からの力は,さまざまな制度的差別,社会的差別を伴いつつ浸透してきたため,平和に生活してきた沖縄の人々の心に深い傷跡をとどめた側面があった。山之口貘(やまのぐちばく)の,〈お国は?〉と聞かれてひとこと〈沖縄〉といえない心の屈折を綴った〈会話〉と題する詩は,辺境“沖縄”であることの社会的被差別の痛みを表現しており,それはそのまま沖縄の近代化の歴史的苦悩を象徴するものでもあった。1879年以後,日本的標準語を使うことで近代文学への足がかりをつくった沖縄の文学は,明治30年代に〈近代短歌〉〈詩〉,40年代に〈小説〉という新しい文学形式を獲得してのち,中央の文学と同質化しようとするけんめいな努力を試みることになるが,山之口貘の独特な詩風を除いては,見るべき作品は生んでいない。沖縄の近代文学が,自覚的かつ自立的な文学として歩みだすのは,戦後の1955年以降にまたなければならない。
執筆者:外間 守善
芸能
沖縄は中国大陸にも東南アジアにも近い地理的環境から,古代日本的な民俗基盤の上に四方の国々の芸能要素を吸収して,汎東洋的ともいえる独特の芸能を発達させた。今日伝承される沖縄の芸能を大別すると,(1)琉球王国時代に王家の儀式などに演じられた宮廷芸能の芸統を伝えるもの。(2)1879年の廃藩置県後,民間に生まれた商業劇場を中心に専業の俳優や奏者によって創造され,その後,舞踊家などの参加によって舞台を中心に発展をみつつある芸能。(3)各市町村の生活の中で地域住民がみずから演奏者となって伝承してきている,いわゆる民俗芸能である。
宮廷芸能
沖縄島を統一した15世紀の第一尚氏王統の時代から第二尚氏王統の初期にかけて,宮廷では儀式舞踊として巫女集団によるコネリ(舞踊の古語。ナヨリとも)などが行われ,また,饗宴の席などでは当時全盛のオモロが赤犬子(あかいんこ)などの歌人によってうたわれたようだが,当時中国から三弦が伝来し,やがて三線(さんしん)とよばれて宮廷奉仕の士族たちがつま弾くようになるとオモロはすたれ,かわりに8・8・8・6調の短歌(琉歌と呼ぶ)を士族たちがつくって,それを三線にのせてうたうようになった。16世紀にはこの三線が本土へ渡って三味線を生むことになるが,宮廷では17世紀に湛水親方(たんすいおやかた)が出て三線歌曲の芸術化が急速に進み,18世紀には聞覚(もんかく),屋嘉比朝寄(やかびちようき)などが工工四(くんくんしい)と称する楽譜を編み,また19世紀には野村安趙が野村流を,安富祖(あふそ)正元が安富祖流を興して,近代の三線音楽を確立した。
舞踊は16世紀ころ,宮廷奉仕の若衆(わかしゆ)(未成年男児)が新国王の冊封に来琉する明国の冊封使を饗応する宴席で,華麗な扮装で踊りを披露し,17世紀にも童児の群舞が行われた。冊封使饗応の宴は宮廷最大の行事で,宴に披露する歌舞を企画・制作するのに高官の中から躍(おどり)奉行を選び,数年前から準備,稽古に入る慣行であったが,1719年,尚敬王冊封のときに躍奉行に選ばれた玉城朝薫(たまぐすくちようくん)(1684-1734)は,従来の舞踊にかえて,三線を伴奏にしながら歌とせりふで物語を展開する組踊と称する歌舞劇を創作して上演した。これが評判をえて,以後組踊が歴代創作されるようになったが,また彼は三線歌曲を伴奏にした舞踊を振付けし,のちの宮廷舞踊の基礎を固めた。この種の舞踊を端踊(はおどり)と呼ぶが,種目には老人踊,二歳踊(成年男子の踊り),若衆踊,女踊の四つがあり,それぞれで扮装と技法が異なる。演者はいずれも士族の子弟が勤め,若衆踊,二歳踊は該当年代の者,女踊は成年直後ごろの者の役割であったが,廃藩置県後はしだいに崩れ,女性も自由に踊るようになった。組踊で現存する台本は47に及ぶが,上演頻度の多いのは玉城朝薫作の《執心鐘入(しゆうしんかねいり)》《二童敵討(にどうてきうち)》《銘苅子(めかるしい)》《女物狂(おんなものぐるい)》《孝行の巻》の5番と,朝薫以後に出た平敷屋朝敏(へしきやちようびん)の《手水の縁》,田里朝直の《万歳敵討》,高宮城親雲上(たかみやぐすくぺえちん)の《花売の縁》,久手堅親雲上(くでけんぺえちん)の《大川敵討》などである。端踊では玉城朝薫が振り付けたと伝える女踊の《伊野波節(いのはぶし)》《諸屯(しよどん)》《作田節(つくてんぶし)》《綛掛(かせかけ)》《天川》《柳》などが,古いコネリの技法を歌舞伎踊の様式に融合させた点で特に優れる。二歳踊は,紋服姿の若者が本土風の七五調の口説歌などにつれて軽快に踊るもので,《上り口説》《前の浜》などの曲がある。若衆踊は,振袖あわせ衣装に引羽織をつけた若衆姿の踊手が《こてい節》などの祝賀曲をういういしく踊る。老人踊は老人姿の踊手が国や人の寿福を祝賀して踊るもので,本土の翁(おきな)に当たる。なお組踊と端踊を含め,宮廷舞踊を冠船踊(御を冠して呼ぶこともある)と総称するが,これは新国王の王冠をたずさえて来琉する冊封使の乗る船を冠船と称したことに由来する。
三線歌曲は,近世以前のものを〈昔節〉〈大昔節〉などといい,前者に《作曲節》《首里節》《諸屯節》など,後者に《茶屋節》《仲節》《十七八節》がある。すべて琉歌に三線を添えたものだが,近世になると,本土の和歌と琉歌を組み合わせた〈仲風(なかふう)〉や,口説を三線にのせるものも生まれた。三線に加えて箏,胡弓,笛,太鼓を合奏することもあるが,箏曲は18世紀初め,稲嶺盛淳が薩摩から八橋流箏曲を学んできたものの流れで,独特の独奏曲も伝承している。
近代劇場芸能
廃藩置県令施行後,禄を失った士族のうち芸に堪能な者が集まって,那覇市中の思案橋や仲毛(なかもう)にかます囲いの芝居小屋を仮設して踊興行を始めたのがきっかけで,1882年ごろにいわゆる沖縄芝居が始まった。当初は組踊,端踊をもっぱら演じていたが,大衆の嗜好に応えるため民謡,流行歌の類を三線にのせ,芭蕉衣や絣着の百姓娘と町女が軽快に踊る姉小舞(あんぐわもうい)を創作上演したり,当時隆盛の廓の遊女の風姿を描いた踊り,遊女と客の交情を描く劇舞踊などを演じて喝采を得た。現在も上演される《浜千鳥》《かなよう》《むんじゅる》《花風(はなふう)》《川平節(かびらぶし)》《金細工(かんぜいく)》などがそれで,これらは旧来の冠船踊に対して,雑踊(ぞうおどり)と総称された。当時,《むんじゅる》などを振り付けた玉城盛重は冠船踊にも熟達し,のちには踊師匠になって後継者養成に専念したので,近代沖縄芸能興隆の祖といわれる。新垣松含,渡嘉敷守良などの名優も輩出し,明治後期には3劇場に3座が鼎立して,歌の掛合で物語を運ぶ歌劇や,こっけい会話の狂言,歴史に取材した史劇などを次々に開拓し,沖縄芝居全盛期をつくりあげた。歌劇の名作《泊阿嘉(とまりああか)》や《薬師堂》《奥山の牡丹》などは今も上演されるが,それらの劇も昭和に入ると映画産業に押されて衰退し,珊瑚座などの活躍が一時はあったものの,太平洋戦争で劇場は壊滅した。戦後,ときわ座,大伸座,乙姫劇団などが出て各地を巡演,民心の鼓舞に功績があったが,テレビなどの普及で衰退した。かわって玉城盛重などの薫陶を受けた旧俳優や踊師匠によって育てられた男女の舞踊家が輩出し,冠船踊や雑踊を舞台にかけ,また創作舞踊を発表するなど舞踊家全盛の時代が到来した。芝居の衰退で伝承が危ぶまれた組踊も,1972年国の重要無形文化財に指定され,後継者養成の事業が進められている。
民俗芸能
沖縄諸島,宮古列島,八重山列島とも昔から芸能は盛んで,町や村の祭りをはじめ,婚礼,新築祝,年祝などの家庭行事,あるいは男女が集まっての野遊びなどさまざまの機会に人々はうたい踊った。大きな祭りは稲,アワの収穫期から次の年への播種期にかけて集中的に行われ,そこでは祭事をつかさどる巫女集団が古風な神歌をうたい,また遊(あそび)などと称する呪禱的な舞踊を演じたりする。沖縄島北部のシヌグや宮古島や大神島のウヤガン,あるいは12年目ごとに行う久高島のイザイホーの祭りなどは,特に古い巫女の歌舞を残している。また,村々の祭りに海のかなたのニライの国から仮装神が来訪する儀礼を伝える村が各地にあり,八重山列島の収穫祭に出現するアカマタ・クロマタや,年替りの節祭に出現するマユンガナシなどは特に名高い。芸能化したものでは,八重山列島に多い弥勒踊があるが,これはニライから稲,アワをもたらす弥勒のおとずれを歌と踊りで示すものである。また全域的にさまざまの祭りに登場する獅子舞も,遠くから来訪して災厄を払い豊穣をもたらすと信じられた神の芸で,シュロなどの繊維で編んだぬいぐるみの中に2人の踊手が入ってデイゴの獅子頭を振りまわしつつ豪快に踊る。その他祭りをにぎわす芸能で全域的に行われるものに棒術,棒踊の類があるが,棒術は真棒(まあぼう),組棒などといって,2人1組の男が三尺棒,六尺棒などを激しく打ち合わせるもの,棒踊はそれの舞踊化で,土地によって赤毛をかぶって曲技を演じたりする。これを南島(はえのしま)などというのは,南中国などから伝来したとの由来談があるからである。太鼓を打ちならす芸は沖縄,八重山にあり,沖縄島の中城(なかぐすく)村伝承の打花鼓(たあふあくう),今帰仁村伝承の路次楽は,ともに中国楽器の哨吶(つおな)(チャルメラ)を吹き,前者は太鼓,鉦,銅鑼(どら)を鳴らし,後者は小太鼓を打ちつつ道中する芸で,いずれも中国からの伝来を説く。また津堅(つけん)島伝承の大踊は本土系の太鼓踊の形を学んだもので,沖縄芸能のもつ芸能要素の多様性がしのばれる。八重山では獅子舞に添う形でペッソーと呼ぶ太鼓踊が行われ,また石垣島の川平には珍しい銭太鼓の踊りが残存する。
全域的には祭りの余興に村芝居を演じるのが盛んで,村ごとに演出を凝らした狂言や組踊を上演し,あいだに村独特の踊りを披露する。一方,島ごとでは,沖縄島にウスデークと呼ぶ女性の集団舞踊がある。琉歌調の歌につれて優雅に踊るもので,巫女の遊の舞踊化ともいえる。宮古島では祭りはもちろん,随時人が集まれば男女ともに踊るものにクイチャーがある。手を打ち,足を力強く踏み,跳ねながら踊る群舞である。八重山では祭りに踊る群舞をマキ踊といい,古風な手ぶりを伝える。盆祭の芸能では沖縄島にエイサーがあり,八重山には盆アンガマがある。前者は男女の集団が村内をめぐって念仏歌をうたい,その後民謡にのせての踊りを披露するもので,後者も覆面,仮装の者たちが各家々をめぐる。念仏は近世初頭ごろ本土渡来の念仏聖や京太郎(ちよんだらあ)と称する宗教芸能者が落とした種子とみられるが,京太郎の芸能は今も沖縄島の沖縄市などに,その演目の一部である馬舞や鳥刺(とりさし)舞などが伝承されている。人形芝居は昔京太郎にもあったが,その伝承は絶え,今帰仁村などに獅子人形の糸操りがわずかに伝わる。江戸時代,八重山在勤の士族間で行われた能囃子が,石垣島に大胴(おおどう)(大鼓)・小胴(こどう)(小鼓)の名で残っているのも珍しい。なお沖縄島で昔村の男女が月明りの晩などにうたい踊ったという毛遊びの風習は絶えたが,人々が集まればカチャーシイと呼ぶ三線の早弾きにのって,即興の手ぶり足ぶりで踊る習慣は今も生きている。
執筆者:三隅 治雄
沖縄[市] (おきなわ)
沖縄県,沖縄島(本島)中部,那覇市の北方22kmに位置する市。琉球王朝時代には越来間切(ごえくまぎり)を基盤に越来城が築かれていたが,首里王府の新政策によって,1666年(寛文6)越来間切と美里間切に分離し,1908年特別町村制の施行で,越来村,美里村に改称した。56年6月越来村はコザ村と改称し,翌月市制を施行した。美里村の一部が石川市となって分離したが,74年コザ市と美里村が合併して沖縄市と改称。人口は13万0249(2010)で,沖縄県第2の都市である。合体により沖縄市の総面積は49km2,そのうち36%が軍用地で,嘉手納基地の一部も含まれる。基地の恒久化に伴って成長してきた都市で消費都市の性格が強い。基地依存からの脱却が進み,市の東部海浜地区では中城(なかぐすく)湾開発が行われており,埋立地に工業団地の建設が進む。70年12月にはアメリカ軍支配に反発するコザ暴動が起こっている。沖縄自動車道の沖縄南,沖縄北の二つのインターチェンジがある。
執筆者:田里 友哲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「沖縄」の解説
沖縄
おきなわ
沖縄史の初めは言語・文化を同じくする日本人の一部がこの列島に住みついたことに始まると思われる。伝説としては,源為朝が八丈島から沖縄島に渡り,土豪の妹を妻として一子を得,これが第1代の王となったとされるが,もとより史実とはいえない。11世紀ごろから按司 (あんじ) と呼ばれる族長が支配する部族国家が分立し,やがてそれらの上に世主 (よのぬし) が出現し,各地に割拠した。14世紀には,北山・中山・南山の3勢力にまとまり,明にそれぞれ朝貢し,特に中山朝は,アンナン・ジャワ・シャムなどを対象とする東南アジア貿易を発展させ,またその商船は博多や坊津に来航して南洋方面との貿易を中継するなどの動きをみせていた。15世紀の初め,尚氏が台頭,同世紀の末には本島を政治的に統一し,16世紀の初めまで琉球史上の全盛期を現出した。この尚王朝が明治維新まで続く。1609(慶長14)年の島津氏の侵攻は琉球王国に大きな打撃を与えた。その後は,島津氏と,中国の明・清への両属を余儀なくされた。しかも島津氏の琉球人に対する本土の風俗・言語の使用を禁じる政策は,本土人と琉球人の民族的一体化を妨げた。明治維新後,新政府は1874年台湾出兵を行い,琉球の日本帰属を諸国に黙認させ(琉球帰属問題),'79年沖縄県とした。沖縄県となってからは知事や県庁の首脳部をはじめ指導者層はすべて本土から派遣され,急速に日本化が推進されたが,本土と同じ自治制度となったのは1920年であり,本土と異なる差別的な特殊事情が存続した。また経済的にも本土の資本や商人の進出で不安定であった。太平洋戦争末期,沖縄は激しい攻防の戦場となり,住民は大きな被害をうけた。'45年アメリカ軍に占領され,以後その軍政下に置かれた。'51年サンフランシスコ平和条約締結以後も,第3条の規定によってアメリカの権力下に置かれたので,住民の自治権は限られ,生活は基地に左右された。悲願の日本復帰運動は '72年に実を結び,沖縄は新しい道を進むことになり,'75年には海洋博覧会が開催された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「沖縄」の解説
沖縄(おきなわ)
1872年,明治政府は琉球(りゅうきゅう)国を琉球藩に吸収し,国王を藩王としたが,その帰属をめぐって中国との間になお抗争が続いていたため,79年に琉球藩の廃止と沖縄県の設置を断行した。帰属問題は未解決な課題を残していたが,日本が日清戦争で勝利したことでその問題は決着するに至った。しかし太平洋戦争末期には大激戦地となり,民間人を含む多数の戦争犠牲者を出した末にアメリカ軍に占領された。その結果,1951年のサンフランシスコ講和会議によりアメリカ施政下に琉球政府が置かれた。その後長い間の交渉と国際状況の変化により,71年に沖縄返還協定が締結され,翌年5月に日本に返還された。ただ返還後もアメリカ軍の基地移転やアメリカ兵犯罪の処置などをめぐって今なお多くの問題を抱えている。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の沖縄の言及
【琉球】より
…沖縄の別称。1372年から1879年までの約500年間,沖縄の公式名称として用いられた。…
【八重山地震津波】より
…1771年4月24日(明和8年3月10日)午前8時ころ,〈石垣島付近東南東数十粁の処を東北東西南西に走る線〉を震源地とし,マグニチュード7.4の地震が発生した。その結果,まもなく未曾有の大津波が八重山・宮古両列島(現,沖縄県)の島々村々を襲った。津波の被害が甚大で,〈明和の大津波〉とも呼ばれる。…
【琉球処分】より
…沖縄の廃藩置県のこと。明治政府は王国体制のまま存続しつづける琉球の処遇について画策し,1872年(明治5)9月,琉球王国をひとまず〈琉球藩〉とし外務省の管轄とした。…
※「沖縄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
今日のキーワード
排外主義
外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

 日本最南端の県。
日本最南端の県。 沖縄県、
沖縄県、