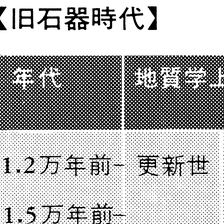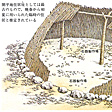精選版 日本国語大辞典 「旧石器時代」の意味・読み・例文・類語
きゅうせっき‐じだい キウセキキ‥【旧石器時代】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「旧石器時代」の意味・わかりやすい解説
旧石器時代 (きゅうせっきじだい)
Pal(a)eolithic
人類の歴史上最古の,そして最も長い時代であり,約300万~200万年前に始まり,約1万年前に終わった。中石器時代,新石器時代がこれに続く。1865年に初めて旧石器時代を定義したJ.ラボックは,ヨーロッパではすでに絶滅してしまった野生動物とともに人類が生活していた時代であるとした。これは地質学上からいえばほぼ洪積世に相当する。当時の人類は,食料を獲得する方法としては狩猟と採集だけに頼っており,牧畜や農耕をまったく知らなかった。道具としては打ち欠きによって作られた石の刃物を主体としたが,例外的には磨製の石器も知られている。また石の道具以外にも,木や角,骨,牙などの材料が用いられた。土器はほとんど,あるいはまったく作られなかった。200万年以上にわたった旧石器時代は,その文化および人類の違いにより,前期,中期,後期の3期に区分される。
ヨーロッパ,アフリカ
前期旧石器時代
約300万~200万年前から約8万年前までの長期間続き,初めは猿人(アウストラロピテクス)が,そして後半には原人(ホモ・エレクトス)が主人公として活躍した。200万年前よりさらに古い人類およびその文化についてはまだ十分な調査と研究がなされていないが,エチオピアのハダールやトゥルカナ湖に流入するオモ川流域のシュングラなどからは,270万年から240万年前と推定される石器が発見されている。これらの資料を別にすると,これまでに人類史上最古の遺跡としての確証があげられているのは同じくアフリカ東部にあるタンザニアのオルドバイ渓谷である。この渓谷は長さ40km,深さが100~130mもあり,下部洪積世の堆積層までも谷が刻みこまれている。ここには,前期旧石器時代のすべての時期の遺物が,多量にしかも層位的に出土するという意味で,世界で最も注目されている遺跡群がある。リーキーは1931年からオルドバイ渓谷の調査を始め,20年以上の年月をかけて多くの地点から層位的に出土する前期旧石器時代の石器群と動物化石とを発見した。人類化石はなかなか見つからなかったが,59年にメアリー夫人が地層中に原位置を保っている人類の歯3本と,岩屑の中から〈こめかみ〉の破片を発見し,下顎を欠くものの,ほとんど完全に復元できるまでの頭骨の破片を集めることができた。人骨に伴う9個の石器,176点の剝片,石のハンマー,小型獣の骨,大型獣の幼獣の骨の破片も採集された。この人骨の年齢は16歳くらいと推定され,リーキーによってジンジャントロプス・ボイセイZinjanthropus boiseiと命名された(現在の学名はパラントロプス・ボイセイ)。オルドバイの最下層である第I層をカリウム・アルゴン法で測定したところ,ジンジャントロプスの年代は実に175万年前であることがわかった。これはそれまで人類の起源を約100万年前としていた世界中の人類学者も考古学者も,ほとんど耳を疑ったほどの衝撃的な年代であった。64年に,リーキーはジンジャントロプスよりもさらに下層から,より進歩した形質をもった人骨が発掘されたという発表を行った。リーキーはそれにホモ・ハビリスという名前をあたえ,オルドバイ第I層の石器を製作したのはジンジャントロプスではなくて,このホモ・ハビリスであったに違いないという新見解を示した。しかも前に発見されたジンジャントロプスは石器製作の能力がなく,ホモ・ハビリスの手にかかって殺されえじきとなった生物ではあるまいか,とさえ考えられるようになった。200万年から100万年前までのアフリカには,3種類の猿人が生息していたが,のちの原人に進化する能力をもっていたのはホモ・ハビリスだけであったというのである。
オルドバイ渓谷では,ほぼ100万年前を境界として,前期旧石器時代文化が二つに分かれている。古い方は猿人の手になったオルドバイ文化で,チョッパーやチョッピングトゥールを主体としている。これらの石器は,自然礫の一端だけに加工した単純なもので,片側から打ち欠いたのがチョッパー(片刃の礫器),両側から打ち欠いて刃をつけたのがチョッピングトゥール(両刃の礫器)と呼ばれている。およそ100万年に近い長期間を,猿人はこれら二つの石器を作り続けたのだが,そのほかにも小型の剝片に加工してスクレーパー,錐,尖頭器,彫刻刀などの工具をも作り出していたことが最近になって明らかにされた。石器製作の際に用いられた石のハンマーも出土している。100万年前以後,新たに主人公として出現した原人は,チョッピングトゥールを改良した新しい器種としてのハンド・アックスを創作した。これはチョッピングトゥールの先端を引き伸ばした形態をもち,両側辺を両側から打ちはがした石器である。初期のものは基部に礫の自然面がそのまま残されており,この形が第Ⅱ層上半から第Ⅲ層まで続く。第Ⅳ層に入るとハンド・アックスの製作技術がさらに進み,両面加工によって木の葉のような形に仕上げられた。実験的な観察によると,鹿角のような軟質のハンマーの使用によって,石の割り取り方の精巧さが増すことが確認されている。先端がとがらず〈ちょうな〉の刃先のようになったクリーバーも新たな器種として加えられた。スクレーパー,錐,尖頭器,彫刻刀などの小型工具も作られた。
アフリカからヨーロッパへ移住した最初の人類は,おそらく150万年前から70万年前の間にジブラルタル海峡を渡ったのではないかといわれている。その頃の人類の遺骸は未発見であり,それが猿人であるか原人であるかは不明だが,オルドバイ文化に属すると思われるチョッパーやチョッピングトゥールが,フランスのバロネ洞窟,シラク遺跡,スペインのビュイグ・デン・ロカ遺跡などから発見されている。70万年前から40万年前になると,アフリカ起源のハンド・アックスを特色とする文化(アシュール前期文化)がヨーロッパに広がった。この時期の遺跡からは原人の化石がかなり発見されており,とくにフランス南部のアラゴ洞窟出土の原人頭骨は著名である。この洞窟からはハンド・アックスを含む10万点以上の石器と共に,50点にのぼる原人化石破片が出土した。またアルデーヌ遺跡では礫を敷きつめた住居と思われる遺構が検出された。火の使用の痕跡が認められるのもだいたい40万年前あたりからである。フランス南部のニース市内にあるテラ・アマタ遺跡は,当時の海岸砂丘の上に残されており,周囲を石で囲んだ楕円形の住居跡が何層にも重複して発見されたが,住居の中央には北側に風よけの石を並べた炉が設けられていた。この遺跡からはゾウやヤギュウのような獣骨多数のほかに,海からとれた魚骨が発見されており,すでに原人が海からも食料を得ていた事実が明らかになった。40万年前から8万年前まではハンド・アックス文化の発展期(アシュール後期文化)であり,遺跡の数も格段に増加し,精巧な作りのハンド・アックスが多産され,石器製作上の新技法であるルバロア技法が開発された(アシュール文化)。おもしろいことに,ハンド・アックス文化に並行しながらオルドバイ文化の伝統を強く残すチョッパー・チョッピングトゥール文化が,ヨーロッパの北部から東部にかけて分布し,さらにパキスタン,インド北部から東南アジアおよび東アジアにまで達していた。一方,ハンド・アックス文化はアフリカからヨーロッパ,中近東からインド南部にかけて広大な分布圏を形成した。
中期旧石器時代
約8万年前から約3万5000年前まで続いた旧人(ネアンデルタール人)の時代であり,地質学上では最終氷期の前半に相当する。ヨーロッパにはネアンデルタール人によって残されたムスティエ文化の遺跡が広く分布している。とくに研究の進んでいるフランスでは,(1)典型的ムスティエ文化,(2)キナ・フェラシー型ムスティエ文化,(3)鋸歯縁石器ムスティエ文化,(4)アシュール系ムスティエ文化という4系統の文化が同時期に入り組んで痕跡を残している。これらの遺跡に共通する特色としては,程度の差こそあるが,石器製作の基本的な技術としてルバロア技法が用いられていることである。この技法は,あらかじめフリントの原石を亀の子形に加工調整しておき,最後の打撃によって1個の逆三角形石片(ルバロア型剝片)をはがし取る方法であり,このとき残った方をルバロア型石核もしくは亀の子形石核と呼ぶ。この方法によって作り出された逆三角形のルバロア型剝片は,両側辺と先端部が鋭利なので,そのまま武器あるいは利器として用いることができたし,また再加工によって尖頭器,スクレーパー,ナイフなどに仕上げることもできた。したがってこの方法は,自然の円礫に最初のハンマーを打ち下ろすときには,製作者がすでに最終的に得られる剝片の形を想定しているという,きわめて計画的な作業であったといってよい。ネアンデルタール人はかなり高度の知能をそなえていたことになる。
ムスティエ期の人類は洞穴を利用して住むことが多かったが,平地住居としてはウクライナのドニエストル川南岸にあるモロドバI遺跡からの報告例がある。8m×9mのほぼ楕円形にマンモスの骨をめぐらし,その内側に数ヵ所の焼土があるだけの単純な構造である。フランスのコンブ・グルナルCombe-Grenal洞窟では,入口近くに打ち込んだと思われる深さ21cmの柱穴が発見されたが,先端が細くとがらされている。
1856年,ドイツ南西部にあるネアンデルタール(タールは〈渓谷〉の意)の洞窟から偶然に1個の化石人骨が発見され,その名前をとってネアンデルタール人という名前が生まれたのだが,その後ヨーロッパ,西アジア,北アフリカなどから発見されたネアンデルタール人の遺骸の数は実に150体以上に達している。ヨーロッパのムスティエ文化人は彼らの間に死者が出たときに穴を掘って埋葬したといわれてきたし,最近では前記のコンブ・グルナル洞窟から楕円形の穴の中に埋葬して,その上に丸い石を配置した例が報告されている。イラクのクルディスターンにあるシャニダール洞窟からは1960年に9体のネアンデルタール人骨が発掘されたが,それらのうち4体は落石による事故死,他の4体は埋葬されたものと判定された。とくにシャニダール4号人骨は三方を石で囲まれ,南枕で西を向き,左側を下にして横たわる成年男子であった。しかもこの墓には後で幼児1体と成年女性2体が合葬されたものと思われる。4号人骨の周辺の土壌の試料を取って分析したところ,キク科,ユリ科,マオウ科などを含む少なくとも7種類の花粉が集中的に検出された。これらの花は5月末から6月初旬にかけて咲くので,遺骸の埋葬された時期を推定することもできよう。ともあれ,ムスティエ文化の人たちは死者に花をそなえるという優しい心をもっていたのであろう。ネアンデルタール人は,それ以後の後期旧石器時代人や中石器時代人にくらべて長寿者が多かったといわれる。31歳から60歳までの年齢層では,ネアンデルタール人は35.8%,後期旧石器時代人は26.7%,中石器時代人は12.7%という結果が発表されている。また,かつてはネアンデルタール人は猫背で野獣のような顔や姿をもった野蛮な人類だという芳しからぬ評価が与えられていた。しかし今日では,特徴のある眼窩上隆起を別にすれば,彼らがその姿勢,器用な手,運動の能力などにおいて,現代の人類とほとんど違わぬところまで進んでいたことが,人類学者によって証明されている。フランスのペシュ・ド・ラゼからは黒鉛で作られたペンシルと石製のパレットが出土しているし,赤あるいは黒で着色された遺物の断片がしばしば発見されている。ムスティエ期の壁画が未発見であることから,彼らは彼ら自身の体に彩色を施したのではないかともいわれている。ドイツやスイスでは熊祭の痕跡が認められると主張する研究者もおり,新人の直接の祖先としてのネアンデルタール人の精神生活は,意外に進んでいたといえそうである。
後期旧石器時代
旧人にかわって新人が主人公となり,道具類の発達,狩猟技術の進展,芸術作品の制作などに見られるように,旧石器時代文化を最高に発達させた時代であり,約3万5000年前から約1万年前まで続いた。まず第1に注目しなくてはならないのは,石刃技法(ブレード・テクニック)の確立によって,石器の作り方が大きく進展したという事実である。石刃というのは,横断面が台形の細く長い石片であり,両側辺にはかみそりのように鋭利な刃をそなえている。フリントの自然礫を打ち欠いてまず円錐形あるいは円筒形の石刃核を作り,その上端の一部を鹿角のハンマーで強く打つと,みごとな石刃がはがれ落ちる。1個の石刃核からは,規格品としての石刃が10個以上も生産される。多量に生産された鋭利な石刃の周辺あるいはその一部を加工すれば,ナイフ,彫刻刀,錐,スクレーパー,槍先などの工具や武器ができ上がる。新鋭の工具は,骨,角,皮革,木材などへの加工を容易にし,生活を豊かにするためのさまざまの道具の発達を促したと推定される。骨や角を削ったり彫ったりして作られた道具には,槍先,銛先,錐,太い針,めどのある縫針,釣針,へら,短剣,石ランプ,石器をはめこむ柄または軸,ハンマーなどが知られている。その中でも鹿の角を削って彫刻を施した投槍器は,狩猟生活にとって画期的な発明であった。それは約30cmの長さに切られたトナカイの角で作られ,一端には投槍の基部をひっかけるための〈かぎ〉が作り出されている。この道具に投槍を着装して飛ばすと,遠心力の働きによってかなり遠くの獲物まで倒すことができた。人間の腕の長さを30cmも長くしたことになる。オーストラリアの原住民もウーメラという投槍器を用いており,単に腕だけで槍を投げたときにはせいぜい60mくらいしか飛ばないが,投槍器を用いた場合には約115mの飛距離が可能となり,とくに軽い投槍では200mまで届いたと記録されている。なお,これらの投槍器は,マドレーヌIV期になると作られなくなったらしいので,この頃になるとさらに有力な武器としての弓矢が出現して,投槍器は廃用されたのであろうとF.ボルドは述べている。
さらに〈旧石器時代のビーナス〉と呼ばれる女性小像が,ヨーロッパの南西部および中部に分布しており,さらに遠くシベリアのバイカル湖周辺からも発見されている。これらは主としてマンモスの牙を彫刻して作られたが,石灰岩や滑石,そしてまれには粘土製品も見られる。ヨーロッパから発見されている女性像は一般的に肉付きがよく,女性の性的特徴を強調した裸体像であって,眼,鼻,口,頭髪というような細部は省略したものが多い。これに対して,シベリアの出土例は扁平でほっそりしており,眼,鼻,口,頭髪などをはっきりと刻み込んでいる。すでにこのような東西の対照的な違いが生じていることも興味深い。
一方,フランス南西部からスペイン北部にかけて分布する多くの石灰岩洞窟の奥深いところに,旧石器人の手になったみごとな壁画や天井画が残されている。分布する地域の名をとってフランコ・カンタブリア美術と呼ばれる洞窟絵画の研究は,1868年にスペイン北海岸のサンタンデル県にあるアルタミラ洞窟において天井に描かれている多くのバイソンの絵が発見されたことに始まる。これまでにヨーロッパでは107ヵ所の洞窟から絵画や彫刻が発見されているという。旧石器人が描いた対象には,ウマ,バイソン,マンモス,ヤギ,ウシ,牝シカ,牡シカ,トナカイ,クマ,ライオン,サイ,イノシシ,カモシカ,シベリア・カモシカ,鳥類,魚類などがあり,ほかには人間およびモンスターといわれる不可解なものも知られている。写実的な絵画のほかにもさまざまな形の記号が残されており,人間の手形や男女の性器を描いたものもしばしば発見されている。壁画には多種の顔料が用いられていて,黒色,白色,赤色,黄色,紫色などがある。酸化鉄が黄土に滲み込んだ赤色オーカーがチョークのようにして用いられ,一端に孔をあけて紐を通し持ち歩いたと思われるものも出土した。
洞窟芸術はどういう目的をもって描かれ彫られたのか,という問題は多くの考古学者によって論じられているが,まだ決定的な答えは出されていない。これまでにも,それは人間本来の芸術的表現であるとか,生活環境を美化するためであるとか,狩猟の収獲を記念するためとか,あるいはまた狩猟の成功を祈るための共感呪術を意味するものであるとかの諸説が発表されている。しかし,A.ルロア・グーランは65ヵ所以上の洞窟と,2000点以上の絵画と彫刻を再調査した結果として,野生動物はウマを中心とするAグループと,バイソンを中心とするBグループとに分けられること,そしてBグループはつねに洞窟の中心部に位置してAグループによって取り囲まれている事実を認めた。ルロア・グーランはそこから,Bグループは女性を,Aグループは男性を意味する動物群であると解釈し,この考えを進めて絵画以外の種々の記号をも男性と女性に区別した。このような分析の結果として,洞窟芸術は旧石器時代人の多産と繁栄に対する祈念を豊かで複雑なシステムとして表現したものではないかと述べている。
後期旧石器時代人は洞窟の入口や岩陰をすみかとして利用した一方,段丘の上におそらく天幕の小屋を建てて住むことも多かった。ドルドーニュのムシダン地方その他から,方形に小石を敷き並べた遺構が発見されており,上部には皮革製の天幕が張られたのであろうといわれている。ウクライナでは,マンモスの頭骨,下顎骨,牙などで組み立てたドーム状の住居が発掘されているし,シベリアのマリタ遺跡では中央に炉をもつ円形の竪穴住居が発見されている。遺跡の中には,永続的な屯営地と,一時的な露営地とがある。彼らは決して放浪者ではなく,すでに半定住的な集落を営んでいたらしい。マドレーヌ期には川べりに残された露営地があり,彼らはそこでサケなどの漁労を行っていたらしい(マドレーヌ文化)。なおA.マルシャークの研究によれば,彼らはすでに太陰暦をもっていたといわれる。それは刻み痕の残された鹿角製の平らな板で,69個の蛇のようにうねって連続する点状の刻みが彫られているが,よく調べてみると刻みには円形,半円形,三日月形などの変化があり,69個の刻みを彫るのに24個の違った道具を用いていることがわかった。マルシャークはこの板には69日間の月齢の変化が記録されているのだと主張している。彼らの食料は主として野獣であったが,南フランスのソリュートレ期の遺跡では1万頭に達するウマの骨が発見されている。その他トナカイやウシも多く捕食されたが,中部ヨーロッパから南ロシアでは,マンモスが最も多く,次いでウマ,カモシカ,ホッキョクキツネ,ホラアナグマ,ライチョウなどの骨が認められている。もちろん肉類のほかにも木の実,草の根,キノコなどが食料に供されたのであろう。
東アジア
中国ではシナントロプス・ペキネシス(北京原人)の遺骸を出土した北京市の周口店遺跡をはじめとして,これまでに23ヵ所の前期旧石器時代遺跡が報告されており,そのうち10ヵ所から原人化石が発見されている。これらの中で最も古いといわれているのは,山西省西侯度の地表下60mの砂礫層から出土した石器であり,古地磁気年代によって約180万年前と推定されている。石器にはチョッパー,チョッピングトゥール,スクレーパー,大型三稜尖頭器その他があり,伴出する動物化石には洪積世初頭に属する剣歯虎,三門馬のほかにサイ,ヤギュウなどが見られる。雲南省元謀からは人類の門歯2本と数点の石器が出土し,29種類の哺乳動物の化石が伴出した。この年代もまた170万年前と推定されている。上記の年代が確実であれば,西侯度と元謀の資料はアフリカのオルドバイ文化に対比されるものであり,中国にも猿人(アウストラロピテクス)の文化が存在したことになる。また約100万年前の人類頭蓋骨と顔の一部の化石が陝西省藍田県公王嶺から発見され,石器と哺乳動物化石も伴出した。山西省 河(あんが)では黄土の下の砂礫層中から,公王嶺と同時期のチョッパー,チョッピングトゥール,スクレーパー,三稜尖頭器などの石器138点が発掘された。河北省東谷坨では地表下45mの泥河湾層中から約2000点の石器と切断痕のある多くの動物の骨などが発掘され,これも約100万年前までさかのぼるといわれている。
河(あんが)では黄土の下の砂礫層中から,公王嶺と同時期のチョッパー,チョッピングトゥール,スクレーパー,三稜尖頭器などの石器138点が発掘された。河北省東谷坨では地表下45mの泥河湾層中から約2000点の石器と切断痕のある多くの動物の骨などが発掘され,これも約100万年前までさかのぼるといわれている。
北京市の周口店にある石灰岩の洞窟は,約60万年前から15万年前まで続いたシナントロプスの遺跡であり,1927年以来長期間の発掘調査が続けられている。これまでにほぼ完全な頭骨6点を含む約40体分の人類化石,10万点に上る石器,骨角器,焼けた骨などのほかに多数の動物化石が発見されている。シナントロプスは生活のために火を使用しており,石英脈岩を打ち割って小型のみごとな石器を作っていた。石器としてはチョッパー,チョッピングトゥール,スクレーパー,尖頭器,彫刻刀,錐,ハンマーなどがあり,台石の上においた原石を石のハンマーで打ち割るという両極打法(バイポーラー・テクニック)を用いているのが特徴的であった。彼らが捕食した動物としては,剣歯虎,ハイエナ,ヒョウなどの肉食獣をはじめとして,ゾウ,サイ,ウマ,ウシ,スイギュウ,ラクダ,イノシシ,ヒツジ,カモシカ,オオツノシカなどが知られている。
シベリアでは,アムール川中流域にあるフィリモシュキおよびクマラ遺跡,さらにオビ川上流にあるウラリンカ遺跡などから,チョッパー,チョッピングトゥールを含む前期旧石器が発掘されている。また韓国では1978年に発見された京畿道漣川郡の全谷里遺跡で,東アジアでは初めてのアシュール系ハンド・アックス文化が確認された。どういうルートを通ってハンド・アックス文化が朝鮮半島の中央部に達したのかは,今のところ未解決の問題である。
東アジアでは,中期旧石器時代文化がヨーロッパのように明確には認められていない。シベリアではアルタイ山麓のウスチ・カン洞窟やエニセイ川流域のドブグラスクなどからムスティエ文化に近い石器が発見されているがまだ数は少ない。中国では8万年前から3万年前までの遺跡として山西省の丁村遺跡が考えられているが,まだ確定的ではない。人類学的に見た場合には,丁村人,馬壩人,周口店の第15地点人,同新洞人,同第22地点人などが旧人の仲間であろうといわれている。したがって東アジアでは,ヨーロッパ的なムスティエ文化のかわりに,地方色の強い文化が続いたのであろう。
後期旧石器文化についてはかなり明らかになってきている。シベリアではバイカル湖周辺にマリタおよびブレチ遺跡があり,ヨーロッパと同じ系列の象牙製ビーナス,マンモスの骨板に彫られたマンモスの線刻画,骨角製の装飾品,骨角器などが発見されている。ヨーロッパからシベリアまでの遠距離を彼らがどういう方法で踏破したのかは不明だが,雪や氷で覆われた地域でのそりの使用が考えられている。中国にも約3万年前以降になると石刃やナイフを主とする文化が出現し,山西省の峙峪(じよく),水洞溝,下川,虎頭梁など多くの遺跡が発見されており,1933,34年には周口店の山頂洞から化石人骨9体が出土し,それらに副葬されたみごとな装飾品も発見されている。
アメリカ大陸
アメリカ大陸へ最初に足を踏み入れた人類はおそらく後期旧石器時代終末期の新人であり,そのルートは海面低下のために陸化していたベーリング海峡(ベーリング陸橋)を渡ったのであろうといわれている。北アメリカで確実に知られる最古の文化はクロービス文化やフォルサム文化であるとされる。これらはパレオ・インディアン文化と総称され,押圧剝離技法で作られた特徴的な両面加工尖頭器を伴う。いずれも1万5000年前以後のものだと考えられている。しかしアメリカ大陸にはこれよりさらに古い文化があると考え,カナダ北西部のオールド・クロウで発掘された人類の手によって加工された骨器などの存在をもとに,最古の移住者は約8万年から15万年前までさかのぼると主張する研究者もいる。しかしこれらの古い時期に関してはまだ不明な点が多い。
日本
日本にも旧石器時代の人間が住んでいたのではないかという問題について,1911年にN.G.マンローが,そして31年には直良信夫が具体的な資料を提示したのだが,いずれも学界からは相手にされなかった。日本に旧石器時代は存在しないという長い間の学界の通説が破られたのは,49年,群馬県岩宿の関東ローム層中に包含されている石器を相沢忠洋が発見してからであった。その後約30年の間に,北海道から九州までの日本全土から旧石器時代の遺跡が続々と発見され,現在ではすでに3000ヵ所以上に達している。これらの遺跡の大部分は立川ロームおよびそれと同時期の地層に含まれているので,すでに新人が出現していた大陸の後期旧石器時代に対比されてよい。
日本の後期旧石器人は川や湖に面した段丘上に住むことが多く,しかも1ヵ所に長期間定住するということもなかったらしい。住居の跡が鹿児島県上場(うわば)遺跡ほか数ヵ所から発見されている。円形もしくは楕円形の浅い竪穴住居や平地住居で,周囲には柱を立て,内部中央には石囲みの炉が設けられていた。屋根はおそらく皮革で張られた天幕のようなものであったと思われる。これまでのところ出土遺物は石器と石製品に限られている。これは包含層が酸性土壌であるために,骨や角のような動物性遺体が酸化して消失してしまったからである。石器の材料としては硬質ケツ岩,黒曜石,安山岩,チャート,スレートなどが選ばれており,器種にはナイフ,彫刻刀,錐,スクレーパー,尖頭器,石斧,ハンマーその他があり,ほぼ5000年くらいの幅で器種や組成に大きな変化があらわれている。約2万5000年前からヨーロッパと同じような石刃技法が出現し,約2万年前からはナイフをはじめとする各器種の変化が著しくなり,約1万5000年前からは細石器という名で呼ばれる組合せ道具としての細石刃が発達する。石器以外の石製品としては,緑泥片岩を用いたこけし形石偶が大分県岩戸遺跡から発掘されており,また北海道湯の里遺跡および美利河(びりか)遺跡では,ともに暗緑色の石製ビーズが出土した。前者はべんがらを散布した墓壙の底から発見されたという。前記岩戸遺跡では,握り拳大の河原石を並べた配石墓が発見され,その中からは微細な人骨の細片4点とアワビとイシダタミの貝殻が検出されたと報じられている。
ヨーロッパとの相違点として,約2万5000年前から局部磨製石斧が出現し,以後東日本では広く用いられたことが挙げられるが,この問題については学界になお論議が続いている。約1万2000年前になると,北海道から中国,四国までの広範囲に有舌尖頭器文化が広がったが,九州には細石刃文化の伝統が残るとともに,土器の製作が開始される。長崎県福井洞穴第3層からは,細石刃と隆線文土器が伴出し,炭素14法による年代は1万2400±350年前を示した。これは今のところ世界最古の土器である。土器製作はやがて有舌尖頭器文化圏に伝えられ,そのまま約1万年前以降の縄文土器文化の誕生につながると考えられる。したがって,約1万2000年前から1万年前までは旧石器時代から縄文時代への過渡的な時期で,大陸での中石器時代に相当する。
3万年以上前の日本に旧人もしくは原人の文化が残されているかどうかについては,いくつかの遺跡が知られている。まず1964年には大分県早水台(そうずだい)遺跡の基盤直上から石英脈岩製のチョッパーやチョッピングトゥールが発掘され,65年から78年にかけて調査された栃木県星野遺跡では,武蔵野および下末吉ロームに相当する地層中からチョッパー,スクレーパー,尖頭器,彫刻刀などを含む大量のチャート製石器が出土した。早水台遺跡は約10万年前,星野遺跡は3万2000年から約8万年前までさかのぼると推定された。岡山県の蒜山(ひるぜん)高原からも明らかに3万年以上前の地層から石英製石器が発掘されているので,将来は日本における旧人・原人の遺跡が各地から姿を現すに違いない。
日本旧石器時代の人骨については,1929年に発見されて話題となった明石(あかし)原人(明石人)の腰骨をはじめとして,葛生(くずう)人,牛川人,三ヶ日人,浜北人,港川人などが報告されたが,いずれの場合も考古学上の遺跡から旧石器を伴って出土したものではないために,いま一つ説得力がない。旧石器と共存した資料としては,残念ながら大分県聖嶽(ひじりだき)洞穴の頭骨破片と,前記の同県岩戸遺跡出土の右側上顎犬歯および切歯の細片4点があるだけである。
執筆者:芹沢 長介
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「旧石器時代」の意味・わかりやすい解説
旧石器時代
きゅうせっきじだい
石器時代を石器の製作法のいかんによって、旧石器時代、中石器時代、新石器時代に三分した場合の最古の時代をいう。old stone ageあるいはpaleolithic ageの訳語。石器時代とは、器具の材料に主として石が使用された時代という意味ではなく、冶金(やきん)術が発明・採用される以前の時代のことである。したがって、ある文化において、おもに木器ないし骨角器が製作・使用されていても、冶金術が知られていない以上、それはやはり石器文化であって、木器文化ないし骨角器文化ではない。旧石器時代とは、石器の製作に喙敲(かいこう)法または磨研法が知られず、もっぱら敲打(こうだ)法によって石器がつくられていた時代をさしている。ただし、石器の製作法に関しては、次の中石器時代のそれとは基本的な相違が認められないため、学者によっては、中石器時代を旧石器時代の末期、すなわち晩期旧石器時代とみなし、独立した時代として中石器時代の存在を認めない場合も少なくない。
旧石器文化が行われたのは、おもに地史上の更新世(洪積世)であるが、更新世というのは、旧石器時代を規定するうえで絶対的な条件とはならない。なぜならば、周辺的な諸地方では、旧石器文化は停滞し、完新世(沖積世)に入ったのちも行われていたからである。旧石器時代人は、今日では絶滅してしまった哺乳(ほにゅう)類動物(マンモス、毛犀(もうさい)のような)と共存することが多かったけれども、これまた旧石器時代を規定するうえで必須(ひっす)の条件とはなっていない。
[角田文衛]
研究史
旧石器時代の遺物の存在は、ヨーロッパでは早くから識者の注意に上っていたが、『旧約聖書』に呪縛(じゅばく)されていたため、学界においても正式にこれが取り上げられることはなかった。1838年に至ってフランスのブーシェ・ドゥ・ペルトBoucher de Perthes(1788―1868)は、ソンム川の河岸段丘で絶滅種のゾウやサイの遺骨とともに多数のフリント製の石器類を発見し、人類が更新世に生息していた事実を証明した。その時分から旧石器の発見は各地で報じられ、学界もようやくこの事実を認めるようになった。この機運に乗じてイギリスのラボックは、石器の製法に基づいて石器時代を二分し、古いほうを旧石器時代、新しいほうを新石器時代と名づけた(1865)。その後、旧石器時代の研究調査は、フランスを中心にラルテ、ド・モルティエらによって急速に推進されたが、後者が西ヨーロッパを主として樹立した編年(時期区分)――いわゆるモルティエ編年――は、もっとも権威あるものとして、1930年代に至るまで学界に通用していた。
20世紀に入ると、フランスやスペイン北部では旧石器時代後期の洞窟(どうくつ)絵画の発見が相次いだし、西ヨーロッパや北アフリカばかりでなく、ヨーロッパの中部、南部、東部、さらには北部、またオリエント、アフリカ各地、インド、シベリア、中央アジア、中国、インドネシア、アメリカ大陸の各地において旧石器時代の遺物・遺跡が続々と発見された。これに並行して猿人、原人、旧人、新人の遺骨も各地で検出され、これらを通じて旧石器文化の様相はとみに判明してきた。なかでも中国の周口店(しゅうこうてん/チョウコウティエン)における北京(ペキン)原人の遺骨や彼らが使用した石器の発見は、東アジアにおける旧石器文化の研究の端緒となった。日本でも、1949年(昭和24)群馬県の岩宿(いわじゅく)遺跡において旧石器文化の存在が確認されて以来、全国にわたって旧石器時代各期の遺跡がおびただしく発見され、研究は爆発的に進捗(しんちょく)した。朝鮮半島でも、1950年代から旧石器時代の遺跡が検出され始め、研究調査は活発に進められている。
[角田文衛]
研究法
旧石器文化は主として更新世に行われたもので、その年代的範囲は200万年以上にわたっている。したがって旧石器時代の研究調査は、考古学を主役としながらも、自然科学系の諸学、すなわち地質・地史学、雪氷学、岩石学、土壌学、古生物学、古地理学、古人類学などとの協力が絶対に必要である。また遺跡の年代決定に関しては、さまざまな物理学的方法が採用されている。さらに遺跡の年代や古景観を明らかにするためには、花粉や火山灰の分析、土壌の粒度分析などが行われている。石器の用途の研究には、顕微鏡による使用痕(しようこん)の検査が不可欠である。さらに古生物学による当時の動物相や植物相の究明は、旧石器文化の生態学的研究に基本的な役割を担っている。
旧石器時代の遺跡は、第一次遺跡と第二次遺跡とに大別される。第一次遺跡とは、人間が生活した「原位置」に存在、または堆積(たいせき)した遺跡を称し、これには住居址(し)、製作址、洞窟、岩陰、埋葬址などの種別がある。洞窟には石灰洞窟が圧倒的に多いが、このうち奥行の深い、トンネル状のものを洞穴といい、奥行の短いものを岩窟とよんでいる。これらに対して庇(ひさし)状の、ときとして岩壁の裾(すそ)に営まれた住居址は、岩陰と称される。洞窟や岩陰には、しばしば明確な層位をなして堆積した包含層がみられ、それらは研究上、役だつことが多い。
第二次遺跡とは、第一次遺跡から押し流された石器類が、動物の遺骨などとともに当時の河床や湖底に堆積した砂礫(されき)または粘土の中に包含されている遺跡のことである。河床は時とともに深く削られていくから、第二次遺跡は河岸段丘にみられることが多い。アシュール文化の名祖となったフランス北部のサン・タシュール遺跡などは、河岸段丘の遺跡の好例である。この種の河岸段丘遺跡の年代決定には、地形学の協力を欠くことができない。
遺跡から発見される遺物の多くは、石製の器具、すなわち石器であるが、そのほか骨角器、木製品(希少)、石・骨角・粘土などでつくられた彫像、同じく石・骨角・貝などを用いた各種の装身具などもみられる。粘土で造形し火で焼いた土偶や動物像は、旧石器時代後期の特別な遺跡から出土するが、土器、すなわち窯(かま)で焼成した粘土製の容器は、まだつくられなかった。石器の研究には、石質の検討、原石の産地の究明、出土した層位と関連しての型式学的考察と分類、製作法や用途の考究、統計学的な処理などのように多角的な検討が要請される。埋葬や祭祀址(さいしあと)は、住居址に関連して発見されるのが常である。アルタミラ、ラスコー、フォン・ド・ゴームなどの洞穴にみられる壁画は、洞内の祭祀所の側壁や天井に描かれたものであるが、その年代がきわめて古きにさかのぼることは、壁面を覆った石灰質の皮膜からも想察される。
[角田文衛]
生活と文化
旧石器時代の大きな特色は、人々が獲得経済で生きていたことである。すなわち、彼らの生業は、自然物の採集と狩猟であり、後期に入ってから漁労が一般化したが、後期には植物栽培も行われたようである。彼らの社会の単位は群herdであったと推定される。後代に比べると人々の定住性はまだ弱かったが、彼らはあてどもなく漂浪していたのではなく、一定の領域をもち、その領域の適宜な場所に定住するか、季節によって領域内で移動するといった生活形態がとられていたらしい。彼らにとってもっとも重要な生産手段である猟場、漁場などは、群共同体の共有であり、その点では彼らの社会は原始共産社会であった。またそれは、前階級社会でもあったが、年齢による階層の別は厳存していたようである。
旧石器時代に関しては、世界各地におびただしい数に上る「文化」が設定されている。ここでいう「文化」とは、一定の地域における一定の期間の諸遺物(とくに石器)の特殊な組合せのことである。これら多数の文化を年代的に系列化し、また空間的に配列することによって、旧石器時代文化の様相、動向、相互関係などが追究されるが、主として石器を資料としており、その石器類が変化に富んでいるため、そうした体系的、総合的研究は、すこぶる困難である。しかし数多い諸文化を巨視的に眺めると、旧石器文化の動向は、3期に分けて理解することができる。
前期は、東アフリカのオルドワイ文化、西ヨーロッパのバロネ文化、アブビル文化などを代表とするもっとも原初的な文化の時期であって、きわめて悠遠な年月、すなわち、ヨーロッパでいえば、それはギュンツ氷期からミンデル氷期の前半に及んでいる。石器は、礫(れき)の一端に撃打を加えてつくった打器、礫の両面に粗い剥離(はくり)を加えた祖形握槌(にぎりつち)、粗大かつ不整形の剥片石器などである。知られている遺跡の大部分は第二次的なもので、住居址はわずかしか検出されていない。
中期は、ヨーロッパのムスティエ文化、ミコック文化などによって代表される時期である。中期には、火の使用も知られたし、岩窟住居も始められた。石器としては、両面に加工した握槌、二等辺三角形の尖頭(せんとう)器、半月状の掻(そう)器、あらかじめ石核の打面を調整したうえで剥取された剥片石器が特徴的である。中期には、大形哺乳(ほにゅう)類動物を対象とする狩猟が盛んとなった。中期の文化を担ったのは旧人――ネアンデルタール人のような――であった。
後期の文化は、約3万年前から1万2000年ほど前に行われたが、それはヨーロッパではもっとも厳しい氷期であるビュルム氷期にあたっていた。世界のどの地域でも、後期の文化を担ったのは、新人であるホモ・サピエンスであった。当期の石器は、主として縦長の石刃(せきじん)を用いて製作されたが、その特徴は、形が小さくなり、先端が鋭くつくられたことと、用途に応じて形が分化したことである。ことに彫器は変化に富んでいる。小さい尖頭器の存在は、弓矢の発明と個人狩猟の開始を示している。骨角器の製作・使用も盛んであり、指揮杖(づえ)、銛(もり)、針、鉤針(かぎばり)などがみられた。西ヨーロッパでは、みごとな洞窟絵画が多数描かれたが、それらの時期区分には困難な問題がある。また石や骨を用いた彫像、石・骨・牙(きば)を材料とした刻画の類も多数みいだされている。これらの美術作品や埋葬によって当時の美術や宗教もかなり明らかにされている。集落の規模も大きくなり(とくにプシェッドモスト文化)、また岩窟や岩陰に加えて洞穴も居住に用いられた。これは、石製のランプの発明と関連していた。ただし、洞穴の場合、人々が居住したのは入口と前庭(テラス)であって、奥のほうは祭祀や貯蔵のみに使用されていた。
高い水準にまで達した旧石器時代後期の文化も、氷河時代の終末に伴う自然環境の激変によって下降し、やがてそれは、中石器文化へと移行した。しかし周辺諸地域では、なお長く旧石器時代的な文化が遺存した。この傾向は、北部を除くアフリカにおいて顕著であった。極北旧石器文化なども、ユーラシア北部のツンドラ地帯に停滞していた旧石器文化であった。
アメリカ大陸は、長い間無人の境であったが、後期に至ってシベリア方面から人間の渡来がみられた。アメリカ大陸では投げ槍(やり)による大形の哺乳類動物を対象とする狩猟が活発に行われ、フォルサム文化のそれにみるとおり、中形で鋭い両面加工の尖頭器(石槍)が盛んに使用された。「新大陸」では、適当な猟獣や食用の植物に恵まれていたためもあって、「旧大陸」に比べて、その文化はより長く旧石器時代にとどまっていた。
[角田文衛]
日本
日本旧石器時代の発見
1911年(明治44)イギリス人医師N・G・マンローは、神奈川県酒匂(さかわ)川や早川の段丘礫層(れきそう)を発掘して得たという旧石器類似資料をその著書のなかに発表した。また直良信夫(なおらのぶお)は、31年(昭和6)兵庫県明石(あかし)市の海岸に露出している更新世(洪積世)の砂礫層中から掘り出した資料を、旧石器時代の石器として学術雑誌に発表し、さらに崖(がけ)下の崩土中から人類の腰骨化石をも発見した。のちに「明石原人」として問題になった人骨である。しかし、日本の考古学者や人類学者の大部分はこれらの発表を認めようとはせず、更新世の日本は無人の地であったと考え続けてきた。ところが49年(昭和24)になって、群馬県桐生(きりゅう)市の南西約4キロメートルにある新田(にった)郡笠懸(かさかけ)町岩宿(いわじゅく)(現在みどり市)の切り通し道で、赤土の中から一部をのぞかせている黒曜石製の石槍(いしやり)を相沢忠洋(ただひろ)が発見したことから、旧石器問題は意外な展開を示すことになった。赤土というのは、1万年以上前の更新世に火山の爆発によって空に噴き上げられた火山灰がふたたび地上に降り積もってできた地層のことであり、地質学者によって関東ローム層と名づけられている。関東ローム層が一面に降り積もった時代の関東地方はおそらく死の火山灰地であり、そこには木も草もなく、人間の生活など考えることもできない、というのがそれまでの地質学者の考え方であった。ところが、そのような地層の中から、疑いのない石器が発見されたのである。同年10月、明治大学考古学研究室は岩宿遺跡の第1回目の調査を行い、関東ローム層中に含まれる上下2枚の旧石器文化層を確認することができた。上層の石器は黒曜石、瑪瑙(めのう)などを材料としてつくられており、概して小形で、切出形石器、周辺加工の尖頭器(せんとうき)、スクレーパーなどであった。これに対して、下層の石器は硬質頁岩(けつがん)をもってつくられ、比較的大形品を主とした楕円(だえん)形石器、スクレーパー、縦長剥片(はくへん)などがみられた。後者は岩宿Ⅰ文化、前者は岩宿Ⅱ文化としてそれぞれ区別された。
[芹沢長介]
岩宿発見後の旧石器時代遺跡
岩宿遺跡の発掘結果は、各地の若い研究者に刺激を与え、数年もたたないうちに、日本全国から同じような土器を伴わない石器の発見が相次いで報告され始めた。1951年7月には東京都板橋区茂呂(もろ)遺跡、1952年11月には長野県諏訪(すわ)市茶臼山(ちゃうすやま)遺跡、1953年には同県上水内(かみみのち)郡信濃町野尻(のじり)湖底杉久保遺跡、同県南佐久(みなみさく)郡川上村馬場平遺跡、さらに瀬戸内海に臨む岡山県倉敷市鷲羽山(わしゅうざん)遺跡、北海道紋別郡遠軽町白滝遺跡など、各地からの発見が積み重ねられていった。新しく注目されだした縄文時代以前の石器について、最初のころはかなり露骨な反対意見を表する研究者も少なくなかったが、このような研究が全国的な規模で行われ始めるようになると、反対者はしだいに沈黙してしまった。岩宿発見以来急速に研究が進展し日本全国から発見された旧石器時代遺跡の数は5000か所以上に達しており、発掘された石器は数えきれぬほどの膨大な量に上っている。
[芹沢長介]
関東ローム層の年代
考古学者によって関東ローム層の中に石器が包含されているという事実が知られてから、地質学者も新しい目で関東ローム層を見直し、再検討しようという機運が高まった。関東ローム層団体研究会が1954年(昭和29)に発足し、日曜日ごとに各地の巡検が繰り返された。その結果として、関東ローム層として従来漠然とよばれていた地層は、古いほうからいって多摩ローム、下末吉(しもすえよし)ローム、武蔵野(むさしの)ローム、立川ロームという4枚の地層が積み重なっている層群であって、それぞれのロームは多摩段丘、下末吉段丘、武蔵野段丘、立川段丘の上に堆積(たいせき)したものであることも知られた。その後、放射性炭素法(炭素14法)やフィッショントラック法などの、放射能による年代測定が関東ローム層に対して実施され、立川ロームは約1万年前から3万年前まで、武蔵野ロームは約3万年前から5万年前まで、下末吉ロームは約6万年前から13万年前まで、多摩ロームは13万年以上前、というような年代が測定されるようになった。したがって、石器の包含されているロームが何であるかがわかれば、その石器の古さもほぼ見当がつくまでになっている。
[芹沢長介]
旧石器時代の時期区分
今日まで日本から発見された旧石器の大部分は、立川ロームもしくはそれと同時期の地層に包含されているので、実年代からいうと約3万年前から1万年前までの間に含まれてしまうことになる。そして約2万5000年前から1万5000年前までは石刃、ナイフ、彫刻刀などが多くつくられ、約1万5000年前から1万2000年前までは細石刃が栄え、約1万2000年前から1万年前になると有舌(ゆうぜつ)尖頭器や片刃石斧(せきふ)のような新しい要素が加わり、北九州では土器製作が開始されたということがほぼわかってきた。ユーラシア大陸では、約3万年前から1万年前までを後期旧石器時代としており、日本の立川ローム期の石器はちょうどそれに相当することになる。それでは大陸の中期もしくは前期旧石器時代、すなわち3万年以上前の時代の日本には、人類が住んでいなかったのかという疑問に対して解答を与える資料の一つは、1964年(昭和39)に発掘された大分県速見郡早水台(そうずだい)遺跡最下層の石器である。早水台遺跡は下末吉段丘と同時期の河岸段丘上にあり、問題の石器は基盤直上の角礫(かくれき)層中から出土した。石器の原料は石英脈岩、石英粗面岩などであり、石器の種類には片刃および両刃の礫器(れっき)(チョッパー、チョッピング・ツール)、祖型握槌(にぎりつち)、尖頭石器、祖型彫刻刀、祖型楕円(だえん)形石器、鶴嘴(つるはし)形石器、剥片(はくへん)、石核などがある。さらに、65年以来5回にわたって栃木市星野遺跡が発掘され、星野第5文化層から第13文化層までは武蔵野ロームおよび下末吉ロームに包含されており、3万年前から約8万年前までの堆積である事実が判明した。また70、71年の2か年にわたって、群馬県岩宿遺跡の再調査が行われた結果、岩宿Ⅰ文化層の下位から、少なくとも5万年以上の古さをもつ石器群が大量に出土し、岩宿ゼロ文化と命名された。
これらの遺跡は、石器の材料、形態、組成、製作手法、出土層準などから判断して、大陸の中部、下部旧石器に対比されるものであり、3万年以上前の日本にも、旧人もしくは原人の仲間が住んでいたということがしだいに明らかになりつつある。
[芹沢長介]
『F・ボルド著、芹沢長介他訳『旧石器時代』(1971・平凡社)』▽『P・アッコー他著、岡本重温訳『旧石器時代の洞窟美術』(1971・平凡社)』▽『ジョン・ワイマー著、河合信和訳『世界旧石器時代概説』(1989・雄山閣出版)』▽『春成秀爾編、岡村道雄他著『検証日本の前期旧石器』(2001・学生社)』▽『白石浩之著『旧石器時代の社会と文化』(2002・山川出版社)』▽『藤本強著『石器時代の世界』(教育社歴史新書)』▽『芹沢長介著『日本旧石器時代』(岩波新書)』
百科事典マイペディア 「旧石器時代」の意味・わかりやすい解説
旧石器時代【きゅうせっきじだい】
→関連項目アジール文化|アブビル文化|上高森遺跡|細石器|沙苑文化|石器時代|芹沢長介|ソアン文化|中石器時代|デデリエ|日本人|パチタン文化|ブルイユ|北方ユーラシア文化|磨製石器|マリタ|モルティエ|鏃|ラスコー|ルバロア文化
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旧石器時代」の意味・わかりやすい解説
旧石器時代
きゅうせっきじだい
Paleolithic (Palaeolithic) Period
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「旧石器時代」の解説
旧石器時代(きゅうせっきじだい)
palaeolithic age
考古学上の年代区分の一つ。第四紀更新世(こうしんせい)に主として存在し,人類による加工または使用の明らかな打製石器を道具として使い,主に狩猟・採集を生業とし,まだ土器や磨製石器を知らない人類文化史上の一過程をいう。旧石器が初めて知られたのは,1846年のことで,北フランスのアブヴィル付近のソンム河谷の洪積層から絶滅種の動物遺骨とともにフリント製石器を発見したブーシエ・ド・ペルトに始まる。イギリス人ジョン・ラボックは磨製石器や土器を伴う既知の石器文化に対して,これらを旧石器文化と名づけたのである。その後,南フランスを中心に研究が行われ,編年(6期)が設定されるに至った。西の石核(せっかく)石器文化圏,東の剥片(はくへん)石器文化圏,さらに東南アジアのチョッパー文化圏といわれたこともある。また,人類が石器をつくりだしてから,原人から,旧人にかけての時代が前期,代表的な旧人のネアンデルタール人やアフリカや中近東における新人出現前後の時代が中期,ヨーロッパに現生人類が登場する前後から約1万年前までの時代が後期におおよそ相当する。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「旧石器時代」の解説
旧石器時代
きゅうせっきじだい
Palaeolithic Age
古くは猿人・原人・旧人の時代より始まり,末期には新人も誕生し,人類史の99%の長い期間にわたっている。すでに火の使用を知り,打製石器,そして末期には骨角器も使ったが,土器の使用を知らず,農耕栽培・牧畜飼育などもなかった。主として穴居 (けつきよ) 生活であったが,末期には簡単な住居もあった。旧石器時代の前に原石器時代をおく説もある。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「旧石器時代」の解説
旧石器時代
きゅうせっきじだい
更新世に相当。人類は血縁的な共同体を形成。採集経済を営み,利器として打製石器や骨角器を使用していた。日本では1949年,群馬県岩宿遺跡の調査の結果,その存在が証明された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の旧石器時代の言及
【古代社会】より
…
〔採取・狩猟・漁労を中心とする社会〕
この段階の原始社会は,先土器文化の時代と縄文文化の時代にわけられる。
【先土器文化の社会】
先土器文化の時代は前3万年前から前1万年前後までで,世界史的には旧石器時代の後期に相当するといわれている。まだ土器の製作を知らない時代である。…
【採集狩猟文化】より
…しかし,彼らの生活様式は,今日なお人類の原初的な文化の伝統を引き継いでいると考えられる。
[先史時代]
人類史の90%以上を占める前期旧石器時代は,ヒトの進化と文化の発達がきわめてゆっくりと進行した時代で,この時代の猿人(アウストラロピテクス)とそれに続く原人(ホモ・エレクトゥス)は,粗雑な加工の石核石器や剝片石器を有していたにすぎない。これらの石器は,狩猟用の武器というよりも,木槍や棍棒あるいは掘棒といった狩猟具,採集具の製作用具として,また,獲物を解体するための刃物として使用されたと考えられる。…
【先縄文時代】より
…先土器時代,無土器時代などの別称もある。しかし現在では,旧石器時代とよぶ人の方が多い。旧石器時代の語を避けて上記の名を使う根拠の一つは,旧石器文化が洪積世に属する人類文化を意味するのに対して,いま日本で旧石器として扱っている石器のすべてが洪積世に属するかどうかわからないという認識による。…
※「旧石器時代」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新