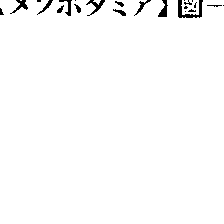翻訳|Mesopotamia
精選版 日本国語大辞典 「メソポタミア」の意味・読み・例文・類語
メソポタミア
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「メソポタミア」の意味・わかりやすい解説
メソポタミア
Mesopotamia
イラク,シリアのティグリス,ユーフラテス両河流域地方を指す歴史的呼称で,〈(両)河の間〉を表すギリシア語に由来する。この地域に人類最古の文明が繁栄した。
地域と風土
メソポタミアは,本来的にはバグダード以北の両河流域地方(ほぼアッシリアに対応)を指し,以南を示すバビロニアと対立的に用いられたようである。アラブは狭義のメソポタミアをジャジーラal-Jazīraと呼んだ。のちにはメソポタミアはザーグロス山脈以西,アラビア台地以東,トロス(タウルス)山脈よりペルシア湾岸に至るまでの両河流域を指すようになった。トルコの両河源流地方はメソポタミアには含まれない。
メソポタミアのかなりの地域は平原をなし,南部は大沖積平野である。たとえばシリア,イラク国境のユーフラテス河畔にあるアブー・カマールAbū Kamālは標高170mほどであるが,アブー・カマールからペルシア湾岸までは1140kmもの河川距離がある。またティグリス河畔バグダードからペルシア湾頭まではほぼ900kmであるが,バグダードは標高34mにすぎない。なお現在,両河は河口近くで合流し,シャット・アルアラブ川と呼ばれている。
メソポタミアの大部分はすこぶる高温であり,しかも降雨量は少ない。北部イラク,モースルの平均年降水量は385mm程度であるが,南部のバグダードでは7,8月の平均気温は34℃,12月,1月は11℃前後であり,しかも年降水量は150mm程度にすぎない。天水麦作農業には少なくとも200mmの年降水量が必要であるから,メソポタミアの低地地方では早くから人口灌漑による農業が行われた。しかし,両河水位は穀類が播種される秋に最も低く,春の収穫期に高くなるから,南部メソポタミアではエジプトのナイル流域地方とは違って両河および諸支流からの通年式灌漑システムが要請された。また増水期には氾濫の危険性が大きく,さらにユーフラテス流路が絶えず変わったから,この地方では水の統御が人間の生活にとって不可欠であった。しかし,灌漑農業は天水農業とは異なり,場合によっては驚異的な高生産力水準に達しうる。前4千年紀末,メソポタミア最南部で最古の都市文明が創出されたのも,このような高度の農業生産力を背景としていた。
なお古代のメソポタミア地方はアスファルトのほかには鉱物資源には恵まれていない。他地域から原鉱石を得るために余剰農業生産物,羊毛製品などを輸出するほかなかったのであり,このような交易システムは,かえって古代メソポタミアでの農業や家畜飼育の大発展を促した。またメソポタミアには周辺諸民族がきわめて容易に侵入しえたから,以下に概観を試みる古代メソポタミア史は諸民族の交替の歴史でもあった。
→ティグリス[川] →バビロニア →ユーフラテス[川]
新石器時代
前1万年ころよりクルディスターン地域で初めて農業と家畜飼養が開始された。のちしだいに村落はザーグロスの丘陵などに広まる。ジャルモが典型的な遺跡であるが,ほぼ同時代のアナトリアのチャタル・ヒュユク,パレスティナのイェリコではすでに大町邑さえも成立していた。前6千年紀には東シリアのハラフ(ハラフ文化),北イラクのハッスナ(ハッスナ文化)などで,より進んだ村落文化がみられる。わずかに遅れてザーグロスの丘陵のチョガ・マミ,サーマッラー近くのテル・アッサッワーンTell al-Sawwānなどにサーマッラー文化が成立した。前者は天水農耕成立のための限界降雨量の地域にあり,また後者では天水農耕はまったく不可能であった。実際,チョガ・マミからは最古の灌漑用水路跡が見いだされているし,テル・アッサッワーンでも確実に灌漑農業が行われていた。遺跡規模はきわめて拡大し,村落ないし町邑を取り巻く防衛施設も発展している。
ユーフラテス流域最南部のペルシア湾に至るまでの地域は,歴史時代にはシュメールと呼ばれた。ただし当時の海岸線は現在のそれよりははるかに北方にあった。シュメール地方では前6千年紀後半のウバイド期(ウバイド文化)にはいってはじめて人間の居住跡が見いだされる。とりわけ最南部のエリドゥではウバイド1期から前4千年紀後半のウルク後期(ウルク文化)に至るまでの時期に,原初的な小祠堂が大規模な神殿へと連続的に発展していた。この事実に注目する学者は,ウバイド期にすでにシュメール文化の原型が成立していたとみなす。ただし南部ウバイド文化の故地は明らかではない。
シュメール・アッカド時代
前4千年紀中葉のウルク期には,シュメール北部にも多くの村落遺跡が見いだされ,ウルク期前半にすでにニップール,アダブなどがほぼ都市的規模の面積に達していた。後期には南部のウルクが大発展を遂げ,巨大な神殿などが相次いで成立し,ウルク最末期には最古のシュメール語粘土書板も現れている。これ以後,前24世紀中葉までメソポタミア最南部でシュメール都市国家時代が続く。なおシュメール語は膠着語系に属し,周辺諸言語とは類縁関係をもたないから,シュメール人の起源については最終的な解答は与えられていない。またウルク期のシュメール文化はユーフラテス流域に急速に伝播し,シリア地方にもウルク期神殿を含む遺跡が見いだされている。粘土板による記録法は次のジャムダット・ナスル期末(ジャムダット・ナスル文化)までにウルク以外の都市にも普及した。これ以後キリスト紀元ころまで粘土板は西アジア各地で記録書板として広く用いられ続けている。
前3千年紀初頭の初期王朝期I期には,シュメールに北接する地域(のちのアッカド地方)に位置するキシュが勢威を有していた。伝承によれば,キシュは〈大洪水〉後に最初に全土の覇権を握っている(キシュ第1王朝)。キシュには早くからセム人が定住し,シリア,ユーフラテス中流域へのシュメール文化伝播に大きな役割を果たしたらしい。のちの叙事詩によれば,キシュ第1王朝の最後の王アッガはウルクのギルガメシュに敗北した。これはキシュの後,ウルクに支配権が移行した(ウルク第1王朝)とする他伝承と矛盾しない。一連のシュメール叙事詩においてウルク支配者の功業が語り伝えられている。とりわけ《ギルガメシュ叙事詩》はアッカド語,ヒッタイト語,フルリ語にまで書き移され,古代西アジア文学中の最大の作品となった。ギルガメシュは初期王朝期Ⅰ期ないしⅡ期に実在したと思われるが,この時期のウルク周辺では多くの小村落が姿を消すとともに,ウルク自体の規模も大膨張した。初めて城壁も建設されており,シュメール地方での軍事的緊張が高まっていたことが示唆される。
初期王朝期Ⅲ期にはいるとシュメール政治史がかなり明らかになる。またウルの〈王墓〉は当時の都市支配者の富を示す。おそらく前26世紀末にラガシュではウルナンシェが現れ,王朝を樹立した。王朝の5支配者に続いて3支配者が多くの政治的碑文を残している。最後のウルカギナ(ウルイニムギナ)はウンマのルガルザゲシに敗北した。ルガルザゲシはウルク王になるとともに他都市をも軍事占領し,ここにシュメール都市国家時代が終わるが,のちルガルザゲシはセム系アッカドのサルゴンに敗れた(前24世紀中葉)。
キシュ王の高官であったサルゴンは,のち独立してアッカド王朝を樹立した。首都アガデの位置はいまだ不明である。サルゴンはシュメール地方を征服しただけでなく,東方エラム地方,ユーフラテス中流域のマリ,さらにはレバノンにまで軍事遠征を行い,最初の帝王として古代西アジアで長く記憶され続けている。またこれ以後セム人がメソポタミア最南部地方にも広く住んだ。第4代王ナラムシンはさらに多くの外征を企て,王朝版図は最大となったが,南部都市を核とする大反乱が発生,また東方蛮族グティ人も王朝内に侵入を開始した。次王ののち王朝はグティ人侵入により混乱に陥るが,南部シュメール地方は比較的平和であり,とりわけラガシュは繁栄を享受していた。
前22世紀後半,ウルクのウトゥヘガルがグティ人を駆逐し,さらに彼の子(ないし兄弟)ウルナンムがウルで独立して,ここにシュメール人の統一王朝が成立した(ウル第3王朝)。2代王シュルギのとき王朝は最盛となる。治世後半には王は神格化された。度量衡も統一され,王朝各地での経済活動は活発であった。ニップール近郊には王朝内外からの無数の貢献家畜を点検する施設プズリシュ・ダガンも建設された。5代王イビシン時代までには西方セム系アムル人(アモリ人)の圧力が強まる。イビシンの高官アムル系のイシュビエラはイシンで独立するとともに,各地を軍事占領した。またエラムの脅威もあって,前2004年ウル第3王朝は崩壊し,シュメール人は民族的実体を失う。
最古の粘土板文書(ウルク出土)が神殿ないし王宮の財産管理記録であったことに示唆されるように,シュメール人は多くの行政・経済文書を残した。なお現存のシュメール文学テキストの多くは,ウル第3王朝崩壊後に書かれたものである。また楔形文字による粘土板記録は早くからメソポタミア各地に普及した。たとえばシュルッパク(現名ファラ)およびアブー・サラビクの文書(前26世紀?)は,シリアの〈エブラ文書〉に酷似しており,ユーフラテス川による濃密な文化交流を示す。シュメール都市を神殿組織の複合体とみなす古典学説は,初期王朝期Ⅲ期の〈ラガシュ文書〉研究の結果成立したものであるが,その普遍妥当性は疑わしい。またギルス(ラガシュ),ウンマ,ニップール,プズリシュ・ダガン,ウルから無数のウル第3王朝時代文書が出土している。
→アッカド →シュメール
イシン・ラルサ,バビロン第1王朝時代
ウル第3王朝の崩壊後,南部メソポタミアではアムル人を中核とする小国家が分立した(イシン・ラルサ時代)。イシュビエラが創始した中部バビロニアのイシン王朝は,ウル第3王朝の政治理念を踏襲した。たとえば〈リピトイシュタル法典〉は,前代の〈ウルナンム法典〉を継承したものである。一方,より南部のラルサは,シュメール地方に覇権を樹立したし,ディヤラ川流域ではエシュヌンナが勢威を振るった。またユーフラテス中流域ではマリが交易中継地として繁栄し,マリからは前18世紀ジムリリム時代の文書が多数発見されている。バビロニアに北接する地域では,アッシリア人の都市アッシュールが前19世紀から前18世紀にかけてのシャムシアダド1世時代に有力となった。アッシリア人は早くからメソポタミアと小アジア間の通商を行い,カイセリ付近のキュルテペ(カニシュ)などには商業植民地を建設している。
バビロン第1王朝第6代王ハンムラピは,前18世紀中葉に南部メソポタミアの小国分立に終止符を打った(古バビロニア王国)。ラルサはリムシン時代にイシンを併合し,中・南部バビロニアを支配していたが,ハンムラピはマリと同盟するなどして国力を蓄え,ついにラルサを破り,メソポタミア南部を統一した。治世晩年に成立した〈ハンムラピ法典〉は,シュメール法とアムル慣習法の融合を示す。次王サムスイルナのとき諸市が反乱し,反乱鎮圧直後に諸市は経済混乱に見舞われ,ウル,ラルサ,ニップールなどは放棄された。また当時,より南方には〈海国Sealand〉が存在した。以後王朝は北部バビロニアを基盤とするが,カッシート人(カッシート)などの圧力に苦しみ,前16世紀初頭ヒッタイトの攻撃を受けて滅亡した。
イシン・ラルサ時代からバビロン第1王朝時代にかけては各種の粘土板文書が多く残っているから,統治体制,司法制度,商業,土地制度,尼僧制などに関して,みるべき多くの研究成果がある。
→バビロン第1王朝
カッシート人,フルリ人,ミタンニ王国
西イランにいたカッシート人は,サムスイルナ時代に南メソポタミアに現れたが,その言語はいまだわかっていない。バビロン第1王朝の崩壊後カッシート人は,前12世紀中葉までバビロニアを支配した。その際,アッカド語を公用語として採用している。前14世紀には首都としてドゥル・クリガルズを建設した。カッシート支配下の南部諸都市は衰弱し,出土文書もきわめて少ない。
前3千年紀末にはフルリ人が北西メソポタミアに現れ,ウル第3王朝は盛んに対フルリ戦争を企てた。彼らの言語の詳細は不明。なお前1千年紀のウラルトゥはフルリ人の後裔による国家である。バビロン第1王朝の頃よりフルリ人は北部メソポタミア,東部アナトリア,シリア海岸地方に勢力を拡大した。前16世紀中葉,この地域にミタンニ王国が成立し,前14世紀中葉まで存続するが,人口の大部分はフルリ人であったらしい。ただしインド・アーリヤ人が支配階級を形成し,彼らを通じて馬,戦車がヒッタイトに伝えられた。ミタンニはエジプト王家とも婚姻関係をもったが,ヒッタイトの攻撃を受けて滅亡した。
アッシリア
アッシリア人は前18世紀以後フルリ人,ミタンニ王国の圧力下にあったが,ミタンニ崩壊にともない,前14世紀中葉に真の意味での領域国家に成長した。前14世紀以来,シリアおよび北部山岳地帯に接する領域を支配し,またバビロニアにも侵攻している。しかしこの頃,セム系アラム人が北部メソポタミアで有力となり,アッシリアは一時衰退した。のちアラム人の諸小国家はアッシリアの勢力回復とともに征服され,前8世紀末には政治的実体を失うが,アラム文字,アラム語は,メソポタミア全域に浸透した。とりわけペルシア帝国治下の西アジア全域でアラム語は最も重要な国際語として用いられた。
前10世紀中葉以後アッシリアは大発展を遂げた。アッシュールナシルパル2世はティグリス河畔にカルフ(現,ニムルド)を建設している。前8世紀後半のティグラトピレセル3世のとき,地中海からバビロニアに至るまでを領有する大帝国が成立した。8世紀末のサルゴン2世はイスラエル王国を属州とし,またバビロニアではセム系カルデア人の抵抗を粉砕している。ニネベ近くには新都ドゥル・シャッルキン(現,コルサバード)も建設されたが,次王は首都としてニネベを再興。エサルハドンのときバビロンを再興し,前671年にはエジプトを侵略,初めてメソポタミアとエジプトが統一された。次のアッシュールバニパルは上エジプト,テーベをも破壊している。アッシュールバニパルは文書記録の保存に熱心であり,ニネベに図書館を建設した。ニネベ発掘の際ここより出土した粘土板記録は,近代アッシリア学成立の基礎材料となった。同王の治世末期にはスキタイの侵入などにより帝国は弱体化する。
一方イラン高原では前670年ころメディア人諸部族が統一され,しだいにエクバタナ(現,ハマダーン)を中心に強盛となった。またカルデア人のナボポラッサルは前625年にバビロンに入城し,カルデア王朝(新バビロニア)を樹立している。アッシリアの首都ニネベはメディア,新バビロニア連合軍によって前612年に破壊され,ここにアッシリア帝国は事実上滅亡した。
アッシリアの帝国形成は,卓越した軍事力と巧妙な外交政策によるところが大きいが,商業の繁栄,貢納・徴税による安定した財政も帝国維持に役立った。また道路網,駅伝制度もよく整えられ,これらはペルシア帝国に受け継がれた。前8世紀ころからは,帝国に編入した諸民族を大規模に強制移住させる政策も定着している。
→アッシリア
新バビロニア時代
カルデア(新バビロニア)朝ではナボポラッサルに次いでネブカドネザル2世が現れ,絶頂期を迎える。バビロンは空前の繁栄を遂げた。ネブカドネザルはシリア,パレスティナをエジプトより奪い,前586年にはユダ王国を征服し,住民をバビロニアに強制移住(バビロン捕囚)させた。彼ののち国は衰え,ナボニドスの治下,ペルシア軍により滅亡した。
→新バビロニア
アケメネス朝ペルシア
アーリヤ系ペルシア人はイラン高原に勢力を得て,キュロス2世のとき姻戚関係にあったメディア王を破り,都をパサルガタエからエクバタナへ移す。キュロス2世は前539年新バビロニアを破り,バビロニアを属州とした。王はエクバタナ,エラムのスーサとともにバビロンを首都としている。
新バビロニア時代からペルシア時代にかけて,メソポタミア,とりわけ中・北部バビロニアの諸都市は大繁栄した。出土文書もウル第3王朝時代に次いで多い。バビロンのエギビ一族,ニップールのムラシュ一族の文書は,商取引によって富を蓄えた階層の実態をよく示している。
→ペルシア帝国
セレウコス朝時代,パルティア,ササン朝ペルシア時代
前331年ダレイオス3世がアレクサンドロス大王に敗北するに及び,ペルシア帝国は崩壊した。アレクサンドロスの死後,部下セレウコスがシリア,メソポタミアを支配した(セレウコス朝シリア)。ティグリス河畔にはセレウキアが建設され,後2世紀にローマに破壊されるまで,行政・通商の中心地として大発展を遂げた。ただしオロンテス河畔にはアンティオキアがシリア地方の都として建設され,その他にも多くの都市が成立した。またギリシア人も各地に入植し,メソポタミア地方にヘレニズム文化が広く普及した。
前3世紀中葉にはイラン高原にパルティア王国が興り,セレウコス朝と対立した。前2世紀中葉のミトリダテス1世はメソポタミアを占領している。さらに西方ローマの大発展とともに,メソポタミアはパルティアとローマの間の抗争の主要舞台となった。後2世紀の一連の抗争では,メソポタミアはほぼローマ属州として維持されている。
後3世紀の前半,ササン朝ペルシアがパルティアに代わってイラン高原を支配し,メソポタミアで再びローマと衝突した。たとえばシャープール1世はメソポタミアを占領,260年にはローマ皇帝ウァレリアヌスを捕虜としている。しかし,この間シリアの都市パルミュラが勢いを得て,シャープール1世を破る。パルミュラはのちローマに屈した。4世紀中葉シャープール2世時代にはササン朝が強盛となり,再びローマとの争いが激化。この頃よりのササン朝とローマ帝国,続くビザンティン帝国との抗争の背景には,ゾロアスター教徒,キリスト教徒の処遇問題が大きな要因として働いていた。6世紀ホスロー1世時のササン朝の大発展ののち,7世紀にはビザンティン帝国にメソポタミアの大部分を奪われ,同世紀のアラブ占領にいたる。
パルティアはティグリス河畔の駐屯地クテシフォンを冬都とし,クテシフォンは続くササン朝時代にも首都として大繁栄した。この両時代に中・南部メソポタミアには灌漑水路網がはりめぐらされ,高い農業生産力が維持されていたらしい。最近の研究は,前3千年紀末のウル第3王朝時代およびササン朝ペルシア時代に中・南部メソポタミアが発展の頂期を迎えたことを示唆している。
→ササン朝 →シリア王国 →パルティア
執筆者:前川 和也
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「メソポタミア」の意味・わかりやすい解説
メソポタミア
Mesopotamia
メソポタミア
Mesopotamia
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「メソポタミア」の意味・わかりやすい解説
メソポタミア
→関連項目イラク|バグダッド|パルミュラ|マリ(遺跡)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「メソポタミア」の意味・わかりやすい解説
メソポタミア
めそぽたみあ
Mesopotamia
ギリシア語で「二つの川の間」を意味し、ティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域に対して古代ギリシア人がつけた地域名。今日ではより広義に、イラクおよびシリア北部を含む広範囲な地域の呼称としても用いられる。この地域には数万年前の太古にさかのぼる人類の居住址(し)があり、紀元前5000~前4000年には農耕を伴う定住民が現れた。そののちシュメール人が南部の川沿いにウル、ウルク、ニップールなどの都市を建設し、文字使用を含む高度の初期文明を発達させた。ついでセム人が南からきてシュメール人を圧倒し、南方にバビロニア、北方にアッシリアの二大帝国を樹立して強大な勢力を誇った。
ペルシア人の来襲、ギリシアによるヘレニズム化を経て、後7世紀後半からアラブ人によるイスラム化が進み、言語もシュメール語、アッカド語、アラム語を経て今日では大多数がアラビア語を使用している。この地域は文明発祥の地として、また多様な文明の十字路として知られる。
[矢島文夫]
山川 世界史小辞典 改訂新版 「メソポタミア」の解説
メソポタミア
Mesopotamia
ティグリス,ユーフラテス両河が流れる地域のギリシア名。ここで世界最古の文明の一つが興った。北部はアッシリア,南部はバビロニアと呼ばれ,バビロニアはさらに北部のアッカド,南部のシュメール地方に分かれる。この地は肥沃であり,人工灌漑により多量の穀物が収穫できる。開放的な地形のため,シュメール人,バビロニア人,アッシリア人,カッシート人,エラム人,フルリ人,ペルシア人などがこの地に侵入し,あいついで支配権を握った。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「メソポタミア」の解説
メソポタミア
Mesopotamia
ギリシア語で「川の間の土地」の意。エジプトとともに世界最古の文明の発祥地で,前3000年ごろシュメール人が都市国家を築いて以来,バビロニア・アッシリアなど多くの国家が興亡した。現在イラク共和国がある地域。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のメソポタミアの言及
【シリア】より
…古代地理では,北はイスケンデルン(アレクサンドレッタ)湾周辺ないしトロス山脈以南から,南はシナイ半島までを含み,現在のトルコ共和国南東端からレバノン共和国,シリア・アラブ共和国,イスラエル,ヨルダン・ハーシム王国にまたがる地域にほぼ相当した。ギリシア人はシリアに〈山あいの(くぼ地の)koilē〉という形容詞をつけ,〈両河potamosの間meso〉のシリアすなわちメソポタミアと対比させた。 地形は全体として縦割りで,それぞれ,しばしば非常に狭まる海岸平野,その東側の丘陵・山岳地帯,そして,オロンテス川流域,ティベリアス(ガリラヤ)湖,ヨルダン川,死海,アラバ涸れ河などからなる,海面下に達する深い地溝,さらにその東側のシリア砂漠に続く高原地帯を特徴とする。…
※「メソポタミア」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新