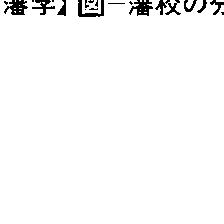精選版 日本国語大辞典 「藩学」の意味・読み・例文・類語
はん‐がく【藩学】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「藩学」の意味・わかりやすい解説
藩学
はんがく
江戸時代、各藩によって設立・経営された藩士の子弟の教育機関。藩黌(はんこう)、藩校、藩学校ともいう。そのほか、医学校、洋学校、皇学校、あるいは郷学校などを総称する場合もある。江戸初期、武断的支配から官僚制的支配への移行が一般化すると、尾張(おわり)藩名古屋の明倫(めいりん)堂をはじめ、各藩は家中の士人教育のため藩学を設立した。さらに江戸後期には、寛政(かんせい)期(1789~1801)松平定信(さだのぶ)の文武奨励もあり、封建危機の深化への対応として、藩政改革にあたって有能な吏僚を育成すべく、各藩が人材養成に力を入れ、ほとんどの有力大名が藩学を設け、発展期を迎え、全国255校をも数えた。初期の、藩主の学問所や招聘(しょうへい)された碩儒(せきじゅ)の家塾的なものから、組織・校舎などが整備され、総合的教育のための藩の重要な施設となった。1871年(明治4)廃藩置県で廃止され、一部は公私立の専門学校、中学校、小学校に変わった。
藩学は各藩さまざまであるが、概観すれば以下のごとくである。主たる対象を藩士の子弟とし、なかに、備前(びぜん)岡山藩、加賀(かが)金沢藩などは庶民の入学を許した。8歳から20歳ごろまでを就学年齢とし、藩士の子弟全員の就学を強制した例は多い。一定の課業の修了を家督相続の条件とした藩もあった。
学習内容は「文武兼備」を目標としたが、実際には文の比重が大きい。年少で入学し、まず文を学び、15歳前後から武をも学ぶ例が多い。藩学教育に剣、槍、柔、射、砲、馬術や兵学などの武芸が積極的に導入されるのは幕末に至ってである。また会津、水戸、萩(はぎ)など三十余藩では水練を行った。学習の中枢は漢学で、すべての藩学で行われており、初学者にも四書五経などの儒学書の素読と習字を課した。儒学の学派は、各藩学さまざまであるが、寛政(かんせい)異学の禁以後は、やはり朱子(しゅし)学派が多くなった。
発展期の藩学は実学的指向が強く、漢学・習字のほか、医学・皇学・算術・天文学などの科を設けたところが多かった。医学科は、化政(かせい)期(1804~30)以降、多くの藩で設けられたが、ことに蘭(らん)医学が導入されるに及んで、日本の洋学発達と科学的合理思想発展に貢献した。幕末期、政情の動揺に伴い皇学も増加している。
教育の組織は、通学生が主で、一部寄宿生を置いた。初学者を小学生、上級者を大学生と分けたり、同程度の学力の者を学級に編成し、会読、輪講、講義などの方法で授業を行い、試験による進級の制度がとられるなど、近代的学校に近づいている点も注目される。しかし、初期以来の、教師・先輩による対面個人的指導も広く行われた。
藩学は藩主の下、家老級の有力者に管轄され、教官には、代々藩に仕える儒者が教授・助教授として任にあたった。藩主は定例的に、あるいは随時、藩学に赴き、釈奠(せきてん)の儀式や試験に臨席し、自ら聴講して、学生の業を励ました。
藩学の校舎は、仙台養賢堂、水戸弘道(こうどう)館、備前閑谷黌(しずたにこう)をはじめ、建物の一部が現存するものもあるが、聖堂、講堂、教場、学寮、演武場などを備えた規模壮大なものが、儒教主義教育の精神を象徴している。ほとんどの藩学は、授業料等を徴することなく、学田を付し、あるいは藩費をもってこれを経営維持したが、壮大な学舎の建設費をはじめ、藩財政の重い負担であった。また多くの藩学で、しばしば出版事業も行われていた。
幕藩体制下、藩学は藩士の忠誠心を養う人格陶冶(とうや)から、藩の富国強兵のための時務に通ずる吏僚の知識技能を培う実学教育を目ざす方向に進んだ。また、この間に、結果として地方文化の振興にも貢献した。
[木槻哲夫]
『文部省編・刊『日本教育史資料』全10巻(1889)』▽『笠井助治著『近世藩校の綜合的研究』(1960・吉川弘文館)』▽『笠井助治著『近世藩校に於ける出版書の研究』(1962・吉川弘文館)』▽『笠井助治著『近世藩校に於ける学統学派の研究』上下(1969、70・吉川弘文館)』▽『宇野哲人・乙竹岩造他著『藩学史談』(1943・文松堂書店)』▽『城戸久著『藩学建築』(1945・養徳社)』▽『R・P・ドーア著、松居弘道訳『江戸時代の教育』(1970・岩波書店)』
改訂新版 世界大百科事典 「藩学」の意味・わかりやすい解説
藩学 (はんがく)
藩校,藩学校ともいう。江戸時代に諸藩が設立した藩士およびその子弟の教育機関。藩学は,狭義にはとくに漢学校を中心とする文字教育と人間教養とを与え,藩士の子弟をすべて入学させるたてまえの学校であるが,広義にはそのほかに,医学校,洋学校,皇学校(国学校),女学校,郷学校,武学校などを含めることがある。普通藩学という際には狭義である。藩学教育は藩士全体を教育の対象とし,特有の士風を教育の力で醸し出そうとするところに重要な役割があった。宝暦期(1751-64)から天明期(1781-89)にかけて,全国的に藩学が数多く設立され,有名なものに米沢藩の興譲館や熊本藩の時習館などがある。このころ以降になると,財政的危機に見舞われた多くの藩では,その克服と再建という藩政改革推進のために必要な有能な藩吏としての人材養成を目的とするにいたった。〈寛政異学の禁〉(1790)を契機に各藩でも藩学を盛んにしようとする動きがあるが,この禁令は藩学で有用な訓練と知識とを与えることが各藩の重要な政務であることを教えた。すなわち,藩体制の動揺と武士層の生活の変貌に対して,藩是を確立し,藩風を振興し,領主的危機に対応する政治的姿勢を打ち出すものが多かった。天保期(1830-44)以降になると,藩学の設立は小藩にまで波及した。大藩では数校を併置するものが現れた。いずれも領主側からみて,幕末期の〈内憂外患〉の破局的な危機への対処方法として,富国強兵・殖産興業政策を行うのには,もっとも有効な政策であると考えたからである。また,それには西欧の知識をもって対処するのでなければ乗り切れない実態が徐々に認識された。それにともなって,漢学を主体とした藩学の教育内容に,国学やそのほか,医学,天文学,測量学,本草学などの洋学の知識導入の必要性が切実に認識されるに至った。このころから,多くの藩学では新しい傾向として洋学が採用され,しばしば洋式の軍事学や練兵が同時に課せられた。
執筆者:津田 秀夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「藩学」の意味・わかりやすい解説
藩学【はんがく】
→関連項目郷学|私塾|民間教育
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「藩学」の解説
藩学
はんがく
藩校・藩黌・藩学校とも。江戸時代,諸藩がその家中の子弟のために設けた学校。広義には,幕末期に多く設けられた洋学所など藩営のすべての教育機関をさすが,通常は儒学を中心とし,多くの藩では経書から学校名をつけた(時習館・明倫堂など)。19世紀を迎える前後から多く設立され,1719年(享保4)創立の萩藩の明倫館などは早い例である。幕藩体制の動揺のもとで,藩士の人材養成・選抜の機関として設けられたことをうかがわせるが,当初は中士以上を入学資格とするところも多かった。教育内容は四書五経が中心で,試験に不合格となると家禄の一部を減じた藩もある。明治期以後の士族の教育熱は,藩学の有形・無形の影響ともいえる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「藩学」の意味・わかりやすい解説
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の藩学の言及
【学校】より
…これは,市井の学者による批判を受けながらも,幕末の国学,蘭学の高揚を迎えるまで権威を保ち続けた。江戸時代の学校としては,このほか,藩校(藩黌,藩学),郷学,私塾,寺子屋などがあり,戦乱のない社会で,それぞれ発展した。藩校は各藩が藩体制強化のため武士の子弟に儒学と武道を教授することを目的として設置された。…
※「藩学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新