デジタル大辞泉 「萩」の意味・読み・例文・類語
はぎ【×萩/芽=子】
2
3 紋所の名。萩の花・葉・枝を図案化したもの。
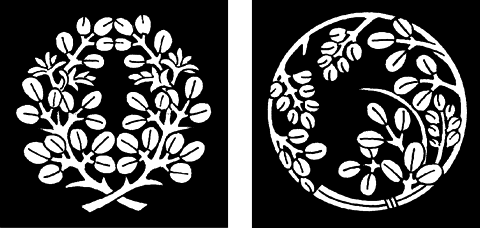
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
山口県北部,日本海に面する市。2005年3月旧萩市と須佐(すさ),田万川(たまがわ)の2町および旭(あさひ),川上(かわかみ),福栄(ふくえ),むつみの4村が合体して成立した。人口5万3747(2010)。
萩市南端の旧村。旧阿武郡所属。1955年明木(あきらぎ)村と佐々並(ささなみ)村が合体,旭村となる。人口2170(2000)。中国山地の中にある山村で,北部に阿武川の支流明木川,南部に佐々並川が北東流し,谷底平野に集落が散在する。村役場は佐々並と明木を2年ごとに交代して置かれていたが,1994年明木に固定された。萩と山口を結ぶ御成道の宿場町として発達し,佐々並には御茶屋が置かれていた。大豆,シイタケ,エノキタケ,ユズの栽培,肉牛の飼育が行われ,特産に豆腐がある。また古くから酒造業が盛んである。国道262号線が通じ,明木は萩,佐々並は山口の商圏に属している。
萩市南部の旧村。旧阿武郡所属。人口1220(2000)。碁盤ヶ岳などの小山地に囲まれ,村内を阿武川が西流する。山間に位置するため林業が盛んで,良質な杉やヒノキを産し,シイタケ栽培も行われる。ユズの栽培も盛んである。アユ漁も行われるが,阿武川ダムの完成後は漁獲が減少した。阿武川ダムは県営の洪水調節,発電用ダムとして1975年完成し,人造湖の湖底には6集落と長門峡の一部が水没した。梵鐘と庭園で知られる梅岳寺,阿武川歴史民俗資料館があり,紅葉で名高い長門峡は県立自然公園に指定されている。天然記念物のユズおよびナンテン自生地がある。
萩市北東部の旧町。旧阿武郡所属。人口3792(2000)。北部は日本海に面しているが,大部分は山間地で,中央部の犬鳴山付近の分水嶺を境に須佐地区と弥富地区に分かれる。中心集落の須佐は日本海に臨む漁港で,1601年(慶長6)石見益田の城主益田元祥が当地に移り,近世を通じて支配した。沿岸航路の寄航地としても栄え,町場も形成された。タバコ,シイタケの栽培が盛んで,肉用の無角牛の飼育も行われている。一本釣り,小型巻網によるアジやイワシの漁獲がある。須佐湾(名・天)を中心とする海岸部は北長門海岸国定公園に指定され,高山(こうやま)の磁石石(天),ホルンフェルスの大断崖千畳敷など雄大な景観がみられる。犬鳴山北麓の唐津には近世に独自の須佐青磁などを焼いた須佐唐津窯跡がある。JR山陰本線,国道191号線,315号線が通じる。
萩市北東端の旧町。旧阿武郡所属。人口3725(2000)。北は日本海に臨み,町の中央を田万川が北流する。日本海に面する中心集落の江崎は天然の良港で,古くから物資の集散地として栄え,江津の湊と称して阿武郡十八郷の米を若狭国へ積み出す港町であった。米作を中心に,クリ,モモ,ナシの栽培,養豚,養鶏が盛んである。特産に煮干し,干しワカメなどの水産加工品がある。室町時代の建築物がある西堂寺や江崎温泉があり,日本海沿岸は北長門海岸国定公園に含まれる。JR山陰本線,国道191号線が通る。
執筆者:清水 康厚
萩市西部,日本海に面する旧市。1932年市制。人口4万6004(2000)。中央部を北西に流れる阿武川は橋本川と松本川に分かれて日本海に注ぎ,その三角州上に中心市街地がある。市域北部を流れる大井川下流域には,金銅製の環頭大刀把頭や耳環を出土した円光寺古墳をはじめとして考古遺跡が多い。海上には羽島,肥島,大島,櫃(ひつ)島,尾島,相島と,はるかに離れて見島の7島が浮かぶ。古く萩浦,萩津とよばれた地は,近世,毛利氏の城下町が開かれたことによって発展,周防・長門両国の政治の中心であった。現在も旧城下の景観をよくとどめ,萩城下町とその東にあたる椿東(ちんとう)にある松下村塾(史),伊藤博文旧宅(史)などの維新史跡に多くの観光客が訪れる。伝統の萩焼や士族授産に始まったナツミカンが特産。沿岸には越ヶ浜,玉江浦など古くからの漁村があり,小型底引網,はえなわ,刺網が盛ん。沿岸部をJR山陰本線が通じ,国道262号によって山陽側の山口市,防府市と結ばれる。
執筆者:三浦 肇
近世,長州藩の城下町。東,西,南の三方に山を負い,阿武川の下流,松本川と橋本川によってできた三角州上に位置する。1551年(天文20)陶晴賢(すえはるかた)により大内義隆が滅ぼされると,石見国津和野の城主吉見正頼は陶晴賢討伐の兵を挙げ,毛利氏とともに戦い,57年(弘治3)阿武郡を攻略した。その功として正頼は長門国阿武,厚狭(あさ)と周防国佐波(さば)の3郡に領地を得たが,このとき当地一帯は吉見領となった。70年(元亀1)正頼は萩の指月(しづき)に隠居所を設けて津和野から移り,のちここで没した。
関ヶ原の戦に敗れ,防長両国に封じられた毛利輝元は幕府と交渉の結果,萩の三角州北西端の指月山(143m)のふもとに城地を定め,1604年(慶長9)築城に着手し,翌年家臣の屋敷割りと町割りを行い,城下町の建設を開始した。08年萩城が完成。三角州の低湿地を埋め立て,萩城三の丸から東にのび東田町で南に向かう基幹道路をつくり,これに街路を平行または直交させて町割りを行った。16年(元和2)橋本川の川筋付替え大工事を行い,城下町の形を整え,松本・橋本両川を天然の外堀とした。城下町は,指月山麓で城に最も近い堀内,北東部の古萩(ふるはぎ),松本川河口西岸にあり廻船問屋や藩の船倉(史)が置かれた浜崎,南部の川島庄の4地区に大別できる。堀内には上層武士の屋敷があり,他地区は侍屋敷,寺社地,町人屋敷が混在していたが,川島庄には百姓屋敷があった。町数は1694年(元禄7)に萩城下本町41,浜崎13であったが(《元禄御国目付記》),1716年(享保1)城下本町で増加して合計58町となり(《巡見御目付集》),以後幕末まで変動はなかった。たびたび洪水に見舞われたため,中央部に1687年(貞享4)新堀川,1739年(元文4)藍場川を開削し,松本川下流に1855年(安政2)姥倉運河を開通させて排水を行い,灌漑や舟運に利用した。1863年(文久3)藩庁が山口に移転したため,萩は城下町の機能を失い,経済的にも大きな打撃を受けた。明治維新後,山口県は勧業局を設置して,士族授産事業としてナツミカン栽培,養蚕,生糸生産,木綿織物,縫製,製陶,養魚,養鶏などを奨励したが,多くは〈士族の商法〉で失敗した。不平士族らによる反政府の萩の乱も起こっている。
旧城下のうち,呉服町と南古萩町は近世の景観をよく残し,萩城城下町として国の史跡。堀内と平安古(ひやこ)地区は重要伝統的建造物群に選定されている。指月山(天)は海に面して花コウ岩の断崖がそばだち,林相も美しく,萩城跡(史)付近は指月公園になっている。新堀川の南,江向(えむかい)には藩校明倫館の水練池および有備館(史)があり,萩市街各所に城下時代の旧跡がある。
執筆者:小川 国治
萩市中部の旧村。旧阿武郡所属。人口2617(2000)。村内を大井川が南西流し,南部の旧川上村との境を流れる阿武川には,1975年完成した県営阿武川ダムがある。中心集落の福井下は萩から津和野に至る石州街道が通じ,近世には宿駅が置かれた。村域の大部分が山林で,米作のほかハクサイ,シイタケ,ブドウ,クリの栽培,無角和牛の飼育が行われている。大井川中流の雄滝と雌滝,秋吉造山運動の一翼を担う佐々連(さざれ)鍾乳洞,半田台のカルスト地形などの景勝や重要文化財の森田家住宅がある。
萩市中部東寄りの旧村。旧阿武郡所属。人口2217(2000)。中国山地脊梁部北側の山間にあり,中央を阿武川の支流蔵目喜(ぞうめき)川が南流する。萩から津和野に至る石州街道が通じ,江戸時代,吉部(きべ)には代官所や駅が置かれ,市も開かれた。林野が広いが,農業が中心で米作,野菜やタバコの栽培,養鶏,肉牛の飼育などが行われ,特産にダイコンなどがある。吉部上に鎮座する吉部八幡宮と牟礼神社は,江戸時代,牛馬の守護神として崇敬された。北部の東台は自衛隊の演習場になっている。北東部を国道315号線が通る。
執筆者:清水 康厚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報
…市街地は山口盆地の北東隅にあって,14世紀後半,大内氏が館を置いて京都を模した街をつくり,約200年間城下町として栄えた。その後,陶(すえ)氏,次いで毛利氏の支配下に置かれたが,近世には萩に毛利氏の本拠が移されたため,山口はさびれた。幕末の1863年(文久3)藩庁が萩から山口に移転して政治中心地として復活し,明治以降も県庁所在地となって発展してきたが,山陽新幹線の小郡(おごおり)駅から山口線で約25分の内陸にあり,鉄道幹線から離れているため,近代産業の定着を見ず,行政・文教面の中心機能をもつにすぎない。…
※「萩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新