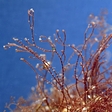精選版 日本国語大辞典 「紅藻植物」の意味・読み・例文・類語
こうそう‐しょくぶつ コウサウ‥【紅藻植物】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「紅藻植物」の意味・わかりやすい解説
紅藻植物 (こうそうしょくぶつ)
red algae
Rhodophyta
体は紅色ないし暗紅色で,色素体内には光合成色素としてクロロフィルaのほかにフィコエリトリンやフィコシアニンなどの色素タンパク質を含み,光合成によりデンプンを生産して貯蔵する植物の総称名。紅藻綱Rhodophyceae 1綱のみからなる。全世界に約5000種が知られ,その大部分は海産である。いずれも卵と精子の合体による有性生殖を行うが,精子は鞭毛をもたないので,波にゆられて移動する。受精卵からできる胞子を果胞子といい,それがどのようにして形成されるかにより,次の二つの亜綱に分類される。
(1)ウシケノリ亜綱(または原始紅藻亜綱)Bangiophycidae 受精卵は直接分裂して果胞子を形成する。おもな仲間にウシケノリ属とアマノリ属がある。ともに果胞子は発芽すると貝殻に穿孔(せんこう)して糸状の胞子体となる。ここにできた胞子が放出されて発芽・生長すると,ふつうに見る藻体となる。アマノリ属にはアサクサノリやスサビノリなど,いわゆる商品の浅草海苔の原料となるものが多く,日本や韓国沿岸の内湾域で盛んに養殖される。
(2)真正紅藻亜綱Florideophycidae 受精卵は造胞糸と呼ぶ分枝する細胞糸を発出させ,そこに果胞子を形成する。真正紅藻亜綱の生活史には数型が知られ,そのおもなものに次の二つがある。(a)イトグサ型Polysiphonia-type 配偶体と配偶体に内生する果胞子体,および配偶体と外形が同じ四分胞子体の三つの世代が順次に循環する世代の交代。テングサ,ツノマタ,イギスなど多くの紅藻に見られる。(b)カギケノリ型Asparagopsis-type 配偶体と配偶体に内生する果胞子体,および配偶体より小型で体制の単純な四分胞子体の三つの世代が順次に循環する世代の交代。ウミゾウメン,カギノリ,コナハダLiagora,イトフノリGloiosiphoniaなどに見られる。
紅藻類はクロロフィルaのほかに,海中の深所に到達する緑色光や青色光をよく吸収する紅色の色素タンパク質を含むので,深所に生育することができる。しかし,アサクサノリやフノリなどのように潮間帯上部の浅いところに生育するものもある。紅藻類には有用なものが多い。代表的なものとして,乾海苔のアサクサノリ類,寒天原藻のテングサ,オゴノリGracilaria類,カラギーナン原藻のツノマタ,スギノリ類,駆虫剤のマクリなどがある。
執筆者:千原 光雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「紅藻植物」の意味・わかりやすい解説
紅藻植物
こうそうしょくぶつ
red algae
[学] Rhodophyta
植物分類学上の1門として扱われる藻類(紅藻類)。世界で約4000種、日本には約1000種の海産種と約20種の淡水産種が生育する。紅藻植物は、光合成色素としてクロロフィルaのほか、r-フィコシアニンとr-フィコエリスリンなどの色素をもち、葉緑体は2枚の膜に包まれ、中に一重のラメラ(薄い層)をもつ。海の深い所に生育するものはフィコエリスリンを多量に含むために、体は赤色となる。紅藻植物の生殖細胞には鞭毛(べんもう)がないために、有性生殖は自己遊泳性のない精子と卵によって行われる。紅藻植物では、卵細胞を造果器とよび、受精卵から生じる胞子を果胞子とよぶ。紅藻植物の受精後の果胞子形成過程には、(1)受精卵自体が直接分割していくつかの果胞子となる、(2)受精卵は分裂して多数の細胞からなる造胞糸を形成し、造胞糸が果胞子を形成する、という二つの様式があり、この様式によって紅藻植物は次の二つに大別される。
(1)の様式がウシケノリ類(原始紅藻類)であり、(2)の様式が真正紅藻類(ウミゾウメン類)である。
ウシケノリ類は、体制と生殖方法によって、チノリモ目、ベニミドロ目、ウシケノリ目、オオイシソウ目に分けられ、真正紅藻類は助細胞の有無と、助細胞の位置によって、ウミゾウメン目、テングサ目、カクレイト目、スギノリ目、ダルス目、イギス目に分けられる。助細胞とは、真正紅藻類の果胞子体発生の際に特殊な機能をもつ細胞構造をいう。カクレイト目、ダルス目、イギス目では、受精後、受精卵より連絡糸が生じて受精卵の近くにある助細胞に複相の核を移入し、助細胞から造胞糸が形成される。紅藻植物の配偶体の核相は単相であるが、受精してから果胞子を生ずるまでの時期は雌の配偶体上に寄生的に生じた複相(2n)体であり、これを果胞子体とよぶ。この果胞子体から果胞子が発芽すると複相の胞子体が生ずる。
紅藻植物の生活史は多様である。ウシケノリ類の代表的なものはアサクサノリ型で、果胞子は放出されたあと、貝殻中に穿孔(せんこう)して生活する。真正紅藻類の果胞子は発芽して四分(しぶん)胞子体となる。ウミゾウメンの四分胞子体は配偶体に比べて小さく、顕微鏡的な大きさであるが、テングサやイトグサの四分胞子体は配偶体と同形同大である。
紅藻植物には産業上有用なものが多い。アサクサノリは水産物のトップクラスを占め、テングサ、オゴノリなどからは寒天を製し、食用とするほかに、医用細菌の培養や電気泳動の基質とする。
[吉崎 誠]
世界大百科事典(旧版)内の紅藻植物の言及
【藻類】より
…このことを少し詳しく説明すると次のようである。クロロフィルaのほかに主要な補助色素としてフィコエリトリンやフィコシアニンなどの色素タンパク質をもち,光合成産物として紅藻デンプンを貯蔵する紅藻類は鞭毛をもたない生殖細胞をつくるのに対し,クロロフィルaとcのほかにフコキサンチンをもち,ラミナランやマンニトールを貯蔵する褐藻類は,長短2本の鞭毛を側部にもつ先のとがった卵形の泳ぐ生殖細胞を形成する。この2本の鞭毛のうち,前方に伸びるものは両側に小毛を並列する,いわゆる羽型鞭毛であり,後方に伸びるものは表面に付属物のないむち型鞭毛である。…
※「紅藻植物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新