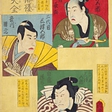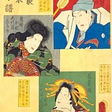精選版 日本国語大辞典 「坂東三津五郎」の意味・読み・例文・類語
ばんどう‐みつごろう【坂東三津五郎】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「坂東三津五郎」の意味・わかりやすい解説
坂東三津五郎
ばんどうみつごろう
歌舞伎(かぶき)俳優。屋号は代々大和屋(やまとや)。
初世(1745―1782)初め竹田巳之助(みのすけ)といい上方(かみがた)の俳優であったが、初世坂東三八が養子にして三津五郎と名のらせた。江戸に下って名をあげた。和実(わじつ)の名手。
2世(1750―1829)1785年(天明5)初世尾上紋三郎が2世を継ぎ、大立者になった。後名2世荻野伊三郎。
3世(1775―1831)初世の子。1799年(寛政11)坂東簑助(みのすけ)から3世を継ぎ、上方の名優3世中村歌右衛門(うたえもん)と人気を争い、文化・文政期(1804~1830)の代表的名優となった。風姿がりっぱで、地芸と所作、時代と世話、どんな役にも優れた技量を示した。とくに和実を得意とした。江戸随一の所作事の名人ともてはやされ、『浅妻船(あさづまぶね)』『願人坊主(がんにんぼうず)』『傀儡師(かいらいし)』『山帰り』『源太(げんだ)』など数々の変化(へんげ)舞踊を演じ、人気があった。江戸深川の永木河岸(えいきがし)に別宅があったので「永木の親方」と親しまれた。
4世(1800―1863)3世の養子。1832年(天保3)2世坂東簑助から4世を継ぐ。3世の芸風を受け継ぎ、和実をよくし、生世話(きぜわ)に優れていた。所作事の名手として、4世中村歌右衛門と対抗して人気を二分した。晩年に中風を病んだので「ヨイ三津」とあだ名された。1850年(嘉永3)11世森田勘弥を襲名。
5世(1813―1855)3世の養子。4世の義弟。風姿と口跡に優れた女方(おんながた)で、坂東しうかと名のって活躍、伝法肌のいわゆる悪婆(あくば)の役を得意とし、とくに8世市川団十郎とのコンビで演じた幕末期の退廃的な美の創造が認められている。死後、5世三津五郎を追贈。
6世(1841―1873)幕末から明治初期にかけて活躍した女方。5世の子。1856年(安政3)6世を継ぐ。顔にあばたがあったので「あば三津」とあだ名でよばれ、人気があった。
7世(1882―1961)12世守田勘弥(もりたかんや)の長男。本名守田寿作。前名2世坂東八十助(やそすけ)。1906年(明治39)7世を継ぐ。青年時代に市村座の座頭(ざがしら)になった。6世尾上菊五郎(おのえきくごろう)、初世中村吉右衛門(きちえもん)らとともに、大正・昭和の歌舞伎を支えた。舞踊の名人でもあり、かつ伝統的技芸の正確な継承者としても重んじられた。1949年(昭和24)芸術院会員、1955年歌舞伎舞踊の重要無形文化財保持者に認定され、1960年文化功労者。
8世(1906―1975)7世の養子。本名守田俊郎。初名3世八十助。1962年(昭和37)6世坂東簑助から8世を継ぐ。実悪(じつあく)、老(ふけ)役を得意とし、舞踊に優れていた。一時期関西歌舞伎に属し、いわゆる武智(たけち)歌舞伎の協力者となって若手俳優を指導した。研究熱心な俳優で、『戯場戯語』ほかの著書も多い。1973年、重要無形文化財保持者に認定されたが、フグ中毒で急逝。
9世(1929―1999)3世坂東秀調(しゅうちょう)の三男。1955年(昭和30)8世三津五郎の長女と結婚し養子となる。前名4世八十助、7世簑助。父の死により坂東流家元の三津五郎を襲名し、1987年9月、歌舞伎俳優としての9世を継ぐ。
10世(1956―2015)9世の長男。1962年(昭和37)に初舞台。前名5世八十助。歌舞伎以外でも、舞台や映画で活躍。2001年(平成13)1月、10世を継ぐ。2005年度日本芸術院賞受賞。
[服部幸雄]
『利倉幸一編著『七世三津五郎 舞踊芸話』(1977・演劇出版社)』▽『8世坂東三津五郎著『戯場戯語』(1968・中央公論社)』▽『8世坂東三津五郎著『歌舞伎 花と実』(1976・玉川大学出版部)』▽『8世坂東三津五郎・安藤鶴夫著『芸のこころ』(1982・ぺりかん社)』
改訂新版 世界大百科事典 「坂東三津五郎」の意味・わかりやすい解説
坂東三津五郎 (ばんどうみつごろう)
歌舞伎役者。屋号は代々大和屋。(1)初世(1745-82・延享2-天明2) 前名竹田巳之助。俳名是業。浜芝居の立者であったが,上坂した初世坂東三八に見込まれ,弟子養子となって,1766年(明和3)冬,ともに江戸に下り,坂東三津五郎と改名。容姿よく,立役,女方,所作事を兼ね,とくに和実の上手として人気を得たが,短命で,森田座に出演中,楽屋で急逝した。(2)2世(1750-1829・寛延3-文政12) 初名尾上藤蔵。前名尾上門三郎,尾上紋三郎。後名2世荻野伊三郎。俳名里遊,是業,初朝。法名群好。1785年(天明5)11月襲名。初世の芸風を伝え,和実,捌き役などをよくした。(3)3世(1775-1831・安永4-天保2) 初名初世坂東三田八。前名坂東巳之助,森田勘次郎,初世坂東簑助。俳名秀歌,秀佳。別号高清亭。通称永木(えいき)の親方(親玉),永木の三津五郎。初世の子。1799年(寛政11)11月襲名。江戸役者の親玉とたたえられ,上方の名優3世中村歌右衛門と拮抗,敵役を除くあらゆる役柄に通じ,なかでも和実と所作事を得意として,《布引滝》の実盛などに新しい人間像を生み,〈永木の型〉として後世に伝えられるとともに,舞踊坂東流の基礎を築いた。(4)4世(1802-63・享和2-文久3) 前名2世坂東簑助。俳名佳朝,秀朝,是好。3世の養子。1832年(天保3)3月襲名。和実と所作事に長じ,実悪をも兼ねた。中風にかかり,ヨイ三津と仇名された。50年(嘉永3)11世森田勘弥(守田勘弥)となり,座元を兼ねた。(5)5世 初世坂東しうかが,死後,5世を追贈された。(6)6世(1846-73・弘化3-明治6) 前名初世坂東吉弥。俳名秀歌,秀山。通称吉弥三津五郎。5世の子。1856年(安政3)5月襲名。顔にあばたがあり,アバ三津と仇名された。(7)7世(1882-1961・明治15-昭和36) 本名守田寿作。前名2世坂東八十助。俳名是好。12世守田勘弥の子。1906年4月襲名。大正・昭和を通じて,古典的な芸の正統を伝え,また,舞踊の名手として名高い。芸談を記録したものに《舞踊芸話》《三津五郎芸談》があり,ほかに《坂東三津五郎舞台写真集》がある。49年芸術院会員,60年文化功労者。(8)8世(1906-75・明治39-昭和50) 本名守田俊郎。初名3世坂東八十助。前名6世坂東簑助。俳名喜好,是真。別号虚仮是真。1962年9月襲名。7世の養子。実悪,老け役に長じた。《戯場戯語》《歌舞伎 虚と実》など十数冊の著書もある。
執筆者:今尾 哲也
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「坂東三津五郎」の意味・わかりやすい解説
坂東三津五郎【ばんどうみつごろう】
→関連項目越後獅子
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の坂東三津五郎の言及
【歌舞伎】より
…だが,南北の才能も,個性の強烈な実力派の役者たちがいてこそ花開いたものである。初世尾上松助(松緑),5世松本幸四郎,5世岩井半四郎,3世坂東三津五郎,7世市川団十郎,3世尾上菊五郎らの実力と個性をよく見きわめ,彼らの芸の魅力を十分に計算した上での作劇の成功が,南北を名作者たらしめたのである。南北の作品の中で,とくに〈色悪〉〈悪婆〉という新しい人間像の典型が確立したことも忘れられない。…
【坂東流】より
…日本舞踊の流派名。3世坂東三津五郎を流祖とし,現9世三津五郎に至る。3世は文化・文政期(1804‐30)の江戸随一の所作事の名手で,変化物(へんげもの)に名作を残した。…
【まかしょ】より
…振付3世藤間勘兵衛。3世坂東三津五郎七変化(しちへんげ)所作事《月雪花名残文台(つきゆきはななごりのぶんだい)》の一。当時の江戸市中を,〈まかしょまかしょ〉と叫びながら札をまき,寒参りを代行する願人坊主(がんにんぼうず)の姿を舞踊化したもの。…
※「坂東三津五郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

 (初世)[1745~1782]
(初世)[1745~1782] (3世)[1775~1832]江戸の人。初世の実子。
(3世)[1775~1832]江戸の人。初世の実子。 (7世)[1882~1961]東京の生まれ。12世
(7世)[1882~1961]東京の生まれ。12世