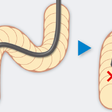内科学 第10版 「内視鏡診断」の解説
内視鏡診断(消化管の画像診断学)
消化器診療において,内視鏡の果たす役割は大きい.内視鏡が観察対象とする疾患は,各臓器における腫瘍性病変,潰瘍性病変,炎症性病変,血管性病変などきわめて多岐にわたる.内視鏡の最大の特徴は病変そのものをカラー画像でリアルタイムに直接観察できることである.そのルーツは19世紀後半から登場した硬性胃鏡に始まり,軟性胃鏡,胃カメラ,ファイバースコープ,電子スコープへと進化し消化器内視鏡診断学を発展させてきた.近年ではカプセル内視鏡も加わり,ますますその診断領域は広がりつつある.そして,従来からの色素散布や超音波内視鏡のみならず,拡大観察や特殊光観察の機能も活用されるようになり,それらの機能は内視鏡による病理学的診断の領域にも近づこうとしている.
一般的な内視鏡本体の全体像を図8-1-1に示す.内視鏡はおもに挿入部と操作部に区分され,挿入部は先端部と湾曲部,軟性部に分けられる.電子スコープの場合,先端部にテレビカメラに相当する半導体撮影素子(charge coupled device:CCD),光源装置から導かれた光を投射するライトガイドがついている.多くの内視鏡では2つのアングルノブによって湾曲部を上下・左右方向に屈曲させることができ,軟性部の前後・回旋操作も用いて内視鏡を操作する.操作部には送気・送水ボタン,吸引ボタンがついており,腸管の内腔を送気によって拡張したり,CCD前面のレンズを送水によって洗浄したり,腸管内容を吸引したりできる.また,ほとんどの内視鏡は鉗子孔を有しており,さまざまなデバイスを用いての内視鏡的インターベンションが可能である.
各疾患の内視鏡診断については別項にゆだねるとして,消化管の内視鏡診断は原則「存在診断」,「質的診断」,「量的診断」の順序で行う.進行癌や活動性潰瘍などの粗大病変の場合,その「存在診断」は比較的容易である.しかし,早期癌をはじめとする微小病変となると容易ではない.微小病変の発見のためには通常観察像でみえる粘膜のわずかな凹凸不整や色調の変化,出血などの微細な所見をまず拾い上げることが重要である.そして,それら1つ1つを読解できなければ,病変の存在すら疑うことはできない.存在を疑うことができれば「質的診断」へと進む.病変の存在部位,大きさ,形状,色調,易出血性,周辺粘膜の性状(襞集中やひきつれなど)などの通常観察所見に加えて,インジゴカルミンによる色素散布,可能であれば拡大観察,特殊光観察などにより総合的に良・悪性を診断する.それらの情報から,病変の中でも病変性状を反映すると思われる部位に対して狙撃生検を行い,後ほど病理診断を得る.次に具体的治療方針決定のための「量的診断」が必要になる.早期癌か進行癌かを,病変の存在部位,大きさ,形状,周辺粘膜の性状や空気量による病変周囲を含めた腸管壁の伸展性などによって診断する.さらに早期癌であれば内視鏡治療適応の有無について,進行癌であれば手術適応の有無についての診断が必要になる(良性疾患であっても切除を要する場合は同様の評価が必要である).ちなみに,遠隔・リンパ節転移の有無,腹水の有無には体外式の超音波検査やCT検査が必要になる.
a.上部消化管内視鏡(esophagogastroduodenoscopy:EGD)
食道・胃・下降脚までの十二指腸をおもな観察領域とする.従来の経口挿入に対して,より挿入時の苦痛が少ない経鼻内視鏡も近年広く普及してきた.腹痛や貧血,胃癌検診のX線検査で異常所見を認めた場合などに検査適応となる.近年では人間ドックの一検査項目として行われることも多い.各種内視鏡検査のうちで最も頻回に行われる検査であり,その操作や所見の読解はほかの内視鏡検査の基本となる.
EGDに課せられてきた最も重要な役割である早期胃癌の診断学は,戦後の内視鏡学の歴史であるといっても過言ではない.早期の食道癌と胃癌については,内視鏡的切除術の適応病変であるか否かの診断が重要であり,近年では特殊光を用いた拡大観察がその診断に活用されている.
b.大腸内視鏡(colonoscopy)
大腸(直腸・結腸)を観察領域とするが,回腸も終末部にかぎり観察することができる.経肛門的に盲腸や回腸末端部まで内視鏡を挿入するが,大腸は腹腔内に固定されていない部分があるため,その挿入はEGDに比して難しく修練を要する.大腸にはハウストラや屈曲部によって内視鏡観察の死角となりやすい部分があり,それらを理解したうえで内視鏡を丁寧に操作し見逃しのない観察に注意を払わなければならない.近年,大腸の腫瘍性病変に対する拡大観察が広く普及するようになった.拡大観察所見に基づいた組織学的評価も確立されてきており,内視鏡的切除術の適応病変であるか否かを診断するにあたっての根拠として活用されている.
c.小腸内視鏡検査(enteroscopy)
以前までは全小腸に対しての内視鏡観察は実用的ではなかった.しかし,近年バルーン内視鏡やカプセル内視鏡が登場し,実用的な全小腸内視鏡観察が可能になった.
ⅰ)バルーン内視鏡(balloon-assisted endoscopy)
観察対象となる臓器はおもに小腸である.しかし,その挿入性の高さから,癒着などの理由により通常の大腸内視鏡では全大腸を観察できないときの大腸内視鏡としてや,Roux-en-Y吻合などで輸入脚を有する患者における内視鏡的逆行性膵胆管造影としても用いられている.
通常の内視鏡との大きな違いは,先端バルーンつきのオーバーチューブを併用して内視鏡挿入を行うことである.そのオーバーチューブ先端のバルーンを拡張させることによって,内視鏡が通過した腸管を内側から把持してその腸管の伸展を防止することができる.それによって複雑な屈曲を有した小腸においても,内視鏡挿入の力が腸管の伸展に費やされることなく,先端部に伝わるようになり深部小腸への内視鏡挿入が可能となる(図8-1-2).オーバーチューブの先端のみにバルーンを有するものをシングルバルーン内視鏡といい,内視鏡の先端にもバルーンがついているものをダブルバルーン内視鏡という(図8-1-3).バルーン内視鏡本体の基本構造は通常内視鏡と同様であり,これによって全小腸における内視鏡観察のみならず内視鏡的インターベンションも可能になった.
ⅱ)カプセル内視鏡(capsule endoscopy)
観察対象となる臓器は小腸であり,現在の保険適応は,上部内視鏡検査・大腸内視鏡検査で出血源を認めず,小腸が出血源と疑われる消化管出血に対してのみである.従来の内視鏡検査とは大きく異なり,被験者は絶食ののちにカメラを内蔵した全長27 mmのカプセル(図8-1-4)を飲みこむだけである.カプセルは腸管蠕動によって小腸内を移動していき,内蔵カメラがとらえた連続ビデオ画像が電波信号によって体外に装着したレコーダーに送信され蓄積される.一般には検査終了後にレコーダーから画像情報をダウンロードし専用のソフトウェアで解析し診断する.カプセルは検査終了後に肛門から体外に排出され廃棄される.カプセル内視鏡の利点は,低侵襲性であることと生理的環境下での小腸観察が可能であるということである.一方,欠点としては現在の技術ではカプセルの移動の意図的なコントロールは実用化されていないので,病変部分を往復しての詳細観察は不可能である.観察のみの機能しかもたないため,組織採取や内視鏡的インターベンションはできない.また,腸管狭窄などがあるとカプセルが滞留し,排出されない場合は開腹手術やバルーン内視鏡による回収を要することがあるので注意が必要である.
d.超音波内視鏡検査(endoscopic ultrasonography:EUS)
EUSの観察対象は全消化管疾患と胆膵疾患,それらに関連したリンパ節などである.その他の内視鏡が病変や病変周囲の表面構造を観察するのに対し,EUSは深達度診断をはじめとする断面での評価が可能である.診断にあたっては,消化管壁の構造,周囲臓器の解剖学的位置関係の把握が必要である.また,超音波の性質にも精通していなければならない.
機材としてはラジアル型の超音波内視鏡専用機または細径超音波プローブを用いることが多い.消化管のEUSの基本壁所見は5層とされている(図8-1-5).観察は腸管内に脱気水を充満して行う.胆膵臓器に関しては,超音波内視鏡専用機によって胃十二指腸内腔から全体像を観察したり,intraductal ultrasonography (IDUS)として胆管内に細径超音波プローブを挿入して胆管・膵管周囲近傍の観察を行う.従来の観察のみの機能に加えて,近年ではコンベックス型の専用機を用いて,超音波内視鏡下穿刺術(endosonography-guided fine needle aspiration:EUS-FNA)による深部組織の細胞採取なども行えるようになってきている.[林 芳和・山本博徳]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報