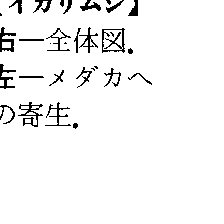イカリムシ (錨虫)
Lernaea cyprinacea
淡水魚類の外部寄生虫の1種。橈脚(じようきやく)亜綱ウオジラミ目イカリムシ科の小型甲殻類。雌の成体は体長4~12mmくらい。体は棒状で,体の前部をウナギ,フナ,キンギョ,メダカなどの皮膚や口腔の粘膜に深く食いこませ,体前部にある錨状の固着器で宿主の体の組織内に固定する。胴部は宿主の体表に出ている。春から秋にかけての繁殖時期には,体の後部に1対の細長い卵囊が現れ,この中の卵からノープリウス幼生がかえり,メタノープリウス,コペポジット期を経て成体となるが,雄は自由生活幼生期の最後の幼生期であるコペポジットで交尾し,その後で死ぬ。雌はコペポジット期になると宿主を求め,その体内に食い入り,変態を完了し,棒状の胴部を宿主の体外に現し,成長を続ける。イカリムシが多数寄生した魚は著しく弱って,ついには死ぬこともあり,養魚池などに多数発生すると大きな被害を与える。
執筆者:蒲生 重男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
イカリムシ
Lernaea cyprinacea
顎脚綱ウオジラミ目イカリムシ科 Lernaeidaeの淡水産寄生動物。体長 7~9mm。体は棒状で,無色ないし淡黄緑色。ウナギ,コイ,フナ,キンギョ,メダカなどの淡水魚の体表や鰓,口腔に寄生する。自由生活をしていた幼虫が成熟して交尾をすると,雄は死ぬが,雌は宿主である淡水魚にとりつく。雌の体は棒状に変態し,頭胸部に 2対の錨(いかり)状の突起が発達する。この突起を宿主の体内に侵入させ,終生宿主にとりついたままの状態でいる。アジアからヨーロッパにかけて広く分布し,養魚上の大敵。イカリムシ科には海産魚に寄生する種が多く,いずれも形態的に特殊化している。(→顎脚類,甲殻類,節足動物)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
イカリムシ
いかりむし / 錨虫
[学] Lernaea cyprinacea
節足動物門甲殻綱ウオジラミ目イカリムシ科に属する水生小動物。ウナギ、コイ、フナ、キンギョなど淡水魚の体表やえら、口腔(こうこう)などに寄生する。ヨーロッパからアジアにかけて広く分布し、近縁種が約50種知られている。体は長さ7~9ミリメートルの棒状で、半透明ないし淡黄緑色を帯びる。雌の頭部が変形して錨(いかり)に似たような2対の突起をもち、それを宿主の体内に挿入して固着し、寄生生活をする。胸部も細長く伸び、終生宿主から離れることはない。卵嚢(らんのう)は紡錘形で、内部に球形の卵が多数収められている。孵化(ふか)したノープリウス幼生は自由生活をしたのちに魚の体表につき、宿主の体液を吸収しながら脱皮、成長する。成熟して交尾すると雄は死んでしまうが、雌は変形して固着生活を続けるという複雑な生活史をもっている。
外見は甲殻類とは思えない姿であるが、基本的な形はよく残っており、糸状の第1、第2触角のほか、第1から第3顎脚(がっきゃく)や4対の胸肢(きょうし)などが認められる。
[武田正倫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
イカリムシ
橈脚(かいあし)類イカリムシ科の甲殻類。ウナギ,コイ,キンギョなどの淡水魚の口腔や鰓(えら)に寄生する。雌は棒状で長さ4〜12mmくらい,ほとんど無色。付属肢は著しく退化し,頸部(けいぶ)までを寄主に挿入している。自由幼生末期に交尾し雄は死亡。雌は寄主を求めて固着,産卵する。養殖魚の大敵で,多数寄生した魚は非常に弱り,死ぬこともある。ユーラシアに広く分布。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報