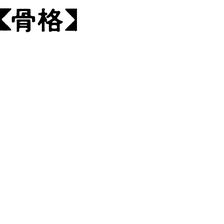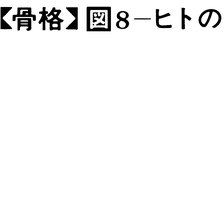翻訳|skeleton
改訂新版 世界大百科事典 「骨格」の意味・わかりやすい解説
骨格 (こっかく)
skeleton
単細胞動物はいうにおよばず,多細胞の動物でも体の構造が簡単なものは,全身が軟組織のみからできているが,体制の複雑な高等動物ではなんらかのしっかりした支柱または枠組みが発達して体を支えるようになる。このような構造を一般に骨格という。骨格ができると多くの場合筋肉がこれに付着するから,骨格は運動のための支点を与えたり,てこの腕として働いたりする。すなわち骨格は動物体の支柱をなすとともに,受動的な運動器官でもある。この点が,支柱の役割だけしかもたない建築物の骨組みと違っている。骨格には外骨格と内骨格の区別がある。外骨格というのは,昆虫や甲殻類に見られるように,体の外表を包んでいる堅い殻で,これは支柱や運動のほかに体表の保護という役目も兼ねている。骨格を動かす筋肉は内部にあって,内側から骨格についている。内骨格というのは,典型的なものは脊椎動物に見られるもので,体の内部にあり,どの部分も体表には露出していない。筋肉はすべて骨格の外部からこれにつく。
動物界における骨格
広義の骨格は動物界に広く分布しているが,それらは必ずしもすべてが相同の器官ではなく,その発生学的由来もまちまちである。
海綿動物はわずかな数種を除いてはみな骨格をもっている。骨格は種類によって違うが,多くの場合には骨片spicule(針骨)という炭酸カルシウムまたはケイ素化合物からなる多数の小体であるが,またある種類では角質様の繊維が構成する不規則な立体的網目細工(これが普通に市販されている海綿である)をなす。
腔腸動物のうちではサンゴの類だけが骨格を有し,しかもそれは風変わりな骨格である。これにもいろいろの種類があり,簡単なものは間充組織中に存在する無数の硬質性の微細骨片である。複雑なものでは間充組織中に石灰質のセメント様物質が分泌されて,骨片を結合するため細密な堅い中軸骨格ができあがる。普通にサンゴとして観賞されるのはこの種の骨格である。
棘皮(きよくひ)動物では外骨格がよく発達し,表皮の直下に石灰質の小甲板の集合からなる骨格をもっている。海岸でウニやヒトデの死体を拾うと,堅い殻だけ残っているが,あれはこれらの動物の骨格である。棘皮動物のうちでもナマコは全身が柔らかく,骨格を欠くように見えるが,実は皮膚の中に微細な骨片が無数に埋もれている。
節足動物はその体表にキチン質の堅い層が発達して一種の骨格をなしている。この骨格は一方では体表の保護をなすとともに,他方では筋肉の付着点を与えて受動運動装置としての役割を営む。大多数の種類では骨格にキチン質の薄いところがあって,そこで体幹や体肢が折れ曲がるようになっている。これは一種の関節で,節足動物の名はここからきている。
軟体動物の大多数は体表に石灰質の貝殻を備えて体の保護をなす。これも一種の骨格と考えるべき装置で,体表の表面から分泌されたものである。イカの甲も初めは皮膚の外表に発生するのであるが,後に体の皮下にうずまるようになる。頭足類はこのほかにもう一つ別の軟骨性の骨格があり,頭の中にあって神経中枢を包んでいる。
脊索動物(原索動物と脊椎動物)では骨格が最もよく発達している。これに脊索,軟骨性骨格,骨性骨格の3種が区別される。脊索というのは系統発生的に最も原始的な段階で,特殊な細胞が集まってできた柔軟単純な棒状体をなし,体の中軸をつくっている。原索動物の被囊類(ホヤの類)の幼生やナメクジウオに見られる。軟骨および骨という組織は脊椎動物特有のもので,軟骨性骨格は板鰓(ばんさい)類(サメやエイの類)に,骨性骨格は硬骨魚類以上の脊椎動物のほとんどすべてに見られる。これら3種の骨格は個体発生的にも認められる。すなわち脊索はすべての種類において,発生の初期に現れ,ホヤとナメクジウオとではこれが終生骨格としてとどまるが,魚類以上の動物ではあとから軟骨性の柔軟な骨格が発生して脊索に代わる。サメやエイのような軟骨魚類ではこの軟骨性の骨格は終生存続するが,硬骨魚類以上の脊椎動物では発生が進むとともに軟骨の大部分が骨性の組織で置き換えられる。それにさらに結合組織の一部も骨化して骨格が充実し,複雑化する。無脊椎動物の石灰質の骨格は炭酸カルシウムを主成分とするのに対し,脊椎動物の骨はリン酸カルシウムを主体とする。脊椎動物の進化の歴史では,脊索が最初に現れたことはほぼ確かであるが,軟骨と骨とはともに起源がきわめて古く,どちらが先に現れたのかは明らかでない。
脊椎動物の骨格は一般的に,頭骨,脊柱,前肢の骨,後肢の骨,前肢を胴につなぐ前肢帯(鎖骨など),後肢を胴または脊椎につなぐ後肢体(骨盤)からなり,そのほかに多少の付属的な骨格がある。
脊柱は脊索に代わって体の中軸をなす骨格で,これは脊椎(椎骨)という骨(または軟骨)が1列に連結されてできている。脊柱にはこれを縦に貫く脊柱管という管があって,その中に脊髄をいれている。この点が単に体の支えと受動運動にだけ役だっている脊索に比べて一段の進歩である。このほか脊椎動物では脊柱の前方に頭蓋(とうがい)(頭骨)という特別の骨格部が発達し,その中に脳をいれている。また各椎骨には1対の肋骨が発達し,体腔壁の支柱をなしている。その腹側端は遊離していることもあるが,多くは胸部前壁中に発達した胸骨と連結する。また頭蓋の腹側には消化管の初めの咽頭部を左右から抱く数対の弓状の骨からなる骨格が付属している。これを内臓骨格といい,内臓骨格を形づくる弓状の各骨(または軟骨)を内臓弓と称する。そのうちとくに第1内臓弓上顎・下顎の骨格になるのでこれを顎弓,第2内臓弓は一部が舌骨になるので舌骨弓(舌弓)といい,第3以下の内臓弓を鰓弓(さいきゆう)というが,ときには鰓弓を内臓弓の同義語に用いることがある。鰓弓の数は5~7対である。鰓弓は魚類ではエラの骨格であるが,四足動物では胚期に現れるのみでその後は他の器官へ分化する。内臓骨格の頭蓋に対する関係は,あたかも肋骨の椎骨に対する関係に似ている。内臓骨格は動物が高等になるにしたがって頭蓋に対する関係が密接となり,両者を切り離すことができなくなってくる。それで内臓骨格に由来する上下顎の骨格と頭蓋を合わせて広義の頭蓋と名づける。
以上が中軸骨格であるが,このほかに高等脊椎動物では体肢の骨格が発達している。これは対をなして前後に2対あるのが普通であるが,いずれにせよ魚類の対ひれ(鰭)を支える骨格部の変形したものにほかならない。これに肢帯と自由部とが区別される。肢帯とは前肢の肩帯と後肢の腰帯(骨盤帯)で,いずれも体壁中に没入して,体表から突出している自由部を中軸骨格に結びつける役割を営む。
魚類の骨格
軟骨魚類では全部が軟骨性,硬鱗魚類では軟骨に一部は骨を交え,硬骨魚類では大部分が骨で,一部軟骨を交えている(一部にはすべて軟骨の種類もある)。骨格の主体をなす中軸骨格は頭蓋と脊柱からなる。椎骨は尾部を除いてはみな1対または2対の肋骨を備えているが,胸骨を欠いている。頭蓋は軟骨魚類では全体が軟骨頭蓋という比較的単純な箱形の骨格部からなり,中に脳をいれている。ところが硬骨魚類になると,この軟骨頭蓋がいわゆる軟骨性骨として骨化するだけでなく,多数の新しい骨が二次的な皮骨(膜骨)として追加されてその様相は著しく複雑化し,その構成骨の数は全脊椎動物中で最も多い。内臓骨格はよく発達し,本来の頭蓋との結合はまだ疎で,多分に独立性を保持している。第1内臓弓すなわち顎弓は,軟骨魚類では口蓋方形軟骨と下顎軟骨とからなり,それぞれ上下顎の支持骨として歯を備えている。硬骨魚類では上顎には顎前骨および上顎骨が,また下顎では歯骨が皮骨として発生し,そのため口蓋方形軟骨は上顎の後内側のほうに押しやられて口蓋骨,方形骨そのほか2,3の骨を生じ,下顎軟骨はその後部が関節骨となるとともに残余のものはメッケル軟骨としてその残形をとどめる。このようにして,顎関節は軟骨魚類では口蓋方形軟骨と下顎軟骨との間にあるが,硬骨魚類ではこれが方形骨と関節骨との間に移っている。体肢の骨格はひれの支えをなし,まだ比較的不完全な状態にとどまっている。
両生類の骨格
椎骨は多く横突起の末端に肋骨をつけているが,肋骨は短小で,ほとんど痕跡的である。腰帯と結合する椎骨はただ1個あるだけである。カエル類では胸骨はよく発達しているが,肋骨とは関係がなく,おそらく高等動物の胸骨と相同の骨ではない。頭蓋では頭蓋の骨が減少し,二次頭蓋(すなわち膜性頭蓋)がこれを補っている。顎関節は方形骨と関節骨の間にある。頭蓋と第1椎骨とを結合する顆状(かじよう)突起(後頭顆)が2個あることが両生類の大きな特徴である。内臓骨格には若干の新しい骨が添加され,上下両顎と頭蓋との間には魚類では舌顎軟骨が介在するが,両生類では,これが耳の空所(軟骨魚類の呼吸孔と相同のもの)に転位して耳小柱(あぶみ骨と相同)になっている。体肢の骨格は,体肢がひれから脚に変わったのにつれて,高等脊椎動物のそれと同一の構成をとるにいたった。すなわち,自由部に上腕(大腿),前腕(下腿),手(足)の3部が区別され,前腕(下腿)には橈骨(とうこつ)(脛骨)と尺骨(腓骨)という2個の骨が並列している。ただしカエル類では,橈骨と尺骨が合体して橈尺骨となり,脛骨と腓骨が合体して脛腓骨となっている。また放射状に分かれた指が形づくられていて,その数は原則として5本ずつであるが,二次的に数の変動が認められる。
爬虫類の骨格
第1頸椎体が分かれて第2頸椎体に癒合し,歯突起をつくるために,鳥類,哺乳類に見るような環椎と軸椎という特殊な椎骨を認める。また頭蓋はただ1個の顆状突起で環椎と結合されている。これらの機構によって頭の上下左右運動が容易になったわけである。胸部の肋骨は長くて,その腹側端が胸骨に連結することが多い(ヘビには胸骨はない)。下顎は歯骨,関節骨など数種の骨からなり,顎関節は方形骨と下顎の関節骨との間に形成され,また中耳の耳小骨が耳小柱だけである点は,両生類と同様である。一部のグループを除き,体肢の骨格は有尾両生類のそれと大差ないが,後肢では足根骨は近位と遠位の2列になって並び,下顎と足との間の関節はこの両列の足根骨間につくられている。
鳥類の骨格
頭骨では後頭骨に1個の顆状突起を有すること,下顎の関節骨と頭蓋との間に方形骨の介在すること,耳小骨は耳小柱のみであること,下顎が関節骨,角骨,歯骨など数種の骨からなることは,爬虫類の状態に同じである。成長するにつれて脳頭蓋の骨は互いに融合して一体化してしまう。下顎の骨も一体化する。脊柱は頸部が長くて屈曲が自由であるが,胸腰部は前後に融合して屈曲性がまったくない。尾部ははなはだ短小である。胸骨は大きく広くて,飛行に最も大きな働きをする胸筋の起始をなしている。またこの筋の付着につごうのよいように胸骨正中部に隆峰という突出部がある。肩帯に肩甲骨,鎖骨,烏口骨(烏喙(うかい)骨)の3骨,腰帯に腸骨,恥骨,坐(座)骨の3骨の見られる点は,爬虫類に等しい。しかし成鳥では仙椎とともにすべて融合して一体となる。前肢は翼の支柱をなしていて,手骨は著しく退化している。後肢では爬虫類と同じく下腿と足との間の関節が足根骨の近遠両列の骨の間にあり,近位の足根骨が下腿の脛骨と合体しているのでこの骨を脛足根骨という。腓骨は小さく退化している。また遠位の足根骨は中足骨と合体し,1本の足根中足骨になっている。このように鳥類では骨格融合が著しいのと,多くの骨で骨壁が薄く,内部が中空になっているのが特徴である。
哺乳類の骨格
軟骨頭蓋は十分に硬骨化し,頭蓋を構成する骨の数は比較的減少している。後頭骨は必ず左右2個の顆状突起で環椎と関節する。下顎はただ1種の骨からなり,これは下等脊椎動物の歯骨に相当する。鳥類以下の頭蓋で見た関節骨と方形骨とは鼓空内にかくれ,それぞれつち骨ときぬた骨とになっている。ゆえに哺乳類のつち骨きぬた骨関節は下等脊椎動物の顎関節に相当するものであり,哺乳類では顎関節は新たに下顎骨と鱗状骨(側頭骨の一部)との間にできている。両生類・爬虫類の耳小柱はあぶみ骨になる。脊椎はおおむね頸,胸,腰,仙,尾の5区域に分けられる。頸椎は動物の種類いかんにかかわらず7個である(ただしナマケモノとカイギュウ(海牛)は例外)。肩帯では肩甲骨はよく発達するが,烏口骨は多くは肩甲骨の一突起(烏口突起)となり,鎖骨は不完全,またはまったく欠如する例が少なくない。自由肢は種類によりひじょうに変化に富む。
執筆者:藤田 恒太郎+田隅 本生
ヒトの骨格
ヒトの骨格は哺乳類としての共通の性格をもつことはもちろんであるが,また哺乳類の中で特殊化したヒトの体制の特徴を示している。そのおもな点をあげると,(1)脳の発達にともなって,ひじょうに大きい頭蓋骨をもつ。顔面頭蓋といって顔の部分をつくる部分にくらべて,脳頭蓋(神経頭蓋)という脳をいれる部分が著しく大きい。(2)ほかの哺乳類にくらべて,ヒトの顔面頭蓋は脳頭蓋に圧迫されて萎縮しているということができ,ヒトに鼻腔(鼻炎など)や副鼻腔(蓄膿症)の病気が多いのも,そのためであると説く人もある。上顎骨と下顎骨が,とくにその歯槽部がサルや類人猿に比して著しく退化しているのはヒトの頭蓋の著しい特徴で,これも歯の病気を多くしている要因と考えられる反面,ものをかむときの脳への衝撃を少なくして脳の発達をうながす一因となった。(3)直立姿勢をとるようになって,ヒトの頭骨は,四足獣のように後方から脊柱で支えられることなく,下方から力学的に無理なく支えられるようになった。大後頭孔(脳から脊髄へのつづきを通す孔)が,四足獣では後下方についているがヒトでは脳頭蓋の直下についている。(4)頭蓋をつくる骨の数が一般哺乳類より多少減って15種23個となっている。これは下等哺乳類では独立していた骨が癒合した結果である。たとえば上顎にある間顎骨(または切歯骨)は,ヒトでは本来の上顎骨と癒着しているし,また下顎骨も多くの哺乳類では縫合によって左右分離しているが,ヒトではサル,ゾウ,イノシシなどと同様に左右のものが一つに癒着している。(5)脊柱は直立姿勢のために上から下へとしだいに太くなり,下肢帯をつける仙骨でもっとも太くなっている。四足獣では脊柱の太さは部位によりあまり変わらない。また上半身や頭部を弾力的に支え,歩行や跳躍のさいの衝撃を緩和するために,脊柱はヒトに特有の湾曲を示す。それにしても直立姿勢の無理は,とくに栄養がよくなって体重の負担の大きい傾向のある近年は人体のいろいろなところに吹き出してくる。脊柱の湾曲の異常や椎間板ヘルニア,種々の腰痛症などはそのような要因によることが少なくない。尾の退化とともにヒトでは尾骨が極度に退化的である。(6)ヒトでは上肢(手)が地面から離れて手仕事をするようになり,下肢(足)だけが体を支えて直立や歩行の用をなすので,上肢の骨格に比して下肢の骨格が著しく大きくなっている。また肩関節や肘関節は上肢の可動性を十分に発揮できるようにつくられ,反面下肢では骨の間のがんじょうな結合に重点がおかれて自由な可動性が後退している。(7)骨盤は,直立姿勢のために腹部内臓を下から受けとめる必要から,また長い胎生期をもつ大きい胎児を受けるために,四足獣に比して大きい鉢の形をなしている。おそらくこのような力学的要請から,骨盤をつくる骨はたがいにがんじょうに靱帯(じんたい)で結合され,可動性がとぼしい。これが動物にくらべてヒトの分娩を困難にしている理由のひとつである。
骨格のコラム・用語解説
【ヒトの骨格を構成するおもな骨】
- 頭蓋 skull
- 一般には頭骨ともいわれる。脳を収容する脳頭蓋と顔面をつくる顔面頭蓋に区別される。前頭骨,側頭骨,後頭骨,蝶形骨,上顎骨,下顎骨などの骨からなる。 ▶▶頭骨
- 鎖骨 clavicle
- 胸の前面の上界をなす骨であり,一方は胸骨と関節を営み,他の一方は肩甲骨と関節でつながる。 ▶▶鎖骨
- 肩甲骨 shoulder blade
- 肩の背部にある骨。鎖骨とともに上肢を体幹につなぎとめる。 ▶▶肩甲骨
- 胸骨 breast bone
- 肋骨とともに胸郭を構成する骨。胸の前面正中部にある骨で,細長く扁平な形をしている。
- 肋骨 ribs
- 胸骨とともに胸郭を構成する細長い骨で,ヒトでは12対ある。弓形をしているが,長さや形は部位によって異なっている。 ▶▶肋骨
- 上腕骨 humerus
- 上腕の支柱をなす骨。棒のように長い骨で,中央部は管になっている。 ▶▶上腕骨
- 橈骨 radius
- 前腕の2本の骨のうち,親指側にある骨。尺骨とともにひじから手首までの骨格をなす。 ▶▶橈骨
- 尺骨 ulna
- 橈骨とともに前腕(ひじから手首まで)の骨格をなす骨で,前腕の内側(小指側)にある。手のひらをやや上へ向けて,前腕を机の上に置けば,尺骨が全長にわたって机の面に触れる。このようにして物の長さを測る(尺をとる)ところから尺骨の名がある。この骨の上端の肘頭(ちゆうとう)という大きいかたまりは,生体ではいわゆる〈ひじがしら〉をつくって突出する。肘頭の前面はまるくえぐれて〈半月切痕〉をなし,上腕骨の糸巻状の〈滑車〉をいれて〈ひじ関節〉をつくる。半月切痕の外側の面には〈橈骨切痕〉という凹所があり,橈骨との関節面をなしている。下端は〈尺骨小頭〉という丸いふくらみをつくっており,その周縁は再び橈骨と関節を営む。小頭の内側下端には〈茎状突起〉という小さい突出がある。肘頭,小頭,茎状突起などは生体でよく触れることができる。
- 脊柱 vertebral column
- 一般に背骨といわれているもので,ヒトの場合,32~34個の椎骨(脊椎ともいう)からなる。 ▶▶脊柱
- 骨盤 pelvis
- 腰部にある骨格で,第5腰椎,仙骨,尾骨,寛骨からなる。寛骨はさらに腸骨,恥骨,座骨に区別される。 ▶▶骨盤
- 大腿骨 thigh bone
- 大腿の中軸をなす骨。長い棒状で,人体中最大の骨で,股関節で骨盤とつながり,膝関節で脛骨とつながる。 ▶▶大腿骨
- 膝蓋骨 patella
- ひざの前面にある平たい骨で,俗に〈おさら〉といわれる。大きさは子どもの手のひらくらいで,後面は全部が関節面をなし,軟骨でおおわれる。靱帯または腱の中に発生した骨を種子骨といい,手のひらに5個,足の裏に2~5個あるが,膝蓋骨も種子骨の一種である。
- 脛骨 shinbone
- 〈すね〉の骨で,その外側に並んでいる腓骨とともに下腿の支柱をなしている。上肢の橈骨に相当するが,上肢では尺骨と橈骨とが対等の価値をもっているのに対して,下肢では脛骨が優位を占め,腓骨は従属的である。中央部の〈体(たい)〉は三角柱の形をなし,その前稜は下腿前面の皮下に長く触れることができる。上端は太くなって脛側顆および腓側顆となり,その上面には浅い1対のくぼみがあって大腿骨の下端部を受ける関節面をなす。そのやや下の前面はざらざらした隆起〈脛骨粗面〉をなし,ここに大腿四頭筋の腱がついている。また下端は内下方に向かって脛骨顆という突起を出している。これは内果(うちくるぶし)として,足首の内側に突出している。
- 腓骨 fibula
- 前腕が橈骨と尺骨の2骨で支えられるように,下腿も脛骨と腓骨を支柱とする。しかし下腿では,脛骨が力学的な負荷の大部分をにない,腓骨は添物のように弱小化している。腓骨はよく骨折を起こすが,脛骨の骨折にくらべれば障害ははるかに軽い。形成外科では,腓骨の一部を切り取って,移植の材料にすることもある。比較解剖学的には腓骨が尺骨に相当する。両生類や爬虫類ではほぼ脛骨と対等の形態と機能を示すが,鳥類や哺乳類では,しだいに脛骨に対する比重を減じ,ときにはほとんど退化している。ヒトの腓骨は,中央部の腓骨体と上端のふくらみ(腓骨頭),下端のふくらみ(腓骨顆)からなる。腓骨顆は外果(そとくるぶし)として足首の外側へ突出している。腓骨頭には関節面があって脛骨と関節を営んでいるが,腓骨顆は脛骨と結合組織結合を営んでいる。そのため腓骨と脛骨との間の相互運動はきわめて小さい。この点が上肢の橈骨と尺骨との間の大きい運動性と対照的である。
→骨
執筆者:藤田 恒夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「骨格」の意味・わかりやすい解説
骨格
こっかく
体を支え、体形をつくっている器官。ヒトの体内には200余個の骨がいろいろの形式で結合して、体の堅固な基本形となる骨格系をつくっている。骨格系は骨が主体となってこれに軟骨組織が加わり、組み立てられている。本来、骨格はこれに付着した筋(骨格筋)によって動かされる運動作用が主体となるが、そのほか、体の支持、保護、造血作用などがある。すなわち、骨格の動きに伴ってつくられる体の姿勢を維持し支える働きとともに、頭蓋(とうがい)にあっては脳髄、胸郭では肺臓、心臓、骨盤では骨盤内臓というように、それぞれを保護している。造血作用とは、新生児、小児では全身の骨格、成人では胸骨、肋骨(ろっこつ)、大腿骨(だいたいこつ)、腸骨などの骨髄で血液細胞産生が行われていることをいう。
骨格を構成する骨の連結は、その働きのうえからみて可動結合と不動結合とに分かれる。骨の連結一般を広義の関節という場合には、可動結合は狭義の関節、不動結合は縫合と線維性軟骨結合とを含むことになる。可動結合(狭義の関節)では関節をつくる二つの骨面の間に関節腔(くう)という小腔をもっている。縫合は頭蓋骨にみられる鋸歯(きょし)状の骨結合であり、線維性軟骨結合は骨盤の恥骨結合、脊椎(せきつい)骨間の結合にみられ、線維性軟骨が骨間に介在する。
全身の骨格は体幹骨(体軸骨格)と体肢骨(上肢骨と下肢骨)に大別される。体幹骨には体の垂直軸を形成する頭蓋骨、脊柱、胸郭に参加する胸骨、肋骨が含まれる。頭蓋骨は23個の骨からなり、下顎(かがく)骨だけは側頭骨と可動関節をつくり、他はすべて縫合により強固に結合している。舌骨のみは下顎骨の下方で遊離して存在する。頭蓋骨は脳を収容する脳頭蓋(前頭骨1、頭頂骨2、側頭骨2、後頭骨1、蝶形骨(ちょうけいこつ)1、篩骨(しこつ)1)および顔面頭蓋(鼻骨2、上顎骨2、頬骨(きょうこつ)2、下顎骨1、涙骨2、口蓋骨2、下鼻甲介2、鋤骨(じょこつ)1)、ほかに舌骨(1)からなる。脳頭蓋は脳を固定、保護し、顔面頭蓋は顔面形成の基盤となっている。脊柱は躯幹(くかん)の中心軸となるもので、頭蓋を支え、胸腔内臓を保護する肋骨の支点となっている。脊柱は脊椎骨(頸椎(けいつい)7、胸椎12、腰椎5、仙椎5、尾椎3~5)が上下に連結し、正中前額面(一般でいう正面)では垂直、正中矢状(しじょう)面(一般でいう側面)では緩いS状の彎曲(わんきょく)を示す。仙椎と尾椎とはそれぞれ融合して1個の仙骨、尾骨となっている。躯幹の運動は脊柱の屈伸(前後左右)運動と回旋運動によって行われる。胸郭は胸椎、肋骨、肋軟骨、胸骨が連結して籠状(ろうじょう)構造をつくり、肺臓、心臓を中心とする胸腔臓器を収容して、それらの支持、保護の働きをしている。この部位の内・外肋間筋の収縮運動によって胸椎を支点とする肋骨の上下運動がおこり、胸郭の容積が増減して肺の呼吸運動となっていく。肋骨と胸骨とを結合する肋軟骨は硝子(ガラス)軟骨で、上位7対は胸骨と肋骨とを連結するが、これに続く下位3対は上位の肋軟骨と結合することによって胸骨と結合している。第11、12肋骨は胸骨まで届かず、先端は遊離していて、いわゆる浮肋となっている。
上肢骨は上肢帯骨(肩甲骨と鎖骨)と自由上肢骨(上腕骨、前腕骨、手根骨(しゅこんこつ)、中手骨、指骨)からなり、下肢骨は下肢帯骨(寛骨(かんこつ))と自由下肢骨(大腿骨、下腿骨、足根骨(そっこんこつ)、中足骨、指骨)からなる。骨盤は寛骨、仙骨、尾骨で構成され、脊柱を支え、骨盤内臓を収容し、保護、安定させている。
骨格の性差を全体的にみると、男性骨格は女性のそれよりも大きくて重い。男女差のもっとも著明な点は骨盤形成の骨と骨盤全体の形である。年齢的な変化から骨格をみると、新生児の頭は身長の約4分の1であるが、成人では身長の8分の1程度となる。また、新生児の脊柱は全体にわたって後方に弓状となる凸彎であるが、生後3か月ころには頸部前彎、生後1年ころには腰部前彎も生じ、緩やかなS状彎曲となる。胸郭は幼児、小児では丸い樽(たる)状で左右径、前後径がほぼ等しいが、成人ではやや圧平された形状となる。
[嶋井和世]
動物の骨格
動物の体の大きさと形の枠組みを決め、筋肉の付着点となる構造体をいう。表皮や真皮からでき、体の外側を覆うものを外骨格といい、無脊椎動物では、節足動物のキチン質の外層、甲殻類や棘皮(きょくひ)動物のカルシウムに富んだ外層、軟体動物二枚貝類の貝殻などであり、脊椎動物の体表の鱗(うろこ)(ヘビ、トカゲ)や甲(カメ、ワニ、センザンコウ)も一種の外骨格である。これに対し、脊椎動物がもつような、体内にある骨や軟骨でできた骨格を内骨格という。脊椎動物の内骨格は、頭骨‐脊椎骨からなる中軸骨格に四肢の骨が付随したものであるが、その形態は、生活環境との適応を示す変異に富んでいる。一般に内骨格は運動性や成長の面で外骨格よりもはるかに有利である。
無脊椎動物に含まれる有孔虫の殻や海綿の骨片も、体を支持する構造であるから内骨格とよばれることがあるが、筋肉が付着するのではないから定義にはあわない。
[川島誠一郎]
普及版 字通 「骨格」の読み・字形・画数・意味
【骨格】こつかく
 〔唐の故工部員外郎杜君(甫)墓係銘の序〕齊・梁に效(なら)ひては則ち魏・晉に
〔唐の故工部員外郎杜君(甫)墓係銘の序〕齊・梁に效(なら)ひては則ち魏・晉に (およ)ばず、樂府(がふ)に工(たく)みなれば則ち力五言に屈す。律、切なれば則ち骨格存せず、閑暇なれば則ち纖
(およ)ばず、樂府(がふ)に工(たく)みなれば則ち力五言に屈す。律、切なれば則ち骨格存せず、閑暇なれば則ち纖 (せんぢよう)備ふる
(せんぢよう)備ふる (な)し。
(な)し。字通「骨」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
百科事典マイペディア 「骨格」の意味・わかりやすい解説
骨格【こっかく】
→関連項目脛骨
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「骨格」の意味・わかりやすい解説
骨格
こっかく
skeleton
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
知恵蔵 「骨格」の解説
骨格
(垂水雄二 科学ジャーナリスト / 2007年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
世界大百科事典(旧版)内の骨格の言及
【体】より
…胸部には1対の乳があり,腹の正中線上には,胎生期の母体との交通路が遺存したへそがある。
[骨格と内臓]
四肢は芯に骨格をもっているが,頭と胴では,骨格はむしろ体壁の一部をなしており,内部の内臓諸器官を保護している。体を支える軸となる骨格は脊柱で,胴の正中背側部を頸の上端から骨盤まで縦走している。…
※「骨格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
今日のキーワード
自動車税・軽自動車税
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新