精選版 日本国語大辞典 「解放」の意味・読み・例文・類語
かい‐ほう ‥ハウ【解放】
とき‐はな・す【解放】
とき‐さ・く【解放】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「解放」の意味・わかりやすい解説
解放 (かいほう)
大正・昭和期の雑誌。
(1)第1次 吉野作造,福田徳三らの黎明会同人を中心として,デモクラシー思想の普及のために1919年(大正8)6月大鐙閣から発行された総合雑誌。創刊号の定価38銭。20年6月号から麻生久,山名義鶴らが結成した解放社によって編集された。創刊号に〈宣言〉をかかげるなど,他の総合雑誌とは性格を異にし,労働問題,社会問題がとくに重視され,社会主義思想の影響を強く受けた。黎明会,新人会の会員が執筆したほか,荒畑寒村,堺利彦,山川均,山川菊栄などの社会主義者も毎号のように登場している。文芸欄には小川未明,宮地嘉六,金子洋文らが執筆,しだいに労働者作家,社会主義的作家の寄稿が増加したが,関東大震災のため23年9月終刊した。
(2)第2次 25年山崎今朝弥(けさや)の経営に移り,日本フェビアン協会の《社会主義研究》を7月号より《解放》と改題,10月号から総合雑誌化された。定価は50銭。第1次よりもはるかに社会主義の色彩が強く,山内房吉,青野季吉らによってプロレタリア文学の発表の場となった。27年5月から一時期江口渙,小川未明らの日本無産派文芸連盟の機関誌となり,その後山崎の自由奔放な編集で体裁を変えながら33年ころまで刊行された。
(3)第3次 34年10月には渡辺潜を編集発行人として清談社から再び発行された。この《解放》は第2次の巻号を継承しているが,従来のものとは異なり総合雑誌の形をとらず,社会大衆党系の政論雑誌の性格をもっている。執筆者には,主宰者の麻生久のほか,田所輝明,菊川忠雄ら同党系の論者が多い。36年(17巻2号)まで確認されている。
執筆者:梅田 俊英
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「解放」の意味・わかりやすい解説
解放
かいほう
第一次世界大戦直後のデモクラシー思潮を背景として創刊された総合雑誌の一つ。1919年(大正8)5月、大鐙閣(だいとうかく)から創刊。23年9月に終刊。総合雑誌として『改造』や『中央公論』よりも社会主義的で、吉野作造(さくぞう)や黎明(れいめい)会の福田徳三、東大新人会の赤松克麿(かつまろ)を中心として、佐野学(まなぶ)、堺利彦(さかいとしひこ)、石川三四郎らが登場。マルクス主義者とアナキストの呉越同舟である。創作欄は、小川未明(みめい)、宇野浩二、宮地嘉六(みやちかろく)らの初期プロレタリア文学系の創作・評論が主流。24年5月に再刊された第二次『解放』は、山崎今朝弥(けさや)、石川らによって編集されたが、第一次よりも急進的で、プロレタリア文学の舞台となり、葉山嘉樹(よしき)や平林たい子らが活躍した。第二次の廃刊時期は不明だが、32~33年(昭和7~8)ごろとされる。
[松浦総三]
普及版 字通 「解放」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「解放」の解説
解放
かいほう
吉野作造・大山郁夫・赤松克麿(かつまろ)・佐野学ら進歩的知識人や社会運動家を編集顧問・協力者として,1919年(大正8)6月大鐙閣より創刊された総合雑誌。山川均(ひとし)・山川菊栄・荒畑寒村・石川三四郎らも労働運動・普通選挙・婦人参政権獲得運動・水平運動などに大正デモクラシー運動を指導する論陣を張った。関東大震災で休刊。25年10月復刊,プロレタリア文学の拠点となり,34年(昭和9)10月社会大衆党系の政論雑誌となる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ASCII.jpデジタル用語辞典 「解放」の解説
解放
出典 ASCII.jpデジタル用語辞典ASCII.jpデジタル用語辞典について 情報
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

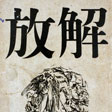
 に之れを囚へ、乃ち府に表して解放せしむ。是れより威恩竝(なら)び
に之れを囚へ、乃ち府に表して解放せしむ。是れより威恩竝(なら)び はる。
はる。