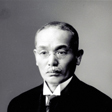精選版 日本国語大辞典 「井上哲次郎」の意味・読み・例文・類語
いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「井上哲次郎」の意味・わかりやすい解説
井上哲次郎
いのうえてつじろう
(1855―1944)
明治・大正期の哲学者。安政(あんせい)2年12月25日、筑前国(ちくぜんのくに)(福岡県)太宰府(だざいふ)に、医師船越俊達(ふなこししゅんたつ)の三男として生まれる。初め中村徳山(なかむらとくざん)に就いて儒教を学んだが、1868年(明治1)博多(はかた)に出て英語を学び、さらに1871年長崎の広運館に入り西洋学を修めた。1875年とくに選抜されて東京の開成学校に入学、1877年東京大学の1期生として哲学を専攻した。1878年井上鉄英(てつえい)(1826―1906)の養子となった。
1880年東京大学を卒業。以後、『東洋学芸雑誌』(1881)を杉浦重剛(すぎうらしげたけ)らと発刊し、日本最初の哲学辞典『哲学字彙(じい)』(1881)の編纂(へんさん)、ベインAlexander Bain(1818―1903)の『心理新説』(1882)の翻訳、『倫理新説』『西洋哲学講義』(ともに1883)の刊行など目覚ましく活動した。とりわけ『倫理新説』は、井上が自らの哲学体系を展開したもので、「余ガ如(ごと)キハ、既(すで)ニ哲学士タラント欲スル者ナレバ、必ズヤ倫理ノ大本ヲ講究セザルベカラズ」と述べて哲学体系への強烈な志向を示している。その間、東京大学助教授として東洋哲学史の編纂に従事した。また一方では、外山正一(とやままさかず)、矢田部良吉(やたべりょうきち)らと『新体詩抄』を出版し、新体詩運動の先駆として、ポエトリpoetryの移入紹介に努めた。
1884年哲学修業のためドイツに留学、クーノー・フィッシャー、W・ブントなどに就学、ドイツ観念論哲学を本格的に研究した。1890年帰朝、日本人として最初の哲学教授に任ぜられた。この年「教育勅語」が渙発(かんぱつ)され、翌1891年井上は政府の意を受けてその解説書『勅語衍義(えんぎ)』を出版した。さらに1893年『教育と宗教の衝突』を刊行し、内村鑑三(うちむらかんぞう)不敬事件などを取り上げ、「要するに、耶蘇(ヤソ)教は元(も)と我邦(わがくに)に適合せざるの教なり」とキリスト教を反国体的宗教として激しく批判した。
井上の哲学体系は「現象即実在論」とよばれ、そのもっとも完成した叙述は「認識と実在との関係」(1900)に示されている。それは、「主観」と「客観」は「実在」の両側面であるとする折衷主義にとどまっている。結局、井上の本領は、『日本陽明学派之哲学』(1900)などの近世儒教研究と、『国民道徳概論』(1912)などの天皇制国家における国民道徳の基礎づけに求められよう。東京都立中央図書館に「井上文庫」として蔵書が収められている。
[渡辺和靖 2016年8月19日]
『船山信一著『増補明治哲学史研究』(1959・ミネルヴァ書房)』▽『渡辺和靖著『明治思想史』(1978・ぺりかん社)』
改訂新版 世界大百科事典 「井上哲次郎」の意味・わかりやすい解説
井上哲次郎 (いのうえてつじろう)
生没年:1855-1944(安政2-昭和19)
明治期の代表的な哲学者。号は巽軒(そんけん)。筑前国(福岡県)太宰府出身。1880年東京大学文学部哲学科卒業後,杉浦重剛らと《東洋学芸雑誌》を発行,また哲学辞典の先駆をなす《哲学字彙》(1881)を著し,外山正一らと《新体詩抄》を刊行。ドイツに6年間留学後,90年帝国大学教授となり,以後日本哲学界の指導者として君臨し,1923年退官とともに東京帝大名誉教授,25年大東文化学院総長,哲学会会長,貴族院議員に選任された。哲学者としては,〈我世界観の一塵〉(1894),〈認識と実在との関係〉(1901)などで,現象即実在論を主張し,《日本陽明学派之哲学》《日本古学派之哲学》《日本朱子学派之哲学》の三部作(1900-05)が特筆される。しかし,明治思想界にあっては,《勅語衍義》(1891)で教育勅語を注釈し,《教育と宗教との衝突》(1893)でキリスト教を反国体的であると攻撃し,《国民道徳概論》(1912)で国民道徳を主張するなど,一貫して天皇制国家主義のイデオローグとして終始した学者として知られている。
執筆者:佐藤 能丸
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「井上哲次郎」の意味・わかりやすい解説
井上哲次郎【いのうえてつじろう】
→関連項目大西祝|柏木義円|桑木厳翼|帝国文学
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「井上哲次郎」の解説
井上哲次郎 いのうえ-てつじろう
安政2年12月25日生まれ。明治15年母校東京大学の助教授。同年外山正一(とやま-まさかず)らと「新体詩抄」を刊行。17年ドイツに留学。23年帰国し,日本人最初の哲学科教授となる。東西の思想の融合統一をめざすとともに,日本主義をとなえ,キリスト教を排斥した。30年東京帝大文科大学学長。昭和19年12月7日死去。90歳。筑前(ちくぜん)(福岡県)出身。旧姓は船越。号は巽軒(そんけん)。著作に「勅語衍義(えんぎ)」「教育ト宗教ノ衝突」「日本古学派之哲学」など。
【格言など】個人的の我は迷いで世界的の我は悟りである
山川 日本史小辞典 改訂新版 「井上哲次郎」の解説
井上哲次郎
いのうえてつじろう
1855.12.25~1944.12.7
明治~昭和前期の哲学者。号は巽軒(そんけん)。筑前国生れ。東大卒。1884年(明治17)ドイツに留学,90年帰国して帝国大学教授。長らく学界に君臨し,スエズ以東第一の哲学者と自称したという。西洋哲学の受容と東洋哲学の研究に努め,両者の融合に腐心したが,一方で国家主義によるキリスト教排撃論を「教育ト宗教ノ衝突」として発表。新体詩運動にもかかわった。東京帝国大学文科大学長・貴族院議員などを歴任。東京学士会院会員。著書「日本陽明学派之哲学」「日本古学派之哲学」「日本朱子学派之哲学」。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「井上哲次郎」の意味・わかりやすい解説
井上哲次郎
いのうえてつじろう
[没]1944.12.7.
哲学者。号は巽軒。東京大学教授。ドイツ観念論の移入に努めるとともに,現象即実在論を説き,東西思想を包括する体系の樹立に努力。『勅語衍義』『教育と宗教の衝突』を発表,国民道徳を唱道し,キリスト教を国体に反するものとして攻撃するなど,国家主義を鼓吹した。多年,哲学界の大御所として君臨した。著書『日本陽明学派之哲学』 (1900) ,『日本古学派之哲学』 (02) ,『日本朱子学派之哲学』 (06) ,『国民道徳概論』など。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「井上哲次郎」の解説
井上哲次郎
いのうえてつじろう
明治〜昭和期の哲学者
筑前(福岡県)の生まれ。ドイツ留学後,東大で哲学史を講じ,哲学界に重きをなす。内村鑑三不敬事件に際して,「教育と宗教の衝突」で国家主義の立場からキリスト教を排撃。新体詩運動にも寄与した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の井上哲次郎の言及
【柏木義円】より
…同志社に学び,1889年卒業後,熊本英学校,同志社予備校で教え,97年以後群馬の安中教会牧師として終生活躍した。同志社教員時代,キリスト教を臣民教育に反するとした井上哲次郎の論理の浅薄さを批判し,安中では《上毛教界月報》(1898‐1936)の編集者として,宗教,教育,政治,社会問題を論じた。とくに一貫した非戦論,キリスト教社会主義を地方民衆とともに生きる視座より唱え,戦争,資本制社会の罪悪を鋭く批判した。…
【国体思想】より
…
[大正デモクラシー期]
まず美濃部達吉の天皇機関説を上杉慎吉が天皇親政論から批判したのに対し,美濃部は国体は文化的概念であるとして法学的世界からそれを除き,吉野作造も日本国体の優秀性は特別の君臣情誼関係という民族精神の問題であるとして政治学の対象から除外し,デモクラシーと国体は矛盾しないとした。大正期には公認のイデオローグ井上哲次郎ですら《我国体と世界の趨勢》で,君主主義と民主主義の調和にこそ国体の安全があると説いた。このため,国体=あるべき国家,政体=現にある国家の意識を生じ,国体論に依拠して体制批判を行う者が労働運動内部にも現れた。…
【新体詩抄】より
…1882年(明治15)に丸善から刊行の日本最初の近代詩集。帝国大学(のちの東京大学)の教官外山正一(ゝ山(ちゆざん)),井上哲次郎(巽軒(そんけん)),矢田部良吉(尚今(しようこん))の共著で,3人の序文,翻訳詩14編,創作詩5編から成る。伝統的な短い詩形を近代には不向きなものと断定し,西洋詩の模倣を合言葉としたが,用語や発想は短歌を基礎としている。…
【ユーモア】より
…そこからhumourの意味はさらに変わって,そのような笑いをつくり出す〈おかしみ〉を表す。明治期の哲学者井上哲次郎はこの英語を日本語に訳すに当たって〈性癖〉(後に〈性向〉と改める),〈滑稽〉〈詼謔〉〈俳趣〉などという語を当てている。英語,英文学に詳しい坪内逍遥は最初〈ヒューモル〉,明治20年代ごろから〈ユーモア〉という,どこの言語にもない日本独特の発音をもつ単語を使い,一般にこの呼び方が定着して今日に及んでいる。…
※「井上哲次郎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新