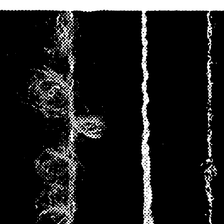精選版 日本国語大辞典 「毛糸」の意味・読み・例文・類語
け‐いと【毛糸】
- 〘 名詞 〙 羊毛その他の獣毛などを原料としてつむいだ糸。編物、毛織物などに用いる。《 季語・冬 》
- [初出の実例]「あねは、毛糸で、あみ物をして居ます」(出典:尋常小学読本(1887)〈文部省〉一)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「毛糸」の意味・わかりやすい解説
毛糸
けいと
メンヨウの毛を用いた糸のほか、ヤギ毛、ラクダ毛、アンゴラウサギ毛、ラマ毛、アルパカ毛、モヘア毛、牛毛などの繊獣毛を原料として紡織した糸の総称。これらを糸にしたときは、それぞれの原料名を付し、羊毛糸、ラクダ糸などとよばれる。また用途によって、織り糸、メリヤス糸、手編み糸、敷物用糸に大別される。毛糸は紡績する方法によって、大きく梳毛糸(そもうし)と紡毛糸とに分けられる。
[角山幸洋]
梳毛糸目次を見る
約1インチ(2.54センチメートル)以上の比較的長い、品質のよい羊毛糸を使った糸で、サージ、ポーラ、ギャバジンなどの服地に使われる原糸は、おもに梳毛糸であるが、メリヤス糸、手編み糸なども含まれる。梳毛紡績は、まず原毛を開俵して、品質により梳毛糸用を、(1)選別したのち、(2)原毛の脂分、糞尿(ふんにょう)など不純分をせっけんとアルカリで洗毛し、(3)梳毛機にかけて毛を引き伸ばして平行状態にそろえ、さらにコーマーで毛の配列を整える。これをトップといい、さらに紡績工程の(4)前紡(ぜんぼう)、(5)精紡を経て糸ができあがる。
[角山幸洋]
紡毛糸目次を見る
これは、比較的短い原毛、梳毛紡績工程で生じる不良の原毛、または毛織物や毛メリヤスのぼろから回収した再製毛などを混ぜ合わせて原料とし、紡績した糸である。繊維が平行状態にならず、糸の表面が毛羽立っている。そのため梳毛糸よりも糸に強力がなく、外観も見劣りがするが、縮絨(しゅくじゅう)性に富んでいるため、縮絨・起毛をして織物組織をみえないように仕上げる織物の原糸に適している。メルトン、フランネル、ラシャ、毛布など厚地のものはだいたい紡毛糸によっているとみてよい。工程は、原料準備、カーディング(繊維の方向をそろえる)、精紡の3工程にすぎない。紡毛糸の原料は再製羊毛が多いため、塵埃(じんあい)を取り除いたのち必要に応じて原毛染めを施し、(1)原料準備をし、(2)カーディングによって繊維が収束され、すぐ粗毛ができあがる。これを(3)精紡するために、多くはミュール精紡機を使い、糸を適当に引き伸ばして撚(よ)りをかけて、紡毛糸ができる。
毛糸は、染色法の違いにより、未染色のものを生地(きじ)糸、染色されている毛糸を色糸(染め糸)といい、紡績工程のどの段階で染色されるかによって区別され、原料の状態の毛を染色する毛染め(原毛染め)、染め上げた毛から毛糸にする中間製品のトップの状態で染色するトップ染め、糸の状態で染色する糸染めがある。
毛糸の太さを表すには恒重式をとり、それにはイギリス式とメートル式がある。イギリス式では、紡毛糸と梳毛糸では基準になる単位が異なっている。紡毛糸は重さ1ポンド(453.6グラム)で長さが256ヤード(約234メートル)の何倍あるかを示す数字が番手数である。梳毛糸では、重さ1ポンドで、長さ560ヤード(約512メートル)の何倍あるかを示す数字が番手数となる。メートル式では、梳毛糸と紡毛糸での違いはなく、重さ1キログラムで長さ1キロメートルあるものを1番手という。日本では、もとイギリス式を使っていたが、現在ではメートル式になっている。イギリス式とメートル式の換算法は次のとおり。
(梳毛糸)メートル式1番手
=イギリス式0.885番手
(紡毛糸)メートル式1番手
=イギリス式1.938番手
また普通、毛糸といえば、機械編み毛糸と手編み毛糸をおもにさすが、これらはとくに甘撚(あまよ)りで弾力のあることが必要で、用途に応じて並太(なみぶと)、中細、極細の3種類が使われ、特殊なものに超極太、極太、超極細がある。原料に手編み用として比較的太めのメリノ種、また雑種羊毛が使われ、合糸数も2~4本を撚合(ねんごう)する。一般には中細が使われるが、用途に応じて使いわけている。
[角山幸洋]
改訂新版 世界大百科事典 「毛糸」の意味・わかりやすい解説
毛糸 (けいと)
ヒツジ,ヤギ,ウサギ,ラクダなど,動物の毛を原料として紡いだ糸の総称で,羊毛糸,モヘア糸,アルパカ糸,カシミア糸,アンゴラ糸ほかがある。毛織物のための織糸,工業的に機械生産するための糸,手編み用の手編糸があり,ここでは通例にしたがって手編糸のことを毛糸と呼ぶ。紡績上の違いから繊維の長い梳毛(そもう)糸と,繊維の短い紡毛(ぼうもう)糸に分けられ,手編糸は一般に梳毛糸が用いられる。毛糸を太さで分類すると,極太毛糸,並太毛糸,中細毛糸,合細毛糸(以上は4本撚糸),極細毛糸,特細毛糸,超特細毛糸(以上は2本撚糸)に分けられる。毛糸の太さはメートル式の番手で表し,1kgにつき1kmあれば1番手,2kmあれば2番手と呼ぶ。並太毛糸は10番手の単糸4本を撚ったものである。毛糸は製造過程において撚りをかけるが,その撚りには右撚り(S撚り)と左撚り(Z撚り)があり,撚りの回数により,甘撚り(1mあたり300回以下),並撚り(300~1000回),強撚(1000回以上)に分けられる。このほか,糸を撚り合わせるときに,太さ,色合い,撚り,張力などを変化させ,特徴のある効果をもたせた意匠撚糸(ファンシー・ヤーン)がある。これには,ループ・ヤーン(まっすぐな糸に輪のある糸を撚り合わせる),ネップ・ヤーン(まっすぐな糸に不規則に節のある糸を撚り合わせる),ブークレ・ヤーン(細い芯糸に撚りの甘い太めの糸を縮れたように絡ませる),ノット・ヤーン(糸を撚るとき,一定の間隔で芯糸の回りに糸を固めて巻きつけ,節をつける),スラブ・ヤーン(繊維の束を一定の間隔で撚り込み,太さに変化をもたせる),モール・ヤーン(細い糸に短い糸をはさみ込む),クレープ・ヤーン(撚り合わせた糸を,さらに2本以上そろえて撚る),リボン・ヤーンなどがある。
執筆者:城川 美枝子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「毛糸」の意味・わかりやすい解説
毛糸
けいと
woolen yarn
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「毛糸」の意味・わかりやすい解説
毛糸【けいと】
→関連項目紡毛紡績|羊毛
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の毛糸の言及
【毛織物】より
…動物の体毛のうち空洞のないものをヘアhair,空洞のある柔らかいものをウールwoolと呼び,羊毛を主体とするウールを糸として織ったものをいう。毛糸には梳毛糸(そもうし)(長さが平均して5cm以上の良質羊毛から短い繊維を取り除き,平行にそろえてひきのばし,撚りをかけて表面をなめらかにしたもの)と紡毛糸(ぼうもうし)(短い羊毛や梳毛の工程ですき落とされたノイルと称する短いくず毛などを混ぜ合わせたもの)があり,それぞれ織られたものを梳毛織物(ウーステッドworsted),紡毛織物(ウールンwoolen)と呼ぶ。梳毛織物は表面がなめらかで光沢があり,組織がはっきりと見えて薄手のものが多い。…
※「毛糸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...