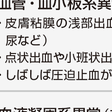内科学 第10版 「出血傾向」の解説
出血傾向(症候学)
生体においては,血管・血小板・血液凝固因子による止血機構と線溶および凝固線溶阻止因子がバランスを保っているが,その破綻により容易に出血したり,あるいはいったん出血すると止血しにくい状態のことを出血傾向という.血小板あるいは血管壁に問題のある場合は一次止血異常とよび,凝固系に問題のある場合は二次止血異常と称する.【⇨14-3-3),14-4】
成因・病態生理(表2-29-1)
1)一次止血異常:
血小板の異常による出血傾向として血小板減少症と血小板機能異常症がある.血小板減少症の病態はおもに,①骨髄での血小板産生の低下(造血不全,無効造血,腫瘍性病変),②クリアランスの亢進に分けられる.後者には血小板に対する自己抗体が出現する病態(特発性血小板減少性紫斑病(idiopathic thrombocytopenic purpura:ITP),SLEなど),または末梢微小血管での血栓形成による消費性の低下による病態(血栓性血小板減少性紫斑病(thrombotic thrombocytopenic purpura:TTP),溶血性尿毒症症候群(hemolytic uremic syndrome:HUS),播種性血管内凝固症候群(disseminatad intravascular coagulation:DIC),ヘパリン誘発性血小板減少症(heparin induced thrombocytopenia:HIT))があげられる.脾腫による血小板分布異常,大量出血や大量輸血に伴う血液希釈,さまざまな薬剤も血小板減少症の原因となる.また,まれではあるが先天性血小板減少症としてBernard-Soulier症候群,Wiskott-Aldrich症候群,Fanconi貧血などが知られる.血小板機能異常症は,薬剤による後天性が大部分であり,先天性血小板機能異常症である血小板無力症,Bernard-Soulier症候群,貯蔵プール欠乏症(storage pool deficiency),May-Hegglin異常はまれである.また,本態性血小板血症などの骨髄増殖性腫瘍でも血小板機能異常がみられることがある.
血小板自身の異常ではないが,一次止血異常を呈する疾患としてvon Willebrand因子(VWF)の量的・質的異常によるvon Willebrand病(VWD)がある.VWFは血管壁への初期の血小板粘着に重要な血漿蛋白であり,かつ血液凝固第Ⅷ因子のキャリアとしてその血中レベルの安定化に必要である.VWDでは一次止血異常に合わせて,血液凝固第Ⅷ因子が低下するために完全欠損型(type 3)では血友病に類似した二次止血異常も呈する.おもには常染色体優性遺伝を呈し,女性の先天性出血性疾患として最も頻度が高い.
血管壁が脆弱で皮膚や粘膜に出血傾向がみられることもある.先天性疾患としては,遺伝性出血性毛細血管拡張症(Osler病)やEhlers-Danlos症候群がある.後天性要因としては,Schönlein-Henoch紫斑病がある.これはおもに小児期に発症し,関節痛・消化管出血・腎症状(血尿と蛋白尿)が出現する.
2)二次止血異常:
先天性凝固因子欠乏としては血友病が最も頻度が高い.血友病A(第Ⅷ因子欠乏症),血友病B(第Ⅸ因子欠乏症)のいずれも伴性劣性遺伝性疾患でおもに男子に発症する.ほかの先天性凝固因子欠乏症はまれである.後天性に凝固因子に対する中和抗体が生じ,血友病に類似した病態をきたすことがある(後天性血友病).これは第Ⅷ因子に対する抗体が産生される病態がほとんどであり,ほかの凝固因子に対しての抗体が生じることはきわめてまれである.また,肝硬変による蛋白質合成障害,長期にわたる抗菌薬使用などによるビタミンKの不足(吸収阻害などによる)では凝固因子の産生が低下し,出血傾向を呈することがある.その他,DICでは血栓形成に伴い凝固因子が消費性に低下する.
3)線溶系異常:
プラスミノゲン活性化因子インヒビター-1欠損症やα2-プラスミンインヒビター欠損症が知られるが,きわめてまれである.後天性のものでは,血栓溶解療法でプラスミノゲン活性化因子を過剰投与された場合にみられる.急性前骨髄球性白血病(acute promyelocytic leukemia:APL)に伴うDICではAPL細胞上のアネキシンⅡ発現により細胞上の線溶活性が上昇することで出血傾向を呈する.
鑑別診断(表2-29-2)
抗血小板薬や抗凝固薬の内服の有無を確認し,出血傾向の発症時期,家族内発症,血族結婚の有無について問診することが,先天性か後天性かの判断に役立つ.診察では出血傾向が局所性か全身性か,皮膚粘膜の浅部出血か関節・筋肉などの深部出血かを確認する.鼻出血だけの場合は,多くは局所的に血管が脆弱なためである(鼻中隔のKiesselbach部位).紫斑は,大きさから点状出血と斑状出血(溢血斑)に分けられる.また,紫斑は紅斑と異なり,圧迫により退色しない.血管炎をベースにした紫斑は,丘疹状に触れる.一次止血異常の場合は,皮膚の点状出血,小斑状出血がみられ,その他,鼻出血・消化管出血・過多月経・血尿などの粘膜出血がみられる.二次止血異常の場合は,皮下・筋肉内・関節腔内・頭蓋内の深部出血が特徴的であり,大斑状出血をきたす.線溶系異常で起こる出血では,いったんは止血するものの,数時間後に再出血がみられる(後出血).老人性紫斑(手背や前腕の赤黒い紫斑)や単純性紫斑(若い女性に多く,四肢に出現する)は,血管が脆弱なために生ずるものであるが,特に検査で異常を認めず,病的意義はない.
出血傾向のスクリーニング検査としては,血算,プロトロンビン時間(PT),活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT),フィブリノゲン,FDP(またはD-ダイマー)の測定を行う.血算測定では採血管に含まれる抗凝固薬エチレンジアミン四酢酸(EDTA)が原因で血小板が凝集塊を形成し,血小板数が低く測定される場合があるが,病的意義はない(偽血小板減少症).また,採血に手間取ると血液凝固に伴い見かけ上の血小板減少やPT,APTTの異常値が生じるので,再現性のない異常値は採血手技を確認する.血小板減少症にほかの血球系異常が合併すれば,特に造血不全,造血器悪性腫瘍を除外する.一般に血小板数が5万/μL以下では外傷時などに易出血性が認められる.また,1~2万/μL以下で脳出血などの危機的出血のリスクが高くなる.ただし,疾患の種類により程度に差がある.たとえば,再生不良性貧血やITPでは,同程度の血小板減少のある急性白血病(抗癌薬などで組織の障害を受けている)に比べて出血傾向が軽度である.また血小板減少症に破砕赤血球を伴う溶血性貧血を合併する場合にはTTPやHUSなどの血栓性微小血管障害症を鑑別し,血小板減少症にFDPやD-ダイマー,PT,APTTの異常を伴う場合にはDICの存在を考慮する.PT,APTTはそれぞれ外因系・内因系凝固反応の評価のための検査である.PT,APTT異常の組み合わせにより測定する凝固因子活性を選択する.たとえば,APTTのみ異常であれば,内因系の異常を考え,血液凝固第Ⅷ因子,Ⅸ因子,Ⅺ因子,Ⅻ因子を測定する.[小澤敬也]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
家庭医学館 「出血傾向」の解説
しゅっけつけいこう【出血傾向 (Hemorrhagic Diathesis)】
どこかにからだを強くぶつけたなど、思いあたる原因もないのに出血がおこり、いったん出血すると止まりにくい状態を、出血傾向(しゅっけつけいこう)(出血性素因(しゅっけつせいそいん))があるといいます。
その原因は、血管の壁に異常があるか、血小板(けっしょうばん)に異常があるか、血液凝固(けつえきぎょうこ)のしくみに異常があるか、の3つに分けることができます。
血管壁の異常としては、血管性紫斑病(けっかんせいしはんびょう)に代表されるように、さまざまな原因で、血管壁から血液がもれ出す(透過性亢進(とうかせいこうしん))ようになります。単純性紫斑病(たんじゅんせいしはんびょう)や老人性紫斑病(ろうじんせいしはんびょう)、アレルギー性紫斑病(せいしはんびょう)のほかに、クッシング症候群(「クッシング症候群」)、ビタミンC欠乏症(「その他の水溶性ビタミンと代謝異常」のビタミンC欠乏症(壊血病))などによっておこってきます。
血小板の異常として、血小板の数が減少するために出血傾向になるものがあります。血小板は血液が固まるときの材料ですから、いわば材料不足によって、出血傾向がおこるわけです。原因とするおもなものに、血小板減少症(けっしょうばんげんしょうしょう)、急性白血病(きゅうせいはっけつびょう)(「急性白血病」)、再生不良性貧血(さいせいふりょうせいひんけつ)(「再生不良性貧血」)などがあります。
そのほかに、血小板のはたらきに異常をおこし、出血傾向になるものもあります。尿毒症(にょうどくしょう)(「尿毒症」)、播種性血管内凝固症候群(はしゅせいけっかんないぎょうこしょうこうぐん)(「播種性血管内凝固症候群(DIC)」)、また抗生物質や非ステロイド抗炎症薬などの副作用によってもおこることがあります。
とくに、アスピリンを使用すると、血小板がくっつき合って固まろうとする能力を低下させてしまいますが、逆に、血液が固まりにくくなる作用を利用して、血栓(けっせん)の予防に使われることもあります。
血液凝固のしくみの異常によっておこる出血傾向の代表的なものに、血漿(けっしょう)中に含まれているべき血液凝固因子(けつえきぎょうこいんし)が先天的に欠けている血友病(けつゆうびょう)(「血友病(ヘモフィリア)」)やフォン・ウィレブランド病(「フォン・ウィレブランド病」)があります。
また、血液凝固のしくみに、後天的に異常がおこることもあります。それは、血液凝固因子をつくっている肝臓の疾患や、血液凝固因子の産生に必要なビタミンK欠乏症(「ビタミンK欠乏症」)によっておこります。
◎一度は専門医の検査を
しかし、こうした病気はめずらしいものです。あざ(紫斑(しはん))ができやすい、鼻血が出やすい、歯肉(しにく)から出血しやすい、なかなか血が止まらない、などと訴える人を検査してみると、たいていは正常であることが多いものです。
したがって出血しやすいからといって、そう心配する必要はありませんが、一度は血液専門医を受診して検査を受けておくこともたいせつです。
たとえ軽症でも、出血傾向がある人は、大きな手術をしたり、交通事故などにあうと止血がむずかしく、出血量が多くなって危険です。
しかし、あらかじめ出血傾向があるとわかっていれば、いざというとき、医師が十分な対策を立てることができ、大出血の危険を避けることができるのです。
世界大百科事典(旧版)内の出血傾向の言及
【肝不全】より
…後者は,進行した肝硬変や肝臓癌,肝臓内に長期間持続して胆汁が鬱滞(うつたい)することなどによって生じ,高度の肝臓萎縮と繊維化,およびその結果生じる肝血流障害,腫瘍性変化などが直接の原因となる。ともに症状として,全身消耗,皮膚や性器の異常,感染に対する抵抗力の低下,循環障害などを伴うが,黄疸の増強,腹水,出血傾向,肝性脳症と,高度の栄養障害が臨床的には重大な問題となる。
[肝臓の機能低下による種々の症状]
(1)黄疸 黄色色素のビリルビンが体内に蓄積して皮膚などを黄色に染める現象を黄疸という。…
【血液】より
…まれな遺伝性疾患として,顆粒球の機能が異常で,殺菌力が欠如しているため身体各所に感染症をきたす疾患もある。(3)止血作用の異常 正常人ではなにもおこらないくらいの外力ですぐ出血し,出血しはじめるとなかなかとまらない状態を出血傾向という。止血は血管,血小板,凝固因子の3者の協同作用で完全となり,このどれが異常でも出血傾向になる。…
【血液凝固】より
…すなわち,凝固する。この血液が凝固する性質は,止血にとって必要な性質であり,血液凝固が正常に起きないと,止血が円滑に行われなくなり,出血傾向を呈するようになる。 先天的あるいは後天的に血液凝固機序が異常を呈するために,出血傾向が生ずる場合が多数存在する。…
【出血】より
…その間,繊維素溶解酵素によって止血栓が崩壊しないように,繊維素溶解に対する阻止因子が働く。
[出血傾向]
これら止血機序になにか異常があると,止血機序が円滑に作動しないため,止血が遅れ,また出血しやすくなる。これを出血傾向という。…
※「出血傾向」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新