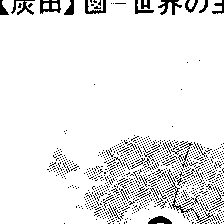翻訳|coal field
精選版 日本国語大辞典 「炭田」の意味・読み・例文・類語
たん‐でん【炭田】
- 〘 名詞 〙 地下に炭層が豊富に存在していて、採掘に値する石炭が埋蔵されている地域。
- [初出の実例]「説明書は重要なる鉱山炭田油井等には一々鮮明なる彩色地質図挿みて説明したる者なり」(出典:風俗画報‐二三九号(1901)広告)
改訂新版 世界大百科事典 「炭田」の意味・わかりやすい解説
炭田 (たんでん)
coal field
一般に採掘可能な炭層を含む夾炭(きようたん)層が連続性をもって分布し,地理的に広い面積を占める地域をいう。それらの地域を地質学的にみると多くは盆状構造をなし,その構造を示す大炭田を炭田盆地ということがある。日本では,炭田の小規模なものや炭層は存在するがその分布や性状が未詳で稼行対象としては価値の少ない地域を含炭地と呼んでいる。
種類と規模
炭田はその生成条件や地殻変動の影響などによって大小さまざまのものがあり,分類についても見方の相違によっていろいろに分けることができる。炭田が形成された場所によって,海岸に近い堆積盆地に形成された〈沿岸炭田〉と,大陸の奥地などで形成された〈内陸炭田〉とに分けられる。
沿岸炭田は海成層と炭層が互層をなしており,夾炭層はしだいに海成層に移り変わる。内陸炭田は沼沢地に形成された炭田が多く,淡水貝や植物化石を多く含む。世界の炭田のうちで沿岸炭田の性質を示すものは,ドイツのルールからイギリスにかけての地域にある古生代の諸炭田をはじめ,古生代以後の炭田に多い。日本では石狩,釧路,筑豊などほとんどすべての炭田が該当する。
内陸炭田としては,ドイツのザール,フランス中部の古生代の炭田,インド,オーストラリアを含む古生代のゴンドワナ大陸中に形成された炭田,アメリカの東部炭田,アジア地域のジュラ紀の諸炭田がある。また炭層形成環境によって,炭層を形成する原植物が繁茂していた場所に堆積した〈原地堆積〉と,遠くから運ばれてきて堆積した〈流移堆積〉とに分けられる。このような分類の,炭層の研究に基づく根拠として,原地堆積では炭層の下盤に下盤粘土と呼ばれるものを伴う場合があり,これは風化土壌が岩石化したもので樹林繁茂時の土壌を示すと考えられていること,この中に根をはって直立する樹幹の化石が発見されることがある,などがあげられ,流移堆積では炭層の上下盤または炭層中に海生あるいは汽水生の貝化石が出ること,下盤粘土と同質のものが炭層直下以外の層準にもみられること,炭層の下盤は粘土とは限らず粗い砂岩やレキ岩の場合もあり,森林土壌が存在したとは考えにくい場合があること,などがあげられる。しかし個々の炭田についてこの両者を明確に区別することは困難な場合が多い。また膨大な植物遺体が広域にわたって長期間連続して運搬堆積を必要とする流移堆積は,特殊な堆積環境下で局部的に生成されるもので,ほとんどすべての炭田は原地堆積によると考えられる。
次に現在みられる賦存状態から分類すると,地表に露頭が現れている〈露出炭田〉と,露頭がなく試錐によってのみ炭層の確認される〈伏在炭田〉とがある。一般に古くから開発された炭田は,露頭で炭層が確認されたのちに地表探査,試錐探査により炭田の規模が確認される。純然たる伏在炭田は重力探査,弾性波探査などの物理探査が開発され,それらによる炭層存在の予知後に試錐によって確認されるのが普通である。地質構造からみると,褶曲(しゆうきよく)がほとんどなく断層を主体とした〈地塊炭田〉と,褶曲を主体とした〈褶曲炭田〉とに分けられる。地塊炭田は一般に傾斜が緩く断層は正断層が主で,地層のじょう(擾)乱を受けることが少ない。褶曲炭田は傾斜が走向方向にも傾斜方向にも変化しやすく,急傾斜の場合が少なくない。また背斜,向斜構造に加えて正,逆,衝上断層を随伴し,地層のじょう乱が多い。
炭田の広さや夾炭層の厚さ,炭層の厚さ,枚数等については,それらの規模の大小によって開発の規模,方法が異なるため,稼行当事者は最も深い関心を寄せている。アメリカ,ヨーロッパなどの古生代の大炭田は数万km2以上の広さをもち,夾炭層の厚さも数千mある。これに比べ日本における第三紀の炭田では,夾炭層の分布面積が最も広いといわれる釧路炭田でも3000m2,石狩炭田は,2000m2である。
炭田の形成
炭田が形成される条件のうち重要な要素は,炭層堆積場所,炭層を形成する植物質の堆積状態,堆積盆地の上昇沈降等の地殻運動,炭層上位の堆積層の性質等である。炭田ができる場所としては,植物の繁茂に適したほとんど平たんな堆積盆地が水位すれすれの状態の沼沢地であること,地盤の沈降と堆積の速度がつり合ってその状態が継続されること,堆積後陸化して大気にさらされることがないこと,などが考えられる。このような条件が長年月を経て繰り返されて数枚の炭層ができ,周期性のある地層,炭層の重なりが往々にして観察される。まず粗いものがたまり,次いで細かいものに変わる。下位から上位に向かって砂岩→砂質ケツ岩→ケツ岩→石炭→ケツ岩の順に地層が重なり,この順序が繰り返されている場合がある。最下部の砂岩がレキ岩やレキ質砂岩であったり,砂質ケツ岩が欠如したり,ケツ岩中に砂岩が夾在したり,炭層直上のケツ岩が欠如するなど多少の変化はしても,下位から上位にかけて粗粒から細粒に移って炭層に至る傾向は変わらない。このような一定の傾向をもった一組の地層の成立ちを堆積輪回といい,これを互いに比較することによって炭層の対比などが行える。堆積後の炭化作用は,上位の堆積層の厚さと質,地質構造の影響,火成岩貫入の状況などによって異なってくる。ロシアの古生代のモスクワ炭田は褐炭田で,時代が古いのにもかかわらず炭化が進んでいない例であり,一方,新第三紀の日本の炭田は激しい地殻変動を受けて炭化作用が進み,歴青炭を産し,さらに大嶺炭田や天草炭田では火成岩の逬入(へいにゆう)による熱変成を受けて無煙炭を産する。
炭田の地質的・地理的分布
地球は45.5億年前にできたといわれているが,陸上植物が現れはじめたのは古生代シルル紀の後半からで,その数が急激に増え,森林を形成するようになったのはデボン紀に入ってからである。しかしこれらの植物が厚い石炭層となるために好都合な環境ができた時代は限られ,世界的にみると古生代の石炭紀,二畳紀,中生代の三畳紀,ジュラ紀および白亜紀の一時期,新生代の古第三紀がその主要時期であった。古生代末期の石炭紀から二畳紀にかけては温暖多雨の気候が続いてシダ植物が繁茂し,陸地には沼沢地が多く,その盆地に堆積した植物質堆積層が今日みられる主要大炭田となっている。中生代の炭田は古生代に比べて大規模なものは少ない。新生代第三紀の炭田は世界中ほとんどすべての国にあるが,堆積盆地が分化しているためその規模は比較的小さい。炭田の地理的分布をみると,北は北緯85°から始まり,赤道直下,南半球そして南極大陸にも分布している。1995年の世界エネルギー会議(WEC)に炭量を提出したのは73ヵ国+旧ソ連の7ヵ国(ロシア,ウクライナ,グルジア,キルギス,カザフスタン,タジキスタン,ウズベキスタン)である(図)。
炭田の探査・開発
炭田を発見し,それを開発するためにいろいろな方法が試みられているが,最近では探査技術の進歩により組織的な調査法がとられている。まず炭層の露頭や夾炭層が分布していると考えられる地域の地質概査を行い,炭層の走向,傾斜,地質構造などを求め地質図を作る。次いで重力探査,弾性波探査などの物理探査と要所に試錐を行い,それらの結果から炭層等深線図,炭層等厚線図などの図面を作る。試錐コアは炭層の厚さ,炭質などの測定,古生物学的・物理化学的方法で研究される。海底炭田の場合は海岸陸上部の地質調査後,ドレッジャーで海底岩石を採取して海底地質図を作り,次いで海上から物理探査を行ったのちに海上試錐を実施する。従来は深い海での試錐はなかなか困難であったが,近年は石油試錐技術の進歩により,それを利用して実施できるようになった。以上のような手順を経て地表,地下の地質状況,炭層状況を十分に把握したのち開発計画を作り,所要の手続を経て開発に着手する。
なお,炭田における石炭埋蔵量については国によって計算基準や範囲が異なるため,いろいろな数値が公表され,それらの数値も相当の開きのある場合がある。とくに実収炭量は技術の進歩,市場動向によって変動する。
→石炭
執筆者:大橋 脩作
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「炭田」の意味・わかりやすい解説
炭田
たんでん
coal field
現代の採掘技術のレベルで採算があって採掘のできる炭量が豊富に埋蔵されている区域を炭田という。石炭は、樹木の遺骸(いがい)が、ある地区に堆積(たいせき)し土砂をかぶって埋没したあと、長年月の間に土砂・岩石等の圧力および地熱、造山運動等の地質的擾乱(じょうらん)の際に生ずる熱作用を受けて、できたものである。このことを「石炭化作用」という。そして「石炭化」の程度によって「褐炭」「亜瀝青(あれきせい)炭」「瀝青炭」および「無煙炭」と変化していく。1998年世界エネルギー会議で推測された、全世界の瀝青炭・無煙炭と亜瀝青炭・褐炭の埋蔵量および技術力と経済性を考慮した採掘可能量によると、全世界では約7兆トンの埋蔵量はあるが、その14%の約9800億トンが採掘できることがわかっている。
炭田の埋蔵量の計算方法は次のようにして行う。すなわち、現採掘区域に隣接し、炭層内の二面で囲んだ範囲内に石炭の存在が確認されている部内の炭量、露頭(炭層が地表に露出している部分をいい、地表で炭層を探査するには最良の決め手となる)・坑道・ボーリング等で炭層の存在が認められていて、かつ採掘が計画されている区域の炭量、さらにこれに加えて、炭層確認度は上記のとおりで、将来採掘を予定している区域に存在する炭量等を合算して「確定炭量」という。次に、現採掘深度内にあり、地質条件等からみて炭層の存在が考えられる部内の炭量に、将来の採掘深度内でも同じ地質条件下にある部分の炭量等を合算して「推定炭量」という。これに対して、地質構造およびボーリング・物理探査等の結果を総合して、炭層があると判定でき、将来採掘が予定できる区域での炭量を「予想炭量」という。なお、予想炭量として算入できるには、日本では炭層の厚さが1メートル以上、炭層の深さは地表から1200メートル以内のものに限っている。以上、確定、推定および予想の三つの炭量の合計が「理論可採埋蔵炭量」であるが、理論可採埋蔵炭量といえども、全量は採掘できるとは限らない。地表条件、地質構造等で採掘不能の部分がある。この炭量を除き、採掘可能と考えられる量を「安全炭量」という。しかし、安全炭量も実際に採掘してみると、坑内条件、保安上の理由等々で、採掘されずに取り残されてしまう炭量が生ずるため、実質上の生産量は安全炭量より少なく、これを「実収炭量」といっている。また一方では、経済的見地から、採算性の考えられる炭量を「経済炭量」ともいい、実収炭量よりさらに少ない量を計算することもある。
以上のように、世界の理論可採埋蔵炭量は莫大(ばくだい)な量ではあるが、うちロシア、アメリカが世界全体の約80%を占めている。なかでも、ロシアは約4兆トンの理論埋蔵量があるといわれている。
[磯部俊郎]
世界のおもな炭田目次を見る
世界の主要炭田についてはIEA(国際エネルギー機関)の資料がもっとも信頼できる。炭田の分類等は国により多少異なるが、無煙炭から褐炭まで含めて、多量な石炭を有する国々はロシア、アメリカ、中国、オーストラリア、ポーランド、南アフリカ共和国、ドイツ、インド、イギリスなどである。
[磯部俊郎]
日本の炭田目次を見る
1998年世界エネルギー会議資料によれば、わが国の理論可採埋蔵炭量は82億7700万トン、うち7億8500万トンが採掘可能と算出されている。石炭は全国的に分布はしているが、炭田といいうるものは、北海道では、中央部の石狩(いしかり)、東部の釧路(くしろ)、最北端の稚内(わっかない)地方にある天北(てんぽく)の3炭田、本州では、福島・茨城県にまたがる常磐(じょうばん)、山口県宇部(うべ)地方の瀬戸内海海底の宇部、同県中央部の大嶺(おおみね)炭田があげられ、九州では、福岡県北部の筑豊(ちくほう)、宗像(むなかた)、福岡の3炭田、同県南部には佐賀県にも及んでいる三池(みいけ)炭田がある。長崎・佐賀両県にまたがる唐津(からつ)、佐世保(させぼ)炭田および長崎県の五島(ごとう)列島と西彼杵(にしそのぎ)半島間の海底にある崎戸(さきと)松島および高島炭田が有名である。両海底炭田は一つのもので、良質原料炭が埋蔵されているわが国最大の海底炭田と考えられ、「西彼杵炭田」ともいわれている。
しかし炭量枯渇や炭質劣化により、また良質炭を産出したところでも安価な海外からの輸入炭に押され鉱山の閉山が相次ぎ、2002年(平成14)の太平洋炭礦(釧路)閉山を最後に大手炭鉱はすべて姿を消した。今後日本は産炭国ではなくなる可能性が大きいが、炭田は保有していると考えてよい。ただし経済炭量はゼロということになる。
[磯部俊郎]
百科事典マイペディア 「炭田」の意味・わかりやすい解説
炭田【たんでん】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の炭田の言及
【炭鉱】より
…石炭または亜炭の採掘を行っている所をいう。これに対し,実際に採炭されていなくても採掘可能な炭層を含む夾炭(きようたん)層が連続性をもって分布し,地理的に広い面積を占める地域は炭田という。 炭鉱で石炭を採掘するうえには次のようないろいろの問題点がある。…
※「炭田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...