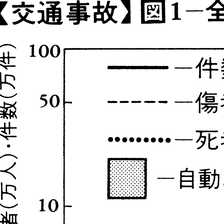精選版 日本国語大辞典 「交通事故」の意味・読み・例文・類語
こうつう‐じこカウツウ‥【交通事故】
改訂新版 世界大百科事典 「交通事故」の意味・わかりやすい解説
交通事故 (こうつうじこ)
広義にはすべての交通に伴う人的・物的損害または往来の危険の発生をいうが,ここでは狭義の交通事故,すなわち道路交通事故についてのべる(他については〈鉄道事故〉〈海難〉〈航空事故〉の項を参照)。
道路交通事故は自動車・原動機付自転車,軽車両もしくはトロリーバスまたは路面電車(以下〈車両等〉という)の交通による人の死傷または物の損壊をさす(道路交通法72条1項)。すなわち車両等の交通により惹起されたものであることを要し,歩行者相互あるいは道路で遊戯中の幼児の転倒によるものなどは含まない。またこの場合,交通とは道路上におけるものをいい,道路以外の場所におけるものを含まない。なお,厚生省統計でいう自動車事故死亡数には,道路上における自動車事故のほか,道路外(ガレージ等)における自動車事故による死亡も計上しているので,警察庁統計による年間死者数を約3割上回っている。
自動車による死亡事故は,1896年イギリスで死者2人を出したのが世界最初といわれている。《警視庁史》に,1907年国産として初の自動車16台が製造され,このうち大倉喜七郎所有の車を工員4人がもち出し,東海道平塚付近で電柱に衝突,4人とも即死したという記録があり,これが日本で最も古い自動車による死亡事故とされている。自動車の普及とともに交通事故も漸増したが,件数は少なく,第2次世界大戦終戦のころまでは死者年間3000人前後の状態が続いていた。交通事故が社会問題として注目されはじめたのは55年ころからで,モータリゼーションの爆発的な進行によって自動車事故は急増し,その後15年を経た70年には,事故件数は8倍にも伸び,死傷者100万人(全人口の1%)に達しようとした。これは日清戦争での日本軍の戦死傷者1万7000人をはるかに上回るもので,交通遺児を残す死亡事故,後遺症を残す頭部外傷事故などの悲惨さとともに〈交通戦争〉と呼ぶにふさわしい状態となった。このため交通事故対策は国家的な重要課題となり,70年交通安全対策基本法の制定により本格的な事故防止施策,活動が開始され,国民の交通安全思想も急速に高まっていった。この結果,翌71年から交通事故は減少に転じ,5年後の75年には事故件数,死者数,負傷者数とも35%前後減少して10~15年前の水準にもどった。しかし,70年代後半から減少率は小さくなり,ついに78年には負傷者が,80年には死者が,それぞれ対前年比増加に転じた。年間の死傷者数は60万人を超え,各種の事故死のうちでは圧倒的に多く,第1位を占めている。また,高速道路の整備の進展によるハイウェー時代の到来,バイコロジー運動などによって自転車交通も増えつつある新しい局面のなかで,交通事故は依然として重要な課題のまま残されている。
執筆者:原田 達夫+斉藤 親
刑罰,行政処分等
車両等の交通によって事故(人の死傷または物の損壊)が発生したとき(事故発生についての過失の有無を問わない)は,その車両等の運転者等の乗務員は,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する措置をとらなければならない(道路交通法72条1項前段)。また,運転者は,現場の警察官,または現場に警察官がいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所または駐在所を含む)に,事故発生の日時および場所,死傷者の数および負傷の程度ならびに損壊した物とその程度,事故について講じた措置等を報告しなければならない(72条1項後段)。前者の救護義務に反した者は,3年以下の懲役または20万円以下の罰金(117条),あるいは1年以下の懲役または10万円以下の罰金(117条の3-1号)に処せられ,後者の報告義務に違反した者は,3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金(119条1項10号)に処せられる。
車両等の運転者が,その過失により,事故を発生させたときは,交通違反(道路交通法違反)となるが,人の死傷という結果を生じさせた場合,業務上過失致死傷罪が成立し,5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる(刑法211条前段)。この場合,車両等を反復継続して運転すること自体が〈業務〉と解され,必ずしも営業で車両等を運転する場合に限られない。なお,まれには重過失致死傷罪(211条後段)で処断されることもある。事故が発生した場合,ややもすると,直ちに過失責任を肯定することになりやすく,処罰を適正な範囲に限定することが必要となる。この過失責任限定の論理として,〈信頼の原則〉が最高裁判所の判例によって認められている。
人身事故発生の場合,警察は,業務上過失致死傷罪の成否等に関し,実況見分,取調べ等の捜査を行い,その後事件を検察官へ送致する。近年,業務上過失致死傷事件として検察官に送致される件数は若干増加している。検察官は,過失の有無・程度,被害の大小など諸般の事情を考慮して,起訴するか否かを決定するが,交通関係の業務上過失致死傷事件(重過失致死傷事件を含む。以下同じ)では,1987年以来,起訴率は減少し,現在ではその著しい低下が見られる(1986年では72.8%であったが,1996年では14.4%になっている)。起訴される事件のうち,比較的軽微で,罰金刑が相当と考えられるものについては,検察官は,正式の公判手続によらず,略式命令の請求を行う(略式手続。刑事訴訟法461条以下)。1996年,交通関係の業務上過失致死傷事件として起訴された9万2007件のうち,正式の公判請求は4862件(5.3%)にすぎず,略式命令請求が8万7145件(94.7%)と大多数を占めている。起訴された者のうち,略式手続によらず,正式の公判手続を経て有罪判決を受けた者は,1996年は,4600人であるが,懲役・禁錮に処せられた者(4587人,99.7%)も,その83.6%はその執行が猶予されている(同年の一般事件の執行猶予率61.1%に比して高くなっていることが注目される)。このように,交通関係の業務上過失致死傷事件のうち,実刑に処せられるのは,かなり少数になっているのが実態である。実刑を受け,刑事施設に収容された者は,他の一般の受刑者とは異なった側面もあり,これらの者を対象として,一定の基準により,特定施設における開放的処遇が実施されている(禁錮受刑者に対しては1961年から,懲役受刑者に対しては,その増加に伴い,76年から実施)。そこでは,交通安全教育を含めた,生活指導,職業訓練等にわたる処遇が活発に行われている。
なお,車両等の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に一定の点数(いわゆるポイント)をつけ,その合計点数によって,都道府県公安委員会による運転免許の停止(6月以内)ないし取消し(欠格1年から3年)が行政上の処分として科される。また,交通事故をおこした交通違反者に対しては,多くの場合,運転免許の停止,取消しが科される。
交通事故に対する対策としては,以上のような法システムによる制裁が事後的措置として重要であるが,事前の予防的措置として,道路交通環境の整備や交通安全教育の意義も大きい。
→交通違反
執筆者:山口 厚
自動車事故をめぐる民事法上の問題
交通機関の運行によって生じる事故のうち,事故件数の多さなどから事故損害の合理的規制が最も強く要請されているのが自動車事故である。そのため日本でも,とくに自動車による人身事故被害者の損害賠償請求権を確保するため自動車損害賠償保障法(自賠法と略称)が制定され(1955),今日では,自動車事故による損害賠償の多くが同法によって処理されている(もっとも,近時,賠償価額が増大し自賠法による保障では賄われえず,任意に保険をかけることが必然的である)。たとえば,ある会社の従業員が社用のため会社所有の車を運転中に事故をおこした場合,一般法である民法によれば,被害者は運転者または使用者に対し損害賠償を請求するためには,運転者の過失を証明しなければならない(民法709,715条)。しかし,自賠法3条は,自動車事故の責任主体として新たに運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者)という概念を創設し,この者が,自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことなどを証明しないかぎり責任を負わされることとなった。このように自賠法3条は,立証責任の転換を通じて運行供用者に事実上無過失責任を負わせようとするものであり,危険責任の意図を実現したものとされている。
運行供用者であるか否かを判断するにあたって通常用いられているのが,自動車に対する運行支配と運行利益という二つの基準である。このうち,前者については,最近では,運行自体に関する直接的支配というよりも人的・物的両側面において事実上自動車の運行を支配・管理しうる地位ないし支配・管理すべき地位(管理責任)が着目されるようになってきた。これによると,上記例で従業員が勤務時間外に私用運転中(無断運転)におこした事故につき会社は通常,運行供用者責任を免れえないことになるし,判例でも一般に,自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者(保有者)が免責される場合は限られている。
損害の類型
被害者の死傷による損害としては,財産的損害(治療費,交通費などの積極的損害と逸失利益のような消極的損害)と精神的損害(慰謝料)がある。傷害の場合には,被害者自身のほかに近親者など現実に治療費を負担した者も賠償を求めることができる。他方,死亡の場合には,日本では,死者の逸失利益のみならず慰謝料請求権までも相続されるという比較法的にもまれな処理が行われている。したがって幼児が死亡した場合にも,将来の稼働能力の逸失利益も算定の基礎に加えられ,それを両親が相続することになる。このような相続的構成には,損害額の算定が困難になるという問題があるほかに,死亡事故については,死者に生じた損害ではなく遺族扶養を中心に損害賠償のあり方を再検討すべきであるとの考え方が有力に主張されている。とくに,生命侵害に対する慰謝料については,民法711条がすでに一定の近親者(両親,配偶者および子)に遺族固有の慰謝料請求権を認めているので,死者本人に生じた慰謝料請求権を相続により取得するという考え方に対しては,最高裁判例があるとはいうものの,なお検討すべき余地が残されているといえよう。
諸外国の補償システム
ところで過失責任主義(民法709条)は,19世紀に頂点に達した自由主義的世界観に由来する。自賠法は,それに代わるものとして提唱された社会国家的法思想に基づく無過失責任ないし危険責任を特別法によって実現しようとする大陸法系の流れをくむものである。しかし,自動車事故による損害補償は,比較法的には,1960年代に主としてアメリカ(キートン=オコンネル案),フランス(タンク案),西ドイツ(ヒッペル案)などで主張された民事責任そのものの枠をとりはずす補償システムの構想によって,まったく新しい局面を迎えることとなった。このシステムでは次の諸点が改革の目標とされている。すなわち,第1に交通事故による被害者にできるだけ包括的な保護を与えること,第2に公平な負担分配を図ること,第3に事故予防に対して十分な配慮を講じること,第4に管理費用の減少である。
新しい理念に基づく補償システムを実現する方法には基本的に二つの考え方がある。第1は,交通事故のような特別の事故類型に限定したシステム(交通災害保険)である。これは,基本的には,加害者の民事責任を排斥し,自動車による運行利益を享受する者などの集団にあらかじめ被害者の補償費用を負担させるものである。スウェーデンの交通事故補償法(交通損害保険。1975制定)は多くの点で災害保険と同様の機能を果たすものとして注目されているが,1970年代に,アメリカの各州で立法化されたノーフォルト(無過失責任)保険は,無過失責任原則の部分的採用というほかに,被害者が自分の加入する保険会社から直接に保険金の支払を受けるという特色をもっている(なお,フランスでは,1985年に,責任要件の立証や加害者の免責の問題について,交通事故被害者の地位をいちじるしく改善する特別法が制定されたことも興味深い)。第2の方法は,交通事故による被害者を一般的に社会保障のなかで保護することである。この構想は,ニュージーランドの事故補償法(1972)で実現されることとなった。ニュージーランドの改革は,交通事故にかぎらずおよそ人身事故による被害者にすべて補償を与えようとするものであるが,これにより,民事責任はそのかぎりで完全にかつての役割を終えることとなった。民事責任に対する鎮魂歌ともいうべきニュージーランドの試みは,19世紀以来の事故法の発展にとって画期的なできごととして世界的に注目を集めている。しかし,このシステムにも運営費用の面で問題のあることが指摘されていることからもうかがえるように,社会保障的解決の前途にはなお楽観は許されないといえる(ニュージーランド法も1982年に大改正され,92年にも原資の徴収を若干多元化する改正があった)。ちなみに,日本でも損害賠償から社会保障への転換を試みる〈総合救済システム〉というニュージーランド型の提案があるが,焦眉の課題となっているわけではない。
執筆者:藤岡 康宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「交通事故」の意味・わかりやすい解説
交通事故
こうつうじこ
交通手段(自動車、鉄道、船舶、航空機など)の運転・操縦においていろいろな要因により異常をきたし、人命の死傷、物の損害を引きおこす事態をいう。交通事故は、交通手段別に道路交通事故(自動車事故)、鉄軌道交通事故(鉄道事故)、海上交通事故(海難)、航空交通事故(航空事故)に大別される。日本における交通事故による死傷者統計を、種類ごとに年代を追って比較してみる。道路交通事故65万3582人(1984)、105万9403人(1999)、91万5029人(2009)、58万4544人(2017)。鉄軌道交通事故1538人(1984)、689人(1999)、683人(2009)、561人(2017)。海上交通事故(死者・行方不明者)252人(1984)、146人(1999)、142人(2009)、54人(2017)。航空交通事故(民間機のみ)46人(1984)、26人(1999)、9人(2009)、28人(2017)。これらの推移から、数は減っているものの依然として道路交通事故による死傷者が多いといえる。道路交通事故の増加は、高度経済成長期における急激なモータリゼーションの発達と自動車台数の増加、自動車価格の低下と所得水準の上昇による所有率増加などによるところが大きい。
1970年代以降、交通手段の大型化、多機能化、高速化が進んだことから、いったん事故が発生すると一挙に大量の人命や財貨を奪う大型事故となる可能性が高い。交通手段の技術的発展が人間社会に恩恵を与える反面、交通事故が国民生活の根底を脅かすという矛盾を生み、現代の「社会不安」の一つとなっている。また、これらの事故を未然に防止する交通安全対策が運輸・交通行政の重要な課題の一つとなっている。
[松尾光芳・藤井秀登]
『F・H・ホーキンズ著、石川好美監訳『ヒューマン・ファクター 航空の分野を中心として』(1992・成山堂書店)』▽『D・ゲロー著、清水保俊訳『航空事故』増改訂版(1997・イカロス出版)』▽『安部誠治監修、鉄道安全推進会議編『鉄道事故の再発防止を求めて』(1998・日本経済評論社)』▽『山之内秀一郎著『なぜ起こる鉄道事故』(2000・東京新聞出版局)』▽『青木勝治著『交通事故とPTSD』(2000・文芸社/朝日文庫)』▽『交通法科学研究会編『科学的交通事故調査』(2001・日本評論社)』
百科事典マイペディア 「交通事故」の意味・わかりやすい解説
交通事故【こうつうじこ】
→関連項目交通違反
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通事故」の意味・わかりやすい解説
交通事故
こうつうじこ
traffic accident
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の交通事故の言及
【交通違反】より
…その多くに対しては,同法第8章に罰則が定められている。事故(人の死傷・物の損壊)を伴う場合には,人身事故のときは業務上過失致死傷罪(刑法211条前段),建造物に対する物損事故のときは業務上過失建造物損壊罪(道路交通法116条)にもあたることが多いが,この場合を単純な交通違反と区別して交通事故ということも多い。 道路交通法違反事件は,犯罪としては軽微なものが多く(1996年の全有罪者数約85万人のうち懲役・禁錮に処せられた者は約7000人であり,約97%は10万円未満の罰金である),また数が非常に多い(1996年に警察は約870万件を取り締まっている)。…
※「交通事故」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...