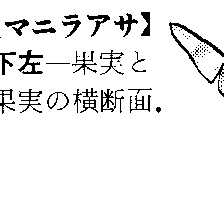マニラアサ
Manila hemp
Musa textilis Née
アバカabacaとも呼ばれ,葉(葉鞘(ようしよう))から繊維を採るために栽培されるバショウ科の多年草。原産地はフィリピンとされ,東南アジア熱帯で栽培される。草姿はバナナに酷似して,高さ約4mの葉鞘が巻き重なって茎状の偽茎を形成し,これが群がって株をつくる。葉身は狭長卵形で,長さ3.5m,幅50cmになる。果実はバナナに似て小型で,種子を有するが,増殖は主として吸芽(株から出た子苗)による。葉鞘から,強靱で弾力のある硬質繊維を採り,ロープや敷物などに利用する。耐水性があり,比重が小さいため,船舶用のロープに多く利用された。
執筆者:星川 清親
フィリピンのマニラ麻栽培
第2次大戦前,とくに1910年代,20年代にフィリピン最大の輸出商品であったマニラ麻も,最近では10大輸出商品の最下位を占めるにすぎず,年輸出額も2000万ドル程度(1982)である。生産低下の主たる理由は,病害のほか,戦後の人造繊維の開発によって工業製品に代替されるに至ったからである。マニラ麻収穫面積は37年に50万haで,生産量も20万tに達したが,72年にはそれぞれ14.5万ha,11万tの最低水準に落ちた。当時,〈死滅しつつある産業〉とまでいわれたが,70年代の石油危機を契機とする人造繊維の生産費上昇によりしだいにマニラ麻への需要が回復し,81年には23万ha,13万tにまで増大した。しかし,マニラ麻を主要所得源とする農家数は1971年に1万2500戸程度にすぎず,栽培農家のほとんどは5ha以下の小生産者で,大農園はきわめて少ない。そのため経営合理化の余地は限られている。
フィリピンにおけるマニラ麻の主産地はルソン島南東部のアルバイ州,南・北カマリネス州,ソルソゴン州を含むビコル地方,レイテ島およびミンダナオ島のダバオ州である。マニラ麻には一定した収穫期がないため,年間均等化した降雨量があり,台風の経路からも外れているダバオ州が適地である。第2次大戦前,ダバオは日本人の一大移民による農業植民地として有名であった。1934年に日本人移民数は1万5000人に達し,その農場面積は約3万8700ha,ダバオで産出されるマニラ麻の8割を日本人が生産した。400haをこえる日本人大農園は25に達したとされ,古川拓殖や太田興業会社の名が知られている。しかし,これら日本人農園は戦後すべて現地国側に接収・返還され,小生産者に分割された。その一部が最近バナナ栽培地に転換されている。マニラ麻は船舶用その他ロープの原料,漁網などにおもに用いられるが,最近では製紙原料として注目され,製紙会社の需要が増えつつある。
執筆者:滝川 勉
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
マニラアサ
まにらあさ
[学] Musa textilis Neé
バショウ科(APG分類:バショウ科)の多年草。茎は地中にあって地下茎となるので、地上に柱状に立つのは、葉鞘(ようしょう)が重なり合ってできている偽茎である。2~3メートルの偽茎の先に長さ約2メートル、幅約30センチメートルの長楕円(ちょうだえん)形の葉身が多数つく。形状は同属のバナナに似ているが、葉身の幅がやや狭く、葉の数が多いことで区別される。花茎は偽茎の中を伸び、偽茎の頂部から抽出する。花は穂状花序につき、花序の軸は太く、多くの節があり、各節に、包葉に包まれた多くの花がある。花穂の先端部には雄花が、基部には雌花が密生する。果実は長さ5~8センチメートル、径約2.5センチメートルで、多数の黒い種子がある。果実の形はバナナに似ているが、食用にはならない。
葉鞘の表皮の下に繊維があり、これを加工したのがマニラ麻Manila hemp, abacaである。繊維をとるには、まず偽茎を伐(き)り倒し、小刀で基部に切れ目を入れ、約5センチメートル幅で紐(ひも)状にはぎ取る。次にこれを挽(ひ)き具にかけて繊維をとる。マニラ麻は強靭(きょうじん)で、かつ水に浮くほど軽く、しかも水湿に対し耐久力が強いので、船舶用のロープの原料として重要で、また漁網や、特殊な織物にも用いられる。麻挽きの残り屑(くず)は製紙原料にもなる。
フィリピン原産で、フィリピンのほか、コスタリカなど中央アメリカでも大規模な栽培が行われている。
[星川清親 2019年6月18日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
マニラアサ
アバカとも。フィリピン原産のバショウ科の多年生木状草本(そうほん)で,高さ5〜7m。バナナに似るが,葉の幅が狭く,より密に束生し,果実は食用にならない。葉の繊維は強靭(きょうじん)でしかも軽く,耐水性が強いので船舶用ロープに最適。ほかに織物,帽子,製紙原料とされる。世界生産量の大部分をフィリピンで産する。
→関連項目アサ(麻)|植物繊維|繊維作物|ダバオ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
マニラアサ
Musa textilis; Manila hemp
バショウ科の大型多年草。フィリピン原産で,繊維をとるために熱帯各地で栽培され,品種も多い。フィリピン名を abacaという。高さ6~7m,外形はバショウに似ていて,バナナそっくりの果実もつくが,果実は食用にはならない。葉の幅が狭く,1株で数十本の茎を叢生することがある。太い頂生の穂状花序は湾曲して垂れ下がり,各包葉の中に2列に 15個内外の花をつける。花序の基部には雌花,上部に雄花をつける。葉鞘からとれる繊維は白色または帯赤黄色で,強くて軽くしかも水に対して耐久力が強いので,船舶用,漁業用のロープ,海底電線の被覆物としてきわめて重要である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のマニラアサの言及
【麻織物】より
…天然の植物繊維である麻を使った織物。麻の種類や幹,茎,葉など採取する部分の相違によって種類,製法もきわめて多く,性能,用途も異なる。おもなものに[亜麻](フラックス。織ったものをリネンと呼ぶ),[苧麻](ちよま)(ラミー,カラムシともいう),[大麻](ヘンプ),黄麻([ジュート],つなそともいう),マニラ麻,サイザル麻などがある。麻類はそれぞれ相違はあるが,多くは繊維細胞が集まって繊維束を形づくっており,繊維束の繊維素以外に表皮や,木質部,ゴム質,ペクチン質などを含有しているので,より細かく分繊して糸にし織物にするのが良く,ロープ,紐類などは繊維束をそのまま撚り合わせて使用する。…
【ダバオ】より
…フィリピン南部,ミンダナオ島南東部,ダバオ湾西岸に位置する都市。人口100万7000(1995)。20世紀初頭にはダバオ河口の小さな町にすぎなかったが,日本人実業家による[マニラ麻](アバカ)農園開発を契機に急激に発展,1914年にダバオ州の州都となり,36年には政令都市に昇格した。市域面積2211km2の超広域都市で,西方にそびえるアポ,タロモなどの火山山麓の緩斜面までが市域に含まれる。第2次大戦直前の市内在住日本人は1万8000人を数え,おもにタロモ川とシラワン川流域に住んでマニラ麻産業に従事,日本人小学校(15校)から病院(4)までもっていた。…
※「マニラアサ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」