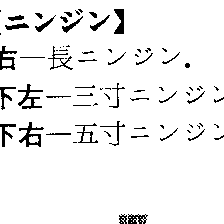改訂新版 世界大百科事典 「ニンジン」の意味・わかりやすい解説
ニンジン (人参)
carrot
Daucus carota L.
セリ科の一・二年草。当初導入されたものが,古来のチョウセンニンジン(ウコギ科)の根と似ていたためにニンジンと呼ばれるようになった。ニンジンの〈根〉は胚軸と根とが肥大したもので,その頂部から葉を叢生(そうせい)する。葉は2~3回羽状に裂けた複葉で,裂片は針状や披針形で,長い葉柄を有する。晩春,60~100cmに茎が伸長し開花する。花は複散形花序で,花色は一般に白色である。食用にされる貯蔵根の中心部は心と呼ばれ,形成層および木質部,髄から成り,心部の細いものが良品とされている。
来歴
ニンジンの野生種であるノラニンジンは,根がニンジンのように肥大しないし,黄白色で,赤くならない。このような野生系統はユーラシア大陸やアフリカ大陸北部に広く分布し,西南日本(瀬戸内地方)にも点々とある。しかし,その多くは栽培系統から野生化したものと考えられている。栽培ニンジンの変異が著しいのはアフガニスタンで,この地域で栽培化されたニンジンが,東へ分布を広げ東洋系のニンジンに,西へ分布していったのが西洋系のニンジンに分化したと考えられる。アフガニスタンで栽培化されたニンジンは,10世紀ごろに中近東からヨーロッパに広がった。15世紀にオランダで品種改良が進み,改良された品種はエリザベス女王時代(1558-1603)にイギリスに導入され,アメリカ大陸には17世紀になってから導入された。現在西洋系の代表的なニンジンとされる短根で橙黄色の品種群(三寸ニンジン)は,17世紀になってからオランダで改良されたものが基になっている。東洋系のニンジンは元朝の時代(1271-1368)に初めて,西アジアから中国に導入されたといわれる。ニンジンの漢名の胡蘿蔔(こらふく)は,西方(胡)から来たダイコン(蘿蔔)に似たものということでつけられたものである。日本へはまず東洋系のニンジンが中国から導入されたと考えられる。最も古い文献として江戸時代初期の《多識編》にセリニンジンの名が記されている。また明治初年になってからはヨーロッパ系の品種が,アメリカ,フランス,オランダなどから洋種野菜として導入されている。現在日本で栽培されているニンジンの多くはヨーロッパ系であるが,日本で品種改良が進み,日本の気候や風土に適したものが育成されている。
品種
ヨーロッパ系は,三寸群,五寸群,ナンテス群,インペレーター群,ダンバース群,ロング・オレンジ群などに分かれる。三寸群は早生,小型で土壌の適応性が広く,生育期間も短いが,収量が少ないので,最近は四寸・五寸系の品種に移り変わってきている。五寸群(五寸ニンジン)は気候,土壌の適応性も広く,大きさが手ごろで作りやすいため,全国的に栽培の中心品種となっている。寒地用としてはチャンテネー系が秋~春まき用に使われ,暖地用としては春~夏まき用に長崎五寸系の品種が多く使われている。ナンテス群はヨーロッパでは優れた品種として扱われているが,日本での実用性は低く,育種親として利用されている。インペレーター群は中根種で輸送性はあるが,日本での栽培は少ない。ダンバース群はおもに寒地の春まき用の品種として利用されているが,暖地の秋まき5月採りにも使われる。ロング・オレンジ群は大長ニンジンとして耕土の深い所に作られるが,最近の栽培は少ない。東洋系のニンジンには大長ニンジンの滝野川大長群と金時群がある。滝野川大長群は長ニンジンの代表種として秋まき用に使われてきたが,最近ではほとんど栽培されなくなった。鮮紅色で美しい金時群は,おもに関西地方で栽培されているが,暖地の夏まき用としても使われる。
ニンジンの栽培は全国的に行われているが,北海道,千葉,青森,徳島,茨城の各道県の栽培が多い。作型は春まき,夏まき,秋まき,トンネル冬まきなどに分かれる。春まき,夏まきは,全国的に広く行われ,秋まき,トンネル冬まきは,中間地,暖地などの栽培に適している。
利用
ニンジンはアルカリ性食品として重要であり,さらに根に含まれる橙色のカロチンは,動物体内にとりこまれるとビタミンAに変化するものであり,ニンジンにはビタミンAに換算すると約1万3000IU(国際単位)と野菜の中ではずばぬけて多く含まれている。用途はサラダ,煮物,揚物,油いため,ジュースなど多くのものに利用されるが,学校給食や外食産業には欠かせない野菜となっている。根だけでなく,香気のある若葉もゆでて食用にされる。またヨーロッパではリキュールをつくるのに,種子からとれる油を香りづけに使ったりする。
執筆者:平岡 達也
料理
煮しめ,揚物のほか,きんぴら,なます,白あえなどにする。白あえは,水気を切った豆腐と白ゴマをよくすりまぜ,砂糖,塩,しょうゆなどで味をととのえたあえ衣で,こんにゃくとともに,せん切りにして下煮したものをあえる。西洋料理ではサラダやシチューなどに用い,バター,砂糖などで甘く煮上げててりをつけたグラッセやクリーム煮にしてつけ合せに用いる。なお,ダイコンとともにすりおろすと,ニンジン中のアスコルビナーゼがダイコンのビタミンCを酸化させるが,酢を加えると酸化が防げるので,ダイコンとの紅白なますではビタミンCの損失はまぬかれる。
執筆者:橋本 寿子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報