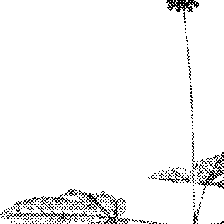改訂新版 世界大百科事典 「チョウセンニンジン」の意味・わかりやすい解説
チョウセンニンジン (朝鮮人参)
Asiatic ginseng
ginseng
Panax ginseng C.A.Mey.(=P.schinseng Nees)
根を薬用とすることで著名なウコギ科の多年草。ヤクヨウニンジン(薬用人参)とも呼ばれ,江戸幕府の薬園に栽培したのでオタネニンジン(御種人参)ともいう。また単にニンジンともいうが,野菜のニンジン(人参)とはまったく別種である。年数を経たものは草丈約60cmとなり,茎の頂部に長い葉柄をもち,5小葉からなる掌状葉を4~6枚輪生する。夏季,茎頂から1本の細長い花茎をのばし,先端の散形花序に淡黄緑色の小さい花をつける。秋季に,小さい球形の果実が赤色に熟する。根は年々ゆっくりと肥大し,発芽後数年を経過した株では,長さ10~20cm,太さ2~3cmに肥大する。先は指ほどの太さで数本に分岐し,この形が人間の体に似るので人参という。中国東北地方や朝鮮に分布するが,薬用植物として栽培もされる。野生のものは生長が遅く,成分が強いとされ,高価なものである。古くは,根の形が人体に似たものほど薬効が高いとされ珍重された。
また日本での栽培は,享保年間(1716-36)に始まり,長野,島根,福島などで良品を産出する。栽培は冷涼で湿潤,かつ弱光条件を好むので,東西に畝を作り,覆いをして北側だけをあけて,陽光を調節する。11月に種子をまくか,別途に苗を養成して移植する。播種(はしゆ)後4年ないし7年で収穫する。
洗って細根をとりさり,そのまま,あるいは漂白し,乾燥したものが白参(はくじん)で,白っぽい色をしている。掘ってからよく洗い,細根をとりさって蒸して,天日あるいは弱い火力乾燥をしたものが茶色の紅参である。このほか糖液につけてから乾燥した糖参などいろいろな調製法がある。
執筆者:星川 清親
薬用
人参は毒性がほとんどなく,万病に効果があるとされる。根にはサポニン,配糖体であるギンセノサイド類,ステロイド,ビタミンB群,コリンなどが含まれる。他の生薬と配合して滋養,強壮,強心,強精,健胃,鎮静薬として賞用され,新陳代謝機能の低下に賦活薬として用いる。
含有エタノールエキスは副腎皮質機能を強化し,大脳皮質を刺激してコリン作動性を増強し,血圧降下,呼吸促進,インシュリン作用増強,赤血球数やヘモグロビン増加の効果がある。またギンセノサイド類にはDNA合成促進作用,中枢抑制作用,中枢興奮作用,溶血防御作用,溶血作用など,ときによって相反する薬効を示す諸物質が含まれる。アメリカ東部産のアメリカニンジンP.quinquefolia L.(英名American ginseng)も薬用に利用され,チョウセンニンジンに劣らない薬効があるとされ,広東人参(洋参)と呼ばれる。また三七人参はP.notoginseng(Burk.)F.H.Chenの地下部で,主として止血,鎮痛,消炎,近年は強心,肝疾患などに,竹節人参はトチバニンジンP.japonicum C.A.Mey.の根茎で,去痰,解熱,健胃に用いられる。
執筆者:新田 あや
歴史
朝鮮では高麗人参ともいう。日本の正倉院の宝物にも見えるように,古来,不老長寿,万病の薬として漢方では最高の位置を占めた。朝鮮の特産物として人参は王室への進上物や中国への貢納には必ず含められ,また日朝貿易でも主力商品となり,ときには対外交易において銀貨の代用物とされた。朝鮮では採取量がふえるにつれて,山中に自生する人参の枯渇が心配され,人工栽培が14世紀末には開城で本格化したことが,李時珍《本草綱目》などに記載されている。以来,開城人参が有名になった。一度栽培した土地では地味が消耗するため,数十年人参栽培はできない。今日では開城のほか,江華島や忠清南道錦山などで大量に栽培され,海外への輸出も多い。栽培種の 参(ポサム)より自生の山参(サンサム)のほうがはるかに貴重とされているが,山参を見つけるのは難しく,親の病を治すための山参採りの孝行話は古くから数多い。山参採取を業とする人々はシムマニとよばれ,身を浄めて入山し,隠語を使い合って山参を探す。両江道,平安道,江原道などでは今日でも山参採取が続けられている。
参(ポサム)より自生の山参(サンサム)のほうがはるかに貴重とされているが,山参を見つけるのは難しく,親の病を治すための山参採りの孝行話は古くから数多い。山参採取を業とする人々はシムマニとよばれ,身を浄めて入山し,隠語を使い合って山参を探す。両江道,平安道,江原道などでは今日でも山参採取が続けられている。
日本でも江戸時代には朝鮮人参の需要が高まり,人工栽培も行われ,また人参の専売権をもつ人参座が成立した。人参は高価であったため,近世には〈人参飲んで首くくる〉という成句が,身分不相応な出費のために身を滅ぼすことのたとえにされたほどである。
執筆者:鄭 大 聲 日本で朝鮮人参の栽培が初めて成功したのは1728年(享保13),日光今市の御薬園においてであったという。その後の発展には本草学者田村藍水の努力が特筆される。37年(元文2),幕府より種子を拝領して試植して以来,彼は《人参譜》《人参耕作記》《参製秘録》などを著してその普及に寄与した。国産物の薬効に対する疑問には,藍水の弟子平賀源内の編になる《物類品騭(ひんしつ)》に反論が見える。広東人参も47年(延享4)以降,清国商人の手で到来していた。これは実は,1710年代にイエズス会士ラフィトーJ.F.Lafitau(1681-1740)がカナダで発見したアメリカニンジンが,フランス東インド会社によって中国広東に輸出されたものであった。フランス本国でもこのころには朝鮮人参(その大半はおそらくアメリカニンジン)が知られていたようで,《百科全書》にL.C.deジョクールが1項をさいて論じているほか,ginsengの語は62年アカデミー・フランセーズによって公認されている。
なお薬効高く形が人間に似る朝鮮人参には,中国では古来さまざまな伝説が語られているが,特に《大唐三蔵取経詩話》や明刊本《西遊記》に見える人参,人参果を,西洋での類似の妖草マンドラゴラ伝説のアラブを介した東漸と関連づける説(中野美代子《孫悟空の誕生》1980ほか)は傾聴に値しよう。
執筆者:松宮 由洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報