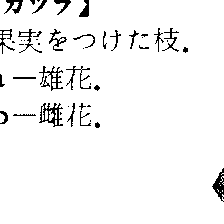カツラ
かつら / 桂
[学] Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
カツラ科(APG分類:カツラ科)の落葉高木。高さ25メートル以上にもなり、短枝が多い。葉は対生し、広卵形で長い柄があり、先は円く、基部は心臓形、縁(へり)に鈍い鋸歯(きょし)があり、裏面は粉白色を帯びる。5~7条の掌状脈がある。雌雄異株。花期は5月ごろ。花被(かひ)はなく、雄花は多数の雄しべがあり、葯(やく)は紅(くれない)色。雌花は3~5本の雌しべがあり、柱頭は淡紅色。果実は円柱形で湾曲する。日本全土の深山の谷沿いの林中に生え、中国には変種が分布する。漢字名の桂は、中国ではモクセイ科の植物のことである。近縁種ヒロハカツラは葉が大形で、樹皮には母種のような裂け目がない。
[古澤潔夫 2020年5月19日]
カツラに漢字の「桂」をあてるのは誤りで、桂は中国ではモクセイのことをさす。この混同は平安時代にまでさかのぼり、『和名抄(わみょうしょう)』は桂(モクセイ)の和名を女加豆良(めかつら)とする。花に芳香のあるモクセイが日本に渡来する以前に、中国からその知識だけが先行して伝わり、またカツラの木灰を抹香の材料に使ったことから、香りのある木として誤って桂の字をあてたのであろう。カツラの中国名は連香樹(レンシャンスウ)、あるいは五君樹(ウチンスウ)、または山白果(サンパイクオ)である。
[湯浅浩史 2020年5月19日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
カツラ
katsura tree
Cercidiphyllum japonicum Sieb.et Zucc.
カツラ科の落葉高木。日本の温帯地域の渓谷林を構成する主要樹種の一つ。株立ちした幹がそれぞれまっすぐに伸び上がった姿は壮観で,秋の黄葉も美しい。木は高さ30m,直径2m以上にもなる。葉は長枝では対生し,次年度はその葉腋(ようえき)からの短枝に1枚の葉がつくので,見かけ上,対生である。徒長枝では互生になることもある。雌雄異株で,春の展葉より前に開花する。花には花被がなく,雄花には多数の紫紅色のおしべが,雌花には数個の紫紅色の離生めしべがある。雌花は,それぞれのめしべが1個の花を代表していて,花序であると考えられている。果実は袋果で,中に細かい種子が多数つまっている。日本および中国に分布する。近縁のヒロハカツラは東北・中部地方の亜高山帯にみられ,種子の両側に翼がつくことで区別される。材は狂いが少ない優良材で,家具,碁・将棋盤,彫刻などに広く利用される。葉は抹香に利用される。また京都の葵祭には,フタバアオイとともに枝葉が必ず用いられる。カツラには桂の字が当てられるが,桂は中国では香木の総称で,モクセイを表す場合もある。
カツラ科Cercidiphyllaceaeは1属2種の単型科。同様に日本準固有の単型科であるヤマグルマ科,フサザクラ科と中国,ヒマラヤ産の単型科スイセイジュ科とともに,系統のはっきりしない,孤立した原始的な科として系統学上有名である。
執筆者:植田 邦彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
カツラ
北海道〜九州の山地にはえるカツラ科の落葉高木。葉は対生し,広い心臓形で縁には鈍い鋸歯(きょし)があり,裏面は粉白色で5〜7本の掌状脈がある。雌雄異株。春,葉の出る前に紫紅色の花を開くが,花被はない。果実は短円柱形で,秋,紫褐色に熟して裂ける。成長が早く,秋の黄葉も美しく,公園樹とし,材は建築,器具,楽器などに用いる。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
カツラ
カツラ科カツラ属の落葉高木。夏から秋に葉を採り、それを乾かし、粉にしてお香を作るのでコウノキ(香の木)とも呼ばれる。材の性質としては軽軟材にあたり、木質は密、香りがよく耐久性に優れる。加工は容易であるが、狂いやすい。造作材、ベニヤ材として用いられる。
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
世界大百科事典(旧版)内のカツラの言及
【ナンジャモンジャ】より
…日本各地に〈ナンジャモンジャの木〉と名づけられた樹が知られている。それらは植物学的には特定の種を指すものではなく,その地方で正体がはっきりしない珍しい樹種につけられていることが多く,クスノキ,カツラ,バクチノキ,ヒトツバタゴなどがこの名で呼ばれていた。それらのうち代表的なものに[ヒトツバタゴ]がある。…
※「カツラ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」