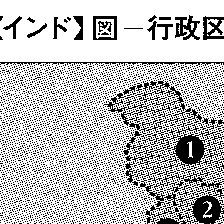改訂新版 世界大百科事典 「インド国」の意味・わかりやすい解説
インド[国]
India
基本情報
正式名称=インドBharat/India
面積=328万7263km2(ジャンムー・カシミール(12万1667km2)を含む)
人口(2010。ジャンムー・カシミールを含む)=11億8211万人
首都=デリーDelhi(日本との時差=-3.5時間)
主要言語=ヒンディー語(公用語),英語(準公用語),テルグ語,アッサム語,マラーティー語,ベンガル語,タミル語など憲法にあげられている17の地方の公用語
通貨=ルピーRupee
国名はヒンディー語ではバーラトBharatという。インドは北半球に属し,その面積は,ヨーロッパの面積からイギリス,アイルランド,スカンジナビア諸国,ヨーロッパ・ロシアの面積を引いたものにほぼ等しい。人口は中国に次いで世界第2位である。人口密度は1km2あたり平均301人(1996。ただしジャンムー・カシミール州を除いた数字)。南アジア世界の中央に位置し,西から順にアフガニスタン,パキスタン,中国(新疆ウイグルおよびチベット両自治区),ネパール,ブータン,バングラデシュ,ミャンマーの7ヵ国と国境を接するほか,逆三角形の半島部のすぐ南東の海上にスリランカ,南西の海上ややへだたった位置にモルジブの両国がある。ただし,パキスタンおよび中国との国境が完全には確定しておらず,アフガニスタンに接するはずの部分は,そのため実際にはパキスタンの支配下におかれている。ここでは国としてのインドを扱うので,1947年のインド独立以前については地域名としての〈インド〉の項目を参照されたい。
自然
インドは地理的に互いに明確に区別される三つの部分から成り立っている。第1は北部を東西に走るヒマラヤ山脈である。世界一の高峰チョモランマ(エベレスト)はネパールと中国の国境にあるが,これに次ぐK2はパキスタン支配下のジャンムー・カシミール州にあり,第3位のカンチェンジュンガはネパールとインドの国境にある。第2は北インド平原で,パキスタンでインダス川にそそぐ諸河川,ガンガー(ガンジス)川とその多くの支流,および北東部を流れるブラフマプトラ川の流域である(ヒンドゥスターン平原)。ヒンディー語を公用語とする6州の大部分はこの地域に含まれ,ヒンディー・ベルトなどと呼ばれる。第3はナルマダー川とビンディヤ山脈から南にひろがる逆三角形の半島で,その大部分はデカンと呼ばれる高原を形づくっている。デカン高原は西から東にかけてゆるやかに低くなるので,半島の北西端でアラビア海にそそぐナルマダーとタープティーを例外として,北から順にマハーナディ,ゴーダーバリー,クリシュナー,カーベリーなどの主要河川はいずれも東のベンガル湾にそそぎ,平野も東海岸に多い。ゴーダーバリーはガンガーに次いでインドで流域面積が広い川である。西海岸近くには南北に西ガーツ山脈が走り,その西側には比較的せまい平野がある。ヒマラヤ山脈,ビンディヤ山脈,西ガーツ山脈はインドの三つの主要な分水嶺である。
半島の部分では年間を通じて気温が高く,乾季と雨季の事実上二つの季節しかないが,北部の平原ではこれに冬季が加わって三つの季節になる。大部分の地域では雨量のほとんどが6月から9月の雨季に集中する。一般に東から西にゆくにしたがって雨量が減少し,またデカンでも雨量は少ない。作物のパターンは基本的にはこれらの自然条件によって決められている。森林面積は国土面積の33%が適当とされているが,全国的に濫伐が進んで19.5%にまで減少し,自然の循環に支障をきたしている。
住民,言語
10年ごとに行われている国勢調査の結果をみると,人口は1921年から増加しつづけており,しかも増加の速度は概して速くなっている。1981年から91年の10年間の増加率は23.8%であった。95年の出生率は1000人当り26.5人,死亡率は同じく9.8人,したがって自然増加率は年に1.67%と推定される。男子人口に対する女子人口の比率は低下する傾向にあり,1991年には男子1000人に対し女子927人となっている。都市部人口の比率は着実に上昇し25.7%となった(1991。都市部とは人口1万人以上の集落というにほぼ等しい)。農村部から都市部への人口移動はかなり多く,また都市部のなかでは人口10万人以上の大・中都市の膨張が目だっている。
主要な言語として憲法にあげられたのはアッサム語(アッサミー)Assamī,ベンガル語(ベンガリー),グジャラート語(グジャラーティー)Gujarātī,ヒンディー語,カンナダ語Kannada,カシミール語(カシミーリー)Kashmīrī,マラヤーラム語Malayālam,マラーティー語,オリヤー語Oriyā,パンジャーブ語(パンジャービー)Punjābī,サンスクリット語,シンド語(シンディー)Sindhī,タミル語,テルグ語,ウルドゥー語の15であったが,92年の改憲によってこれにコンカン語,マニプル語,ネパール語が加わった。カンナダ,マラヤーラム,タミル,テルグの4語がドラビダ系(ドラビダ語族)に属し,マニプル語はシナ・チベット系に,他はインド・アーリヤ系(インド・ヨーロッパ語族)に属している。話者人口の比率はインド・アーリヤ系の3に対しドラビダ系がほぼ1である。97年からのインドの紙幣は,マニプル語とシンド語以外のこれらすべての言語に英語を加えた17言語で金額を記している。国語とされるものはないが,北インドを中心に話者人口が最多のヒンディー語が公用語と定められている(憲法343条)。
政治史
独立への歩み
独立後のインド政治史を理解するためには第2次世界大戦から分離独立にかけての時期にまでさかのぼる必要がある。インドが独立を獲得することが確定的となったのは第2次大戦中の1942年3月である。それは,不利な戦局に直面したイギリス政府がインドおよび同盟国アメリカの世論への配慮から,閣僚の一人クリップスをインドに派遣して,インドを独立国家とするための制憲議会を戦後ただちにインド人の手によってつくることを認めると言明したからであった(クリップス使節団)。このときの交渉は失敗したが,このように近い将来における独立の見通しがついたことによって戦時下のインド政局の動きが早められた。そのおもな流れが二つある。
ひとつは国民会議派と左翼諸党派との対立の激化である。国民会議派は古くからの民族主義政党で,おもにヒンドゥー教徒を代表していたが,1930年代半ばの国民会議派社会党の結成やインド共産党の台頭によって国民会議派に対する左からの圧力が強まり,民族運動内部の主導権争いが激化していた。しかし,共産党が42年6月の独ソ戦開始以後の戦争を人民の戦争と規定してイギリスの戦争努力を支持し,7月にはじめて合法化されたのに対し,会議派は,イギリスのインド撤退を要求した8月の〈インドを立ち去れQuit India〉闘争で大量の投獄者を出した。このため,共産党は国民会議派によって民族運動を裏切ったと宣伝され,一時的にその影響力をそがれるにいたり,戦後の独立交渉で左翼勢力はほとんど発言力をもてなかった。民族運動の主導権争いはこうして共産党など左翼勢力に不利な形で決着した。
もうひとつは,ムスリム(イスラム教徒)を代表する政党であるムスリム連盟が戦時中に非常にその力を伸ばして国民会議派とならぶ位置を得たことである。連盟はムスリムが多数を占めるパキスタンという名称の国家をインドのムスリム多住地域につくること,つまり植民地インドがインドとパキスタンの二つに分離して独立することを要求するようになったから,連盟の勢力拡大は事態がインドの分割に向けて大きく進んだことを意味した。分割が確定的となったのは,イギリスがインドに派遣した内閣使節団の調停の失敗,カルカッタ暴動,ノアカリNoakhaliとビハールでの暴動という46年の一連のできごとによる。東部ベンガル(現,バングラデシュ)の農村県ノアカリでのムスリム貧困農民の暴動は,直接の戦火は免れたにせよ第一線に近かった地域の荒廃と大量の復員兵士の帰村という背景で起こったものであり,したがって日本がビルマ(現,ミャンマー)を基地としてインドに侵入しようとしたことと深い関係がある。
ともかく,第2次大戦から戦後にかけて共産党など左翼勢力の封じ込めとムスリム連盟の強大化という2点を中心としてインドの政治地図は大きく塗り替えられた。このことは,独立とともに分割が避けられないであろうということ,および新国家の建設において当面は左翼勢力,したがって人民大衆が大きな発言権をもちえないであろうということを意味した。これらの点はほぼ同じ時期に起こった中国革命との大きな相違点である。左翼勢力の発言力が復活したのは,57年のケーララ州共産党政府の成立によってである。最後のイギリス人総督マウントバッテンは1947年6月3日に分割案を発表し,それが会議派と連盟のそれぞれの議決機関で票決に付されて受諾された。票決に参加した人々,すなわち分割による独立か統一による独立かという決定に参加した人々の数は600人前後であった。分離独立の直接の法的根拠となったのはインド独立法Indian Independence Actと呼ばれるイギリスの法律で,47年7月18日に制定された。
分離独立
パキスタンは47年8月14日,インドは翌15日に独立した。いずれも大統領をもつ共和国ではなく名目上はイギリス国王が任命する総督をもつ自治領であった。インドが共和国となるのは50年1月の憲法発効による。インドとパキスタンの独立は第2次大戦後のイギリス植民地独立の第一歩であった。両国はイギリス連邦のメンバーとなったが,これはイギリス帝国内のイギリス国王に忠誠を誓う少数の独立国のグループであった。インドが共和国となるときに共和制がイギリス国王への忠誠とどのように両立しうるかが問題となったが,これはイギリス国王をイギリス連邦の首長と認めるという形で解決した。これによって共和国インドは引き続きイギリス連邦にとどまっているが,このことはその後イギリスから独立した多くの国がイギリス連邦に加盟する道を開くことになった。独立とともにインドはただちに二つの重要な問題に直面した。ひとつは藩王国の処理であり,他は分割にともなう混乱の解決である。
藩王国とはインドの国内に存在していた約500の大小さまざまの君主国で,イギリスの一種の保護国であり,その内部では藩王による専制的な体制が維持されていた。独立と同時にこれらの藩王国もイギリスの束縛から解放され独立しうることになるので,インドは各藩王国をまずそのまま独立インドに加盟させ,次いで第二の段階としてこれらを州制度のなかに吸収してその独自の主権を奪い去った。これによってインド全体がはじめて同一の政治制度をもつことになり,独立までのイギリス国王の臣民と藩王の臣民,および独立後の自治領の市民と藩王の臣民というインド人のあいだの身分的な区別が取り払われた。
分割にともなう混乱のうちもっとも深刻だったのは宗教暴動の続発,パンジャーブ州とベンガル州の真ん中に人為的に引かれたインドとパキスタンの東西の国境線を越えての住民の移動(ヒンドゥー教徒とシク教徒がインドに,ムスリムがパキスタンに),大量の難民の発生である。会議派のシンボル的な存在であったM.K.ガンディーはこのような状況をみて独立達成の意義に疑問をもつようになっていたが,彼自身もそのムスリムへの宥和的態度を憎む狂信的なヒンドゥー教徒によって48年1月にニューデリーで暗殺された。
ネルー政権の基盤
独立によって総督,あるいは共和制に移行してからの大統領の地位は名目的なものとなり,政治の中心は連邦首相に移った。首相は独立から64年5月の病死まで17年間,ジャワーハルラール・ネルーであった。ネルーは高名な弁護士の子で若くしてすでによく知られ,知識階層と労農大衆に対して大きな個人的アピールをもつためM.K.ガンディーによって国民会議派指導部のなかで重用された。言い換えれば彼の存在意義は保守的な国民会議派指導部に知識階層や民衆の支持を取り付け,これらの層に対して左翼諸党派の影響が及ぶのを防ぐことにあった。このことは普通選挙制が実現した独立後の時期にはさらに重要となった。
ネルー時代の国民会議派の選挙における確固とした支持基盤は,彼自身の出身カーストであり知識階層の多くの人々のそれでもあるバラモン,分割後もインドに取り残されて社会的に不安定な立場にあるムスリム,ヒンドゥー社会の底辺を形づくる指定カースト(不可触民)の三つであったといわれる。この3者だけで全人口の30%をこえると推定される。このことはムスリムや指定カーストが実際に独立後の改革や開発の恩恵を受けてきたことを意味するのではない。かれらの多くがネルー個人に希望を託して国民会議派の候補者に投票したということである。選挙が1選挙区定数1名という徹底した小選挙区制をとり,有権者は候補者の名を書く必要はなく,各政党のシンボルマークのなかから一つを選んで印をつければよいという投票制度もこのことを容易にした。ネルーという指導者のイメージが特定のシンボルマークと結びついて全国に宣伝されればよいからである。ネルーの出身はウッタル・プラデーシュ州だが,同州は独立後は人口第1位の州で,しかも国勢調査のたびに州の議員定数が人口に応じて調整されるため連邦議会に送る議員数も最も多い。同州をはじめとするヒンディー語諸州出身の議員団が彼の議会における直接の支柱であった。ネルーがもっていたこのような投票の際の支持基盤とヒンディー語諸州の人口の強味とはそのまま娘のインディラ・ガンディーと孫のラジーブ・ガンディーRajīv Gāndhī(1944-1991)に引き継がれ,80年代までのインド政治の特徴をなした。ではその基盤の上にどのような開発がなされたのか。
独立以後の発展の特質
発展の方向
独立以後のインドでは,特に1950年代半ば以降,大づかみには次の四つの方向が示されてきたということができる。
(1)公共部門中心の重工業化 1951年度から第1次五ヵ年計画が開始されたが,ネルー政権が考える発展の方向は56年度からの第2次計画によって明確になった。それは,まず工業化を目標とするが,基幹産業を公共部門に作り,その他の産業は民間部門に委ねるというものである。この結果,数個の製鉄所を中心とする一群の公共部門企業が生み出されると同時に,これと共存する形でターター財閥,ビルラー財閥をはじめとする民間財閥も発展した。このようにできあがった工業は世界経済から保護され,輸入代替的,自給自足的な色彩の強い経済が成立した。外資を含む投資活動も政府の煩雑な統制下におかれた。インドの識者の中には,かりに最初は経済統制が必要であったとしても70年代には緩和されているべきであって,そうならなかったことがインド経済の活力を奪ったとする見解が強い。90年代の自由化政策はこのような開発方式を大きく変えた。
(2)緑の革命による農業の発展 緑の革命は世界的な現象であったが,インドでは小麦地帯である北西のパンジャーブ,ハリヤーナー両州や,その東のウッタル・プラデーシュ州西部を中心に1967年から始まった。その過程で改良品種の作付け,灌漑設備の拡大,灌漑のためのディーゼルや電力の使用,化学肥料や農薬の投入が増加し,米と小麦,特に後者の生産が上昇した。米と小麦の生産量の比は1960年代初頭に約3対1であったが,70年代末に約3対2,90年代半ばで約4対3になっている。単位面積当りの平均収量でも1960年代後半に小麦が米を追い抜いた。これによってインドは食糧の自給を達成した。市販余剰をもつ富農,中農の立場は飛躍的に強化された。自由化政策は一面で緊縮財政を目指しているため,化学肥料などに支出されていた多額の補助金が削減されて農家経営に打撃となる可能性がある。
(3)左翼勢力の提示した方向 共産党の勢力は主要な州ではおもにケーララと西ベンガルに限られ,このほかにはトリプラ州で有力な程度である。しかし,1959年にケーララ州の共産党政権が解任された後も,これらの州では繰り返し同党による,あるいは同党の参加する政権が誕生した(インド共産党は中ソ論争のあおりを受けて1964年にソ連寄りのインド共産党(CPI)と自主独立派のインド共産党(マルクス主義)(CPI(M))とに分裂した。ここでは64年後については後者を指している)。後にみるケーララでの教育,保健,女性の地位などの面での著しい進歩はこのことと深い関係がある。西ベンガルでは77年から97年の今日まで同党を中心とする左翼戦線政府が州政府を組織して,保有上限を上回る土地の分配,小作条件の改善,農業労働者の賃金の上昇などで見るべき成果をあげている。自由化政策に対しては,勤労大衆の生活を圧迫するとして強く警戒している。
(4)自由化政策 1990年8月からの湾岸危機による石油の値上げ,湾岸諸国からの15万人の労働者の帰国,これら諸国への輸出の減少などのためにインド経済は大きな打撃を受け,91年には手持ち外貨が20億ドルを切る状態となった。すでに債務支払率は1986年度から25%台に上昇していたが,ここにきて債務不履行の可能性が生まれた。第10回総選挙で成立した会議派のラオP.V.Narasimha Rao(1921- )政権はIMFや世界銀行などの勧告を受け入れ,91年6月の成立直後から自由化と規制緩和(単に自由化と略)に踏み切った。そのおもな内容は,外資を含む投資への規制緩和,緊縮財政,その一環としての公共部門企業の経営改善,貿易の自由化などである。この結果,輸出入および外資の流入がいずれも急増してインド経済にはこれまでにない活気がみられる。インド経済は輸入代替的ではなくなったが,輸出主導型に転換しうるであろうか。
これら四つの方向を念頭におきながら,以下にそれらの特質を掘り下げてみることにする。
議会制民主主義
インドはアジアの発展途上国の中で普通選挙権に基づいた選挙を定期的に行っているほとんど唯一の国で,〈世界最大の民主主義国〉といわれる。選挙は連邦下院および各州Stateの下院の双方に関して行われてきた。連邦の上院と州の上院は間接選挙によって選出される議員を主体とし,あまり権限がない。州によっては一院制をとっている。連邦および州の政権はそれぞれ連邦下院と州下院の多数派によって構成され,それぞれ首相Prime Minister,州首相Chief Ministerを長とする。連邦には間接選挙によって選出される任期5年の大統領,州には大統領が任命する同じく任期5年の知事Governorがいるが,いずれも名目的な存在で,政治の中心は連邦や州の首相である。
これまでの連邦議会や州議会の選挙がいつも自由であったとは言いきれない。またカーストなどの集団が集票組織として活躍することもある。それにしても,大づかみには民意が反映されたと見られる選挙によって,いくつもの中央や州の政権が交代している。中央だけをとっても,1952年の第1回総選挙から最近の96年の第11回総選挙の間,1977年の第6回,80年の第7回,89年の第9回,91年の第10回,96年の第11回の5回の総選挙の結果によって政権が平和的に交代している。この交代から,最近になるほど政局が流動化していることがわかる。
これをネルー・ファミリー(いわゆるネルー王朝)に即して見ると,ネルーは首相として最初の総選挙の舵をとり,これを含めた3回の総選挙に勝利したが,娘のインディラ・ガンディーは第4,第5回で勝利した後,第6回で敗北し,第7回でカムバックした。インディラの息子のラジーブ・ガンディーもインディラ暗殺後の第8回で勝利したが第9回で敗北し,野党の指導者として第10回の選挙戦活動中に暗殺されている。第6回でのインディラ・ガンディー首相の敗北は,インドを独立に導き独立後も中央で政権を担ってきた会議派の最初の,このファミリーとしても最初の敗北であった。その意味でこの総選挙は独立後の政治史の分岐点である。首相として1975年6月に発動した非常事態の期間中の,彼女およびその側近たちの法に基づかない行動が有権者の批判を浴びたのであり,言論への統制や野党の活動への制約にもかかわらず与党が敗れたことは,民主主義がインドに根付いていることを示すものであった。
第11回総選挙による獲得議席数は,インド人民党(BJP)161,協力する諸政党を合わせて187,会議派136,統一戦線112(両共産党44を含む)などであった。第1党となったBJPがまず組閣したが,下院の過半数の支持を受ける見通しが立たず間もなく辞職し,その後は会議派の支持を受けながら統一戦線が政府を組織している。自由化を進めてきたのは第10回総選挙によって成立した会議派政権であるが,この政権が5年後に敗れたことは自由化の性格を示唆するものとして興味深い。ラジーブの暗殺以後,ネルー・ファミリーは政界に指導者を出していないが,その未亡人(イタリア出身)に政界への登場を促す声が会議派の中で高まっている。
インドは陸海空三軍あわせて100万人を超える強大な軍隊をもっているが,これまでのところ文民統制が貫徹していて軍隊は政治に関与したことがない。軍隊が政治に関与する可能性が指摘されたことが少なくとも2回あった。第6回総選挙で敗北したインディラ・ガンディーが軍隊の介入を促したとされるとき,および首相にカムバックした彼女がパンジャーブ州のインドからの独立を要求していたシク教徒の過激派がたてこもるシク教の総本山であるアムリトサル(アムリッツァル)の黄金寺院を軍隊で攻撃し,軍隊内に重要な地位を占めるシク教徒に動揺が見られた84年である(これが同年の彼女の暗殺につながる)。もし前者の場合に軍隊が出動していれば,インドは多くのアジア諸国にみられる開発独裁に移行していたかもしれない。いずれの場合にも軍隊は動かなかった。イギリス統治下でイギリスはインド人の軍隊を外征用として育成し,これにM.K.ガンディーの非暴力思想が対応したと見ることができる。その伝統がいまなお生きている。
中央集権的な連邦制
インドは連邦国家であるが,州の力はそれほど強くない。州の境界は基本的には1912年に引かれたものが分離独立や藩王国の統合を経ながら50年代まで存続し,56年の言語別の州再編によって大きな変化を遂げている。州は1919年のインド統治法によって初めて一定の権限を与えられ,35年の統治法によってさらにそれが強化されて独立にいたった。このように,州とは最初は地名にすぎなかったが,独立運動の要求にイギリスが譲歩することによって次第に政治的・行政的な実態を持つようになったのである。その意味でインドの連邦制はアメリカ,カナダ,オーストラリアなどの成り立ちとは逆である。しかも,独立以前のこのような分権化の動きは独立によって停止し,50年に施行された独立インドの憲法とその運用の仕方は,州に対する連邦の優位を以下にあげるさまざまな形で示している。
(1)連邦議会と州議会の間の立法権の配分。憲法の第7付表は,連邦議会にのみ立法権がある事項をリストⅠ,州議会にのみ立法権がある事項をリストⅡ,双方に立法権がある事項をリストⅢとしてあげている。リストⅠは防衛,原子力,外交,鉄道,航空,郵便,電信電話,放送,通貨,外貨,外国からの借款,貿易,州間の商取引,銀行,工業,石油および石油製品,鉱業,所得税,関税,物品税など多くの重要事項を含み,連邦議会,したがって中央(連邦)政府の権限は極めて大きい。加えて,州の法律は州議会を通過した後も州の知事,場合によっては大統領の裁可を経なければならない。また,リストⅢの事項に関しては連邦の法律が州の法律に優先する。
(2)連邦政府による州政府に対する監督。連邦政府は,州知事の報告などによって州の政治が憲法に従って運営されていないと判断した場合には,州政府を解任してその州を大統領の直接統治の下におくことができる。その場合には立法権も州議会に代わって連邦議会が行使する。上記の州知事による州の法律に対する裁可の場合と同じように,ここでも通常は名目的な存在である知事が大きな役割を持つ。57年の州議会選挙によってインド西南端のケーララ州では共産党の政権が誕生し,世界最初の選挙による共産党政権といわれたが,2年4ヵ月後にネルー首相の中央政府によって解任された。州政府罷免権が初めて注目されたのがこのときである。それ以来,州政府の罷免権はしばしば発動されている。大統領の直接統治の期間は最高1年と定められているが,87年5月にパンジャーブで発動されたこの措置がなかなか事態を収拾できず,そのためたびたび憲法が改正され,同州に限って直接統治が5年間まで有効とされた。
(3)インド行政職Indian Administrative Service(IAS),インド警察職Indian Police Service(IPS)といわれるエリート官僚グループの存在。彼らは連邦政府の管轄下にあり,連邦と州の行政,警察の主要なポストを占め,連邦制を動かす要となっている。現在IASの総人員はおよそ5000人である。
(4)州の連邦に対する財政上の依存。95年度の予算において各州の経常歳入合計1兆3644億ルピーのうち連邦からの交付金は5325億ルピーに達した。資本収入3885億ルピーのうちの連邦からの借入金の割合はさらに高く2139億ルピーで,主要な財源が連邦の手中にあることがうかがえる。
インドの連邦制ではこのように中央に大幅な権限が集中している。独立直後の憲法制定議会の起草委員長を務めたアンベードカルは,1948年11月の草案提出の際に,草案の規定する連邦制は,アメリカのそれと比べてはるかに単一国家に近く,また戦時には単一の仕組みとなるようにできていて他には類を見ないと言っている。実際それは75年からの非常事態の間にほとんど単一国家として機能したといってよい。このような意味でインドにおける意思決定の仕方はトップダウン方式である。
社会,経済
大きな国内格差の存在
インド憲法には後進諸階級Backward Classesおよびこれに類似のさまざまな表現がある。その意味するところは今も議論の対象となっているが,本来の後進諸階級が指定カーストscheduled castesと指定部族scheduled tribesを指すものであることには見解の差はない。指定カーストとはヒンドゥー教徒とシク教徒の中のいわゆる不可触民のことで,英語が複数形になっているのは州ごとにそのジャーティ(サブ・カースト)のリストがあるからである。連邦議会や州議会の選挙,公務員への採用,公立学校への入学などに関して,人口比例でこれらの人々に特別の枠が留保されている(留保制度reservation system)。指定カーストの人口は1億3822万人で総人口の16.5%を占め,州ごとにみるとパンジャーブの28.3%を筆頭に,人口1000万人以上の主要15州の大部分で15%前後から25%前後を占めている。指定カーストとそれ以外の人々との間に必ずしも明確な境界があるとはいえないが,その多くは穢れをもった存在であると見なされ,偏見や差別は今でも強い。またカーストを持たないはずのイスラム教徒やキリスト教徒の中にも指定カーストに相当するグループがある。
他方の指定部族とは非アーリヤ系先住民など森林地帯や山間部に多い住民のことで,やはり州ごとに指定され,さまざまな留保を受けている。人口は6776万人,総人口の8.1%で,中央部と北東に多い。留保措置の必要から,独立後の国勢調査では,カーストについての項目はないが,指定カースト,指定部族への所属に関しては設問がある。指定カースト,指定部族へのこれらの保護措置は憲法に従ったもので,最初は10年間だけの措置であったがすでに4回10年ずつ延長され,当面2000年まで継続されることになっている。連邦下院選挙では543の選挙区(小選挙区)があるが,その79が指定カースト,40が指定部族に留保され,これらの人々にしか被選挙権がない。州議会の選挙でも同様である。
この二つのほかにも憲法には〈その他の後進諸階級〉,あるいは〈社会的・教育的に後進の諸階級〉などの表現がある。その範囲を定めるために任命された第2次後進諸階級委員会が1980年に提出した報告書(マンダルMandal報告書)は,指定カースト,指定部族以外の事実上すべてのヒンドゥーのジャーティについて,社会面・教育面・経済面を含む複合的な尺度によってそれが後進的といえるかどうかを判断した。その結果,人口の52%が後進的であると見なされ,指定カースト,指定部族とならんでこれらの人々にも留保その他の保護措置がとられるべきであると勧告した。この報告書には合わせて3743の集団が後進的であるとして記載されている。
マンダル報告書は突如として現れたものではなく,バラモンやクシャトリヤほど上層ではないが,指定カーストや指定部族ほど下層でもなく,カースト制度の中間に位置している諸ジャーティが,独立後に普通選挙権を得たことによって自らの政治的な力を意識しつつ,指定カーストや指定部族なみの特権を要求したことに対応するものであった。中間諸ジャーティへの保護措置は南インドや西インドではすでに独立以前にもみられ,そのきっかけを作ったマドラス州(当時)の反バラモン運動は有名である。その要求が独立後に北インドに波及したものということができる。このようにインドの広範な農村部では上層諸カースト,後進諸階級(特にその上層部分),指定カーストの三つ巴の対抗関係が生まれている。マンダル報告書の勧告に対しては,それはインド社会をカーストによって分断するものだ,後進諸階級のカテゴリーから排除された上層の人々にとって不公平である,人の出自を重視し能力を無視する,後進諸階級の中でも恵まれた部分の要求である,などの批判がある。しかし,インド政府は90年にこの勧告を基本的に受け入れることを決定した。
同時にマンダル報告書は〈根本的な土地改革によって現在の生産諸関係の締めつけが打破されるまでは,支配的な上位諸カーストへの権利を持たない諸階級の,情けないまでの依存は永久に続くだろう〉として各州政府が土地改革を進めることを強く勧告する部分を含んでいる。事実,土地改革はあまり進んでおらず,若干の州における左翼政権の一手専売となっている。土地の集中の度合を90年度の保有地holdingについて見ると次のようになる。最も多いのは1ha未満の土地で,保有地数合計59%(その面積合計では14.9%)。次いで1~2haが19%(同17.3%),2~4haが13.2%(23.2%),4~10haが7.2%(27.2%),10ha以上が1.6%(17.4%)である。保有は所有とは異なるが,ほぼ経営を表すものと見ることができる。2ha未満の土地が80%近くだが,その経営面積を合計しても,全保有地面積の32%程度にしかならない。しかも保有地の平均面積は1970年度の2.3haから90年度には1.57haに減少し,限界的といわれる1ha未満の保有地の割合が増加している。しかも,インドの農民の中には土地を持たない農業労働者がきわめて多い。1981年と91年の国勢調査を比べると,前者では耕作農民9150万人,農業労働者5540万人だったものが,後者ではそれぞれ1億0710万人,7380万人で,農業労働者の方が増加率が高い。
このようにみてくるとインドの社会経済的な格差は非常に大きい。この格差は階級,カースト,性別の三つの面からつかむ必要がある。このことは,高度成長が開始される前の韓国や改革開放が開始される前の中国が徹底した土地改革を実施していたのに比べてインドの大きな特徴である。
不十分な人間能力の開発
インドにおける人間の能力あるいは人的資源の発展の度合は,特に教育と保健衛生に関してアジア諸国の中で遅れている。
まず識字率の低さがある。1991年の国勢調査では識字率は52.2%で,81年の43.6%に比して9%程度の上昇がみられた。しかし上昇速度が遅いうえに,性別に見ると男子は64.1%,女子は39.3%で大きな差がある。この差は以前からまったく縮まっていない。識字者でないということはそれ自体が社会的な差別の結果であるとともに,さまざまな差別あるいは不利益を受ける原因ともなる。女子の識字率のこのような低さはインドの教育の最大の問題点である。男女を問わずこの水準の識字率では,たとえ急速な経済成長がなされても一般の国民にその成果を受け取るだけの条件ができていないことになる。91年の女子の識字率を州ごとにみると非常に興味深い状況がみられる。ケーララ州のそれは86.2%で他をはるかに引き離している。パンジャーブ,ハリヤーナーの農業先進州では50~40%で以外に低い。ケーララは経済の面で成長の著しい州とはいえないから,成長がみられなくても社会的な条件を整備することができる,逆に成長が起こってもそれが自動的に社会的な基盤を整備することにはならないことをこれらの数字は示している。他方で,女子識字率はビハール,マディヤ・プラデーシュ,ラージャスターン,ウッタル・プラデーシュの4州では,そしてこの4州でのみ,20%台である。この4州はいずれもヒンディー・ベルトにあり,インドの中央部から北部にかけてのひと続きの広大な部分を占めて一括してBIMARUとよばれ,面積では全国の38%,人口では40%に達している。各州からはほぼ人口に比例して連邦下院に議員を選出しているから,ヒンディー・ベルトの政治的な発言力はそれだけ大きい。言い換えれば,独立後の政治は女子の識字率を向上させる方向に,より広くは女子を含めた社会の弱者層の立場を強化する方向に作用してきたとは言いがたいのである。
男女とも識字率が低いのは,成人教育の未整備もさることながら,大きな原因は初等教育が完備していないからである。インドの学校制度は初等教育5年,前期中等教育5年,後期中等教育2年,大学3年が標準である。ここで大学というのはカレッジのことで,その上にユニバーシティがあって大学院教育を行う。一つのユニバーシティが多くのカレッジをその傘下に持つというイギリス式の仕組みである。独立後の学校教育の拡大は上級の学校ほど顕著である。そのため,一方で,農村で5~9歳の男子の52.5%,女子の40.4%しか初等学校に通学していない(1987。しかも女子の通学率はBIMARU4州でもっとも低く,最低のビハール州では20%にもみたない)という状況があるにもかかわらず,国内に222のユニバーシティと8613のカレッジがあって611万人の学生(人口比で中国の6倍)が就学しているという,非常にいびつな状況になっている(カレッジ,ユニバーシティの数字は最近のもの)。先にみたように,後進諸階級からは公立学校入学に際しての留保枠設定への要求が強い。これは彼らの中の,経済的により恵まれた部分の要求と理解することができる。高等教育の目覚ましい発展は部分的にはこの要求に見合うものである。社会の底辺における膨大な非識字層を残したまま高等教育が拡大しているのである。膨大な児童労働あるいは都市のストリート・チルドレンの存在がこの状況に対応している。
次は保健衛生の水準である。インドの乳児死亡率は少しずつ低下して1990-92年に80となり,その後さらに低下したと見られる。これを反映して合計特殊出生率も1991年には3.6に低下した。その限りでは多産と乳児の多死という悪循環からインドの女性は解放されつつあるようにみえる。しかし,乳児死亡率,合計特殊出生率とも州ごとの開きが極めて大きい。前者では,ケーララの数字が17で,他のどの州もこれと肩を並べることができない。他方,オリッサのそれは120で最高である。この州は先のBIMARU4州の南東にあり,もしもこの5州を合わせるなら西はパキスタンとの国境,北はネパールとの国境,東はベンガル湾にいたる面積人口ともに全国の43%を占める地域となる。その4州の数字も概してオリッサに次いで高い。合計特殊出生率でも,ケーララは1.8で最低,タミル・ナードゥの2.2がこれに次ぐが,他の諸州はいずれも3以上で,BIMARU4州だけは4を超え,人口最大のウッタル・プラデーシュ州では5.1で最高である。
これらのことは,女性が劣悪な衛生状態の中で出産と育児に忙殺されている非常に広い地域がまだ存在するということである。これは,州ごとの平均余命,妊婦死亡率,15~19歳の女性の既婚者率,出産数中の産院での出産数の比率,幼児の免疫ワクチン接種比率,安全な飲料水へのアクセスが可能な家庭の比率などを比較することによってさらに確認することができる。教育と保健衛生の面でインドの人的能力はまだ未開発であり,経済の成長が起こっても多くの人々がその果実を十分に手に入れる状態にはない。そのしわ寄せは特に女性にかけられている。これを端的に示すのが持参金(ダウリー)問題で,このところ持参金が少ないとして婚家が嫁を虐待するケースが目だち,ユニセフの97年の報告書によれば,このため年間5000人の女性が自殺するか殺害されている。
また女性人口の中の寡婦の割合が高いこともあげられる。1921年には女子全体の18%近くが寡婦であった。平均寿命が伸びたことも手伝って91年には8%に低下しているが,男やもめの比率に対してはるかに高いのは,寡婦の再婚に対する強いタブーの存続を物語っている。性比(男子1000人当りの女子の数)は1901年から91年までの10回の国勢調査を通じて概して低下しており,1901年に972であったものが91年には927になっている。女性差別の集約的な結果であるといえる。91年の性比を指定カースト,指定部族についてみると,前者がわずか922であるのに対し後者は972である。指定部族における男女の関係がより平等であるためとみられ,その意味で彼らが一つのモデルになりうるのである。
環境条件の悪化
インド政府が環境森林省を設置したのは1985年である。このこと自体が環境条件の悪化を示すものであった。その状況をいくつかの項目について見ることにする。
(1)森林と土壌 インド政府が1988年に発表した全国森林政策では国土の33%が森林でカバーされていなければならないとしているが,実際の森林面積は19.5%で,しかもこれは急速に減少しつつあると思われる。1980年代の衛星観測によると,毎年の森林減少面積は約1万km2であった。インドには熱帯雨林といえるものは少なく,したがって木材が大量に輸出されるということはない。森林の減少は主として宅地や工場などへの転換,木材原料への国内需要,家庭燃料,家畜の過放牧によるものである。森林の減少は土壌を風雨にさらしてその劣化を促進し,洪水や干害を引き起こして影響が極めて大きい。森林の状態との直接の関係は明らかでないが,地方によって地下水の低下,農業用水の枯渇が報告されている。このことから農業用水の売買が進むものと考えられ,それが農家の階層格差を拡大するものとみられる。一部では原料としての木材を確保するためのプランテーション的な植樹もみられるが,本来の森林の回復とは異なるものである。森林その他のローカルな資源,特に共有地のそれの管理には自治体,特にパンチャーヤットと呼ばれる県レベル以下の3段階の議会が当たるのが最適であるとの指摘が多い。93年の第73次憲法改正でパンチャーヤットの活用のため任期5年の議員の選挙を行うことが新たに規定されたことは,中央集権的な行政への一つの歯止めとなるであろう。そこには同時に,人口に比例した指定カースト・指定部族への議席の留保と,少なくとも3分の1の議席の女性への留保も規定された。
(2)エネルギー インドの商業エネルギー消費量は石油換算で1人当り243kgで,タイや中国のおよそ3分の1であり,今後も増加することは確実である。エネルギーの中心は火力,それも石炭で,その生産は2億7000万tに達する。97年度から開始される第9次5ヵ年計画では,最終年次の需要見込みが4億5000万tであるのに,生産見込みは3億5000万tにすぎず,その増産は〈至上命令〉とされている。インドの石炭は灰分が多く環境に不都合なので利用技術の改善が望まれている。
これまで大型水力プロジェクトの建設に関してはさまざまな問題があった。典型的なのはナルマダー・ダム・プロジェクトである。インド中央部に発してアラビア海に注ぐナルマダー川に予定される一連のダム建設の結果,およそ10万人の立ち退きと,塩害やマラリア発生などの環境的な影響が懸念されたのである。その最初のダムであるサルダール・サロワール・ダムは1987年から本格工事が始まり,その発電設備に世界銀行との協調融資の形で日本のODA(円借款)も約束されたため,ダム・サイトの住民を代表するNGOの代表団が90年に来日してダム建設への反対を訴えた。これは日印関係史に残る一幕であったが,ここまで問題が大きくなったのはナルマダー・プロジェクトによって得られる農業用水を周辺の3州でどのように配分するかの調整に手間取り,その間に地元の住民が何の相談にもあずからなかったためである。現地はいわば山間の僻地で住民は指定部族が多く,開発のコストが明らかに弱者層にしわ寄せされていたのである。ナルマダーのほかにヒマラヤ山麓のテヘリー・ガルフワール・ダムも水没地の広さと環境への影響から問題になっている。
(3)都市問題 インドの都市人口は総人口の伸びをはるかに上回る速度で増加している。1981年から91年の10年間に人口の増加率は23.8%であったが,都市人口のそれは36.5%で,人口中の都市人口比も25.7%に達した。州別にこの10年間の都市人口の増加率をみると,意外にもケーララが61%で最も高い。同州はこの10年間の人口増加率が全国最低だが,それにしてもこの間の人口の増加はほとんどが都市に吸収されていて農村人口には目だった変化がない。ケーララの教育や保健衛生の水準の高いことはすでにみたが,その農村人口は扶養力の限界にきているのかもしれない。
都市(人口1万人以上の集落というにほぼ同じ)の中でも,クラスIあるいはシティといわれる人口10万人以上のものの比重が国勢調査ごとに高まり,91年にその合計人口は都市人口の65.2%になっている。1981年から91年の間に人口100万人を超える都市は12から23に,10万人以上100万人未満の都市は200から271になった。ボンベイ(現,ムンバイー),カルカッタ(現,コルカタ),デリー,マドラス(現,チェンナイ)が四大都市で,メトロポリタン・シティとも呼ばれる。四大都市の合計人口はおよそ3700万人であるが,その40%がスラム生活者であるといわれる。おそらくボンベイが居住条件の悪化を最も鮮明に示しているであろう。それは住居のほかに排水,ごみ処理,伝染性疾患,道路などについてもいえることである。伝染性疾患については,結核,ふたたび蔓延する危険を持つマラリア,トラコーマなどと並んで,HIV感染者の増加が懸念される。97年の国際エイズ会議ではインドのHIV感染者数は300万人から500万人と指摘された。
都市,特に大都市への急速な人口集中やスラムの大規模な存在は,これまでの都市化が農村からのいわゆる〈プッシュの要因〉によるものであることを示している。言い換えれば,これまでの開発過程でそれだけ多くの負担が弱者層にかけられたのである。この意味で四大都市での1981-91年の人口増加率がカルカッタで最も低かったのは,左翼政権下の西ベンガルで農村からのプッシュが減少したことを示唆している。
ごみの問題は自由化による消費財の出まわりによってより困難になっている。さらに自動車の増加による空気の汚染が進行している。インドの乗用車は1981年の116万台から急増して95年に363万台に達しインドもクルマ社会に入りつつあるが,その中の100万台前後が四大都市,特にデリーに集中しているからである。
(4)産業公害,環境保護運動,NGO 1984年12月にマディヤ・プラデーシュ州の首都ボーパールのユニオン・カーバイド社農薬工場で大量のガス漏れがあり,2500人の死者と多数の長期療養者を出した。この工場は閉鎖されたが,その前に立てられた碑には〈ノー・ボーパール,ノー・ヒロシマ,我々は生きたいのだ〉と記されている。このようなことからインドでは産業公害・産業汚染に対する警戒心が高い。自由化にともなって環境的な規制も緩和され,あるいは環境面ですでに悪名のある外国企業の進出があるのではないかという懸念も強い。
環境保護の運動は,1973年に始まるヒマラヤ山麓の森林地帯で,農家の女性たちが数人ずつの輪で一本の樹木を囲み,伐採業者に対抗して森林を守ろうとしたチプコChipko運動などから自然発生的に起こった。〈森林が土壌と水ときれいな空気を与えてくれる〉がその標語であった。しかしこの場合にも村々をまわって危険を訴えた先駆的な人々がいた。今では,ナルマダー・プロジェクトについて触れたような多くのNGOが,環境問題だけでなく広く社会問題について,全国ほとんどいたるところで活動している。最近これらのNGOは多くの環境問題を法的に取り上げ,その結果90年代半ばから最高裁判所は,公害を発生させている1500以上の工場にデリーからの立ち退きを命令するなど,いくつかの重要な判決を行っている。このような判決の場合には,短期的にみれば,例えば労働者の雇用に関して開発と環境のどちらを重視するかという衝突が起こる。
宗教的対立
1991年のインド国民の宗教別構成は次のようである(ジャンムー・カシミール州を除く)。ヒンドゥー教徒82%,ムスリム(イスラム教徒)12.1%,キリスト教徒2.3%,シク教徒1.9%,仏教徒0.8%,ジャイナ教徒0.4%,その他0.4%。ムスリムがこれだけ多いのは,分離独立前に人口の約4分の1を占めていたムスリムが現在のインド,パキスタン,バングラデシュの3国にほぼ3等分されているからである。
1947年の分離独立は,ヒンドゥーとムスリムは別々の民族でともに一つの国家を構成できないという論理を結局は受け入れたものであったから,公式には政教分離の世俗国家であるインドの内部に,この両者の対立が一種の制度として植えつけられてしまった。このことがカシミール帰属をめぐるインドとパキスタンの不安定な関係と呼応しあっている。しかしヒンドゥーとムスリムは本来的に対立すべきものではなく,この不安定さは多分に政治的なものである。このことが明確になったのは1980年代初めにインド人民党(BJP),その基盤である民族義勇団(RSS),および関連する諸団体がヒンドゥー原理主義(ヒンドゥー至上主義)というべき立場をとるようになってからである。BJPの前身は1951年に創設されたヒンドゥー主義的な政党のジャン・サングJan Sanghである。同党は非常事態下で行われた第6回総選挙でインディラ・ガンディーの会議派政権を倒すための野党連合に参加し,選挙に勝利して成立したジャナタ党政権で外相などのポストを得た。80年の第7回総選挙でジャナタ党が敗れると,新たにBJPとして再編された旧ジャン・サングはヒンドゥー原理主義の力によって政権獲得を目指すようになる。80年にカムバックしたインディラ・ガンディーは各州に自らに忠実な政権を作るため,ジャンムー・カシミールではムスリムが多数を占めるにもかかわらずヒンドゥーを会議派のまわりに固め,パンジャーブではシク過激派を支持するなど,宗教を利用した便宜主義的な行動をとった。このこともBJPに有利に働いた。
BJPなどがヒンドゥー原理主義のムードを劇的に高めたのは,ウッタル・プラデーシュ州北部のアヨーディヤーにラーマ寺院を建設する運動によってであった。当地には16世紀に建てられたイスラムのモスクがあるが,これがヒンドゥーの主要な神の一人ラーマの生誕地に造られているのは不当だから,取り壊してその後にラーマ寺院を造るべきだという主張をしたものである。この主張の背後には,インドのムスリムは独立後に不当に優遇されてきたという認識がある。したがって,ラーマ寺院建設の主張は社会的経済的格差などへの国民の不満を宗教的な感情によってそらすものであった。この主張はラーマーヤナ神話などを動員しながら84年から系統的に広められ,92年12月6日ついに彼らは実力でモスクを破壊した。このとき以来,北インド各地,特にラーマ神話と関係をもつ諸都市では両教徒の間の緊張が絶えない。両者が混住してきたところでは襲撃を警戒して少しずつ住みわけが行われているとの報告もある。パキスタンとの分離独立の際にはムスリム多数地域が東西パキスタンとして囲い込まれたが,住民交換による多くの悲劇が起こった。また当時のムスリムの3分の1はインドに残った。いまはジャンムー・カシミールを例外としてインドの中にムスリムが多数を占める州はなく,その意味で第2のパキスタンを作ることは問題にならない。ジャンムー・カシミールにしても,パキスタンはこれは自国領であるとしているが,当時の藩王国帰属の手続きからすれば同州がインドに帰属することは不当ではなかったし,同州のムスリムもそれを望んでいた。
ムスリムを疎外しこれを敵にまわすヒンドゥー原理主義の方向はインドにとって非常に危険である。ヒンドゥーの中にも原理主義はインドの当面する問題にとって何の解決にもならないとする強い批判がある。インドの統一が保たれてきたのはこのようなセキュラリズム(世俗主義)の立場によるのである。BJPやRSSの中心部分はヒンドゥーの上層諸カーストであるが,彼らはマンダル報告書が示すような後進諸階級保護措置の具体化が自らの既得権益を脅かすものとの認識をもっている。原理主義の立場がヒンドゥーとしての団結を訴えるのは,後進諸階級その他の弱者層の台頭への上層諸カーストによる反撃の一環であり,先に触れた三つ巴の闘争の一部である。
→コミュナリズム
外交
非同盟の立場
最後に,国際政治の面でのインドの行動の枠組みとなった非同盟の立場に触れよう。これは特にネルー首相の名と結び付くものである。1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)を成功に導き,冷戦の中でどちらの陣営にも属さないアジアから北アフリカに至る広大な地域の存在を世界に印象づけたことは,とりわけ彼の役割による。この会議でネルーは中国の周恩来首相のアジア・アフリカ諸国への紹介役も務めたが,その中国とは間もなく国境問題やチベット問題をめぐって衝突する。本格的な非同盟運動は,中国との対立がインドの立場にとって打撃となりはじめていた1961年からである。その前年は〈アフリカの年〉で,これに代表される新興諸国の台頭と国連の変化を受けて,米ソ対立の緩和のため61年に当時のユーゴスラビアで,ユーゴのチトー,エジプトのナーセル,ガーナのエンクルマ,インドネシアのスカルノ,それにネルーの5人の首脳を中心人物とする25ヵ国からなる第1回の非同盟諸国会議が開かれた。以後,非同盟運動は冷戦状態の緩和に大きな役割を果たした。
非同盟の立場にもかかわらず,インドは特に71年からソ連と密接な関係にある。これは,公共部門中心の工業化政策を掲げたが中国との関係改善を果たせなかったインドとしては当然であった。1962年の国境地帯での中国による武力攻撃(中印国境問題)も中ソ対立の一環という面をもっていた。71年に当時の東パキスタンでバングラデシュ独立運動が起こると,インディラ・ガンディー首相はソ連と20ヵ年の友好平和協力条約を結んでアメリカや中国を牽制し,バングラデシュの側に立って介入に踏み切った。これによってパキスタンを重視していたアメリカとの関係も冷却した。冷戦の終結は南アジアにも変化をもたらした。パキスタンはソ連のアフガニスタン侵略以来,アメリカにとってはソ連に対抗する重要な拠点であったが,いまやそのような価値はなくなり,反面で自由化によってインドの市場としての価値が高まった。
85年末にインド,パキスタン,バングラデシュ,ネパール,スリランカ,ブータン,モルディブの南アジア7ヵ国は南アジア地域協力連合(SAARC,本部はネパールのカトマンズ)を結成した。しかし主としてインド,パキスタンの対立から,この機構はその役割を十分に果たしていない。94年のインドとパキスタンの軍事費は両国の国内総生産(GDP)のそれぞれ3.6%,7%を占めている。これはカシミール問題に端を発した3度にわたるインド・パキスタン戦争,62年のインドと中国の戦争,および米ソをはじめとする諸国からの武器売込みの結果である。この巨大な軍事費はより平和に役立つ仕方で支出しうるもので,例えば両国の戦車1台の購入費400万ドルがあれば両国の400万人の子どもに免疫ワクチンを投与することができる。これが〈平和の配当〉であろう。またインドとパキスタンの緊張緩和は確実にインドにおけるヒンドゥー原理主義への抑制ともなるであろう。
旧ソ連との関係を受け継いだロシアとの関係も緊密である。これまでルピー決済であった貿易関係は96年現在でインドにまだおよそ80億ドル相当のルピー債務を負わせているが,その大部分は武器の購入費である。
中国との緊張は緩和された。しかし国境問題は未解決で進展の兆しを見せていない。加えて中国の持つ核兵器に対する警戒心も強い。96年にCTBT(包括的核実験禁止条約)署名問題でインドは世界的にほとんど孤立したが,この条約が1995年に更新された核不拡散条約とともに核兵器保有国に有利で,その他の諸国に不公平であるとするその立場は揺らいでいない。インドは1974年に1度だけ核実験を行っていたが,98年5月2度目の核実験(地下)を実施し,同月末これに対抗してパキスタンが初の核実験を行い,両国の緊張は一挙に高まった。
インドは92年から国連安保理事会の常任理事国となる希望を表明している。非常任理事国にはこれまで6回当選している(1997年末現在)。
見通し
このようにインドが内外で当面する困難は多様かつ大きなものである。しかし,もしもインドが,成長一点ばりの考えにとらわれず,その人口の膨大な底辺部の生活向上を主眼とした発展を,民主的な枠組みの中で,しかも宗教的な対立を克服して複合的な文化を作り出しながらなしとげることができれば,それは現在の途上諸国ばかりでなく広く人類の歴史にもかつてなかった試みとして世界的な注目を浴びるに違いない。それこそが今日,インドだけが発しうるメッセージである。また,その方向に向けて日本が協力する可能性も見いだしうるのではないか。
執筆者:山口 博一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報