精選版 日本国語大辞典 「鱗」の意味・読み・例文・類語
うろこ【鱗】
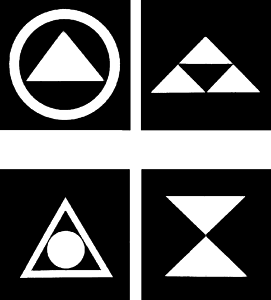
いろくず いろくづ【鱗】
(2)一四世紀ころからウロクヅが見えはじめ、一六世紀には優勢となり、イロクヅは文章語・歌語などに用いられる雅語となった。
うろくず うろくづ【鱗】
いろこ【鱗】
こけら【鱗】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
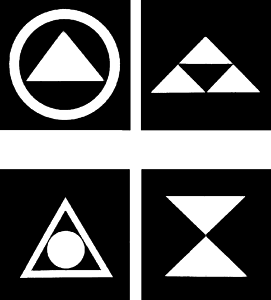
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
動物の体表に存在する硬い小片を一般にうろこといい,〈こけら〉とも呼ばれる。動物学的に定義すれば,脊椎動物の皮膚に生じたリン酸石灰質あるいは角質(ケラチン質)の小片である。うろこは体の保護,乾燥に対する防御だけでなく,感覚器としての機能をもつ場合もある。〈うろこ〉が魚の代名詞として使われたことからもわかるように,日本人にとって最もなじみ深いのは魚類のうろこである。現生の硬骨魚類にみられるうろこのほとんどは,骨鱗と呼ばれる真皮中に生じた骨質の小板であるが,原始的な硬骨魚類や軟骨魚類は由来や形態の異なるうろこをもつ。
そもそもうろこの起源は最古の脊椎動物である古生代初期の甲皮類の甲羅(外骨格)にまでたどることができる。甲皮類の多くは,象牙質からなる歯状突起をそなえた骨質板でつくられた甲羅をもっていて,なかでも腔鱗類は現在のサメ類の楯鱗(じゆんりん)に似た歯状突起だけで体を覆われていた。軟骨魚類の楯鱗は,皮歯ともいわれ,発生上も構造上も歯と相同で,あご上の楯鱗が発達して歯が形成されたと考えられる。楯鱗はギンザメ類やエイ類では退化的であるが,サメ類では〈サメ肌〉としてよく発達しており,古来より刀剣の柄や鞘の装飾に用いられている。デボン紀の原始硬骨魚類は,ガノイン質,コズミン質,骨質からなる硬鱗をもっていた。条鰭(じようき)類では,ガノイン鱗が発達するが,後に骨質のみが残った骨鱗になった。現生の条鰭類は,ガーパイクがガノイン鱗をもつ以外は,ほとんどが骨鱗である。骨鱗には,ニシンやコイなどにみられる円鱗と,スズキなどの櫛鱗(しつりん)が区別されるが,中間的形態のものや,両者をともにもつもの,うろこをもたないものもある。一方,総鰭類や肺魚類では,初期にはコズミン鱗であるが,後には骨鱗になっている。唯一の総鰭類の現生種であるラチメリアは,多数の歯状突起をもつ骨鱗で,腕鰭類のポリプテルスはコズミン鱗である。
エナメル質(ガノイン質)と象牙質(コズミン質)の形成には,上皮細胞と間葉細胞がともに関与するが,骨質は間葉細胞のみによって形成される。したがって楯鱗やガノイン鱗,コズミン鱗は成長にともなって脱落または吸収と新生がおこる。しかし骨鱗は真皮中で生涯成長しつづけるため,形成の速い季節と遅い季節の違いから樹木の年輪のような成長線がみとめられ,魚の年齢を知る重要な形質となっている。
両生類以上では,エナメル質や象牙質をもつ外骨格は口腔の歯として残るのみで,真皮中の骨片は皮骨として骨格の構成要素に組み込まれている(哺乳類では頭骨の大部分と鎖骨が皮骨由来である)。一方,陸上生活とともに表皮の角質化が始まるが,この角質層の発達したものが爬虫類の角鱗である。角鱗は上皮細胞にケラチンが生成・沈着したもので,魚類のうろことは発生も組成もまったく違うものである。多くの爬虫類の角鱗は真皮中の皮骨によって補強されているが,カメ類では皮骨が内骨格と癒合して甲羅をつくり,その上を角鱗が覆っている。タイマイのうろこはべっ甲として装飾品に利用される。角鱗は鳥類の後肢,哺乳類アルマジロやセンザンコウの体表,ネズミの尾にみられ,鳥類のくちばしと羽毛,哺乳類のつめ・ひづめ,サイの角などは角鱗の変化したものと考えられる。
執筆者:後藤 仁敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…楽曲のうちに用いられる音を整理して高さの順に配列したものが音階である。音楽の様式は時代や民族によってそれぞれに違っているので,その基礎となる音階にも多くの種類がある。西洋音楽では音階はすべてオクターブを枠として,この中に配列された音がオクターブごとに繰り返されるが,各地の民俗音楽やヨーロッパ以外の民族の音階には,オクターブを越えても反復しないものがあり,また完全4度あるいは完全5度のような小さい音域を音階の枠としているものもある。…
…単細胞の毛と多細胞の毛があり,ふつう液胞がよく発達して葉緑体などは含まず,表面はクチクラに覆われる。細胞が1列に並んだ毛のほかに,分枝のみられる星状毛や,細胞が平面的に並んだ鱗片scaleも毛の一種である。毛の類型化はいろいろの基準によって行われ,形状から刺毛,鉤毛(こうもう),絨毛(じゆうもう),綿毛,剛毛,棘毛(きよくもう),囊状毛,星状毛,鱗毛,乳頭突起など,性質や働きから腺毛,粘毛,根毛,吸収毛,散布毛,側糸,感触毛などが分類される。…
…高温の大気中で金属物体の表面に生成する厚い金属酸化物の層をいう。普通の金属は,金属光沢をもっていても数百nm程度の薄い酸化皮膜を有しているが,スケールは薄くてμm,厚いものではmmのオーダーの厚さである。 金属を熱間加工したり,焼きなまし,焼入れの際に高温に熱すると空気中の酸素が物体表面で金属原子と結合して酸化物をつくるが,この生成速度は温度の上昇に対して指数関数的に増大する。また分厚いスケールは金属の下地からはがれやすく,金属を熱する炉や熱間加工機械の中に落下する。…
… 第2に,地図は,地球の表面を縮小して表現するという性格をもっている。縮小の度合を縮尺(スケールscale)と呼び,一般に5000分の1,5万分の1,100万分の1などの分数で示される。縮尺の大きい地図というのは,5000分の1などのように分母の数字の小さい地図であり,縮尺の小さい地図とは,100万分の1などのように分母の数字の大きい地図である。…
…一般にはスケールscaleと呼ばれ,粗加工部品の寸法をパス,トースカンなどを用いて測定するものである。1mm目盛,または0.5mm目盛である。…
…物体と分銅とを直接に,あるいは間接に比較して物体の質量を測定する器具,機械,装置の総称。物体の重量(質量と重力の加速度との積)と分銅の重量および図5に示す各種の力とを直接または〈てこ〉などを介してつり合わせて物体の質量を知る。この場合,分銅の重量以外の力を用いたはかりの目盛は分銅で検査される。また,ばねの弾力や電磁気力を用いたはかりは重力の加速度の違いによる影響を受けるので目盛の検査にはこの影響が加味される。…
…いわゆる〈ひび〉で,角質層の厚い手掌,足底で目立つ。(6)鱗屑(りんせつ)scale 皮膚の表面に付着し,容易にはがれおちる白っぽい部分。“ふけ”もこれである。…
…計測器などで量の大きさを示すために記された線または点の集りである。目盛線は目盛を構成する線で,相隣り合う2本の目盛線の中心間隔を目幅といい,目幅に対応する測定量の大きさを目量という。目量のことを1目の読みということもある。このように目盛線で測定量を連続的な大きさで表示する計器をアナログ計器といい,測定量を数字を用いて離散的な値で表示する計器をディジタル計器という。【横山 豊】…
…昆虫,とくに鱗翅(りんし)目(チョウ,ガ)の体表や羽の表面を覆う微小で扁平なうろこ状構造物をいう。発生学的には剛毛と同じように,表皮の生鱗細胞がまず体表に突出したのち小さい袋状となり,細胞が退化するにつれて扁平なうろこ状になる一方,血液によって運ばれた色素粒が内部に満たされる。形状はいろいろで,鱗片の柄部は翅膜面にあるソケットに差し込まれて,屋根瓦状に配置されている。鱗片表面には細い縦・横しま模様の彫刻があって,それによって光沢のある色彩となる。…
※「鱗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新