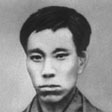改訂新版 世界大百科事典 「高杉晋作」の意味・わかりやすい解説
高杉晋作 (たかすぎしんさく)
生没年:1839-67(天保10-慶応3)
幕末期,尊攘・倒幕運動の中心人物の一人。長州藩士。松下村塾の逸材で,奇兵隊を創設したことで有名。萩の菊屋横丁,150石の家に生まれ(父は小忠太,母は道子),名は春風,字は暢夫(ちようふ),通称は晋作,東一または和助ともいう。号は東行(とうぎよう),西海一狂生など。藩校明倫館に学び,入舎生に選ばれたりしたが飽きたらず,吉田松陰の松下村塾に入門,久坂玄瑞と双璧をうたわれた。松陰は久坂の〈才〉に対し,高杉の〈識〉を高く評価した。1858年(安政5),20歳のとき江戸に出,昌平黌(しようへいこう)に学んだ。60年(万延1)には軍艦教授所に入学,また明倫館舎長,同都講を命じられた。この年,井上方(まさ)(山口町奉行井上平右衛門次女,数え年15歳)と結婚したが,以後死ぬまでの7年余は家庭生活とはほど遠く,馬関(下関)には愛妾おうのがいた。各地を歴訪,佐久間象山,横井小楠らと会っている。61年(文久1),藩世子毛利定広の小姓役となったが,翌年,藩命で上海に行った。ここで高杉は,列強資本主義に半植民地化されつつある中国の実情を見,また,その民族的抵抗に触れた。この体験が,帰国後のイギリス公使館(品川御殿山)焼打事件や身分にかかわらない有志による奇兵隊の創設の背後にあったとみてよい。高杉はみずからの行動を〈狂挙〉と呼ぶが,いうところの〈狂挙〉には,歴史変革への鋭い直感と,伝統的枠組みに対する異端的行動の意味を読み取ることができ,また,そこには一見無謀にみえる背後に慎重な配慮もかくされていたといえる。イギリス公使館襲撃の際の退路の準備や,藩の〈正兵〉に対する〈奇兵〉という命名の案出などにそれをみることができる。奇兵隊創設時は,馬関総奉行手元役,政務座役,奇兵隊総監の役職につき,ついで奥番頭役になったが,文久3年8月18日の政変後の情勢下で脱藩。その罪により64年(元治1)投獄されたが,4国連合艦隊の下関砲撃の危機を前にして免され,和議に臨んだりした。しかし,第1次征長下に長州藩の実権は保守派に握られた。これに対し,高杉は,64年末から65年(慶応1)初めにかけて,諸隊の一部を率いて馬関に挙兵,藩の主導権を奪い返し,木戸孝允らと挙藩軍事体制をつくって第2次征長をめざす幕府と対決した(長州征伐)。このとき海軍総督になって活躍したが,肺結核にかかり,67年4月,馬関で死去した。死の枕頭で,親交のあった野村望東尼(もとに)と,〈おもしろきこともなき世をおもしろく すみなすものは心なりけり〉という合作の一首を残した。ここには満27年8ヵ月の波乱の生涯を生きぬいた高杉の人生が凝縮されているといえよう。
執筆者:田中 彰
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「高杉晋作」の意味・わかりやすい解説
高杉晋作
たかすぎしんさく
(1839―1867)
幕末期長州藩における討幕派の中心人物であり、奇兵隊の創設者。名は春風、字(あざな)は暢夫(ちょうふ)、号を東行(とうぎょう)。大組(おおぐみ)(馬廻組(うままわりぐみ))士、家禄(かろく)150石高杉丹治(たんじ)の嫡子として出生。少年期、藩校明倫館(めいりんかん)に入学するが、1857年(安政4)19歳のとき松下村塾(しょうかそんじゅく)に入り、吉田松陰(よしだしょういん)の教育を受ける。やがて久坂玄瑞(くさかげんずい)とともに「村下の双璧(そうへき)」と称され、将来を嘱望される。1858年江戸へ出て幕府昌平黌(しょうへいこう)に入学。1859年松陰刑死後は遺骸(いがい)引き取りに奔走する。1860年(万延1)帰国後明倫館に勤務するが、やがて世子元徳(もとのり)付きの小姓(こしょう)となる。1862年(文久2)幕府の使節とともに上海(シャンハイ)に渡り、西洋列強国侵略の実情をみる。このため帰国後藩府に対し、公武合体策を放棄し富国強兵策の採用を進言する。しかし藩府が不採用のため亡命し、攘夷(じょうい)運動を推進する。同年末、江戸御殿山(ごてんやま)のイギリス公使館を同志とともに焼打ちする。1863年剃髪(ていはつ)し東行と号して帰国するが、下関(しものせき)戦争が始まり馬関(ばかん)総奉行(そうぶぎょう)手元役に抜擢(ばってき)される。そこで武士隊の敗北を知り、奇兵隊を創設し総監となる。奇兵隊は士農工商を問わず入隊でき、階級差別のない新しい軍隊であった。この後、下関講和交渉の正使となるが、藩府と意見があわず亡命する。1864年(元治1)下関で諸隊を集め、翌1865年(慶応1)内訌(ないこう)戦に勝利し藩府の主導権を握る。1866年第二次長州征伐(四境(しきょう)戦争)では小倉口(こくらぐち)方面の指揮官および全軍の総指揮官となり、勝利するが、慶応(けいおう)3年4月14日肺結核のため下関で死去。29歳であった。
[広田暢久]
『奈良本辰也著『高杉晋作』(1965・中央公論社)』▽『高杉東行先生百年祭奉賛会編・刊『東行――高杉晋作』(1966)』
百科事典マイペディア 「高杉晋作」の意味・わかりやすい解説
高杉晋作【たかすぎしんさく】
→関連項目イギリス公使館焼打事件|伊藤博文|河上彦斎|禁門の変|久坂玄瑞|斎藤弥九郎|薩長同盟|長州征伐|野村望東尼|山県有朋
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
朝日日本歴史人物事典 「高杉晋作」の解説
高杉晋作
生年:天保10.8.20(1839.9.27)
幕末の長州(萩)藩士。父は小忠太。安政4(1857)年藩校明倫館に入学。次いで吉田松陰の松下村塾に入り久坂玄瑞と共に双璧と称せられる。翌年7月江戸に赴き昌平黌に入学。獄中の松陰に金品を送る。文久1(1861)年世子毛利定広の小姓役,翌年5月藩命により幕府船千歳丸に乗船し上海へ渡航,植民地の実情を観察し帰国。同年11月久坂らと品川御殿山に新築中の英国公使館を焼打ちにする。翌文久3年1月松陰の遺骨を小塚原から回収,武蔵国荏原郡若林村に改葬。3月上洛。尊攘運動の興奮をいとい10年間の暇を乞う。「西へ行く人を慕ふて東行く 心の底ぞ神や知るらん」と,僧形となり東行と号して萩に隠棲。時に長州藩は外国船砲撃を断行し,報復攻撃にあって敗北。直後の6月藩命により下関防御の任に当たり奇兵隊を結成,自ら総督となる。時に25歳。奇兵隊の「奇」は正規軍の「正」に対する「奇」で,庶民も入隊できる有志隊であった。 8月18日の政変で京を追われたのち,長州藩内に高まる武力上洛論に反対,翌元治1(1864)年1月脱藩し上京,帰国して獄に入れらる。出獄後の同年8月,四国艦隊による下関砲撃の善後処理を命じられ講和条約を締結。第1次長州征討の進行に伴い佐幕派の藩政府が誕生,危機を察して九州に脱走し野村望東の平尾山荘に潜伏。下関に帰り,同年12月に挙兵。死を覚悟し「故奇兵隊開闢総督高杉晋作,則ち西海一狂生東行墓」の墓誌を用意した。佐幕派藩政府を相手に勝利を収めたのちイギリス留学を希望。次いで脱藩し讃岐の日柳燕石のもとに身を寄せる。帰藩後,用所役として藩政指導を担当。慶応2(1866)年6月海軍総督,幕府との開戦直後,小倉方面の戦闘を指揮した。同年10月,肺結核を重くして退職,翌年4月下関に病没した。享年29歳。のちの顕彰碑には「動けば雷電の如く発すれば風雨の如し,衆目駭然,敢て正視する者なし。これ我が東行高杉君に非ずや……」とある。<著作>『高杉晋作全集』
(井上勲)
出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「高杉晋作」の意味・わかりやすい解説
高杉晋作
たかすぎしんさく
[没]慶応3(1867).4.14. 下関
幕末の尊王派志士。長州藩士 150石高杉春樹の息。号は東行。松下村塾に学び,毛利定広の近侍となった。文久2 (1862) 年藩命を帯びて上海に密行し,外圧を意識して帰国。周布 (すふ) 政之助らと尊王攘夷運動の画策にあたり,藩内の百姓,町人をも含めた奇兵隊を組織し,士族の軍事専権制を打破した。翌年の文久三年八月十八日の政変で長州藩が京都で失脚し,第1次幕長戦争 (→長州征伐 ) で敗れると,蟄居させられた。元治1 (64) 年四国艦隊下関砲撃事件に際して再び起用され,正義党の中心人物として反幕府の方向に藩論を統一,第2次幕長戦争では大いに幕府軍を破ったが,まもなく病没。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「高杉晋作」の解説
高杉晋作
たかすぎしんさく
1839.8.20~67.4.14
幕末期の志士。萩藩士。名は春風(はるかぜ),字は暢夫(ちょうふ)。号は東行(とうぎょう)。変名谷梅之助・谷潜蔵。吉田松陰に学び久坂玄瑞と並び称される。1862年(文久2)幕艦で上海に渡る。帰国後久坂らと品川御殿山のイギリス公使館を焼き打ちし,また藩論の航海遠略策を批判した。63年萩藩の下関における攘夷決行に対する米仏艦の反撃に際し,奇兵隊を組織。翌64年(元治元)の四国連合艦隊下関砲撃事件では,藩の正使として講和に応じた。幕府の征長軍組織化にともなって藩の保守派が実権を握ると一時脱藩し,同年末から翌65年(慶応元)にかけて諸隊を率いて下関で挙兵,保守派を倒す。慶応軍制改革に参与し,66年の第2次長州戦争では小倉口参謀として活躍。67年下関で病死。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「高杉晋作」の解説
高杉晋作 たかすぎ-しんさく
天保(てんぽう)10年8月20日生まれ。高杉小忠太の長男。長門(ながと)(山口県)萩(はぎ)藩士。松下村塾にまなぶ。文久2年江戸品川のイギリス公使館焼き打ち,3年奇兵隊の創設,第2次幕長戦争での幕府軍撃退など,尊攘(そんじょう)運動の先頭にたった。慶応3年4月14日下関で病没。29歳。墓所は東行(とうぎょう)庵(山口県下関市)。名は春風。字(あざな)は暢夫(ちょうふ)。変名は谷梅之助,谷潜蔵。号は東行。
旺文社日本史事典 三訂版 「高杉晋作」の解説
高杉晋作
たかすぎしんさく
幕末の志士
長州藩士。松下村塾で吉田松陰に学ぶ。1862年上海に渡り海外状況を見聞し,帰国後尊王攘夷運動に活動。'63年長州藩の外国船砲撃直後の軍備強化で奇兵隊を組織した。翌年幕府の長州征討に降伏謝罪した藩当局に反して挙兵,保守派を倒し,藩論を「尊王討幕」にまとめる指導的役割をなした。第2次長州征討でも奇兵隊を率いて九州小倉の幕府軍を撃退('66)するなどの活躍をしたが,翌年大政奉還の半年前に病死した。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
防府市歴史用語集 「高杉晋作」の解説
高杉晋作
367日誕生日大事典 「高杉晋作」の解説
高杉晋作 (たかすぎしんさく)
江戸時代末期の長州(萩)藩士
1867年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
デジタル大辞泉プラス 「高杉晋作」の解説
高杉晋作
世界大百科事典(旧版)内の高杉晋作の言及
【奇兵隊】より
…結成は1863年(文久3)6月で,場所は下関の豪商白石家。上海で中国の半植民地化をまのあたりにした長州藩士高杉晋作が,安政期以降の長州藩軍制改革の成果に立って,藩主の信任のもとにつくったのが奇兵隊である。ときに長州藩は,攘夷期限(1863年5月10日)の外船砲撃の結果,米・仏などの反撃によって武士階級の無力さを暴露されていた。…
【馬関戦争】より
…優勢に立ったヨーロッパ連合軍は陸戦隊2000名を前田砲台や下関市街周辺に上陸させ,砲台を破壊し,あるいは奪い取り,3日間で戦闘が終了した。長州藩は高杉晋作を起用して14日に調停が成り,海峡通航の外国船保護,砲台の武装解除,下関市街を焼き払わなかった償金の支払,償金支払を幕府と列国の交渉に任すことが合意された。この事件によって長州藩の改革的勢力は一時後退したが,攘夷派が決定的な打撃を受け,やがて開国論が政府の主流となり,またヨーロッパとの軍事力の違い,軍艦・火砲の威力,さらに長州藩兵のなかで士気が上がったのは奇兵隊など諸隊だけであったことなどが深刻に認識され,慶応期の画期的な軍制改革の伏線となった。…
※「高杉晋作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
脂質異常症治療薬
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

 [1839~1867]江戸末期の
[1839~1867]江戸末期の