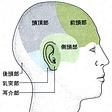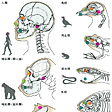デジタル大辞泉 「頭」の意味・読み・例文・類語
あたま【頭】
㋐首から上の部分。かしら。こうべ。「
㋑人間では、頭髪の生えた部分。動物では頭頂のあたり。「
2 脳の働き。思考力。考え。「
3 髪。頭髪。髪の形。「
4 物の先端、上端。てっぺん。「
5 物事のはじめ。最初。はな。「来月の
6 うわまえ。「
7 主だった人。人の上に立つ者。首領。長。かしら。「
8 人数。頭かず。「
9 (「ひとり」の下に付き、接尾語的に用いて)人を単位とすることを表す。…あたり。「ひとり
10 新聞の一面トップ記事。題号の左や下を占める。→肩
11 相場の最高点。天井。「
12 「
13 マージャンで、
[下接語]
[類語](1)
とう【頭】[漢字項目]
[学習漢字]2年
 〈トウ〉
〈トウ〉1 あたま。「頭骨・頭部/出頭・台頭・低頭・点頭・
2 物の先端。上端。「頭注/
3 物事の初め。「初頭・年頭・
4 上に立つ人。トップ。「頭首/会頭・巨頭・地頭・
5 その付近。ほとり。「駅頭・街頭・
 〈ズ〉あたま。「
〈ズ〉あたま。「 〈ト〉あたま。「
〈ト〉あたま。「 〈あたま〉「頭数・
〈あたま〉「頭数・ 〈かしら(がしら)〉「頭文字/尾頭・波頭・旗頭・
〈かしら(がしら)〉「頭文字/尾頭・波頭・旗頭・[名のり]あき・あきら
[難読]
かしら【頭】
 [名]
[名]1 人間や動物の首から上の部分。あたま。こうべ。「尾
2 髪の毛。頭髪。「
3 物のいちばん上、または先の部分。先端。「八歳を
4 一団の人々を統率する人。統領。特に、
5 (「首」とも書く)人形の首から上の部分。特に、人形浄瑠璃の人形の頭部。「
6 能で扮装に用いる仮髪。前は顔までかかり、横は両肩に垂れ、後ろは背丈に及ぶ長いもの。黒頭・赤頭・白頭があり、役によって使い分ける。「
7 もつ焼きで、豚の頭部の肉。
 [接尾]助数詞。
[接尾]助数詞。1 動物を数えるのに用いる。
「鹿の一―にても殺す者あらば」〈宇治拾遺・七〉
2 仏像を数えるのに用いる。
「(仏師ニ)幾―造り奉りたるぞと問へば」〈宇治拾遺・九〉
3
「折らぬ烏帽子十―、直垂、大口などをぞ入れたりける」〈義経記・七〉
4 人の上に立つ者、特に大名などを数えるのに用いる。
「あれへ大名一―、
[類語]
とう【頭】
 [名]
[名]1 あたま。
「黒き―かな、いかなる人の漆塗りけん」〈平家・一〉
2 集団の長。かしら。おさ。
「右の―には
3 「
「―の君心掛けたるを」〈源・末摘花〉
4 祭礼・集会などの世話役。
「
 [接尾]牛・馬・犬などの動物を数えるのに用いる。「牛七
[接尾]牛・馬・犬などの動物を数えるのに用いる。「牛七がしら【頭】
1 動詞の連用形に付いて、そうした時、そのとたん、などの意を表す。「出会い
2 名詞に付く。
㋐その中の第一位の者の意を表す。「出世
㋑その入り口、先端などの意を表す。「目
3 日時を表す名詞に付いて、その初めの意を表す。
「月―には東にあり、月の末には西にあると申す」〈謡・藤戸〉

 〉と記される。(b)大鼓の打音名。腕を十分に伸ばして打った,強く響く音。〈チョン〉と唱えられ,譜面上では〈△〉または〈
〉と記される。(b)大鼓の打音名。腕を十分に伸ばして打った,強く響く音。〈チョン〉と唱えられ,譜面上では〈△〉または〈