精選版 日本国語大辞典 「開国」の意味・読み・例文・類語
かい‐こく【開国】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「開国」の意味・わかりやすい解説
開国
かいこく
幕末、欧米列強の圧力により日本の鎖国制度が否定され、外交、貿易が開かれたこと。日本は開国によって資本主義的世界市場に従属的に組み込まれ、その影響は政治、社会、経済、文化のあらゆる面に急激な変化を引き起こし、幕藩体制の解体を促進して、明治維新とその後の近代化の決定的条件となった。
[中村 哲]
日本が組み入れられた世界
16世紀に始まる世界市場の形成は、16~18世紀の重商主義段階から18世紀末~19世紀前期の産業革命を経て自由主義段階に達し、1857年(安政4)に最初の世界恐慌が発生する。また、欧米からもっとも離れ、前近代的ではあるが統一国家のもとで鎖国政策が行われ、欧米勢力の侵入を長年にわたり阻んできた東アジアが、アヘン戦争を経て1842年の南京(ナンキン)条約による清(しん)(中国)の開国、58年の安政(あんせい)条約による日本の開国によって世界市場に組み入れられ、地理的にも世界市場がほぼ地球上を覆い尽くすのが1850年代である。
当時の世界市場の中心はイギリスであり、消費財のみでなく生産財においても工場制工業が確立し、「世界の工場」としての地位を確立していた。他の欧米諸国――フランス、ドイツ、アメリカなどは、イギリス資本主義に影響を受け、それに経済的に依存しつつも産業資本が確立し、いちおう自立的な国民経済が成立する。しかし、非欧米地域――アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、オセアニアは、欧米資本主義の従属的市場として組み入れられてゆく。この19世紀中期における後進地域の世界市場への編入は、前近代における貿易関係とは質的に異なっていた。圧倒的な生産力格差に基づいた商品の大量流入による在来産業の破壊、相対的過剰人口の形成、イギリスなどへの原料・食糧などの農産物輸出の発達、過剰人口を基礎とする高額現物地代を搾取する寄生的な地主制の形成など、旧来の伝統的生産関係が破壊され、欧米資本主義に従属する経済構造につくりかえられていった。19世紀中期に至って、資本主義は世界的規模で後進地域の内部経済を変革し始めたのである。この世界資本主義の底辺に強制的に組み入れられた地域は、さらに三つの類型に大別できる。第一はイギリスの白人植民地(カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ケープ植民地など)であり、第二は政治的独立はいちおう維持されたが、自由貿易規定を中核とし、協定税率、治外法権などを含む不平等条約を強制され、政治的、経済的に従属させられた諸国であり、ペルシア、トルコ、シャム、清(中国)、日本などがこれにあたる。第三は欧米にとっての異民族植民地であり、政治的、経済的自立性を奪われ、本国に完全に従属させられた点で世界資本主義の最底辺を構成する。19世紀後半~20世紀初頭にアジア、アフリカの多くの地域が植民地に転落してゆくが、19世紀中期においてはインドがその典型である。
[中村 哲]
ペリー来航と日本の開国
列強のアジア侵略を主導したのはイギリスであるが、19世紀中期にはクリミア戦争やインド、中国との戦争・民衆反乱鎮圧などに忙殺されていた間隙(かんげき)を縫って、日本の開国はアメリカ合衆国によって行われた。アメリカは、発展しつつある中国貿易においてイギリスに対抗するため、太平洋横断航路を開く意図をもち、その寄港地を日本に求めたこと、当時アメリカの捕鯨業が全盛期にあり、北太平洋に出漁する捕鯨船が増加し、日本に漂着する遭難船の乗組員の保護や、日本に避泊・補給港を求めたことなどによって、日本への関心が他の列強よりも強かったのである。
アメリカの遣日特派大使兼中国・日本分遣艦隊司令官ペリーは、4隻の軍艦を率いて1853年7月8日(嘉永(かえい)6年6月3日)浦賀沖に侵入した。黒船渡来の報は日本全国を震撼(しんかん)させたが、ペリーは大統領の国書を幕府に受理させて、いったん中国に引き揚げた。翌54年2月(旧暦1月)7隻の軍艦を率いて再度来航し、武力を背景に強硬に開国を迫り、ついに3月、日米和親条約(神奈川条約)が結ばれた。この条約は、下田(しもだ)・箱館(はこだて)での欠乏品供給、遭難海員・渡来民の保護、最恵国(さいけいこく)待遇、領事駐在などを規定し、通商条項は含んでいなかった。この条約に基づいて56年8月(安政3年7月)総領事として着任したハリスは、第二次アヘン戦争によるイギリス・フランスの中国侵略、中国の敗北を背景に、幕府と通商条約交渉を行い、58年7月(旧暦6月)日米修好通商条約が調印された。翌8月(旧暦7月)にはオランダ、ロシア、イギリス、10月(旧暦9月)にフランスと、相次いで、日米条約を原型とする条約が調印された(安政五か国条約)。
[中村 哲]
不平等条約の内容
安政条約は自由貿易規定を中核とし、片務的な領事裁判権(実質的な治外法権)、協定税率、最恵国条項を主要な内容とし、当時欧米列強が後進諸国に押し付けた不平等条約の一つである。とくに1858年6月に調印され安政条約のモデルになった天津(てんしん)条約とは基本的に同じ内容である。しかしいくつかの重要な相違点もある。関税率は、天津条約では輸出入とも原価の5%を基準とする従量税であるが、日米条約では従価税で、輸出税は5%、輸入税は5%、20%、35%の3段階に分かれ、大多数の商品は20%であった。しかし、1866年(慶応2)の改税約書(江戸協約)によって中国と同一の5%に引き下げられた。第二に、天津条約では外国人の国内通商権が認められたが、安政条約では開市開港場に限定され、外国の経済的侵略を防ぐうえで一定の役割を果たした。第三に、天津条約では、中国政府がキリスト教保護の義務を負い、中国領海内の海賊鎮圧のため外国軍艦が中国の港に自由に入港することを認めるなどの列強の内政干渉を招きやすい条項があるが、安政条約にはそうした条項はない。安政条約は典型的な不平等条約であるが、天津条約と比べるとその従属性は弱かったといえる。こうした条約の性格が、国内条件と結び付いて独自の国内変革(明治維新)を行い、自立的な資本主義を形成する一つの条件となったのである。
[中村 哲]
貿易の発展とその影響
安政条約に基づいて1859年7月(安政6年6月)から横浜(神奈川)、長崎、箱館の3港で自由貿易が開始されたが、その最初の影響は猛烈な金貨流出と洋銀流入であった。安政条約の内外通貨の同種同量交換規定が、東アジアにおける国際通貨であった洋銀=メキシコ・ドルと、国内において金貨の補助貨であった一分銀との間に適用されたため、国際金銀比価と国内金銀比価の格差がきわめて大きくなったことが原因であった。幕府はこの事態に対処するため1860年に金貨悪鋳を行ったため急激なインフレーションを引き起こし、幕府・藩財政や家臣団の窮乏を激化させて幕藩支配体制の解体が促進される結果を招いた。金銀比価の国際的平準化とともに貿易が急速に伸び、1859年の輸出89万ドル、輸入60万ドルから、1865年に輸出1849万ドル、輸入1514万ドルとなった。輸出では生糸が圧倒的で、茶が第2位、両者で大部分を占めた。輸入では綿製品が第1位、羊毛製品が第2位であり、ほかに幕末維新の動乱期に武器、艦船の輸入が増加した。取引相手国はイギリスが圧倒的に優位で、アメリカ、フランス、オランダ、プロシアなどであり、日本は、欧米資本主義の工業製品の販売市場、原料・食糧の購買市場という従属的な形で世界市場に組み入れられた。
貿易は完全に外国商人の独占であり、取引は開市開港場に設けられた外国人居留地内の外国商館で行われた。居留地は外国人の自治が行われ、領事裁判権と結び付いて実質的に司法・行政・警察権を外国に握られた国内植民地であり、商取引は日本人商人に不利であった。貿易の外商独占体制は、資本力、海外市場知識の独占、海運、海上保険、外国為替(かわせ)の便などの点での日本人商人との格差に加え、不平等条約に支えられて強力であった。外商はさらに日本人売込み商への前貸し支配によって国内流通にも進出し、居留地内に茶再製工場を設け、造船、炭坑経営など生産面への進出もみられた。国内経済は養蚕・製糸業、製茶業などが輸出産業化して急速に発展した反面、輸入品に圧倒されて綿業をはじめとする商品生産の破壊・衰退が進み、急激なインフレーションの影響とともに本源的蓄積を推進した。
[中村 哲]
尊王攘夷運動
ペリー来航に際して、当時すでに幕府は諸藩統制力が弱まっていたので、独力で対処できず、諸藩、幕吏の意見を徴した。これは異例のことであり、かえって幕政批判の道を開くことになった。さらに通商条約の調印に際しては、揺らぎつつある幕権を補強するため幕府は条約の承認を天皇から得ようとし、これに対して雄藩勢力や下級武士尊攘(そんじょう)派は勅許を阻止しようと運動した。これに、幕政改革をめぐる対立、将軍継嗣(けいし)問題をめぐる対立が加わり、激しい政争が展開されたが、幕府専制を維持しようとする保守派から井伊直弼(いいなおすけ)が大老(たいろう)に就任し、勅許を得られぬまま条約調印を強行し、反対派を弾圧した(安政の大獄)。その結果、かえって尊王攘夷運動は全国的に拡大するとともに急進化し、1860年(万延1)3月、水戸浪士らは井伊を暗殺した(桜田門外の変)。
本来、尊王攘夷思想は幕藩体制と対立するものではなかったが、現実の尊王攘夷運動は幕政批判の武器となり、高まりつつある民衆の封建支配に対する反抗の気運を背景として、激しい現状打破運動として展開した。また、欧米列強の圧力で不平等条約が結ばれ、貿易の影響とインフレーションが急速に全国的に広がるにつれて、そうした民族的危機に対して国家統一を要求する民族主義的性格をも帯び、倒幕派の母体ともなったのである。
[中村 哲]
『石井孝著『増訂 明治維新の国際的環境』(1966・吉川弘文館)』▽『石井孝著『日本開国史』(1972・吉川弘文館)』▽『中村哲著『世界資本主義と明治維新』(1978・青木書店)』▽『芝原拓自著『日本近代化の世界史的位置』(1981・岩波書店)』▽『浜屋雅軌著『開国期日本外交史の断面』(1993・高文堂出版社)』▽『松本健一著『日本の近代1 開国・維新』(1998・中央公論社)』▽『井上勲編『日本の時代史20 開国と幕末の動乱』(2004・吉川弘文館)』
改訂新版 世界大百科事典 「開国」の意味・わかりやすい解説
開国 (かいこく)
対外的に鎖国をつづけていた封建日本が,欧米の先進資本主義列強に近代的な国交・通商関係を強いられ,不平等条約の締結を起点として資本主義的世界市場と近代国際政治のなかに従属的に包摂されたこと。
条約の締結
日本の開国は,1853年7月(嘉永6年6月),浦賀に来航したペリー提督が率いる蒸気艦隊に威圧された幕府がまずアメリカ大統領国書を受領し,翌年(安政1)3月,再度来航したペリーとのあいだに日米和親条約(神奈川条約)を締結したのを発端とする。以来,幕府は,イギリス,ロシア,オランダとも和親条約を結び,外国船の寄港と補給のために下田,箱館,長崎などを開港したが,なお自由な通商貿易を認めてはいなかった。しかし,日米和親条約にもとづいて56年(安政3)に来日した日本駐在総領事T.ハリスは,幕府との執拗な交渉の結果,58年7月29日(安政5年6月19日),あらためて日米修好通商条約を締結した。この条約は,天皇の勅許を待つということでその調印をひきのばしていた幕府が,第2次アヘン戦争(アロー戦争)で中国(清朝)を屈服させたイギリス,フランスの大艦隊がそのまま日本に転進して新条約の締結をせまるという情報をハリスからうけて,勅許を待たずにあわてて調印にふみきったものであり,ひきつづき幕府は同年中に,オランダ,ロシア,イギリス,フランスとも同様な修好通商条約の締結を余儀なくされた。これらのいわゆる安政五ヵ国条約では,外交関係のみならず締結各国との自由な通商貿易も規定され,ここに日本の開国は最終的に確定したのである。
これらの条約で日本は,まず首都(江戸)に公使を,開港場に領事を駐在させ,彼ら各国外交代表の職務上の国内旅行権を承認した。また神奈川(横浜),長崎,箱館,ついで新潟,兵庫(神戸)を開港場とし,江戸と大坂を開市場として官吏の干渉なき自由貿易を行うことも認めた。各開港場には居留地を設定してそこに外国人が居留すること,開市場に逗留することにも同意した。そのうえ,締結各国に領事裁判権を与え,輸出入の関税率の決定は彼我双方の協定によることとされ,各国に対して片務的に最恵国待遇を与えることが規定された。とくに,これら不平等の三本柱とされる領事裁判権,協定関税制,片務的最恵国条款によって,来日した外国人はすべて事実上,本来は外交代表のみが享受しうる治外法権に等しい特権を獲得し,日本はいわゆる関税自主権をも奪われ,各国はすべてあらたな条約上の利益には自動的に均霑(きんてん)しうるようになるなど,政治上,経済上の対外従属的地位は明確となった。しかも条約には,外国貨幣の国内自由流通,内外貨幣の同種同量交換,地金銀・通貨の無税輸出入と自由鋳造など,日本の幣制自主権をも拘束する不平等で変則的な規定も盛りこまれていた。
貿易の影響
欧米列強はさらに,これら条約上の特権を利用して各開港場の居留地の治安と行政を掌握しつつあたかも列国共同の領土のように自治管理し,この日本のなかの異国のような居留地を幕府に迫って拡大させ,さらには攘夷運動からの自衛を口実として,そこに軍事基地さえも建設した。また外国商人たちは,当時の東アジアの国際通貨たるメキシコ・ドル(洋銀)を持ちこんでは国際的には相対的に安かった国内の金貨(小判)と交換して自由に国外に持ちだし,ぼろもうけをした。さらに,当初は一律従価5%とされた輸出関税率,5~35%とされた輸入関税率も,1866年(慶応2),江戸協約(改税約書)を強要して輸出入関税とも一律従価5%規準の従量税という低税率に改定させ,欧米資本主義の市場拡大の一環として日本市場をさらに深く開放させていった。
こうして展開しはじめた対外貿易では,横浜がすぐにその中心となった。かくて横浜は通商港として急膨張しはじめ,外商たちが殺到してきたが,しかしその中心はすでに東インド貿易や中国貿易の経験をつんで世界の市況に通じた近代商社,植民地銀行群や大海運会社であった。いずれもイギリス系のジャーディン・マセソン会社,東洋銀行,香港上海銀行,P&O汽船会社などは,その代表的なものである。そのため,海運や貿易金融をふくむ商権はすべて欧米列強が独占し,日本人貿易商といえば,外商に国産品を売りこむ売込商,外商が持参した諸商品を買いとる引取商というのがせいぜいで,日本人の手になる直輸出・直輸入などは皆無に近かった。このような半植民地的な貿易形態と対応して,貿易構造もまた従属的であった。すなわち日本は,手工業的な半製品たる生糸や,茶,水産物などの第1次産品を輸出する一方,まず大衆的に需要される綿製品,さらに毛織物,砂糖また武器・艦船などの資本制大工業生産物の輸入が急増し,それらの輸入全体が輸出総額を上まわるようになっていった。メキシコ・ドルの流入・金貨流出にともなう幣制の混乱とかさなったこの綿製品や砂糖の大量流入のなかで,国内各地の広範な綿業や糖業など商業的農業・農村手工業は打撃をうけて衰退し,物価急騰と経済の混乱,各地民衆の生活破綻にともなう社会不安もまた未曾有となった。
倒幕の発端
開国とともに,これに反発する尊王攘夷運動も,当初はおもに封建的な理念にもとづいた下級武士層のそれが中心であった。しかし,まずは条約の違勅調印と反対派弾圧をあえて行った大老井伊直弼や対外屈従の幕閣たちへの襲撃,外国の外交官や外国人への襲撃を主としていた尊王攘夷運動も,かかる国民的な苦難を背景として徐々に反幕・倒幕運動に展開しはじめた。他方,開港および通商開始以降の生活混乱とむすびついたこれら政争激化にともなう負担増が,中・下層農民や都市民を中核とした〈世直し〉の百姓一揆や都市打毀(うちこわし)を急激に拡大,激化させていった。こうして日本の開国は同時に,二百数十年来の江戸幕府の倒壊と明治維新による国家統一という歴史的大変革の,直接の発端ともなったのである。
開国の意義
日本は,第1次アヘン戦争と南京条約(1842),第2次アヘン戦争(アロー戦争)と天津条約(1858)による中国の開国からやや遅れて開国した。しかも,イギリスへの敗戦の結果として賠償金を支払い,香港,九竜を割譲し,領事裁判権,協定関税制,片務的最恵国条款のほかに外国人の内地通商権やキリスト教布教権なども外国に握られた中国に比して,日本の対外従属的地位はやや緩和されてはいた。とはいえ,1850年代末までの中国と日本の開国は,世界史的にみれば,カリフォルニア(1848),オーストラリア(1851)における大金鉱脈の発見と両地方への植民ラッシュ(ゴールドラッシュ)とともに,それまではいわば処女地だった太平洋地域が,近代産業資本を主役とする国際通商網のなかに最終的にくみこまれる画期となった。すなわち中国と日本の開国は,あたかもこの50年代にこそ進行しつつあった資本主義的世界市場・世界体制の確立の最後の一環としての意義をもち,東アジア諸国もまたそこに半強制的,従属的に編入されることによって苦難にみちた近代史を迎える,歴史的な画期を象徴するものであった。
執筆者:芝原 拓自
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「開国」の意味・わかりやすい解説
開国
かいこく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「開国」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「開国」の解説
開国
かいこく
1854年,アメリカ使節ペリーの威圧的な交渉に屈して日米和親条約を締結したことに始まり,'58年,日米修好通商条約を締結,続いてイギリス・ロシア・フランス・オランダなどとも同様の条約を結んだ。すでに18世紀末以来,ロシアついでイギリスが開国を求めて来航していたが,たまたま1853年以来のクリミア戦争の時期に,アメリカが諸国に先んじて日本の開国を実現させたことは,世界史的にみても注目を要する。開国の結果,政治的には,開国の是非論と将軍継嗣問題が結合して政争の激化をもたらし,幕府滅亡の遠因をつくった。社会的には,下級武士の窮乏と幕政への不満,百姓一揆と打ちこわしの激化という社会不安をもたらした。経済的には,物価騰貴と経済界の混乱を招く一方,製糸業に工場制手工業経営の発達をうながした。こうして時代は大きくかわり,近代化への道が開かれたが,それが自発的なものではなく,外圧によったことが日本の近代化に基本的特色を与えた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新

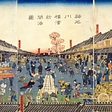
 叢(さんそう)
叢(さんそう) び魚鳧(ぎよふ) 國を開くこと、何ぞ
び魚鳧(ぎよふ) 國を開くこと、何ぞ 然たる 爾來四
然たる 爾來四
 千
千 秦塞と人
秦塞と人 を
を ぜず
ぜず