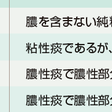精選版 日本国語大辞典 「痰」の意味・読み・例文・類語
たん【痰】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
内科学 第10版 「痰」の解説
痰(咳・痰)
健常者でも1日約10~100 mLの気道分泌物があり,おもに気管支の気管支腺や杯細胞から産生される.気管支腺は粘液細胞と漿液細胞からなる混合腺である.粘液細胞は糖蛋白を分泌し粘稠度を増加させる.漿液細胞は水分,電解質,分泌型IgA,分泌型IgM,リゾチームなどを分泌し,粘稠度を低下させる.産生された粘液は気道上皮表面を薄く覆い,気道の乾燥を防ぐとともに,吸入された塵埃や微生物をとらえる.その後,気道上皮細胞の繊毛運動により中枢気道に送られ,喉頭で無意識に嚥下されている.種々の原因により気管支腺や杯細胞が刺激されたり,それらの肥大化や増生が促されると気道分泌物量が増加し,痰として自覚される.すなわち痰とは気道の過剰分泌物である.ときに後鼻漏や気道に吸引された唾液,肺実質の化膿性分泌物,肺胞への漏出物や滲出物が痰として喀出されることがある.
痰が気道に滞留したり,喉頭でからむとぜろぜろとした咳となり,いわゆる湿性咳嗽となる.またしばしば気道を閉塞し,呼吸困難や無気肺,閉塞性肺炎,低換気による低酸素血症の原因となる.
原因
痰を生じる原因で最も重要なものは気道感染である.特に細菌性では好中球が動員され,その結果好中球に多く含まれるペルオキシダーゼにより痰は黄緑色となる.そのような痰は膿性とよばれる.痰に臭気を伴う場合には嫌気性菌感染が疑われる.非膿性痰のうち,粘稠度の高いものは粘液性とよび,そうではないものは漿液性とよぶ.粘液性の痰は喘息,急性気管支炎などでみられ,漿液性痰は肺水腫,喉頭炎,肺胞上皮癌などで,膿性痰は気管支拡張症,びまん性汎細気管支炎,慢性気管支炎,肺化膿症などで観察されることが多い.喘息では発作時に特に粘稠な痰が増加し,攣縮を起こした気道の内腔をさらに狭める.肺水腫では肺胞へ血漿成分が漏出するために,漿液性からときに泡沫状の喀痰が喀出される.肺胞上皮癌ではきわめて大量の漿液性喀痰が産生されることがあり,気管支漏とよばれる.
臨床検査
痰には気道や肺実質の病変に関する多くの情報が含まれている.感染症の原因菌同定のために,痰を用いた細菌の塗抹検鏡,培養,同定が行われる.痰が下気道由来で細菌学的検査に適しているか否かの評価は重要である.そのための痰の肉眼的性状を表すMiller-Jones分類を表2-35-1に示す.膿性が強くなるほど細菌学的検査には有用である.Gram染色による細菌の形態や染色性から,肺炎球菌,黄色ブドウ球菌,モラクセラ・カタラーリス菌,インフルエンザ菌,緑膿菌などは推定可能である.白血球によるそれらの菌の貪食像があれば,原因菌である可能性が高い.貪食像がなくとも定量培養で106~107 CFU (コロニー形成単位)/mL以上であれば,原因菌である可能性が高い.また痰の細胞診により,悪性細胞の有無を検査する.さらに痰中の炎症細胞の主体が好中球であれば原因病態が感染症の可能性が高く,好酸球であればアレルギー性の要素が大きい.
治療
治療は,痰を産生する原因を明らかにし,それに対して適切な治療をすることが主体となる.細菌感染であれば,適切な抗菌薬を投与する.対症療法として粘稠な痰に対して粘液溶解剤を使用する.β2刺激薬も狭窄した気道を拡張させて痰の喀出を促進し,咳を鎮める働きを期待して使用されることがある.しかし,逆に気管支腺を刺激して粘液分泌を増強させることがあるので注意が必要とされる.[山口悦郎]
■文献
木村 弘,山田嘉仁:喀痰,血痰,喀血.チャートで学ぶ病態生理学,第2版(川上義和,他編),pp40-41,中外医学社,東京,2000.永井厚志:痰.今日の診断指針,第5版(亀山正邦,他編),pp337-338,医学書院,東京,2002.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「痰」の意味・わかりやすい解説
痰 (たん)
sputum
気道から吐き出される粘稠性のある液状物質で,喀痰(かくたん)ともいう。そのおもな成分は気管や気管支の粘膜からの分泌液であるが,これに炎症や鬱血(うつけつ)などによる種々の細胞を含んだ滲出液や,外部から侵入した細菌や塵埃(じんあい)などの異物と吐き出す際に加わる唾液が混じっている。
健康人では1日に約100mlの気道分泌液がつくり出されており,これらは気道粘膜の繊毛上皮細胞の繊毛運動によって,細菌やほこりなどの異物とともにたえず口腔に向かって送り出され,無意識のうちに食道に飲み込まれている。その輸送速度は,気管では2~3cm/min,気管支では0.25~1cm/minといわれており,末梢の気管支へいくほど遅くなっている。このように,気道分泌液の役割は,気道内に吸入して粘膜表面に沈着した細菌やほこりを包んで運び出して浄化するとともに,吸入する空気に湿度と温度を与えることによって,繊毛の働きを維持し,肺を守ることである。気管支の炎症などによって気道分泌液の産生量が増加し,しかも繊毛上皮の働きが悪くなって輸送能力が低下すると,気道分泌液は気管支内に停留する。ある程度以上たまると,気管支の異物除去作用の一つである咳によって吐き出されることになる。これが痰である。
気道分泌液は一種の粘液であり,その構成成分はおもにムコタンパク質とムコ多糖類からなるムチンと呼ばれるものである。これらを産出する細胞は気管支腺と杯細胞の二つであるが,気管支腺がはるかに大きな役割をしており,その比率は40:1といわれる。気管支腺を顕微鏡で見ると,健康人では漿液産生細胞(径約35μm)と粘液産生細胞(径約50μm)とがほぼ同数であるが,慢性気管支炎などでは圧倒的に粘液産生細胞が多くなり,しかも大きさが増す。気管支腺でつくられた分泌液は,導管を通して気管支粘膜の表面へ送り出され,繊毛上皮をおおう。
気道分泌液が粘液であり,単なる水でないことは,繊毛上皮細胞による輸送を考えるうえでたいせつな点である。気道分泌物の物理学的性質は,ある程度以上の圧力を加えないかぎり流れず,また与える圧力と流れる速度とは直線状(比例)ではなく,曲線状である。このような性質があるからこそ,気道分泌液は,1秒間に10~15回といわれる繊毛のビーティングによって,あたかもエスカレーターで運ばれる固体のように輸送されることができるのである。繊毛上皮をおおう粘液は,上がゲル層,下がゾル層と二つの層に分かれている。しかし,現在のところ,これがどのような意味をもっているのか,また,この二つの層は化学成分が異なるのか,あるいは繊毛運動による単なるチキソトロピー現象であって,可逆的な変化をしているにすぎないのかは明らかでない。
→喀痰検査
執筆者:工藤 翔二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「痰」の意味・わかりやすい解説
痰【たん】
→関連項目去痰薬|鎮咳薬
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「痰」の意味・わかりやすい解説
痰
たん
sputum
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「痰」の意味・わかりやすい解説
世界大百科事典(旧版)内の痰の言及
【喉頭】より
…また気道狭窄を伴うと,呼吸困難や喘鳴(ぜんめい),咳などの症状を呈することがあるが,これは喉頭腫瘍のほかに,喉頭炎,両側声帯正中位固定症などでみられる。咳や痰などの増加は,正常粘膜への異常刺激に基づく分泌過多を伴うことが多く,さまざまの病変に伴うことが多い。喉頭痛はとくに嚥下時に強く,喉頭炎や潰瘍によることが多い。…
※「痰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新