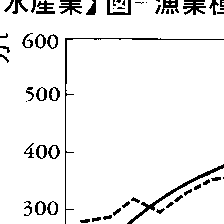精選版 日本国語大辞典 「水産業」の意味・読み・例文・類語
すいさん‐ぎょう ‥ゲフ【水産業】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「水産業」の意味・わかりやすい解説
水産業
すいさんぎょう
水産業は、水界の動植物の採取・増養殖、その生産物の加工製造、および最終消費に至るまでの流通の各分野を担当する産業の総称である。第一次産業の漁業・水産増養殖業、第二次産業の水産加工業、第三次産業の水産物流通業の三つの産業分野から成り立っており、水産資源を人間の生活のために利用する経済活動の統合的なシステムであるといえる。なお、「漁業」「水産増殖」の項もあわせ参照されたい。
[高山隆三]
システムとしての水産業
水産物、とくに魚貝類は、動物性タンパク質をはじめとして、ビタミン、ミネラルなどの栄養素に富む食品であり、人類は原始の昔からそれらを食料としてきた。しかし、魚貝類は一般に陸上の食用動物に比べると、死後硬直から自己消化を経て腐敗する速度が著しく速い。したがって、魚貝類など水産物の自己消化と腐敗からおこる変敗によって利用価値が低下したり失われたりすることを阻止する技術が、漁業生産活動に劣らず、水産資源の有効利用にとって重要となる。
そのような事情から、鮮度を保持する冷蔵・冷凍技術、自己消化・腐敗を防ぐ加熱・乾燥・塩蔵などの加工製造、生鮮魚貝類の漁獲から消費までの時間を短縮するための運輸手段の開発・整備などが進展し、これによってまた、漁業生産自体も発展を遂げてきたのである。水産物の変敗を防止することが、生産から最終消費に至るまでの各産業分野を緊密に結び付け、水産業という一つのシステムを形成するのである。しかし、欧米では、国民食料における水産物の比重は日本のように高くはなく、また水産物の取扱量も大きくないこともあって、実態としてのシステムは形成されていても、一般的に、漁業fisheryと区別した水産業ということばは用いられていない。
[高山隆三]
水産業の発展
原始・古代
魚貝類は、河川、湖沼、海洋に広く生息し、その採捕は鳥獣類より容易で危険性が少なかったから、水産資源が豊富な地域では原始以来、重要な動物性の食料源であった。同時に変敗が速やかであることから、鮮度に関する知識・経験が必要であり、その調理・保存方法にさまざまのくふうが施されてきた。
紀元前2000年以前といわれる古代エジプトの壁画には各種の漁業、魚の調理・加工の姿が描かれており、同時代の墓石には池中のティラピアが彫刻されていて、養魚も始まっていたことを示している。またバビロンの前2300年以前の文書に50種類以上の魚名が記されており、ハムラビ朝時代(前1700)にも市場で18種類の魚が取引されていた記録があり、池中養魚が行われていたことも知られている。古代ギリシアにおいても魚貝類の生産が盛んであり、水産物の取引も広く行われ、その販売に関する規則もみられる。とはいえ、生鮮魚貝類の市場は、腐敗性のゆえに主として生産地の周辺に限られていたし、水産加工品は塩蔵品が主であった。
古代ローマでは、地中海産の魚貝はほとんど食用に供された。紀元後1世紀初頭(19)にはローマでカキ養殖が行われ、養魚池が造成されてそこに海水を引き入れたものもつくられ、ヒラメなどが飼われ、餌料(じりょう)にもくふうが凝らされた。また数千の奴隷が漁労に使役された。ローマ時代に一般的な調味料は、リクアメンとよばれる魚醤(ぎょしょう)で、おもにイワシ類に塩をして、素焼の容器で発酵させたものである。魚醤は現在でもベトナムのニョクマン、カンボジアのトクトレなど東南アジアおよび朝鮮半島でつくられ、重要な調味料となっているが、ヨーロッパでは中世には用いられなくなった。
古代中国においても多くの水産物が食用に利用され、養魚も紀元前すでに行われていた。水産物加工法としては塩蔵、乾燥が一般的であるが、古代中国では6世紀の『斉民要術』に記されているものに、魚に塩をして麹(こうじ)を加えて発酵させた魚醤、および魚に塩をしたものと米飯を交互に甕(かめ)に漬け込んだ「なれずし」がある。
日本では貝塚から発掘される魚貝類の骨などから、すでに縄文初期、今日われわれが食用としているものをほとんど利用していたことが知られている。『日本書紀』『風土記(ふどき)』など古代文献に現れる魚類は31種類で、そのほか、貝類、海藻類も貢納品のなかにみられる。水産加工品には干しあわび、干しなまこ、塩蔵あゆなどがあげられるが、加工法として塩蔵、乾燥のほか、なれずしもつくられていた。またカツオを天日で干した堅魚(かつお)の煮汁である「煎汁(いろり)」は調味用に貢納されている。魚の料理法では、酢を用いた鱠(なます)もつくられている。ところで、魚貝類の保存にとって重要な役割を果たす塩については、製塩土器が海浜の遺跡から多く出土している。縄文後期になると濃縮した海水を土器で煮沸して製塩したのである。塩が貴重品であることは洋の東西を問わなかった。
[高山隆三]
中世・近世
漁業生産技術は、航海技術、漁船、漁網、釣り具の各面で進歩を遂げていったが、前代に引き続き経験と知識をもつ人々が生産の主力であった。加工に関しても塩蔵、乾燥が依然として主要な方法であった。しかし、中世ヨーロッパでは、北大西洋、北海、バルト海における漁業が、地中海より厳しい自然的な条件を克服しながら発展した。
8世紀末から、バイキングはこれらの海域における沖合・遠洋漁業を営み始めた。漁業生産の発展は、保存・加工用の塩、樽(たる)用の木材、漁業用の綱・網の素材の麻、釣り針用の鉄、などの取引を発展させたし、魚の取引に関しては、早くも1154年に魚商ギルドがロンドンで結成されている。12世紀までに、バスク地方やオランダの漁業者も遠洋漁業に進出し、前者は捕鯨も行い、後者は延縄(はえなわ)を開発した。
15世紀には、バスク、フランス、イギリスの漁業者はアイスランドの漁場を利用するまでになった。14、15世紀にはバルト海域でニシン漁業が栄え、ニシンの流通については、ドイツのリューネブルク産の塩を独占していたハンザ商人が優越した地位を占めた。ニシンは塩漬けにされ樽に詰められてハンザ諸都市に送られた。塩蔵にしんの消費が拡大した社会的背景には、キリスト教の普及があった。ローマ・カトリックでは、四旬節(復活祭の前夜までの40日間)や金曜日には肉食を慎んだことから、魚の需要がこの期間や金曜日には高かった。また、ヨーロッパ内陸部では、塩蔵か乾燥かの加工を施した水産物でなければ輸送日数からいって、食用には向かなかったのである。僧院などでは養魚池、生け簀(いけす)を利用して、コイやマスを飼っていたことが多かった。14世紀前半にニシンを求めてイギリス沿岸まで出漁したオランダ漁業者は、15世紀に漁獲物を船上で塩蔵することを始めた。これによって品質が向上し、販路も拡大して、オランダ漁業のその後の発展を導いた。船上加工は漁船の大型化を促し、それがさらに遠洋出漁を促進したのである。塩蔵にしんと並んで日干したらも重要な中世の保存食であり、ノルウェーのストックフィスクstockfiskが広く消費された(しかし、これを調理するのは楽ではなく、まえもって木槌(きづち)で1時間ほどたたく必要があった)。
15世紀末には、北アメリカ大陸東岸のニューファンドランド沖のタラ漁場が開発され、1580年にはヨーロッパ諸国から300隻以上の帆船の出漁をみている。塩干したらに対する需要はフランス、スペイン、ポルトガルなど南欧で強く、タラ漁業は初期アメリカの植民者にとっても重要な産業であった。このことから、イギリス対フランスのタラ漁場と加工用地をめぐる戦争が17世紀末に始まっており、アメリカ独立後は、アメリカ対イギリス・カナダの紛争が続き、この決着は1910年ハーグの国際司法裁判所の判決を待たなければならなかった。以上のように中世末までに西欧諸国は、北海、北大西洋の主要漁場をほとんど開発したのである。
日本においては、中世後半に大規模な網漁業や釣り漁業が発展してきて近世に連なる。地引網が広く使用され、底刺網(そこさしあみ)も現れ、手繰(たぐり)網も平安末に若狭(わかさ)(福井県)で用いられたとみられる。ニシンが記録に現れるのは室町時代の終わりからであり、東北、北海道の漁業も近世に入るとおこってくる。
江戸時代を通じて漁業は著しく発達し、捕鯨業が広まってくる。人口増加と魚肥利用によって魚貝類需要は増加し、江戸後期にはニシン漁業が発展し、各地でカツオ漁が盛んとなり、大型の定置網でマグロが漁獲されるようになった。17世紀末には中国(清(しん))への水産物輸出も始まっている。加工品では、かつお荒節(あらぶし)が紀州(和歌山県)で17世紀末につくられるようになったが、現在のかつお節の製法は1758年(宝暦8)土佐与市(とさよいち)によって考案され、安房(あわ)(千葉県)、伊豆、焼津(やいづ)に伝えられていった。また、広島湾でカキ、浅草でノリの養殖が17世紀末には始まっている。各城下町では専門的な魚市場・魚問屋が営業するようになった。ヨーロッパのように牧畜業の発展をみなかった日本では、古代から、仏教の影響によって支配者から肉食が禁じられたことと相まって、日本近海の世界有数の漁場を開発して、魚食を日常化する食文化を形成、定着させていった。この土壌が、近代において日本漁業の発展を受け止める基盤となっていったのである。
[高山隆三]
近代
産業革命以降の工業の発展を基礎として、水産業も飛躍的に発展した。造船業の発達によって大型の蒸気力、さらにディーゼルエンジンを動力とする漁船が建造され、綿紡績工業の発達によって大規模な綿網が生産され、漁法でも、トロール網が改良されてゆき、動力を用いて網を引き揚げるようになって、工業的な大量漁獲の工程が整ってくる。水産加工面でも、従来からの塩蔵、乾燥、酢漬け、薫製に加えて、新たに缶詰製造技術と、製氷・冷凍機が開発されて、生鮮魚貝類の保存法が大きく変革されていった。さらに、鉄道網の展開は、先進諸国内陸部における生鮮・冷凍魚類の市場を広め、水産物の性格を地方商品から全国的商品に転換していった。
真空の密閉容器で食品を保存する技術がフランスのニコラ・アペール(1752―1841)によって考案され、1804年に瓶詰が製造された。この食品保存法は、やがて壊れやすい瓶からブリキ缶にかえられ、1812年イギリスに最初の缶詰工場が設立される。1820年代に入ると、大規模な缶詰製造がアメリカで開始され、1868年以降手工業的な生産から機械的生産に移ってゆき、大量生産体制が整っていく。日本では明治初年、長崎で松田雅典(まさのり)がフランス人から缶詰製法を習得して製造したのが最初であるが、1875年(明治8)アメリカ、フィラデルフィアで開催された万国博覧会に明治政府から派遣された関沢明清(せきざわあききよ)が人工孵化(ふか)事業と缶詰業を視察し、翌1876年に北海道開拓使に缶詰製造所を設立したことから、缶詰生産が普及してゆく。日清・日露戦争による軍需の拡大が水産缶詰工業の興隆を導き、第一次世界大戦によって欧米輸出が増大し、これが、缶詰機械を設置したサケ・カニ工船漁業を発展させることになり、第二次世界大戦前まで水産缶詰は重要な輸出産品となったのである。
生鮮食品の保存に冷蔵が適していることは古代から知られており、天然氷の利用がくふうされてきたが、1873年にアンモニア冷凍機が実用化され、1874年、機械製の氷がイギリスで販売され始めた。これは、食品保存に変革をもたらしてゆく。冷凍運搬船が運航したのは1877年のことで、当初は肉の輸送にのみ用いられた。この製氷・冷凍技術の発展は魚類市場の拡大に大きく寄与した。1860年代以降の漁船の動力化は、船足を速め、鉄道輸送網の形成とともに、氷蔵した鮮度の高い魚類を消費者に届けるまでの時間を短縮していった。日本でも天然氷の製造販売が明治初年から始まるが、1883年(明治16)に製氷機が輸入され、翌年、機械製氷の営業が開始された。天然氷との競争を乗り切って、機械製氷が主位を占めるのは明治30年代であり、徐々に漁獲物流通に用いられるようになった。漁獲物用の冷蔵庫の建設が始まるのは第一次世界大戦直後の1920年(大正9)からで、アメリカの冷凍技師の指導によって凍結冷凍工場がつくられ、1922年に冷凍運搬船も建造され冷凍食品流通が形成されてくるのである。1923年に政府は「水産冷蔵奨励規則」を公布して、その普及に努めた。鉄道ではすでに1908年(明治41)に冷蔵貨車が製作されている。
低温流通体系が整備されてくる一方、アメリカでは料理に手間のかからないフィレ(切り身)に加工した魚の流通が1930年代に広まってくる。フィレは水揚げ地で製造されるが、これによって、1匹のままでは消費しにくい魚の販売も容易になった。アメリカの大西洋岸の大形のスズキは、1934年にフィレに加工されるようになってから、漁獲の対象となった。このように加工技術の開発は、未利用水産資源の利用を可能としていったのである。フィレ加工から、さらにフィッシュスティックが製造されるようになり、魚が規格化された食品素材となることによって、手軽なフィッシュバーガーなどの食品に利用されるようになった。
近代の漁獲物利用で顕著になったことは、魚粉(フィッシュミール)など非食用向け利用が増大したことである。漁獲物は、近代以前から肥料、魚油の原料として利用されてきたが、肉需要の増大を背景とした畜産業の発展が、20世紀に入るとタンパク質飼料としての魚粉の需要を高め、欧米の各地でそれを工業的に生産するようになっていった。日本でも1931年(昭和6)に魚粉工船が建造され、北洋で操業し、生産物を欧米に輸出するようになった。
以上のように水産業は、近代工業の発展を基礎として発達してきた漁業を中心に、その大量漁獲物の加工・流通過程の革新によって、システムとして確立されてきた。第二次世界大戦勃発(ぼっぱつ)前年の1938年、世界の総漁獲量は2100万トンに達した。
[高山隆三]
世界の漁業生産
第二次世界大戦後の特徴
世界の漁業生産は、第二次世界大戦後、綿網より軽く耐久性のある化学合成繊維網の普及、魚群探知機の実用化、自動航行装置をはじめ急速冷凍施設を備えた近代化した大型漁船による操業、などによって一段と生産力を向上させ、漁獲量も増大した。
全世界の漁獲量(海藻類を含む)は、1950年に約2100万トンと戦前水準に回復したあと、1980年までの30年間に3倍以上に伸長した。とくに1970年までの20年間は年率で5.7%の伸びを遂げ、農業生産の伸び率2%を大きく超えて、世界の食料・飼料の供給に貢献したが、生産量は1970年にほぼ7000万トンに達しながら、1970年代前半には生産量を減少させる不安定な状況に陥った。1970年代後半からふたたび漁獲量を増加させていくが、1980年代前半においても8000万トン弱の水準にとどまっており、1970年から1982年までの伸び率も年率0.9%とそれ以前に比して大きく低下した。この低下の原因には、第一に、1970年までに開発された優良漁場における水産資源の利用が限界に達し、一部の漁場では水産資源の枯渇がもたらされたこと、第二に、一部の水産資源が、水温、海流など自然の変化の影響を受けて大きく減少したこと、第三に、1970年代後半の、世界的な200海里の排他的経済水域の設定という新しい海洋利用秩序によって、漁業先進国の生産性の高い漁船による自由な操業が制約されてきたこと、があげられる。
第二次世界大戦後の世界の漁業生産の一つの特徴は、歴史的に漁業の先進国であったヨーロッパ諸国の生産の停滞に対し、日本をはじめ、旧ソ連などの社会主義諸国、一部開発途上国・中進国の生産が増大したことであった。1983年の世界の漁獲量の約50%を開発途上国・中進国が占めている(1960年には42%であった)。同年の生産量10位までの国は、日本を筆頭として、旧ソ連、中国、チリ、アメリカ、ノルウェー、韓国、インド、タイ、インドネシアで、開発途上国・中進国が6か国に上る。また、これら10か国で総生産量の62%を占める。漁業生産は特定の諸国に集中しているのである。このなかには、1977年に海洋の分割が行われ、世界的に200海里体制に移行したあとでも高い生産量を維持し、さらには生産の上昇傾向をみせている国もある。これら10か国は、おおむね、広い200海里水域を占有しているか、または200海里水域内に好漁場をもっているか、あるいは両者を兼ね備えている国である。アメリカ、ロシア、中国、インドのような大国は広い200海里水域を占有することになり、また、インドネシアのように多くの群島からなる国も広い水域を確保した。日本も国土は狭いが200海里水域の面積では世界第7位である。
日本漁業は第二次世界大戦による生産低下を1952年までに回復し、その後も漁船、漁法の近代化、漁港、水産物加工、流通設備の整備、大きな需要に支えられて生産を伸ばし、ほぼ漁獲量世界第1位の位置を確保してきた。200海里体制は、他国の200海里水域における遠洋漁業の操業の撤退を余儀なくしているが、他方では日本近海のイワシ資源の増大によって沖合漁業生産が伸びるという結果をもたらし、生産量は1984年には初めて1200万トン台を記録した。海面養殖業生産も1983年に100万トンを超えるに至った。日本漁業は、欧米先進国に比べて、経営体数、漁業従事者数ともにはるかに多い。漁業従事者は、EC最大の漁業国スペインの約10万人に対し、日本は44万人である。20万7000の経営体のうち、おもに自家労働力によって沿岸漁業に従事する経営体が95%。一方、戦前から北洋漁業、トロール漁業、底引漁業、捕鯨業で資本蓄積を進めてきた資本金10億円以上の大資本企業も活動しており、大・中・小経営が並存しているのである。1983年の海面漁業・養殖業の総生産量のうち、遠洋漁業18%、沖合漁業55%、沿岸・養殖漁業27%のシェアであるが、生産額の割合では、それぞれ24%、30%、46%となっており、沿岸・養殖漁業の比重が高いことが特徴である。遠洋漁業の生産量は1973年の400万トン弱を最高に減少をたどり、1979年には半減し、以後、200万トン強が維持されているが、国際的規制の強化によってさらに生産の減退が見込まれる。遠洋漁業に依存してきた大漁業資本は経営の転換を図り、漁業部門から、輸出入、魚類取引などの商業部門の活動に重点を移してきており、その売上げは1980年代に入って全売上げの70%前後という高い割合を占めるようになった。
第二次世界大戦後のソ連の漁業生産の伸びは日本をしのぎ、1950年の162万トンから、1976年には1000万トンと著しい。ソ連は遠洋漁業の増強に努め、大型トロール船などを計画的に新造し、加工設備を船内に設けた1万トン以上のトロール工船も建造して生産を急速に伸ばしてきた。ソ連水産業は、国内の農業・畜産業の不振を補い、国民に動物性タンパク質を供給することを目的として1960年代にさらに振興が図られた。水産物輸出を外貨獲得の一助にすることも目的としていた。サケ、マス、カニなどの増養殖事業にも努力している。しかし、日本と同様、ソ連も200海里体制への移行に伴い遠洋漁業が制約され、1978年以降の生産量も900万トン台で低迷しており、100トン以上の大型漁船を1980年から削減し、とくに100トンから499トンの規模の漁船は1980年の2000隻から1984年には1100隻へと半減させている。しかし500トン以上の漁船では、1984年においても隻数、トン数ともに世界の500トン以上漁船総数の50%、58%を占めている。ちなみに日本のそれは、2.5%、3.4%である。
中国の漁業生産の伸びも著しく、1950年の91万トンから1983年には670万トンへと上昇した。中国漁業では内水面漁業と海藻生産の比重が高く、両者で生産の4割を占めており、伝統的な内水面養殖も発展を遂げている。また海面養殖ではコンブの生産が伸びている。海面漁業も1960年代に漁船・漁具への国家投資が行われ、漁獲量が増大してきたが、乱獲現象がみられて1970年代は生産が停滞、1980年代に入って漸増してきている。
戦後、生産量が大きく変動したのはペルーである。ペルーは1950年に11万トンの漁獲量であったが、沖合いのカタクチイワシの漁場開発と魚粉生産設備の整備がおもにアメリカ資本によって進められ、1962年に日本の生産量を抜いて世界一となり、以後1971年までそれを維持し、1970年には1260万トンを記録した。しかしそれを最高として、1972年から漁獲は大幅に減少し、これが1973年の世界的な飼料穀物価格の高騰の一因となった。その後も減退傾向をたどり、1983年には150万トン弱の漁獲量に低下した。このような変動は自然条件の変化による水産資源の自然的増減によってもたらされたものである。
このペルーの生産減少に対して、隣接するチリでは1970年代後半からイワシ・アジ資源の増加と漁場開発によって生産量を急伸させ、1983年には400万トン台に達して、世界で漁獲量4位となった。
アメリカは、自国の200海里内の好漁場における外国漁船の操業を制限したことを契機として漁業生産が活性化し、1970年代前半まで200万トン台の生産であったものが、1983年には400万トン台に達し、100トン以上の大型漁船隻数も1980年から1984年の間に24%増加させ、200海里体制下の先進国で大型漁船を著しく増加させてきている数少ない国の一つである。
200海里体制は、アメリカに示されるように自国の水域内の水産資源の利用を刺激する作用を果たしてきており、遠洋漁業への依存を高めていた国でも自国水域で操業する100トン以下の漁船は漸増してきている。
[高山隆三]
魚種別生産
世界の主要魚種別生産を、海面漁業生産と内水面漁業生産に分けてみると、前者の生産量が1970年代にほぼ90%を占めているが、後者もそのシェアをこの10年間にわずかながら上昇させてきている。1983年の総生産量のうち、魚類が84%を占めており、その86%、総生産量に対しては72%が海水魚類である。したがって、海水魚類の資源状況が世界の漁業生産量に大きな影響を与えることになる。その他の生産では、総生産量に対し、カニ・エビなどの甲殻類が4%弱、貝類やイカ・タコなどの軟体類が7%、藻類その他が4%、ウナギ類、サケ・マス類などの回遊性魚類が2%強となっている。
海水魚類のなかでは、暖流水域を大回遊するカツオ、マグロの生産は微増しているが、需要の強いマグロ類の資源はほぼ限界に達するまで開発されており、生産が増加しているのはカツオ類である。沿岸・沖合いを大量に群れをつくって回遊するニシン、イワシ、アジ、サバなどの沿岸性浮魚(うきうお)類は海水魚類生産の約50%を占め、これら魚類の生産が世界の生産量に大きな変動を与える。これら魚類の生産量は、1950年には500万トンであったが、ペルー沖のイワシ生産量の急伸もあって、1970年には2100万トンと4倍強に増加した。しかし、その後、自然条件の影響を受けて資源が減少し、1973年には1100万トンに急減した。しかしそれを底として、徐々に生産を伸ばして、1982年、1983年には1700万トン台まで回復、1970年代後半からの総生産量増加に大きく寄与してきている。カレイ、ヒラメ、タラなど、海底に生息して、浮魚のように大きく回遊しない底魚(そこうお)類の生産も、1970年まで急増したが、その後1200万トン前後の生産量で停滞している。エビ類の生産は、日本・アメリカなどの先進国の需要が強く、熱帯産のエビ資源の開発が進み、また養殖が開発途上国においても1970年代後半から行われるようになり、生産量を漸増してきている。イカ・タコ類は1970年代後半以降にも生産を増加させてきている。アルプス以北のヨーロッパ諸国やアメリカではイカ・タコ類消費の食習慣が歴史的に普及してこなかったこともあって、資源開発の余地は残されているものとみられる。
第二次世界大戦後の世界の魚種別生産の推移をみると、全体として1970年以降生産量の伸びが大きく落ち込んだが、とくに底魚類の生産の一部に乱獲が現れ資源状況が悪化し、マグロ資源も限界に達した。一部のクジラ資源には減少から絶滅に瀕(ひん)するものも出てきたことから捕鯨禁止の主張が強まり、1982年の国際捕鯨委員会で、沿岸捕鯨は1986年、南氷洋捕鯨は1985年秋から商業捕鯨を全面的に禁止する決定がなされた。このように水産資源の一部には、需要の強さから、資源の自然的再生産の限度を超えた漁獲が行われ、資源を劣化させている状況がある。
他方、海洋には未開発・低開発の漁場、水産資源があり、たとえば5000万トンから1億5000万トンあるといわれるオキアミ類資源の有効利用技術が開発されれば、漁業生産は飛躍的に増加する可能性を秘めている。それはスケトウダラのすり身加工技術の開発が1960年代に日本の北洋におけるスケトウダラ漁場の開発をもたらし、その漁獲を急上昇させた例からも知られるところである。しかし、そのような技術開発が今日なお出現していないとすれば、現在利用している水産資源の自然的限界を前提としながら、それを合理的に開発・利用することが、食料生産産業である世界の漁業の課題であり、そのためには各国間における協調と生産の調整が必要となる。200海里水域の設定以後、ECでは、本格的に水産資源の保存と合理的利用を企図して、共通漁業政策の策定と調整が行われているのである。
[高山隆三]
水産物の利用
第二次世界大戦後の漁業生産の増大を支えたのは、世界的な人口増加を基礎とする食料としての水産物需要の強さであった。世界の漁獲量のうち食用として利用されるものの割合は、1960年代、70年代初頭では60%台の前半であったものが、1970年代後半には70%前後となり、1980年代には74%程度まで上昇し、年率で3%強の伸びを示している。もっとも、先進諸国では食用需要はほとんど停滞しており、その伸びは主として開発途上国における消費拡大によるものである。
1960年代前半までは、食用に向けられる漁獲物のうち生鮮品で供給されるものの比率は50%であり、保存方法としては旧来からの塩蔵、乾燥、薫製などの比率が20%以上、冷凍が15%前後、残りは缶詰であった。しかし、冷凍施設の整備が進んでくるにしたがって冷凍品の比率が高まり、1983年には31%となり、生鮮品は32%に低下した。すなわち、世界的にみた場合、漁獲量の3分の1が生鮮で供給され、3分の2が加工に向けられ、そのなかでも、冷凍に向けられるものが旧来の加工や缶詰に仕向けられるものを上回る。魚類の保存方法としては冷凍が主となっており、とくに先進国ではその傾向が著しい。1980年にイギリスでは、食用向けのうち塩蔵などに向けられたものは1.4%にすぎず、43%が冷凍に向けられている。しかしフランスでは、83%が生鮮向けで、冷凍向けは3%にすぎない。日本では、生鮮向けが46%、冷凍向けが32%となっており、1970年から1984年までに冷蔵能力は37%伸びている。アメリカでは生鮮品と冷凍品との区別がなく、質的に同一のものとして取り扱われている。生鮮・冷凍向けの比率は約67%、缶詰向けは31%。缶詰向けのシェアが高いことが特徴である。
食料としての水産物の消費のされ方は、各国の漁業生産の歴史と、そこで形成されてきた魚類消費の習慣によって異なっており、先進諸国の国民1人1日当り供給栄養魚貝類タンパク質の量をみると、1978年にイギリス、アメリカ、カナダ、旧西ドイツで2グラム台、フランスで5グラム弱、デンマークが10グラム前後、日本が17グラムで、日本が著しく高く、供給栄養動物性タンパク質のうち魚貝類の占める割合は、イギリス・アメリカで3%台、フランスで6%、日本は45%前後となっている。このような相違はあるにしても、先進諸国では、生鮮あるいは冷凍品という形態で漁獲物が流通する傾向が、冷蔵・冷凍施設と運輸手段の整備によって強まってきている。こうしたなかで1980年代、欧米先進国において、水産物の健康食品としての価値が再評価されてきたこともあって、魚類需要が高まる兆候がみられる。アメリカにおける鮨(すし)の普及はその一例としてあげられるであろう。
漁獲物のうち、魚粉・魚油原料という非食用向けには、食用需要を超えた部分があてられてきた。第二次世界大戦後、とくに1970年までの漁業生産の急速な伸びは、非食用向けの魚粉の生産量も増大させてきたが、1970年代前半の漁業生産の低迷と、漁獲物の食用としての需要が高まってきたことから、1970年代後半から、世界の魚粉・魚油原料向けの総量は、漁獲量が増大してきたにもかかわらず、1900万トン前後で推移しており、したがって、総漁獲量中に占める割合は、1975年の30%前後から、1983年には25%へと低下している。ただし、日本は、イワシの生産量の増加と、飼料・養殖漁業用餌料の需要増大によって、非食用向け水産物量は1975年の236万トンから1984年の455万トンに増加し、その割合も23%から38%へと高まっている。
[高山隆三]
水産物貿易の動向
第二次世界大戦後、水産物貿易は、先進諸国、なかでも、アメリカ、日本のエビ、マグロ、サケ、マスなど高価格魚種への需要を背景とする、開発途上国などからのそれらの輸入と、一方における先進国から開発途上国へのイワシ・サバ缶詰など低価格魚種加工品の輸出とを中心に伸びてきた。
水産物の国際的な取引は、すでに中世ヨーロッパの塩蔵にしん、乾燥たらをはじめ、塩干物が主であり、日本の江戸時代における清国への輸出水産物も、干しあわび、ふかひれ、干しなまこのいわゆる俵物三品をはじめとして、昆布、するめなどの干物であった。水産物貿易においても、その拡大を促したのは、近代における缶詰および冷凍技術の発達であった。第一次世界大戦を契機とする日本の欧米向け水産缶詰の輸出の増大は、北洋におけるカニ、サケ・マス工船漁業の発達を促進し、1935年(昭和10)前後には、缶詰に、魚粉・鯨油・冷凍まぐろ、真珠の輸出も加わって、水産物は日本の五大輸出品の一角を占めるに至ったのである。
第二次世界大戦後の世界の水産物貿易では、冷凍品が主要な形態となり、腐敗性の高いエビを冷凍技術によって国際的商品に仕立てていった。日本も戦後の高度成長による所得の増大によって、エビ、マグロ、サケなどの特定水産物の需要を増加させ、欧米の大部分の国と同様に、1971年には水産物輸入国となり、以後、急速に輸入量・額とも増加させた。額では、1971年以降アメリカに次ぐ世界第二の輸入国となり、1970年代後半にはアメリカを超える場合もあるほどの、アメリカと並んだ水産物輸入大国となった。この急激な輸入拡大には、1977年の世界の200海里水域設定という、水産資源の国際的再分割という事情が作用している。1984年には、ドル表示で1970年の輸入額の約20倍になった。他方、輸出は、同期間に4倍伸びたにとどまっている。水産物輸入量は、1977年に100万トンを超し、また輸入金額も1982年には1兆円台に達した。1984年の水産物輸入数量の82%が生鮮・冷蔵・冷凍品で、加工調製品の割合は数量・金額ともに低い。水産物輸入金額のうちエビのみで3000億円を超え、水産物輸入品目の1位であるだけでなく、1980年代に入って、その輸入額は、日本の食用小麦の輸入額を上回るものとなってきている。
アメリカは、輸入額も増大してきたが、それ以上に輸出の伸び率は高く、輸出額は1970年代後半には日本と肩を並べるようになり、カナダに次ぐ有数の輸出国となってきている。アメリカは200海里体制以降、対日水産物輸出を急増させ、1984年には、日本の水産物輸入においては、数量・金額(円表示)とも、韓国を抜いて第1位を占めるに至った。アメリカは戦前から日本の水産物の主要な輸入国であったが、1977年以後、対日輸出が日本からの輸入を上回り、農産物はもちろんのこと水産物でも対日輸出国となったのである。その品目でも、かつて日本からの輸入品であったサケ・マスを、冷凍・冷蔵品として大量に日本向けに輸出するようになり、1984年の日本の冷凍サケ・マス輸入量の86%がアメリカからのもので、その金額はアメリカの水産物輸出額の約3分の1を占める重要なものである。このようなアメリカのサケ・マス対日輸出の増加は、母川国主義を強め、ロシア連邦と同様に、日本の北洋の公海におけるサケ・マスの漁獲を強く規制しているのである。
[高山隆三]
水産業の現況
現代における水産業は、200海里体制以降、200海里水域内への他国漁船の入漁関係、漁業合弁企業の設立など国際的関係を深めてきている。また先進諸国内部では、漁業生産、加工・製造、流通、消費の各過程の緊密で複雑な関連が発展し、たとえばEC諸国においては、海上における1人の職場が、陸上における5人の職場をつくりだすと見積もられている。これには、漁船の建造と修理、漁網・漁具の生産から、水産加工・製造、冷凍・冷蔵機器の製造、冷凍・冷蔵庫の建設、水産物運搬用のトラック製造、卸売・小売業等々の広い分野が含まれている。
日本では、1983年に水産食料品製造業の従事者4人以上の事業所数は1万1000、従業者数は20万1000人、生鮮魚貝卸売業が1万3000店、従業者数11万6000人、鮮魚・乾物小売業が6万5000店、従業者数17万1000人となっており、漁業に直接的な関連をもつこれらの分野の従業者だけで、漁業就業者を約4万人上回っている。しかし、鮮魚・乾物小売業は店数・従業者数ともに1976年以降減少傾向をみせている。これは、家庭内調理の簡便化が共働き家庭の増加を背景に進んできたことの反映とみられる。魚貝類の摂取量そのものは、外食・高次加工品への消費の移行もあって、ほとんど変化をみせていない。水産食料品製造業は、事業所(従業者4人以上)の総数には大きな変化がみられないが、冷凍水産食品製造業の事業所が1975年から1983年の間に2倍以上の増加を示している。水産物輸送については、1960年代から、鉄道にかわって、荷積み・荷下ろしが容易で、配送に便利で時間短縮が図れるトラックが主役を演じるようになり、主要漁港から消費地市場への出荷は1982年にはトラック輸送によるものが90%を超えるに至った。また一部の高価格の生鮮魚貝類などが、国内で、あるいは海外から空輸されるようになってきている。
[高山隆三]
水産業の役割と課題
水産物は、食料として、歴史的に動物性タンパク質の供給に大きな役割を果たしてきた。第二次大戦後だけをみても、水産業は、世界的な人口増加を支える食料供給の一端を担ってきた。食料としての水産物への需要は、世界各地の歴史的に形成されてきた食習慣によって大きく異なり、先進諸国においても、ヨーロッパ諸国は日本に比べれば、魚貝類からの動物性タンパク質の摂取量は少なく、また畜産物に比べても量的に少ない。そのヨーロッパでさえ、魚貝類タンパク質の供給量をすべて畜産物で供給するとすれば、ヨーロッパの耕地面積の40%にあたる6000万ヘクタールを必要とするという試算が行われている。
このような観点にたつと、水産業は、食料としての動物性タンパク質の供給にとって重要であるだけではなく、地球上の陸地の、さらに限られた農用地の代替という重要な役割を果たしていることになる。日本は1984年に飼料穀物を2000万トン輸入し、加えて70万トンの肉を輸入しているが、魚貝類による動物性タンパク質の供給をかりに畜産物で行うとすれば、さらに2000万トンの飼料穀物の輸入が必要となると見積もられるし、このためには最低でも、日本の耕地面積をはるかに上回る1000万ヘクタールの農用地を必要とすることになるのである。
今後の人口増加と限られた農用地を見通すとき、食料供給源としての海洋と、食料としての水産物の効率的な利用がいっそう強く求められることになる。水産資源の未開発・低開発がある一方、歴史的に早くから開発された漁場では、水産資源の自然的限界を超える過度の利用が、近代以降の漁業生産力の発展と漁業経営間の過当競争によって引き起こされてきた。乱獲による資源の枯渇を防ぐため、各国において漁業生産規制が図られ、国際的にも漁業条約によって水産資源の適正利用を図る努力が払われてきたが、その効果は十分なものではなかった。
1977年の200海里体制という海洋利用秩序の再編成は、水産資源利用秩序を新たに形成させる契機となったのであるが、各国が囲い込んだ200海里水域の水産資源を合理的に利用・管理することは各国の課題であり、利益であるだけではなく、人類の存続にとっての責務ということになろう。そのためには、水産資源の管理と有効利用、その技術開発に加えて、海洋の汚染の防止が、それぞれの国の水産資源の維持にとっても必要であり、国際的な汚染防止協調体制の確立が要請されるのである。
[高山隆三]
『高山隆三他編著『現代水産経済論』(1982・北斗書房)』▽『谷川英一・田村正他著『新編水産学通論』(1977・恒星社厚生閣)』▽『網野善彦他編『塩業・漁業』(『講座・日本技術の社会史 第2巻』1985・日本評論社)』▽『レイ・タナヒル著、小野村正敏訳『食物と歴史』(1980・評論社)』▽『篠田統著『中国食物史』(1974・柴田書店)』▽『European Communities-CommissionThe European Community's Fishery Policy (1985, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg)』
改訂新版 世界大百科事典 「水産業」の意味・わかりやすい解説
水産業 (すいさんぎょう)
水界の動植物を生産対象として行われる漁業と養殖,その生産物を原料とする水産加工,生鮮および加工水産物の輸送・保管・流通,以上の各事業分野を包括するものとして水産業という用語がある。漁業,養殖業のいずれも,その生産物は生物であるところから,品質の変化が大きくかつ急速であり,品質の劣化や腐敗によって商品としての使用価値を損ないやすい性質をもっている。このため,加工や輸送・保管過程が漁業・養殖の生産過程に劣らず大きな経済的意味をもち,かつ相互に緊密な関係を結んで全体として他産業から独立した一つの産業システムを形成している面がある。漁業(一般に養殖業を含む名称にもなる)という用語のほかに,とくに水産業という総称が用いられるゆえんである。漁業発展の歴史(とくに第2次大戦前まで)については〈漁業〉の項に詳しいので参照されたい。
→水産加工
世界の漁業生産の推移
FAO統計は1938年の世界の総漁業生産量を2110万tとしており,この程度が第2次大戦前の最高の水準と推定される(表)。戦争の影響で生産の停滞さらには低下が起こるが,その回復は比較的速く,50年には戦前水準の2110万t,55年2890万t,そして60年には4020万tになり,その後もほとんど直線的な生産増加を続けて70年の生産量は6558万tに達する。世界生産量が戦後初めて減少をみせたのは1969年で,これ以降,長期的には増勢を維持しているとはいえ非常に緩やかなものになり,かつ不規則な年変動を示す不安定なものに変わってきている。1960年代の生産量の平均伸び率は5.3%と非常に高かったのが,70年代には1.2%に低下し,世界人口の伸び率1.8%を下回るものになってしまった。一つには,既開発水産資源の自然的限界性の発現によるが,同時に資源利用に対する国際規制の強化,国際通貨不安や73年,79年と2次にわたる石油危機の発生,さらには200カイリ水域制の国際的定着といった社会・経済環境の激変が,漁業生産の成長を世界的規模で抑制し,かつ変動させるようになったためである。
世界の漁業国のなかで際立って生産量の多い国は日本とソ連である。81年の総生産量7476万tのうち日本1066万t,ソ連955万tで,両国だけで全体の27.1%を占める。3位は中国で461万t,以下10位まではアメリカ377万t,チリ339万t,ペルー275万t,ノルウェー255万t,インド242万t,韓国237万t,インドネシア186万tという順になる。日本の漁業生産量は,第2次大戦中の大幅な減産状態から再出発して急速かつ持続的な増加をみせ,1976年には1066万tに達したが,ソ連の生産の伸び率はそれ以上に大きく,1948年の149万tから76年の1013万t(同国の最高記録)へと日本とほぼ同等の水準まで増大した。70年代の増勢からみて,77年の200カイリ制への移行がなければ,ソ連はおそらく日本を抜いて世界第1位の水産国になっていたに違いない。日本は世界有数の遠洋漁業国であり,1976年の総生産量の33%を外国の200カイリ水域における漁獲に依存していた。しかしソ連は日本以上にその傾向が強く,世界漁場に向けての遠洋漁業の拡大を通じて同国の急速な生産増加を図ってきたのである。100トン以上の大型漁船についてみると,ソ連の保有隻数は日本を2,3割上回る程度であるが,トン数のほうは3倍以上の規模であり,世界の総トン数の約4割を占める。しかも200カイリ制以降もその態勢を変えていない。
戦後,日本はおおむね世界第1位の漁業生産を続けてきたが,1962年から71年までの10年間はペルーが700万tから1000万t台の生産をあげ,日本を追い越した。これは同国沿岸水域のカタクチイワシ資源の著増によるもので,日本やソ連における近代的な生産技術と大量の漁獲手段投入によって構成された生産力とは質を異にする。したがって,漁況の変化によって同魚種資源が減退すると,漁業生産のほうも72年以降,急激に減少してしまった。第3位の中国は,その広大な内陸部における淡水魚生産(129万t,1981),および海藻生産(139万t,同)の比重が大きい点に特徴がある。同国の自然条件と人口数から考えて将来の飛躍が予想されるが,FAO統計に見るかぎり,80年代前半まではまだその明確な兆候を現していない。上記の国以外は,各国それぞれの年次変動を見せながら,総じて発展途上国の生産が先進国の伸びを上回る形で推移し,ことに1970年代は,デンマークを除いてアメリカ,カナダ,ノルウェー,スペインといった先進資本主義国の漁業生産はいずれも停滞状態に陥った。
1977年の200カイリ制への移行は,そうした各国漁業の推移のなかで,水産資源の国際的再分割という様相を色濃く現している。すなわち,77年以降顕著な減産を示したのがソ連を筆頭にノルウェー,スペイン,イギリスといった遠洋漁業国であり,逆に顕著な増産を示しているのはアメリカ,カナダ,メキシコ,アイスランド,フィリピン,インドネシアといった沿岸漁業国である。他方,世界の総漁業生産量は1970-75年の平均年率-0.32%の停滞から,75-81年には平均3.55%の伸びに転じているから,結局200カイリ制はそれが漁業生産に抑制的に働いた面よりも,沿岸・近海漁業に新たな条件と刺激を与え促進的に作用した面のほうが,世界全体としてはより大きかったといえるであろう。
水域別生産および漁獲可能量
世界の漁業生産の大部分は海面からの漁獲である。中国のように内水面漁業の比重の大きな国もあるが,世界全体の内水面漁業生産は11%(1981)にすぎない。また,養殖生産の比重は,日本のように盛んな国でも数量で9%,金額で19%である。なお日本の漁業種類別生産高をみると,1973年以降遠洋漁業が激減し,沖合漁業が伸びている(図)。海面漁業の主要な生産水域は北半球であり,太平洋および大西洋の北部水域の生産量は世界総量の49%に達する。とくに日本周辺水域は漁場豊度が際立って高い水域で,ソ連・韓国・中国を含む太平洋北西部域の海面漁業生産量は全世界の30%を占める。これに次ぐのが,ヨーロッパ諸国の伝統的な漁場の北海をはじめとする大西洋北東部域で,その生産割合は17%である。以上の2水域以外では,太平洋南東部(10%)と同中西部(9%)の生産が大きい。前者はチリ,ペルーにおけるマイワシ,カタクチイワシ,アジの特定魚種に集中した大量漁獲によるものであり,後者はインドネシア(187万t),フィリピン(174万t),タイ(165万t),ベトナム(80万t)といった比較的生産規模のそろった多数の国が,多種資源を対象にこの水域を集約的に利用しているところに特徴がある。
漁業による資源開発の度合は各水域によってさまざまであるが,世界全体として将来どの程度まで漁獲を伸ばすことができるかを推定した多くの試算がある。それらの推定値は,理論と方法の違いにより,5000万t程度から20億tまで非常に大きな差異があるが,そのなかの一つ,FAOが計測した1976年基準の漁獲増加可能量は次のとおりである。すなわち,底魚類1500万t,小型表層魚(とくにカタクチイワシ資源の回復に関係する)2500万~3000万t,その他魚種(主としてカツオなどの大型表層魚)200万t,頭足類(主として外洋性のイカ類)1000万~1億t余,中層魚類(ハダカイワシなど)おそらく1億t,オキアミ類5000万~1.5億t余,その他甲殻類100万t,淡水魚類500万t,養殖2000万~4000万t余であり,以上を合計すると2.3億~4.45億t余になる。
この推定値からわかるように,漁獲あるいは利用加工上の技術的限界や経済的条件等を捨象し,かつ単なる物量(つまり人間生存のための栄養量)として水産資源からの生産可能量をとらえるのであれば,現在の食用向け数量が5000万t台であることからみて,当面はまだ漁業生産の絶対的限界を問題にしなくてもよいであろう。しかし,現在の消費・技術・経済の諸条件のもとで生産対象となりうる魚種と漁場は限られており,漁獲努力がそれら特定の資源に集中するため,その自然的限界から起こる乱獲問題が世界の各地で発生している。一方における資源の未開発ないし低開発と,他方における過大開発とが混在しているのである。そうした乱獲による資源の壊滅や漁業経営の破綻(はたん)を防ぐため,多くの国際漁業条約が国家間に結ばれ,それに基づく資源管理機関が設置されてきた(〈国際漁業〉の項参照)。国際捕鯨委員会(IWC),北太平洋オットセイ委員会(NPFSC),太平洋オヒョウ国際委員会(IPHC),北西大西洋漁業国際委員会(ICNAF,1979年北西大西洋漁業機構NAFOに改組),全米熱帯マグロ類委員会(IATTC),大西洋マグロ類保存国際委員会(ICCAT)等である。しかし少数の例外的な成功があるだけで,多くの場合,資源の適正利用の実現には至らなかった。1977年からの200カイリ制によって,それらの国際的な機構はほとんどみな事実上の変質を迫られ,世界は今新しい資源利用秩序を形成する過渡期にある。
→水産資源
水産物の利用配分と輸出入
漁業生産物の利用形態のうち魚粉・魚油等の非食用向け数量は,1970年代初めにペルーのカタクチイワシ減産が影響して2000万tの水準に低下した後,72年以降は多くても2300万t止りで10年間にわたり横ばいを続けている。資源の自然的増大による漁獲増が食用需要を超えた分だけ非食用に回るといった面が強く,その数量の変動は多分に自然依存で受動的である。それとは対照的に食用向け数量は,1960年代,70年代とも年率で3%近くの増大を続けた。もっともその内訳を国別に見ると,先進国の場合は微増,とくに70年代はほとんど横ばいで,全体量の拡大傾向を支えたのは,60年代3%強,70年代5%強という発展途上国における顕著な食用水産物仕向けの増大である。また食品形態別では生鮮品の横ばいに対し,塩・干・薫製品,缶詰,冷凍品の加工水産物が増加しており,とくに冷凍品の増加傾向が目立つ。
途上国における食用水産物の生産増加は,一つには国内消費の増加によるけれども,より大きな要因として先進国への輸出増加がある。国際貿易の流れとしては,途上国から先進国への高価格魚(エビ,イカ,タコなどの冷凍品)の輸出,先進国から途上国への低価格魚(サバ,イワシ缶詰等)の輸出が伸びてきた。このことを最も典型的に展開したのが日本である。日本は高度成長のなかで生み出された高い国際的購買力と,水産物に対する強度の選択的需要とを背景に水産物輸入を70年代急激に拡大し,さらに200カイリ制による資源の国際的再分割がその傾向を助長した。ためにその輸入額は世界第1位を続けてきたアメリカに追いつき,それを凌駕(りようが)するほどとなった。82年の水産物輸入額(FAO統計)は日本40億ドル,アメリカ32億ドルであり,2国だけで世界総額の44%を占める。他方,輸出額のほうはもう少し分散的で,カナダ13億ドル,アメリカ10億ドル,デンマーク9億ドル,ノルウェー9億ドル,日本8億ドル,アイスランド5億ドルという順位になる。このうちアメリカとカナダは,200カイリ制以降,対日輸出によってその実績を急激に伸ばしてきたものである。なお日本の水産物輸入は,その規模が大きく,かつ魚卵,刺身材料,塩サケといった他国にない独特の商品需要が多いことから,相手国の水産業に特殊に強くかつ不安定な影響を及ぼしかねないところがある(以上については〈水産物貿易〉の項参照)。
日本の水産業
日本漁業は第2次大戦後の戦後インフレと食糧増産政策のもとでいちはやく生産力を回復し,外地引揚資本や転換資本の参入もあって,漁船数は1948年に早くも戦前の最高水準にもどったとされている。しかし,この敗戦直後の〈漁村ブーム〉は,〈経済安定九原則〉に基づく49年からのデフレ政策の強行が大衆購買力を抑制するなかで,たちまち消滅する。さらに50年の朝鮮戦争の勃発は資材価格の高騰を引き起こし,魚価低迷と相まって漁業経営を強く圧迫した。〈以西底引網漁業の三割減船整理〉(1949)や小型底引網漁業の減船整理をねらった〈五ポイント計画〉(1951)に代表される漁業の縮小再編成へ水産政策の基調が大きく転換していく。漁村の封建制打破をねらった〈漁業制度改革〉(新漁業法の施行は1950年)も一つにはそうした経済状況に拘束されて,総じて新しい飛躍的な漁業生産力を生み出すようには働かなかった。1950年前後の漁業停滞からの脱出は,講和発効(1952)による操業禁止ライン(いわゆるマッカーサー・ライン)の撤廃,北洋をはじめとする漁場の外延的拡大によってもたらされた。沿岸・沖合漁業における労働・資本の過剰投入と経営窮迫を,〈沿岸から沖合へ,沖合から遠洋へ〉という玉突き型の漁業生産力展開によって解決するという政策が導入され,同時に沿岸漁業については養殖業を発展させて集約的な漁場利用の実現を図る,いわゆる〈構造改善政策〉が実施された。漁業生産量は,敗戦の年の1945年に182万tまで減少し,戦前の最高量(433万t,1936)の1/2以下になったが,51年には429万tとほぼ戦前最高水準に回復,52年には463万tと上回った。上記の遠洋化や養殖化を軸とする展開は,戦後の新たな生産力段階を意味するもので,以降漁業生産量は1973年の第1次石油危機の年の1000万t水準まで,ほとんど直線的な伸びを示す。
戦後の水産物市場は,食用水産物消費量の面では実は1950年に早くも戦前の最高水準を超えていた。戦後の農地改革が生み出した農村における食用水産物市場の拡大がその背景になっており,その増勢は60年代後半まで続く。高度成長期の水産業の展開において,農村市場の役割が相対的に大きいのは,その前期である。その全期間にわたり,かつ後期になるほど大きな影響を与えたのは,人口の過密化を進めた都市の水産物市場であった。都市家庭における生活様式の急激な変化が基になって,水産物の消費形態を変え,流通・輸送・加工から,さらには生産過程にわたる水産業全体の構造的変化にかかわっていった。そうした変化の主要な面を列記すれば次のとおりである。(1)個人単位の選択的消費の進展および家庭内調理を省略する簡便化の追求。その結果として,購入水産物の多様化と高価格化。(2)商品流通における冷凍魚の増加(六大都市中央卸売市場において生鮮品の入荷量がしだいに減少し,1972年以後は冷凍品と加工品のほうが多くなる),および中央卸売市場以外のいわゆる〈場外〉流通の増大。(3)輸入魚の急増(1971年からは輸入額が輸出額を上回るようになった)。(4)鉄道輸送からトラック輸送への転換(東京市場への入荷量のうち,トラックによるものが鉄道によるものよりも1965年以降多くなり,81年には94%に達する)。(5)大部分の食用魚生産者価格の高率な上昇,およびそれとは対照的な特定多獲魚価格の低位安定した推移(この価格差を経済的動機として,1960年代後半から給餌養殖業が発達する)。
2次にわたる石油高騰,低成長経済への移行,そして200カイリ制の定着は,高度成長期の漁業発展を支えてきた三つの主要な条件,魚価の高騰,低く安定した燃料油価格,そして世界漁場への外延的拡大をすべて消滅させた。日本の場合はソ連と異なり,200カイリ制以降も1000万t台の生産水準を保持しつづけているとはいえ,それはマイワシ資源の増大期と偶然に重なり,銚子~北海道海域を中心に300万tもの漁獲をなしえているからであって,安定した生産の持続が将来とも保証されているわけでは少しもない。石油危機以降,慢性化している漁業全体の経営窮迫から抜け出すために,長期の政策課題として,日本周辺水域の合理的資源管理を基礎とする,漁業構造の縮小再編成を迫られている。
執筆者:長谷川 彰
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「水産業」の意味・わかりやすい解説
水産業【すいさんぎょう】
→関連項目水産資源
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水産業」の意味・わかりやすい解説
水産業
すいさんぎょう
marine products industry
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新