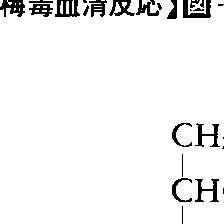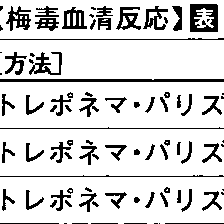改訂新版 世界大百科事典 「梅毒血清反応」の意味・わかりやすい解説
梅毒血清反応 (ばいどくけっせいはんのう)
serological tests for syphilis
STSと略す。抗原抗体反応の原理を用いて被検者血清から脂質抗原に対する抗体(レアギン),または病原体のトレポネマ・パリズムTreponema pallidum(TPと略す),およびその構成成分に対する抗体を検出し,梅毒感染の有無の診断の助けとする検査法の総称。1901年,J.ボルデらは彼らが開発した補体結合反応の原理を用い,梅毒の診断を試みたが成功しなかった。05年E.ホフマンらによって病原体のトレポネマ・パリズムが発見されると,翌06年A.ワッサーマンらは,それを多く含むと思われた梅毒胎児肝臓の食塩水抽出液を抗原として,補体結合反応を行い,患者血中の抗体を検出してその診断に成功した。この方法はワッセルマン反応として有名になり,梅毒の血清学的診断法の代名詞のように使われた。その後,病原体と無関係と思われる正常ヒト肝臓,ついでウシ心臓のアルコール抽出液がこの反応に有効な抗原となることがわかり,コレステロールを添加して反応性を強めたウシ心臓の抽出液(リポイド抗原)が長く使われた。また方法の面では,操作が複雑な補体結合反応から,簡便な沈降反応(1907),さらに凝集反応(1943)形式のものが考案され,実用化されるようになった。このころまでには,考案者の名をつけた多数の検査法が開発されている。1940年代に入るとパングボーンM.Pangbornは,ウシ心臓から新しいリン脂質,カルジオライピンを取り出し,これに適当な比率にレシチン,コレステロールを混合すると,すぐれた抗原が得られることを見いだした(1941)。この抗原はリポイド抗原と区別して脂質抗原という。これを契機にVDRL(ガラス板)法,梅毒凝集法,RPRカード法,緒方法等の新しい方法が開発・実用化され,従来の方法もこの抗原に合うよう改変された。日本では,同じ検査試料を用いてこれらの方法の優劣の検討がなされ,ガラス板法,カーン法,梅毒凝集法,緒方法等が標準的なものとして用いられるようになった。 病原体と直接関係の低いリポイド抗原,脂質抗原を用いた方法で,なぜ梅毒に高率の陽性反応が得られるかは未解決の部分が多い。反面,この抗原を用いた反応には,梅毒以外にも結核症,マラリア,ハンセン病等の他の多くの病気にも高率に,健康者にすら陽性の反応を示すという問題があり,脂質抗原で改善されたにしても,根本的な解決はいまだなされていない(結核等による陽性の反応は少なくなったが,ハンセン病等では依然として陽性を示し,ヒロポン,麻薬常用者も陽性を示すことがわかった)。このような現象を生物学的偽陽性反応biological false positive reaction(BFPRと略す)というが,典型的な症状を示さない現在の梅毒の診断の最も大きな問題点となっている。しかし,これは病原体を抗原として用いれば避けうることでもあるから,梅毒の血清反応が開発された早い時期(20世紀初頭)からその試みはあった。しかし,トレポネマ・パリズムの培養は今でもかなり困難であるが,当時は2期の梅毒患者の皮膚発疹から取った病原体を抗原に用いており,これには患者の抗体がすでに結合していたため,確実な成績は得られなかった。その後,ウサギ睾丸に植えついだ病原体を取り出し,一時的に生かしておいたものに抗体と補体を働かすとその運動性を失うことを応用したトレポネマ・パリズム不動化試験(TPI,1948)が考案・実用化され,この方法はアメリカでの診断法の標準的なものとされている。これをきっかけとしてトレポネマ・パリズムを抗原とした各種の方法が開発された。日本では,抗原成分を血球に吸着させたものを用いた受身血球凝集反応の原理によるTPHA法が実用化されている。
現在,日本では,脂質抗原を用いるガラス板法,梅毒凝集法,カーン法,RPRカード法,緒方法のうち2~3種の方法を組み合わせ,これにTPHA法,免疫蛍光法の原理によるFTA-ABS法のどちらかを併用する。脂質抗原を依然として用いる理由はいろいろあるが,その方法が簡単なことと,感染初期にTPHA法が陽転するまで脂質抗原による方法より時日を要することなどが挙げられる。なお,いったん感染したヒトでは治療してもTPHA法は原則として陰性となりにくいので,この反応が陽性であることと他への感染能力をもつこととは別の問題でもあるが,治療をどこでやめるかの判断も難しい。
執筆者:木村 一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報