精選版 日本国語大辞典 「時間」の意味・読み・例文・類語
じ‐かん【時間】
(2)「哲学字彙」(一八八一)に至り、time に「時間」、space に「空間」をあてて、「附音挿図英和字彙」の再版(一八八二)では、space と time の双方の訳語になっている。「改正増補和英語林集成」(一八八六)では、長さや区切りを表わす場合には「時間」、ある刻限を表わす場合には「時刻」という区別が見られる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
世界におけるすべての変化および無変化において保持されている何ものかを時間と呼ぶ。一面から言えば,時間はまた人間と外の世界との接点に現れるものでもある。例えば,私は〈今〉,外の世界を見,聴き,感じている。それは〈過去〉につながり,また〈未来〉につながる。そうした人間と世界の接点に示される〈今〉〈過去〉〈未来〉の三つの様態を貫くものが時間である,と定義することもできよう。もっとも,過去,現在,未来という時間の三態のどこに主眼点を置くか,という問題は時間をめぐる重要な論点の一つである。例えばインドの仏教経典では,この三態の順序はほとんどつねに過去,未来,現在として取り上げられるが,それは,現在のみが時間としてリアルにとらえられていることを示しているとみられる。そこでは未来も過去も,ともに現在のために付随的に考えられた時間態であると考えられる。こうした発想は,洗練された形では西欧にもニーチェの〈永遠の今ewiges Jetzt〉というような概念として登場するが,ニーチェのそれもインド仏教の影響という点から考えられるとすれば,やはりインドに特徴的である。
過去,現在,未来の順序に固執するところからは,時間の流れ,もしくは〈流れる時間〉が出現する。しかも流れる時間では二通りの〈流れ方〉を想定できる。その第一は,直線的な時間の流れ方であって(より正確には〈線分的〉と言うべきであろうか),ユダヤ・キリスト教的な世界観のなかに特徴的なものとして知られている。始点(神の手による世界創造)と終点(最後の審判)の間に張られた一直線の時間の流れの上に,この世界の変化が一つのドラマとして展開される,と考えられているからである(終末論)。これに対して,インドやギリシアでは,時間は流れても回帰的であり,構造としては螺旋(らせん)的なモデルで把握できる。それは自然界のなかに起こる事象の繰返し(天体の運行,動植物の生活史,季節の循環など)を土台にして時間感覚が築かれたことを示している。ギリシア神話の神でのち〈時〉と結びつけられたのはクロノスであるが,それは,天空の神ウラノスと大地の女神ガイアの子どもとして生まれている。自然(天と地)の周期変化が結果として時間と結び付いた好例だろう。それは〈計時〉方法にもなる。正確に繰り返される周期変化を標準にして,他の変化や無変化をその標準との比較によって測るのが計時であるが,多くの場合天体の運行がその始まりを構成する。
仏教的な時間のもう一つの特徴は〈無常〉である。この世界のいっさいは〈諸行無常〉,変化し定まらぬ。その意味では,これは恒常的な世界の否定ではなく,むしろ,変化する世界の根元を積極的に表現した言葉と解すべきなのかもしれない。ギリシア的な構造のなかでは,いっさいの表面的な変化の背後に根源的に不変なるものを想定したパルメニデスに対して,火をいわばエネルギーとする変化こそ世界の本質としたヘラクレイトスの思想が,インド的な無常に相当するかもしれない。
時間論を(空間論とともに)詳細かつ体系的に仕上げたのは,ギリシア思想の影響を受けているにせよ,中世ヨーロッパのスコラ学においてであった。それはアウグスティヌスの時間論を下敷きにしているが,そこでは,日常的な時間の三態から時間を解きほぐしていく間に数多くのアポリア(難問)が生じてくることが示される。例えば,〈今〉はどうしてリアルと言えるのか。過去は〈もはやない〉ものであり,未来は〈いまだない〉ものである。〈もはやない〉ものと〈いまだない〉ものとの接点に,〈今〉は一種の通過点として存在するのか。時間はいかに分割できるのか。そもそも,時間はどこにあるのか。アウグスティヌスはそうした問題を解く鍵を人間の魂(精神)に求めた。精神こそ,みずからのうちに過去,現在,未来を統一的に把握し,永遠のなかに分割された(数え上げられた)時間間隔を把握し,時間の持続を把持するものとして考えたという点で,彼は〈心理主義〉的時間解釈の出発点をなすと考えられる。
スコラ学では永遠を神に帰するが,永遠はその意味では,時間性の延長ではない。むしろ,時間(存在,持続,変化を示すための)を超えて認められなければならない。それは〈流れるfluens〉ものではなく,〈とどまるstans〉ものである。さらに,こうした超時間的な存在様態をもつ神と,時間的な存在様態しかもたぬ世界ないし人間の中間に,橋渡しとして〈永代aevum〉なる概念が取り入れられている。またこの点は,時間が被造かどうかの問題にも連なる。トマス・アクイナスは,世界の創造は〈時間とともにcum tempore〉行われたと考えており,〈時間においてin tempore〉創造が行われたものでないことを強調して,神の超時間性を強く主張した。
自然科学的な時間概念はニュートンの〈絶対時間〉と〈相対時間〉の区別(これは空間にも並行的に適用される)から始まったと言われる。確かにニュートンはこうした概念を立てて区別したが,それは,必ずしも,現在われわれが〈科学的〉文脈で論ずるような概念と同じではなかった。ただ,後世この概念が,時間の問題を論ずるためにはしばしば援用されるようになったことは事実である。例えばニュートンの代弁者S.クラークとライプニッツとの著名な論争のなかでもニュートン的時間とライプニッツ的時間の対立は鮮明である。この論争では,ニュートン的時間は,事物の存在や変化とは独立に措定されるべきものとして主張されており,ライプニッツ的時間は,事物の生起する順序関係の結果として構成されるものと主張されている。
近代西欧哲学の中心的存在とされるカントは,この二人の先哲の立場のどちらをも採らず,第3の道を用意した。彼は,人間の認識の〈形式Form〉(カテゴリー)としての時間概念や空間概念を提案した。人間は,いわば時間と空間という枠組みのなかでしか,外界の認識を行うことができないとされるのである。
このように,近代西欧哲学のなかでは,時間は,世界の存在の形式か,世界の存在を支える枠組みか,人間の認識の形式か,いずれにしても人間のいきいきとした〈生〉そのものとは無関係な広域的概念になりつつあったが,それを人間の生の様式へ引き戻そうとしたのが,19世紀末以降のベルグソンによる〈持続〉やフッサール,ハイデッガー,サルトルらの現象学的な〈時間性〉の提案だった。さらに20世紀初頭における相対性理論と量子力学の誕生は,時間概念に決定的な新しい展開を与えた。相対性理論では,絶対時間や絶対的同時性が成立しないことが明らかになった(そこから〈双子のパラドックス〉が生まれる)ばかりではなく,それまで空間と別個の座標軸を与えられていた時間が,空間と独立に扱われるべきでないという新しい事態を迎えたし,量子力学では,エネルギーとペアとなって非可換な2量を構成する時間(物理的観測量としての)が,ハイゼンベルクの不確定性原理を満足すべきものであることが明らかにされ,そこから,一種の〈多時間〉的な発想も生じた。
時間をめぐる現代的諸問題は数限りなくあると言えるが,そのおもだったものをいくつか挙げておこう。
(1)時間の方向性の問題。とくに,エントロピーの増大,もしくは不可逆的な現象との絡みでしばしば問題になるが,一般に〈時間の可逆・不可逆〉を論ずることは無意味であるように思われる。不可逆的時間が前提にされているからこそ,現象の可逆・不可逆が言えることは論理的に証明できるはずだからである。
(2)歴史的時間の問題。とくに,進歩史観的な時間概念は,依然として広く受け入れられているが,生命史における進化の側面も含めて,世界が時間とともに啓(ひら)かれて行くというような〈進歩〉の観点が,どれだけ維持できるのかが問われている。
(3)社会的側面にかかわる問題。ここでは近代社会における〈時間感覚〉の喪失が指摘されよう。人間の生はかつては日常性と非日常性の交代によって,時間的な意味と構造が与えられていたが,日常のなかに非日常を構成するための最も重要な死や祝祭が日常生活から遠ざけられ,一方では,性を含むあらゆる非日常的なことがらが,メディアと制度の〈発達〉のために日常化されるに及んで,近代社会における生は,アトム化,均質化し,時間的分節構造を失いつつある。こうした状況が,人間の〈時間性〉をどのように変えていくか,という問題は,今後ますます重大になるだろう。さらにこの問題は個人の生の構造のみならず,人類全体のそれにもかかわってくるはずである。
(4)心理的時間の問題。客観的で共通な時間を前提に動いている近代社会のなかで,人間の心理的時間のもつ個別性や特殊性をどのように評価するか。こうした点は,従来まったく別の観点から論じられた問題にもつながってくる。例えば,工業社会にあっては,仕事が必要とする〈時間〉は基本的に悪である。その時間は短ければ短いほど善である(それが能率ということの一つの面である)。しかし,農業社会では明らかにそうではない。生物が種子から実りをもたらすまでの時間は,絶対に必須のものである。それを認めるという評価系は,工業社会のそれと相反する。生命と時間の問題はこうしたところにも登場する。また,(達成)/(時間)という分数表現ではなく,(時間)/(達成)という分数表現で表されるような評価系が考えられるのではないか,という提案もありうるだろう。
(5)共時性と継時性の問題。継時的秩序は,共時的秩序と同型であるか,という問題意識は,結局は歴史と文化とは同一の構造をもつか,という問いに帰着するが,人間活動と時間性とのかかわりのなかでも,興味深い問題である。
こうした点を振り返ると,時間の問題は,およそ人間と世界にかかわるあらゆる問題の起点であり,一方で不易の問い(時間とは何か,過去,未来,現在の区別とは何か,時間は実体的存在であるか,など)が繰り返し登場する主題であると同時に,他方で,優れて現代的,社会的な問題を生む宝庫でもあると言えよう。
→空間 →暦(こよみ) →時刻
執筆者:村上 陽一郎
われわれは暦や時計によって経験の流れを〈勤務時間〉と〈休み〉,あるいは〈播種期〉〈除草期〉〈収穫期〉といった意味をもつ単位に分割している。時間は,分割された意味単位とそれらのつながりとして社会的に形象化される。形象化の仕方は社会によって異なるが,社会的に共有され,個人の外にあって個人を拘束する。社会組織は,一つの劇の中の〈幕〉や〈場〉のように分割された意味単位の中で諸個人に割り当てられる諸役割の連関として形成され,分割・構造化された時間においてのみ具体化される。構造化された時間にとらえきれぬ自己の経験の多方向の流れである〈生きられた時間〉も,移ろいながら連続する諸意味単位・諸役割の束として〈現在〉と〈自己〉を意味づけてはじめて成立する。
民俗社会の時間の意味単位は,具体的活動や労働の一区切りを意味内容としており,近代社会において支配的な数量的意味しかもたぬ単位(秒,分,時間など)は顕著でない。東アフリカの牧畜民ヌエル族では,一日の時間の経過を示しできごとの時刻を参照する時計は,数量化された時計や太陽の位置ではなく,牛舎から牛を出す-搾乳-牛の放牧-ヤギや羊の搾乳-牛舎の掃除-牛を牛舎に戻す,などの一連の牧畜作業の区切りからなる〈牛時計〉であった。また民俗社会の暦の多くも,農事暦のように作業単位からなり,数量的な日付をもたぬ暦もある。例えば,〈畑の伐採の月〉は作業に応じて伸縮し,〈雨の降り始める月〉は雨季になって始まる。これらの時計や暦の意味単位は,作業単位間の重複の禁止や労働の禁じられる祭りによって分割される。
時間の形象化は,〈振動する時間〉と〈不可逆的時間〉に大別できる。〈振動する時間〉(E.リーチ)は,二つの意味単位の交替反復による時間形式であり,〈昼〉と〈夜〉の交替が典型である。この〈昼〉〈夜〉は,自然的時間というより,二分した意味単位間の質的差異化による社会的形象であり,労働する〈昼〉の〈俗なる時間〉に対し,労働の禁じられる〈夜〉は,恐怖と快楽の支配する〈聖なる時間〉となる。〈振動する時間〉においては,意味単位は分割によって部分化されず,それぞれ一つの全体として他方と対立している。それに対し〈不可逆的時間〉は,分割によって部分化された意味単位が有機的に結ばれた時間形式である。その典型は人の一生だが,それも自然的時間というより,〈乳幼児〉〈子ども〉〈成人〉〈老人〉〈死者(祖先)〉など,社会によって異なる意味単位からなる社会的形象である。意味単位間は,農作業単位などと同様に,隔離や禁止の伴う儀礼(〈聖なる時間〉)によって区切られる。その間の移行は,流れ作業のように不可逆であり,それぞれの単位は不可欠だが一部分としての意味しかもたない。
ヌエル族の〈牛時計〉が通用するのは,共同体の中で共有されている限りであり,作業の区切りの異なる他の共同体や農耕民とは〈牛時計〉を共有できない。共同体内での時間に比べ,共同体間での時間は,具体的活動の意味単位がうすれ天体の運行や数量的な,共通化しやすい単位によって形象化される。
共同体内の時間の様態は社会形態の違いによって異なる。離散集合を繰り返す小集団からなる採集狩猟民社会では,〈昼〉と〈夜〉,〈雨季〉と〈乾季〉などの〈振動する時間〉が支配的であり,意味単位のそれぞれはその場での生の全体を表す。そこには人の一生を超えて存続する親族集団もなく,〈取返しのつかない〉時間の流れもない。農耕社会において,分割され部分化された農作業単位による形象化,数世代にわたり存続する生産関係である親族集団の組織化,および〈貯蔵〉の出現によって,〈不可逆的時間〉が優勢となる。また交易の発展に伴い,共同体間の時間も,例えば共同体の外で定期的に開かれる市などによって形象化され,礼拝や巡礼によって形象化される信仰的時間も現れる。そこでは,農作業単位による時間,市による時間,礼拝による時間といった〈複数の時間〉が存在しうるが,それらは次元の違う時間として明確に区別され,共同体内時間と共同体間時間が峻別されている。
近代市民社会では,〈数量化された不可逆的時間〉が支配的となる。数量化された時間は,近代以前においても共同体の外にいる商人たちによって貨幣市場経済での〈利潤〉の計算に用いられていたが,貨幣とともに共同体内から排除されていた。共同体の解体と市民社会の成立に伴い,貨幣が共同体内に浸透して交換の単一的基準となったと同じように,〈商人の時間〉である数量的時間も,共同体の内と外の境界を破り〈複数の時間〉の質的差異を無にし,社会全域の単一的な時間の基準となったのである。
執筆者:小田 亮
現代人は公的な生活においては均質的で直線的な時間のなかで生きている。われわれが時間の飛躍や境界を意識するのはせいぜい時差を経験する海外旅行のときぐらいである。しかしながら私的な生活においてはわれわれは必ずしも均質的な時間のなかでだけ生きているわけではなく,密度の濃い時間と薄い時間があり,また時間はしばしば回帰する。1年の終りには忘年会を開いてその年のすべてを清算して,われわれは新しい気持ちで新年を迎える。このようにわれわれは直線的な時間意識と回帰的・円環的な時間意識との二重の時間意識のもとで生きている。ところで世界史の全体を眺めてみるとき,どの地域のどの民族においても円環的な時間意識が生活の大きな枠となっていた。にもかかわらず現在,世界のほとんどの国において公的には西暦紀元を軸とする直線的時間意識に基づいて生活が営まれている。それは何よりもまず,11,12世紀に西欧において時間観念の大きな社会的転換が起こったことに起因するものなのである。
11,12世紀以後の西欧でユダヤ教に発するキリスト教的な直線的時間意識が公的生活を規定する以前のゲルマン世界においては,円環的な時間意識が支配的であった。ゲルマン人が時tið,timi(time)というとき,そこには時間の正確な計測はみられず,季節やかなり長い時の経過が示されていた。tiðはのちに英語のtide(潮の干満)につながってゆき,年ár(year)も年ごとに繰り返される収穫の意味であった。古ゲルマン人の時間意識は具体的つまり人間的であって,抽象的なものではなかった。こうした時間意識の背後には農耕社会における人間と自然との関係があった。自然の規則正しい繰返しが人間の意識と行動をも規定していたのである。そこでは変化ではなく,繰返しが時間の通常の姿であった。
ところが11,12世紀に終末論をかかげる異端の登場によって鮮明となるキリスト教の時間意識はまったく異質なものであり,神を目ざすひとつの方向に進む直線的な構造をもっていた。そこでは繰り返す時間の観念は否定され,終末に向かって進んでゆく時間の変化が問題となった。このような時間意識の変化は基本的なところで死生観の変化を前提にしている。ゲルマン人の円環的時間意識のもとでは人間は死後冥界に入るが,冥界は現世と交流可能な世界であり,死者は消えてしまうのではなく,現世とのつながりを保ちつつ,別な世界で生きつづけるのである。しかしながらキリスト教の直線的な時間意識のもとでは,人間はひとたび死ねば煉獄へ,そして天国か地獄に行き,最後の審判をまつしかない。聖人のような例外的存在を除けば,一般の人間は死によって現世とのきずなを絶たれてしまう。人は1回生き,1回死ぬだけなのである。このような教会の教えた死生観は11,12世紀以後の西欧社会に特異な刻印を押すことになった。死後の救いとは人間に永遠の生を約束するものであった。現世における人間の行動はすべて死後の救いを確保するために営まれねばならず,そのためには世俗の富に対する執着を捨てることが求められたのである。現世においてどれほど大きな富をつんでも教会を通して神や貧者に寄進しない限り,天国での救いにあずかることはできない。したがって富める者は競って教会に土地や富を寄進し,中世社会における教会の突出した財政的基盤がつくられてゆく。そして王権も国家もこの教会と結ぶことによって彼岸を見通すことのできる位置にたち,みずからの公的権威を確立したのである。
ところが11,12世紀はまた商業の復活に伴って貨幣経済が展開していった時期でもあった。十字軍遠征によって東方へと視野を広げ,都市の成立によって西欧社会に力強く根づいた新興都市の商人たちは,活発な経済活動によって巨大な富を築いていった。これらの商人たちはその仕事の性質上,仕事に要する日数と費用との計算をしなければならず,いわば計測可能な時間観念が当然必要となってくる。即座に清算できる者よりも多くの金(利子を含む)を即座に清算しえない者から取りたてる権利があるという考えが生まれ,時間が富を生むことが知られていったのである。このような商人の合理的・客観的な時間の計測の要求にこたえたのが,本来修道院で発達していた歯車時計であったことは皮肉なめぐり合せであった。13,14世紀には西欧各地でこれまでの日時計や水時計,砂時計といった自然のリズムに合わせた時計に代わって,自然のリズムとは何の関係もない客観的な人工のリズムを刻む歯車時計が登場し,市庁舎の塔にすえられることになった。〈市民共有の大時計は,自由都市を牛耳る商人たちの,経済的・社会的・政治的支配の道具〉(J. ル・ゴフ)となったのである。市民の生活は時間の厳密な計測による労賃の支払や,支払期限の確定などによって合理化されていった。
このように世俗化され,合理化された時間意識のなかで生きていた商人たちも,中世においては凪(なぎ)と嵐,洪水などの自然の影響を免れることはできなかった。しかも,このような合理的な時間意識を生み出した商人たち自身もキリスト教徒だったのである。商人は仕事に従事しているときには世俗的・合理的な時間を生き,みずからの力の及ばない自然の影響下におかれたときや,彼岸を遠望するとき,つまり死を予感するときには,キリスト教の聖なる時間の意識に目覚め,現世における悪業(富の蓄積)を償うために教会に多くの寄進をし,遺産のなかからも遺贈したのである。13世紀には告解の慣行が生まれ,キリスト教徒の商業活動を正当化するために教会も協力していた。こうして中世末にいたるまで西欧においては,世俗的な時間と聖なる時間とが拮抗しつつ日常生活をさまざまな面で規制していた。個々人の彼岸における救いは現世における行動によって定まるという死生観の成立がこの二つの時間の拮抗の根底にあったから,両者の拮抗は西欧における人間の日常生活のみならず思想の次元にも決定的な影響を与え,西欧文明の根幹を形づくることになった。特に歯車時計(機械時計)の成立による厳密で合理的な時間の計測は,労働の組織化のはしりでもあり,その意味で近代社会の原理を先取りするものでもあった。また歯車時計に体現される自動装置は産業革命におけるあらゆる自動機械の先駆けであり,その点でも11,12世紀における時間意識の転換は,西欧のみならず近代における全世界の時間意識を規定してゆく大きな動きであった。
執筆者:阿部 謹也
河内国南河内郡の山付の村の庄屋筋の人が1700年ころに書き残した《河内屋可正旧記》に次のような言葉を発見する。〈夏秋の間は早く行水をすまし,七つ時(4時ころ)には身じまいをすると気持のよいものだという人がある。しかし農家の者は早朝から起き出し,夕は暗くなるまで働くものだから,4時ころに行水するなどということは農家の仇だ〉というのである。同じころの紀伊国伊都郡の人の著書《地方の聞書》(《才蔵記》)にも,暗きより暗きまで働けとしたあと,他人を多く使う農家の主人は,翌日の作業のために,人数分だけの道具を前夜より用意しておけと書いている。さらに一つの仕事を皆がやっている間に次の仕事の準備をし,家から畑,畑から家への移動のときにも,必ず物を持って動かすように指図をする。それだけではなく,これだけの仕事を終えたらタバコ休みをしよう,あれだけ終えたら昼飯だと,働く人に励みを与えなければいけないと書いている。
このような勤勉力行の教えは早く幕府の《慶安御触書》にも出てくる。朝は早く起き朝草を刈り,昼は終日耕作にかかり,夜は夜で夜なべ仕事に縄や俵を作れというのである。こういった教えを実行すれば百姓は主人から下人にいたるまで働きつづけることになる。藩によっては初期から繰り返し朝寝をするなというお触れを出している。そのことは朝起きの行われにくかったことを示しているといってもよい。後にいろいろなやり方の博奕(ばくち)を禁じる触書が繰り返されるが,農村に博奕の深く浸透していたことを示すものであろう。
朝は暗いうちから朝草刈に出かけ,朝食・小休みと作業を休止し,田畑の仕事を日の暮れまで続ける。夕闇のなかを家に帰って農具の片付け,夕食,夜なべ仕事,就寝と,毎日繰り返し行っていると,働く百姓にとっての時間は夜あけ,日の暮れの間を作業と休息で区切ったものになる。それに晴れた日の太陽の位置などが加わって,場所ごとの時刻の基準もできる。季節によって異なる夜明け,日の暮れの間を仕事で区切った時間の意識があったであろう。
雇人に仕事を与える主人の働きがきびしくて,一定の休止以外は昼も夜も働きづめであったとすると,史実の上からみて,あるいは明治以後の作男・作女の労働慣行からみて重要な疑問が残る。それは中世末における傍系血族や下人層が,家を持ち結婚をして子を育て,やがて独立していく姿のしばしばみられることによるのである。傍系血族の多くは下男・下女に近い形で主家の耕作を手伝う慣行が少なくない。そのなかで自家労働による不安定地の開墾を行い,主家の耕作の余暇にその地を耕し,家族持ちの生活を営む。傍系血族や下人が独立していく過程はこのようなものと考えることができる。このような開墾を行い,家族生活のために働く時間はどこから出てくるかということが問題となる。
中世の傍系血族が開墾地をもつこと,下人層が同時に小作人であることを示す一,二の資料を例示しよう。1398年(応永5)香取佐原井土庭住人案主吉房から弥二郎にあてた譲状のなかには,〈大橋の年神の松よりいとほまちまで川中のほまち1枚〉のほか16枚のほまちが譲与されている。〈ほまち〉というのは〈新開(しんがい)〉などと同じように余暇労働で開墾された土地である。弥二郎は吉房の庶子の一人であり,正式の譲与をうける前も,吉房の家の労務に服しながら,その余暇に乱流する川のほとりを開墾したのであろう。それが譲状によって,正式にその持分となったのである。下人が同時に小作人である例としては,1311年(応長1)の是枝半名の売券に〈下人たりといえどもあつけおく〉と記されているのをあげることができる。是枝半名を預けられた下人は,その地を耕作し,下作料を支払いながら下人の務めをも行ったのである。このような例は1204年(元久1)の中野能成への関東下知状にも見ることができる。信濃中野郷に給与された名田10町は所従に耕作させてもよいとされている。直営のばあい所従の労働を使うことは当然なので,このように記されるのは所従に一部を分け与えて耕作させ,地子を取ることを意味するものであろう。下人がその開墾地の名義を検地帳の上で認められている例もみることができる。傍系血族や下人・所従が自分のために開墾をし,主家の小作人となって自分のための耕作をしているとき,主家のための労働はいかなる形のものだったのであろうか。この点について直接明らかにする史料はない。
それについて想起すべきことは古代の朝廷に働く人について《延喜式》の各所に記される長功・短功制の一日工程の記述や,近世の村明細帳に記される1人当何段とか何畝とかする地方によって異なる耕作能率,あるいは個別農家の〈家内吉例帳〉などにあらわれる1日1人の義務作業量の記述である。冒頭に記されたような朝暗きうちから夜暗くなるまで働く永年の労働慣行はおのずから1人労働の完遂作業量を決めうるようになる。とくに他人労働を多く使用する中世の地頭・名主の直営地経営や,近世以後の地主手作では他人労働に対してだけでなく自家労働に対しても標準成果量の達成を求める形に変わってくる。暗きより暗きまでの労働量は,時間の経過によってではなく,その間に達成される労働成果の量で計られるようになる。朝草刈の男の作業量は馬の背一杯(重量で30貫前後)と人の背に一背負(籠を使っても背板でも20貫前後)といった量になる。馬耕の荒起しは何段,代搔は何段,鍬による田打は何畝,夜なべの縄ないは何尋(何丸),草鞋は何足という基準が家によって,または村によって定まってくる。朝から晩までという時の経過はこういう一日標準作業達成量によって測られるものに変わってきているのが他人労働使役の実際である。一日仕事が個別的に達成されうる諸作業の連続であるばあい,個々の雇人の確保労働量は異なった時間経過によって達成される。大部分の人が暮六つまでかかる仕事を七つに仕上げれば一時(2時間)が余暇労働となる。これに夜なべ仕事で生み出す半時を加えれば,一日3時間を下人の自家用に使うことができる。傍系血族や下人が主家の労務を果たしながら自己の持分に帰する開墾をやり,主家の耕地の下作をやることはできる。このような下人層の独立は近世に入っても続く。畿内の柄在家(からざいけ)はそのようなものとして説明されるし,各地の宗門帳には家族持ちの下人があらわれるし,作男が小作地を耕し,やがて独立して小作人となりながら,主家の祝儀愁嘆に特別の役割を果たす出入り百姓となる例は少なくない。
このような一日仕事の例二つを示そう。信濃伊那郡上穂村(現,長野県駒ヶ根市)の小町谷家の文政から天保の間(1818-44)の主人の手控の《家風録》には年中の行事を示すが,その〈男女仕事〉の項には日役・一人役と呼ばれる作業量を記している。農作業の一,二を記せば,あぜの皮むき(古畦の外側を崩すこと)1人4反くらい,畦塗ならし1人1反,小切1反2人,あらくれかき(荒代搔)2反等である。藁仕事などの基準も記されるが,これは安芸山県郡中野村(現広島県山県郡北広島町,旧芸北町)深井家の1834年(天保5)の《万覚記》によれば,その仕事覚のなかに〈なわ一日一束二房,夜は三房づつ〉などの記述がある。草履草鞋は1日12足,夕なべには2足,莚は1日1枚,夜は1枚分の縄をなうなどの記述がある。夕なべ仕事をするのは秋彼岸から春彼岸までの夜長の時期だけである。労働時間は〈朝は早朝におき仕事に出,夕は早く相休〉と一般原則を言っているが,多くの仕事に1日量が決まっているのである。越中新川郡の1800年(寛政12)の改作奉行あてに出された《奉公人仕方帳》では〈奉公人召仕様,朝六ツより暮六ツ迄〉農業をさせると言っているが,農家の実際では作業別の一日仕事の進行が時間の基準となるのである。
執筆者:古島 敏雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
この世界において生起するあらゆる変化を通じて保持されるものを時間とよぶ。もっともこの言い方は、変化を通じて保持される何ものかが「存在している」ことを含意しているかのようにみえるが、その含意を肯定すれば、すでに時間に関する「実在説」の観点をとることになる。むしろ、変化において仮設的あるいは構成的につくりだされたものが時間である、という時間の「構成説」をとれば、前記の含意は否定される。西欧近代哲学の伝統のなかで主流をなす二つの時間観は、こうして対立する。前者の代表をニュートンとすれば後者のそれはライプニッツであろう。カントは第三の立場を選んだ。人間は、世界を認識するにあたって、時間および空間という「形式」に従ってしかそれを行えないという主張を試みたカントは、時間を人間主体の側に還元したともいえる。
時間意識の出発点は、自然の周期現象であることは容易に推測されるが、そうだとすれば、当然、時間もまた周期的・回帰的なものとしてとらえられる。事実、多くの古代文化圏(インド、ギリシア、ゲルマンなど)において輪廻(りんね)的時間が設定されている。それは、人間の死後の時間とも結び付いているが、ユダヤ・キリスト教は、ほとんど例外的に、始点と終点とを備えた一回性の直線的時間構造を備えていることが注目される。
過去、現在、未来という時間の三態は、また時間の流れ、方向の問題にもかかわる。人間の記憶、現実感、そして期待や予期という意識状態にも重なるこうした時間の特性は、西欧近現代の哲学のなかで、生の形式を論ずるベルクソン、フッサール、ヤスパース、ハイデッガーらの手で問題にされ、新たな時間論を形成した。
現代物理学の相対性理論と量子力学、さらに古典的統計力学もまた、時間論に大きな衝撃を与えた。絶対時間や絶対的同時性に対する根本的疑問を提出した相対性理論、エネルギーと対になる時間を物理的観測量とみなす量子力学、エントロピー増大の方向と時間の流れとの一致という挑戦的問題を生み出した統計力学は、いずれも、今日の時間をめぐる問題の宝庫でもある。
[村上陽一郎]
通常、時間といえば、現象が前後し継起することを表示する変数をさすことが多い。またこの変数のとる値を時刻、時刻と時刻の間を時間間隔という。時間の単位として秒が用いられる。1968年10月国際度量衡委員会(CGPM)は、セシウム133の原子から放射される放射の周期の91億9263万1770倍を1秒と定めた。
時間を測定しこれを量的に表現するには、前記の放射のように、規則正しく運動する周期運動を用いる。基準の時間を設けることにより、物理現象の時間変化を研究し法則をみいだすことができる。このことは基準に用いた周期運動と対象とした現象が互いに恒常的な対応性を有し、自然が統一的であることを意味する。時間を用いて現象を研究し認識することができること自身が自然の統一性に対する検証である。同時にこのことは、自然現象、とくに物理現象における時間の進み方が物理現象とは独立ではなく、物理現象と同様物理学の研究対象であることを意味する。
[田中 一]
ニュートンはその運動法則の前提として絶対時間を導入した。ニュートンの絶対時間は何物とも無関係に一様に流れている超経験的なものである。運動の第二法則が成り立つためには、すべての座標系(厳密には慣性系)に対してこの共通の絶対時間を用いねばならない。このことが時間の超経験性・絶対性の観念を誘ったのも自然なことである。アインシュタインは相対性理論のなかで、時間の進行が、相互に運動している慣性系の間で異なることを示した。が示すように慣性系Oからこれに対し速さvで動く慣性系O'の時間をみてみよう。慣性系Oからみたときの慣性系O'の振り子A'の周期は慣性系の振り子Aの周期の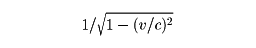
倍になっている。cは光の速さである。慣性系O'の時間の進行は慣性系Oからみたとき慣性系Oよりも遅くなっている。これを時間の遅れという。この場合、逆に慣性系O'からみたときの慣性系Oの時間は慣性系O'の時間よりも遅れている。二つの異なる場所でおこる事象の時刻が同じであること、すなわち同時性も慣性系ごとに異なる。ある慣性系からみて同時刻におきた二つの事象の時刻も、これをみる慣性系に応じて前後する。しかし2個の時空の点t1、x1、y1、z1とt2、x2、y2、z2の間に
c2τ2=c2(t1-t2)2-(x1-x2)2
-(y1-y2)2-(z1-z2)2>0
の関係があれば、すべての慣性系においてt1>t2かt2>t1かのいずれかが成り立つ。したがって同一の空間点(x1=x2, y1=y2, z1=z2)の事象の時間の前後はすべての慣性系に対して変わらない。τを固有時という。この符号は通常の時間差と同じにとる。四次元ベクトルv0、vが先の条件すなわちv02-v2>0を満たすとき、このベクトルを時間ベクトルという。重力が作用している場合にも時間の進み方は遅くなる。重力ポテンシャルを∅とすれば一般相対性理論によればその割合は|∅|が小さい場合1+|∅| /c2である。この効果は1965年、地上と塔の間の22メートルの高さの違いによる鉄のアイソトープからのγ(ガンマ)線放射の振動数のずれを測定して確かめられた。
[田中 一]
時刻t1から運動量p1の粒子が古典力学あるいは量子力学の運動方程式に従って状態を変え、時刻t2で運動量p2になったとする。このとき時刻t2で運動量-p2から出発して運動方程式に従い状態を変えると、時刻t1には運動量-p1の状態になる。古典力学に基づく運動の場合には、最初時刻t1のとき位置x1にあった粒子が時刻t2のとき位置x2にきたとすれば、逆の運動では、位置x2から時刻t2に発して時刻t1では位置x1に達する。いいかえれば、この場合には時間の向きを逆にした状態変化も運動方程式を満たす。このような時間逆向きの変化を時間反転という。一般に運動方程式あるいは運動法則は時間反転に対し不変であるが、1964年、中性K中間子の崩壊が時間反転に対して不変でないことがみいだされた。
一般に力学の法則は時間反転に対して不変であり、任意の現象に対してこれと逆向きの方向に進行する現象がおこりうるが、一方、熱現象が不可逆的であることがよく知られている。このような不可逆性は粒子集団に対して統計的な仮定を付加して導き出されている。時間反転に対し不変でない現象や不可逆な現象はいずれも現象の物理的特徴であって、時間の流れが一方向であることを根拠づけるものとはいいがたい。
[田中 一]
『向坊隆編『東京大学公開講座31 時間』(1980・東京大学出版会)』▽『エル・ヤ・シュテインマン著、水戸巌訳『空間と時間の物理学』新装版(1989・東京図書)』▽『町田茂著『時間・空間の誕生』(1990・大月書店)』▽『スティーヴン・カーン著、浅野敏夫訳『時間の文化史――時間と空間の文化』(1993・法政大学出版局)』▽『ジョン・アーチボルト・ウィーラー著、戎崎俊一訳『時間・空間・重力――相体論的世界への旅』(1993・東京化学同人)』▽『小山慶太著『物理学の広場――時間の話・空間の話』新装版(1996・丸善)』▽『イアン・ヒンクフス著、村上陽一郎・熊倉功二訳『時間と空間の哲学』復刊版(2002・紀伊國屋書店)』▽『中山康雄著『時間論の構築』(2003・勁草書房)』▽『滝浦静雄著『時間――その哲学的考察』(岩波新書)』▽『中島義道著『カントの時間論』(岩波現代文庫)』▽『マイケル・ゲルヴェン著、長谷川西涯訳『ハイデッガー「存在と時間」註解』(ちくま学芸文庫)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…移りゆく時の一つの点を時刻という。時刻と時刻との間の時の長さを時間という。時間を定めるには,二つの時点を定めその間の時の長さを単位として測定しなければならない。…
…この困難を解決するためにいろいろな考え方が提出されたが,最終的な解決は1905年,アインシュタインによって発表された特殊相対性理論によって与えられた。この理論は,時間と空間に関する従来の考え方を根本的に変えることを要求しており,その結果として,時計のおくれ(あるいは双子のパラドックス),質量がエネルギーをもつことなど,おどろくべき結果を多数予言した。それらはいずれも直接,あるいは間接に検証され,とくに,光速に近い速さで運動する素粒子の研究には,理論,実験をとわず,特殊相対性理論を駆使することが必要不可欠となっている。…
…〈恥〉や〈罪〉は,それぞれの文化を背負った人々が概念化し,その特殊な概念に名を与えたものである。 時間,空間,色などに関する名は,名付ける側の文化的規定性と名付けられる対象自体の性質の中間に成立するものであろう。たとえば,時間そのものは連続的なものであり,それをどのように分節するかによって異なった概念および名が出現する。…
…あるものの世界は,現在である。現在は次々に現れて,次々に去る,その現在の継起(連続)が時間である。この時間には始めがなく,終りがない。…
…しかしながら産業革命が出現するはるか以前に,ヨーロッパ世界は産業革命を用意する環境をつくり上げていたのであって,そのときまでさかのぼって観察しないと,この問いに十分に答えたことにはならないだろう。 近代ヨーロッパ社会が他の諸文明と異なった形の近代文明をつくり上げることができたのは,何よりもまずヨーロッパにおいて時間と空間の観念が均質化されたためであり,次いで,貨幣経済が他の諸文明よりも徹底して展開されたためである。他の諸文明においては物を媒介とした互酬の関係が近代に至るまで人間関係の主たる絆であったのだが,ヨーロッパにおいては11世紀の段階で互酬関係が転換し,貨幣経済の浸透とともに,物をめぐる人間と人間の関係に一種の合理性が貫かれることになった。…
※「時間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新