精選版 日本国語大辞典 「星」の意味・読み・例文・類語
ほし【星】
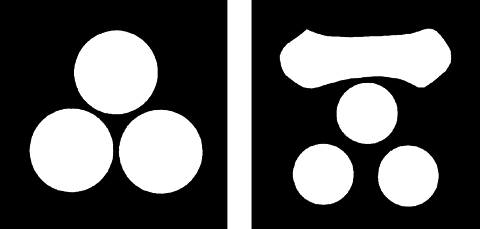
せい【星】
ほし【星】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
翻訳|star
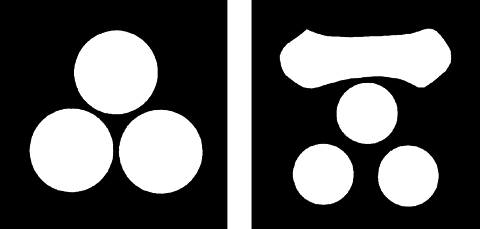
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
 〈セイ〉
〈セイ〉 〈ショウ〉ほし。「
〈ショウ〉ほし。「 〈ほし(ぼし)〉「星影・星空/
〈ほし(ぼし)〉「星影・星空/普通、太陽、月のように円板状に見えず、点状に輝く天体を「星」という。したがって星ということばには、広くは恒星、惑星、衛星、彗星(すいせい)、流星などを含む場合もあるが、狭義には星座をつくる恒星をさす。英語のスターstarの場合は恒星のみをさす。惑星はプラネットplanet、衛星はサテライトsatelliteということばで区別する。
広義の星に含まれるそれぞれの天体が天文学の対象であることはいうまでもないが、自然科学的な記述はそれぞれの項目に譲り、この項では、星の民俗、文化、信仰などについて展開する。
[石田五郎・藤井 旭]
古代の諸民族には死者の魂が天上に昇り、星になると信じていたものが多い。強者が死ぬと明るい星に、弱者が死ぬと暗い星になると考えた民族もある。
天体の運動が人間社会に大きな影響力を与えるということは、紀元前数千年にオリエントのバビロニア王国で信じられており、日月五星(太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星)の動き、およびそれに従うさまざまな判断が、出土した粘土板の楔形(くさびがた)文書から明らかである。バビロニアではとくに金星が観測され、その配置から兵乱、地震、洪水、暴風などの災害を予言した。また天体の動きを詳細に調べるために、とくに太陽その他の天体の通り道である黄道(こうどう)帯の天域が観察され、1年12か月の太陽の位置に対応して黄道を12の星座に分割することが行われていた。そしてこれが誕生時の天象から人の運命を占断するホロスコープ天文学の淵源(えんげん)となった。
バビロニアの星の知識はギリシアに移植され、ギリシア神話に登場するさまざまな人物、動物、器物の名を冠した星座が48個も制定された。黄道十二宮も、おひつじ、おうし、ふたご、かに、しし、おとめ、てんびん、さそり、いて、やぎ、みずがめ、うお、と今日の形に確定された。誕生日に太陽がどの星座に位置しているかによって人の一生の運命が決まるが、さらに複雑、詳細な判断をするために、月、5惑星と12の星座との親疎関係を定め、また誕生時刻に東の地平線に昇ってくる星座を重要視するなどした。
中国では、月の運動を重要視し、周期27日余りの動きに対応して全天を28の不等な部分に分割し、二十八宿(にじゅうはっしゅく)とよんだ。昴(ぼう)宿(プレヤデス)、畢(ひっ)宿(ヒヤデス)、参宿(オリオン座三つ星)、柳(りゅう)宿(うみへび座δ(デルタ))、心宿(さそり座アンタレス)などがこれである。二十八宿に付属して、全天1166星が宮廷内の制度に対応した名前でよばれる。天皇大帝のいる帝座、王宮である北極紫微垣(しびえん)、十二諸侯の府である太微垣(たいびえん)、行政立法府である天市垣(てんしえん)がある。細目では、天厩(てんきゅう)(うまや)、天溷(てんこん)・天廁(てんそく)(いずれも便所)、外屏(がいへい)(外の塀)、天屎(てんし)・外厨(がいちゅう)(台所)、玉井(ぎょくせい)(井戸)、酒旗(しゅき)(宴会場)などまで用意されている。これは地上界と同じ行政機構が天上界にも存在し、地上に起こることはまず天象によって示されると信じたことによる。そのため、日食・月食や客星(見慣れない星の出現)、彗星や大流星、赤気(オーロラ)などの天変は天帝の戒めとしてもれなく記録した。日食・月食の推測計算を専門に行うことは天文博士(はかせ)の重要な仕事であった。これは西洋のホロスコープ占星術に対し、東洋の天変占星術ということができる。
以上のような天文学に関する中国の知識はそのまま日本に取り入れられた。そのため日本の多くの歴史書には天変現象の記録(とくに日食、月食、惑星の合(ごう))が多い。
[石田五郎・藤井 旭]
ヨーロッパではギリシア神話などに由来する名前が星につけられている。また中国でも前述のような占星術も関係して星に名前がつけられている。これに対し、日本には古来星の和名がない、と信じられていた。これは日本は農業国であり、農民は激しい昼間の仕事の疲れのため、夜はあまり星を見なかった、という説による。この説に反発した学者の新村出(しんむらいずる)の論説に感じた野尻抱影(のじりほうえい)は、その九十有余歳の生涯をかけて700種の星の和名を採集した。
日本古来の星を表す神の名としては、天津赤星(あまつあかぼし)と天津甕星(みかぼし)があり、二つともに金星を示す。
平安時代の中期、源順(みなもとのしたごう)が著した『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』のなかには「日、陽烏(やたがらす)、月、弦(ゆみはり)月、満月、暈(かさ)、星、明星(あかほし)、長庚(ゆうつづ)、牽牛(ひこぼし)、織女(たなばたつめ)、流星(よばいぼし)、彗星(ははきぼし)、昴星(すばるぼし)、天河(あまのかわ)」の15項目がある。陽烏は太陽、明星は木星、長庚は金星である。清少納言(せいしょうなごん)の『枕草子(まくらのそうし)』には「星はすばる、ひこぼし、夕づつ。よばい星少しおかし、尾だになからましかば、まいて」とある。
すばる(おうし座のプレヤデス)はよく目につく星である。とくに農事に関係して、「すばるまんどき粉八合」のたとえがある。「まんどき」は午(うま)の刻、すなわち南中のことで、明け方にすばるが天頂高くあるときにソバの種を播(ま)くとよくとれることを教えている。すばるはその形から、六連星(むつらぼし)、羽子板星、一升(いっしょう)星、苞(つと)星などの名がある。これに対し、おうし座のヒヤデスはその形から、釣鐘(つりがね)星、あるいはすばるに続いて出てくるところから、後(あと)星の名がある。
北斗七星(ほくとしちせい)もよく目につく星列である。位置が北に寄っているため見える時間が長く、仏教の密教では、北斗、北辰(ほくしん)を祀(まつ)る行事が盛んであった。『倭名類聚抄』には北斗の名は出てこないが、『和漢朗詠(ろうえい)集』には「北斗星前横旅雁」(劉元叔)の詩句が出てくる。北斗、七桝(ななます)星、七つの星は平安時代の和歌に現れる。四三(しそう)の星は、北斗七星をさいころの四の目と三の目とを並べた形に見立てたもので、双六(すごろく)遊びのさいころの目の特殊なよび方である三一(さんいち)、三六(さぶろく)、四一(しっち)、四三(しそう)、五一(ぐいち)、五四(ぐし)のなかからとった名であり、江戸時代の『物類称呼』や『和漢三才図会』にもこの名が出てくる。七曜の星と書いて、ヒチヨウノホシ、ナナヨノホシとよぶ地方もある。またその形から柄杓(ひしゃく)星、鍵(かぎ)星、瀬戸内地方では舵(かじ)星ともよぶ。
北斗の柄(え)の先の星は破軍(はぐん)星とよばれ、中世の武人に好まれた。今日では芝居の舞台で、武人が手にする軍扇の模様にみられる。この星は剣先(けんさき)星ともよばれる。日周運動により一昼夜の間に十二支の各方位を一周するが、陰陽道(おんみょうどう)では、この剣先に金神(こんじん)が宿るとし、この剣先が示す方向に向かって戦えばかならず敗れ、公事(くじ)(裁判)、勝負事には不利であるという。北斗の柄の先から2番目の星は、中国では開陽とよばれているが、そのすぐそばに小さな星があり、これは輔(ほ)、あるいは輔(そえ)星とよばれる。
七夕(たなばた)の牽牛(けんぎゅう)、織女は乞巧奠(きっこうでん)(陰暦7月7日の行事)に飾り祀られ、織女星は織女、七夕とよばれ、牽牛星は彦(ひこ)星、犬飼(いぬかい)星の名がある。『倭名類聚抄』にも以奴加比保之(いぬかいほし)と訓じている。
北極星は、北辰、妙見(みょうけん)とよばれた。陰陽道で北極星を尊王(そんのう)に見立て、妙見菩薩(ぼさつ)としたためである。平安時代に北辰に法燈(ほうとう)を捧(ささ)げ、真言(しんごん)宗では七曜(北斗)の星祭(ほしまつり)が行われ、北辰・北斗は同時に祀られるようになり、以後、北辰と北斗とが混同されることが多い。北極星は一つ星、子(ね)の星の名もある。これは子(ね)の方角、つまり真北に見えるからである。
北極星のそばにあるこぐま座の二つの星を遣(や)らい星、番(ばん)の星とよぶ。これは北斗七星が日周運動で北極星の周りを回って、北極星をねらっているのを、北斗七星と北極星の中間に位置する二星が、追い払う、番をしているという意味である。
W字形のカシオペヤ座は錨(いかり)星、山形(やまがた)星、五曜の星などの名がある。オリオン座のδ(デルタ)、ε(イプシロン)、ζ(ゼータ)星は日本各地で三つ星とよばれているほか、三光(さんこう)、三丁の星、三星様(さんじょうさま)、三大星(さんだいしょう)、かせ星、稲架の間(はざのま)といった名もある。オリオン座のα(アルファ)星(ベテルギウス)、β(ベータ)星(リゲル)は赤、白の対比の美しい輝星であり、平家星、源氏星の名がある。またオリオン全体を鼓に見立てて、鼓(つづみ)星の名もある。
ふたご座のα、β星は二つ星、門杭(かどぐい)、または蟹の目(かにのめ)、猫(ねこ)の目とよばれる。おおいぬ座α星(シリウス)は全天で第一の輝星で青星(あおぼし)、大星(おおぼし)の名がある。
りゅうこつ座α星(カノープス)は日本では地平線すれすれにしか出ないため、珍しい星とされた。中国では南極老人星とよばれ、「老人星現れば治安く、見えざる時は兵起こる」といわれた。日本では醍醐(だいご)天皇の昌泰(しょうたい)4年(901)、その前年に老人星が見えたことから年号を延喜(えんぎ)と改めた例がある。この星は漁師の間では布良(めら)星、和尚(おしょう)星の名でよばれるが、海で遭難した人の霊であるという。兵庫県ではこの星の見える方角から、鳴門(なると)星、淡路(あわじ)星の名がある。また南の空に出るとすぐに沈んでしまう横着な星ということから横着星の名もあり、岡山県では讃岐(さぬき)の横着星、香川県では土佐の横着星と、星が見える方向の地名をつけてよぶ。
惑星の名前では金星に関する和名が多い。明星(あかぼし)、夕星(ゆうつづ)が広く使われているが、一番星、宵(よい)の明神(みょうじん)、彼(か)は誰(た)れ星(ぼし)、また出入りが早いところから飛び上がり星、盗人(ぬしと)星などもある。明け方早く出ることから飯炊(めした)き星、炊夫(かしき)泣かせという名もある。
流星は流れ星、奔(はし)り星、飛び星、抜け星、星の嫁入りなどがあるが、古くは婚(よば)い星(与八比保之(よばいほし))が普及している。
以上のように星の和名は、農耕漁労の実生活に密着して、庶民の生活に根ざした名前が多く使われており、民俗学的に興味深い。しかし、古来の日本人は太陽や月ほどに星を意識していなかったのではないかと思われる。中国から渡来した星名以外には、日本国内に全般的に流布した星名が少なく、ローカル性の強いことが特徴である。したがって星に関する神話的説話も少なく、宗教的信仰は、真言密教の星祭を除いてはあまりみられない。
[石田五郎・藤井 旭]
古代バビロニア、古代エジプトでは星々は超越神として尊敬され、人間の運命を支配する超自然的な存在として畏怖(いふ)され、ここに占星術が誕生する基盤があると考えられている。ギリシアに入り、星座が神話によって装飾され、一般的通念として星空は神の世界とされていたが、イオニア学派に始まる自然哲学者により、星を自然界の物体として考える傾向が現れてきた。太陽は灼熱(しゃくねつ)の石であるとしたのは哲学者アナクサゴラスである。
星の配置・明るさを記録し、星表を完成したのはアレクサンドリア時代(紀元前2世紀)の天文学者ヒッパルコスで、1000個の星、45の星座を記録する星表は、原表は失われたが、プトレマイオスの『アルマゲスト』に再録されてその面影を今日に伝えている。当時は肉眼視準の四分儀、六分儀を使用、角度で秒までの精度を保持している。
このような星の座標の幾何学的研究は以降、イスラム教国のアラビア文化のなかで進められたが、恒星はあくまで惑星の位置を測るための目盛りにすぎず、星の本質にかかわる問いかけはなかなか現れなかった。1609年ガリレイが手製の望遠鏡で天体観測を始め、天の川が微光星の集まりであることを発見したことは、恒星の天文学上の意義が大きい。それは肉眼では見えない数多くの星が存在し、しかもそれらがはるかかなたの宇宙の深部まで広く分布していることを教えたからである。星が空間に固定したものでなく、空間を運動することを教えたのは1718年ハリーの固有運動の発見であり、これ以降、星の空間運動が社会通念となった。
星が集まってつくる銀河系宇宙という考えは18世紀末のW・ハーシェルの大反射望遠鏡による探査によって始まり、大口径望遠鏡の出現によりその研究はいっそう進められた。星というものを正確に理解したのは1838年のベッセルの恒星の年周測定によるものである。恒星の距離が正確に理解され、太陽もこれら恒星のなかの平凡な一つにすぎないことが確定されたのである。星の進化はそのエネルギー源に関する理論的研究によって果たされた。1940年代に星の分光学的研究が進められ、星が自然界の実体として解明され、それまでの恒星に関するすべての知識が塗り変えられた、といっても過言でない。
[石田五郎・藤井 旭]
人類は古来、晴夜には天空に星を仰ぎ見てきた。それは、人間を取り巻く諸々の自然現象のなかでもとりわけ神秘に富んだものであり、人々の想像力をかき立てずにはおかなかった。今日一般に用いられている星座名の多くはギリシア神話によるものであり、それはさかのぼって古代オリエントの星辰崇拝(せいしんすうはい)につながっている。これほど体系的で、しかも多数の星についての神話をもつ文化は世界的にも少ないが、とくに顕著な星・星座については多くの民族が独自に名称をつけ、さまざまな伝承を発達させてきた。星座については、主としてその形状から神や動物や器物などに見立てるが、その見立て方は多様である。たとえば北天のとくに顕著な「北斗(ほくと)七星」(おおぐま座)を見ても、ギリシア神話では、カリストという名のニンフがゼウスの子を身ごもって月と狩りの女神の怒りに触れ、大熊(おおぐま)の姿に変えられたのだとしており、また北米先住民の一部にもこれを熊の姿に見立てるところがある。中国では「北斗」すなわち北天にかかる柄杓(ひしゃく)の形に見立て、日本の農村でもひしゃくぼし、しゃくしぼしなどという所が多い。また北欧やバビロニアではこれを神や王の乗った車に見立て、アラビアでは柩(ひつぎ)に見立てている。北斗七星は北半球の中緯度以北の地域では、1年を通して地平下に没することがないため、天につながれた大熊(ギリシア)、盗賊(キルギス)、親の仇(あだ)をねらって巡り歩いている娘たち(イラン)などに見立てられることも多い。中国では「北斗」は、いて座の「南斗」と対(つい)をなし、人間の死を扱う天の役人とされた。
南天の顕著な星座の一つに「さそり座」があるが、この名称もさまざまで、ギリシア人がオリエント起源の伝承を受け入れてこれをサソリとしたのに対し、中国人はこれを天の青竜と見なし、日本では尾部を釣り針、頭部の三角形を駕籠(かご)かつぎや天秤(てんびん)に見立てている。ポリネシアの広い地域では尾部のS字形を「マウイの釣り針」とよんでやはり釣り針に見立てているし、タヒチでは頭部をカブトムシとしている。
星に関する伝説としてとくに有名なものに七夕(たなばた)伝説があり、中国を中心に広く分布している。これはいうまでもなく織女(しょくじょ)星(ベガ)と牽牛(けんぎゅう)星(アルタイル)にちなむ伝説だが、日本へは奈良時代前後に入った。
星は方角の手掛りとしても重要であり、ことに大海原や大平原を旅する航海民族や遊牧民族の間ではそうであった。たとえば航海術に長(た)け、小船での大航海移民を成し遂げたポリネシア人たちは、星についての多くの知識をもっていたことで知られる。ハワイ―タヒチ間は3000キロメートル以上もあるが、この間を彼らは北極星(ホク・パアア)を頼りとし、ヒョウタンでつくった観測器でその高さを測りながら正確に航海した。日本の漁民や船乗りにとっても、北極星はその航海の目安とされ、ねのほし、あてぼし、ひとつぼしなどとよばれた。北極星は天の北極付近にあって一晩中ほとんどその位置を変えないから、方角の目安とされているが、天文知識の発達したエジプトでは、ピラミッドをつくる際に、内室と北極星とを結ぶ線上にトンネルを掘り、これを中心線としているものがあるという。
星は季節を知らせるものとして、農耕とも関係が深い。日本ではとくにすばる(プレヤデス星団)が播種(はしゅ)の時期を知らせる星と考えられている地域が多い。ボルネオ島のある部族では、農作業によって1年を8期に分けているが、焼畑の伐採、火入れ、播種などの時期を知らせるのは、やはりすばるの高さであるという。また、古代エジプトでは、シリウスの昇る時刻によってナイル川の増水を予知した。ナイル川の増水は氾濫(はんらん)を引き起こしたが、沃土(よくど)をももたらし、シリウスは農耕の女神、イシスの化身とも信ぜられていた。あるいは、北海道のアイヌたちは織女星を「客人姿の星」とよび、その出現で春の訪れを知り、すばるを「アルワン・ノチウ」とよんで、それが東方に昇るのを見てサケの漁期を知った。
さらに星は吉凶の前兆ともされた。とくに古代バビロニアでは、星の位置、運行から人間の運命を予知しようとする占星術が発達し、それはヘレニズム期にギリシアへ入るとともに、インドや中国にも伝播して梵暦(ぼんれき)や易経のなかに体系化されたという。もちろん、そのように体系化された占星術のほかにも、星を前兆とみる風習は世界各地にある。彗星、日食、月食などを忌むことはその例である。中国ではさそり座のアンタレスがその赤色の光ゆえに不吉な星とされ、国に大乱の訪れる前兆として恐れられた。また、ヨーロッパではシリウスがその強烈な光ゆえに干魃(かんばつ)、熱病をもたらすものとして忌まれた。日本では、南天に低くかかるアルゴ座(りゅうこつ座)のカノープスは、めらぼし、だいなんぼしなどとよばれ、漁民から大時化(しけ)の前兆とされた。また日本では、この星やシリウスを怨霊(おんりょう)の星とみなす伝承も少なくない。一方、中国ではカノープスを南極老人星と称し、これが見える年は天下太平であるとした。日本ではこのほか、農耕との関連で、さそり座のアンタレスなどをてんびんぼしとよび、これが高く昇る年は豊作であるとした。
このように、世界各地の星に関する伝承は無数にあるが、一般的にいうと、採集狩猟民のような単純な文化をもつ人々においては、星についてあまり体系的な神話や知識は知られていない。天体や星座の名称も、ごく顕著なもののみに限られる傾向がある。これに対し、星についての信仰や知識が体系的な発達を遂げたのは、主として高文明地域においてである。古代バビロニアの星辰崇拝と占星術はまさにその例であり、その影響を受けたギリシアでも星に関する大掛りな神話が生まれた。エジプトでは太陽暦がつくりだされ、さらにそれはシリウスの観察によって精緻(せいち)な暦法に発展した。新大陸でも、マヤやインカでは高度な天文知識、暦法、占星術が行われた。日本へも中国経由で体系化された神話や知識が入ったが、日本の星に関する伝承は、農漁民の生活感に基づく素朴なものが多い。
[瀬川昌久]
太陽と月以外の天体である星の信仰は、古代世界ではとくにギリシア、ローマやバビロニア、インド、中国、メキシコのマヤなどがよく知られているが、各地の先住民族でも多少は行われており、サン人(かつての俗称「ブッシュマン」)やエスキモーおよびイヌイットなどでは、星は死んだ人間の霊がなったものと信じられている。またアメリカ先住民やポリネシア人などでは、天の川、北斗七星、宵の明星(よいのみょうじょう)、明の明星(あけのみょうじょう)など、目だつ星だけが神話や俗信の対象となった。
太陽の通路としての黄道(こうどう)を中心にいくつかの束をなしている恒星の群を星座といい、中国では宿(しゅく)とよぶが、ギリシア神話のおおぐま座・こぐま座などの話で知られるように、これをいろいろな神や英雄、動物などの姿に結び付けて神話や俗信を語ったりする風習は、もともとはバビロニアの占星術が源泉となっている。占星術は、恒星とは動き方の違う5惑星(火、水、木、金、土星)や彗星(すいせい)、日月などの色や動き、またそれらと恒星の座との関係が帝王や個人の運命、さらには国家や社会の運勢にまで影響するという観想から生まれた卜占(ぼくせん)法であり、この発達とともに天文観測の技術や天文台、そして後の天文学が生まれた。バビロニア、中国、朝鮮の新羅(しらぎ)、マヤなどでは、天文台とともに占星台も設けられていた。バビロニアの12の星座(十二宮)や中国の二十八宿の星は、占星術と結び付いて尊崇されていた。日本では、星辰信仰は奈良時代以前から陰陽道、宿曜道(すくようどう)などを通じて盛んとなり、とくに北斗七星は寿命をつかさどる神として、北辰とか妙見とかよばれて尊崇されている。朝鮮でも北斗は古くから寿命の神とされ、七星堂、七星岩などの聖壇で安産祈願などに信仰されている。
[松前 健]
『野尻抱影著『星の神話・伝説集成』(1969・恒星社厚生閣)』▽『吉田光邦著『星の宗教』(1970・淡交社)』▽『原恵著『星座の文化史』(1982・玉川大学出版部)』▽『大崎正次著『中国の星座の歴史』(1987・雄山閣出版)』▽『斉藤国治著『古天文学の道――歴史の中の天文現象』(1990・原書房)』▽『青木信仰著『人間と宇宙――天文学小史 地球を考える』(1994・日本基督教団出版局)』▽『ロバート・ボーヴァル、エイドリアン・ギルバート著、近藤隆文訳『オリオン・ミステリー――大ピラミッドと星信仰の謎』(1995・日本放送出版協会)』▽『斉藤国治著『宇宙からのメッセージ――歴史の中の天文こぼれ話』(1995・雄山閣出版)』▽『榎本出雲・近江雅和著『21世紀の古代史 消された星信仰――縄文文化と古代文明の流れ』(1996・彩流社)』▽『堀田総八郎著『縄文の星と祀り』(1997・中央アート出版社)』▽『アンソニー・アヴェニ著、宇佐和通訳『神々への階――超古代天文観測の謎』(1999・日本文芸社)』▽『長島晶裕他著『星空の神々――全天88星座の神話・伝承』(1999・新紀元社)』▽『前川光著『星座の秘密――星と人とのかかわり』(2000・恒星社厚生閣)』▽『坂上務著『暦と星座のはじまり』(2001・河出書房新社)』▽『北尾浩一著『星と生きる――天文民俗学の試み』(2001・ウインかもがわ)』▽『野尻抱影著『星の民俗学』(講談社学術文庫)』▽『野尻抱影著『星と伝説』(中公文庫)』▽『矢島文夫著『占星術の起源』(ちくま学芸文庫)』
星ということばは,広くは太陽と月を除く天体すなわち恒星,惑星,すい星,星団あるいは星座を指し,狭くは恒星だけを指す(ただし太陽と月も場合によっては星と呼ぶ)。
原始時代の人類にとっては,彼らがもっとも畏怖(いふ)の目で仰いだ太陽と月とが,偉大な精であることはもちろん,空の無数の目のようにきらめく星もみな精であり,ときには神でもあった。バビロニアの楔形文字の〈神〉が星の形であるのもこのことを示している。また星の青い光から,これを死者の魂が化したものと信じている民族もすこぶる多い。たとえばオーストラリアのアボリジニーは,強者が死ぬと大きな星になり,弱者が死ぬと小さい星になるという。エスキモーは,ある星は先祖の生まれかわり,ある星は魚や獣の生まれかわりと区別しているという。またアフリカのサンは,星はいちどは地上に生まれた人間や,ライオンやウミガメなどが,空に上って生まれかわったものと信じているという。
ときおり起こる日食,月食は未開民族を恐怖させ,これが戦争,疫病,飢饉(ききん)などの前兆であると信じられた。また不意に出現するすい星に対しても同じ迷信をいだいた。それと同時に星の中でも顕著な五惑星(水,金,火,木,土)が,ときに東しときに西して空をさまよう現象も,それらに宿る神々ないし祖先の霊が吉凶を黙示しているものと信じて,やがて占星術を生むようになった。そしてこのために空を細かく観察して,太陽,月,五惑星のとおり道(黄道)にあたる星々を,バビロニアでは太陽の1ヵ年の旅から十二宮に区分し(黄道十二宮),他の星々をも幾群にも区分して,それらに神々,神話人物や動物などの形を空想した名をつけた。これが今日の星座の原型である。また中国でも,黄道を月の毎月の旅から二十八宿に区分し,全天の星をそれぞれに付属させて,皇帝,后妃(こうき)を初め多く宮廷関係の名をつけた。こうして五惑星がめぐっていく星座,星宿を観察し,またその通路にあたらぬ部分でもそこの星々の光,またたきなどを見て,国家,国君および個人の運命をも占った。西洋の天文学はやがて占星術を母胎として生まれたが,中国では久しく迷信から脱しきれず,日本へもこれが陰陽道として伝わり,天文学の発達を妨げた。しかし一方では,星の推移を自然暦に用い,進んで農耕の季節を知るうえにも利用し,また航海者や旅行者が星を方角の判断に用いたことなどが,東西ともに天文知識を助長したことはいうまでもない。
ところで上代の日本人は星をどう見ていたであろうか。《古事記》と《日本書紀》には,星に関する記事はきわめて乏しい。天照大神と月読(つくよみ)尊が太陽と月の神格化であることは疑いがない。星の記事では,《日本書紀》神代下のはじめに,葦原中国に〈多(さわ)に蛍火の光(かがや)く神および蠅声(さばえな)す邪神(あしきかみ)あり,また草木ことごとく能く言語(ものいう)ことあり〉とあって,〈蛍火の光く神〉が星を意味することは多くの学者が一致している。草木がみな物いうとあるのも,万物に精霊があると信じたもので,星をも同じ信仰により悪霊の宿るものと見ていたのである。ついで同巻に〈天津甕星(あまつみかぼし)〉が現れている。記紀を通ずる唯一の星神の名で,神々に抵抗した後に誅せられたとある。これが何の星で,この神話が何を意味するかはわからないが,記紀編集の目的のため捨てられたと思われる自然神話の中で,わずかに残存する星の貴重な文献であるに違いない。
日本言語学の祖といわれたチェンバレンは,日本人は農業国民で昼のつかれで早寝をしたため,星にはあまり関心をもっていなかったのだろうと書いている。これは星の名の伝わるものが少ないためのことばだが,しかし,源順(みなもとのしたごう)が《和名抄》に初めてあげた星名〈すばる〉が,記紀に盛んに出てくる上代人の玉飾〈御統(みすまる)〉から出たことは,国学者の間で一致している説である。この星団が古来諸民族から農耕のしるべとして仰がれ,現在でも南方諸島で重要視されている事実から考えて,すでに農業時代にはいっていた日本の上代人もその例外でなく,すばるの美称をつけたのもそのために違いない。かつこれから類推して,さらに著しい北斗七星やオリオンなども農村,漁村から親しまれて,しかるべき和名があったと思われる。しかし文字の行われることが少なかった時代には,もっぱら中国から伝わった名が記載され,平安時代にはいってようやく和名を散見するようになった。江戸時代からは方言集,随筆などにその数を増して,それに現在,諸地方に残るものをあわせると600~700に上る。なお星の和名の特色は,星を結んだ形を農具,漁具その他の民具に見たててその名で呼んでいることで,西洋伝来の星座が神人や動物の形と見ているのに比べ,素朴な国民性が現れている。また中国,とくに南方民族の見かたに相通ずるものが多いことは注意に価する。
星や星座の起源に関しては,多くの神話群の中でも,ギリシア神話がもっとも豊富な内容を伝えている。ギリシア神話によれば,星は曙の女神エオスがアストライオスAstraiosという神と結婚して生んだ子どもたちだという。ヒヤデス星団となったヒュアデス,すばるとなったプレイアデス,オリオン座にその名を残すオリオンなど,星座の起源譚も多い。しかし星座の起源についての説明は,ギリシア神話のなかでもつねに一定しているわけではない。たとえばおうし座は一説によれば,フェニキアの王女エウロペをゼウスの愛人にするために背に乗せて海を渡り,クレタ島まで運んだ牛が天にあげられたものだが,別の伝承によれば,クレタ王ミノスの祈りにこたえて,海神ポセイドンが海から出現させた牛である。ミノスの妃パシファエがこの牛に恋し,名工ダイダロスにつくらせた本物そっくりの牝牛の模型の中に入って,その牛の種を受けて半牛半人の怪物ミノタウロスを生んだという。そのあとこの牛は英雄テセウスによって殺され,星座になった。
またギリシア神話の星座の起源譚の中には,しばしばオリエントの神話がとり入れられている。たとえばうお座の起源は,怪物の王テュフォンを恐れ,神々がそれぞれ動物に姿を変えて姿を隠したときに,美の女神アフロディテは,息子の愛の神エロスとともにユーフラテス川に飛びこみ,魚たちにかくまってもらった。そこでその魚たちが,その功績によって星にされたと物語られている。これは実は,ギリシア人によってアフロディテと同一視されたシリアの女神アタルガティスAtargatisの神話にほかならない。それによると,魚たちが星にされたのは,ユーフラテス川の中で発見した卵を岸に運び上げ,それからアタルガティスが誕生するのを助けたためであったという。
北欧神話によれば,太古に神々の王オーディンが2人の弟ビリとベーと協力して宇宙をつくったときに,世界の南の果てにある灼熱の火焰界ムスペッルスヘイムから吹き出る火花を取って天空に置き,それぞれに場所と運行を定めてやったのが星の起源だという。
ブラジルのボロロ族の神話では,星の起源は次のように説明されている。あるとき女たちが畑でトウモロコシを収穫し,その場で粉にひいていたところ,1人の男の子がそのトウモロコシを盗み,竹筒の中に隠しもって先に村に帰った。そして1人で留守番をしていた祖母に頼んで菓子にしてもらい,仲間の少年たちといっしょにむさぼり食った。彼らはこの悪事が露見するのを恐れて,祖母の舌と村に飼われていたコンゴウインコのうち1羽の舌を切ってしまい,他のインコはすべて放してしまったうえで,ハチドリに頼んで取りつけてもらった節のある長いつる草をよじ上って,天に逃げていった。村に帰ってきた女たちは子どもたちがいないのに気づき,祖母とコンゴウインコに尋ねても答えが得られない。そのうちにつる草を登っていく少年たちを発見し,大声で呼びかえそうとしたが少年たちは耳を貸さず,母たちは必死で彼らのあとを追って登り始めた。するとそれを見た列の最後にいた少年が,天に着いたところでつる草を切ったために,母たちは地面に墜落してつぶれ,いろいろな種類の動物になった。少年たちも罰を受け,星に変えられて,夜ごと自分たちの所為で母たちが陥った不幸な状態を眺めさせられることになった。夜空に見える星の輝きは,下界を見下ろしている彼らの目であるという。
ガイアナ(南アメリカ)のワラウ族の神話によれば,狩りの名人があるとき人食いの女の怪物に捕まり,えじきにされかかった。しかし怪物の2人の娘が彼に恋し,命乞いをしてくれたおかげで危うく助かり,妹娘と結婚して怪物の家で暮らすことになった。ところが,いくらたくさんの魚を取ってきても,大食の化物はたちまち食い尽くしてしまうので,彼はやがて疲れ果て病気になり,同情した妻といっしょに逃げ出す決心をした。そして怪物をだましてサメ(またはワニ)に食い殺させておいて逃げていくと,そのことに気づいた姉娘が鋭い小刀をもって追ってきた。急いで妻を高い木に登らせ,自分もあとから登ったが,そこへ追い着いた姉娘によって片足を切り落とされてしまった。それでも夫婦はともかく天にたどり着き,妻はすばる星に,夫はヒヤデス星団になった。夫の切られた足は,オリオン座の三つ星になったという。
執筆者:吉田 敦彦
暗い夜空にあって光り輝く星は,太陽や月と並んで,それ自体神的な存在として崇拝されるとともに,もっともポピュラーな聖性,永遠,不死,希望などの象徴となっている。世界の多くの神話において特定の星が神と結びつけられているし,英雄や聖人など神に嘉(よみ)された者が天にあげられて星となる例もまた少なくない。星を持物(アトリビュート)とする神も多く,バビロニアのイシュタル,ギリシアのアフロディテ,ローマのウェヌス(ビーナス)など,とくに金星と縁の深い女神の系列が目だつ。一般に太陽に対して,星は月とともに女性原理と高い親和性を示すようだ。
星が人間に対して影響力をもつという占星術の信念も,星の力が神の意志として観念されていることに由来する。そこでは,あらゆる人間的事象がその支配星によって決まると考えられるから,人間の運命とはすなわち星のめぐりにほかならない。欧米各国語には,英語に限っても,例えば,〈be born under a lucky star(幸運な星の下に生まれる)〉〈thank one's star(星まわりに感謝する)〉〈One's star is in the ascendant(運が向いてくる)〉など,運命と星を同一視した多くの言い回しがある。また神の意志の表明としての星の出現は当然ながら重大事の予兆ともなる。〈ベツレヘムの星Star of Bethlehem〉は,キリスト降誕の際,天に現れて東方の三博士をベツレヘムへと導いた(《マタイによる福音書》2:1~10)。ただし吉兆ばかりではなく,とくに流星やすい星の出現はしばしば凶兆とされた。
星に現れるこのような神威にあやかるため,これを図形化して護符などとして用いることが古くから行われた。以下にその代表例をあげる。(1)四芒星形 元来はバビロニアの太陽神シャマシュの標章で,マルタ十字はこれに由来するという。(2)五芒星形(ペンタグラム) 霊力,啓示,知識などの象徴。〈ソロモンの封印Seal of Solomon〉も同形。ピタゴラス学派によって尊重され,魔術書にも多くの例を見る。(3)六芒星形 〈ダビデの星Star of David〉と呼ばれイスラエルの国章として有名なもの。一般に創造の象徴とされるが,二つの正三角形が組み合わさった形なので両性具有,対立物の統一の象徴ともなる。(4)八芒星形 金星を表すものとして女性の生産力を象徴するとされる。タロットの〈星〉の札にはこれが描かれることが多い。
なお,ヒトデはその形状から,ラテン語ではstella maris(〈海の星〉の意),英語ではstar-fishと呼ばれる。その多くが五芒星形である。これが奇妙なことに,キリスト教では尽きざる愛の力や聖霊の象徴とされるのは,触れるものすべてを焦がし,食べたものを即座に燃やしてしまうというような古代伝承(大プリニウス《博物誌》第9巻)の影響もさることながら,前述した金星=地母神の系譜に連なる聖母マリアの属性が,〈海に落ちた星〉であるヒトデに反映した結果と考えられそうである。
→占星術 →太陽 →月
執筆者:松宮 由洋
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…儀式は人長の作法と,本・末の受け持つ神楽歌から成るが,人長の指図で座を鎮め,《庭火》の曲で各楽器の音を試みることから始まる(人長式)。以下の構成は,〈採物〉〈小前張(こさいばり)〉〈星〉という三つの違った傾向をもつ神楽歌のグループから成るが,ここで現行神楽歌一具(御神楽における神楽歌次第)を掲げる。(1)人長式の部 《神楽音取(かぐらのねとり)》《庭火》《阿知女作法(あじめのさほう)》。…
※「星」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新