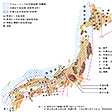日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本(にほん)」の意味・わかりやすい解説
日本(にほん)
にほん
総説
位置・範囲
アジアの東方海上、太平洋の北西部にあり、東および南は太平洋に、西は日本海と東シナ海に、北はオホーツク海に面する島国。北東から南西へ弓なりに連なっている島々、すなわち北海道、本州、四国、九州の四つの島および三千数百の小島からなり、ほぼ温帯に属している。その範囲は、東端が東経153度59分(東京都小笠原(おがさわら)村南鳥島)、西端が東経122度56分(沖縄県与那国(よなぐに)町)、南端が北緯20度25分(東京都小笠原村沖ノ鳥島)、北端が北緯45度33分(北海道稚内(わっかない)市弁天島)の広きにわたっている。総面積は37万7976.41平方キロメートルである。
[斉藤 孝]
領土の消長
日本が近代国家として諸外国にまみえた明治維新のとき、日本の領土は、本州、四国、九州、北海道とその属島であり、沖縄はまだ日本の統一国家としての主権が十分には及んでいなかった。すなわち、それまで沖縄は琉球(りゅうきゅう)王国として薩摩(さつま)藩と清(しん)国との両方に従属する小国家であり、明治政府は琉球国王を琉球藩王としたが、清国に対する宗属関係については不問のままであった。1879年(明治12)明治政府は強制的に琉球藩を廃し、沖縄県を設けて、日本の完全な主権の下に置いた。なお北海道は、江戸時代にほぼ日本の支配下に置かれ、千島は1854年(安政1)日露和親条約によって国後(くなしり)島以南を日本に、得撫(うるっぷ)島以北をロシアに帰属させたが、ついで1875年にロシアと千島・樺太交換条約(ちしまからふとこうかんじょうやく)を結び、樺太をロシア領とし、得撫島以北の千島を日本領とした。その後、南鳥島が日本領土として宣言された(1898)。日清戦争の結果、下関条約(しものせきじょうやく)(1895)によって台湾と澎湖(ほうこ)島を獲得し、日露戦争の結果、ポーツマス条約(1905)によって、北緯50度以南のサハリン(樺太)および属島を獲得し、関東州租借地をロシアから譲渡された。1910年(明治43)韓国に日韓併合条約を強要して朝鮮を併合した。さらに第一次世界大戦の結果、国際連盟から赤道以北の南洋諸島を委任された。名目は委任統治であるが、事実上領有であった。こうして、日本の領土は総面積68万平方キロメートルに及んだが、太平洋戦争の敗北の結果、日清戦争以前の領域に縮小された。
沖縄は、太平洋戦争において市民をも巻き込む地上戦闘が行われた国内で唯一の県であり、戦後7年間はアメリカ軍の軍事占領が続き、1951年(昭和26)サンフランシスコ講和条約によってアメリカの施政権下に置かれた。アメリカは沖縄を戦略上の見地から軍事基地として確保しようとしたのである。沖縄で日本へ復帰しようとする運動が高まるにつれて、日本でも沖縄返還運動が積極化し、1971年、日米沖縄返還協定が調印され、翌1972年祖国復帰がなった。
領海は、1870年以降、沿岸から3海里幅を採用してきたが、1977年、12海里を領海とした。なお漁業水域は200海里である。現在の日本は、北方領土および竹島と尖閣(せんかく)列島を除いては、とくに領土をめぐる紛争は抱えていない。
[斉藤 孝]
行政区分
日本は行政区分として、1都、1道、2府、43県に分かたれている。都や道、府および県の間にはとくに相違はないが、政令指定都市として、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、北九州、札幌、川崎、福岡、広島、仙台、千葉、さいたま、静岡、堺、新潟、浜松、岡山、相模原、熊本(指定年順)があり、区制を敷いている。首都は東京であり、明治維新の際、明治天皇が東京へ移ったという既成事実に基づいている。東京都は特別区を設けている。
地理上、日本は北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の八つの地方に分けられるが、このほかに、気象上、交通上、産業上など目的に応じてさまざまな区分がある。
[斉藤 孝]
住民
日本は単一民族国家であるという「神話」が長く流布されてきた。日本語は公用言語であるが、これも事実上の慣習であって、裁判所法に日本語をもって裁判所の用語とする(第74条)とあるほか、憲法などには用語の規定はない。つまり、日本語は単一民族の言語であることが既成概念になっているのである。しかし、沖縄で使われている琉球語は、日本語と同種同系であるが、多少日本語と異なる。またアイヌ人にはアイヌ語があるが、現在ではほとんど用いられていない。日本民族以外で日本に居住する民族として、まず朝鮮人がある。日韓基本条約(1965)に伴う協定の規定によって、在日朝鮮人(1945年8月15日以前から日本に居住している者およびその直系卑属)に対しては永代居住権を認めた。1995年時点で、これらの朝鮮人(韓国籍および朝鮮籍)が約67万人、日本国籍に帰化した者が約12万人いる。次に中国人が多く、約11万人を数える。1980年代からは、とくに東南アジアその他から労働力として日本に渡来する者がしだいに多くなってきている。この他民族居住者に対する処遇が最近問題となっている。
[斉藤 孝]
日本民族の起源
現在の日本人がどのようにして形成されたかは、明らかではない。北方渡来説もあり、また南方渡来説もあって一定していない。身体的特徴からはいくつかの種族の複雑な混合であろう。基本としては、朝鮮半島を通って渡ってきたツングース系の種族に、東南アジアからきた種族やアイヌ系の種族などが、長い間に混ざり合って日本民族を形成したのであろう。旧石器時代の遺物が日本においても発見されているが、学問的に旧石器時代と新石器時代との関連を解明するところまでには至らない。
日本国家の起源について、『古事記』や『日本書紀』の伝えるところでは、神武(じんむ)天皇が日向(ひゅうが)(現在の宮崎県)から東征して、大和(やまと)(現在の奈良県)で国を始めたことになっており、現在、国家が制定している建国記念の日(2月11日)は、この神話伝承に基づくものであるが、これはそのまま史実としては受け取りがたい。日本の歴史は、5世紀以前は史料的には確実ではなく、この時期については考古学の進歩を待つほかない。3世紀の日本について中国の『魏志(ぎし)』東夷(とうい)伝倭人(わじん)条に記載があり、この記述をめぐって諸説が争っている。この時期にはおそらく多くの小国家が割拠していたのであろう。大和政権がそのなかでもっとも有力であり、7世紀にはほぼ大和政権が統一国家をなしていたと思われる。
[斉藤 孝]
国の呼称
『古事記』『日本書紀』によれば、古い時代には「豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)」あるいは「葦原中国(あしはらのなかつくに)」などとよばれた。大和政権が伸張するにつれて、ヤマトが日本全土を表すものとなった。中国では日本のことを「倭」とよんでいた。日本でも、中国に対するときは、自国を「倭」とよんだ。これと日本でのヤマトが結び付いて、「倭」を「やまと」と訓ずるようになった。日本は「日出処」から由来したらしく東方の意味で、対外的にこの名称が採用されたのは7世紀ごろである。「日本」は「やまと」と読まれたが、漢字音で「にほん」あるいは「にっぽん」と読まれるようになった。「にほん」か「にっぽん」かという論議は、日本が近代国家として世界に登場するようになってからしばしば繰り返されたが、今日でも決着はついていない。1934年(昭和9)3月、文部省臨時国語審議会は「にっぽん」を正式の呼称とし、最近では、たとえば郵便切手や国際スポーツ大会などではNipponと表記しているが、これが一般的とはいいがたく、また法的にも根拠はない。外国語では日本をJapan(英語、ドイツ語)、Japon(フランス語)、Japón(スペイン語)、Giappòne(イタリア語)などとよんでいる。これはおそらく、マルコ・ポーロの『東方見聞録』にあるジパングに由来するものであろう。日本を中国語の漢音で発音したものをジパングと聞いたものであるというが、定説があるわけではない。なお、現憲法では、日本の国号を日本国としている。
[斉藤 孝]
国旗・国歌
日本の国旗、国歌については、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)で、国旗は日章旗、国歌は『君が代』とすると定めている。日章旗あるいは日の丸は太陽を象徴したものであり、白地の長方形の中に赤い円を描いたものである。これが日本を象徴する旗として用いられたのは、1854年徳川幕府が日本の総船印(ふなじるし)として採用したのが最初であり、1870年の太政官(だじょうかん)布告がこれを踏襲した。当時、その意義は船舶などを外国と区別するためであって、とくに国旗ということを明示してはいなかった。『君が代』は『古今集』の歌を本歌としてとったものである。この歌詞に作曲して、1893年、初等教育において祝日の儀式の際に斉唱すべき歌として公布した。以後、実際上の国歌として歌われてきたが、法的規定に関しては、国旗の場合と同様に1999年(平成11)に制度化された。
[斉藤 孝]
自然
総論
風土について
風土という語は多様な意味で使われているが、大別すると、(1)ある土地の気候、地形、地質、地味その他を含めた自然環境、(2)文化論的あるいは和辻(わつじ)哲郎のいう人間学的考察の対象としての風土および、(3)風土病、風土記という場合に意味する地方などに分れる。本稿では、(1)の意味での日本の自然についてそれぞれの専門家が記述する。
日本の自然は長い間、日本人の生活の場であり、日本人は自然環境とかかわりをもちながら、自然を利用し、改変しながら歴史時代を通じて日本的風土を形成してきた。日本の国土は南北3000キロメートルにも及び、亜熱帯から亜寒帯(冷帯)に至る気候帯をもつとともに複雑な地質構造からなり、各地が小規模な山地、盆地、平野に分断されている。しかも山地の面積が多く、長い間に孤立的な地域ごとに独自の風俗習慣が形成された。この傾向は幕藩体制下でさらに強まったが、明治維新後、急速に近代化が進み、文明開化に伴う交通・通信機関の発達によって、それまで孤立していた地域がしだいに他地域と交流を深めていくにつれて地方の独自色は薄れていった。初等教育の普及はその画一化をさらに促進した。
明治以降の西洋文明の輸入は、それまでの自然と共存する形の東洋的自然観とは逆に自然を人工改変の対象として積極的に働きかける考え方をもたらし、自然破壊を促進した。とくに1960年代(昭和35~44)以降の急激な経済成長に伴う開発工事が、各地で多様な形の自然破壊をもたらした。日本的風土の代表とされた田園風景も、水田化という国土の改変ではあったが、その景観は自然に同化したものであった。しかし近年の土木工事に伴う改変は生態系の破壊、ときには特定の生物種の絶滅をもたらした。
1972年6月にストックホルムで人間環境会議が開かれた。この会議のスローガンは「かけがえのない地球」で、人類をとりまく環境の汚染が予想外に深刻化していることを広く一般大衆に認識させることを目的とした。
日本では無計画な地域開発によって工場と住宅が混在または接近し、産業公害が頻発した。産業の発展に伴う産業廃棄物中の有害物質の増大が人体に悪影響を及ぼすこと、大気中に放出されるフロンガスのように一般家庭も汚染源であることなどがマスコミによって報道されるにつれて一般の認識も深まったようであるが、原子力廃棄物のようにその処理をめぐって国際問題になりかねない物質も増えつつある。日本の各分野で国際化が叫ばれているが、まず外国に依存せずに自国内で有害物質を処理することも必要であろう。1998年(平成10)3月にダイオキシン規制強化を環境庁(現、環境省)が決め、ほぼ同時に発表された全国総合開発計画(五全総)もこれで最後という点は、昨今の事情を象徴的に表している。
[髙山茂美]
地質
日本列島弧
日本は本州弧、千島弧の南西端部、伊豆‐小笠原弧、琉球(りゅうきゅう)弧からなる。本州弧はフォッサマグナによって西南日本弧と東北日本弧とに分けられる。明治初期に来日したドイツの地質学者ナウマンによって命名された東北日本弧は、本州弧から北海道、樺太(からふと)までをあわせたものである。
島弧の配置は、現在のプレートの配置と、それらの間の相対運動の結果で決まる。日本列島付近は、現在、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、オホーツクプレート(北アメリカプレート)、太平洋プレートの四つの主要なプレートが分布している。西南日本弧および琉球弧は、ユーラシア大陸や日本海、東シナ海と一体となってユーラシアプレートの一部をつくっている。これら二つの弧は、その南東側にあるフィリピン海プレートが南海トラフおよび南西諸島海溝(琉球海溝)から沈み込むことによって形成されている。東北日本弧および千島弧はオホーツクプレートの一部であり、それらの南東側にある太平洋プレートが日本海溝から沈み込むことによって形成されている。伊豆‐小笠原弧は、フィリピン海プレートの東端にあり、東側の太平洋プレートが伊豆‐小笠原海溝から沈み込むことによって形成されている。なお、オホーツクプレートは、西側のユーラシアプレートにより日本海東縁の位置から沈み込みを受けているが、この沈み込みに応じた明瞭(めいりょう)な弧は形成されていない。
島弧ができあがる過程は、大山脈ができあがる過程と同じく、造山運動とよばれた。しかし、日本列島区はずっと大洋の周辺にあって、数億年前から現在まで繰り返して地殻変動を受けているので、二つの大陸の衝突で成長した大山脈であるアルプスやアパラチアとは、そのでき方を大きく異にする。
[木村敏雄・村田明広]
日本列島の地質構造区分
本州弧は糸魚川(いといがわ)‐静岡構造線によって北海道南西部の渡島(おしま)半島までの「東北日本」と、九州までの「西南日本」とに分けられ、西南日本は中央構造線と臼杵(うすき)‐八代(やつしろ)構造線の主要部によって北側の内帯と南側の外帯とに分けられている。琉球弧は奄美(あまみ)大島、沖縄本島を含む外弧と吐噶喇(とから)列島などからなる内弧とに分けられる。これらはさらに細区分されている。
島弧をつくる地殻変動には安山岩の火山活動、花崗(かこう)岩の貫入活動が密接に関連している。これらはまた当時の大洋プレートの沈み込みに関連している。過去の本州弧の安山岩、花崗岩は、古生代のシルル紀・デボン紀には黒瀬川‐大船渡(おおふなと)帯に、古生代のペルム紀(二畳紀)後期から中生代のジュラ紀中期には飛騨(ひだ)帯およびその西方延長に、中生代白亜紀初めには北上(きたかみ)地区と領家(りょうけ)帯に、白亜紀後期には広く東北日本日本海側と西南日本内帯に、新生代の古第三紀には本州弧の日本海沿いなどに、新第三紀には北海道、東北日本日本海側、フォッサマグナ、西南日本内帯などに顕著に分布している。このように位置と時代とを異にして火成活動区ができたことは、シルル紀以降その範囲と性格とを変えない地質構造区分があったのではなくて、時代によって地質構造区のもつ意味とその配列とが異なったことを示す。特定時代の構造区分はその時代の地殻変動の特徴をもっとも強く示し、過去とは構造区境界の位置が変わっても、過去の構造区分の特徴を受け継いでいる。
[木村敏雄・村田明広]
地層と岩石の形成およびその分布
先カンブリア界の岩石が岩体をつくっている所は、日本では飛騨帯の一部にみつかっている。その時代の礫(れき)があることから、飛騨帯、領家帯にかつて先カンブリア界岩体があったと推定されている。オルドビス系は飛騨外縁帯福地付近の小地域に分布する。その上にシルル系が重なる。シルル‐デボン系は、飛騨外縁帯と、南部北上帯の大船渡付近から西南日本の黒瀬川帯(黒瀬川地帯)にかけての黒瀬川‐大船渡帯に分布する。サンゴ礁石灰岩が多く、流紋岩質ないし安山岩質の凝灰岩を多く含む。
石炭系とペルム系は、おもに秋吉帯のペルム紀付加体(付加堆積物の集合体)中や、美濃(みの)‐丹波(たんば)帯および秩父(ちちぶ)帯のジュラ紀付加体中にみられる。玄武岩質火山岩類とその上に重なる厚い石灰岩は、海洋地殻の上にあった海山のものとされ、ペルム紀やジュラ紀の砕屑(さいせつ)岩類と混じり合って付加体を形成した。秋吉帯の秋吉石灰岩、阿哲(あてつ)石灰岩、美濃‐丹波帯の伊吹山(いぶきやま)石灰岩、秩父帯の津久見石灰岩はこのような石灰岩である。南部北上帯にもこの時期の石灰岩があるが、これは大陸地殻の上に堆積(たいせき)したものである。古生代石炭紀からペルム紀にかけてのチャートも上記の付加体中にみられる。ペルム紀の砕屑岩は、飛騨外縁帯、秋吉帯、舞鶴帯、黒瀬川帯(黒瀬川地帯)、南部北上帯にみられる。
三畳系および下部~中部ジュラ系は、チャートおよび珪質(けいしつ)泥岩が美濃‐丹波帯、足尾帯、領家帯、秩父帯、北部北上‐渡島帯などのジュラ紀付加体中にみられる。これらのチャートの上には、ジュラ紀中期から後期の砕屑岩が堆積している。一方、三畳系の砕屑岩は、秋吉帯のペルム紀付加堆積物を不整合で覆ったり、黒瀬川‐大船渡帯、南部北上帯などに分布している。中生代三畳紀の石灰岩は、三宝山(さんぼうさん)帯や北部北上‐渡島帯にみられるほか、一部、秩父帯北帯にも分布する。
上部ジュラ系および白亜系は、飛騨帯、秋吉帯などに陸成層および海成層が分布する。また、黒瀬川帯(黒瀬川地帯)には、石灰岩を伴う上部ジュラ系から陸成層を伴う白亜系に至る地層が、付加堆積物等を不整合に覆いながら分布する。南部北上帯には上部ジュラ系から白亜系に至る砕屑物が分布する。四万十(しまんと)帯北帯には、玄武岩質火山岩類、チャートを伴い、砂岩を大量に含む白亜紀付加堆積物がみられる。北海道の日高帯や常呂(ところ)帯にも白亜紀の付加堆積物がみられ、四万十帯北帯の延長と考えられている。また、常呂帯には白亜紀後期の高圧型変成岩が分布する。白亜紀前期の安山岩・流紋岩・花崗岩活動は、領家帯から北部北上帯、さらに北海道の礼文(れぶん)島に至る地域で生じた。白亜紀後期には、西南日本内帯と東北日本の日本海側の広範囲にわたって花崗岩活動があった。
ジュラ紀から白亜紀の地殻変動によって、日本列島区は広く陸化した。これにより、日本列島の地体構造、つまり地質の基本的な枠組みが形成されたことになる。西南日本外帯に形成された四万十帯北帯の白亜紀付加堆積物の太平洋側には、海洋底あるいは海山の玄武岩質火山岩類やチャート・珪質泥岩などの遠洋~半遠洋堆積物が砕屑岩類と混ざり合い、四万十帯南帯の古第三紀から新第三紀中新世最前期の付加堆積物が形成された。しかし、日本の古第三系の多くは半海成ないし陸成層である。釧路(くしろ)、石狩(いしかり)、常磐(じょうばん)、筑豊(ちくほう)炭田には石炭層が堆積した。古第三紀最初期の花崗岩は山陰にあるが、奄美大島、徳之島にもある。古第三紀初期から後期にかけての花崗岩、後期の安山岩は、北海道の日高山脈や陸別地区に南北性方向をもって分布する。また、後期の安山岩は、男鹿(おが)半島から島根県にかけて本州弧北西縁に分布する。
新生代新第三紀中新世前期になると、それまでアジア大陸の東縁に位置していた日本列島区は、西南日本弧が時計回り、東北日本弧が反時計回りに回転しながら移動し、背後に日本海を形成した。これにより、現在に近い、いくつかの島弧の集合体としての日本列島が形成された。東北日本、西南日本の境界部には糸魚川‐静岡構造線が形成され、これに沿って東側にフォッサマグナが形成された。フォッサマグナは細長い凹地帯で、新第三紀中新世以降の厚い砕屑物が堆積した。南部フォッサマグナでは、伊豆‐小笠原弧が東北日本・西南日本境界部に衝突したことにより、大量の火山岩類と陸源堆積物が付加された。東北日本の日本海側は、西進する千島弧の外弧の影響で、かなり厚い地層の堆積場となった。北海道中軸山地の両側、山陰―北陸、九州北西部、瀬戸内、関東南部、西南日本の太平洋寄りの区域、琉球列島などに、時代によって位置を異にして、概して浅海性の堆積区ができた。秋田や新潟には油田が生まれた。房総半島の鴨川(かもがわ)ではまた、古第三紀の超塩基性岩が新第三紀に固体貫入している。量は多くないが、そこには新第三紀に海底噴出した玄武岩質火山岩類もある。花崗岩質岩は、日高山脈、東北地方日本海側からフォッサマグナや、屋久(やく)島を含めた西南日本外帯、甑(こしき)島、対馬(つしま)にある。千島から東北地方日本海側を経て伊豆に至る区域には安山岩類が広く分布し、海底噴出玄武岩類もわずかにみられる。また東北地方などには、安山岩活動に伴う黒鉱鉱床がある。このほか、山陰から九州北部にかけては陸上噴出の玄武岩があり、九州中部から琉球内弧には安山岩活動があった。瀬戸内火山岩類の活動は、東は関東の銚子(ちょうし)に、西は九州の佐世保(させぼ)付近に及んでいる。
[木村敏雄・村田明広]
地殻変動の歴史
日本列島区は古生代シルル紀から現在に至るまで絶えず地殻変動を受けてきた。シルル紀~デボン紀には飛騨帯と黒瀬川‐大船渡帯とは近接していたとみられるが、石炭紀のころに両者は分離して、中間に縁海を生じた。列島となった黒瀬川‐大船渡帯は、当時は比較的直線状の輪郭をもっていた。ペルム紀には、秋吉帯、舞鶴帯、超丹波帯と一部の秩父帯で付加体の形成があり、このとき沈み込んでいた海洋プレートは、ファラロンプレートとされている。この時期の花崗岩活動についてはよくわかっていない。
中生代三畳紀からジュラ紀にかけては、飛騨帯で高温型変成作用、三郡帯で高圧型変成作用、美濃‐丹波帯、秩父帯で付加体の形成があった。このとき沈み込んでいた海洋プレートはイザナギプレートである。白亜紀には、領家帯で高温型変成作用と花崗岩の貫入があり、三波川(さんばがわ)帯では高圧型変成作用があった。これらの変成岩の原岩は、いずれもジュラ紀の付加堆積物とされているが、四万十付加堆積物に対比される白亜紀の付加堆積物が多く含まれていることが明らかになってきた。これらの変動に引き続いて、西南日本内帯の広い範囲で花崗岩の貫入があり、大洋側の四万十帯北帯で付加体の形成があった。東北日本・北海道では、神居古潭(かむいこたん)帯と常呂帯の一部に高圧型変成作用があった。同時期の高温型変成作用はかなり離れた阿武隈(あぶくま)帯にみられ、花崗岩活動は阿武隈帯、南部北上帯、北部北上帯に広くみられる。このとき、大洋側の日高帯と常呂帯で付加体が形成された。四万十帯北帯と日高帯、常呂帯の付加体形成時に沈み込んでいた海洋プレートは、クラプレートである。
新生代古第三紀には、西南日本内帯の北部で広範な花崗岩の貫入がみられ、同時期の付加体は四万十帯南帯で形成されている。このとき沈み込んでいた海洋プレートは太平洋プレートとフィリピン海プレートである。よくわかっていない点も一部あるが、大洋側で付加体の形成があるときには、その大陸側で高圧型変成作用が生じており、さらに、大陸側では高温型変成作用および花崗岩の貫入が生じている。
ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、オホーツクプレート、そして太平洋プレートの四つのプレートの相互作用によって、琉球弧、西南日本弧、伊豆‐小笠原弧、東北日本弧、千島弧が存在するが、二つの弧の接合部では、屈曲や衝突がおこったり、大規模な凹地が生じたりしている。たとえば、西南日本弧と琉球弧の接合部の屈曲は、前者が時計回りに回転した結果であり、屈曲部の大洋側のフィリピン海プレート上には、九州‐パラオ海嶺が存在する。西南日本弧と東北日本弧の接合部は、伊豆‐小笠原弧の衝突によって屈曲などの大きな変形を受けていて、フォッサマグナを生じている。また、東北日本弧と千島弧の接合部では、千島弧の外弧が西方へ向かって東北日本弧に衝突しているために、日高山脈が形成されている。このように日本列島は、片側からつねに海洋プレートの沈み込みを受けることにより、異なる時期に異なったタイプの複数の変動を受けてきた。また、弧の接合部で変動を受けて複雑な造山帯を形成しており、ただ一回の造山運動で形成されたものではない。
[木村敏雄・村田明広]
地形
大地形の地形区
日本列島では岩石や地層の分布は複雑である。現在も地殻変動は顕著であるし、温暖でかつ降水量も多く、河川によるものなど水に伴う侵食、堆積(たいせき)作用が大きい。したがって、日本の地形は欧米のおもな地域とかなり違っている。いわゆる大陸的スケールの地形は少ない。
侵食、堆積を主原因とする地形と異なり、島弧、山地、盆地などの大地形の輪郭、分布と配列は、若い地質時代とくに新生代新第三紀以降の地殻変動によって大きく規制されている。したがって、大地形の地形区は新第三紀の地質構造区にほぼ相応する。しかし、丹沢山地と箱根・伊豆区域との境界は、地形区としては酒匂(さかわ)川にあるのに対して、地質区としてはそれよりも北に位置する神縄(かんなわ)衝上断層にあるように、地形区と地質区との輪郭は一致しないことが多い。
[木村敏雄・村田明広]
島々の輪郭
本州弧の輪郭の大要はいまから数千万年前の中生代白亜紀末ごろにできあがっている。その後、瀬戸内海や、半島、湾入、海峡などの形成によって、島々の輪郭の大要ができた。瀬戸内区が湖として形成され始めたのは新第三紀中新世の最末期で、それが海となったのは新第三紀鮮新世の末期である。半島と湾入には島弧にほぼ平行のものと大きく斜交するものとがある。それらの地形の多くは、新第三紀後期の隆起または相対的沈降によって生じている。島弧に平行な佐田岬(さだみさき)半島(愛媛県)、志摩半島(三重県)、渥美(あつみ)半島(愛知県)はこれらを連ねる長大な隆起帯に沿っている。青森県の津軽半島は背斜構造に基づいており、その東にある下北(しもきた)半島とともに陸奥(むつ)湾を抱いている。鹿児島県の薩摩(さつま)半島、鹿児島湾、大隅(おおすみ)半島は琉球(りゅうきゅう)弧に平行である。島弧に斜交する半島、湾入地区は普通、島弧方向の地殻変動をも受けているので、島根半島(島根県)、能登(のと)半島(石川県)のように島弧に平行の方向と斜交する方向とが重なった輪郭を示すものがある。この二つの半島の基本は、南北軸をもつ波曲的な背斜形成に伴って、鮮新世に生まれた。近畿地方南部の紀伊半島、高知県の室戸岬(むろとざき)半島、足摺岬(あしずりみさき)半島がそれぞれ南北に延びた輪郭をもち、これらの半島の間に一定の間隔をもって海峡や水道、さらに土佐(とさ)湾奥が配置することは、ほぼ同じ波長の南北性隆起・沈降軸があることを示す。この地区には南北軸波曲のほかに、佐田岬半島、志摩半島に示されるように東西性波曲もあった。これらの半島の南北軸波曲状背斜、土佐湾の湾入の形成はともに中新世に始まっている。東西性波曲は鮮新世に、海峡、水道の開通は鮮新世末期におこっている。
[木村敏雄・村田明広]
山地・盆地・平野
日本では山地や盆地の輪郭もまた新第三紀以降の地殻変動に規制されたものが多い。中央構造線、松山‐伊万里(いまり)線などに沿っては断層線崖(がい)が連続してみられる。そのほか山地と低地との境界にしばしば断層線崖がみられる。平野の多くもまた、地殻変動によって生じた大きい凹地に河川や三角州の堆積物が堆積してできている。
北海道の宗谷(そうや)岬から襟裳(えりも)岬に至る山地は、白亜紀の地質構造区とはやや斜交し、かつ東側に断層をもつ複合地塊として中新世中期に生まれた。天塩山地(てしおさんち)の東側の中央低地帯、日高山地の東の十勝(とかち)平野の前身の凹地も同じころ生まれている。札幌‐苫小牧(とまこまい)低地帯の前身の凹地はこれらよりも早く中新世初期に生じている。
東北地方では山地や盆地はその輪郭を南北方向と北北西―南南東との基盤構造に規制されている。周辺を中新世層に囲まれた旧期岩石からなる地塊として生成した北上高地(きたかみこうち)、阿武隈高地(あぶくまこうち)は、そのために、いびつな細長い菱形(ひしがた)をなす。一般には南北方向がより顕著で、奥羽山脈(おううさんみゃく)がその方向に長く延び、その西に横手盆地(秋田県)、新庄(しんじょう)盆地(山形県)がある。これらには新生代第四紀にも断層活動がおこった所がある。出羽丘陵(でわきゅうりょう)地区では南北方向は顕著でないが、その西に秋田平野がその方向に延びる。越後(えちご)平野地区も同様で、第四紀に及ぶ地塊隆起運動に伴って生じた背斜構造が細長い丘陵地形をつくる。関東山地は新第三紀初期には古い地層からなる地塊として生成した。その東の関東平野は新第三紀以降の東西性、南北性の複合凹地(関東堆積盆地)として生まれ、そこを地層が埋め立てて形成されている。その凹地形成は現在も進行している。
飛騨山脈(ひださんみゃく)、木曽山脈(きそさんみゃく)、赤石山脈は初めから雁行(がんこう)山脈として生まれたかの見かけを呈する。しかし、これらは伊那山地(いなさんち)とともに白亜紀にはすでに異なる地塊となっていた。鮮新世には、飛騨・木曽山地・三河(みかわ)高原と伊那・赤石山地とがそれぞれ大きくみて一体となって隆起している。能登半島から紀伊南部に至る能登‐潮岬(しおのみさき)複合波曲帯は、近畿中部では、琵琶湖(びわこ)などの中間凹地を含むものの鈴鹿山脈(すずかさんみゃく)などからなる南北性地塁帯となって、東西に走る瀬戸内凹地帯内の伊勢(いせ)湾、大阪湾周辺区域を分かっている。西南日本の東西性背斜状波曲として中国脊梁山地(ちゅうごくせきりょうさんち)、南部中国山地、讃岐(さぬき)‐和泉(いずみ)‐高見山地、祖母山(そぼさん)‐佐田岬半島‐剣山(つるぎさん)‐志摩半島を通る外帯北部隆起帯などがある。中国脊梁山地は中新世中期と後期との少なくとも二度の隆起をしている。ほかのものは中新世後期ないし鮮新世初期の隆起が顕著である。これらの隆起によって中国と四国との東西性脊梁山地が形成されている。九州では瀬戸内凹地帯の延長は鮮新世の別府(べっぷ)‐雲仙(うんぜん)陥没帯となって、それ以後の盛んな火山活動を促した。しかし、琉球弧に平行の九州の南北方向は、有明(ありあけ)海‐佐賀平野の起源としての凹地を含め、新生代古第三紀初期にはすでに生まれ始めている。
[木村敏雄・村田明広]
河川・氷河地形
湿潤な気候下にあり、かつまた氷期に氷河が発達しなかった日本では、谷川による下刻(かこく)作用と斜面に沿う表土や岩石の移動(マスムーブメントmass movement)によって谷地形がつくられている。下刻作用がとくに顕著におこった所では黒部川のように峡谷ができている。未風化の中・古生層など堅い岩石が分布する所に険しい地形ができている。氷河地形としては、日本アルプスや日高山脈にカールKar(ドイツ語、圏谷)やモレーンmoraine(堆石)が残されている。山地の多い日本では、北海道の石狩川のように平野を大きく蛇行(曲流)する川はまれである。しかし穿入(せんにゅう)蛇行が多いこと、とくに、江の川(ごうのかわ)などのように、河川流域の中途にできた隆起帯に穿入した川があることなどは、地殻変動が著しい日本の特徴である。
[木村敏雄・村田明広]
海岸
面積に比べて海岸線が長い日本では種々の海岸地形がみられる。三陸海岸のように高い海食崖(かいしょくがい)(海崖)が続く所がある一方、千葉県の九十九里浜(くじゅうくりはま)のように砂浜が長く続く所がある。堅い岩石が分布し、隆起運動が顕著で、かつ海食作用が強い外海に面した所では高い海食崖ができる。これに対して、柔らかい新第三紀層などからなる地域では高い海食崖はできにくい。大きい河川が多量の砂を供給し、かつ沿岸流が顕著な所に長い砂浜を生じている。海岸段丘(海成段丘)は日本の各地にあって過去の隆起を示す。北海道とくに北部ではあまり開析されない低い段丘が発達している。一方、リアス海岸は沈降を示し、京都府・福井県にまたがる若狭(わかさ)湾などにみられる。三陸にもリアス海岸があるが、ここには高い海岸段丘もある。異なる時期に沈降も隆起もおこったためである。
[木村敏雄・村田明広]
河岸段丘・山地小起伏面(平坦(へいたん)面)
第四紀に隆起がおこった場所が多い日本では河岸段丘も各地にみられる。利根(とね)川、信濃(しなの)川、木曽川など関東、中部地方に大規模なものがある。山地小起伏面も小規模なものは各地にある。大規模なものは福島県の阿武隈高地、中国山地にあり、「準平原」とよばれている。阿武隈高地は地塊となる前から白亜紀後期以後ずっと地表に現れており、長期間の平坦化を受けた。中国地方の小起伏面も、その平坦化は古第三紀にすでに始まっており、中新世を通じて進行した。脊梁山地が隆起したため、高い脊梁山地面とより低い広島県から岡山県にまたがる吉備高原(きびこうげん)面とに分かれたが、その後もそれぞれにおいて平坦化がおこっている。山地小起伏面はそのような長期間の平坦化作用の総決算である。
[木村敏雄・村田明広]
変動地形・火山地形
褶曲(しゅうきょく)運動、断層活動、火山活動が現在も進行しており、それによる地形を残しているのは日本の大きな特徴である。褶曲や傾動が完新世の現在も進行している活褶曲は、信濃川や東北地方日本海側の大きい河川の河岸段丘の傾き方によって知られている。断層活動による変位地形は岐阜県南東部の阿寺断層(あてらだんそう)などに表れており、多くの活断層の存在が知られている。四国の中央構造線活断層系や兵庫県の山崎断層などの横ずれ活断層は、直線的な谷地形をつくっており、人工衛星からの画像でも明瞭(めいりょう)に認められる。1891年(明治24)の濃尾地震の際の根尾谷断層(ねおだにだんそう)や、1995年(平成7)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の際の野島断層のように、地震の際に断層崖ができたり、石垣が横ずれした地震断層の例もある。ただ、日本では侵食や堆積の作用が大きいので、断層崖が地すべりをおこして緩斜面になったり、侵食によって崖(がけ)が後退したり、埋め立てられたりしていることが非常に多い。
断層面が露出して崖となっている場合は断層崖(だんそうがい)であるが、断層崖が侵食されて後退していると、断層線崖として認識されることになる。山地と平野の境が直線的である場合には、活断層が存在していることが多く、たとえば四国の讃岐(さぬき)山地(阿讃(あさん)山地)と吉野川平野の境には中央構造線活断層系が通っている。四国や紀伊半島の南岸では隆起に伴って海岸段丘が多く形成されている。四国の室戸岬周辺では、標高180メートル程度の高さに約12万年前に形成されたと考えられる段丘面が存在する。これより低い標高にも複数の段丘面が形成されており、古い段丘面ほど高い位置にある。
火山には富士山、開聞岳(かいもんだけ)のような成層火山、有珠火山(うすかざん)のように溶岩円頂丘をもつ火山がある。八幡平(はちまんたい)は楯状(たてじょう)火山であるといわれる。男鹿(おが)半島の一ノ目潟(いちのめがた)はマールmaar(爆裂火口)である。成層火山が火砕流の大噴出をおこして陥没による大火口ができると阿蘇山(あそさん)や十和田湖(とわだこ)のようなカルデラcalderaができる。このような陥没大カルデラは二つの島弧が合する地域に多い。磐梯山(ばんだいさん)のように大爆発による火口を残すものもカルデラとよばれる。火山は侵食量よりも噴出物の供給量が大きいことにより形成され、かつその形が保たれる。活動がやんで噴出物の供給がなくなると急速に侵食が進行する。
[木村敏雄・村田明広]
土壌
土壌は地球の岩石圏の表面が長い年月の間に風化して生じたものである。したがって、地表が削られたり、あるいは新しい崩土で覆われたりする不安定な場所には、成熟した土壌は生じない。台地や丘陵の平坦部のほか、急斜面を除く山地に、数千年来風化作用を受けてきた地表の物質が成熟土としての特徴を現している。風化(土壌化)の仕組みを決定する最大要因は気候であり、気候の地域的違いに対応して土壌が類別される。そのようにして分類される土壌、すなわち成帯性土壌は、日本の国土内で数種類が分類される。
[浅海重夫]
成因論的分類
温帯湿潤気候に属する日本でもっとも広く分布する成帯性土壌は褐色森林土である。広葉樹または混交林の植生に対応し、鉄分の酸化物による褐色土層で特徴づけられたこの土壌は、ヨーロッパの同種土壌に比較してカルシウム分などの溶脱が強く、酸性に傾いている。日本の降水量が概してヨーロッパの2倍近くあるためとされる。針葉樹林下に発達するといわれるポドゾルは、日本では北海道と青森県の低い山地丘陵、および海岸砂丘にみられる。しかし、タイガ地方の典型的ポドゾルより発達度は弱く、かつ広域の分布をなしていない。中部山地の亜高山帯にはさらに局地的ながら、灰色溶脱層の明らかな山岳性ポドゾルがある。
一方、温暖気候に対応する成帯性土壌は赤黄色土で、南西諸島に生成している。酸化鉄・水酸化鉄の顕著な集積による赤みの強い酸性土壌である。しかしこのアリット化作用allitizationとよばれる風化作用の終局段階で生成されるラトソル(台湾以南に分布)は、日本には存在しない。東海地方以西の台地と丘陵平坦部にも赤黄色土とみなされる土壌がある。これは、その生成期が過去の地質時代(新生代第四紀の間氷期)の温暖期にさかのぼるとして、古土壌の一種と考えられ、遺物土壌(レリクトrelict)であって分布も断続的である。褐色森林土と現生の赤黄色土との移行地帯に、両型の中間的性質をもつ黄褐色森林土の存在を指摘する見解がある。
地球的分布で論ずるときに重要な位置を与えられる草原土(チェルノゼムなど)は、日本の気候下に存在しない土壌の一つである。もちろん砂漠土もありえない。ただ、考古学遺跡と出土層の研究で、縄文時代以来の生業(カヤ場、焼畑、放牧など)がかなりの広域に二次植生としての草地をつくり、火山灰被覆地域にみられるチェルノゼム類似の厚い腐植土層を生じさせたのではないかとの推論がある。
火山活動の盛んな日本の国土は、その過半が風成火山灰に覆われている。火山灰域内のとくに平坦地や緩斜面の土壌はアンドソルとよばれ、気候に対応する成帯土壌群から除外されて、成帯内性土壌(または間帯土壌)とみなされている。その理由は、母材であった火山灰物質の主成分の二次生成鉱物(非晶質のアロフェンなど)が、他の岩石の風化物にない特性をもつことに由来して、母材の性質が強く長く残っている土壌とみなすからである。また、イネ科植物の分解遺体から生ずる腐植物質が活性アルミニウムと結合し、厚層をなして集積するという生成過程も特異的である。火山灰土壌(アンドソルに、未成熟火山放出物風化土壌を含める)は日本の土壌の特色をなすもので、その分布は北海道のほぼ南半全域、東北・関東地方の平野・盆地・丘陵の全部、中部地方の東半分、中国地方の北東部、北九州以外の九州各地に及ぶ。また、火山灰被覆地と周辺の沖積低地には二次火山灰堆積物が混合した土壌があるため、影響はさらに広い範囲に及んでいる。先述した褐色森林土をはじめ成帯土の分布域は、火山灰降下地域のアンドソルによって著しく狭められている。
沖積低地の土壌は氾濫(はんらん)原堆積物の表面に生成中の未成熟土といえるが、土壌型の特性を決める一つの断面層位として、地下水位の浅い土地に発現するグライ層の存在が取り上げられる。そこで、沖積地および同じ地下の水環境をもつ高冷地の緩斜面や台地上の凹地などに、グライ性土の分布が認められる。古来水稲栽培の好適地となっている沖積低地が水田開発され、そこに人為改変型の水田土壌が生じた。灌漑(かんがい)施設を施された台地や段丘上にも水田土がある。その特徴は、夏の冠水期間に表面水型グライ土が発現したことに示される。沼沢地が乾陸化したあとの湿原には、泥炭の集積による水生植物の遺体を母材とした泥炭土、または黒泥土が生じている。広域に分布するのは北海道の石狩川・天塩川・十勝川流域や根釧(こんせん)台地、青森県の津軽平野などで、小域の分布は千葉県九十九里平野や静岡県浮島沼などの海岸の堤間低地に、また秋田・岩手県境の八幡平(はちまんたい)、長野県の霧ヶ峰などの山頂平坦地にみられる。
最後に、生成分類論では非成帯性土壌として一括される土壌がある。それぞれの土壌型としては、高山や急崖の裸岩地を薄く覆う未風化のリソソル、植生を欠く砂丘や砂州のレゴソル、活火山麓(ろく)に降下した新期粗粒火山砕屑(さいせつ)土などが分類され、いずれも断面形態の特徴を備えていない未熟土である。
[浅海重夫・渡邊眞紀子]
気候
日本の気候は四季の移り変わりが明らかなことで特徴づけられる。熱帯は一年中高温で、1年の間に、夏と冬というような半年の周期で繰り返す気温の波はない。むしろ、1日のうちで夜と昼の差が熱帯では明らかである。世界中には、また、雨季と乾季で季節が区別される所もある。あるいは、季節風によって1年の周期が規定されるような地域も多い。一方、高緯度地方は長い冬と短い夏だけで、春と秋を欠く。
わが国の気候は、こういう世界のいろいろな気候に比較すると、春夏秋冬の気温の変化が明瞭(めいりょう)で、それに加えて梅雨、秋雨、台風の季節というような雨季があって、まことに豊富で多様な気候を備えている。日本国民は、こういう意味では気候を楽しんでいるといってもよかろう。もちろん、これから述べるように、洪水、強風、豪雪、冷夏など、さまざまな気象災害も多い。人命さえも失われることがまれでない。
[吉野正敏]
春
1年の12か月を4等分したときには、3、4、5月を春とするが、気圧配置暦、つまり、それぞれの季節を性格づける気圧配置型の出現頻度からみてつくった暦からみると、春は3月1日から5月21日までとされ、このなかを細分すると、初春が3月1日から17日、春が3月18日から5月4日まで、晩春が5月5日から21日までである。気温は一進一退を繰り返しながら上昇する。一つの低気圧の通過するごとに暖かくなる。4月3、4日、21、22日ごろは曇りか雨が多く、後者を「菜種梅雨(なたねづゆ)」とよぶ。5月2、3日ごろの移動性高気圧に覆われた明け方には放射冷却で冷え込み、中部日本では霜が降り、「八十八夜の別れ霜」とよび、養蚕が盛んであったころはクワの凍霜害が心配された。最近でも果樹などのつぼみや茶の新芽に凍霜害がある。
[吉野正敏]
夏
気圧配置暦からは、初夏は5月22日から6月10日、梅雨が6月11日から7月16日、夏(盛夏)が7月17日から8月7日、晩夏が8月8日から20日までとされる。新緑の候が、しだいに濃い緑に包まれる。鳥や昆虫の動きが活発になり、木々の花が盛りを過ぎるころには梅雨の空となる。5月もなかばとなると「走り梅雨」が沖縄からの便りに聞かれる。6月11日からとされる梅雨は、もちろん西南日本ではもっと早く、東北日本ではもっと遅くなる。これは前線帯が北上するのに時間がかかるためである。また、梅雨は年による差が大きく、同じ土地でも、早い年・遅い年の差があり、雨の降り方も著しい差があるのが特徴である。7月になると「梅雨末期の集中豪雨」があり、九州や山陰から北陸・東北地方にかけての日本海側では集中豪雨による被害も大きい。例年は7月17日から小笠原(おがさわら)高気圧に覆われた真夏または盛夏とよばれる、高温で多湿の季節を迎える。このころ海岸部では海陸風が発達する。8月6日ごろにはいったん小笠原高気圧の勢力が弱って、暑さが弱まるが、その後また暑さが戻り、これを残暑という。日本の南には台風が現れ、西南日本を襲う。
[吉野正敏]
秋
気圧配置暦からは、初秋は8月21日から9月11日、秋雨は9月12日から10月9日、秋は10月10日から11月3日、晩秋は11月4日から25日までとされる。8月下旬には台風が本土に上陸することが多く、初秋は台風の季節でもある。しかし、台風一過、秋晴れとさわやかな涼しさを迎えることが多い。秋雨は、本来は梅雨と対をなす前線帯に伴う陰うつな天候の季節であるが、台風活動と重なると、大雨が降り自然災害をもたらす。
10月中・下旬は秋たけなわ、日本では最良の天候を迎える。秋晴れの好天、暑くもなく寒くもなく、収穫、秋祭、スポーツで代表される。11月3日は文化の日であるが、気候の立場からは移動性高気圧に覆われて好天になる確率が非常に高い日である。11月4日以降は北国からは雪便り、中央日本でも初氷の報告が珍しくなくなる。
[吉野正敏]
冬
気圧配置暦で特徴ある「西高東低」の冬型気圧配置の頻度からみると、初冬は11月26日から12月25日、冬(真冬)は12月26日から1月31日、晩冬は2月1日から28日までとなる。
冬の季節風がしだいに勢力をつけ、日本海側では雪の季節となり、海は荒れる。それと対照的に太平洋側では晴天が多くなり、山間地では気温の逆転によって、気温の低い空気がたまる状態、すなわち冷気湖(寒気湖ともいう)が発達し、明け方、霧が出ることが多い。日中は晴れる。
クリスマスごろ、寒さが弱まることが多い。これは全世界的なものである。正月休み後からは寒さが厳しく、日本海側の積雪は日ごとに深くなる。スキー・シーズンである。豪雪地帯では雪に悩まされる毎日を送らなければならない。2月4、5日ごろは冬型気圧配置の出現頻度が少なく寒さが弱まることが多いが、その後、「寒の戻り」となって、厳しい冬に逆戻りする。2月も下旬になると、日中の長さが長くなってくるのにつれて、早くも西南日本からは春便りがやってくる。
最近、地球の気候の温暖化により、暖冬や暑夏の年が多くなってきた。それに伴い、季節の推移は、春が早く、秋が遅れがちである。
[吉野正敏]
海洋
日本付近の海況
日本列島は、熱帯から亜寒帯まで2400キロメートルにもわたって南北に長く連なる。したがって、海洋の亜熱帯循環と亜寒帯循環とによる両方の海流が日本近海を流れ、しかも太平洋の西縁部にあたるので西岸強化作用を受け、強い流れとなっている。
亜熱帯循環に乗って、日本付近を南から北上してくるのが黒潮であり、亜寒帯循環に乗って北から南下してくるのが親潮である。
[安井 正]
黒潮と親潮
黒潮は、日射が強く、大陸から遠く離れて陸水の流入のない赤道海域に源を発するので、高温(22℃以上)、高塩分(約34.8)で、微細な泥砂やプランクトンも少なく、著しく透明で濃碧(のうへき)色を呈する。これに対し親潮は、寒冷で大陸に近いベーリング海に端を発し、河川水の流入の激しいオホーツク海の海水を合しているので、低温(中心部約2℃)、低塩分(33.5以下)のうえに、陸地からの細かい土砂やプランクトンも多く、透明度は小さく、緑ないし青緑色をしている。したがって、黒潮と親潮は、船上から一見して識別できる。黒潮と親潮の間には両者が混じり合ってできた、中間の性状(水温10~15℃、塩分34.0前後)の水塊が介在する。三陸沖には、これらの水塊が大きさ十数キロメートルから数百キロメートルの渦をなして東西に並び、たいへん複雑な海況を示す。この部分は混合水域とよばれ、混合水域と黒潮域の間には黒潮前線、親潮域との間には親潮前線と名づけられる明瞭な潮境が生ずる。
太平洋側の1500メートル以深には、低温(約1.6℃)、高塩分(約34.65)、貧酸素(海水1リットル当り2ミリリットル以下)のきわめて均質な海水がある。大西洋の両極海域で沈降した海水が、はるばるとオーストラリアの南を迂回(うかい)し、海底に沿って流れてきたもので、北太平洋深層水と名づけられている。塩分の高いこの深層水と表層の黒潮との間に、親潮前線から塩分の低い親潮系の海水が潜り込み、南のほうまで延び出し、亜寒帯中層水とよばれている。
東シナ海の黒潮の一部は北東進を続け、朝鮮海峡から日本海へ流れ込み、対馬暖流(つしまだんりゅう)となって蛇行しながら本州沿岸部を北上し、約半分は津軽暖流として津軽海峡から太平洋へ、残りの大部分は宗谷暖流(そうやだんりゅう)として宗谷海峡からオホーツク海へ流れ出し、流域沿岸部の冬季の温暖化をもたらしている。しかし、日本海は外界とつながる海峡が狭く浅いために、その他の海水交換がなく、その形状は池に近い。とくに深さ300~400メートル以深、日本海全体の約84%は、毎冬にシベリア沿岸部で冷却されて沈降した、低温(0.5℃)、低塩分(34.1)、豊酸素(海水1リットル当り5.2ミリリットル)の日本海固有水と名づけられた著しく一様な海水で占められ、太平洋側と対比をなしている。
オホーツク海では、アムール川河口付近の海水は著しく低塩分(33.0以下)で冬季には結氷し、東樺太(からふと)海流に乗って北海道にまで押し寄せ、北東海岸を流氷で埋め尽くす。この地域は世界中でもっとも低緯度の流氷地帯として有名である。
このように、日本付近では、性質の著しく違う水塊が複雑な海況を呈している。このため流路や潮境の位置が変わると、その場所の水質はがらりと変わり、社会生活に大きな影響を及ぼし、海況異変ととらえられる。
黒潮には、四国沖から房総沖にかけて岸近くを流れるケースと、四国沖で南転し、紀州沖で岸から350キロメートル以上も南を迂回するケースの二つがある。1906年(明治39)から1996年(平成8)までの間に迂回コースは8回現れた。いったんどちらかのコースをとると、10年以上も継続することもある。岸近くを流れれば沿岸部まで高温、高塩分であるが、迂回コースをとれば流路の内側には低温、低塩分の下層の海水が湧き上がってくる。どのような原因で、どちらのケースをとるかには諸説があるが決定するには至っていない。
同じように親潮にも、約10年に一度ぐらいの割合で、混合水域を押しのけて、本州東岸沿いに南の方まで枝状に伸びだす現象が認められている。とくに1963年(昭和38)や1983年(昭和58)には、先端が犬吠埼(いぬぼうさき)沖まで達し、利根川にサケが現れたり、アワビやウニが海岸に打ち上げられたりの異変を生じた。シベリア高気圧の発達による季節風の影響と考えられている。
日本は四面を海に囲まれているので、産業や経済は海に依存するところが大きい。潮境が変われば生息する魚種が変化するばかりでなく、生態系に影響が出て個体数にも大きな増減が表れ、漁獲量の違いとなる。海流が変わると、輸出入品の輸送にあたる船団の経費に響き、水温そのものが変わるだけでも気候や気象に影響する。したがって、海況の現状を知り将来を予測して上手に利用する必要がある。気象庁では北太平洋の水温および表面海流の現況と予報図を、毎日、ホームページで公開していて、各方面で活用されている。
[安井 正]
植物相
植物相(フロラflora)とは、ある地域に生育している植物の種の総体をいう。高等植物だけに限ってみると、世界には25万の種があると推定されているが、日本の植物相は約4500の種(被子植物3950、裸子植物40、シダ植物500)によって構成されている。また、日本に産する裸子植物、被子植物の約40%にあたる1600種は日本の固有種である。日本での種数を約4000、固有種を300とする説もあり、学者によって見解は異なる。なお、環境庁(現、環境省)が資源環境保全のための基礎調査の結果として発表した『植物目録修正版』(1994)では、約7931種(亜種、変種を含む)を掲げている。種数が大きく食い違うのは帰化植物を含むためである。いずれにしても、種の数が多いほど、その植物相は多様性に富んでいる、あるいは単に豊かであると表現できる。日本とほぼ同緯度にあり、面積的にも似通った北アメリカ北東部の高等植物相は2835、ニュージーランドは1871の種からなるが、これらの地域と比べた場合、日本の植物相は多様性に富んでいるといえる。しかし、近年の低湿地などでの開発や山草業者の乱獲により、自生植物のおよそ3分の1が絶滅の危機にさらされている。そのうち、カミガモソウ、ナルトオウギ、タカノホシクサなど35種は、すでに絶滅したとみられる。
[大場秀章]
日本の植物相の起源
日本の植物相の起源とその形成過程についてはまだ不明の部分が多い。植物区系でみると、南北に長い日本列島を旧熱帯区系界と全北区系界の境界が横断している(区系とは、その起源と成立の歴史を異にしているとの仮定に基づいて設定される概念である)。琉球(りゅうきゅう)諸島、小笠原(おがさわら)諸島、南鳥島(マーカス島)は旧熱帯区系界に属し、前二者は東南アジア区系区に、後者はメラネシア・ポリネシア区系区に分類される。これらの地域を除く日本の全域は全北区系界に入るが、異なる三つの区系区が水平・垂直的に重層している。すなわち、各地の高山帯は極地・高山区系区、北海道北東部は東シベリア区系区、それ以外の大部分は日華区系区に属する。日本において、チシマアマナやヒゲハリスゲなど、極地に類縁関係のある植物がみられるのは、過去の氷期に南下した極地の植物が高山帯に残存しているためである。東シベリア区系区に分類される北海道北東部の植生はタイガに比することができ、それを構成する種には樺太(からふと)(サハリン)や沿海州と共通のものが多い。九州、四国、本州、北海道(北東部を除く)の植物相は、多少とも地方的な特色を有するものの、基本的な構成において共通していると考えられ、全体として日華区系区に含められる。日本の植物相が多様な理由の一つは、複数の起源の異なる植物相が重層しえた日本の地理的位置、地形に由来するためである。
[大場秀章]
日華区系区
日華区系区は比較的起源の古い植物を数多く含んでいる。この区系区内には10の固有な科があり、そのなかには、カツラ科のような被子植物としては特異な無道管植物が含まれる。さらに、イワユキノシタ属、ギンバイソウ属、クサアジサイ属、チャボツメレンゲ属、アオキ属など多数の固有属がある。一方、日華区系区に産するカヤ、サンカヨウ、ツバメオモトなど350以上の属は、北アメリカにも分布するものである。日華区系区に固有な科のうち、コウヤマキ科とシラネアオイ科は日本特産である。さらに日本の固有属としては、オサバグサ、ホツツジ、クサヤツデ、オゼソウなど22属がある。日本の固有科・属はいずれも遺存的性格が強く、日本は日華区系区の植物相の起源の地というよりは、島という特殊な環境にあって相対的に起源の古い種を温存してきたと考えられる。
日本では、さらに地方ごとの特色に基づいて地方的な植物区系の区分が試みられている。一例をあげれば、ハイイヌガヤ、トガクシショウマ、ユキツバキ、ケハギなどは日本海側の多雪地帯に分布する種で、このような種の存在によって日本海区という区系が設けられている。日本の地方的な区系の多くは気候的な特性を反映したものである。地方的な固有種、変種にはケハギやハイイヌガヤのように環境に適応して新たに誕生したと推定されるもの(新固有という)もある。
[大場秀章]
気候変動と植物相の多様化
過去の気候変動に伴い、日本をはじめ世界各地において植物相の北上、南下などの移動、分散、隔離の現象がおこった。この過程で絶滅に追い込まれた種もあるが、一方では環境の激変に適応した新しい種の形成が行われた。ヨーロッパでは、第四紀の氷期における植物相の南下がアルプス山脈によって阻まれたため、アルプス以北では、それまでに発展を遂げた植物相は壊滅的な打撃を被ることとなった。これに対して、日本や北アメリカ東部では、山地が氷期における植物相の南下の妨げとはならず、また、複雑な地形が局所的な植物の避寒場所ともなったため、植物相の全滅は回避することができた。これが、日本の植物相がヨーロッパの同緯度地域と比べものにならないほどの多様性をもつに至ったゆえんである。
日本は島国であるが、植物相が多様性をもつのは、大陸から北方系ばかりでなく南方系の新しい植物が渡来し、それらが定着、あるいは固有植物へと進化したためと推定される。南方系の植物の渡来の過程は、以下のように推定される。(1)間氷期における大陸では、南方系の植物相が北方へ向けて分布を拡大するが、海面上昇のため、日本のような島への移動は容易ではない。(2)氷期になると、これらの植物相はふたたび南方へ退却するが、このとき、氷期の海面低下に伴う属島の大陸への連繋(れんけい)が生じ、日本などの島へも大陸の植物の移動が行われる。以上のような経過を経て、日華区系区を特徴づける種の一部が日本に渡来したと考えられるわけである。つまり、間氷期の北上と氷期の南下、およびそれらに伴う分断や隔離が、日本列島内におけるローカルな固有種や固有変異の形成をも促進したと考えられる。上述の過程によって、冷温帯に起源をもつ伊豆諸島や屋久(やく)島高地に産する固有種の形成が説明できる。
[大場秀章]
植物相の形成と散布
植物の種子、果実などの散布体は、海流や風、あるいは鳥などの動物によって運ばれるものが多い。小笠原諸島の最南端に位置する南硫黄(みなみいおう)島の山頂には、他の小笠原の島々には分布しない本土との共通種(ガクアジサイ、オニヒカゲワラビなど)があるが、これらは、風によって運ばれた散布体が定着したものと考えられる。こうした散布体は、温度、水分、土壌などの環境条件が適せば発芽、定着する。また、海に囲まれ、雨に恵まれた島国である日本では、とくに温度の勾配(こうばい)が種の分布範囲の決定に大きく関係している。たとえば、年最低気温が平均零下3.5℃の等温線は、本州南岸線(ハマオモト線)とよばれ、この線を分布の北限とする植物に、ナチシダ、ハマオモト、イヌガシ、ウバメガシなどがある。また、暖温帯林は、この線を越え、最寒月の平均気温が0℃の等温線まで北上し、ここを北限とする。植物が「気候を読む物差し」といわれるのは、このような等温線を分布の北限や南限とする種が多いためである。
一方、生態学的な立場からは、飽和状態にある植物相のなかに、新参の種が定着できる可能性は低いといわれている。つまり、気候変動や火山の誕生などによる植物相の攪乱(かくらん)や空白地帯の出現といった植物相の不飽和状態が生まれて、初めて新参の種が定着できるというわけである。たとえば、小笠原諸島の新しい火山島である南硫黄島は、起源の古い父島や母島とは異なり、いまだ植物相が生態的な飽和状態には達していないため、今後も新たな種が分布する可能性があると考えられる。
[大場秀章]
二次的種分化
遺存的な種の一部は、染色体数の倍化のほか、さらに他の近縁種と交雑して、その遺伝的な適応力を増したり変化させたりして繁栄している。全般的な傾向としては、極地や高地の植物ほど倍数化が進んでいるといわれている。日本でも、ノガリヤス、エンレイソウ、トリカブト、キクなどといった多くの属で、このような倍数化と雑種形成による種分化が確かめられている。染色体数の倍数化や雑種形成による新しい種の形成を「二次的種分化」とよぶが、こうした種の形成が、日本の植物相をいっそう複雑多様なものとしていくわけである。
[大場秀章]
動物相
日本列島はアジア大陸の東縁に、北緯20度から45度にわたって南北に連なり、生態的条件ならびに地史が複雑なため、動物相(ファウナfauna)は比較的多様で、列島の中部と北部を占める地域は旧北区に、南部は東洋区に属する。両区の境界は、両生類、爬虫(はちゅう)類、哺乳(ほにゅう)類などでは七島灘(なだ)付近(渡瀬線(わたせせん))にあるとみなされるが、昆虫のチョウ類では大隅(おおすみ)半島と種子島(たねがしま)の間(三宅線(みやけせん))、鳥類では琉球(りゅうきゅう)諸島と先島(さきしま)諸島の間(蜂須賀線(はちすかせん))にあるといわれ、一致した見解がない。これは、日本の陸生動物に、海を越えて移動する能力が低く地史の影響が強いもの(陸生哺乳類、両生類など)と、移動力が強く海流や風の影響が強いもの(鳥類、飛翔(ひしょう)する昆虫など)とがあり、進化速度も分類群によって異なるためと考えられる。
[今泉吉典]
東洋区に属する地域の動物
渡瀬線以南の南西諸島には固有属や固有亜属に属するものが多い。哺乳類のアマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、イリオモテヤマネコ、鳥類のノグチゲラ、両生類のオットンガエル、ホルストガエルがこれにあたる。アマミノクロウサギとイリオモテヤマネコは新生代第三紀後期に東アジアから渡来した古い種と推定され、ルリカケスなどと同じく旧北区系と考えられる。固有種はさらに多く、哺乳類ではオリイジネズミ、リュウキュウイノシシ、イリオモテキクガシラコウモリ、鳥類ではルリカケス、ヤンバルクイナ、爬虫類ではクロイワトカゲモドキ、アオカナヘビ、キシノウエトカゲ、サキシマアオヘビ、ガラスヒバァ、ハブ、サキシマハブ、イワサキセダカヘビ、両生類ではナミエガエル、イシカワガエル、イボイモリ、シリケンイモリなどがある。このほか東洋区系のものに、哺乳類ではカグラコウモリ、クビワオオコウモリ、オナガジネズミ、鳥類ではカンムリワシ、オオクイナ、シロガシラ、ズアカアオバト、キンバト、爬虫類ではセマルハコガメ、キノボリトカゲ、ホオグロヤモリ、ヒャン、サキシマスジオ、メクラヘビ、両生類ではアイフィンガーガエル、ハナサキガエル、無脊椎(むせきつい)動物ではヤシガニ、アナジャコ、サソリ、サソリモドキ、ヨナクニサンガ、オオゴマダラ、ツマベニチョウ、コノハチョウなどがある。
小笠原(おがさわら)諸島には固有属のメグロ、オガサワラマシコ(絶滅)のほか、固有種のオガサワラオオコウモリ、オガサワラカラスバト(絶滅)、オガサワラガビチョウ(絶滅)などが分布する。
[今泉吉典]
旧北区に属する地域の動物
屋久(やく)島以北の日本はすべて旧北区に属するが、北海道の動物相は沿海州のものに酷似するので、ここを北海道地区、本州、四国、九州とその属島(佐渡島、隠岐(おき)諸島、壱岐(いき)、種子島、屋久島など)を本土地区として区別する。両地区の境界線がブレーキストン線である。対馬(つしま)の陸生哺乳類は約半数が本土系、ほかが朝鮮系であるから、ここを対馬地区とする。北海道地区には、ムクゲネズミ、エゾサンショウウオなど少数の固有種のほか、ヒメネズミ、トカゲ、カナヘビ、アオダイショウ、シマヘビ、ジムグリなどの本土系の日本固有種も生息する。しかし、ここの大多数の動物は沿海州系である。哺乳類ではエゾシカ、ヒグマ、キタキツネ、エゾオオカミ(絶滅)、クロテン、キタリス、シマリス、エゾモモンガ、エゾヤチネズミ、ヒメヤチネズミ、ユキウサギ、ナキウサギ、ヒメトガリネズミなど、鳥類ではシマアオジ、ノゴマ、クマゲラ、ヤマゲラ、ミユビゲラ、ミヤマカケス、エゾライチョウ、タンチョウ、シマフクロウ、オオワシなど、両生類ではキタサンショウウオ、エゾアカガエル、昆虫類ではウスバキチョウ、アサヒヒョウモンなどがそれで、本土に普通のイノシシ、カモシカ、ムササビ、ニホンザル、モグラ属、キジ、ヤマドリなどをみない。
本土地区には固有属としてヒミズ、ヤマネ(両属とも西ヨーロッパの中新世から近年発見された)、ヒメヒミズ、オオダイガハラサンショウウオなどを産するほか、固有種が多い。哺乳類ではカモシカ、ニホンオオカミ(絶滅)、ツキノワグマ、テン、イタチ、ニホンカワウソ(絶滅)、ニホンザル、ニホンリス、ホンドモモンガ、ムササビ、アズマモグラ、カワネズミ、ハタネズミ、スミスネズミ、カゲネズミ、アカネズミ、コキクガシラコウモリ、コテングコウモリなど、鳥類ではヤマドリ、アオゲラ、爬虫類ではシロマダラ、両生類ではイモリ、オオサンショウウオ、クロサンショウウオ、そのほか多数のサンショウウオ類、カジカガエル、モリアオガエル、タゴガエルなどが固有種である。朝鮮半島や中国と共通の種は、鳥類ではトキ、コウノトリ、オシドリ、アカゲラなどごく普通で、爬虫・両生類でもタカチホヘビ、ヒバカリ、ヤマカガシ、マムシ、ニホンアカガエル、トノサマガエル、アマガエル、ツチガエルなどをみる。しかし、哺乳類では少なく、家ネズミ、コウモリ類、カヤネズミなどがあるにすぎない。高山帯にはツンドラ系のライチョウ、タカネヒカゲなどが遺留分布する。ムカシトンボ、ガロアムシなどは古い時代の生き残りで「生きている化石」といわれる。また、外国から人為的に移入したものが野生化した「帰化動物」には、ヌートリア、マスクラット、チョウセンイタチ、コジュケイ、カササギ、ウシガエル、ソウギョ、アメリカザリガニなどがある。
対馬地区には本土系のヒミズ、ヒメネズミ、アカネズミ、ツシマテンなどと、朝鮮半島系のツシマヤマネコ、チョウセンイタチ、コジネズミ、クロアカコウモリ、キタタキ、アムールカナヘビ、スベトカゲ、アカマダラ、チョウセンヤマアカガエルなどを産する。しかし、ツシマジカ、クチバテングコウモリ、ツシマサンショウウオ、ツシマアカガエルなどの固有種もある。
なお、海生動物の分布は、日本近海の海流(暖流、寒流)の影響を受けて複雑であるが、一般に太平洋沿岸では金華山か銚子(ちょうし)沖付近(オットセイの回遊南限)、日本海沿岸では能登(のと)半島沖が南北両系種の分布境界とみなされている。日本固有のものとしては世界最大のタカアシガニが著名で、岩手県以南の50~200メートルの海底に生息する。相模(さがみ)湾などのラブカ、北海道以南各地沿岸のギンザメ、瀬戸内海のカブトガニ、和歌山県沿岸のオキナエビスなどは「生きている化石」として知られる。
[今泉吉典]
菌類相
日本の菌類相(ミコラmycora)を構成している菌類は、次のように区分される(本郷次雄「日本産ハラタケ目の地理的分布」の区分法による)。
(1)世界的広分布菌類 腐生菌が多いが、寄生菌も含まれる。分類的には、変形菌類のほか、卵菌類のミズカビ目、接合菌類のケカビ目、不完全菌類などのカビの仲間、子嚢(しのう)菌類のウドンコカビ目・マメザヤタケ目・チャワンタケ目、担子菌類のクロボキン目・サビキン目、およびキツネノコンニャク、スエヒロタケ、ナギナタタケ、アンズタケ、ハラタケ、ヒトヨタケ、イヌセンボンタケ、イタチタケ、ツチグリ、ホコリタケなどのキノコがある。
(2)北半球分布菌類 この仲間は比較的少数であり、ヌメリイグチ、ヤグラタケ、スギヒラタケ、タモギタケ、コガネタケ、クギタケなどがある。
(3)ヨーロッパ・アジア分布菌類 この仲間にはアミタケ、オウギタケ、ムレオオフウセンタケ、および温帯林のブナに生ずるサルノコシカケ類などが含まれる。
(4)北アメリカ・東アジア分布菌類 この仲間には亜寒帯針葉樹林のサルノコシカケ類(たとえばマツ属の樹幹に生ずるヒトクチタケ)や、オオキノボリイグチ、フサクギタケ、温帯のベニハナイグチ、キイロイグチ、アケボノアワタケ、セイタカイグチ、キリノミタケなどがある。
(5)東アジア分布菌類 この仲間にはアカヤマドリタケ、マツタケ、ツキヨタケ、コガネテングタケ、キハツタケなどがある。
(6)東南アジア分布菌類 この仲間にはカゴタケほか、温・暖帯針葉樹林のサルノコシカケ類などがある。広葉樹のコナラ属の樹木に寄生するサルノコシカケ科のキノコは、世界に17種があり、そのうち、日本には11種、東南アジアには5種がある。また、暖帯林に多いクロニガイグチ、ムラサキヤマドリタケ、カブラテングタケ、ヒメベニテングタケなどは、氷河期以後に常緑広葉樹のカシ類とともに南から北へと分布が広がったといわれている。
(7)亜熱帯・熱帯分布菌類 この仲間は琉球諸島、小笠原諸島などに多い。子嚢菌類ではカキノミタケ、担子菌類ではアラゲキクラゲ、シママンネンタケ、アミヒカリタケ、ヤコウタケ、ダイダイガサなどである。
(8)寒帯または高山帯分布菌類 日本には寒帯も高山帯もないが、これに属する菌類があるとも考えられる。しかし、現在のところほとんど未調査の状態である(厳密には、日本の中部高山は亜高山の低木帯であって亜寒帯に相当する)。
(9)日本特産菌類 現段階で特産と考えられる菌類には次のようなものがある。子嚢菌類ではタマカビ目のトラフタケキン(虎斑竹菌。ナリヒラタケに寄生)、担子菌類ではマツノコブビョウキン(サビキン目)、ヤブシメジ、ハエトリシメジ、ドクササコ、ナメコ、オニフスベなどである。また、ブナ帯のサルノコシカケ類にも特産種が多いと考えられる。
なお、特殊な菌類にニオウシメジがある。このキノコは、大小約1000個のキノコが直径約120センチメートル、高さ80センチメートルの一塊をなすもので、重さは80~110キログラムほどになる。ニオウシメジは、1970~1978年の間にアフリカの4か所から発見されたほか、1974~1985年の間に西表(いりおもて)島(沖縄県)をはじめ、沖縄諸島、熊本県、神奈川県、群馬県で発見されている。さらに、1986年に神奈川県で再発見されたものは、直径140センチメートル、重さ168キログラムであった。
日本列島は海に囲まれ、亜寒帯から熱帯に至るという恵まれた地理的・気候的条件をもつため、菌類相も多種多様であるが、その調査は、まだ十分とはいえない段階である。
[寺川博典]
自然災害
日本は災害の多い国といわれている。自然現象が災害の発生や拡大のおもな要因となっているものを「自然災害」という。
自然災害のうち、台風や集中豪雨に代表される気象に起因するものを「気象災害」、地震や火山に代表されるものを「地象災害」という。とくに地震は「震災」ともいう。冷水塊(れいすいかい)やエルニーニョ現象に代表される「海象」も水産業には大きな影響があるが、日本では異常気象との相互作用として注目されている。
[久保木光煕]
気象災害
気象災害はその誘因別、災害の時間スケジュールなどによって分類することができる。
(1)気象現象が直接の破壊力となるもの。台風、低気圧、前線などによる強風害、海難、豪雨・大雨による水害、季節風による豪雪、雪圧害、その他雷災、凍霜害など。災害は短時間でも破壊力が被害を受ける側の抵抗力を上回ったときに発生する。破壊力がとくに強くなくとも抵抗力が低下している場合には災害が発生することがある。その場合、一般には災害とはしない。一定の治山治水や耐震構造を前提としているのである。日本はなぜ災害が多いのか。第一に考えられるのは日本の地理的位置から冬季や夏季の季節風が強く、低気圧の往来が多く、かつ台風の通路に当たっていて、気象環境が厳しいという点。第二に地形が急峻(きゅうしゅん)で急流河川が多いこと。第三に地質構造が弱く、崩壊や土砂の流出が多い。第四に人口が稠密(ちゅうみつ)で災害の被害が予想以上に拡大する点である。
(2)気象災害が直接的な誘因だが、時間スケールが長期的で、積算的である場合。異常暖冬、長雨、冷害、干魃(かんばつ)など、いわゆる「異常気象」である。一般に過去30年間の平均値で示されるような気候値を平年値といっているが、天候の変動が平年値を中心に一定の範囲に収まっている間は問題は起こらない。しかし通常の変動幅から極端に逸脱し、1か月、2か月以上も似たような天候が続くと国民生活や産業に影響が出てくる。気象庁は、過去30年間、あるいはそれ以上にわたって観測された平均値に対して大きく偏った場合の天候を、異常気象と定義している。
30年に一度という基準は月平均気温の場合、平年値からの偏差が標準偏差の2倍を超えたとき、異常高温・低温としている。このような似通った天候の持続は大気大循環の偏りに由来しているが、その持続性は火山噴火や海面水温、雪氷面積の変化などの原因が取りざたされている。
エルニーニョ現象は太平洋赤道域の東部で海面水温が平年に比べて数度も上昇し、半年~1年半ほど続く現象で、数年に一度発生する。通常低海水温のこの海域の水温異常は、大気に影響する熱源を突如交換したことになり、世界中にさまざまな異常気象をもたらす。日本では暖冬・冷夏の公算が大きく、梅雨(つゆ)明けが遅い傾向がある。
(3)気象現象の間接作用が破壊力となるもの。塩風害、融雪洪水など。人間の不注意による火災も、強風や湿度の低下による乾燥が災害を大きくしている。
(4)人間活動の増大による自然環境、社会環境の変化によるもの。人間活動の増大によってさまざまな大気汚染(公害)、水質汚染がもたらされているが、もっとも今日的な問題は地球の温暖化である。温室効果ガスの現状認識は次のようである。大気中の二酸化炭素やメタンは温室効果ガスとよばれ、赤外線を吸収して地表の温度を上げる。世界の平均気温は過去100年間に0.6℃上昇し、この状況が続けば21世紀末には3℃上昇する。また昇温に伴い、極地方の氷がとけて、海水位が65センチメートル上昇する(1994年異常気象レポート、気象庁)。第二に注目されるのはオゾン層の破壊である。フロンなどの人造物質によるオゾン層の破壊は現在も進行しており、その顕著な例は南極のオゾンホールである。この地方のオゾン全量は1979~1992年の13年間で2分の1に減少しており、札幌、つくば、鹿児島、那覇(なは)などの日本国内の資料でもこの傾向は同じである。オゾンの減少による有害紫外線の増加が心配されている。
気候の変動の要因は大気自身のもつ変動性のほか、地球表面の70%を占める海洋、火山噴火によるエーロゾル(エアロゾル、大気中の微粒子)の増加、さらに太陽活動が関与しているが、今日、新たに人間活動による温室効果ガス、エーロゾルの増加、森林破壊などの影響が飛躍的に増大している。しかし人類をも含めた生物の存在に関わる問題だけに、1997年(平成9)12月に開かれた「地球温暖化防止京都会議」によって今後の気候変動の観測・監視、研究および情報提供に関する国際計画が推進されてきている。
[久保木光煕]
地象災害
日本およびその周辺は世界的にも地震や火山活動の非常に多い地域として知られている。これは太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北アメリカプレートがせめぎ合っている地域だからである。
(1)地震・津波の防災。地震はプレート境界で発生するものとプレート内部で発生するものがある。後者は1995年(平成7)の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)がその例で、帯状の地震活動の活発な所、地震帯で起っている。この地震帯に含まれながらも近年顕著な地震の発生がない所は、地震空白域として今後地震の起こる可能性が強く、監視を怠るわけにはいかない。1983年の日本海中部地震(地震規模マグニチュード7.7)、1993年の北海道南西沖地震(マグニチュード7.8)、1995年の兵庫県南部地震(マグニチュード7.3)の重大な災害を経験して広範な防災体制が進められた。現在、全国574地点に地震計、震度計が設置展開され、地震活動など総合監視システム(東海地震対策)、地震津波監視システム(地方中枢)として、データが自動処理されて監視に利用されている。また10か所の超音波式、76か所の水圧式津波観測施設から寄せられるデータは、気象衛星経由で処理され、約3分以内で津波予報として情報の伝達が行われている。
(2)南関東地域直下の地震の監視体制。1923年(大正12)の関東地震(マグニチュード7.9)の前例のある地域で、1992年から東海地域に準じて常時監視体制の充実が図られる。
(3)東海地震の予知。一般に地震の予知はむずかしい研究領域だが、東海地域に発生が予想されるマグニチュード8クラスの巨大地震に対してのみ監視体制と予知体制の研究が進められている。
(4)火山の監視。1974年、火山噴火予知連絡会が学識経験者や関係機関の専門家によって発足した。事務局は気象庁である。予知連絡会の検討結果に基づき、気象庁では活火山の定義を「概(おおむ)ね1万年以内に噴火した火山」、「現在噴気活動が認められる火山」とし、全国108の火山を活火山として選定している。とくに活動的な伊豆大島、浅間山、雲仙岳、阿蘇(あそ)山、桜島などについては地震計や傾斜計を設置して監視している。
災害防止をどうするか。日本は台風、集中豪雨、豪雪、異常気象、地震、津波、火山など自然災害を受けやすい国土条件がある。しかもその誘発の原因のなかには人間活動も加わって複雑になっている。なによりもまず災害の観測・監視体制の確立、予知・予測の防災情報の向上、その的確・迅速な情報伝達が重要になろう。
[久保木光煕]
開発と環境保全
開発方式の変遷
わが国における環境改変は農地の開発に始まる。弥生時代末期から古墳時代にかけて瀬戸内や近畿地方で農業用の溜池が築造され、大化改新以後の条里制によって農地開発はいっそう拡大した。条里制に基づく開発はおもに西日本で行われ、東日本の平野部では大河川の洪水対策が進む近世までは、ほとんど不可能であった。
資源採取を目的とした鉱産資源開発や森林伐採は地被の剥離(はくり)を伴う。これらの開発行為は他の災害(たとえば山地の崩壊)につながり、鉱産物の採取は地盤沈下を招いた。このような単一資源の開発の弊害を除くために多目的総合開発方式が考案された。これは元来、アメリカ合衆国のテネシー川流域開発公社(TVA)の事業がモデルとなっている。
[髙山茂美]
日本の国土開発
日本の総合開発は1950年(昭和25)制定の国土総合開発法に基づき、全国で22地域が特定地域開発計画の対象として指定を受けた。その多くは河川の流域が対象となり、多目的ダムを建設し、水力発電、灌漑(かんがい)、上水道、工業用水の供給、洪水統御を目的とした。その趣旨からも多目的ダムによる地域開発は流域の環境保全を考慮すべき性質のものであるが、開発の結果は必ずしも環境保全と整合してない面も多くみられた。たとえば1963年(昭和38)の天竜川の飯田市川路(かわじ)付近の水害はその下流側に築造された泰阜(やすおか)ダムの排水が計画とは異なって著しく上流まで波及して桑畑が浸水した例である。ダムの下流側では土砂の運搬が減少したために河水のエネルギーが下刻作用に利用されて河床が低下し、農業用水の取水口が相対的に浮き上がって取水不能となった例も各地に発生し、このために人工的に合口(ごうぐち)を作らなければならなくなった。河床低下は橋脚の浮き上がりも起こす。長野県上伊那郡の美和ダムは洪水制御を目的の一つとした多目的ダムであったが、ゲリラ性集中豪雨で放水時間を誤まり、下流側の農地に浸水被害を及ぼした。治水と利水が両立しない例である。
1960年(昭和35)に始まった所得倍増計画は太平洋ベルト地帯を中心とした工業生産を増大させ、農村から都市への人口移動が行われた結果、過密・過疎地域が生じた。この地域格差を解消する目的で新産業都市法促進法に基づく新産業都市が1967年までに15地区で指定された。また、工業整備特別地域促進法の制定により6地区が特別に指定された。これらの計画は1962年に制定された「全国総合開発計画」を具体化したもので拠点開発方式とよばれる。
1998年(平成10)3月に発表された五全総(全国総合開発計画)ではこれまでの全総と異なり、国土総合開発法を抜本的に見直し、国よりも地域が主体となり、住民や企業など多様な主体による「参加と連携」方式を掲げている。過去の全総で追認してきた大型開発事業を「いまさら、やめるとは言いがたい」という官僚的発想が根底にあり、中途半端なものになっているが、自然環境重視路線へと転換せざるをえなくなっているのは多少の進歩であろう。全総イコール開発という見方は依然根強いが、五全総で終わりという点は評価してよい。
わが国の国土は山地が多く、平地部のごく一部に人口が集中し、そのうち60%以上が東京、大阪、名古屋の三大都市圏内に居住している。都市の過密と農村の過疎は国民生活の快適さと安全を損ね、産業経済の発展を阻害した。これらの問題を解決するために1969年に「新全国総合開発計画」が制定され、各地域の交通網を設定して開発を進める方式を樹立した。しかし、1973年の第一次石油ショックのためにこの計画の見直しが迫られ、1977年に定住圏構想を中心とした三全総を制定した。この計画では自然的、社会的に200~300くらいの定住圏を設定して、地域開発やコミュニティの基礎的圏域としている。四全総は国際化、技術革新・情報化の進展や急速な産業構造の変化等に的確に対応するため、東京の一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を図ることを基本として、特定地域への人口集中や諸機能の過度の集中がない多極分散型国土の形成を目標として1987年6月に制定された。前述の五全総はこれを継承して国土構造を一極一軸型から四つの国土軸による多軸型国土の形成を提唱し、首都機能移転の具体化を積極的に検討するとしている。
[髙山茂美]
将来への課題
地域開発は、自然の可能性を人間の生活や地域の特性に合せた方法で引き出すべきである。大規模な都市や工業地域の開発などは環境アセスメント(環境事前評価)の結果を踏まえて行うことが望ましい。高度経済成長期(1960年から1970年代前半まで)のように自然界の適正なバランスを考えずに開発を進めることは「かけがえのない地球」を失う危険性がある。このスローガンのもとにストックホルムで行われた1972年の国連人間環境会議で決定した「人間環境宣言」は人類の永遠の課題として、環境保全に対する貴重な警鐘を打ち鳴らしたといえる。
われわれの周囲には、数多くの文化遺産が先人によって刻みこまれている。日本各地の歴史的環境、伝統的町並み、地場産業、文化財、伝統的行事、緑の保全なども自然環境とともに人間にとってかけがえのない生活環境である。これらは自然条件、社会環境、歴史的伝統とともにその地域の独特の風土を形成するものであって、われわれはそれぞれの環境保全を進め、平和にして健康・安全・快適な社会を創出し、世界の平和に貢献するように努める必要がある。
[髙山茂美]
住民・言語
人口
日本の人口は、縄文時代以来幾度かの増加期と停滞期のサイクルを繰り返してきたが、江戸時代後期には3000万人前後でほぼ停滞していたと考えられる。しかし明治以降の産業化とともに日本人口は新たな増加局面に入り、1891年(明治24)に4000万、1912年(明治45)には5000万を突破した。そこから倍増して1億に達したのは55年後の1967年(昭和42)であり、この間の年平均増加率は1.26%という高率である。しかし1970年代後半以降の出生率低下により、人口増加率は低下し、しだいにゼロに近づいている。
2000年(平成12)国勢調査による日本の総人口は1億2692万5843人であり、1995~2000年の年平均増加率は1.1%であった。国立社会保障・人口問題研究所の『日本の将来推計人口』(平成14年1月推計)によると、日本の人口は2006年の1億2774万人をピークに、以後減少に転じると予想される。
死亡率は短期的な上下動を伴いながらも一貫して低下を続けており、これが20世紀なかばをピークとする人口増加の主要因となった。平均寿命(その年の年齢別死亡率が不変と仮定した場合の平均生存年数)は、1920年代前半の男子42.1、女子43.2から、2000年には男子77.72、女子84.60と男子で約35年、女子では約40年延びた。現在の日本の死亡率は、世界でもっとも低い水準を示している(2000年の数値は『平成12年完全生命表』による)。
一方出生率は、1930年代に一時低下の兆しをみせたがその後反騰し、とくに1947~1949年の第二次世界大戦後のベビーブームは「団塊の世代」とよばれる大出生集団を生じた。合計特殊出生率(その年の女子の年齢別出生率が不変でかつ出産年齢女子が死亡しないと仮定した場合の平均出生児数)でみても、ベビーブーム期には4.3~4.5という高率を記録したが、1950年代には急低下して2.0前後の水準となった。その後、丙午(ひのえうま)の年(1966年)の1.58を除けば、1970年代前半までの合計出生率は2.0~2.1で推移していた。しかし1975年以降ふたたび低下し、増減はあるものの2002年には1.32と史上最低記録を更新している。
出生性比のかたよりと出産年齢女子の死亡のため、合計出生率が2.0では人口の維持に不足であり、現在の死亡率では2.08が人口を維持できるぎりぎりの水準(人口置換水準)とされる。わが国の合計出生率は、1970年代なかば以降、この水準を大幅に下回る「超低出生率」の状態が続いている。その結果、将来の人口減少は避けられず、先述のように2010年より以前に人口減少が始まる公算が強い。
超低出生率のもうひとつの帰結は、急速な人口高齢化である。65歳以上人口は2000年(国勢調査)に約2200万人で総人口の17.3%にあたり、15歳未満の年少人口(1847万人)を上回っている。前述の将来推計人口によると、65歳以上人口は2006年に2617万人で総人口の20%を突破し、2033年には3482万人で30%を突破するものと予想される。このような急速な高齢化は、年金・雇用・医療・介護といった各種制度に深刻な影響を及ぼすであろう。
18世紀の江戸は世界でも有数の大都市だったとされるが、かりに人口が100万を超えていたとしても全国人口の3%程度であり、他の都市をあわせても農業社会が養いうる都市人口の割合は10%に満たなかっただろう。しかし産業化は、農業から工業へ生産の比重が移る過程であり、必然的に都市への人口の大移動を伴う。全国人口に市部が占める割合は、1920年(大正9)には18.0%、1940年(昭和15)には37.7%に達していた。
その後、戦争による混乱で都市化のプロセスは一時後退したものの、戦後の高度成長期にふたたび急速に進行し、1970年には市部人口が72.1%を占めるに至った。この時期、とくに東京・大阪・名古屋を中心とする三大都市圏への人口集積が進んだ。オイル・ショック(1973)以降は、大阪圏・名古屋圏への人口流入が鈍化する一方、東京圏への人口集積が続いて現在に至っている。東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県が全国人口に占める割合は、1970年にすでに23.0%に達していたが、その後も増加して2000年には26.3%となっている。
全国人口はまだかろうじて増加を続けているが、地域によってはすでに人口減少が始まっており、1995~2000年の間に人口が減少した都道府県の数は23であった。国立社会保障・人口問題研究所の『都道府県の将来推計人口』(平成14年3月推計)によると2005~2010年には36、2015~2020年には45と、人口減少県は今後着実に増えると予想される。このなかで埼玉・千葉・神奈川の3県は他より高い増加率を維持するため、1都3県が全国に占める割合は2030年に28.5%と、さらに増加するとされる。
法務省によると、2001年末における外国人登録者数は177万8462人(182か国)で、総人口の1.4%にあたる。外国人人口の割合は1950年代から1980年代前半までは0.6~0.7%で推移していたが、バブル経済期の1980年代後半から急増し1%を超えるに至った。
国籍別で最大なのは韓国・朝鮮籍の63万2405人で、登録外国人の35.6%に当たるが1991年末(約69万人)以降は減少している。その多くは戦前から日本に住み、1952年の対日講和条約発効によって日本国籍から韓国・朝鮮籍に変わった人々とその子孫である。ついで多いのは中国籍の38万1225人(21.4%)で、やはり1952年に日本国籍から変わった人々とその子孫を含む。これに対し、1980年代末以降急増したのはブラジル人で、26万5962人(15.0%)である。ブラジルをはじめ南米からの入国者の急増は、1989年の入管法改正で日系人の入国・就労が容易になったことによる。このほか、フィリピン(8.8%)、ペルー(2.8%)、アメリカ(2.6%)、その他(13.8%)となっている。
バブル経済期には年間3万人以上の入国超過を記録した外国人の流入も、1993~1994年には一転して約6000人の出国超過となり、1994~1995年にはほとんどゼロになり、1995~1996年にはふたたび2万人の入国超過を記録するなど、国際人口移動の情勢はめまぐるしく変化している。今後も日本国内および近隣諸国の経済状態と国際関係の動向によっては、国際人口移動がまったく新たな局面を迎える可能性もあり、予断を許さない。
[鈴木 透]
言語
日本語が唯一の公用語として使用され、その話者の人口は1億2000万人を超え、世界のなかでも屈指の多数である。しかし対外的には交流が少なく、近時は外国人の日本語学習熱もようやく高まったが、国際的勢力は弱小である。歴史上外国との接触が少なかったのが原因であろう。日本語はウラル・アルタイ語族の一つと説かれてきたが、近時は反論が多く、南方語またはチベット・インドの諸語との関係、さらには南方系言語のうえに北方系言語が重なったなどの諸説があるが、いまだ定説を得ない。地域的に隣接する朝鮮語、アイヌ語などとは、かならずしも同系の証明が成立していない。日本語の方言は琉球(りゅうきゅう)方言と本土方言とに大きく二分され、本土方言はさらに東部・西部・九州の三大方言に分かれるが、東京方言を中心とした「共通語」が標準となっている。「共通語」の母音は、a,i,u,e,oの5種で、開音節を中心とする音韻体系をもち、子音にはk,g,s,ʃ,z,ʒ,t,tʃ,ts,d,dʒ,dz,n,h,Φ,b,p,m,r,j,wがあり、有声音・無声音の対立はあるが、有気音・無気音の対立はない。文法は「主語―目的語―述語」の構文を主とし、実体概念を表す名詞・動詞・形容詞などの下に、関係を表す助動詞・助詞がつき、膠着語(こうちゃくご)の一つとされる。語尾変化は、動詞、形容詞(・形容動詞)および助動詞に存し、名詞、副詞などには存しない。単数・複数、性、格などによる語形変化は存せず、接尾語の添加などによって表す場合があるにすぎない。過去・現在・未来・推量などは、主として助動詞によって表し、格関係・条件関係・強調・感動などはおもに助詞によって表す。
日本語の歴史は、5世紀以来の文献と、若干の口承(こうしょう)文芸などによって知られる。8世紀には8母音が区別されていたとされる(近年異説がある)が、9世紀以後、5母音に減じて現在に至っている。文法史的にみると、16世紀と17世紀との間に大きな変化があり、「古代語」と「近代語」とに二分される。活用は古く動詞に9種、形容詞に2種あったが、中世以後しだいに減じて、現代では動詞5種、形容詞1種となった。そのほか、助動詞も語形・活用が大きく変わった。基本的な名詞・動詞・形容詞などは、語彙(ごい)の変化が少ないが、副詞・接続詞・助詞などは、語形や用法に歴史的変化が大きい。また、中国から古代以来大きな文化的影響を受け、多数の中国語語彙を漢語として輸入した。そして文字も中国製の漢字を受け入れ、その中国字音を日本的に変容させて使用したが、さらに漢字について日本語独特の読み方(和訓)を定着させ、そのうえ、漢字の表音的用法に基づいて、平仮名・片仮名という日本独特の文字を創案した。ローマ字は16世紀に初めて渡来したが、19世紀中葉以後、欧米文化の摂取とともに、英語、ドイツ語、フランス語などの外来語が多数輸入された。しかし音韻体系、文法体系の基幹はほとんど変化しないで現在に至っている。
[築島 裕]
歴史
日本史における「時代区分」の歴史と時代区分
時代区分とは、歴史の流れを一定の基準によって区分することであり、研究者・歴史家の思想(歴史認識の方法)と深く関連する。いかなる時代区分によって歴史を研究し叙述するかは、史学史の展開を特徴づけるメルクマールでもある。
[佐藤和彦]
「時代区分」の歴史
日本の史学史上、一貫した史観と個性をもった史書が現れるのは、中世に入ってからである。
藤原氏の栄華を叙述した『大鏡(おおかがみ)』は、神代より藤原道長(みちなが)までの歴史を、(1)皇極(こうぎょく)天皇まで、(2)孝徳(こうとく)天皇から仁明(にんみょう)天皇まで、(3)文徳(もんとく)天皇以降、の3期に区分している。この区分は、藤原氏の栄華の発生と発展の要因を、外戚(がいせき)関係のあり方に求め、それを基準としたものである。
保元(ほうげん)の乱をもって、貴族社会から武家社会への転換が始まり、その変化を不可避的なものであるとする慈円(じえん)の『愚管抄(ぐかんしょう)』は、歴史の推移を「道理」の展開としてとらえている。その「道理」は、天皇家と藤原摂関(せっかん)家との関係のあり方に求められた。慈円は神代より後鳥羽(ごとば)天皇までの歴史を、(1)宇多(うだ)天皇まで(上古)、(2)後三条(ごさんじょう)天皇まで(中古)、(3)後鳥羽天皇まで(末代)、と3期に区分し、上古における天皇親政、中古の摂関政治に続く末代に至って、もろもろの道理が錯綜(さくそう)し、戦乱が継起していわゆる末世となり、この時期に武家の進出が決定的となったと説いている。この時代区分の根底には、摂関家存続についての歴史的意味の問いかけがあり、「道理」の発現が時代区分の基準であった。このころ、王朝貴族をとらえていた「末世」「末法」思想が、慈円をも深くとらえていたのである。
14世紀の内乱のさなかに叙述された北畠親房(きたばたけちかふさ)の『神皇正統記(じんのうしょうとうき)』は、日本の歴史を神代と人皇の代とに大きく二つに区分し、さらに、人皇の代を、(1)神武(じんむ)天皇より陽成(ようぜい)天皇まで(上古)、(2)光孝(こうこう)天皇より白河(しらかわ)天皇まで(中古)、(3)白河上皇の院政以降(近代)、とに3区分する。親房は、仏教のみならず儒教(じゅきょう)・神道(しんとう)を重視し、不徳の君が出現するとその皇統が断絶し、傍系のうちから有徳の者が帝位につくと述べている。親房は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の神慮が日本の歴史を貫徹していること、皇位継承が、継承者の徳・不徳によって左右され決定されること、この二要因を時代区分の基準とした。摂関政治が天照大神の神慮にかなう政道であるとの見解は、慈円の場合と同一である。ただし、慈円が武士の登場を歴史的必然であるととらえたのに対し、親房は、武士の台頭を乱世の原因ととらえ、あるべき政道の実現が断絶したためであると説く。武士の登場に対する歴史的評価は正反対である。徳・不徳のあり方が皇位継承と深くかかわるとの考え方は、戦乱に次ぐ戦乱が人々の生活を混乱させ、治国安民(ちこくあんみん)が人々の要求であり理想であった内乱期の思想として重要である。
近世に入ると、大義名分(たいぎめいぶん)論・勧善懲悪の儒教史観を特徴とする林家(りんけ)の歴史学に対抗して、18世紀の前半、合理性と実証性とを重視する史家新井白石(あらいはくせき)が現れた。『藩翰譜(はんかんぷ)』『古史通(こしつう)』などに白石の実証性と合理性とをみることができる。「本朝天下ノ大勢九変シテ、武家ノ代トナリ、武家ノ代、又五変シテ当代ニ及ブ」と説く『読史余論(とくしよろん)』は、貴族政治の衰退と武家政権の発展とを、独自の時代区分によって活写している。鎌倉時代から南北朝時代に、天皇・貴族の政権が武家の政権へと変化する様相を鮮明に描き出した白石の歴史認識は、史実の合理的解釈と、時代区分にあたっての易姓(えきせい)革命論とを特徴とする。
荻生徂徠(おぎゅうそらい)から経世済民(けいせいさいみん)の学を継承した太宰春台(だざいしゅんだい)は、日本史の流れを、(1)郡県制から国司(こくし)・守護(しゅご)併置の時代、(2)守護支配の展開する時代(自然の封建制)、(3)戦国乱世から徳川幕府の時代(真の封建制)と3区分する。春台は、郡県制から封建制へという制度の変化を基準にして時代を区分している。
19世紀に入ると、幕府の衰退、社会不安、対外関係の緊張などを反映して、伊達千広(だてちひろ)『大勢三転考(たいせいさんてんこう)』などの歴史思想が生み出された。『大勢三転考』は、「皇国の有状、大に変る事三たび」と述べて、神武天皇より江戸時代に至るまでの日本の歴史を3区分している。(1)「上つ代」は、国造(くにのみやつこ)・県主(あがたぬし)に代表される「骨の代」(かばねの世)であり、国務はかばねと領土とを世襲する各氏族の長によって分担されていた。(2)「中つ代」は、大化改新を起点として始まる「職(しき)の代」(つかさの世)であり、天皇から官職を授けられた者によって国家が統治された時代である。「職の代」は、摂関時代を最盛期として平氏政権に至る。(3)「下つ代」は、源頼朝(よりとも)の守護・地頭(じとう)の全国設置によって始まる「名の代」(みょうの世)である。大名・小名が国政を担当した時代であり、戦国争乱を平定した徳川幕府に至って全盛期を迎えた、という。「上つ代」から「中つ代」の変化が「上の御心より」生じたものであるのに比して、「中つ代」から「下つ代」の変化は「下より」生起したものと論じ、この変化をもっとも重視している。平清盛(きよもり)の時代を論じて、「これぞ職の代の極みにして、名の代に移る時なりけり」と述べているように、その最盛期のなかに次代への変化の芽が生まれ始めているとの認識が、千広の歴史観の特徴である。彼の時代区分は、政治形態および社会制度の変化を基準とするもので、幕末の変動期に紀州藩政に携わった千広の歴史観が、ここに集約されている。
明治維新ののち、政府はフランス民権論の影響の強い在野の啓蒙(けいもう)史学に対抗するため、ランケ学派のリースを招聘(しょうへい)し、帝国大学文科大学に史学科を創設した。このため、ドイツ流の実証主義史学が歴史学界の基調となった。
しかし、日本史学の研究は、天皇・貴族・将軍などの支配者層を中心としたものが盛んであり、時代区分も、支配者の交替を基準として、王朝時代(公家(くげ)時代)と武家時代とに分ける2区分法や、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代など、政権の所在地による区分がもっぱら行われていた。
20世紀に入ると、ヨーロッパ史学の影響を受けた福田徳三(とくぞう)、内田銀蔵(ぎんぞう)、原勝郎(かつろう)などによって、政治史、法制史、経済史の分野が開拓され、古代、中世、近代という3分法が採用されるようになった。1920年代から1930年代にかけての社会経済史学と唯物史観にたつ科学的な歴史学の結合と発展は、経済・政治・文化が構造的に関連しあう社会構成の特質をもって時代区分の基準とすべきであるとし、原始社会、古代社会、中世社会、近代社会という4区分法を提唱した。この4区分法は、第二次世界大戦後の歴史学界でもっとも有力な学説として定着し、今日においては歴史教育の分野においても、日本史の時代概念として採用されている。
[佐藤和彦]
時代区分
(1)原始社会
数万年前の旧石器時代から始まる日本の社会は、縄文文化(じょうもんぶんか)を伴う新石器時代を経て、紀元前3世紀ごろには弥生文化(やよいぶんか)へと発展した。石器時代の社会は貧富の差がほとんどなく、共同労働と労働用具の共有を特徴としていた。大形石棒(せきぼう)や土偶(どぐう)などの遺物は呪術(じゅじゅつ)的世界の表象であり、人々は食料を求めて移住生活を続けていたと推定される。水田農業と金属器を伴う弥生文化は、中国・朝鮮の文化の影響を受けて生産力を発展させ、集落が各地に形成されるようになった。農業社会の成立過程は私有財産と身分・階級を発生させ、1世紀の後半には100余国の小国が分立し、漢王朝に朝貢するに至った。『魏志(ぎし)』東夷伝倭人(とういでんわじん)条によれば、3世紀には女王卑弥呼(ひみこ)の邪馬台国(やまたいこく)が勢力を強化し、30余の小国を連合させたという。邪馬台国には厳しい身分秩序があり、中国王朝との交渉が国家公権の維持に必要であった。
(2)古代社会
4世紀には畿内(きない)を中心とする大和(やまと)朝廷の支配体制が強化され、国家の統一が進んだ。世襲制を確立した大王(おおきみ)(天皇)が君臨し、農具と武具の独占を通じて、族長が土地と人民を支配した。族長は朝廷から姓(かばね)を与えられて貴族となり、氏人(うじびと)と隷属民を率いて朝廷に仕えた。屯倉(みやけ)・田荘(たどころ)とよばれる大土地を所有した大王は、耕作民として部民(べみん)を所有した。7世紀の政治改革によって皇室を中心とする支配階級の結集が図られ、支配階級は唐の制度を模倣した律令(りつりょう)制度を支配の基本体制とした。人民は、公民(良)と奴婢(ぬひ)(賤(せん))とに分けられた。班田収授法(はんでんしゅうじゅほう)によって一定の土地を与えられた公民は、租(そ)・庸(よう)・調(ちょう)のほかに、兵役・雑役(強制労働)を負担した。それは特殊な奴隷制社会であった。8世紀末から9世紀にかけて、律令国家の基盤であった班田制が崩れ、貴族・寺社の私的大土地所有(荘園(しょうえん))が発達した。10世紀以降、荘園・公領の耕作を請け負った農民上層(田堵(たと)、のちに有力名主(みょうしゅ)へ発展)がしだいに土地の耕作権をもつようになり、自立した経営を営み始めた。そして耕地と経営を守るために武装化した有力名主や、郡司(ぐんじ)・在庁官人(ざいちょうかんじん)などのなかから武士が発生する。彼らは、近隣の武士、さらには中央貴族・寺社勢力との対立抗争を通じて勢力を伸張させ、古代社会を克服し、歴史の前面に登場した。
(3)中世社会
中世社会を前期封建社会と後期封建社会に分ける。
(a)前期封建社会 古代末期の内乱の結果、12世紀末に武士階級による初めての政権(鎌倉幕府)が成立した。中央貴族・寺社勢力は、依然として勢力を保持していたが、鎌倉幕府の滅亡、建武(けんむ)政府の成立と崩壊を経て展開した14世紀の内乱の過程で、古代的諸勢力は完全に没落し、武士階級による支配が決定的となった(室町幕府)。14~15世紀には、各地の荘園・公領において、単婚家族労働によって農業生産を営む小農民(農奴)が広範に成長した。畿内および周辺では、宮座・村堂を媒介として農民結集が図られ、有力農民の指導によって惣村(そうそん)が形成された。惣村は共有財産をもち、自検断権(じけんだんけん)を行使して、自治的に村政を運営した。寄合(よりあい)を中心とする農民結集は、抵抗の砦(とりで)でもあった。内乱の過程で、荘園制的支配の根幹であった職(しき)の体系が崩れ、各地に守護や国人(こくじん)領主による支配領域が生まれた。
農業生産力の発展を基盤とする分業・流通の展開は、農村と地方都市とを結び付け、民衆蜂起(ほうき)(土一揆(つちいっき))の条件をつくりだした。一味神水(いちみしんすい)と起請(きしょう)によって結集力を強めた。土一揆の頻発は室町幕府の支配体制に打撃を与え、体制内矛盾を激化させた。応仁(おうにん)の乱以降16世紀にかけて、武士相互の戦闘が日常化する。戦国争乱のなかで、国人領主・土豪地侍(どごうじざむらい)が新しい支配階級へと成長し、戦国大名とよばれるに至った。下剋上(げこくじょう)の社会を生き抜くために、彼らは独自の法をもち、強大な軍事集団(家臣団)を編成し、領内のあらゆる人々を支配する大名領国を形成・展開した。戦国争乱の最終段階に至って、兵農分離を基本政策として、検地(けんち)・刀狩(かたながり)を強行して統一政権の完成を目ざす織豊(しょくほう)政権が登場した。
なお近年、農業民を中心にとらえられていた従来の中世社会観に対し、遍歴し、交易に従事する非農業民(漁民、山民、芸能民、商工業民)に視点を据えて中世社会の歴史を把握すべきであるとの学説が発表され、多大の影響を与えつつある。中世社会は、多元性、分裂性を特徴とし、多様な価値観の存在する社会であり、さまざまな職能集団が活躍したとする所論や、南北朝内乱期に未開社会から文明社会への分水嶺(れい)的位置を与える見解もある。
(b)後期封建社会 織豊政権が基調とした兵農分離の政策は、17世紀初頭に成立した江戸幕府に引き継がれた。幕府は、大名の改易(かいえき)、減・加封を繰り返して家臣団所領の再編成を行い、武家諸法度(ぶけしょはっと)を発布し、参勤交代(さんきんこうたい)の制度化によって統制力を強めた。さらに、外国貿易の管理と統制のために鎖国政策を実施した。
幕藩体制の経済的基礎は自給自足的経済の農村にあった。農業生産から離脱した武士階級は、農業生産の担い手である百姓(小農)から生産物の過半を年貢として収奪した。農民は田畑永代売買禁止令、分地制限令などによって、田畑の売買・質入れを原則的に禁止され、土地に緊縛され、死なぬよう生かさぬようにと位置づけられて、年貢生産にのみ専心させられることとなった。
武士階級は三都(江戸、大坂、京都)や城下町に住み、農民から収奪した年貢米とその換金によって生活した。三都や諸大名の城下町に住んだ商人は、年貢米の販売や必要物資の調達など、武士階級の経済的要求を満たした。
自給的色彩の強い農村社会を基盤とした幕藩制社会も、17世紀後半以降は貨幣流通、商品流通の農村への浸透によってしだいに変質する。18世紀初頭には、農具の改良により農産物が増大し、19世紀の20年代には商品作物栽培が全国化して、富裕農民の土地集積と地主化がみられるようになる。農民層分解が進み、農村工業が展開するなかで、問屋制家内工業やマニュファクチュアなどの資本制生産関係が成立する。
貨幣経済の発展は、領主階級にも影響を与えずにはおかなかった。支出の増大により財政の窮乏化した幕藩領主は、年貢の増徴を図るに至った。しかし過酷な年貢収奪に反対する百姓一揆(惣百姓一揆→全藩一揆)が頻発し、都市では町人層を主体とする打毀(うちこわし)が続発した。封建支配を根底から揺り動かす世直しの民衆運動が展開したのである。19世紀には幕府や諸藩において財政の立て直しを基調とする諸政策が進められたが、効果はほとんどなかった。
欧米列強のアジア進出は、日本にも深刻な事態を引き起こした。幕府による開国を契機として、全国各地に尊皇壤夷(そんのうじょうい)の風潮が高まり、討幕運動が激化するという、内乱状況のなかで、1867年(慶応3)江戸幕府は崩壊した。
(4)近代社会
明治政府は、1869年の版籍奉還、1871年の廃藩置県、1873年の地租改正などの諸政策を進めることによって、幕藩体制支配を払拭(ふっしょく)した。そして、欧米先進国の法律・制度・文化などを積極的に取り入れて、近代的な機構を整備していった。国会開設と憲法を求める自由民権運動は、1889年の大日本帝国憲法の発布、1890年の国会開設となって結実した。
政府の富国強兵と殖産興業などの諸政策は、1890年代から1910年代にかけて資本主義を急速に発達させることとなり、この過程で機械制工場生産が確立した。朝鮮・中国における市場獲得の要求が、日清(にっしん)・日露の戦争を生起させた。日本資本主義の特徴である低賃金と長時間労働は、日本資本主義が農村における半封建的な寄生地主制のうえに構築されていたことと深くかかわっている。欧米資本主義に対抗した日本資本主義は、1910年代の第一次世界大戦以降、独占資本主義(帝国主義)として独自の展開を遂げたが、1945年の第二次世界大戦の敗戦によって崩壊した。敗戦後の農地改革、財閥解体、なかんずく日本国憲法の公布(1946年11月)以降を現代社会の始期とすることができよう。
[佐藤和彦]
日本人はどのように歴史を意識し、認識してきたか
日本人の歴史意識もしくは歴史認識を探ることは、日本人の時間に対する観念や世界観、ひいては社会意識・人生観などを解明することにつながる。
歴史意識・歴史認識が時代や地域によって異なることはもちろんであるが、それを意識または認識する主体が支配者であるか、被支配者であるかによっても変わる。これまでは、歴史書を中心に分析が行われてきたため、被支配者のそれについてはほとんど光があてられてこなかった。そこで、以下、古代、中世、近世、近・現代と時代別に民衆の歴史意識・歴史認識を含めて、総体として日本人がいかに歴史を認識してきたかを明らかにし、意識の面から日本史の再構築を試みることとする。これは、人間の意識が社会によっていかに規定されたのか、逆に人間の意識がいかに社会を変ええたのかを考えることになり、今日、わたしたちが置かれている状況を再認識することになろう。
[関 和彦]
古代における歴史意識
古代における歴史意識の変化を全体的に把握し、その特色を析出しようとするとき、いろいろな研究上の障害・制約が存在する。その障害・制約の根源は、課題追究の素材となる史料そのものが、古代における歴史意識の全体像を知るための素材としての歴史的性格をもっていないところにある。古代の人々の歴史意識の特徴を析出するには、単に六国史(りっこくし)等を中心に通史的に把握するよりも、人々の生活の場に視点を置いて考察すべきであろう。
いままでの研究では、古代における歴史意識といえば、記紀にみえる古代天皇制イデオロギーが中心であった。しかし、ひと口に古代の人々といっても、天皇を頂点とする支配階級と被支配階級との対立があったのであり、考察なくしてすべての人々の歴史意識を一括して記紀イデオロギーとしては非学問的である。
ここでは試みとして二つの視点を提示し、古代の人々の歴史意識の側面を析出してみたい。それは血縁・地縁意識という視点である。血縁・地縁はあらゆる意味でわれわれの生活を左右する日常的存在であり、それなくしては良(よ)きにつけ悪(あ)しきにつけ生きていけない生活基盤である。それは古代の人々にとっても同様であったと思われる。
(1)血縁からみた歴史意識
日本古代における歴史意識は、基本的には血縁を要(かなめ)とする系譜意識として形成されたと考えられる。著名な埼玉県稲荷山古墳(いなりやまこふん)出土の鉄剣の銘文をみると、乎獲居(おわけ)臣は大彦以来の祖先系譜を明確に示している。『出雲国風土記(いずものくにふどき)』意宇(おう)郡条にみえる語臣猪麻呂(かたりのおみいまろ)の報復事件は、風土記編纂(へんさん)時の60年前のできごと(現代史)であるが、語臣與(あたう)の父(猪麻呂)の時代として語り継がれている。同様の歴史意識は同風土記にいくつもみえ、支配階級のみならず一般民衆の世界にも系譜意識は広がっていたことがわかる。『古事記』、六国史の場合、大きくみて、時代区分・設定は天皇治世をもってなされているとみてよい。しかし、一般民衆の日常生活においては、今日の元号使用という状況と相違して、生活に密着する形(例、父の時代)でとらえていたと思われる。王権とのかかわりで考えても『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』所引の有馬(ありま)温泉起源伝承「土人(くにひと)の云(い)へらく、時世の号名を知らず。但(ただし)、嶋大臣(しまのおおおみ)の時と知れるのみ」をみてもわかるように、土人(民衆)は天皇治世と無関係の場で生活していることがうかがえる。
(2)地縁からみた歴史意識
次に地縁的歴史意識であるが、現在、地方の時代といわれ、郷土史・地域史の再検討が課題となってきている。古代においても民衆には郷土愛・土地所有といろいろな側面があると思うが、自分たちの先祖が生産活動等で活躍した場、生活の舞台である郷土との触れ合いを歴史(伝承)的に伝えようとしている。その典型は記紀、風土記に多数みえる地名起源伝承である。「英保(あぼ)と称(い)ふは、伊予(いよ)国英保(あぼ)村の人、到来(き)たりて此処(ここ)に居(お)りき。故(かれ)、英保村と号(なづ)く」「常に五月(さつき)を以(もっ)て此(こ)の岡に集聚(つど)ひて、飲酒(さかみづ)き宴遊(うたげ)しき。故(かれ)、佐岡(さおか)といふ」(『播磨(はりま)国風土記』)をみても、移住・農耕行事の歴史が語られている。いままでの研究では牽強付会(けんきょうふかい)な伝承として無視されてきたが、そこにこそ民衆レベルの地縁的歴史意識がかいまみられるのである。
いままでの古代の歴史意識といえば、記紀にみえる「邦家(ほうか)之経緯・王化之鴻基(こうき)」(古事記)に典型的にみえる天皇制イデオロギーでまとめられる傾向にあったが、以上述べてきた二つの民衆レベルの歴史意識を抜きに考えることはできないのである。記紀の叙述のみを追えば天皇制イデオロギー一色であるが、それはあくまで歴史的産物の一つである。民衆レベルの血縁・地縁的歴史像は記紀編纂段階において天皇治世・行為が付され、「難波長柄豊前天皇(なにわながらとよさきすめらみこと)の世、揖保郡(いぼのこおり)を分ちて、宍禾(しさわ)郡を作りし時、山部比治(やまべのひじ)、任(よ)されて里長(さとおさ)と為(な)りき。此の人の名によりて、故(かれ)、比治里(ひじのさと)といふ」(『播磨国風土記』)という形で「邦家之経緯・王化之鴻基」の歴史へと編成されたのである。支配階級の記紀にみられる歴史意識は基本的には六国史に継承され、民衆レベルのそれは地域伝承として語り継がれたと考えられる。
[関 和彦]
中世における歴史意識
中世には、未来を予言した未来記が数多く書かれた。ここでは、それを手掛りにして当時の歴史意識を探ってみたい。
(1)未来記にみえる歴史意識
「王位を日に競い、君臣序をたがえ、国務を奪い争う。父子義絶し、国王后妃その数国に満つ。官物(かんもつ)滅亡し、王臣相共に恒乏飢渇(けかち)す。鬼神ことごとく怒りて、疾疫(しつえき)日々なり。百姓擾乱(じょうらん)し、兵殺綿々たり」。1007年(寛弘4)に発見された『四天王寺御手印縁起(してんのうじごしゅいんえんぎ)』は、仏法が滅び尽きたときの社会のありさまをこのように描いている。聖徳太子が未来を予見して書き残したとされる『聖徳太子未来記』は、これ以後、中世社会を通じて次々と生み出されてくる。1054年(天喜2)、河内(かわち)国にある太子の墓近くの土中から、「吾入滅以後四百卅余歳に及びこの記文出現する哉(かな)」などと刻まれた石が発掘された。慈円(じえん)の『愚管抄(ぐかんしょう)』にも「世滅法と聖徳太子の書きおかせ給(たま)えるも、あわれにこそ、ひしとかないて見ゆれ」とあり、藤原定家(ていか)は日記『明月記(めいげつき)』に1227年(嘉禄3)「人王八十六代の時東夷(とうい)来る」で始まり「獼猴狗(びこうく)人類を喰うべし」という奇怪なことばで結ばれた石の記文が掘り出されたことを記している。また「末代土を掘る毎(ごと)に御記文出現」とも書かれており、このころには頻繁に未来記が発掘されたようである。
南北朝内乱期には「聖徳太子未来記五十巻」という大部のものも現れ、「帝王九十五代、春秋を経て在位し、仏法王法の繁昌(はんじょう)今秋なり。但し七百日滅尽すべし。……」「人王九十六代、天下大いに兵乱す。東魚来りてこれを静む。しかる後西鳥東魚を食う」などが知られている。95代は後醍醐(ごだいご)天皇にあたるとされている。『太平記(たいへいき)』にも楠木正成(くすのきまさしげ)が将来への確信をもったとされる未来記があり、それは次のようなものである。「人王九十五代、天下一たび乱れて主安からず。この時東魚来りて四海を呑(の)む。日西天に没すること三百七十余箇日、西鳥来りて東魚を食らう。その後海内一に帰すること3年。獼猴の如(ごと)くなるもの天下を掠(かす)むること三十余年。大凶変じて一元に帰す」
応仁(おうにん)の乱が勃発(ぼっぱつ)した1467年(応仁1)の『大乗院寺社雑事記(だいじょういんじしゃぞうじき)』には、仏法王法公臣の道がいままさに断絶するかという切迫した現状に触れたあとで、「本朝の代終わり、百王の威尽きる」と始まる未来記が書き付けられている。
このように、未来記は中世において繰り返し生み出され注目を浴びてきた。もうすでに死んでしまった過去の聖なる存在が書き残した予言、それが土の中から掘り出される。これは確かに当時の人々にとって心ひかれるできごとであったに違いない。初めは宗教的な性格の強かった予言は、だんだんに政治的色彩の濃い内容のものへと変化し、承久(じょうきゅう)の乱や南北朝内乱そして応仁の乱といった危機の時代にはかならず現れている。このように、次々と生み出されてくる未来記をつなぎ合わせると、中世における一つの歴史意識の流れが浮かび上がってくる。平安期の未来記にみえる「太子入滅後何年すれば」という表現は、釈迦(しゃか)入滅という時を起点にして、1000年間の正法(しょうほう)そして1000年間の像法(ぞうほう)の時期が過ぎると末法(まっぽう)の世が到来するという、あの末法思想に相通じるものがある。入末法の年についてはさまざまな考え方があったが、もっとも広く信じられた説では、1052年(永承7)が末法元年にあたるとされている。その末法に入ってすでに久しい鎌倉期になると、第何代目の王の時にどういったことが起こる、という表現が目だってくる。これは、当時、歴代の天皇を中心にした年代記が数多くつくられていて、人々が歴史をとらえるときの枠組みになっていたことを示すものである。しかし、同時にまたここでは、王は100代をもって滅ぶとする考え方が共通の軸となっており、100代まであと何代残っているのかという点に大きな力点が置かれていることを見落としてはならない。
末法思想や百王思想は、末世の到来あるいは百王の威尽きるなどという形で、未来に一つの約束された結末を設定する。しかし、そこでは末法ののち、百王ののちの具体的イメージが語られることはない。仏法滅尽王法衰微の末世という現実認識を基礎にして、次々と、より遠い未来に終末と崩壊を設定し続ける。いいかえれば、世界の破滅をつねに意識し、そしてそれを未来の方向に押しやり続けるところに、中世の時間意識の特異さがある。
(2)冥と顕の二つの世界
ところで、中世の人々は、歴史を動かし、未来に一つの結末をもたらすものが、現実の歴史の内にあるとは考えていなかったし、できごとの因果関係を歴史内在的にとらえきれるとも思っていなかった。彼らはつねに、現実の歴史の背後にもう一つの世界が存在すると考えていた。それは人々の目からは見えず、その意志も計り知れないものであるが、つねに人々の動きを見守り続け、その方向を支配するものであった。慈円は現実の世界を「顕(けん)」とし、それに対して、人々の目には見えない超越したこの世界を「冥(めい)」の世界と位置づけている。中世に幾度となく書かれた起請文(きしょうもん)には、もし偽りをいったならば、伊勢(いせ)大神宮や八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)をはじめ日本国中の大小神祇(じんぎ)、さらには大地をつかさどる地神に至るまでの「冥罰(みょうばつ)」をわが身に蒙(こうむ)るべしと記されている。ここでも人々は、いつでも自分たちの言動を注目しているものたちがいることを意識しており、そのものたちの照覧が誓約を成立させる大きな力となっている。この「冥」の世界は、秩序だった神々と仏だけの世界ではない。たとえば頻発する火事は「天魔の所為か」とされ、また将軍の没落を声高に告げ知らせるものがいて洛中(らくちゅう)騒動という事態が起きたときも、それは「天狐(てんこ)のしわざか」ということになってくる。「天魔」や「天狐」、そして『太平記』で縦横に跳梁(ちょうりょう)する「天狗(てんぐ)」や「怨霊(おんりょう)」などの霊的で呪術(じゅじゅつ)的な要素をもつ存在をも含めた多様なものによって、「冥」の世界は形づくられていたのである。
末法の世になると、現実の世界の動きを支配している「冥」の世界の道理を認識できなくなり、人々はこの世の移り行く方向をとらえきれなくなる。では「冥」の世界とつながり、その意志を計りうるものはまったくなくなってしまうのか。慈円は願文に、「顕」と「冥」が隔たってしまって混迷に陥ったなかで、未来を知る手だてはただ夢だけだ、と記している。夢は「冥」の世界から発せられるテレパシーのようなものと受け止められ、夢告の意味を知ろうとして人々は大きな努力を傾けるのである。そしてもう一つの手だてが、「冥」の世界からの化身としてこの世界に到来した特別な聖なる存在である。すべてを予見できる優れた能力をもった予言者とされる聖徳太子も、そうした超越的な者の1人である。それゆえ彼の予言は、「冥」の世界からの架橋であり、二つの世界を結ぶ神秘的な回路と考えられた。
中世社会を通じて、次々と繰り返し生み出され続けた未来記には、当時の人々の歴史に対する、こうしたとらえ方が示されているのである。
[酒井紀美]
近世における歴史認識
近世においては、権力の推移について具体的で系統的な歴史認識を有する者は、基本的には支配層に属する者だけである。それは、学校という場で歴史を教えられる機会がなかったためばかりではない。むしろ歴史認識が、権力者がその支配の正当性を弁明するために行った修史事業のなかで形成されたという本質的事情による。しかも民衆が政治に参加することを許されない以上、権力の正当性を表明する対象もまた本来的には支配層に限られていた。したがって、日本の国家の具体的な歴史事象に対する認識に限定すれば、近世という時代に歴史認識を有する者は支配層に限らざるをえないし、拡大してみてもせいぜい、そのなかにあって時の権力者とは距離のある者、あるいは権力的な歴史認識に対する批判を内包した一部の知識層の者にまで広げられるだけであろう。一方、近代へと移行するこの時代は、民衆が歴史そのものに参加してくる時代、あるいは参加していたはずの民衆がそのことを自覚してくる時代である。このことを踏まえれば、民衆のなかにたとえ断片的もしくは人物伝的なものであっても、そこにはより広い意味での歴史意識、あるいは漠然とした歴史観とでもいうべきものが形成されているはずである。重要なことは、そのような歴史意識あるいは歴史観が、民衆のなかにどのようなものとして存在していたかをとらえることであろう。
(1)支配層および一部知識層の歴史認識
近世前期におけるもっとも権力者的な立場からの歴史書は、幕府儒官の林羅山(らざん)・鵞峯(がほう)(1618―1680)父子が幕命によって編纂した『本朝通鑑(ほんちょうつがん)』と、水戸藩が編纂した『大日本史』であろう。『本朝通鑑』は、一般には儒教的合理主義にのっとった編年体の史書とされているが、羅山個人の歴史観を貫くものは儒教的もしくは朱子学的合理主義とはいいがたい。羅山の歴史観が率直に表れているのは『神道伝授(しんとうでんじゅ)』や『東照大神君年譜序(とうしょうだいしんくんねんぷじょ)』『神祇宝典序(じんぎほうてんじょ)』などであるが、そこでは朱子学的合理主義が有する歴史観の核心である湯武放伐(とうぶほうばつ)=易姓(えきせい)革命の論理と、その思想的本質である格物致知(かくぶつちち)は無視され、もっぱら天皇家と徳川家の血縁の連続の論理が貫かれている(家康皇胤(こういん)説など)。羅山らにみられる歴史観の非朱子学性(神儒習合的性格)は、『中朝事実(ちゅうちょうじじつ)』や『武家事紀(ぶけじき)』などで、「天皇が不徳のため統治を武臣に交替する」という論理を明確に展開した山鹿素行(やまがそこう)らにも共通してみられるもので、彼らのそうした歴史認識には、天皇を形式上の君主として承認して初めて成り立つ幕藩制国家のあり方が直接反映していたといえよう。
近世中期では新井白石がその著『読史余論』において、儒教的合理主義の発想から歴史の発展段階的区分(九変五変観)を試み、武家政権発展の延長に徳川幕府権力が位置することを主張し、その治世の史的意義を礼賛したことが特筆されよう。一方、水戸藩主(2代)徳川光圀(みつくに)が多くの史家に命じて編纂を始めた紀伝体の史書『大日本史』には、南朝を正統と主張したり、忠臣・逆臣を弁別するなど独自の尊王論が展開された。
後期に至ると、その編纂を継承した藤田東湖(とうこ)・会沢正志斎(あいざわせいしさい)などが新たな国家観・歴史認識を展開する。彼らの歴史認識は、ヨーロッパ勢力が外圧として押し寄せ、幕藩体制内部の矛盾も露呈されてきた時点で、支配層が抱いた民族の危機意識の一つにほかならず、これは、東湖においては尊王攘夷(じょうい)論の主張として、また会沢においては国体論の主張として展開された。とくに会沢の著『新論(しんろん)』には、その根底にヨーロッパ列強に対する劣等感覚を内包した(それと表裏の)優越感覚が、神話的な「神州」に対する陶酔感として漂っており、狭量で排外主義的な歴史認識が「情熱的」に表明されている。また、後期水戸学の歴史認識の形成には、本居宣長(もとおりのりなが)に発し平田篤胤(あつたね)に至る国学の歴史認識と国家観が強く働いている。宣長の『古事記伝』における考証学的作風も、篤胤の『古史徴(こしちょう)』にはみられず、神道的要素が非合理的・国粋主義的方向で展開されている。これらが、後期水戸学の歴史認識と相まって、幕末期の尊王論者―維新政権の官僚たちに大きな影響を与え、近代天皇制国家の権力的な歴史認識=皇国史観を形づくっていったのである。
なお、『日本外史(がいし)』を著した頼山陽(らいさんよう)や、幕末に『大勢三転考(たいせいさんてんこう)』を著した伊達千広(だてちひろ)などは、いずれも独自の歴史認識を有していた。ことに山陽は天皇権威の絶対性、皇室の無窮性を主張し、かつ現実の政権交替の不可避性をあわせ述べており、これらも幕末の志士たちの行動に一つの歴史認識上の根拠を与えていった。
以上の史論・史書にみられる歴史認識は、おおむね支配者的な立場からのそれであると一括しうるが、知識層のなかからこれらの史観とは根本的に対立する歴史認識を有する人物も出ている。そのなかでも安藤昌益(しょうえき)はもっとも徹底的に反権力的な歴史観を表明した者である。昌益はその著『自然真営道(しぜんしんえいどう)』や『統道真伝(とうどうしんでん)』において、支配者(「聖人」)が民衆(「衆人」「真人」)から搾取する(「不耕貪食(どんしょく)」)ような治世のあり方自体が、歴史上のすべての乱の基であるとして現実の階級社会(「法世」)を否定し、本来の人間社会である無階級のユートピア社会(「自然世」)を、やがてくるべき社会として想定しており、農民本位の空想的社会主義の歴史観を表明している。
(2)民衆のなかの歴史観
近世の民衆がどのような歴史観・歴史意識を有していたかについてはまだまとまった研究はない。したがって、ここではそれを考えるうえでのいくつかの手掛りを提示し、若干の検討を加えることで今後の素材とする。まず、民衆が一定の歴史観・歴史意識をもちうる機会・背景を列挙すると、(a)名主(なぬし)など村役人層による村運営の際や寺子屋などを通じて断片的な歴史事象が知らされうること、(b)浄瑠璃(じょうるり)・歌舞伎(かぶき)などの芸能の世界に触れること、(c)仏教や民衆の信仰のなかの生命観・自然観に含まれる広義の歴史観に日ごろから触れていること、などである。以下順次考察を加えたい。
まず(a)についてであるが、これはどちらかといえば、前述の支配層が有する歴史認識が持ち込まれうる機会である。ただし、幕末期に平田派国学に傾斜したいわゆる草莽(そうもう)の国学的な名主が村政運営する場合などには、そうした歴史認識の一端が村内に直接的に持ち込まれることがあったとみてよいが、一般的には名主や村役人自身がそれほど具体的な歴史認識を持ち合わせていない。彼らが記したかなり詳しい参宮道中記などをみても、旅中の史跡に対する知識は、おおむね『太平記(たいへいき)』などの軍記物や芸能からのものであり、物語的歴史認識である。したがって、支配層が有していた天皇と武家にかかわる歴史認識などが、上から意図的に注入されることはほとんどなかったとみられる。また、寺子屋なども特殊な場合を除けば読み書きなどの技術の習得が中心で、近代の学校のように、支配の要請によって儒教的な思想が歴史認識にかかわることとして系統的に教授されることは少なかった。
次に(b)について述べる。近世中期に上方(かみがた)で盛んになった人形浄瑠璃や、後期~幕末期に江戸で栄えた歌舞伎などの作品にも、ある意味の歴史観・歴史意識が潜んでいる。江戸・大坂・京都の三都の富裕町人や、伊勢参宮などの旅に出た地方の上層農民らが江戸や大坂でこれらに親しんだが、たとえば歌舞伎の『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』『義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)』『勧進帳(かんじんちょう)』などでは歴史の「敗者」に同情が寄せられ、強い権力や勝者を好まない情本位の歴史観が提供される。また『本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)』では、敵対する武将の娘への恋に苦悶(くもん)する武田勝頼(かつより)が描かれている。これ以外にも、武士が主君への忠義のため親子・夫婦の情愛を犠牲にするようなテーマ・場面が多く、儒教的封建道徳を優先させながらも、それがしばしば人間の情に対立するものであることが描かれており、観衆の側で武家社会のあり方を相対化する契機が含まれていたことは、民衆の歴史観を検討するうえで留意すべき点であろう。また、幕末期の百姓一揆(いっき)の激発のなかで、1851年(嘉永4)に江戸中村座が上演した『東山桜荘子(ひがしやまさくらそうし)』(佐倉義民(さくらぎみん)伝)は、いままで不動のようにみえていた武家の支配が大きく動揺してきたときだけに、歴史に対する民衆の主体的なかかわりについて、観衆のなかになにがしかの意識をもたらしたものと思われる。
最後に(c)について考えてみたい。近世は、寺檀(じだん)制度の下で中世以上に仏教ないし仏教的習俗が民衆の生活のなかに定着した時代であった。仏教的世界観・生命観が、経文の諳誦(あんしょう)や法話、節談説法(ふしだんせっぽう)、絵解き仏教説話などを通じて、広く民衆の生活意識として根づいていった。宗派による差異が著しいので一概に論じられないが、輪廻転生(りんねてんしょう)観、因果応報(いんがおうほう)観、他界観などは、人間の歴史に対する見方を包摂する観念であり、それらが実に多様な形態で生活のなかに漂っていた点を十分に検討すべきであろう。自己およびいっさいの生命を、過去(宿世)から現在(現世)そして未来(来世)へと転生するものとするとらえ方、また来世での浄土往生に至上の価値をみいだす価値観などは、その展開のありようによっては、現実の歴史における権力者的な価値観を相対化する役割を果たすものである。たとえば、能の世界では、現世の戦いで数々の武勲をたてた武士が、来世においてその殺生の罪のために修羅(しゅら)の苦しみを受け、成仏できずにいるような場面が少なくないが、そこでは現世の封建的価値観は仏教の普遍的人間観によって否定されている。こうした仏教的思惟(しい)が、特定の歴史観の受容以前に、近世民衆のなかに広範な規範として存在していたことは見落とせない。すなわち、近代において国家的「民族的」な一国史観が、封建的忠孝観念を媒介にして上から押し付けられてくる以前に、それを拒絶しうる、より普遍的な思惟のあり方が民衆のなかに存在していたことをみておく必要があろう。なお、海の彼方(かなた)からやがてこの世に弥勒(みろく)の世がもたらされるという弥勒信仰も、民衆がもっていた土俗的なユートピア感覚であり、民衆的歴史観の一つといえる。幕末の百姓一揆の高揚や世直し情勢のなかで、そうした弥勒信仰的な歴史観の発露があったことも記憶にとどめたい。
[奈倉哲三]
近・現代における歴史認識
近・現代における歴史認識の推移を、各時期の主要な課題・思潮と歴史学のあり方とのかかわりに中心を据えて、みていくことにしよう。
(1)文明開化と文明史学
日本人の近代的な歴史認識は、明治初年の「文明開化」の思潮のなかに源を発する。ギゾーやバックルの文明史、およびスペンサーの社会理論が、その湧出(ゆうしゅつ)に多大な影響を与えた。啓蒙(けいもう)思想家たちは日本社会の近代化を図ろうとする優れて実践的な意識に支えられて、日本の過去と直面し、これと対決した。福沢諭吉(ゆきち)は『文明論之概略』(1875)を書いて、野蛮→半開→文明という一種の発展段階論を提出し、半開日本の文明化を希求した。「日本国の歴史はなくして日本政府の歴史あるのみ」、彼は政権交替の叙述に中心を置くこれまでの歴史書をこう批判して、人民の歴史、被治者の歴史を指向し、「権力の偏重」に日本歴史の特質をみた。こうした日本社会の病弊の告発は、西洋と日本とを対比するという世界史的視野を前提として初めて成り立ったものであった。しかし、福沢の功績は特質の把握に終わって、日本社会の発展過程の解明は、次に出た田口卯吉(うきち)の手にゆだねられた。自由主義経済学者として著名な田口は『日本開化小史』(1877~1882)を書き、史料に依拠して日本の歴史を発展的に描き出した。彼は歴史の法則的認識を目ざし、歴史発展の原動力を人間の本来的欲望と、生産力の発展に求めた。歴史に向き合う田口の主体的姿勢は、自由民権運動にくみし、当年の政府の干渉主義的経済政策を厳しく批判していた実践と深くかかわり合うものであった。
(2)明治国家とアカデミズム史学
在野の文明史学が近代的な歴史認識の水門を開いているとき、政府の側は正史編纂事業を進めていた。これを担当したのは修史局に集まった考証学系の漢学者、重野安繹(しげのやすつぐ)・久米邦武(くめくにたけ)・星野恒(ほしのひさし)らで、彼らは新史料に基づく考証の結果、『大日本史』に代表される大義名分的・勧善懲悪的歴史認識をしだいに退けていった。一方、1880年代、ドイツ流に傾斜していく国家路線に対応して、歴史学にもドイツの影響が及び始めた。1887年(明治20)帝国大学文科大学に史学科が設置され、ランケの弟子リースが教授として着任。その助言で史学会が創立され、『史学雑誌』が創刊された。また、修史局は1888年に帝国大学に移管されて、重野らは1889年設置の国史学科教授となった。こうして、考証史学とランケ風ドイツ史学を基礎にアカデミズム史学は成立した。草創期の『史学雑誌』は考証派の論文を掲げて、儒教的大義名分論と対決した。しかし、第5号誌上でリースが、抽象的な議論をやめて史料に基づく調査・研究に従事すべきことを提起してから、実証主義・史料主義が主流となっていった。1890年教育勅語が出されたとき、星野はこれに迎合する道を選び、他方、久米は論文「神道は祭天の古俗」が神道家・国家主義者の攻撃にあって、大学を追われた。こうして官学アカデミズムは、政治権力に従属しながら、問題意識を欠いた実証主義を歴史学の基本とする道を歩んでいく。
(3)民友社と史論史学
アカデミズム史学の成立期は、他方で史論史学の台頭期でもあった。それは、1890年前後から1900年代初頭にかけて、「官」に対する「民」の側から、文明史学を受け継ぐ民間史学として登場してきた。代表的担い手は、山路愛山(やまじあいざん)、竹越与三郎(たけごしよさぶろう)、徳富蘇峰(とくとみそほう)らで、いずれも雑誌『国民之友』に拠(よ)る民友社系のジャーナリストであった。彼らは考証に拘泥する官学史学への対抗意識を抱きながら、政治・経済・社会・思想・文化の幅広い領域で史論を展開し、歴史に生命を吹き込んだ。政治的には民党の側にたって藩閥政府を批判するという現実に対する実践的姿勢が、新しいテーマの発見へと導き、党派的立場が史論の明快さを生んだ。ただし、史料に基づく実証方法に弱点があったことは否めない。
(4)大正デモクラシーと自由主義的史学
日露戦後から第一次世界大戦前後にかけて高まりをみせたデモクラシーの機運は、法律学における天皇機関説、政治学における民本主義を生み出したが、このような自由主義的思潮は歴史学のうえにも及んだ。『神代史の新しい研究』(1913)、『文学に現はれたる我が国民思想の研究』(1916)などを書いた津田左右吉(そうきち)は、ヨーロッパ近代の神話学・宗教学・民俗学・心理学・文献学に学んだ合理主義的研究方法を駆使して、日本民族の独自性を究明しようとした。とくに『古事記』『日本書紀』の厳密な史料批判を通じて打ち立てた日本古代史研究によって、古代に関する歴史認識は初めて神話から解放された。津田史学の基底に据えられていたのは、「国家」「国体」ではなく、「国民」であった。1911年(明治44)国家権力の弾圧を受けて野に下った喜田貞吉(きたさだきち)もまた、1919年(大正8)雑誌『民族と歴史』を発行し、「国民側」「劣敗者の地位」にたって、天皇の歴史、権力の歴史ではなく、民族の歴史、民衆の歴史を明らかにしようとした。国史学の政治史偏重に対して社会史を対置したのである。また、民俗学を樹立した柳田国男(やなぎたくにお)は、権力者が残した史料にもっぱら依拠するこれまでの歴史学によっては顧みられることのなかった農民に目を注ぎ、その暮らしと伝承を通じて日本と日本人のあり方に迫った。柳田民俗学は、政治史を中心とした歴史学の英雄史観に、生活史を中心とした「常民」史観を対置し、民衆の日常性から過去をとらえようとした。京都大学の西田直二郎(なおじろう)は『日本文化史序説』(1932)を書いて文化史学を創始し、世界史的視野から日本史の全体像を展望した。それは、各部門の羅列ではなく、歴史家の主体的判断によって部分から全体を構想しようとする明確な歴史理論に裏づけられていた。その背後にあったのは、リッケルトやディルタイから学び取った歴史哲学的省察であった。また、国史の枠の外では、経済学部を基盤とした経済史学が経済政策と結び付き、日本資本主義の要請にこたえながら発展していた。本庄栄治郎(ほんじょうえいじろう)(1888―1973)らがその中心であった。すでに1900年代、内田銀蔵(ぎんぞう)が日本経済史と歴史理論に大きな成果を残していたが、西田・本庄の研究はこれを継承・発展させたものであった。こうして、自由主義的な史学の潮流は、国民の歴史意識を国家・国体から解き放ち、より自由な市民的・民衆的方向へと転換させる機能を果たした。これを歴史学における「民本主義」の表れとみることもできよう。
(5)マルクス主義と唯物史観史学
1920年(大正9)前後の時期に社会史的研究が登場してきた背景には、第一次世界大戦後の社会問題の深刻化、労働運動・農民運動など社会運動の発展があった。こうした状況はさらに進んで、労働者の側にたつ史学、唯物史観を方法とする史学を生み出した。分析の指針となったのは、いうまでもなくマルクス、エンゲルス、レーニンらの理論である。政治史偏重でもなく、政治史を捨象した経済史でもなく、文字どおり経済的下部構造と政治的上部構造の統一物として歴史は構想されることとなった。しかも、日本の近・現代を本格的な歴史的分析の対象としたのは、唯物史観史学が最初であった。それは、現状を変革しようとする優れて実践的な立場から歴史が問題にされたことに由来している。1922年前後の佐野学(まなぶ)による社会史研究を先駆とし、福本和夫(かずお)の唯物史観に関する理論的提起を前提として、それは1927年(昭和2)前後に成立した。野呂栄太郎(のろえいたろう)『日本資本主義発達史』、服部之総(はっとりしそう)『明治維新史』が唯物史観史学の成立を告げる記念碑的作品である。ついで羽仁(はに)五郎が出てブルジョア史学に鋭い批判を向け、マルクス主義史学の優位性を主張した。彼らの研究は、きたるべき革命の性格を規定する現状分析の問題と密接な関係をもち、迫りくるファシズムと戦争の危機に立ち向かう運動の一翼を担った。その結晶が、『日本資本主義発達史講座』全7巻(1932~1933)であり、この達成はその後、歴史学ばかりでなく、社会科学の諸領域にわたって深甚の影響力を及ぼしていくこととなる。『講座』に結集した平野義太郎(よしたろう)は『日本資本主義社会の機構』(1934)に、山田盛太郎(もりたろう)は『日本資本主義分析』(同)に、それぞれの成果をまとめあげた。こうして、日本資本主義の「軍事的半農奴制的」=封建的特質を指摘し、天皇制絶対主義の支配を打破することに当面の課題を設定する講座派理論が成立した。天皇制と正面から対決する歴史認識が初めて登場したのである。これに対して、雑誌『労農』に集う理論家は日本資本主義のブルジョア性を強調し、両者の間で日本資本主義論争が展開された。論争を通じて問われたのは、日本社会の全体像を世界史のなかにいかに位置づけるべきかであった。
(6)ファッショ化と皇国史観
『講座』が出たころ、官学アカデミズムのなかには、歴史学を戦争とファシズムの具に供しようとする勢力が登場していた。平泉澄(ひらいずみきよし)がそのリーダーである。彼は陸軍皇道派や新官僚などのファッショ的政治勢力に接近するとともに、東大学内に朱光会(しゅこうかい)をつくって、皇国史観の主導者となった。このような天皇を中心とした国家体制の正当化を目ざす非科学的歴史認識は、文部省編『国体の本義』(1937)などに集約され、国民を国粋主義的に統制するイデオロギーとなっていった。すでに1936年講座派が弾圧にあい、1937~1938年労農派も弾圧されて、唯物史観史学の前に政治権力が立ちはだかった。そればかりではない。官憲は1940年には極右勢力の攻撃を受けた津田左右吉を出版法違反容疑で起訴し、古代史の研究書4冊を発売禁止に付した。学問研究の自由は奪われた。しかし、ファッショ的支配のもとでも、歴史学研究会を拠点とする研究者や、羽仁の指導を受けた人々によって科学的・実証的研究は続けられ、敗戦後、新たな歴史認識を提示する前提が準備されていた。
(7)第二次世界大戦後の変革と科学的歴史認識
敗戦を機として日本社会の民主主義的変革を目ざす動きは高まった。これに即応して、歴史認識においても、封建制を克服して民主化・近代化を達成しようとする強烈な課題意識に支えられた成果が現れて、大きな影響を与えた。経済史の大塚久雄(ひさお)は、西欧を理念型とした近代社会像・近代的人間像を提示して、日本近代の歪(ゆが)みをえぐり出した。政治思想史の丸山真男(まさお)は、西欧近代を基準とした超国家主義の分析を通じて、日本近代の思想的特質を明らかにした。法社会学の川島武宜(たけよし)は、日本社会の家族的構成を明らかにして、その封建的特質を解明した。このような非マルクス主義の社会科学者とともに、この時期、戦時中の研究蓄積を踏まえたマルクス主義歴史家の活躍も目覚ましかった。彼らは史的唯物論に基づいて日本社会の発展過程の法則性を明らかにし、科学的歴史認識を打ち立てようとした。ただ、その歴史認識には、西欧基準の「世界史の発展法則」がいかに日本社会に貫徹しているかを検証しようとする傾向が強く、一国史的・公式主義的性格はぬぐいがたかった。しかし1950年代に入ると、対日講和問題・朝鮮戦争などで政治情勢が緊迫の度を深め、他方、アジア、アフリカ、ラテンアメリカでは民族運動が高まった。こうした情勢に刺激されて、歴史学においても民族の問題が提起され、また、国際的視野とアジアへの視角が導入されていった。これは、1960年代以後、国内的契機と国際的契機の統一的把握によって世界史像・日本史像を再構成しようとする認識へと連なっていく。
(8)帝国主義的歴史観と民衆史・人民闘争史
1960年代に入ると、経済の「高度成長」と即応して、日本の工業化・近代化を美化する歴史認識がアメリカの駐日大使ライシャワーらによって持ち込まれ、国民の大国意識の伸長を図った。また、「建国記念の日」の制定、「明治百年」記念式典の実施、教科書の検定など、歴史認識を国家が統制しようとする動きも強まった。こうした帝国主義的歴史認識に抗しつつ、科学的歴史認識を構築するための活動は続けられた。1960年代後半以降、「60年安保」の経験を踏まえて登場した民衆のエネルギーと意識に注目する民衆史・民衆思想史、国家権力と、これに対抗して変革を志向する人民の諸闘争に分析を加える国家史・人民闘争史は、そうした歴史認識の試みであった。そのなかで、民衆を歴史の基本的主体とする認識が固められ、女性史・部落史・地方史などさまざまな分野で認識の広がりと深まりが獲得されていった。
(9)社会史への傾斜と「国家」相対化の志向
第二次世界大戦後の歴史学は歴史認識の基礎に民衆を置き、世界史的な視野で歴史を構想しようとする流れをかたちづくってきた。しかし、「高度成長後」の1970年代なかば以降、従来の視点や方法に対する再検討の気運が高まってきた結果、この流れも新たな様相を呈することとなった。国家中心、権力中心の政治史や、闘う人民の闘争史とは異なって、多様な民衆の日常生活や意識・心性の復元への関心が強まった。このいわゆる社会史は、ヨーロッパの研究潮流の影響を受けつつ、新しい研究分野を開拓し、研究領域の拡大も促した。また、文書にとどまらず、伝承や絵画など、過去のさまざまな素材を史料として活用する道をひらき、方法面でも社会学・人類学・言語学などとの協力関係を深めた。他方、国際化の進展は、「国家」の枠組みを相対化しようとする志向を強めさせ、「単一国家」「単一民族」観への批判は顕著となった。自己完結的な「一国史」の枠を打破しようとする志向も強まり、東アジア世界のなかで「日本」の歴史をとらえようとする潮流が各時代を通じて顕著となった。また、現代史においては、侵略戦争、とくに加害の実態を究明する研究が前進し、国民の戦争認識にも大きな変化を引き起こすこととなった。1990年代に入って、こうした流れはさらに加速されたが、他方で「国家」「国益」を強調してその逆流をはかろうとする試みも浮上し、両者の相克状況は「日本人」の歴史認識のあり方を、改めて問い詰めることとなった。
[大日方純夫]
日本史発展の特質
日本史における人民支配の体制
(1)階級と身分の発生
日本における階級の発生は、弥生(やよい)時代中期(紀元前後)に共同墓地の甕棺墓(かめかんぼ)の中に鏡や剣などの副葬品をもったものが現れてくることや、その後、支石墓(しせきぼ)や方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)など共同体内の支配者の墓と考えられる特別の墳墓が出現することなどによって確認できる。また、文献的には、中国の史書『漢書』地理志(かんじょちりし)や『後漢書』東夷伝(ごかんじょとういでん)から、紀元1、2世紀の「倭(わ)」に「百余国」の国があり、そのなかの一国王「帥升(すいしょう)」が「生口(せいこう)(=奴隷)百六十人」を献じていることなどが記されており、すでに階級が成立していたことがわかる。
この階級差を具体的に知ることができるのが『魏志(ぎし)』東夷(とうい)伝倭人(わじん)条に記された「邪馬台国(やまたいこく)」の場合である。邪馬台国では、女王や奴隷だけでなく、社会の構成メンバーのなかにも「大人(たいじん)」「下戸(げこ)」という身分差が明確に現れてきており、また官僚制も一定程度発達し、「諸国を検察」する「一大率(いちだいそつ)」や中国の漢時代の「刺史(しし)」のような地方官が存在したことが知られ、階級国家としての体裁を整えつつあったといえる。
(2)氏姓制度と部民制
4世紀に入り大和王権(やまとおうけん)が成立すると、氏姓(しせい)制度と部民制(べみんせい)という新たな支配制度がつくられたが、それが明確な形をとってくるのは5世紀のことといわれる。氏姓制度は、中央貴族や地方豪族が国政上の地位や身分の尊卑に応じて、王権よりウジやカバネ(臣(おみ)・連(むらじ)など)を与えられ、国家的な身分を表示するとともに、王権内部における特定の官職を世襲し、それに基づいて土地・人民を支配した制度である。
氏姓制度が支配層内部の秩序を形づくったのに対し、人民支配の根幹が部民制である。部民制の成立過程については未確定の部分が多いが、4~5世紀の大和王権の征服過程と並行して諸豪族領有下の人民(部曲(かきべ))をトモ・品部(しなべ)として王権に従属・編成して、労役の提供や生産物を貢納させる体制をつくりだし、6世紀初頭ころに確立したと考えられている。こうして体制的に成立した部民制は、(a)品部=大王(おおきみ)の民、(b)子代(こしろ)・名代(なしろ)=大王家の私有民、(c)部曲=諸豪族の私有民、の3種類から構成された。
しかし、大和王権の基盤を形成した部民制も、群集墳の発生などにみられるような在地構造の変化と、それに伴う支配基盤の動揺に対応するため、7世紀中葉には廃止され、王権による一元的な人民支配が進められる。その契機をいつに求めるかは、いわゆる646年(大化2)の「大化改新詔」の信憑(しんぴょう)性とも関係する難問題であるが、ここでは「改新詔」、664年(天智天皇3)の「甲子の宣(かっしのせん)」、そして675年(天武天皇4)の「部曲廃止令」を通して、部民制の廃止と、一元的な人民支配政策が遂行されたと評価しておきたい。それは律令(りつりょう)制の導入と密接に関係するが、人民支配の具体的な形態としては、670年(天智天皇9)の庚午年籍(こうごねんじゃく)、690年(持統天皇4)の庚寅(こういん)年籍という戸籍の作成と関連して進められた。
(3)編戸制と班田制
日本の律令制は近江(おうみ)令(存在を疑問視する見解もある)、飛鳥浄御原(あすかきよみはら)令、そして701年(大宝1)の大宝(たいほう)律令の施行によって法制的な完成をみるが、その人民支配の特徴は、まず人民を「良」と「賤(せん)」の2身分に大きく区分して支配したことである。しかし、「賤」は全人口の1割程度であったから、実質的な意味をもったとは考えられず、実際に人民支配を担ったのは良民の支配制度である編戸制と班田制である。
律令制国家の人民支配の基本的な単位は「戸(郷戸(ごうこ))」で、5戸で保(ほ)を構成して治安・納税上の連帯責任を負わせた。そして50戸で1里を構成し、地方支配機構の最小の単位に位置づけられた。このように戸を基準に編成された支配体制を編戸制といい、その台帳が戸籍・計帳である。戸籍は6年に一度作成され、人民の身分の確定をするとともに班田収授の台帳にもなった。班田面積が男子に多く(6歳以上の男子に2段(たん)、女子にその3分の2)、かつ、租税も正丁(しょうてい)(成年男子)を中心とした負担体系であったから、律令制国家の人民支配体制は「戸」を単位としながらも成年男子を支配の中心とした体制であったといえる。このことは、編戸が兵士徴発の前提であったことによく示されている。
律令制的人民支配のもう一つの特徴は、国郡里制を敷き、国司(こくし)は中央派遣にするなど中央集権的な地方支配体制をとったにもかかわらず、郡司(ぐんじ)はその地の有力豪族を任用したことである。すなわち、律令国家の地方支配は国司までの中央集権的な体制と、郡司以下の旧来の在地的な支配体制の温存という二重構造をとったのである。
このような支配の二重構造の評価を含めて律令制的な支配体制の完成期については、平城京(へいじょうきょう)遷都前後に完成期を求める定説に対して、奈良時代は法としての律令と、現実の社会制度との間にまだ整合性が認められず、律令が社会に内実化していくのは平安時代、とくに10世紀以降であるという新説が出されており、今後の研究が期待される。
(4)公田・負名制
編戸と班田による人民支配も、9世紀に入ると編戸支配を打破した「富豪浪人(ふごうろうにん)」=富豪層などの成長によって大きく動揺する。初め律令政府は彼らを支配体制を否定する存在として禁圧の対象とした。しかし国家財源の確保と支配体制の再編のための現実的な対応から、彼らを「田堵(たと)」として認め、9世紀末~10世紀初頭の国政改革を通じて、彼らの経営を収取の基盤とした体制を成立させる。それが負名制(ふみょうせい)である。負名制は、班田制(口分田支配)にかわってすべての田地を公田として掌握しなおし、その公田を耕作者の能力に応じて耕作させるとともに租税の納入をも請け負わす制度であった。このような土地制度を公田・負名制とよぶ。したがって、この制度は能力主義を基本としたが、一方で租税未進の場合は耕作権も否定されるという「有期的請作(うけさく)」が原則であった。ここに至って中央政府が戸籍・計帳によって人民を個別的に(戸を介在するが)支配する体制は完全に放棄され、国家の人民支配は「負名」=在地の有力者の支配を通じてしか実現できない間接的な体制となった。この重層的な支配体制は、以後中世を一貫して存在し、豊臣(とよとみ)秀吉による検地帳の作成、江戸時代の宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)や五人組帳の作成による百姓支配体制まで続くのである。
(5)荘園公領制
このような能力主義に基づく収取体制の採用は、在地有力者の公領の開発・再開発を推進させ、11世紀中ごろになると在地領主層の開発をもとに大規模所領が成立し、公領支配の再編が進んだ。そして、それらの運動を基盤に中世的な荘園(しょうえん)が形成され、12世紀前半には荘園公領制として中世的な土地制度が確立する。荘園公領制に基づく支配体制の完成については、天皇家(院を含む)・武家・大寺社の諸権門が相互に権限を分掌し補完しあう体制、すなわち権門体制に求める見解と、鎌倉幕府の成立による守護(しゅご)・地頭(じとう)制の確立を待たなければならない、とする説に分かれている。完成した荘園公領制は寄進地系荘園を中核としていたから、支配領有関係は重層的な構造をとった。下から上への寄進関係と、それに対応した上から下への職(しき)(一定の得分(とくぶん)権を伴った役職)の補任(ぶにん)とによって構成されたこのような重層構造は「職の体系」といわれ、支配階級の秩序を形成した。
荘園公領制下の収取体制は、公田・負名制から発展し有力農民層を支配の対象とした名主―名田制(みょうしゅみょうでんせい)である。その収取関係と彼らの結合によって成立した中世村落とを通じて人民支配が遂行されたが、それは国家による直接的な人民支配の実現ではなかったために、社会の秩序を保つシステムとして身分制がより重要な位置を占めることになった。
中世法の代表である「鎌倉幕府法」は「侍」「凡下(ぼんげ)」「下人(げにん)・所従(しょじゅう)」という3身分を設定し、一般民衆をさす凡下には体罰が許されるが、侍には許されないなど刑罰の面でも厳密な区分が規定されている。さらに、そのような大まかな区別だけでなく、現実的には侍・凡下という身分のなかにもいくつかの階層的な区別が存在した。たとえば凡下の場合には、まず農業民と非農業民(漁民や職人)に区分され、さらに農民は、少なくとも農民上層部の百姓で村落の運営を担った名主(みょうしゅ)百姓、小経営としては不安定であったが、いちおうは自立経営で農民層の多数を占めた小百姓の2階層に区分された。そしてそのほかに、その土地の本来の住民でなく流動性も強く、なかには卑賤視された者も含まれた間人(もうと)・非人(ひにん)、名主百姓以上の階層に人格的に隷属していた所従・下人などの階層が存在した。このような村落内身分秩序を通じて中世民衆は支配されていたのである。
荘園公領制は、鎌倉後期以後の一円領支配の進展や南北朝内乱そして大名領国制の展開による支配体制の変化、また惣村(そうそん)などの成立による村落結合の進展によって変化していくが、村落を媒介とした人民支配は戦国時代においても基本的には維持された。
(6)幕藩体制
中世の名田(みょうでん)制を媒介にした重層的な人民支配を克服して、一元的な支配体制を形成したのが近世幕藩制(ばくはんせい)国家である。その前提は豊臣秀吉の諸政策(太閤(たいこう)検地や兵農分離など)によって形づくられたが、確立するのは鎖国の完成後のことである。
幕藩体制の人民支配は兵農分離制と石高制(こくだかせい)によって実現された。兵農分離制は武士と農民を身分的に明確に区分するとともに、農民を収奪の主対象として位置づけた「士農工商」という身分制を成立させ、都市=城下町に集住した武士階層が全体として農村を支配し農民を収奪する体制をつくりだした。その収奪の具体的な内容を規定したのが石高制で、徹底した検地によって直接生産者である単婚小家族を本百姓として掌握し、中世的な重層的な収取体系を否定するとともに、彼らを耕地に縛り付けて、田畑ばかりでなく屋敷・山林からも米年貢を収奪する体制を成立させた。兵農分離制と石高制に基づく人民支配は村請制(むらうけせい)を通じて実現された。村請制は村高に応じた年貢や諸役を一村全体の百姓の連帯責任で納めさせた制度で、その実務と責任は村方(むらかた)三役(名主(なぬし)・組頭(くみがしら)・百姓代(ひゃくしょうだい))が負った。したがって村方三役、とくに名主は人民支配の末端として明確に位置づけられることになった。
また、支配と収奪を維持するために本百姓を耕地と村落に緊縛するための法令と制度が次々と打ち出された。法令としては田畑永代売買の禁令(1643)、分地制限令(1673)、そして農民の日常生活までに厳しい制限を加えた慶安(けいあん)の御触書(おふれがき)(1649)が著名である。また、制度としては年貢の完納や犯罪防止の連帯責任の制度である五人組、キリスト教対策としての寺請(てらうけ)制や宗門人別改帳があった。なかでも寺請制は檀那(だんな)寺を単位とした一種の戸籍制度の役割を果たし、農民ひとりひとりの身分と移動を掌握するための重要な制度であった。
一方、石高制は支配階級(武士)内部の秩序も規定した。将軍を頂点として大名・旗本―陪臣の間に重層的に構成された主従関係は、石高を基準とした重層的な知行(ちぎょう)給与(土地所有)とそれに対する軍役を基本とした奉公の関係によって成立していたのである。兵農分離制と石高制を幕藩体制の根幹と評価するゆえんである。
(7)近代国家への移行
このように幕藩体制は本百姓体制を基本としたから、小商品生産の展開によって本百姓体制が動揺するにしたがい、崩壊の道を歩み始める。それが決定的になったのは1854年(安政1)の開国である。そして1867年(慶応3)の大政奉還と明治初年の諸改革を通じて近代国家ができあがるが、その人民支配は四民平等政策によって近世以来の封建的な身分制を解消したものの、華族・士族・平民という新たな身分制度をつくりだした点に特徴がある。とくに被差別身分に位置づけられていた穢多(えた)・非人を新平民として残存させたことは、初期の明治国家が人民支配の装置として、依然、封建的な身分制を重視していたことを示している。
このような封建的な性格を残しながらも、1872年(明治5)の壬申戸籍(じんしんこせき)を最初とする近代的な戸籍制度と、1889年にいちおうの完成をみる市町村制によって、明治国家の人民支配は遂行されていくのである。
[木村茂光]
日本社会の社会構造的特質
(1)古代
日本の古代社会の特質をみる場合、私たちが問題としなければならないのは「氏(うじ)」である。古くは、「氏」を出自(しゅつじ)集団としての氏族=クランとする見方もあったが、津田左右吉(そうきち)によって「氏」は血縁集団ではなく政治組織で、血縁集団の家の集合体であるとされて以来、学界の主流は、血縁集団の「家」が古代以来、社会の基本単位となり、その原理が日本社会を貫く普遍的原理であるとした。
しかし、最近の研究動向はこれに大きく修正を迫りつつある。すなわち、近年の人類学の成果に依拠して、日本の「氏」を非単系(双系)制、非外婚制で階層性を特質とする一集団類型として把握しようとする説が登場してきたのである。この説では、「氏」は一系的系譜をもつ族長を通して大王に奉仕する集団としての性格をもつと同時に、成員からすると複数の祖から発して自己に収斂(しゅうれん)する系譜があり、「氏」は出自集団としてはあいまいな集団であった。
一方、家族形態についてみると、これまでの説が単系的な家父長を頂点とする血縁、非血縁を含む集団としてきたのに対して、新しい説では、家族は双系(双方)的性格が強く、夫婦の居住も夫方・妻方が相なかばし、財産も夫婦別産、父子別産という個人所有の形態をとっているきわめて流動的なものであるとする。したがって、このような家族形態の下では、単系に父―子関係を基本とする「イエの継承」観念は未発達であり、継承観念は「氏」を基本とする始祖のマナ(呪術(じゅじゅつ)的霊威・魂)の継承という形で発現するしかなかったとする。
このような社会のなかに律令制が導入されると、律令国家は、首長位が傍系親を含む範囲で移動し、構成員も変動する「氏」の組織では国家の支配単位として流動的なため、嫡子制の導入によって「イヘ」(古代の家族)を支配体制の基礎としたり、三位(さんみ)以上の貴族には公的な制度としての「家」を設けたりした。しかし、いずれにしても「イヘ」は継承単位として存在しておらず、公的「家」も現実には小「氏」として存在することになった。
しかし、このような体制の変化が「氏」を出自集団として純化させたことも事実で、8世紀末~9世紀前半には「氏」は未熟な家を結集する集団へ展開してゆくことになる。
(2)古代から中世へ
家族というものは普遍的に存在するが、時代によってその形態やそれを律する原理が異なる。8世紀以前の社会では、先述のごとく「イヘ」は双方的親族関係に規定された不安定な集団であり、律令国家が戸籍を通じて個人を把握しなければならなかったのは、支配の強固さによるというよりも、このような未熟で、不安な「家」の特質によるものという見方もできる。
しかし、9世紀以降は兄弟共同体的原理を基軸とした家族共同体が自立し始め、律令国家はこのような「家」を前提に税、負債の追求を行うようになる。同時に、律令国家はたてまえ上では戸籍制度を維持はしていたが、負担能力をもつ富豪層に注目し、これに税を請け負わせるという形で収取制度の末端に組み入れ始める。10世紀に入ると、律令国家は富豪層にみる請負的支配システムを国家の地方支配のなかに導入し、負名(ふみょう)、郡司、国司などの官物(かんもつ)請負制を推進し、律令国家的人別支配を放棄してゆく。
一方、中央では令外官(りょうげのかん)の出現と発展に対応し、令制の官職および官庁はその機能が形骸(けいがい)化または変質し、10~11世紀には全官庁機構の再編が進む。加えて、令制、令外の別なく、特定の氏族が特定官司を世襲的に請け負う傾向が生まれる。
やがてこの両者の請負方式は、いわゆる寄進地系荘園(しょうえん)が成立する11世紀後半には、中世国家の収取制度の骨組みとなる「職(しき)」の体系として結実する。すなわち、「職」は特定の「家」が中央へ税を集めるシステムのなかの一職掌を請け負い、その見返りに得分(とくぶん)(収益)を得るという官職的側面と、それをその「家」が「家産」として世襲化するという面の二面を有しているが、10世紀まで継承という面では未熟であった「家」が、11世紀以降は婚姻形態の安定化と開発の進展などによって永続的経営体として立ち現れ、これが「職」と結び付くことによって、家産をつくりだし、それを直系の親―子へ継承する傾向が生まれる。ここに日本で初めて親子の連鎖による承家の観念が成立することになる。
しかし、この中世的「家」は「職」と表裏一体の関係にあって継承も可能となっているという性格はもっているが、「家」が1世代ごとに解消するというその世代性を克服するには至っていない。継承の面では家嫡はいちおう長子が優先されるが、当初はその家の家業(職)を担う能力(器量)の有無が問題で、それは家父長(基本的に親)が作成する譲状(ゆずりじょう)によって決定され、上級領主がそれを追認した。このような社会では器量をもつ家父長の決定権、すなわち親権が社会の中心的規範となっていた。
ところで、9世紀までに単系的出自集団に純化を遂げた「氏」は、10世紀以降はその継承性をもつ、「家」の出現によって大きく変化させられる。古代的な「氏名(ウヂナ)」は10世紀以降、中央に寡占化が進行し、いわゆる源、平、藤(とう)、橘(きつ)、中原、大江などに絞られ、氏集団として事実上の意味は失われる。それに対して「一家」「一門」「一流」とよばれる「イエ」(中世的家族)的集団が登場する。この集団は経営体としての「家」を内包、分出するが、特定の範囲では、その始祖の居住地、あるいは開発地の地名をその集団の名称とし(これはのち名字(みょうじ)となる)、共同の祖先祭祀(さいし)を行っている。すなわち、中世前期の社会は、「氏名」と「名字」がそれぞれ実質的意味をもって並存している時代といえる。たとえば、北条泰時(やすとき)は公式の場、公式の文書では平朝臣(たいらのあそん)泰時と称している。名字はどの集団に帰属するかを示し、「氏名」(姓)は、古代以来の天皇(朝廷)に奉仕する者としての称と認識されているのである。農民層においても、自らを平民百姓(公民)と主張する場合などは「氏名」を使用している。
(3)中世から近世へ
南北朝の内乱を境に、荘園公領制は激しく動揺し、「職」によって支えられていた「家」的秩序も崩壊の危機に瀕(ひん)する。
地方では、地域連合体としての一揆(いっき)体制が新たな秩序として現れ、在地では惣郷(そうごう)―惣村という形で村落が自立化して共同体規制を強化し、「家」の秩序はそのなかに組み込まれ始める。戦国期に入ると、大名はこれらの秩序を領国支配のなかに包摂し、それを主従制的原理で律してゆく。個々の「家」の家父長も主従制的原理をその家内部の支配原理として優先させるようになり、中世前期・中期にみられた親権支配の原理が最優先される社会から、主従制を絶対視する社会となる。親権を象徴する譲状は、この時期から、しだいにその機能を喪失し始め、家父長の地位も以前は家父長が死亡するまでもち続けたが、隠居制が採用されると、親権と家長権は分離され、家長権が「家」を律することになる。
したがって戦国期の乱世のなかではこの主従制的秩序は力の論理となり、器量ある者が主君として君臨し、新しい主従の論理を構築した。また、在地村落においても村落間の相論(そうろん)に「自力救済」の論理が働き、絶え間ない争いが続いた。16世紀後半のこのような状況のなかで、大名にとっては支配の安定のための広い統合的秩序の形成、すなわち「天下統一」が政治的課題となってくる。
ここに登場してくるのが織田信長、豊臣(とよとみ)秀吉である。信長は、中央権門、「国」の支配者大名を統合し、国役(くにやく)賦課によって百姓の旧来の諸関係を断ち、天下的公儀の道を希求した。秀吉は征服地域に「惣無事(そうぶじ)」令(平和令)を出し、武力的解決法を禁止するとともに、太閤(たいこう)検地を実施し、中世的秩序の温床となっていた重層的土地支配のあり方を完全に否定した。さらに刀狩(かたながり)令、身分統制令によって、新しい身分秩序(士・農・工・商―賤民(せんみん))をつくりだし、自身はその支配の正統性を天皇に求め、豊臣姓を与えられるとともに、太政(だいじょう)大臣、関白の地位に座った。
江戸幕府は、朝廷を遠ざけるが、基本的に秀吉の路線を継承し、大名や武士の統制として相変わらず官職秩序を巧みに利用し、その限りで天皇制を存続せしめた。また一方では、すでに戦国大名や村落共同体が掌握しつつあった家の象徴である名字の与奪権を完全に握り、農民以下の名字を剥奪(はくだつ)した。また石高制によってその「家」の収益を表示し、また役の体系によって家秩序をつくりあげ、村落は村高を分割する高持(たかもち)百姓と役屋(やくや)の体制により、その秩序を完成させた。近世の家(ことに武家、百姓)は家産が支配秩序のなかに組み込まれており、その継承は家父長の意志を超え、個人より公の秩序に組み込まれた「家」の論理がより優越するようになった。なお最近の研究では、小農民層の永続的、継承的家が成立するのは地域によって多少異なるが、寛文(かんぶん)・延宝(えんぽう)期(1661~1681)ごろが一つの画期であったといわれている。
(4)近世から近代へ
近世の「家」が基本となり、近代的「家」秩序が成立したと一般にいわれる。しかし、近代国家の「家」が近世の「家」と決定的に異なるのは、欽定(きんてい)民法によって戸主を家長と定め、「家」を天皇制と直結させた点である。近世国家の「家」的秩序の頂点にあったのは将軍であったが、近代の天皇はこの将軍権力を奪い、天皇の下に象徴的にあった「氏」の秩序を復古し、「家」を支配単位とした。そのため、将軍権力の下、家の名として存在していた名字と、天皇が象徴的に掌握していた「姓」「氏」が、明治以降、同体となる。したがって、「家」なるものを中心に日本の歴史を振り返るとき、近代の「家」が天皇制イデオロギーのもとで国家の細胞として位置づけられ、国は皇室を宗家とする一大家、すなわち「家の家」になったのだという点を、日本における近代的な家の特殊な存在形態として再認識する必要がある。
これまでも日本社会の特質をイエ社会ととらえ、それが日本の伝統的社会制度であるとみる見方があった。近年、日本の経済発展のなかで、日本社会の特質をイエ社会とし、その間柄主義が日本の近代化、戦後の高度成長を推進した主要な要因であり、将来もこのイエ社会の特質は失われるべきでないとする説が近代家論として出されている。しかし、これまでみてきたように、「家」は支配・体制の支配単位として機能したというマイナスの歴史があり、この面を無視して、イエ社会を肯定することは危険である。また、日本における「家」の歴史は長いが、これも歴史的に形成された産物である。「家」も時代によって変化を遂げており、歴史的には「家」は解体する方向へ進んでいるようにみえる。ただ、このことの是非はともかくとして、われわれが「家」や家族といった問題を改めて問い直さねばならない時期にきていることは間違いない。
[飯沼賢司]
日本人の国土意識と国際意識
(1)古代
4世紀以降、倭(わ)(日本)は朝鮮半島の百済(くだら)・新羅(しらぎ)・高句麗(こうくり)に対し優位にたとうとする。471年(雄略15)に比定される埼玉古墳群(埼玉県)の稲荷山古墳出土鉄剣銘の「治天下大王」は、そうした「大国」意識を表している。倭は600年(推古8)に遣隋使、続いて630年(舒明2)に遣唐使を派遣し中国との対等外交を志向するが、そこには、隋、唐の国際秩序=冊封(さくほう)体制下に入った朝鮮3国を倭の下位に位置づける意図があった。660年(斉明6)に新羅が唐と連合して百済を滅ぼすと、倭は662年(天智1)百済の人質余豊璋(よほうしょう)を百済王に冊封し、倭中心の新たな国際秩序作りを企てる。しかし翌年、白村江(はくそんこう)の戦いで百済は滅亡した。新羅はさらに668年に高句麗を滅ぼすが、その後対唐戦争に突入し、かえって倭に接近してくる。倭はその新羅を外藩として自らの国際秩序に編成しようとする。こうした動きを背景に7世紀後半、倭は国号を日本、大王の称号を天皇と改めた。一方日本列島内では、645年(大化1)の大化改新後、朝廷は王化にまつろわぬ東北のエミシ(蝦夷)経略を進め、改新後まもないころ道奥(みちのく)(陸奥(むつ))国を置き、宮城県南部まで支配下に治めた。また南九州では、天武(てんむ)・持統(じとう)朝ごろ(672~697年)、隼人(はやと)の一部を畿内およびその周辺に移住させるとともに朝貢させた。
701年(大宝1)大宝(たいほう)律令が制定され、律令国家が成立した。律令国家は天皇が国土と人民を公地公民として支配する一方、対外的には隣国・蕃(藩)国(ばんこく)・夷狄(いてき)という三通りの対外関係を設定し、天皇の権威と徳治を宣揚した。隣国は日本からみて対等の国、中国の唐がそれにあたる。蕃国は日本より下位にみた国で朝鮮半島の新羅と渤海(ぼっかい)、夷狄は日本列島の北と南に居住する、いまだ王化に服さない蝦夷と隼人である。朝廷は東北に712年(和同5)出羽(でわ)国を設け、724年(神亀1)多賀(たが)城を築いて陸奥の国府と鎮守府を置いた。また、南九州に701年唱更(はやと)(薩摩(さつま))・多禰(たね)両国を、713年大隅(おおすみ)国を置き、蝦夷・隼人地域の国郡制的な編成を進めたが、蝦夷と隼人の造籍・編戸はままならず、帰服した蝦夷を俘囚(ふしゅう)・夷俘(いふ)とよび、薩摩国に隼人11郡を存在させるなど、その支配を貫徹できなかった。それゆえ逆に、蝦夷と隼人を辺境の化外(けがい)の民と位置づけたのである。薩摩・大隅隼人の朝貢は、716年(霊亀2)に6年1交替制に強化された。
8世紀始め、日本は唐・新羅・渤海(ぼっかい)と外交関係があった。日本は新羅を朝貢国とみなしたが、新羅は唐と国交を修復すると、735年(天平7)日本に対等外交を要求してきた。それ以降、日羅関係は険悪になっていった。753年(天平勝宝5)には遣唐使が唐の朝廷で新羅使と席次を争い、日本が新羅より上位にあることを唐に認知させる事件を起こした。日羅関係は779年(宝亀10)の新羅使を最後に断絶する。そこで日本は727年に隣交を求めてきた渤海に対し、高句麗を継承することを理由に朝貢関係を迫った。
800年(延暦19)朝廷は薩摩・大隅両国に班田制を実施した。律令的な支配が及ぶことになったので翌年、薩摩・大隅隼人の朝貢は停止された。東北では774年以来北上川中流域=胆沢(いさわ)地方の蝦夷との戦いが続いていたが、811年(弘仁2)に終結し、陸奥国が岩手県盛岡市付近まで広がった。ここに日本列島内の夷狄の世界は解体した。蕃国は779年に日羅関係が断絶したので渤海だけになった。840年(承和7)新羅の張宝高が大宰府に遣使してきたが、日本は臣下に外交の権なしとこれを拒絶した。これ以降、日本は対外的に消極的姿勢を強め、894年(寛平6)遣唐使を停止し、922年(延喜22)には渤海との国交を断絶する。対外関係が断絶した10世紀、朝廷は、927年(延長5)の『延喜式(えんぎしき)』によると、日本の四至(しいし)を東は陸奥、西は遠値嘉(おぢか)(五島)、南は土佐、北は佐渡までととらえている。
(2)中世
12世紀には、東は外(そと)が浜(はま)(津軽(つがる)半島北端)から西は鬼界島(きかいしま)(薩摩の硫黄(いおう)島)までが国家の領域と考えられている。そして、その外側に夷島(えぞがしま)(北海道)、琉球(りゅうきゅう)または高麗(こうらい)があった。この時期、日本は奥羽北部から夷島にかけての住人を、改めてエゾ(蝦夷)とよび異民族視した。鎌倉幕府はこの「東夷」の支配権をもち、津軽・下北半島を勢力圏とする安東(安藤)氏を蝦夷管領(かんれい)に任命して蝦夷鎮撫(ちんぶ)にあたらせた。
中世の正統的な国家観念である神国思想は、「万世一系」の天皇の存在を唯一の根拠に、日本を他国より優れている、逆に他国を日本の従属対象としてみるという独善的な国際意識をもっていた。神国思想は、13世紀末の蒙古襲来後高まりをみせる。しかし、神国思想の対外的な優越感は、逆に言うと、対外的な恐怖心の裏返しにすぎない。たとえば、室町幕府の対明(みん)外交が断絶した1419年(応永26)に朝鮮が倭寇(わこう)の本拠地とみなした対馬(つしま)を攻撃するが、この応永(おうえい)の外寇を日本人は事実の確認なしに蒙古の来襲と受け取って恐怖した。この後も、日本人は外からの脅威をムクリ・コクリ(蒙古・高麗)とよんで恐れるようになる。
1401年、足利義満(あしかがよしみつ)は明に遣使して国交を求めた。翌年明の恵帝(けいてい)は義満を「日本国王源道義(みなもとのどうぎ)」と称し、大統暦を授ける。1404年には永楽(えいらく)帝が義満を日本国王に冊封する。日本は明の国際秩序=冊封体制のなかに入り、武家外交が成立した。しかし義満が始めた対明外交は、瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)の『善隣国宝記』(1470年)によると、日本国王と称し明年号を用いる朝貢形式に批判が強かった。そのため4代将軍足利義持(よしもち)は1411年、1419年に来日した明使の入京を禁じ、明との国交を断絶する。しかし、6代将軍足利義教(よしのり)は1432年(永享4)に遣明船を派遣し、1434年日明国交が再開する。このとき「黒衣の宰相」といわれた満済(まんさい)が、日本は神国だから隣国の好(よしみ)で明に通交すべきであると義教に進言している。
日本と朝鮮は明の被冊封国として対等な関係にあるが、足利将軍は朝鮮国王あての国書に「日本国源某」と称し、日本年号を用いた。国王と名のらなかったのである。これは朝鮮を日本より一段下にみる伝統的な朝鮮観の反映であるといわれる。琉球もまた明の朝貢国であるが、室町幕府と琉球の間には1414~1527年(大永7)に足利将軍が琉球国世主(よのぬし)にあてた文書が4通残っている。それは日本年号と印章(徳有隣)を用い外交文書の体裁をとっているが、国内の臣下にあてる御内書(ごないしょ)の様式でもあった。1530年(享禄3)ごろと推定される「鶴翁字銘并序(かくおうあざめいならびにじょ)」(『幻雲文集』)によると、日本は琉球を「附庸(ふよう)」国とみなしている。
(3)近世
1592年(文禄1)豊臣秀吉(とよとみひでよし)は明出兵(朝鮮侵略)を起こし、同年5月、日本・朝鮮・明3か国の支配構想を明らかにした。それ以前秀吉は、1582年(天正10)に亀井茲矩(かめいこれのり)を「琉球守(かみ)」に任じ、ついで1592年明国浙江(せっこう)省台州の「台州守」に転任させているが、これによって判断すると、秀吉は東アジア諸国を征服し国郡制的に支配することを構想していたと考えられる。1598年(慶長3)朝鮮侵略は失敗に終わり、翌年以降、徳川家康が明との講和、いいかえると日明国交を追求する。この対明政策の一環として、家康は1604年蝦夷地のアイヌとの交易を松前氏に管理させ、1607年宗氏を通じて朝鮮と国交を回復し、1609年島津氏に命じて琉球を征服した。中世では日本の外側にあった琉球と蝦夷は、幕藩体制下の「附庸国」「蝦夷地」として位置づけられることになった。
日明国交は、結局、実現しなかった。そのため幕府は朝鮮・琉球との間に日本を中心とする国際関係の形成を進め、1630年代(寛永7~16)に徳川将軍を大君(たいくん)と称する大君外交が成立した。1635年に幕府は日本船の海外渡航を禁止する。一方海外からは1634年に琉球使節が、続いて1636年に朝鮮通信使の来日が始まる。こうして大君の御威光を東アジアに及ぼす外交体制が成立した。島原の乱後、1639年に日本はポルトガルと断交する。1644年(正保1)には中国で明から清への王朝交替が起こり、日本を取り巻く国際環境が緊張した。日本はこうした新たな事態に対処するため、「奥国」(東南アジア)と「北高麗」(北東アジア)とよぶ地域を設定し、この二つの地域の動きを警戒した。琉球征服後、日本は琉球を日中両属の地位に置いたが、1719年(享保4)に日琉関係を隠蔽(いんぺい)する。それを受けて琉球は1725年、日本の属島度佳喇(とから)(七島、南西諸島北端)と通交しているとの論理を創出する。
1792年(寛政4)ロシア使節ラクスマンが蝦夷地・根室に、続いて1804年(文化1)レザノフが長崎に来航し貿易を要求する。これに対し幕府は、通信国・通商国以外の国とは新たな対外関係を拒否する方針を固めた。ここにいわゆる「鎖国」祖法観が成立した。ロシアとの緊張を背景に、幕府は1799年東蝦夷地を、続いて1807年西蝦夷地を直轄化した(1821年まで)。1801年(享和1)に志筑忠雄(しづきただお)はケンペル著『日本誌』の1章を翻訳し『鎖国論』と名づけた。これが「鎖国」の語の成立である。
アヘン戦争(1840~1842)後、1844年(弘化1)にオランダ国王ウィレム2世Willem Ⅱ(1792―1849)が12代将軍徳川家慶(いえよし)に開国を勧告してきた。それに対し翌年、幕府は外交関係の通信国は朝鮮・琉球、貿易関係の通商国は中国・オランダと言明し、オランダの勧告を拒否する。『通航一覧』(1853)はその序に、通信国・通商国は寛永年間(1624~1643)に成立したと述べる。『徳川実紀(とくがわじっき)』(1849)は、1635年に幕府が行った日本船の海外渡航の禁止を「海禁」と位置づける。このように幕末、ヨーロッパより開国を求められた日本は、1630年代に海禁を行い通信国・通商国を設定したとする日本型華夷(かい)意識の論理を創造した。
[紙屋敦之]
政治・国際関係・防衛
総論
1945年(昭和20)8月、日本国は第二次世界大戦で決定的な敗北を喫し、戦勝連合諸国が注視するなかで、新しい「国づくり」を開始することになった。「国づくり」のため民主主義と平和主義を標榜(ひょうぼう)する新憲法がつくられたが(1946年公布、1947年施行)、戦後の最大の課題は政治諸改革よりもむしろ経済復興に向けられた。壊滅した経済、産業を回復させ展開のめどをつけることを至上命令とする「国のかたち」は、その後一貫して日本国を刻印づけた。経済優先主義あるいは経済至上主義はこの国の「国是」となり、国民の意識のなかに深く織り込まれたのであった。
この国是は、いろいろな紆余曲折(うよきょくせつ)があったものの、みごとに成功した。経済、産業は立ち直り自立し、やがて高度成長を志向し成長率の限りなき増長を目ざすようになった。とりわけ、1970年代において二度にわたり諸国の経済に深刻な打撃を与えた石油ショックから日本はいち早く立ち直ることができ、1970年代の終わりには、気がついてみたら世界に冠たる「経済大国」になりおおせていた。「経済大国」になるについては、国内的には憲法が目ざした市民的な諸自由、諸権利の確保と民主主義的な政治・社会秩序の形成があずかって大きな力になったこと、および国際的には、これまた憲法が掲げた平和主義、国際協調主義のもとで、この国が軍事的緊張状態にさらされることがほとんどまったくなかったこと、など国内外の環境のよさを軽視してはならない。すなわち個人主義的なリベラリズム、民主主義的政治原理、そして平和主義の確立という条件が「経済大国」への道を背面から支えてきたのであった。しかしながら、国是としての経済至上主義が成り立つ限りでは、権威主義、秩序優先主義、集団主義その他、明治以来この国の伝統になってきている政治文化、社会通念を、そのまま温存させるのを得策と考える傾向が強かった。こうして、経済的な効果を達成するためには、市民的な自由や権利の伸張を抑え、民主主義的な原則には目をつぶって官僚的な支配を是認するのを当然のこととして許してきた。経済の「近代化」による超高度成長はかならずしもこの国の政治、社会の実体や人々の公共意識の「近代化」をもたらすことにはならなかった。
1980年代に入ると経済にかげりを見せ始めたアメリカとの間で貿易摩擦などの不調和に苦慮させられることもあって、「経済大国」としての日本国は、外に向かって「政治大国」にならなければならない、と社会支配層は主張するようになる。内に凝縮して力をつけ外国への発言力を高めようという立場から、伝統的に「日本的なるもの」を掘り起こしその価値を再認識すべしとする日本および日本人(アイデンティティ)論が花盛りとなる。こういう風潮のなかで、現在の日本の歴史的原点にあたる「戦後民主主義」の虚妄性を突き、これを、日本国を見舞った一時的なあだ花と見なして「総決算」してしまおうという主張が出てきた。こう主張する人々にとっては、日本国憲法は、「戦後民主主義」の諸悪の根源にほかならないから、すべからく速やかに憲法改正が行われなければならないのであった。
このような「経済大国化」論のイデオローグたちは、日本が諸外国、とりわけアメリカと伍(ご)してさえ優位に立てたのは、「単一民族国家」であることに由来するとか、日本社会に独特な人間関係を反映した「日本的経営」の特質に原因があるとか、などなど、特別に「日本的なるもの」の重要性を強調した。1980年代後半日本経済が高みに登りバブルの渦中で急速回転するころには、「いまやパックス・アメリカーナは崩壊した。やがてパックス・ヤパーナの時代がやってくる」とか、少なくとも「いまやアメリカを含め、いかなる国も日本のモデルではなくなった」といった自信に満ちた積極論が飛び交った。こうした意気軒昂(けんこう)な日本経済論のあおりを受けて、諸外国の間には「日本異質論」を踏まえた新しい「黄禍論」がささやかれるようになった。
けれども、1989年ソ連邦を頂点に置く社会主義体制が崩壊し冷戦構造が消失して国際関係が大変革を蒙(こうむ)るなか、日本は一方で1990年代初期の湾岸危機、湾岸戦争に対応するとともに、他方バブル経済の崩壊という予期しなかった大規模の経済危機を切り抜けなければならないことになった。
日本を取り巻くこうした大状況の変化は政治、経済、社会の深刻な再編成を要求するものであったが、そのうち政治改革についていえば、すでに1987年に成立した竹下(たけした)内閣が国際化の時代に対応すべく政党再編、保守二党体制への移行を基本目標に、選挙制度改革に着手しようとした。衆院における小選挙区比例代表制の導入、政治資金の規制、政党への公的資金助成の三点セットの政治改革課題を背景に1990年代前半には政党の分裂再編、短期内閣のたび重なる交代と、基軸を欠いた目先だけの慌ただしい政界の動きがあった。こうしたなかで、1993年(平成5)7月の総選挙で自民党が過半数をとれず野党に転落し、非自民、非共産の8党派の合意による連立内閣が生まれ、さらに1994年6月には自民、社会、新党さきがけの3党が「共同政権」をつくるといった、新しい展開がみられた。自民党はその後の総選挙で勢力を回復したが、依然連合内閣の形を崩せないままになっている。
1990年代に入って、戦後政治の基本的特徴をなしていた55年体制が崩壊し、自民党単独政権下において当然視されていた政、官、財、産の癒着関係、ゆがみ、ひずみなどがいやおうなく明るみに出され、その是正が求められるようになった。短期連立型内閣が次々と交代するなかで、市民の発言力が増し市民的利益を反映した諸立法が日の目をみるといった動きがあったのは、それなりに評価されるべきであろう。しかし、政局の安定は当分の間望むべくもない。また日本経済の低迷はきわめて深刻なものらしいということもだんだんわかってきた。そうしたなかで、最近、識者の一部に「反米思想」が流行しつつあるなど、「右寄り」孤立主義の風潮が出てきていることとか、藤岡信勝(ふじおかのぶかつ)(1943― )らの唱える「自由主義史観」論に象徴されるような激しいナショナリズムに共鳴する流れが勢いづいてきていることは軽視できない。
現在の状況から推して、政局の安定は当分の間望むべくもない。しかしながら、深刻な経済の低迷から抜け出すという当面の緊急課題に対処するためだけからも、日本にはなさねばならない改革が山積している。
1997年(平成9)1月、通常国会での所信表明演説で橋本龍太郎(はしもとりゅうたろう)首相が掲げた六大改革課題、すなわち、金融システム、財政構造、行政、社会保障構造、経済構造および教育の6分野にまたがる改革課題は、そうした事情の必然的な反映である。これらの課題を十全に果たすためには明確な問題意識と断固たる問題処理能力がなければなるまい。
いまこの国は限りなく不透明な岐路に立たされている。
[奥平康弘]
法体制
総説
日本の国家体制は、基本的には現在の憲法典(1946年制定、翌年施行の日本国憲法)に基づいてできあがっている。だが、それに先だつ歴史的な背景をも視野に置く必要がある。この場合、1867年(慶応3)からの明治維新までさかのぼれば、さしあたり十分である。幕藩体制、さらにはそれ以前の政治制度は思想上はともかく、制度のうえでは、現在ほとんど痕跡(こんせき)をとどめていないからである。明治維新以降、近代国家形成が模索された。当初のうちこそ、古代律令(りつりょう)制国家の機構の再現などが試みられることもあったが、やがて西欧諸国の憲法体制をモデルとして踏襲することが既定の方針となった。1889年(明治22)に成立した大日本帝国憲法(明治憲法、翌年施行)は、おおむねプロイセンおよび南ドイツ諸邦の憲法に倣っている。明治憲法体制下、政党が発達し議会が政治の中心となる傾向が強くなるとともに、イギリス型の憲法(議院内閣制)がモデルとして考えられるようになった。昭和前期の非立憲的な戦時体制期を経て、敗戦とともに始まった再生復興期のなかで誕生した日本国憲法は、色濃くアメリカ合衆国憲法に影響を受けているのが特徴である。それぞれの時期に、憲法運用のレベルで日本の独自な性格が出てくるのは当然であるが、憲法体制の骨組み自体はむしろ欧米先進国に準拠し、それらと共通のものを採択しようと努めてきたといえる。
[奥平康弘]
明治憲法制定以前
江戸幕府の大政奉還、王政復古などに端を発して、明治維新という一大政治・社会変革が展開することになる。明治政権の担い手たちは薩長(さっちょう)その他の有力藩閥出身者であり、彼らなりの政治的なもくろみで国づくりに着手した。内に向かっては文明開化、殖産興業、富国強兵を通じて強い国家を志向する。自由民権運動に象徴されるような、下から、あるいは政府外から国家形成の主導権を脅かす動きに対しては、厳しい弾圧を加えた。こうして著しく警察国家的な相貌(そうぼう)を呈した。他方しかし、日本が世界の舞台に登場するためには、かつて幕府が諸外国と取り結んだ不平等条約を撤廃することが不可欠であり、かつ、諸外国にこれを同意させるためには、わが法体制を欧米の水準に近い形で近代化する必要があった。政府は、1882年伊藤博文(ひろぶみ)らに憲法取調べのため渡欧を命じたが、彼らの関心は、強力な君主権を背景に置いて執行府中心の統治が行われる体制を探すことにあった。伊藤らは、市民革命を不発に終わらせたまま「上から」の近代化を推し進めつつあったプロイセン、南ドイツなどのドイツ型憲法を範型ととらえた。こうした憲法構想に基づいて草案づくりをするとともに、1884、1885年ごろから、華族令、内閣官制、公文職(くもんしき)、裁判所官制など、新しい憲法の受け皿づくりに着手した。
[奥平康弘]
明治憲法
1889年に公布された明治憲法は天皇の名により臣民に下された欽定(きんてい)憲法である。これと同時に、皇位継承、即位、皇族などに関する皇室典範も公布された。天皇、皇族は国家の中枢に位する存在だから、皇室典範も憲法の一つに属した。明治憲法は相矛盾する二つの魂の妥協の産物といえる。一つは、天皇を政治の中心に据える考え方で、これは神々につながる他国に類(たぐい)ない天皇が統治権を総攬(そうらん)するという形で憲法のなかに結晶化した。もう一つは、西欧の立憲主義に近い外見をとるべきだという考えで、こちらのほうは権力分立の原則および法治主義原理の採用という線で憲法に体現した。前者は神権的な側面で、後者は民権的な側面といえる。明治憲法施行後しばらくは、両方の魂が相拮抗(きっこう)して国づくりが展開した。藩閥的な有司専制を貫こうとする政治権力は、衆議院(民選議院)の支配が及ばないよう超然内閣の体制を維持しようとした。しかし、政党の伸張、衆議院の政治的地位の上昇はいかんともしがたく、衆議院が内閣の人事、政策に影響を与えるようになり、やがて衆議院の多数派が内閣を構成するというイギリス型議院内閣制(政党内閣)が憲政の常道といわれるようになる。いわゆる大正デモクラシーがこれにあたる。この時代には、憲法の神権的な側面を極限まで抑え込み、逆に民権的な側面を強調し民権的な憲法解釈を最大限に押し出した。こうして政治機構での近代化がみられたけれども、政治の中身、とりわけ表現の自由、集会・結社の自由など市民的な自由の領域では、目にみえた改革が行われなかった。1925年(大正14)衆議院議員選挙法の改正により男子普通選挙制が成立したが、これとまったく同時に、市民的な自由をまっこうから否定することになる治安維持法が制定されたのは、示唆的である。
昭和前期、日本が中国に軍事介入をし始めるとともに、反動的右翼思想に根ざした全体主義的政治体制を指向するようになる。そうなると、いままで出番を失っていた憲法の神権的側面が絶大な意味をもつのは当然である。天皇は統治権を総攬するばかりではなく(4条)、陸海軍を統帥する(11条)といった諸規定が神がかり的な思想に粉飾されて、権力把持者(軍部その他)に無制約の権力行使を許す根拠となる。曲がりなりにも憲法が採用した、権力分立の原則や法治主義原理は無意味になる。こうして戦時体制の深化は明治憲法の崩壊を内包していた。1945年(昭和20)8月、日本はポツダム宣言を受諾することにより太平洋戦争の終結をみたが、同時に国家体制=憲法の変革を課題とすることになる。降伏条件の文書であるポツダム宣言には、「民主主義的傾向ノ復活強化」および「基本的人権ノ尊重(確立)」がうたわれており、それは憲法改正を示唆していたからである。
[奥平康弘]
日本国憲法の制定
1946年11月、日本国憲法が公布された(翌年5月3日施行)。この制定過程で占領軍が果たした役割は大きい。ここから「押し付けられた憲法」論議が出てくるが、当時の国民のこれに対する歓迎ぶりからみて単なる「押し付け」とはいいにくい。また、この議論と、憲法をもう一度改正すべきかどうかの争点とは区別したほうがいい。日本国憲法は、明治憲法の改正という形式をとったが、実質的にはまったく異なった新憲法である。それは、旧憲法の基軸が天皇主権にあったのに、新憲法はこれと相いれない国民主権をとったことに端的に表れている。日本国憲法は、象徴としての天皇を存続させるなどの点で旧憲法的な魂との妥協の産物といえる面があるが、民主主義的な原則――主権在民、基本的人権の尊重、議会中心主義を踏まえた権力の分立、地方自治の本旨など――に忠実な、その意味で首尾一貫した政治理念を踏まえている。
[奥平康弘]
政治機構
日本国憲法によれば主権は国民にあるが、その権力は代表者により行使されるたてまえ(代表民主制)をとる。国民代表機関たる国会が政治機構上「最高機関」(41条)の地位を占める。国会は、衆議院と参議院の両院からなるが、どちらも全国民を代表する選挙された議員で組織しなければならない(43条)。国会は法律の制定、予算の議決、条約の承認など、政治運用の根拠になる国家行為にあずかるが、その決定には普通、両議院の可決が必要である。けれども、法律案につき両院の議決が異なる場合には、衆議院が3分の2の多数で再可決することによって法律は成立する。また予算については、参議院が異なった議決をしても、最後には衆議院の議決が貫徹することになる(予算の自然成立)。条約の承認の場合も同様。こうした仕組みを衆議院の優越という。国会は国民代表機関として政治の全般に関し情報を取得する必要がある。各院に国政調査権が与えられている(62条)のは、そのゆえである。国会の承認した法律や予算に基づき、政治、行政を実際に行うのは、内閣である。内閣は、国会議員の互選に基づき指名された者が就任する内閣総理大臣、および内閣総理大臣の任命する国務大臣から構成される合議体である。憲法では、国務大臣のうち過半数は国会議員のなかから選ぶよう規定しているが(68条1項)、実際の運用では、国会議員以外の者が大臣に任命されるのは、ごくまれであり、しかも、圧倒的多くは衆議院議員の間から選ばれるのが通例である。すなわち、国会と内閣とは、その構成員において強いつながりがある。自由民主党は1955年の結党以来長期にわたって国会で多数議席を占め、内閣を支配してきた。1993年(平成5)7月の総選挙で、永久に続くかと見まがうばかりの自民党政権がようやくにして終幕をみた。これとともに、1955年に成立し日本の政治、経済、社会をあまねく支配してきた55年体制も崩壊した。さらに1998年7月の参院通常選挙で自民党は予想外に惨敗し、首相交代を含む内閣の大規模変革を行わざるをえなかった。しかしながら、55年体制のもとで培われ、それをバックに「経済大国化」を押し上げてきた自民党の政治支配に特有の政、官、産、財の癒着癒合構造はそれほど容易に崩れ去るものではなく、しばらくは政治的に不透明な時期から抜け出せそうもない。
内閣は連帯して国会に対し責任を負う。国会との間に信頼関係があることが前提となる。衆議院から不信任(あるいは信任の不承認)を受けた場合には、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して、信を国民に問い直すべく、総選挙を行う。憲法には明文の規定がないが、信頼関係が壊れたわけでもない場合にも、内閣は衆議院を解散させることができると一般に解されており、実際歴史上すでに何度かこの種の衆議院解散が行われている。
司法権を担うのは、最高裁判所および法律で定められた下級裁判所である。裁判所法によれば、下級裁判所とは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所をさす。これら以外の国家機関の行う審判のようなものが禁じられているわけではないが、それは最終的には裁判所の行う裁判につながってゆかねばならない。司法権は厳正中立であることを要する。司法権の独立の確保と、裁判官の身分保障が重要である。最高裁判所の裁判官は、内閣が任命し、その長官は、内閣の指名に基づき天皇が任命する。これらは、任命後、衆議院議員総選挙の際に国民審査に付される。下級裁判所の裁判官は、最高裁の指名した名簿に基づき内閣が任命する。司法には、民事事件(およびその変型としての行政事件)と刑事事件とがあるが、日本国憲法の特徴は、こうした事件を通じて、法律その他の国家行為が憲法に違反するかどうかの判定を裁判所が行うことにしている点である(司法審査制)。これは普通、憲法裁判(憲法事件)とよばれ、最上級審たる最高裁判所の判定がものをいう。現に有効な法律が違憲と判定された事例には、尊属殺重罰規定事件(1973)、薬事法事件(1975)、衆議院議員定数規定事件(1976)、同(1985)、および森林分割事件(1987)がある。法令が違憲無効とされたわけではないが、1997年の愛媛玉串(たまぐし)料違憲判決のような例は特記に値する。愛媛県知事が靖国(やすくに)神社の例大祭などに際し、県費で玉串料を奉納したのは、憲法が禁止する政教分離原則に違反するとして、県知事の行為を違憲とした。これは、政治的な意味合いの濃い法領域において、最高裁が違憲と判定した珍しい例である。
[奥平康弘]
政党
憲法のとる議会主義が政党を基軸にして展開するという点では、日本では間違いなく政党政治が行われている。ただ、第二次世界大戦後の短い一時期を除いて、保守政党、とりわけ1955年(昭和30)以降1993年(平成5)までは自由民主党が政権を独占してきており、他の政党の追随を許さない勢いであった。これは日本政治史上特徴的な現象である。この現象をどう理解したらいいか。政党政治が未熟であった証拠とみる見方、政党とりわけ与党たる自民党の派閥的な仕組みおよびその独特な運用の仕方に由来するという考え方など、いろいろな説明が並列して可能であったようである。どちらにしても、自民党単独政権の長期化は、各方面によどみとゆがみを生じさせ、それらを許す構造をつくりあげたのであって、55年体制の崩壊とともに、各方面の改革課題が浮かび上がってこざるをえなくなった。
[奥平康弘]
第二次世界大戦前―政党の成立
日本における政党の始原は、明治初期の自由民権運動のさなか板垣退助らがつくった愛国公党(1874年結成)にさかのぼる。明治憲法の施行に伴い民選議院が成立するが、藩閥政府は政党政治の展開を嫌い超然内閣の線をとった。けれども結局は政党の発達を抑えることができず、「米騒動」のあった年、1918年に原敬(はらたかし)を首班とする、最初の政党(政友会)内閣が誕生した。軍部両大臣および外務大臣を除いて、閣僚はすべて政党員から選ばれた。これ以降、政友会と拮抗して憲政会、国民党、革新倶楽部(くらぶ)、立憲民政党など離散集合しながら、1931年の犬養毅(いぬかいつよし)による内閣(政友会)まで、政党が政治の実権を握った。犬養内閣は翌1932年の五・一五事件で首相が殺されたことをもって瓦解(がかい)する。これ以降は軍部が跋扈跳梁(ばっこちょうりょう)する世の中になる。
政党が政権を掌握した時期が約15年あったとはいえ、官僚的な政治体制にほとんどメスを入れることができなかった。情報、能力、組織の点で政党はむしろ官僚に依存した。また軍事関係については、軍閥の支配に任せた。昭和初期、日本が準戦時体制から総力戦体制に移るにつれ、政党はこれにほとんど抗しえず、むしろ進んで政党を解体させ挙国一致の大政翼賛会へとなだれ込んだ。
[奥平康弘]
第二次世界大戦後の展開
戦後は、戦前の流れをくんで進歩党、協同党および自由党が保守政党として成立した。戦前は非合法であった共産党が政治の舞台に公然と登場しうるようになる。弾圧を気にしながらか細い活動に終始してきた社会主義者や社会民主主義者らも、敗戦を契機に社会党を結成した。保守諸党は1955年、自由民主党へと発展解消し、社会党を相手とする二大政党制の成立が語られることになる。55年体制の成立である。その後、社会党から枝分かれして民主社会党(1960)が成立し、ついで新しい大衆政党として公明党(1964)が誕生し、むしろ多党化の時代になる。さらに新自由クラブ(1976。1986年解党)、社会民主連合(1978)が誕生した。絶対的支配力をもつ一巨大政党の周辺に多党が併存する状況となった。
1980年代の終わりごろになると、自民党単独支配の政治体制では、これからの国際化の時代に対応しないという観測から、選挙制度改革を通じて保守勢力内部での二大政党体制をつくりあげようという試みが浮上する。衆院小選挙区比例代表制導入をはじめとした政治改革法案は1990年代初め与野党間で激しい争いの的になり、自民党政権内部で何度かの首相変更があったのち、自民党から分裂して新生党が成立し、日本新党、新党さきがけが旗揚げし、社会党が社民党と改名し(新社会党が分裂独立し)、やがて新生党、公明党、民社党、日本新党などが寄って新進党ができあがり、その一部が太陽党となり、さらに新進党も解体、その中核勢力が自由党を結成、それとは別に民主党が結成され、その後民主党と自由党が合併するといった、非常にめまぐるしい、極度にわかりにくい政党の離合集散が続いて、いまに至っている。この間にあって不変なのは、ひとり日本共産党のみといえる。共産党は「唯一の野党」と誇り、1995年1月に施行された政党助成法に基づく政党交付金を受け取らず、その年の参院選および1996年の総選挙、1998年の参院選でもそれぞれ議席を伸ばした。
現時点では、日本の政党が安定化に向かってどのように結晶化し、それぞれがどのような特徴をもってどんな役割を果たすことになるかを見通すことは不可能である。そこで以下には、55年体制のもとで形成されてきた政党的な秩序がどんな性格のものであり、どんな役割を果たしてきたかという、過去を振り返る叙述を行う。今後の政治は、この過去をどう克服するべきかが課題となる。
一部の政党を除いて、これまでの日本の政党は下部の大衆的基盤がきわめて弱かった。党員数は少なく、収入のうち党費の占める割合はごくわずかである(1983年時点で、自民党11.2%、社会党28.5%。1996年時点では、自民党7.2%、社会党から党名変更した社民党14.3%。収入には、1995年実施の政党交付金が含まれているので、これを除外すると、それぞれ15.3%、27.8%となる)。業界、企業、労働組合、宗教団体などの巨大な社会組織と結び付いて存在する。資金面では企業・団体などの外部からの献金に頼らざるをえない(1983年時点で、自民党49.8%、民社党62.3%。1996年の自民党は46.2%)。いきおい、政策決定や立法活動、予算配分などの過程には、資金源の巨大組織の利害が反映されがちである。また、政策決定とりわけ政策実現過程において政党は、官僚機構に深く依存するという戦前からの体質をそのまま残している面がある。与党において官僚出身者の数がきわめて多いのは、官僚依存型の反映である。官僚出身議員は、どこをどう押さえれば何が出てくるかを心得ており、実際上も押さえることができるから、重宝である。こうして与党にあっては、「党人派」よりも「官僚派」が優位を占める傾向にあったが、自民一党独占が破られることなく長期間続いているなかで、自民党側の政策関与・発言力が増大し、いまや官僚主導型ではなく党主導型になったといわれる。これには、官僚の側が政権を担う可能性がまったくない野党を無視してもっぱら自民党政権への「擦り寄り」を行うようになったこと、および官僚出身議員と並んで、特定分野に精通した政策立案者が党内で重きをなすに至ったことなどに由来する。こうして自民党と官僚が一体化し、独特な「権力共有システム」が形成され、そしてそのことが政権交替をますます困難ならしめてきた。
自民党はいくつかの派閥から成り立っている。派閥が業界、企業などからの政治資金の受け皿として機能してきた。自民党のこの多元構造が、野党も含めた党外の諸勢力の利害を吸収したり、妥協させたりするのに役だった。他面、万年野党に甘んずる政党のほうは、批判党に堕していた。いい争点をみつけて自民党にぶつけた場合、自民党はうまくこれを受け止め、自分たちの政策に取り込んでしまう。逆に、まずい批判は、ただ野党に不利になるだけに終わった。ここにも自民党の安定化要因が組み込まれていたのである。
しかしながら、1990年代に入ってから、自民党の単独政治支配は陰りをみせ始め、選挙のたびに非自民党勢力の進出が目だってきた。いわゆる55年体制が崩壊し、各政党の離合集散があれこれと試みられながら、しかし、きわめて深刻になりつつある経済・金融危機から脱出できないまま、政界再編のめどがつかない状態に陥っている現状にある。
[奥平康弘]
第二次世界大戦後の政治過程
終戦直後
1945年(昭和20)8月15日、ポツダム宣言受諾を発表した鈴木貫太郎内閣は総辞職し、8月17日東久邇稔彦(ひがしくになるひこ)を首班とする内閣が成立し、敗戦処理にあたった。「一億玉砕」をスローガンとする本土決戦体制を急速に無条件降伏へと切り替えてゆくに際し、皇室の権威が必要となり、宮様内閣が登場した。敗戦にもかかわらず「国体」すなわち天皇中心主義の日本国の本質は変わらない、と国民に説き、「一億総懺悔(ざんげ)」して新事態に対処しようと強調した。8月末から連合軍による日本占領が始まるが、実質的にはアメリカ軍の単独占領であった。ドイツの場合と違い、日本では占領軍は間接統治方式を採用した。すなわち、日本の既存法体系やその執行機関を使いながら、占領軍は自らの意思(政策)を貫徹する方法である。これにより日本の官僚機構はほんのすこしの修正を受けただけで生き残ることができたし、旧秩序の変更もある程度のところで押しとどめることができた。もちろん占領軍には占領軍なりの目的があったし、ポツダム宣言には軍国主義の除去、民主化、基本的人権の確立、平和的で責任ある政府の樹立などが明示されていた。「戦後改革」は不可避であった。「戦後改革」の頂点に新憲法の制定という作業があった。これは、幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)内閣の課題となる。しかし、政治支配層は憲法改正を欲しなかったので、この作業は占領軍のイニシアティブで行われた。これが後年、「押し付けられた憲法」論(「したがって自主憲法制定が必要だ」という議論)を招くことになる。主権在民、軍備撤廃、人権保障、政治機構の民主化を命ずる新憲法が、その後の政治過程に与えた影響は絶大である。敗戦直後、食糧危機をはじめ経済状況の悪化はその極に達していたこともあって、労働者、農民その他の大衆運動が著しく高揚した。こうして幣原内閣および吉田茂(第一次)内閣のもとで、農地改革、財閥解体その他の大型改革が行われる。
[奥平康弘]
吉田内閣期
1947年4月、新憲法下初めての総選挙で社会党は第一党となり、社会党主導の片山哲(てつ)連立内閣が成立した。これは社会党内部の対立により翌1948年2月総辞職し、かわって芦田均(あしだひとし)(民主党)を首班とし社会党、国民協同党が参加する中道内閣が成立したが、昭和電工(汚職)事件が発生してその年10月芦田内閣は終焉(しゅうえん)をみ、吉田(第二次)内閣の成立となる。これ以降、日本は保守党のみが政権を担う「保守王国」となる。
1948年12月、日本政府はアメリカ政府から直接「日本経済の安定と復興を目的とする九原則」(経済安定九原則)を実施するよう要請された。日本経済の自立化をねらいとするドッジ・ラインである。戦後危機から立ち直り「復興」への道をとることとなるが、おりから1950年6月末朝鮮戦争が勃発(ぼっぱつ)し日本では「特需ブーム」を招き、経済復興のためのまたとない好機となった。朝鮮戦争は他面では、自衛隊の母体となる警察予備隊の創設をもたらした。レッド・パージを生み、共産党は手ひどい弾圧を受けた。政治的不自由、不寛容の時代の到来である。この時期(1950年7月)、反共民同派の労働勢力が結集してつくった総評(日本労働組合総評議会)が、その後の政治過程ではむしろ左翼的な労働組織の中心と考えられるようになるのは、歴史の皮肉に属する。こうしたなかで、ソ連、中国も含む「全面講和」を要望する広範な知識人層の声を押さえて、日本およびアメリカは「単独講和」の路線を選択した。1951年9月、西側諸国との間に限って、対日講和(サンフランシスコ)条約が締結された。こうしてソ連、中国その他重要な国々とは戦争が終わらないという変則状態のまま日本は独立国となった。サンフランシスコ条約と同時に日米間で安全保障条約が締結され、独立後も米占領軍はそのまま――ただし駐留軍と名を改めて――日本に残った。占領体制は安保体制へと転換する。1953年10月、吉田首相の私設特使として渡米した池田勇人(はやと)(自民党政調会長)は、米国務次官補ロバートソンWalter Spencer Robertson(1893―1970)と会談し、日本の防衛力増強とアメリカの対日軍事援助についての共同声明を発表した。この池田・ロバートソン会談に基づき1954年3月、日米間の相互防衛援助協定(MSA)が調印され、アメリカの援助により日本の軍事力を強化することが約束される。こうして1952年、警察予備隊は保安隊へと改組拡充され、1954年には自衛隊へと成長することになる。この間、1946年5月の第一次吉田内閣、1948年10月の第二次吉田内閣およびそれ以降、総理大臣として日本政治を牛耳(ぎゅうじ)ってきた吉田茂は、ワンマンといわれながらも、アメリカに対してものがいえるかけがえのない政治家とみなされ、国民の人気を博してきた。けれども占領が終結し日本が復興期に入るとともに、吉田時代も底をみせるようになる。1954年1月、造船疑獄事件が明るみに出されるや、吉田の意向に沿って法相犬養健(たける)が検事総長に指揮権を発動し、自由党幹事長佐藤栄作の逮捕を阻止するということがあった。これが材料になって、衆院で内閣不信任案が可決され、第五次吉田内閣は総辞職。吉田は、合計して7年2か月座っていた首相の席をついに離れた。これより先、1951年10月、社会党は講和・安保両条約問題をめぐって左右の両派に分裂していたのが、政界再編をねらって1955年1月、統一された。
[奥平康弘]
鳩山内閣期
吉田退陣後の総選挙は1955年2月、鳩山(はとやま)一郎選挙管理内閣のもとで行われた。選挙では、鳩山一郎、岸信介(のぶすけ)らの民主党が真正面から憲法改正、再軍備を打ち出したのに対抗し、社会党は「平和憲法擁護」の線で闘った。左派社会党は、先の1953年総選挙において鳩山らの唱える改憲論に「青年よ、銃をとるな」のスローガンをぶつけて躍進していた。統一社会党はこの線を踏襲した。選挙の結果、民主党は第一党となったものの、議席数は185、自由党をあわせても299しかとれなかった。その分だけ社会党左派が増えた。総選挙後の1955年11月、民主、自由両党が合体して自由民主党ができあがった。保守合同により、社会党と対応する形の二大政党制が標榜(ひょうぼう)されることになる。しかし実際には、この五五年体制はまさしく保守一党の、自民党の絶対優位体制の礎石となるのであった。鳩山は、吉田の選んだ片面講和の結果、課題として残されていた日ソ関係を修復することを念願とした。1956年10月鳩山自らがモスクワ入りして交渉にあたり、ようやく共同宣言調印にこぎ着けた。しかし、宣言は領土問題を棚上げにして初めて可能なものであった。日ソ共同宣言をきっかけに、その年12月18日、国連は満場一致で日本加盟を承認した。念願かなったのを見届けて鳩山は辞職した。鳩山にはもう一つの念願があった。憲法改正による再軍備である。総選挙の結果、国会両院の3分の2以上の議席を獲得することが不可能になったので、これを可能にすべく、保守派に有利な小選挙区制を敷こうと企てた。しかしその政治的意図があまりにもはっきりしており、選挙区割も目にみえて恣意(しい)的なので、世論の支持が得られず、廃案になった。
[奥平康弘]
岸内閣期
短命に終わった石橋湛山(たんざん)内閣を引き継いで内閣を統轄することになった岸信介は、東南アジアとの間に「経済外交」を展開するとともに、アイゼンハワーと会談して「日米新時代」をうたう共同声明を発表した。岸は、憲法改正と日米安保条約改定との二つを自らの政治課題とした。その前哨(ぜんしょう)戦が、教職員に対する勤務評定の実施と警察官職務執行法(警職法)の改正をめぐる攻防であった。教育と警察は、「戦後改革」を受けた分の多くを、すでに教育関係法の改正(1954年および1956年)および警察法(1954年)で大きく修正されていた。前者では日本教職員組合の弱体化が、後者では警官の権限強化が図られた。しかし警職法改正案の場合は、戦前の「オイコラ警察」の復活だと広範な国民大衆の反対運動が盛り上がり、政府はこれを廃案にした。保守反動的法案を後退させた珍しい事例である。岸は安保改定により日米の相互防衛を対等なものとすることにより、日本の軍事力を強化しようとした。アメリカとの間で改定をめぐる交渉が始まるや、社会党など革新団体は改定阻止の「国民会議」をつくって反対運動を開始した。おりから「三池(みいけ)」炭鉱の解雇問題に端を発する労働闘争が始まり、政治闘争とリンクした。1960年1月、国会では安保特別委員会を中心に、条約改正の論戦が始まった。国会周辺には連日請願デモが繰り広げられた。5月19日、政府・自民党は警官500人を衆院に入れ社会党議員をごぼう抜きにしたうえで、50日の会期延長を議決。5月20日未明までにいっさいの審議採択を終えて、条約の批准承認は衆院で可決された。しかし、こうしたかつてない強行採決は全国に広範な抗議デモを招来し、批准書交換のため初めて日本を訪れる予定だったアイゼンハワー大統領に対し、日本政府は訪問を中止するよう要請しなければならなかった。新安保条約は6月19日、抗議する市民33万人が国会周辺に座り込むなか、参院の議決を経ないまま自然成立した。岸内閣は極秘のうちに批准の手続を進め、それが終わった23日、総辞職した。
[奥平康弘]
池田内閣期
岸の後を継いだのは池田勇人(はやと)であった。池田は「寛容と忍耐」を説き、「所得倍増政策」を打ち出した。まことに「経済政治の時代」の幕開きにふさわしいスタイルであった。日本は経済高度成長路線をまっしぐらに進むことになる。高度成長そのものは1950年代後半から現実に展開しつつあった。池田はこの経済の現実にあわせて「所得倍増」の政策をつくったのである。高度成長は着実に進展したし、それにあわせた政策――産業基盤の強化育成、エネルギー対策、農業の近代化、合理化など――は大当りだった。この裏には中小企業の切り捨て、都市化、自然破壊、過疎化などの矛盾が生じたが、それらの対策は本質的には1970年代へと譲られる。戦前日本では地主が支配的な階級であったが、それが完全に後退し、この時期には大企業、財界の政治支配が確立する。財界は政党への政治献金の見返りとして、希望する立法や政策を――高級官僚を媒介にすることを通じて――採択させた。経済団体連合会、日本経営者団体連盟などの経済団体が陰に陽に政治の舞台に登場し、決定的役割を果たすようになる。他方、高度経済成長という現実を踏まえて、野党とりわけ社会党のなかに路線変更を要求する声が出てきたのも、特徴的である。書記長江田三郎らの唱える構造改革論がそれで、「アメリカの高い生活水準、ソ連の徹底した社会保障、英国の議会制民主主義、日本の平和憲法」を目標に「国民諸階層の生活向上」を達成しようと訴えた。しかし、党内では、この論は改良主義的であり、現代資本主義体制を是認するものにほかならないという批判が強く、1962年11月江田は書記長を辞任した。高度成長の結果生ずる社会変動は、農業就業者の激減で自民党に不利に、逆に産業労働者の急増で社会党に有利に働くだろうという予測(前労相石田博英(ひろひで)(1914―1993)の1963年初めに出た論文)が注目されたにもかかわらず、1963年11月の総選挙では、自民党の議席はほとんど減らず、これに反し期待の社会党は1議席を失った。第三次池田内閣の下で日本は、「IMF8条国」となり、OECD(経済協力開発機構)への加盟が認められて先進国の一員となったのみならず、東海道新幹線の開業、オリンピック東京大会の開催などがあった(いずれも1964年)。しかし池田は病気のため辞任せざるをえず、かわって内閣を引き継いだのが佐藤栄作である。
[奥平康弘]
佐藤内閣期
第一次佐藤内閣は、日韓基本条約のような懸案の外交問題、ILO87号条約に体現される公務員労働権問題を、野党の抵抗を排して強行処理するとともに、占領下農地改革をめぐる地主の不満に農地報償法を制定してこたえた。高度成長に伴う社会変動の一つに人口移動がある。これは、選挙区における議員定数配分の再編を要請するものであった。1960年代に入ると、これを争点とする憲法訴訟が提起され、国会は1964年、戦後初めて議員定数是正を図る法改正を行った。19議席の定員増で是正しようとする、その場しのぎの改正であったが、このもとで行われた総選挙が1967年1月のそれである。自民党は前回に比べ14議席を減らし、その相対得票率が初めて50%を割って48.8%に下がった。社会党もまた3議席を失い不振であった。両党にかわって点を稼いだのは、この選挙で初めて衆院進出に打って出た公明党である。25議席を獲得した。民社党も7議席増やして30人を当選させ善戦した。二大政党制は夢と化し、一党優位体制下での多党化というパターンが成立した。
佐藤内閣は沖縄返還を重要課題の一つとした。1969年11月ワシントンでニクソン大統領と会談し、「核抜き本土なみで72年に沖縄施政権を日本へ返還」を内容とする共同声明が発表された。佐藤はこれを果実にして民意を問うべく、帰国早々12月初め衆院を解散し、年末ぎりぎりの27日総選挙が行われた。自民党は当選後入党した者も含め300議席を獲得した。前回より20議席も増えた。これに反し、社会党は一挙に51も減らして90議席をとるにとどまった。公明党の進出が目覚ましく、前回の25から47とほぼ2倍の議席を獲得した。民社党32、共産党14。多党化現象はぬぐうべくもない。
高度成長のひずみをもろに受けた地方から、「地方自治の復権」が語られるようになるのもこのころである。中央とは別な政治配置がみられることになる。1967年4月社会党と共産党の推薦で美濃部亮吉(みのべりょうきち)が東京都知事になり、1970年代前半にかけて10名の革新知事を数えた。1968年1月の米原子力空母エンタープライズ佐世保(させぼ)寄港に反対する学生運動、各大学の学園闘争およびそれとリンクした成田・三里塚の農民・労働者らの大衆運動、1969年1月の東京大学安田講堂占拠事件などは、「70年安保」の前哨戦という意味をもった。けれども肝心の安保条約は内容上の修正の申し入れがどちらの政府からもないまま、その効力が自然に延長したため、反体制側は安保闘争を組む余地がなかった。1970年はむしろ、大阪で開催された「万博の年」として記憶に残ることになる。6421万余の見物客を集めたという。
佐藤内閣は、高度成長のツケとしてその後の歴代の内閣が直面しなければならない日米貿易摩擦を、繊維の領域で受け止めなければならなかった。日本の繊維輸出の規制を求めるアメリカの要求にどう対処するかという問題である。1971年、日本は二度の「ニクソン・ショック」を経験する。一つは、日本の頭ごしに行われたキッシンジャー訪中であり、もう一つは、一連のドル防衛策で、「ドル・ショック」ともいわれる。1ドル=360円の円安レートで輸出を伸ばしていた日本経済の修正を迫るものであった。変動相場制への移行を余儀なくされ、のち「狂乱物価」につながる。佐藤は、1972年5月沖縄復帰記念式典を見届けたのち、6月なかば引退を表明した。7年8か月に及ぶ最長記録をつくった。
[奥平康弘]
田中内閣期
だれが後継者となるかをめぐって田中角栄と福田赳夫(たけお)の間に「角福戦争」が行われ、結果は田中の勝利となった。田中は、学歴こそないが、抜け目ない立回りと計算力の強さで成り上がった政治家で、大衆の間に不思議な人気があった。首相になる直前、彼の名で出された本、『日本列島改造論』は、「開発」を当て込む民衆のベストセラーとなった。1972年7月田中内閣は成立早々、中国との国交回復を目ざして精力的に活躍した。9月下旬、大平外相、二階堂進(1909―2000)官房長官を伴って田中は北京(ペキン)入りし、日中共同声明に調印した。戦後27年にしてやっと中国との戦争状態が正式に消滅した。このあと11月、田中は衆院解散、総選挙に打って出た。自民党は意外に振るわず、共産党の躍進(14から40へと議席増)が目だつ選挙であった。第二次田中内閣はすこしもいい目をみなかった。1973年から1974年にかけて物価が異常に高騰し、民衆の生活感覚を逆なでした。「狂乱物価」は、ドル・ショックの後遺症である面、「開発」を当て込んだ土地投機、その他の買占めに由来する面などがある。加えて、石油ショックが日本列島を直撃した。中東戦争による原油価格の値上り、これを利用した国内諸企業の流通・物価操作の所産である。大衆は日常生活に危機感を覚えた。「日本列島改造論」は裏目に出た。田中の人気は急速に衰える。1974年7月のいわゆる七夕(たなばた)(参院)選挙は、「金権選挙」の批判が強いなかで闘われたが、自民党は6議席減。参院に関する限り、与野党「伯仲」の時代になった。選挙後まもなく、「田中金脈」問題が浮上する。いろいろな不正が取りざたされ、国会論議はこれに集中して空転した。結局田中は、11月末辞意を表明せざるをえなかった。海の向こうアメリカではその3か月余り前、ウォーターゲート事件の絡みでニクソン大統領が辞任していた。
[奥平康弘]
三木内閣期
田中の後任には、清廉と党の体質改善というセールス・ポイントが買われて、小派閥の三木武夫(たけお)が選ばれた。三木は党および政治の近代化を図ろうと、政治資金、選挙関係の一連の法律改正を提案するが、どれも十分に実を結ぶことがなかった。1976年2月、アメリカ上院外交委員会の小委員会でのコーチャン証言などロッキード航空機の日本売り込みに関連する賄賂(わいろ)情報が流れてきた。三木は真相究明に熱意をみせ、アメリカ側へ捜査協力を依頼する。6月ないし7月にかけて、丸紅、全日空の幹部の逮捕から始まって、田中角栄とその秘書榎本敏夫(えのもととしお)(1926―2017)の逮捕があった。さらに元運輸次官佐藤孝行(こうこう)(1928―2011)、元運輸相橋本登美三郎(とみさぶろう)(1901―1990)が逮捕された。逮捕を逃れたが「灰色」の疑いがある政治家の名がほのめかされたりもした。自民党主流は、こうしたロッキード疑獄騒ぎを苦々しく思い、それを政治問題とすることを最小限度に食い止めてきた。田中らの逮捕により刑事事件となったのを好機とみた。この問題はいっさい裁判に預けられている、という戦法をとった。金権政治にメスを入れた制度改革がなにひとつ結実しないままで、「三木おろし」の工作が顕然と行われた。三木は、日本国憲法史上初めて衆議院議員が4年の任期いっぱいを務めるのを見届けたうえで、1976年12月総選挙を行った。自民党は、過半数を割るという敗北を初めて経験したものの、無所属当選者の入党を認めて260議席を掌握、過半数を維持した。自民党の敗北は、誕生したばかりの新自由クラブの善戦(18議席を獲得)と連動していた。社会党の伸び悩みに反し、公明、民社が選挙協力の協定を取り結んだ結果、ずいぶん得をした。共産党は前回の40から19議席へと低落する。
[奥平康弘]
福田・大平・鈴木内閣期
三木にかわって登板した福田赳夫(たけお)は、経済の立て直しという本題ではあまり振るわなかった。むしろ彼の在任中の仕事としては、1978年8月調印し10月批准書を交換した日中平和友好条約がある。田中角栄が1972年に修復した日中関係は、より実質化されるべき運命にあった。条約締結の前に、党内の台湾派を押さえるとともに、ソ連を刺激しないよう配慮して「全方位外交」路線を維持する必要があった。自民党は、三木が退陣する際提言した「総裁公選制」をとることを約束していた。1978年11月それが行われた。福田優勢の予想に反して、大平正芳(まさよし)が圧勝した。大平に肩入れした田中派のすさまじい票買いがこの結果を生んだといわれる。また、タカ派の福田ではなくハト派の大平が選ばれた背景には、与野党伯仲、したがって連合政権への対応を模索しなければならないという要因があったようである。タカ派は、有事立法、元号法制化、靖国(やすくに)神社参拝などの争点で、福田内閣時代、かなり点数を稼いでいた。有事立法論議は自衛隊の存在感を強化するのに役だち、後の国家秘密法(スパイ防止法)論議の布石となった。また「昭和」の終焉(しゅうえん)に対処するための元号法制化は、福田の推進した路線で次の大平内閣の時代にそのまま結実した。さらに、「内閣総理大臣 福田赳夫」と記帳したうえでの終戦記念日の靖国神社参拝は、「公式」のものではないと弁解して行われたが、のちに1985年になると中曽根(なかそね)首相は、「公式参拝」でも一定の制約形式を踏めば政教分離を命ずる憲法に違反しないという議論をたてて、公式参拝と銘打つものを強行する。こうして、反動化ではないにしても右傾化への傾向がうかがえたが、大平政権はこの傾向にはっきりと対抗することなく、むしろ党内派閥の均衡を図り、「待ち」の政治に徹した。
田中金脈問題が未解決のところへ、1978年末アメリカにおけるダグラス・グラマン事件が翌年日本関係へと波及するとか、鉄建公団などの不正経理が明らかになるとか、政府・自民党に不利な材料があったが、支配体制は全体としては順風満帆といったところであった。大平内閣は国民の間には「保守復調」がはっきりうかがえると観測し、一般消費税を導入しての財政再建を掲げて、1979年10月総選挙に打って出た。ところが「保守優勢」「自民党大勝」の予想に反して、自民党は公認候補だけでは過半数をとれないほどの負けぶりであった。負けたのは自民党だけではない、社会党も117から107へと10議席も失った。かわりに共産党が躍進し(19から39議席へ)、公・民「中道」協力が成功して「中道連合政権」構想が語られるようになった。大平首相は選挙結果が不利に終わったにもかかわらず田中元首相の強い勧めなどもあって退陣せず、政権に固執した。しかし、総選挙後、国会で行われた首相指名選挙においては、大平と福田との分裂がみられるという異例のことが生じるほど、自民党内における反大平勢力は強かった。
1980年5月、社会党が衆議院本会議で提出した内閣不信任案が、福田、三木など反大平派の本会議ボイコットの結果、可決されるというハプニングがあった。これを受けた大平は衆議院を解散し、総選挙で臨むことにした。自民党優位をねらって、総選挙は参議院通常選挙と同日(6月22日)と設定された。同日選挙は史上初のイベントである。選挙運動の真っ最中、大平首相の急逝というハプニングもあった。野党は社会党と公明党、公明党と民社党というぐあいにブリッジ政策共闘をもって闘ったが、自民党が圧勝した。与党は安定多数を上回る284議席を獲得、野党は前回躍進した共産党も含め、全般に不振で、わずかに新自由クラブと社民連が若干議席増をみただけ。野党「連合政権」を語るべき条件は消えてなくなり、野党は冬の時代を迎える。
自民党は、圧勝を背景に、「自主憲法」制定に照準をあわせて、10年間も休眠していた憲法調査会を再開し、靖国神社の公式参拝問題をまた浮上させるなど、明らかに右に寄った。「和」の政治を唱える鈴木善幸(ぜんこう)新首相は、こうした右寄りに同調する傾向がみられた。鈴木は行政改革に政治生命をかけるといい、大平がやれなかった財政再建を最重要課題とすると称したが、「腰が据わらない」「指導力欠如」という批判が行き渡った。不況に悩む西側諸国との貿易摩擦、アメリカからの防衛力増強要求、中国などから出された教科書問題など、日本外交は岐路にたたされる兆しが濃くなった。鈴木の「和の政治」手法はとくに財政再建での取り組み不十分が非難の的になり、これが引き金となって、鈴木は1982年10月突然退陣の意思を表明した。11月の総裁選で田中・鈴木両派の支援を得て中曽根康弘(やすひろ)が勝利を収めた。
[奥平康弘]
中曽根内閣から森内閣まで
古くから憲法改正を公然と主張してきた中曽根は、同じく改憲論者で知られる瀬戸山三男(党憲法調査会長。1904―1997)を文部大臣に選ぶなど、この方面の意欲の強さをうかがわせた。1983年1月、中曽根は訪米してレーガン大統領と2回会談。席上「日米両国は太平洋を挟む運命共同体だ」と発言し、日米軍事協力の強化が示唆された。中曽根は、また『ワシントン・ポスト』紙上で「全日本列島を不沈空母のようにし、ソ連のバックファイアー爆撃機の侵入に対する巨大な防壁を築く」と語り、ソ連を潜在敵国とすることでアメリカを喜ばせた。5月、アメリカのウィリアムズバーグで開かれた主要先進国首脳会議(サミット)では、「欧州へのパーシングⅡと巡航ミサイルの配備を断行する必要がある」と主張し、日本がアメリカの世界戦略を補完する「西側の一員」として役割を分担することをはっきりさせた。これは「全方位外交」が否定されたことを意味する。11月はレーガン大統領の訪日があり、「ロン・ヤス」の親密な対等の関係が大いに強調された。中曽根はこうした積極外交で国民の人気を集めた。中曽根は、戦前の価値体系への回帰を指向しながら、「戦後政治の総決算」というナショナリズムの色彩の強いスローガンを掲げ、他方、経済的自己中心主義でやってきた過去の日本は、世界に開かれた国際国家にならねばならないと説く。「経済大国」になりおおせたのだから、今度は「政治大国」を目ざすというわけである。中曽根は「戦後史の転換点」にたって自らその舵(かじ)取りをしようと意欲満々であった。キーワードの一つは行財政改革である。彼は前内閣のとき行政管理庁長官の地位にあってこの政策の直接の責任者であっただけに、行財政改革を断行しなければならないと受け止めた。もう一つの重要課題としたのは教育改革である。1983年6月、従来からの中央教育審議会とは別に、首相の私的諮問機関として「文化と教育に関する懇談会」を設け、山積する教育諸問題を「戦後教育の見直し」の観点から検討するよう要請した。首相就任当初はあからさまに改憲志向を打ち出したものの、反響があまり芳しくないこともあり、これを表向きには出さないことにして国内の社会の改編を着実に実行する路線がとられることになった。
1983年(昭和58)6月、全国区を廃止して「拘束名簿式・比例代表制」にかわった参院通常選挙が初めて行われた。比例代表区、選挙区とも史上最低の投票率(57%)を記録したが、選挙の結果は政局に大きな変動を及ぼすようなものではなかった。このときの選挙と抱き合わせに衆院総選挙、いわゆる同日選挙をやるよう田中元首相は示唆したというが、中曽根は「田中曽根」と蔑称(べっしょう)されているような田中角栄寄りの印象をぬぐうべくあえてこれを避け、自分の線でいけるとにらんで11月末衆院解散、年の瀬詰まった12月18日総選挙を決行した。おりから10月なかば田中元首相に対する第一審有罪判決があって、選挙では「政治倫理」が争点にならざるをえなかった。自民党は派閥の調整がつかないまま乱立したことも一因となり、過半数割れ(250議席)で敗北、その後の政局運営のため新自由クラブと連立することを余儀なくされた。この選挙でも投票率が低く全国平均で67.94%、過去最低のものであった(もっとも、その数値も1996年10月の総選挙の小選挙区での投票率59.65%に比べたらまだ高い)。社会党と公明党、公明党と民社党、さらに新自由クラブや社民連など中道4党の選挙協力がある程度功を奏した。選挙の結果、共産党を除いて野党は総じて「連合政権」の構想のもと、政策や立場の再検討を始めた。こうして「野党の右傾化」が指摘されるようになる。なかでも社会党は「抵抗政党」から「政権政党」への脱皮を図ろうと、たとえば自衛隊を認知する理論(「違憲合法」論)に飛びつき、党の内外から批判された。他方中曽根内閣は、陰りをみせ始めた「田中支配」からの切り離しを印象づける努力を払いながら、行政、財政、教育の三大内政改革に懸命の取り組みを図る。1984年9月上旬には韓国の全斗煥(ぜんとかん/チョンドファン)大統領の来日があったが、日韓関係史上最初のイベントであった。中曽根首相は中国、東南アジア、ヨーロッパと精力的に訪問した。「仕事師内閣」というイメージのもと、たいへんに国民に受けた。1986年6月、中曽根内閣は衆院を解散して7月に衆参同日選挙を実行した。その結果、衆院で自民党は304議席獲得という圧勝を経験した。新自由クラブと連携する必要のない安定政権を確立した。新国会では、国鉄分割・民営化が本決まりとなり、これで専売、電電とともに三公社はすべて解体することになった。税制改革、防衛費増強、教育改革といった懸案事項に着手する構えがうかがえた。こうしてまず、三木内閣時代防衛費上限の枠として設定したGNP1%を突破する予算案を作成すると同時に、多段階の売上税導入を決断して、1987年1月の通常国会に臨んだ。ところが、ここで登場した売上税法案は、大型間接税導入は行わないという自民党の選挙公約に違反するという声が世論を支配し、内閣は厳しい国会運営のあげく、新税法案は廃案とせざるをえなかった。
売上税に代わって1988年竹下内閣のもと消費税が導入されたが、消費税に対する世論の反対は強く、翌1989年(平成1)7月に行われた参院通常選挙では、消費税、リクルート疑惑そして農産物自由化問題のいわゆる逆風三点セットが自民党にとって不利にはたらき、与野党逆転の結果となった。自民党は参院で多数を占めることができないという国会運営上の「ねじれ」を初めて経験した。1990年に入るや、米ソ冷戦の終結、イラクのクウェート侵入、湾岸戦争など国際環境に激変が生ずるなか、国内では自衛隊の「国際協力」をめぐる議論が闘わされ、選挙制度改革(小選挙区制導入)、政治資金法改正、政党助成法の導入による政治改革などをめぐって諸政党に大きな動きがあった。1993年7月の総選挙では「政権交代」が争点となった。これで自民党は半数割れして野党に転落、日本新党の細川護熙(ほそかわもりひろ)代表が特別国会で首相に指名された。こうして8党会派からなる連立政権が誕生し、五五年体制が崩れた。このとき連立第一党の社会党から土井たか子が衆院議長に選ばれた。史上初めての女性議長である。その年連立与党のもとで政治改革法案の大枠に合意がみられ、翌年1月ようやく成立した。その後政党間の離合集散がめまぐるしく、首相の短期交代が続いた。その間にあって、1994年6月、自民、社会、さきがけの三派連合による村山富市(とみいち)内閣の成立、社会党の路線転換(自衛隊と日米安保の容認、国旗、国歌の承認)がありながらも、社会党はその政治力を著しく失い、1996年1月、社会民主党と改名したのち、同年10月の総選挙を闘うが、新党さきがけともども敗北を余儀なくされたまま、橋本龍太郎自民党内閣には閣外協力の立場をとった。しかし1998年6月初め、来る参院選挙に備えて、閣外協力関係を解消した。その年7月に行われた参院選で自民党は予想外の大敗を喫したため、おりからの金融危機打開、日米安保体制立て直し、行政諸政策などの政治課題においては、争点ごとに非自民党政治勢力との折衝と妥協を重ねながら、課題をかたづけてゆくほかない局面に立たされた。橋本内閣の後継となった小渕恵三(おぶちけいぞう)内閣は、1999年1月、小沢一郎(おざわいちろう)党首の自由党と自自連立政権を発足させ、「日米防衛協力のための指針」関連法、中央省庁等改革関連法、国旗・国歌法、通信傍受法などの重要法案を成立させた。さらに1999年10月には、公明党を加えた自自公連立政権を発足させたが、2000年4月に自由党が連立を離脱、その直後に小渕が脳梗塞(のうこうそく)で倒れる事態が生じた。あとを継いだ森喜朗(よしろう)内閣は、自民・公明・保守(自由党内の連立離脱に反対するグループが結成)3党による連立政権となった。同年12月に内閣改造を行ったが、2001年に入ると、中小企業経営者福祉事業団に絡む贈収賄事件、アメリカの原子力潜水艦と日本の高校実習船の衝突事件に際しての不手際などで、内閣支持率が極端に低下、3月に森首相は退陣を表明した。
小泉内閣成立以後
森首相の退陣を受けて、2001年4月に小泉純一郎、橋本龍太郎、麻生太郎、亀井静香(1936― )の4人による自民党総裁選挙が行われた。当初、橋本有利とみられたが、地方票で圧倒的な票を獲得した小泉が当選、森内閣と同じく自民・公明・保守3党による連立政権を発足させたが、そのときの内閣支持率は80%を超えるきわめて高いものであった。小泉内閣は構造改革を第一に掲げ、歳出削減による財政再建政策を打ち出した。「聖域なき構造改革」をスローガンに特殊法人などの改革に着手したが、すぐに激しい抵抗に直面した。また、国民的人気のあった田中真紀子(1944― )外相が外務官僚との軋轢(あつれき)により、更迭された直後には支持率は50%に低下した。しかし、2001年9月の北朝鮮訪問と日本人拉致被害者の帰国により、支持率は回復した。小泉首相は国民に人気が高く、つねに高い内閣支持率を示していた。一方、小泉首相は毎年靖国神社に参拝しており、これによって中国、韓国の激しい反発を招いている。また、2004年1月のイラクへの陸上自衛隊派遣や、有事関連法の相次ぐ成立など、タカ派的な姿勢が現れている。2003年11月に発足した第二次小泉内閣では、保守新党が自民党との合併により解党したため、自民・公明2党による連立政権となった。この内閣において年金改革が着手されたが、その審議は紛糾した。さらに、国会議員の国民年金未加入あるいは保険料未納問題が発覚、福田康夫官房長官が年金未納のため辞任するという事態になった。そして2004年6月にようやく年金改革法が成立したが、抜本的改革とはなっておらず、批判の声が強かった。次に小泉首相は長年の持論である郵政民営化に手をつけた。9月に郵政民営化担当相を新設し、竹中平蔵経済財政相に兼務させた。しかし、郵政民営化に対する自民党内部での抵抗は強く、2005年7月の衆院で、自民党内からの反対票のため、かろうじて郵政民営化法を可決させたものの、参院では否決されてしまった。小泉首相は「郵政民営化について民意を問う」として衆院を解散した。そして9月に行われた衆院選挙では自民党が296議席を獲得して圧勝、10月に郵政民営化関連法が成立した。こうして郵政民営化を実現した小泉首相は、公約どおり次期自民党総裁選挙に出馬せず、退陣した。
総裁選挙で圧勝した安倍晋三(しんぞう)を首相とする内閣は、2006年9月に発足した。戦後生まれで初めて首相となった安倍は、所信表明演説で「新しい国づくり」を提唱、憲法改正に意欲をみせた。また、首相の諮問機関として教育再生会議を設置するなど、教育問題についても積極的に取り組む姿勢を示した。そして、憲法改正の手続を定めた国民投票法を制定し、教育改革のための学校教育法などの改正を行った。しかし、農水大臣をはじめ、大臣の不祥事による相次ぐ辞任で大きなダメージを受け、参院選で過半数を失う大惨敗を喫し、2007年9月に安倍首相は突然辞任した。安倍内閣を引き継いだ福田康夫首相は、4人の大臣を交替させただけで、ほぼ前内閣と同様の陣容でスタート、生活者重視の政策を打ち出した。しかし、参院では与党の議席は過半数に達していないため、「ねじれ国会」となっていて苦しい議会運営を強いられた。
1990年代に入って自民党単独政権が崩れて以降、新しい政治秩序の構築を目ざすきざしがみえ、事実、公的介護保険、日銀改革、NPO法(NPOとは民間非営利組織のことで、NPO法はNPOが法人格をとりやすくする、税制上の優遇措置を講ずるなどを内容とした「市民活動促進法」)、被災者生活再建支援法など、若干の成果がみられた。けれども、住専問題に象徴される金融界のよどみ、沖縄米軍基地の整理縮小、年金問題など多くの課題を残した。また行政改革の実行は情報公開法の実施、その他の霞が関(かすみがせき)改革とともに、いまでは一歩も後退を許されない政治課題となった。
日本の国際関係
概説
太平洋戦争の敗北により被占領国になった日本が、主権を回復し独立国家としてともかくも国際社会への復帰の道を歩むことができたのは、1952年(昭和27)4月28日、連合諸国の批准を得てサンフランシスコ対日平和条約が発効した時点からである。しかしこれは、外交関係を処理する地位をある程度回復したことを意味するだけである。ソ連および中国とは依然として戦争状態が残っていた。フィリピン、インドネシアのように平和条約締結そのものに反対する国があったし、アジアのほぼすべての諸国との関係では賠償問題を処理する責務が残されていた。朝鮮との国交はまったく未知数であった。サンフランシスコ条約は、そこへ至る道筋が示すように、冷戦下におけるアメリカの戦略が帰結したものであった。日本は、この条約と同時に日米安全保障条約を取り結び、そのもとで締結した行政協定により、アメリカ占領軍は基地、施設もろとも、在日駐留軍と改称して居残った。日米関係はその後ずいぶん変化したが、その基本的な枠組みはほとんど修正されないまま現在に至っている。ひと口でいえば、日本は外交および防衛においてアメリカの国際政策および戦略体制の一環として組み込まれており、対米従属的な性格が著しく強い。そしてこれは、アメリカの対日占領体制以来刻印づけられてきたものである。
対米外交と矛盾しない限りで、これまでの日本は「全方位外交」「等距離外交」をとることに努めてきた。1980年代に入って、対米従属性が強められ、この点での修正がみられたが、日本には日本固有の創造的な外交があるはずだという考えは、当然のことながら完全に消滅してしまったわけではない。日本は1956年(昭和31)末念願の国際連合加盟が認められて以来、国連中心主義ということを外交原則の一つにしてきている。事実、国連分担金の負担など、経済の面で応分の責任を果たしてきた。けれども、国連のなかで世界の尊敬をかちえる名誉ある独自の活動をしているかどうかは、評価の分かれるところであった。
1980年代末から1990年代初頭にかけて、ベルリンの壁の崩壊に象徴される東欧革命、ソ連邦解体などの激変があって、米ソ冷戦体制は崩れ去ろうとしていた。こうして日本防衛体系にとっての永年の「潜在的敵国」がいなくなろうとするやさき、イラクによるクウェート軍事侵攻、クウェート併合などペルシア湾岸危機が発生、1991年1月なかばには湾岸戦争へと展開した。「戦争」そのものは、イラク軍のクウェートからの撤退によって2月末に終了したが、湾岸のこのできごと、およびこれに対するアメリカ主導による国際連合の軍事介入の動きは、日本防衛政策立て直しの好機となった。日本政府はまず米軍を主力とする多国籍軍の軍事展開に130億ドルの財政支出を行い、ついで国際平和維持活動(PKO)協力法を制定し、自衛隊の平和維持軍参加を模索した。戦争終結後の1991年(平成3)4月末、政府は掃海艇4隻、掃海母艦、補給艦の計6隻をペルシア湾に残存する機雷処理のために派遣した。
従来からの「国連中心主義」の観念のうえにたって、自衛隊の「国際協力」の契機を強調することにより、冷戦終結後の自衛隊の生き残りと発展が図られることになった。湾岸戦争を経過するなかで、自衛隊の存在そのものを違憲とする考え方が急速に弱まった。「平和維持活動」の名のもとに、自衛隊の海外派遣も許されるという見方が浸透しはじめた。個別的自衛権という憲法上の枠を超えて、集団的安全体制に加わること、さらには他国との軍事協力を行って自国を防衛することを是認する集団的自衛権へと、「自衛」観念を変質させようとする動きがきわめて活発になった。2003年のイラク戦争後、日本はイラク復興支援特別措置法を成立させ、米軍の支援・イラクの戦後復興を目的として自衛隊をイラクに派遣している(地上部隊は2004年から2006年まで)。イラク戦争はいちおうの終結をみているが、その後もテロ行為が多発、戦闘状態が続いており、そうした外国領土における自衛隊の本格的活動は初めてのことである。
これは、「国連中心主義」を梃子(てこ)とした憲法9条および軍事政策の変質の流れであるが、この流れと並行した形で日米安保条約を梃子とした防衛領域の変革が行われつつある。アメリカは冷戦後の世界戦略体系の立て直しをするなかで、ヨーロッパにおける北大西洋条約機構(NATO(ナトー))新戦略に対応して、日米軍事同盟を持ち込もうとしており、その布石として1996年(平成8)4月以降、安保「再定義」、ガイドライン見直しなどの新しい課題を日本側に提示している。日本側には旧来から固有の防衛増強論があり、またアメリカからのこうした「外圧」に喜んで応じようとする勢力もあるが、他方、この路線を直進すればアジア諸国から激しい反発があるのは必然であるから、日本の支配体制としてはその間の調整をどう図るかという、たいへん困難な岐路に当面しつつある。
「経済大国」になりおおせた日本は、今後は国際関係にあって「政治大国」として認知され、そう振舞うべきだと言われ続けてきた。国連安保理事会への「常任理事国入り」はそうした念願の現れの一つであるが、この問題は国連そのものの改革と無関係には論じえないものがあり、そしてまた、国連改革問題は気の遠くなるほどたくさんの論点を含んでいるから、日本だけが「大国化」の証(あかし)として「常任理事国入り」を求めても、そう簡単にはいくまい、と観測される。この方面には、「従軍慰安婦」問題に象徴されるような戦争責任、戦後処理の「し残した課題(unfinished businesses)」など、いまになってなお諸外国から解決を迫られる問題を日本は抱えもっている。こうした問題状況に誠実に対応することは、日本の「大国」要件とまったくかかわりなく、「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」という憲法前文が掲げる悲願にこたえるために、ぜひ必要なことであろう。
[奥平康弘]
対中国関係
対米従属あるいは日米協調の路線を基軸に、日本は国際社会へ徐々に展開し始めた。処理しなければならない課題は山積していたが、なかでも重要なのは中国との関係であった。サンフランシスコ体制は、「二つの中国」のうち台湾(中華民国政府)を選択し、本土の中国(中華人民共和国政府)を切り捨てて成立した。日本支配層のなかには、その後も根強く台湾派が有力であり続けるが、これは押し付けられた選択であった。1950年代には日中双方の民間貿易団体により貿易協定が結ばれ、それが何度か更新される「積み上げ」方式で、平和共存の原則に基づく日中の正常化の道が模索された。一時、台湾派の岸信介が首相であった際(1958、昭和33)に、日中関係が全面中断するという不幸な事態を招来したが、1962年高碕(たかさき)達之助・廖承志(りょうしょうし/リャオチョンチー)の間で「日中貿易に関する覚書」が締結され、「政経分離」原則のもと交流が再開された。正常化に「前向きの姿勢」をとらなかった佐藤栄作政権の時代に若干の揺れがあったが、1970年秋にはカナダ、イタリアその他日本以外の諸国が相次いで中国との関係の修復を済ませてしまったこともあって、日本国内でもなんとかしないわけにはゆかなくなる。経済界でさえ国交回復を要求する声が有力となった。佐藤首相一流の「待ちの政治」で無為に過ごすうちに、1971年7月15日、ニクソン大統領が全米向けテレビ放送で中国訪問計画を発表した。キッシンジャー補佐官が秘密裏に交渉してつくられた計画だが、日本政府はこの間の情報をまったく与えられていなかった。日本にとって寝耳に水の、アメリカの動きを(第一次)「ニクソン・ショック」という。1972年2月、ニクソンの訪中があったのち、その年9月下旬、田中角栄首相が訪中、周恩来と「復交三原則」を含む共同声明を行い、ここで初めて両国国交が正常化することになった。1974年に入ると実務協定が次々に締結され、平和友好条約の交渉に入る。当時のソ連を刺激する「反覇権条項」で交渉は難航するが、1978年8月なかば、福田赳夫(たけお)首相の時点でようやく日中平和友好条約が調印された。この条約の締結によって、日本の国際的な位置――日中協調、日米連携およびソ連との間のある種の対抗関係――はほぼ確立した。
その後の日中関係は概していって円滑で、たとえば1988年(昭和63)には両国貿易が往復194億ドルとなって史上最高を記録した。ところがその翌年の1989年(平成1)6月、北京で生じた天安門事件(第二次)のショックは両国間の関係にきわめて深刻な影響を与え、以来冷却の一途をたどることになった。1994年から1996年にかけて中国が行った核実験は被爆国日本の人々の感情を著しく刺激したし、1995年から1996年にかけて台湾周辺で行われた軍事演習は「中国脅威」論を触発した。他方、中国側から日本の動きを見れば、日本の政治家がたび重なる戦争責任を否定する発言を行い、藤岡信勝(ふじおかのぶかつ)らの「自由主義史観」が横行するなど、もともと底流にある反日感情を逆なでするイデオロギー状況があり、そこへもってきて湾岸戦争以降の日本の防衛政策の新展開、1996年以降の日米安保「再定義」による日本軍事力の機能変化の試みなど、「日本軍事大国化」論を助長する動きがあるのを、軽視するわけにはいくまい。さらに日中間には東シナ海の海中ガス田に絡む国境問題が発生している。2001年以来、毎年行った小泉純一郎首相の靖国神社参拝に中国が激しく反発し、日中間での首脳の相互訪問がとだえてしまった。2005年には中国各地で反日デモがおこるなど、日中間は冷却の一途をたどった。2006年10月、安倍晋三(しんぞう)首相は初外遊に中国を訪れ、久しぶりの日中首脳会談が行われた。福田康夫首相も2007年12月に中国を訪れ、胡錦濤(こきんとう/フーチンタオ)主席らと会談、2008年5月には胡主席の訪日もあり、日中関係は回復基調にある。両国関係の修復のためには何が必要かは、それ自体論議が分かれるだろうが、それは日本にとって緊急の課題であるのは確かである。
[奥平康弘]
対ソ・対ロ関係
日ソ国交回復は、片面講和後の1953年(昭和28)8月、当時のソ連首相マレンコフが日ソ関係の正常化が必要であると示唆したのを機縁に、急速に気運が高まった。1955年6月、日ソ交渉はロンドンで始められた。翌年夏、重光葵(しげみつまもる)外相に続いて鳩山(はとやま)一郎首相が訪ソし、「アデナウアー」方式――講和条約によらない戦争状態の終結措置をとること、つまり領土問題を棚上げにして国交回復する方式――をとって、日ソ共同宣言の合意をみた。日本人俘虜(ふりょ)、北洋漁業、日本の国連加盟など交渉すべき事項があったが、なかんずく問題なのは領土問題であった。これより先、アメリカは、ソ連を対日講和に参加させる可能性を見込んで、サンフランシスコ講和条約では日本に「千島列島」をサハリン(樺太(からふと))やその周辺の島々とともに「放棄」させていた。日本側は、歯舞(はぼまい)諸島(歯舞群島)および色丹(しこたん)島は歴史的に日本の領土であるという立場をとり、交渉過程のある時点ではソ連代表はこれら「小千島列島」を返還してもいいという態度を示したこともあった。しかし、その後、日本政府は、「南千島」とよばれてきた国後(くなしり)、択捉(えとろふ)両島も「千島列島」には入らないという見解を打ち出した。これによりソ連は態度を硬化し「『領土問題』は解決ずみ」という態度を一貫して譲らず、歯舞、色丹の引き渡しも、日本からの外国軍(米軍)が撤退しない限りは認めない立場を堅持することになり、これに関する限りはその後もなんら進展をみせていない。「千島列島」を「放棄」させたのもアメリカなら、「千島列島」の自主的解決のいかんによってはサンフランシスコ条約と抵触することあるべしと警告を発して、日本の自主外交路線に牽制(けんせい)球を投げたのもアメリカであった。アメリカからみれば、日ソ両国が領土「問題」を抱え持ち、ある種の緊張関係にあるほうが望ましい。下手な「問題」解決は、まだアメリカの手中にあった沖縄のみならず、日本全域に配置されている軍事施設への重大な変更をもたらしかねなかった。逆にソ連はこれを、日本を対米従属から非同盟中立へ引き込むための手段としてとらえた。しかもソ連にとってみれば日本の北方領土問題は、ソ連がヨーロッパ各地に残している「領土問題」と連動する性質のものであって、それだけ切り離して特別扱いしにくい面があった(そしてこれは、現在のロシア連邦も引き続き抱えている問題である)。
1960年代に入り日本が経済の高度成長期を迎えると、ソ連を含む海外から資源輸入が必要になり、ソ連もまたシベリア開発に日本の技術協力などが欲しい事情があり、経済面での日ソ関係は緊密になった。1975年(昭和50)ソ連から日本に対して「日ソ善隣友好条約」締結を提案してくる動きがあった。日本側も、たとえば1977~1978年に日中間の平和友好条約締結交渉の際、中ソ対立に巻き込まれないよう、ソ連を刺激しないよう気を遣いながら「反覇権条項」に対処してきた経緯が示すように、ソ連圏との友好関係をもだいじにする「全方位外交」を方針としてきたのであった。ところが1970年代の末になると東西関係が全般的に悪化し、1979年2月ソ連のアフガニスタン侵攻、危機迫る中東地域への肩入れ強化など軍事・外交面の硬化が目だつとともに、アメリカは日本の軍事力増強をますます強く要望してきた。日本国内でも積極的に防衛体制に取り組むべしとする気運が急速に高まった。1980年代に入ると、日本はアメリカと防衛体制を協力しあう「同盟」関係にあるという言明が公然となされ、日本は「西側の一員」だと強調されるようになる。1970年代なかばまで外交政策の基調であった「全方位外交」は捨て去られ、ソ連は潜在敵国視されることになった。1986年1月シェワルナゼ・ソ連外相が来日し、安倍晋太郎(あべしんたろう)外相と会談ののち共同コミュニケが発表された。これによれば、日本にとって最重要課題である領土問題も含め、日ソ平和条約締結の交渉を今後とも継続するとされた。
日ソ関係最大の外交問題である北方領土問題は、1990年代に入ってからの米ソ冷戦体制の終焉(しゅうえん)という大状況の変化によって、その位置づけが大きく変わった。日米にとってロシアはもはや潜在敵国ではなくなったから、北方領土問題が内包した軍事的問題性は大きく影をひそめた。また、ロシアはアメリカおよびEU(ヨーロッパ連合)をはじめとする西側諸国との関係を改善して、悪化する国内経済状況から脱却するのと同じように、日本からの経済援助を引き出し貿易関係を緊密化することに意を用い始めている。こうして1993年(平成5)10月エリツィン大統領訪日から1996年4月の橋本首相の訪ロ、さらに、1997年11月、両国首脳のシベリア・クラスノヤルスクでの非公式会談、1998年4月のエリツィン大統領の訪日などというように両国首脳間の交流のなかで、永年の懸案である領土問題解決を内容とする日ロ平和条約の締結の機が熟しつつある、と期待されている。エリツィンのあとを継いだプーチン大統領も2005年11月に来日し、日ロ間の友好関係を強調したが、領土問題については進展がないままであった。
[奥平康弘]
対韓関係
韓国が日本にいちばん近い外国であるには違いないが、その国交関係はなかなかむずかしい。韓国が旧日本帝国の植民地であったという歴史的事実、そこからくるさまざまな問題について両国民の認識の仕方に大きなギャップがある。加えて、韓国は朝鮮半島の北半分を占める北朝鮮ときわめて特殊な関係にたっており、それは朝鮮民族固有の問題であると同時に、米中ロ国際関係そのものに左右される性格をもつ。
日韓両国は当初から波瀾(はらん)含みの緊張関係にあった。1952年(昭和27)1月、韓国は「海洋主権宣言」を行って李承晩(りしょうばん/イスンマン)ラインを敷いた。公海上に韓国の主権を唱え、その水域に立ち入った日本漁船を頻繁に拿捕(だほ)した。アメリカの仲介で日韓の正式会談がもたれたものの、李承晩ライン、対日請求権、在日朝鮮人の法的地位など山積する問題のどれひとつもらちがあかず、交渉の成果は実らなかった。やがて、韓国では軍事クーデターにより朴正煕(ぼくせいき/パクチョンヒ)政権が誕生し(1961年5月)、この時点から両国関係改善の兆しがほのみえてくる。1961年秋、大平正芳(まさよし)外相と金鍾泌(きんしょうひつ/キムジョンピル)(1926―2018)中央情報部長との会談の結果、最大の難問の一つ、請求権問題が日本側の5億ドルの経済協力という形でいちおうけりがつけられる見込みとなった。けれども日韓交渉に対する韓国国民の反対運動は激しく、1965年6月「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」が東京で調印され、同年末ソウルで批准書が交換されて国交正常化の緒につくまでの道のりは坦々(たんたん)たるものではなかった。この基本条約とともに、漁業協定および在日韓国人の法的地位と待遇に関する協定が取り結ばれた。前者により李ラインは最終的に撤廃された。けれども、在日韓国人の法的地位を例にとってみても、この協定で解決されたのは永住権関係のほんの一部であって、差別問題はいっこうにかたづけられていないと批判が絶えない。外国人一般に対する指紋押捺(おうなつ)の強制、外国人登録証明書の常時携帯義務などの外国人法制問題は、氷山の一角である(指紋押捺制度については、1999年に全廃された)。
1973年(昭和48)8月、金大中(きんだいちゅう/キムデジュン)が東京のホテルから誘拐された事件から始まり、1982年6月まず中国が提起した日本の学校用教科書問題の韓国での論議、そのほか日韓関係修復のための経済協力要請問題、日本と北朝鮮との国交修復問題など、論議の対象は尽きることがない。1983年1月、中曽根首相が訪韓し、これにこたえて翌1984年9月、全斗煥(ぜんとかん/チョンドファン)大統領が訪日した。韓国大統領の史上初めての訪日は、天皇の「おことば」のなかでどんな表現の「おわび」を挿入して植民地時代からのしこりをなくすか苦慮したことに象徴されるように、「日韓成熟」の新時代を画そうとするねらいが込められていた。
1990年(平成2)5月、盧泰愚(ろたいぐ/ノテウ)大統領の訪日があった。それがきっかけになってあらためて日韓両国にまたがる「し残した課題(unfinished businesses)」がいくつもあることが露呈した。在日韓国人処遇問題(指紋押捺、外国人登録証常時携帯など)、日本側の韓国植民地化に対する正式謝罪の欠如(盧大統領訪日時の天皇の「おことば」――過去の「不幸な時期」についての「痛恨の念を禁じえません」)、戦後賠償その他の戦争責任の処理などである。また湾岸戦争に伴う日本防衛政策の新展開は「軍事大国化」の現れだとする批判も誘発した。1997年に入って韓国・朝鮮人元慰安婦への賠償問題がいちだんと深刻化する一方で、懸案であった日韓新漁業協定づくりが頓挫(とんざ)し、現漁業協定は日本側の一方的通告で破棄されるという事態となった。韓国の経済は1990年代に入りかけるころから徐々に悪化しはじめていたが、1997年ごろには危機はいっそう深刻なものになった。IMF(国際通貨基金)と日米を含む先進7か国による100億ドルの前倒し支援がその年末に決定された。
しかし、1997年12月に行われた大統領選挙で悲劇的な政治家であった金大中がみごと当選を果たし、翌年2月の大統領就任とともに新しい政治の幕が切って落とされ、日韓関係は新時代を迎えた。1998年(平成10)10月上旬、金大中大統領は日本を訪問した。これを契機に永年山積したまま緊張要因であり続けた、数々の歴史的諸問題の解決への糸口が見つけられると期待される。2002年には日本と韓国がサッカーのワールドカップを共催しており、こうした共同作業の成功を通じて、両国の関係改善に役立てようという声が強い。金大中のあとを受けて大統領となった盧武鉉(ノムヒョン)は歴史問題を大きくとりあげ、日本の植民地時代の親日行為を究明するなど、日本に厳しい態度を示した。小泉純一郎首相の靖国神社参拝、竹島問題、従軍慰安婦問題などが絡み、日韓関係は冷却化した。しかし、2008年に就任した李明博(イミョンバク)大統領は、冷えきった日韓関係を修復する意向を示している。
日本は、朝鮮半島のうち韓国とだけ国交の正常化を図ってきているが、これは一種の外圧のしからしむるところである。日本からみれば、北朝鮮を含む朝鮮半島全体の平和と安定こそが望ましいのであって、そのためには北朝鮮との国交関係を改善することもまた重要な課題である。歴代政府は、アメリカや韓国の顔色をうかがいながら、民間あるいは野党が行いつつある諸交流を慎重に見守ってきたといえよう。
米ロの軍事的な対立関係が急速に消失していくなかで、本来は北朝鮮が与える軍事的な脅威もまた大きく後退するやに思えるのだが、1993年には、北朝鮮が核兵器を開発していてそれは日本国に向けて装置されているらしい、という「核疑惑」が広く喧伝(けんでん)された(2002年10月、北朝鮮は核兵器の開発計画があったことを認めている)。「疑惑」は絶妙な効果を生み、日米安保「再定義」への世論づくりに役だった。北朝鮮は、1990年代に入ってからの農業不振に由来したきわめて深刻な食糧危機に見舞われていて、日本からの食糧援助も大いに望まれている。日本では北朝鮮に対する援助に絡めて、日本人拉致事件(らちじけん)に対し北朝鮮政府が前向きに対応することを条件にすべきだという政治論が主張され、日本の対北朝鮮政策は国際的に評判がよくなかった。こうした評価と別に、日米安保「再定義」が北朝鮮の「脅威」と深く結合している事実とを加味すれば、日朝関係は日韓問題と違った意味で、なかなかに難しいことだというのが実感される。そうしたなか1998年9月下旬、北朝鮮が日本海および日本本土を越えた太平洋海域に破片を落下させる方法で、ミサイル(テポドン)を発射させたという情報が伝えられた。このミサイル発射は、後に、人工衛星の打ち上げ(あるいはその失敗)であった、とアメリカや韓国では観測されているが、日本では、軍事ミサイルも平和目的の人工衛星も、日本の防衛にとってはどちらも同じように危険だという政策判断がとられており、日朝関係は、その改善がきわめてむずかしい状況が続きそうであった。しかし、2002年(平成14)9月、日本の首相小泉純一郎と北朝鮮の最高指導者金正日(きんしょうにち/キムジョンイル)による日朝首脳会談が行われ、両首脳は、日朝の国交正常化交渉を進める、北朝鮮によるミサイル発射実験の凍結期間を延長する、などを内容とする日朝平壌(ピョンヤン)宣言に署名した。また、同時に北朝鮮によって拉致された日本人の生死に関する情報が提示され、同年10月、事件被害者のうち5人が日本へ帰国した。その後2004年5月に小泉は再度訪朝、金正日との会談において日朝双方の日朝平壌宣言の履行などを確認。また拉致事件被害者の家族8人のうちの5人の日本帰国が実現した。
[奥平康弘]
対米関係
日本の外交政策は、少なくともこれまでは、対米関係を基軸とし、これに規定されて展開してきた。その日米関係であるが、1950年代(昭和25~34)まではアメリカのほぼ一方的なイニシアティブのもとで形成されたものであった。日本は、そのもとで戦後復興、自立化、発展の基盤づくりの諸過程を経て、1956年(昭和31)12月国際連合への加入が認められ、ようやく国際社会への復帰を達成するめどがつけられた。1960年代に入ると日本は、高度成長期を迎え、急速な経済発展を遂げることになる。それにつれ、日米安全保障体制を中心とする日米関係において、イコール・パートナーシップを求める動きが日本支配層のなかに出てきた。こうして1961年箱根で第1回日米貿易経済合同委員会が開かれた。1964年には日本はIMF8条国に移行し、翌年には日本の対米貿易が黒字に転ずるが、この時期には、対米輸出品目が従来の軽工業製品からしだいに鉄鋼、テレビ、自動車などに転換しており、アメリカ市場への影響が広がり始める。1960年代後半には沖縄返還問題と日本経済自由化の2点が重要になる。日本では「核抜き本土なみ」返還と表現したものの、沖縄返還に伴う日米間の会談では、「韓国条項」(在韓米軍を有事の際日本が援助すること)の承認、事前協議制の弾力的な運用(核兵器に関する合意)が図られ、その結果、日本は日本国土のみならずアジア全体の防衛体系にコミットすることになった。安全保障に関し日米の相互依存がより強められた。
次に経済の自由化問題がある。国家的な保護育成のもとに成長した日本産業は総じて国際的競争力に著しく欠けていた。アメリカの自由化要求を「第二の黒船」と称し、それへの対応をできるだけ遅らせ、時間を稼いで、その間に、産業構造の高度化、近代化を実行し国際競争力をつけようとした。アメリカはベトナム戦争が泥沼化し通貨が不安定となるなどして、1960年代後半には国際収支が悪化した。保護主義をとり続ける日本に対してアメリカからの批判が日増しに増大する。資本の自由化をめぐる対立も似たような状況にあった。1969年(昭和44)から約2年間もの間、毛・化合繊の輸出自主規制をめぐって日米紛争が続いたが、似たような貿易摩擦が1970年代に入ると、自動車、電子産業を含む工業部門全般、さらにはサービス業、農業というように各分野にまたがるようになる。日米両国は、それぞれ国内の産業界と政界の利害関係をにらみながら、貿易、通商にかかわる外交を処理しなければならなかった。双方意味合いがすこしずつ違うが、両国の相互依存度が深まることにより、内政と外交との微妙な調整を図ることがますます必要になった。
1970年代初め、日本は二つのニクソン・ショックにみまわれ、改めて日米間の距離を思い知らされた。第一のショックは、1971年7月なかば、日本政府に事前通知なしにニクソンの訪中計画が決定され、米中関係に大きな変革がありうることがわかった。第二のショックは、その1か月後、8月なかばに発表された新経済政策である。ニクソン大統領は金・ドルの交換を停止する緊急対策を発表、これにより事実上ドル切下げを断行した。日本はこの結果膨大なドルを買い支えねばならなくなり、一時はインフレが深刻化した。1973年(昭和48)10月には、日本は国際関係においてもう一つ大きなショックを受け止めなければならなかった。第四次中東戦争をきっかけとする石油ショックである。中東の石油エネルギーに完全に依存する日本は、アラブ諸国と取引して生き延びるほかないと判断し、政府は戦後初めて自主外交らしい路線をとって中東政策の転換を行い、アメリカとは違って、アラブ支持を明確にした。日本は、中東向け経済援助に力を入れると同時に、石油危機の衝撃を経済政策、産業政策のうえでどう緩和し、あわせて石油供給の安定化をどう図ってゆくかに腐心することになる。このころから、日本の外交は対米向けの二国間レベルから、ようやく西ヨーロッパ主要国や中東を含む多元的なものへと転換するようになった。1975年11月ランブイエで開かれた第1回主要先進国首脳会議(いわゆるサミット)に仲間入りしたのは、その一つの現れである。
こうして日本外交の多極化現象がみられるとともに、予想以上に無難に石油危機を乗り越え、安定成長への道を確実にし始めた「経済大国」日本は、アジア、アフリカなど発展途上国への経済援助の量的拡大と質的転換を期待されるに至った。対中国、対ソ連との関係修復を課題としていた1970年代中葉においては、対米追随を基調としながらも、ともかくも全方位外交、等距離外交が国是であった。しかるに、1979年末、イランの政変、ソ連のアフガニスタン侵攻、米ソ対立の激化と続く国際情勢の展開は、一挙に従来の外交路線を変更し、明確に西側先進諸国と歩調をあわせて、ソ連と対決する姿勢をとらしめることになった。アメリカは貿易摩擦を切り札に使いながら、日本に対する防衛力増強をますます強く要望するようになった。「経済大国」になりおおせたというので、日本国民の間にも応分の軍備は当然と考える層が増えたこともあって、アメリカのこの方面の要求は増大し、かつ成功を収めた。とくに1982年(昭和57)11月成立した中曽根康弘政権のもとで、日米関係は「ロン・ヤス関係」という名称で象徴されるように、レーガン大統領と中曽根首相の個人的な信頼関係、イコール・パートナーシップが強調されるなかで、武器輸出禁止三原則の例外扱いによる対米武器供与、財政縮減と逆行した防衛費の突出増額、SDI(戦略防衛構想)への積極的な参加などが進展した。「日米新時代」といわれながらも、アメリカの戦略体系に規定されている基本的な枠組みには、50年間本質的な変更はみられなかったといえる。
第二次世界大戦後の日本の「国のかたち」のできあがり方から見て、アメリカが「日本外交の基軸」であり、かつ、そうであり続けるだろうということは疑いえない。しかし、1990年代に入ってから時々刻々、「日本外交の基軸」たる意味合いが変わってきている。その要因の一つは、米ソ冷戦体制の終焉(しゅうえん)とそれに伴う国際関係の激変という、日米間の環境変化である。そしてもう一つの要因は、1980年代にアメリカが景気後退したのに対し日本が順調に高度成長を続け、「21世紀は日本の世紀」といわんばかりの勢いがあったのが、1990年代中葉に至ってバブル崩壊に見舞われ青息吐息の状態となったのに対し、逆にアメリカはかつてない好景気を経験しはじめたという、経済関係の激しい動きがある。
日米安保は、東欧社会主義諸国の頂点に立つソ連を「仮想敵国」としていたのに、冷戦体制の終焉はその「仮想敵国」を亡きものにしてしまった。アメリカは世界戦略を根底から組み直すほかなかった。1990年夏の湾岸危機、1991年初めの湾岸戦争への発展は、アメリカの軍事戦略を立て直す好機であった。アメリカは国連安保理事会を媒介として世界秩序の支配権を維持しようと図った。日本にも、国連中心の安全保障体制への参加をもとめた。アメリカはしかし、日本と違って国連中心主義のような理念も幻想ももっておらず、新戦略はヨーロッパ方面ではむしろ北大西洋条約機構(NATO(ナトー))を軸とする軍事政策に置かれ、それとあわせたアジア方面での新戦略の一環として、日米安保の再利用を確認する安保「再定義」を位置づけた。アメリカは日本の相応の軍事協力を「後方支援」という名目で引き出すとともに、「極東」という地理的な制約を超えて、状況と必要に応じて概念づけられる「周辺事態」を場として日本軍の協力を獲得することを約束させようとしている。2003年のイラク戦争をめぐる日米の対応はまさにその象徴ということができるかもしれない。安保領域で残る最大の問題はいかにして、またいかなる論理をもって沖縄の在日米軍基地を確保するかという点をめぐってくすぶっている。アメリカからすれば、沖縄に軍事基地が集中しているという既成事実のうえに乗っかっていればいいのであるが、いつかやがて、なぜそれが既成事実なのかをきちんと論理化する必要が出てくるかもしれない。
日本がバブル経済を一方的に享受していたときには、日米間の経済摩擦が目だち、それが両国間の関係のありようをぎくしゃくさせもした。けれども、バブル崩壊後日本金融界が経験しているビッグバンが、アメリカ金融資本支配下での再編成になりつつある状況に象徴されるように、日本はアメリカの利益と矛盾対立しない日本経済の再建を模索しつつあるように、少なくとも現在はみえる。その限りで日米関係は当分のあいだ安定しているといえるかもしれない。
[奥平康弘]
防衛
自衛隊の概要
自衛隊は、陸上、海上および航空の三つから構成されている。陸上自衛隊は、定員18万人、予備自衛官4万3600人、編成は全国5個方面隊に分けられ、12個普通科(歩兵)師団、1個機甲師団、2個混成団、4個特科(砲兵)群、8個高射特科(対空ミサイル)群、1個空挺(くうてい)団、1個戦車群、1個ヘリコプター団となっている。戦車1100両、装甲車730両に、対戦車ミサイル発射機を含む多種の火砲や対戦車ヘリコプター86機などヘリコプターを中心に489機などが主要装備とされる。海上自衛隊は、定員4万5752人、予備自衛官定員1100人、主要装備は護衛艦58隻(18万1000トン)、潜水艦16隻(3万7000トン)など就役艦156隻(34万9000トン)、それにP-3C哨戒機(しょうかいき)99機、哨戒ヘリコプター100機など計209機となっている。航空自衛隊のほうは、定員4万7207人、予備自衛官定員800人、主要装備は迎撃戦闘機F-15が190機、F-4EJが112機、そのほか、対地支援戦闘機、早期警戒機など計155機からなる(以上、1997年6月30日現在)。これを国防費支出の点からみれば、1996年および1997年それぞれの防衛費総額は4兆8455億円および4兆9414億円(うち、装備品購入額が9157億円と8347億円、研究・開発費が1496億円と1605億円)で、対GNP(国民総生産)比ではそれぞれ0.98%と0.96%となっている。防衛費については政府は、1970年代初めに「防衛費はGNPの1%以下」と現状を説明していたし、1976年(昭和51)11月、三木内閣のとき「当面、国民総生産の100分の1に相当する額を超えない」と閣議決定した。しかしその後、GNP上昇率が鈍化し、かつ人件費・兵役の単価が上昇したこともあって、1980年代には防衛費の比率が高くなり、ついに1987年度予算では1.004%と1%枠を超え、論議をよんだ。これ以降はGNPの伸びに支えられて、かろうじて1%枠が守られている。
[奥平康弘]
自衛隊の成長過程
現在の自衛隊は1954年自衛隊法に基づき成立したが、1952年の保安隊、さらには占領体制下の1950年マッカーサー総司令部の指令により創設された警察予備隊にさかのぼる。「軍隊」でも「戦力」でもなく単なる「警察力」であるから憲法第9条には違反しない、という理由で誕生した警察予備隊が、その後約50年、漸増を重ねて今日に至っている。しかし、警察予備隊、保安隊、そして自衛隊と発展していく全過程で、憲法9条に基づく憲法論議がついてまわった。憲法9条は第1項で戦争を放棄し、第2項で「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めている。「自衛隊」等は、この憲法が禁ずる「戦力」に該当するのではないか、という疑いが生ずるのは当然である。政府および支配政党は次のような憲法解釈によって自衛隊は憲法で禁ずる「戦力」にあたらず、したがって合憲だと主張してきている。すなわち、どんな国家も急迫不正の外敵がその国土を侵害してきた際には、その外敵を国土の外に追い出し自国を守る権利があるはずである。これを(個別的)自衛権という。これはどんな国家にも自然的に備わっている権力であるから、日本国憲法もこうした意味の自衛権を否定してはいない。そして、自衛権がある以上はこれを現実に行使するに必要な実力(装置)もまた憲法上否定されていないのである。日本国が設けている自衛隊は、この「自衛のために必要な最小限度の実力」であるから、「戦力」ではない――これが政府の自衛隊合憲解釈のすべてである。
この憲法解釈がそれ自体として説得力を備えているかどうかは大いに議論が分かれるところであるが、ともかくも実際の世界では自衛隊が創設され増強し、災害出動、日米軍事訓練などにおいて機能し、厳然として存在し続けている。国民の圧倒的多数は、この存在を既成事実として受容している。このような国民世論の動向にあわせて、その創設時から長い間自衛隊違憲論を唱えてきて有力な政治団体であった日本社会党が、1983年に「違憲だが合法的な存在だ」という妥協的な解釈を打ち出して、自衛隊肯定論へ傾斜する第一歩を踏んだ。
1989年(平成1)から始まる米ソ冷戦構造の変質は、アメリカの世界戦略下にある自衛隊にとっての「仮想敵国」の消失を意味するから、自衛隊の存在意義を揺るがすかもしれない環境変化であったはずである。けれども、自衛隊の存続にとって幸運なことは、1990年夏、ペルシア湾岸危機が生じ、翌年1月には湾岸戦争へと展開するという国際的緊張状況が生じたことである。日本政府は、アメリカが主導権をにぎる国連安全保障体制へ自衛隊を参加させ、これによって一方では自衛隊の生き残りを図り、他方では自衛隊の国際的な認知を勝ち得ようと考えた。「『大国』にふさわしい『国際協力を』」という謳(うた)い文句がはやりにはやったが、その合意の重要要素には自衛隊の「国際協力」、すなわち「海外派遣」への期待がこめられていた。政府はこの好機にのって自衛隊の海外派遣を実行したかったが、この企ての足を引っ張ったのが、その政府が拠(よ)ってたってきた自衛隊合憲論そのものであった。政府は既述のように、もっぱら個別的自衛権に基づいて自衛隊の合憲性を説明してきたのであるが、個別的自衛権論によれば、自衛隊の目的および働きは日本本土のみに限られ、自衛隊の海外出動はありえないこととされてきたのである。政府は湾岸戦争をにらみながら、今後の自衛隊の「活性化」を図るためには、いまでは自衛隊を制約する論理となってしまった個別的自衛権論と、「国際協力」の契機とをうまい具合に折り合いづけなければならなくなった(政府は1990年、湾岸危機に応じていち早く国連平和協力法案を提出して、自衛隊の多国籍軍参加を目論(もくろ)んだが、世論の反対が強く、その年11月に同法案は廃案となった)。「武力の行使」たる軍事活動と区別して「国連平和維持活動および人道的な国際救援活動」(PKO活動)というコンセプトを設置し、こうした活動に従事する目的の自衛隊海外派遣に法的根拠を与えたのが、1992年に制定された「国際平和協力法」である。この法律のもとで自衛隊員が「平和協力隊員」として海外に派遣された例は、1997年1月現在で4件、通算期間3年8か月、延べ派遣人数1851人、支援隊員を含めると約2600人に達する。
自衛隊員の多国籍軍参加を容認した国連平和協力法案(1990年)に抵抗してこれを廃案に追い込むのにあずかって力があった社会党は、その直後の参院選挙で惨敗したのち、1993年8月成立の細川連立政権へ参加して自衛隊と日米安保の現状を追認する立場を明らかにした。1994年7月には「非武装中立は歴史的役割を終えた」と宣言した。こうしていまや自衛隊の存在そのものに憲法上の疑惑をもつ政治勢力は、日本共産党、新社会党など寥々(りょうりょう)たるものになった。
比較的最近、各地における民族対立や権力争いに伴う紛争から生ずる危険を避けるために、自国民を脱出避難させる軍事介入が目だつようになった。日本でも1997年7月に起こったカンボジアでの武力衝突に際し、橋本首相(当時)は航空自衛隊のC-130輸送機3機をタイへ派遣して待機させた。しかし、民間機利用が可能であったため、このせっかくの措置は無用の空振りに終わった。さらに1998年5月のインドネシアでの治安情勢に際して政府は自衛隊機C-130輸送機6機と海上保安庁巡視船2隻をシンガポールに向け出発させたが、このときも救出作業を行うことなく無為のうちに撤退を余儀なくされている。いったい、自衛隊機の「邦人救出」のための海外活動はいかなる場合、いかなる手段に基づいて行われるべきか法的規定があいまいで、カンボジア危機とインドネシア危機の二度にわたる出動例は法的にも政策的にも疑問が多い。政府はなにがなんでも自衛隊の「出番探し」をしているのではないかと批判される余地がある(なお、「邦人救出」のための艦艇派遣については法的規定がない。今後のことに備えて、法律上の根拠を与えるべきだという議論が保守陣営に強い)。
[奥平康弘]
旧日本帝国軍隊の特質
明治維新とともに成立した近代日本は、富国強兵をスローガンに掲げた。まず1873年(明治6)1月全国募兵の詔書が出され、ついで徴兵令が制定された(1889年1月には徴兵令が改正され、国民〔男子〕皆兵制の採用が明確化された)。当時なお国内には士族反乱が絶えなかったので、軍隊はその鎮圧にあたったが、その一方で早くも1879年以降、朝鮮、清(しん)国と二度にわたる京城事変で事を構えるなど、大陸作戦を準備した。こうして対外的武力としての海軍の整備にも意を用いるようになった。陸海軍軍備がいちおうできあがったところで、1894年7月、日清戦争が起こされ、さらにその10年後の1904年2月、飛躍的に充実した軍備を背景に、日露戦争が生じた。両戦役に勝利した日本軍隊は、次に南満州の利権で対立関係にたつアメリカを仮想敵国とし、これと対抗しうる海軍力をもとうとアメリカとの間で激烈な建艦競争を行うことになる。なかでも第一次世界大戦中の海軍費の増大は目覚ましく、1921年(大正10)の場合には国家予算の32%にも達した。同年11月から翌年にかけワシントン海軍軍縮会議が開かれ、日本が相当に譲歩して建造費縮減に同意したのはもっともなことであった。その後しばらくは陸軍も含む軍備縮減が行われたが、1931年(昭和6)9月、一部軍人の計画的挑発を発端とする満州事変以降、軍備は拡張の一途をたどった。軍縮条約にもかかわらず海軍の建艦も急ピッチで進められた。1935年を例にとれば、直接軍事費が国家財政上占める比率が46.1%とたいへん高い。1937年7月7日の盧溝橋(ろこうきょう)事件に始まる日中戦争、そして1941年12月8日の真珠湾「奇襲」攻撃に始まる太平洋戦争へと展開することになる。この間における軍備拡大は膨大なもので、そのために軍需工業拡充五か年計画、重要産業五か年計画などがたてられ、軍需工業動員法が発動され、国家総動員法が適用された。1941年度には陸軍飛行機年産3500機、戦車年産1200台、弾薬年産43師団会戦分の能力があったといわれる。
1945年8月、日本の降伏が決まったとき、陸軍は一般師団169、戦車師団4、飛行師団15、その兵力は約550万であった。海軍は艦艇のほとんどを失い、飛行機、特攻艇と陸上警備部隊で、その兵力約170万。合計すれば720万(うち370万は内地)、たいへんな数である。数だけは膨大だが、当時すでに、軍隊としての実質はまったくなく、崩壊寸前の様相を呈していた。無条件降伏に伴い、1945~1946年にかけて日本軍隊はほぼ完全に解体した。
戦前の日本軍隊は、法制上独特な制度としてつくられていた。まず、陸海軍の編制および常備兵額は天皇が定めるとして、これを天皇大権のもとに置いた(明治憲法12条)。予算は帝国議会の審議するところであったとはいえ、予算が成立しない場合には、政府は前年度の予算を施行すればよろしいという憲法条項(明治憲法71条)があったので、軍事費に対する議会の支配力は弱かった。なによりも問題なのは「統帥権の独立」(明治憲法11条)である。統帥権とは、直接戦闘を目的として、陸海軍を統一し、兵力を発動させる権力のことであって、憲法はこれを天皇直轄としていたのである。いわば軍隊のソフト部分は、帝国議会の関与しえないこととされていたのであった。また、一般臣民の権利自由に関しては「法律」で制限する仕方を定めていたのと対照的に、軍人に対しては「陸海軍ノ法令又ハ紀律」によって例外を設けることが可能であった(明治憲法32条)。さらにまた軍刑法、軍法会議など特別な法体系が用意されており、軍隊・軍人は法的に別世界に置かれていたのである。要するに法制上、帝国軍隊は、内において人権無視の非人間的で独特な階層秩序を構成することが許されただけでなく、外に向かい軍国主義、排外主義、侵略主義の非難を浴びるようなふるまいをする自由を認められていた。
[奥平康弘]
防衛と政策
現在の自衛隊が日本国憲法第9条に違反し、そもそも存立すべきものでないかどうかという憲法論は別として、自衛隊が成長して今日に至る全過程で、シビリアン・コントロール(文民統制)が問題になったのは、軍部独走・独裁についての戦前の苦い経験があるからである。シビリアン・コントロールのうちいちばん強いのは、憲法第9条からくる法的確信である。これを反映する世論があればこそ、国会の統制、防衛省の非制服組官僚の統制、安全保障会議、さらには財務省主計局による防衛省予算原案の査定などがともかくも機能しているのである。現在の自衛隊は、第二次世界大戦前の軍隊と違って、いかなる意味でも自らに特有な法体系をもつことは認められない。軍法会議のような特別裁判所も成立する余地がない。またこれまでの憲法解釈によれば、自衛隊の海外出動はありえず、他国を防衛する集団的自衛権も認められていない。憲法から派生するのか、単なる政策なのか争いがあるが、歴代内閣は非核三原則によって核武装を禁止するとともに、武器輸出三原則をとって武器の対外供与を禁じている(ただし、1983年中曽根内閣は、対米関係においてはこれを例外とした)。
戦前の日本軍隊と現在の自衛隊を画然と区別するもう一つの特徴は、自衛隊がアメリカの防衛戦略の一環として、これと有機的に結合して存在しているという点である。すなわち日本は、アメリカと取り結んでいる安全保障条約により「個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる」(3条)と約束している。条約は日本国の施政下にある領域に加えられた武力攻撃に対して共同防衛する義務を定めているとともに、アメリカの三軍が日本国内で基地を提供されたうえ駐在することを認めている(6条)。在日米軍の総兵力は、陸軍1813人、海軍6780人、海兵隊1万8791人、空軍1万4075人、合計4万1459人である(1997年6月30日現在)。両国の防衛協力に関しての大綱は、1978年11月、日米安全保障協議委員会の了承した「日米防衛協力のための指針」(いわゆるガイドライン)であった。1996年(平成8)4月、日米間に構築されている協力関係を増進するため、「ガイドラインの見直し」が合意された。東西の冷戦終結にもかかわらず、「アジア太平洋地域には潜在的な不安定性と不確実性が依然として存在しており、この地域における平和と安定の維持は日本の安全のためにいっそう重要」であるという理解のもと、新ガイドラインは、次の三つを柱とする協力関係の必要性を打ち出している。(1)平素から行う協力、(2)日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合、(3)日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力、これである。日本側としては、この新指針の内容を詰めながら、これを実効あらしめるための立法措置(周辺事態法)を講ずる必要があるが、その審議過程で日本が期待される協力関係の内容と範囲、そのための手続、周辺事態の定義、武力使用の要件など、憲法9条を踏まえた検討が望まれる。そうでなければ、これをきっかけに集団的自衛権が黙認され自衛隊が変質するばかりでなく、日米安保条約が日米軍事同盟条約へと変容することになってしまう可能性があるからである。
新ガイドライン、周辺事態法の動きと連動して、有事法制論があらためて浮上した。政府は1980年ごろから有事に備えて特別な権力発動を可能とする立法の必要性を説き、その検討を進めてきたが、有事法制は言論統制や国民の各種動員を含みうること、土地その他の財産の特別収用をはじめとした私権の制限、さらには市民生活上の神経にあたる交通や通信などへの特別規制などを内容とする可能性が強い。国民の自由や権利を制限しかねない有事法制であるがゆえに、歴代の政府はその準備を唱えながらも、あえて立法化に着手するのを遠慮してきたのであるが、そんな遠慮などかなぐりすてて、小泉内閣は2003年(平成15)~2004年にかけて立法化した。しかし、その前提条件である、日本国を「有事」に追い込むような外敵の侵入はいったい本当に想定しうるのか、想定しなければならないのか。
海上・航空の共同訓練に加え、1981年から陸上自衛隊によるものも開始された。1980年以来の海上自衛隊のリムパック(環太平洋合同演習)参加をはじめ、シーレーン防衛ということが強調され、「日本列島不沈空母」論、「四海峡封鎖」論などの中曽根発言もあって、この方面における、アメリカ戦略中の日本軍事力の位置がますます重要になりつつある。これにつれ防衛力も着実に増強してきているが、さてこうした変化が、多極的な国際関係において日本が果たすべき役割という、より高次の政策とどうつながるのか、考慮しなければならない大問題である。
[奥平康弘]
経済・産業
総論
はじめに
書籍版『日本大百科全書』に収録するために本項の初稿が執筆されたのは1980年代前半であったが、1980年代末の日本経済はバブルを伴いつつも、世界のトップランナーとして隆盛を極めていた。それに反して、第二次世界大戦後の覇権国家アメリカは、1987年のブラック・マンデーによる株価の暴落と、財政ならびに経常収支のいわゆる双子の赤字、そして産業の空洞化に悩んで低迷していた。それから約10年、日米経済の様相は180度のさま変わりをみせている。アメリカは、長年の懸案であった財政赤字も克服の見通しがたち、株価の目覚ましい上昇にバブルの気配を示しつつも、ハイテクと第三次産業を中心に好況を持続してきた。他方で日本は、1990年代に入ってバブルが崩壊したのち、長期の停滞が持続し、そこからの出口をみいだせないまま深刻な閉塞(へいそく)感に陥っている。しかし、好況の後に不況が訪れ、不況はいずれ好況に転じるのが資本主義経済のならいである。そこで、以下はこうした約10年周期の変動を歴史的叙述の部分以外は捨象して、日本経済の素顔に迫ることにしよう。
[柴垣和夫]
世界経済のなかの日本――「経済大国」の諸相
まず世界全体のGDP(国内総生産)総額に占める主要国(地域)のGDPの割合を1960年(昭和35)、1994年(平成6)についてみると、1960年当時、アメリカは全世界GDPの約3分の1を占めていたのに対して、日本はわずか3%弱で、アメリカの10分の1以下の比重しかなかった。またヨーロッパの主要国、旧西ドイツ、イギリス、フランスのいずれよりも小さかった。ところが1994年には、アメリカの比重が26%に低下したのに対して、日本の比重は18%に上昇し、西欧諸国のいずれをも上回るに至った。この34年間にアメリカの比重は7ポイント低下したが、日本の比重は実に15ポイントの上昇を示したのである。この間の日本の伸張がいかに目覚ましいものであったかがわかる。
以上は国民経済規模での比較だが、国民1人当りGNP(国民総生産)も日本は世界のトップ・レベルに到達した。いまから約30年前、1965年の日本のそれは760ドルでアメリカ(3240ドル)の4分の1以下、旧西ドイツ、フランスの各1620ドル、イギリスの1550ドルと比べても半分以下であった。ところが1995年には3万9640ドルと、イギリス(1万8700ドル)、フランス(2万4990ドル)はもちろん、ドイツ(2万7510ドル)、アメリカ(2万6980ドル)を抜いて、ルクセンブルク(4万1210ドル)、スイス(4万0630ドル)に次ぐ世界第3位に到達した。もっとも1995年の年平均対ドル為替(かわせ)相場は102.9円だったから、前述の3万9640ドルを1998年5月のレート135円で換算すると3万0214ドルに低下する。このように為替レートは近年大幅に変動し、時々のそれが実際の購買力平価を表しているとはいえない。それゆえ、単純な換算による比較は不正確を免れないが、それにしても日本人の「豊かさ」が世界のトップ・レベルに到達していることは確かであろう。
世界のGDPの2割弱を占める日本は、世界貿易においてもほぼ同様の比重を占め、1995年には輸出・輸入額ともにアメリカ、ドイツに次いで第3位の位置にある。30年前の1965年には、輸出・輸入額とも前記の両国のほかイギリス、フランス、カナダを下回る第6位であった。さらに驚異的な事実は、資本輸出国、対外債権国としての地位の急上昇である。日本が資本の輸入国から輸出国に転化したのは、1年間のフロー(一定期間中に動く財貨の総量)では1965年、ストック(残高、資本・財貨などの蓄積量)では1968年のことであったが、以後二度の石油危機による一時的例外期を除く経常収支の黒字基調とその累積を背景に、対外証券投資、借款、直接投資ともどもに急増した。とくに1983年から1984年にかけて、対外資産から対外負債を差し引いた純資産は373億ドルから743億ドルに倍増し、アメリカ、旧西ドイツを抜いてイギリスに次ぐ第2位に躍り出た。その後アメリカが純債務国に転じ、1991年には日本の純資産が3831億ドルに達して世界第1位となり、以後その地位を保持し続けている。経済大国日本は金融大国でもあるのである。
以上は日本経済の国際的地位をマクロ的な数字からみたものであるが、国際的にみた日本経済の特徴は、単に前述の量的比重の高まりだけではない。その質的にみた経済パフォーマンスの好調が注目されなければならない。周知のように、第二次世界大戦後の世界経済は、1950~1960年代の「繁栄」ののち、1970年代に入って国際通貨危機(ニクソン・ショック、1971)、第一次石油危機(1973)といった激しい混乱を経験し、日本もその例外ではなかったが、少なくとも1970年代後半以降1980年代末までは、日本は他の欧米先進諸国に比べて相対的に優れた経済パフォーマンスを実現した。1990年に入って、バブルの崩壊による金融分野(銀行、証券、保険)の不調が現れたが、製造業分野の堅調を基礎として、それは、ME(マイクロエレクトロニクス)革命とよばれる新技術革新による産業構造の省資源・知識集約化、低い失業率のもとでの安定した労使関係と労働生産性の上昇、安定した物価水準、それらを背景とした日本製品の価格・品質両面での強い国際競争力、などに表現された。そこから日本経済に対する高い国際的評価が生まれ、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」(E・ボーゲル、ハーバード大学教授)といった賞賛や、「日本に学べ」といった声が聞かれるようになった。とくに日本経済の活力の源泉と目された「日本的経営」は、国際的注目の的となり、それは経済効率の低さに悩む旧ソ連・中国など社会主義諸国からも注目されたのであった。
しかし、このような日本経済の量質両面における好パフォーマンスが、それに対する高い評価・賞賛と同時に、他面では貿易摩擦をはじめとする激しい国際経済摩擦の原因となり、諸外国による厳しい対日批判・非難を生み出したことも事実であった。自動車、電気・電子機器をはじめとする機械機器を中心とした日本商品の集中豪雨的な輸出は、輸入国における当該産業の不振と失業の増大を生み出し、労使一体となっての対日非難を呼び起こした。累積する日本の貿易・経常収支の黒字は、日本市場の閉鎖性を示すものとしてその赤字国からの非難の対象となり、日本の市場開放への要求を強めると同時に、赤字国での保護貿易主義を台頭させた。さらには、日本商品の強い国際競争力の背後に、欧米諸国と比較しての日本の労働者の長時間労働があることが指摘され、日本人の「働きすぎ」が批判されるに至った。日本経済の強さが生み出したこれらの対外経済摩擦に対して、その対応策として急速に展開したのが対外直接投資、つまり日本企業の海外進出であった。それは1980年代後半に入ってからの為替レートの急激な円高の進行もあって加速された。日本企業の海外での工場立地は、これまでのところ現地の雇用を拡大するものとして歓迎されているが、それは同時に「日本的経営」の国際的適応能力、あるいはその国際的適用可能性が問われることでもあった。日本企業の多国籍化とそこから発生する諸問題への取り組みは、21世紀においても日本経済の重要課題の一つとなり続けるであろう。
以上は主として欧米先進諸国との関係にかかわる問題であるが、世界にはいまなお飢餓線上にある最貧国をはじめとする数多くの開発途上諸国が存在する。「経済大国」日本にとって、これら途上諸国との経済協力の必要はますます大きくなりつつあり、事実その量的規模は急伸しているが、その効果については問題が多い。従来の大型経済開発プロジェクト中心のそれは、フィリピンの旧マルコス政権下のケースにみられたような腐敗の温床となる危険があり、民衆の目には日本の経済的帝国主義の復活と映る場合もある。日本が先進国でありながら「アジアの一員」を自負するからには、途上諸国の現実に密着した、そして経済開発だけでなく、教育・文化・保健・医療といった幅広い長期的視野にたった経済協力のあり方が追求される必要があるであろう。同時に、韓国、台湾など、1970年代後半以降途上国の域を脱してNIES(ニーズ)(新興工業地域)として登場してきた諸国(地域)との関係では、工業生産における新しい水平分業に立脚した貿易関係の構築が課題となっている。
目を国内に転じよう。なるほど日本は「経済大国」になり、世界でもトップ・レベルの「豊かな国」になったが、それは主として日本の企業とくに大企業の強さ・豊かさによるものであって、国民生活のレベルでみると欧米諸国に比べてなお多くの立ち遅れが目だっている。欧米諸国から非難されている既述の長時間労働もその一つであり、人々は十分な余暇に支えられたゆとりある生活からほど遠い状態にある。住宅、下水道、公園など生活関連の社会資本もなお劣位にあるし、世界一高い大都市の高地価に災いされて勤労者は遠距離・長時間通勤に悩まされ、それがまた大都市およびその近郊における地域社会の形成と充実を妨げている。日本のサラリーマンに特有の「単身赴任」現象は、教育制度その他によるいろいろな原因があるとはいえ、家庭が「企業の繁栄」の犠牲になっている現れといえなくはない。ジョギングとダイエットの流行は「飽食の時代」を象徴するものではあるが、物質的充足を超えた精神文化の享受という点では、なお改善の余地が大きく存在するのである。
加えて現在の日本は急速に高齢化社会に向かって移行しつつある。保健・医療水準の向上は日本を世界最高の長寿国にしたが、他方における出生率の低下と相まって、人口構成における高齢者の比重は確実に高まりつつあり、2020年には4人に1人が65歳以上となることが予想されている。そこから高齢者の雇用や福祉の問題、年金をはじめとした社会保障費の世代間負担問題など、さまざまな新しい社会問題が生起しつつある。これらの高齢化社会の到来に伴う諸問題は、既述の国民生活の質的充実の課題とともに、21世紀の日本経済の重要課題となるに違いない。
さて、以上では、日本経済が当面するであろう内外両面での諸問題・諸課題を概観したが、以下では、現在に至るまでの日本経済発展の歩みと現状の細部を、もうすこし立ち入って考察することにしよう。
[柴垣和夫]
日本経済の展開過程
日本の封建社会と商品経済
近代資本主義経済の世界史的起源は、いわゆる大航海時代のスペイン、ポルトガル、オランダによる16世紀の世界商業革命にまでさかのぼることができるが、日本の場合もその初発については、西欧諸国にさほど遅れたものではなかった。13世紀の初頭、鎌倉時代に形成された日本の封建社会は、元寇(げんこう)以降早くも緩み始め、南北朝時代、室町幕府、戦国時代と続く動乱のなかで商品経済が急速に発展し、それは定期市(いち)をつくるほどの市場圏を各地に成立させた。また八幡船(ばはんせん)に始まり、勘合貿易、朱印船貿易と展開した貿易は、ヨーロッパ人に伍(ご)して東南アジア各地に日本人町を築くまでに至り、鎖国直前にその規模は華僑(かきょう)をしのぐ勢いであったといわれる。こうした商業・貿易を担う商人層と結び付いて成立した中央集権的な織豊(しょくほう)政権は、ヨーロッパにおける絶対王政に類似した性格の政権だったといえよう。ところが、豊臣(とよとみ)氏の後を継いだ徳川幕府は、一方で参勤交代制や貨幣鋳造権の独占など絶対王政的集権傾向を強めながら、他方では1635年(寛永12)に鎖国を断行、これによって貿易は極度に制限され、日本人の海外進出は阻止されるに至った。その結果、以後200年余にわたり、日本はヨーロッパの商人資本による世界的な商品経済の発展から疎外されることになったのである。
もっとも、鎖国のもとでも国内の商品経済はそれなりに発展し、年貢米や各地の特産物の取引を通じて商人資本や金貸し資本を台頭させ、農村への商品経済の浸透は農民層の分解による地主・小作関係を成立させた。製糸・織物などで問屋制家内工業が広範に形成され、幕末には一部で工場制手工業(マニュファクチュア)の成立もみられた。さらに200年余の太平は日本固有の文化を成熟させ、諸藩の藩校や蘭学(らんがく)塾、寺子屋の盛行は、庶民を含めた国民の教育、文化水準の向上に貢献した。これらは、のちにアジアの大部分が欧米諸国によって植民地化されるなかで、日本のみが近代化に成功する一つの条件となった。
[柴垣和夫]
幕末の開港と明治維新
日本が鎖国によって太平の夢に浸っていた17~18世紀、西欧諸国は重商主義的植民を進め、19世紀に入るとイギリスを先頭に次々と産業革命を達成して資本主義的工業化を実現した。1850年代に至り、欧米諸国は相次いで来航して幕府に開港を迫り、幕府はこの圧力に屈して開国(1854年日米和親条約、以後イギリス、ロシア、フランス等にも開港)した。開国は貿易の激増による商品経済の発展を促す一方、幕藩体制の政治的動揺を激化し、ついに1868年(慶応4)、西南雄藩の下級武士層を主体とする王政復古によって明治維新政権の成立をみるに至った。新政府の担い手が武士であったとはいえ、彼らは、アヘン戦争後、半植民地化の道をたどった中国(清(しん))の経験に学び、封建制度の解体による資本主義の建設を意識的に目ざした点で、この変革は西欧における市民革命(ブルジョア革命)の性格をもつものであった。
新政府は廃藩置県とともに、封建的身分制、職業選択や移動についての封建的制限を撤廃することによって、資本主義成立の前提をなす労働力商品化(無産階級創出)の制度的条件を創出し、さらに地租改正によって近代的土地所有と近代的租税・財政制度を確立した。新政府はまた、地租による財政収入を基礎に、公債を与えて封建的家臣団を解体し(秩禄(ちつろく)処分)、交通、通信や教育制度を整備し、自ら官営事業を営んで近代機械制工業の移植に努めた(殖産興業政策)。もっとも、これらのための膨大な財政支出は、租税だけでまかなえるものではなかった。政府はこの過程で、三井や三菱(みつびし)などの政商的商人・金貸し資本に利権を与えて彼らの力を利用する一方、不換紙幣の増発や国立銀行による不換銀行券の増発によって財源の不足を補った。その結果激しいインフレが生じたが、これを収束したのが1881年(明治14)に始まる紙幣整理である。インフレは一転して深刻なデフレとなり、農民や士族は土地や資産を手離して無産階級に没落していった。こうして日本資本主義は、そのいわゆる原始的蓄積の過程を経過し、その歴史的基礎を確立したが、以上の過程で特徴的なことは、一貫して政府のイニシアティブが著しく強かったことであり、これは、当時欧米の資本主義がすでに自由主義段階の最盛期を過ぎ、帝国主義段階の入口に差しかかっていた時期にようやくスタートを切った日本資本主義の後発国としての条件によるものであった。
[柴垣和夫]
産業資本の確立とその限界
1881年に始まる紙幣整理が一段落したのち、1887年から1890年にかけて日本経済は最初の民間での企業勃興(ぼっこう)を経験した。企業熱は鉄道から綿糸紡績、そして鉱山へと波及していったが、重要なのは綿糸紡績業の成立である。同業は主として関西地方の商人・地主の資本を集中した株式会社の形態で相次いで設立され、いずれも最初から一万錘(すい)以上の規模をもってスタートした。また原料を国産綿花から輸入綿花(最初は中国綿、のちインド綿)に切り替え、細糸はつくれないが生産性の高いイギリス製リング紡機と蒸気機関を採用し、さらに安価な出稼ぎ型女子労働力、電灯の導入による深夜業実施などに支えられ、1890年代を通じて輸入綿糸(中国糸、インド糸)を駆逐して国内市場を制覇し、日清戦争(1894~1895)後には輸出産業にまで成長した。これは、日本における産業資本の確立を意味するものであった。だが、綿工業以外の近代工業、とくに当時ドイツやアメリカで発展しつつあった重化学工業は、資本の不足、技術水準の低位のゆえに定着せず、それらの製品は欧米諸国からの輸入に依存しなければならなかった。その輸入のための外貨は特産品である生糸や米、茶、石炭、銅などの一次産品の輸出で獲得したが、その結果、確立期日本資本主義の再生産構造は、アジア地域との関連では、綿工業を担い手として原料農産物(綿花)を輸入して工業製品を輸出するという、先進国的・工業国的構造を形成しつつ、対欧米諸国との関連では、一次産品・半製品を輸出して工業製品を輸入するという、後進国的・農業国的な二面的性格に彩られることとなった。また、綿工業による産業資本の確立は、三井、三菱などの旧政商的性格からの脱皮を促し、この時期彼らは、流通、金融、鉱山などに拠点をもつ総合事業体に転化した。
なお、移植産業である綿糸紡績業が株式会社形態による大規模企業として成立したのに対して、在来産業である製糸業、織物業等が無数の中小・零細企業にとどまった結果、いわゆる日本産業の二重構造の原型が形成されるとともに、後者は長らく商人・金貸し資本による問屋制的支配のもとに置かれることとなった。また、綿工業を含めて工業における労働力需要が大部分婚前期の出稼ぎ型女子労働力に限られたため、農村には膨大な過剰人口が滞留し、その結果、農業経営は零細な家族経営のまま維持されるとともに、小農経営のもとでの農産物価格形成が利潤範疇(はんちゅう)の成立を阻害することによって、農民層分解は地主・小作関係の再生産に歪曲(わいきょく)されるメカニズムが定着した。これらの限界面をもちつつも、1897年には日清戦争の勝利による償金を基礎として金本位制を確立し、日本資本主義は国際的にも定着したのである。
[柴垣和夫]
帝国主義化と二度の世界大戦
20世紀の開幕による帝国主義時代の本格化は、年若き日本資本主義にも早熟的な帝国主義への転化を促した。日清戦争、日露戦争(1904~1905)の勝利で台湾、南樺太(からふと)、朝鮮を植民地化する一方、両戦争後の戦後経営で官営八幡(やはた)製鉄所の創設や陸海軍工廠(こうしょう)の増強、鉄道国有化など、軍拡のための重工業の育成が進められた。この際にも、民間の資本蓄積の低位から、政府が主役を演じなければならなかったのである。しかし、そのための支出は、賠償がとれなかった日露戦費支出とともに過大な財政負担となり、また重工業化のための資本財・原料輸入の増大もあって、財政ならびに経常収支の赤字化を招いた。外債の発行による外資の導入がそれを一時的に糊塗(こと)したものの、明治末年にはそれも限界に達し、第一次世界大戦(1914~1918)直前には国民経済的に行き詰まるに至った。第一次世界大戦はヨーロッパを主戦場としたため、日本はアメリカとともに一大輸出ブームに浴し、それによって得た外貨が日本経済に一時的な余裕をもたらしたが、戦後恐慌(1920)、関東大震災(1923)、金融恐慌(1927)と続いた恐慌や災害は、ふたたび危機を深化させ、日本は1920年代後半に欧米諸国でみられた「相対的安定」さえ実現できなかった。ただ、この間、大戦中のヨーロッパからの輸入途絶を背景として、民間における重化学工業の企業勃興がようやく本格化したこと、戦中・戦後の都市化の進行が公共投資主導の成長下支え効果を発揮したこと、慢性不況を背景として資本の集中が進み、三井、三菱、住友などの財閥コンツェルンと綿工業独占体による金融資本の独占体制が確立したこと、には注目しておく必要がある。
だが、1930年(昭和5)第一次世界大戦以来禁止していた金輸出の解禁を実施(金本位制再建)したまさにそのとき、日本経済は前1929年秋アメリカに始まった世界恐慌の渦中に巻き込まれ、これによる不況の深化のもとで農村問題をはじめとする社会問題が激化し、左右両翼の社会運動も高揚し始めた。日本帝国主義は、この危機の打開を、大正デモクラシー以来の政党政治にかわる軍部ファシズムによって、一方における左翼の弾圧、他方における対外軍事侵略(1931年満州事変、1937年日中戦争)に求め、それを1931年末の金輸出再禁止後の為替ダンピングによる輸出と軍需インフレによる好況で実現した。この金輸出再禁止による金本位制の最終的放棄は、日本資本主義の現代資本主義(=国家独占資本主義)への移行を示すメルクマールであり、赤字公債発行による軍需インフレ政策は、国家独占資本主義を特徴づけるケインズ主義的フィスカル・ポリシー(財政による有効需要創出策)の国際的に先駆的な成功例であった。しかし、世界恐慌後のブロック経済下における輸出と軍事侵略による日本の対外進出は、やがてアメリカ、イギリスなど欧米連合諸国との帝国主義的対立を激化し、1941年には対米・英宣戦による第二次世界大戦を引き起こした。緒戦に勝利を収めたとはいえ、彼我の経済力の差は戦争の長期化とともに戦局の悪化を招き、1945年8月、日本の敗北をもってこの大戦は終結したのである。
[柴垣和夫]
占領下の戦後改革と経済復興
第二次世界大戦敗戦とともに日本は連合国(事実上はアメリカ)の占領下に置かれ、占領軍のイニシアティブのもとにいわゆる経済の民主化が実施された。財閥解体によって家族支配による財閥コンツェルンは法人間株式持合いによる企業集団に転化し、農地改革は農地から地主制を一掃して自作農体制を創出した。労働改革によって初めて労働三権を保障された現代的労使関係が定着した。財政・金融制度についても、たとえば赤字公債の発行とその日本銀行による引受けの禁止など、一定の改革が行われた。これらの諸改革は、男女平等普通選挙権による大衆民主主義的政治制度の導入をもたらした憲法改正などとともに、戦後改革の一環をなすものであり、日本資本主義の構造を現代独占資本主義にふさわしいものに改変した制度的変革であった。
こうした改革を実施しつつ、戦後の日本経済は、当初、生産の崩壊と悪性インフレによって困難を極めたが、東西冷戦の開幕を背景とした占領政策の転換に伴い、アメリカの対日経済援助と、鉄と石炭に重点を置いた傾斜生産方式の採用によって1948年(昭和23)ごろから復興の端緒についた。しかし、戦後復興を決定的に促進したのは、ドッジ・ライン(1949)による不況を経て、1950年6月に勃発(ぼっぱつ)した朝鮮戦争によってであった。日本は朝鮮半島に出動した米軍の軍事基地・補給基地として機能した結果、膨大な米軍特需を受注することとなり、これによって鉱工業生産は一挙に戦前水準を回復したのである。ただし生産復興の内容は、繊維や石炭など戦前以来の基幹産業の復興によるもので、戦後的新しさはいまだにみられなかった。また、戦後復興が東西冷戦の熱戦への転化を背景に実現されたという事情は、その後の日本資本主義の著しい対米従属・依存関係をつくりだすこととなり、一時は憲法で放棄した軍備も占領軍の指示で復活することとなった。1951年9月に締結され、1952年4月に発効したサンフランシスコ講和条約によって日本は独立を回復したが、同時に日米安全保障条約が締結されて、その後も日本はアメリカの「核とドルの傘」のもとで発展することとなった。
[柴垣和夫]
第一次高度成長と重化学工業化
1955年から1964年まで、ちょうど昭和30年代の10年間、日本経済は実質GNP成長率年平均10%弱という高度成長を実現した。民間設備投資の主導によるもので、投資ブームはこの間、神武(じんむ)景気(1955~1956)、岩戸景気(1958~1961)、オリンピック景気(1963~1964)と三度大きなうねりをみせた。高度成長の内容を経済の実体面からみると、それは産業構造の高度化、製造業の構成が重化学工業に傾く過程であった。鉄鋼、造船、重電といった古典的重工業から、両大戦間期に欧米諸国で確立した自動車、家電などの量産型耐久消費財産業、さらに第二次世界大戦の戦中・戦後にアメリカを舞台に登場した合成繊維、石油化学、エレクトロニクス、原子力などの新産業が、日本ではこの10年間に同時並行的に確立した。大規模な電源開発や大型火力発電プラントの建設が行われ、前者と関連して建設業も近代化した。こうした重化学工業化を内容とする高度成長を可能にした条件は、概括的には戦争による破壊からの復興需要(戦後性)と先進諸国とくにアメリカへのキャッチ・アップの動力(後進性)にあったといえるが、より具体的には生産要素調達における以下の4点が重要である。
(1)アメリカを中心とする欧米諸国からの技術導入――上記諸産業の技術革新は、基本的に先進諸国からの導入技術と、その日本的条件への修正的適用によって実現された。
(2)安価な中東原油の輸入――戦後中東で大量に開発された原油は、国際石油資本(メジャーズ)による消費地精製主義戦略のもとできわめて低価格(1バレル=2ドル前後)で供給され、それは一面では国内の石炭産業を斜陽化させたが、重化学工業にとっては原燃料面での大きなメリットをもたらした。
(3)良質・安価で豊富な労働力の供給――戦前以来の農村過剰人口のなかから中等教育(中学義務化、高校進学率上昇)のレベルを備えた新規学卒若年労働力が、年功賃金体系のもとでの低い初任給賃金で大量に供給された。
(4)家計の高貯蓄に支えられた豊富な資金供給――重化学工業の建設には莫大(ばくだい)な資金を必要としたが、家計の高貯蓄が銀行や郵便局→政府金融機関を通して産業資金として供給され(間接金融)、それでも不足する分は日本銀行の信用膨張(オーバーローン)によって供給された。
ところで、以上のような諸条件によって支えられた高度成長を担った経済主体は、主としては民間の私的資本であった。とくに旧財閥系企業の再結集によって編成された三菱・住友・三井の三大企業集団、ならびに富士銀行・第一銀行(第一銀行はのち第一勧業銀行となり、富士銀行、第一勧業銀行は合併・再編により、2002年4月からみずほ銀行、みずほコーポレート銀行となっている)・三和銀行(現、三菱UFJ銀行)を中心に形成された三金融系列集団は、独禁法体制のもとで、集団内にあらゆる産業分野の企業を確保しようとする行動様式(ワンセット主義)をもって新産業への進出を競い、重化学工業化を担った。重化学工業化に伴い、中小企業の存在様式も変化し、第二次世界大戦前の製糸・織物業における問屋制支配下のそれから、重化学大企業に直結した部品生産あるいは二次・三次加工製品生産主体として再編成された。もっとも、民間経済主体中心の高度成長であったとはいえ、政府の役割が皆無だったわけではない。国民経済に占める財政規模は先進国のなかでもっとも小さく、税の自然増収によって公債依存を免れた均衡財政が維持されたとはいえ、支出の内容は資本支出に重点を置いた資本蓄積促進的性格に彩られていたし、財政投融資の運用対象は、初期には直接基幹産業に、のちには道路・港湾・橋梁(きょうりょう)など産業基盤の充実に重点が置かれた。対外政策では、外貨予算割当制度を利用しての輸入規制が、育ちつつある重化学工業にとって温室の役割を果たした。さらに種々の個別産業の育成・合理化立法や通産省(現、経済産業省)による行政指導もそれなりの効果を発揮したし、国民経済全体にとっては、1955年から策定が開始された5~10年単位の中長期経済計画が、民間経済主体に投資の目安を与えた。とくに1960年の安保条約改定をめぐる政治的緊張のあと、池田勇人(はやと)内閣によって策定された国民所得倍増計画は、国民に高度経済成長への確信を与える効果をもたらしたといえよう。このようにして展開した高度成長の過程で、戦後の混乱期以来の階級闘争的労働運動も1960年の三井三池炭鉱の争議を最後に退潮に向かい、労使協調を旨とする日本的労使関係が成熟していったのである。1964年4月、日本はIMF(国際通貨基金)8条国に移行し、OECD(経済協力開発機構)に加盟して先進国の仲間入りをした。1955年に始まる第一次高度成長期は、戦後日本資本主義がもっとも順調な展開をみせた時期であったといって過言ではない。ただ、成長の主動力が既述のように民間設備投資という内需にあり、それが盛り上がると輸入が急増して輸出が停滞し、経常収支が赤字となり、戦後のIMF制度下の固定為替レート制のもとでは、その克服のために強力な金融引締めを必要とした点に(いわゆる「国際収支の天井」)、成長の限界が存在していたのであった。
[柴垣和夫]
第二次高度成長と「経済大国」化
1964年から1965年にかけて、日本経済は高度成長開始以来初めての深刻な不況を経験した。これは、1960年代に入って、それまでの成長要因の一つであった新規学卒若年労働力の供給が限界に達し、初任給賃金の急騰に端を発して賃金コストが低下から横ばい、上昇に転じたこと、それと、それまでの銀行借入に依存した設備投資の償却費、金利負担の上昇が相まって、企業利潤率の急激な低下が生じたことによるものであった。この不況に加えて、さらにアメリカが、これも1960年代に入って顕在化したドル危機への対策として要求してきた貿易の自由化がスタートし、さらに資本取引の自由化も日程に上っていたことが、産業界の危機感を募らせていた。産業界では自由化対策として、大企業間の合併や提携が盛行したが、政府は1965年秋、特別立法により、財政法が禁止している赤字国債の発行に踏み切り、翌1966年度からは建設国債の発行による財政需要の拡大で不況の乗り切りを図った。ところが、この不況は、実際には大方の予想に反して短期間で克服され、自由化の危機感も杞憂(きゆう)に終わった。1965年に始まるアメリカによるベトナム戦争介入のエスカレーションを背景に、輸出が急増したからである。それまで赤字だった対米貿易は1965年から黒字に転じ、貿易・経常収支も赤字基調から黒字基調に転換した。その結果、長期資本収支も入超から出超に転じ、資本輸出国へと成長した。輸出に先導された景気回復は、ふたたび大型の設備投資を呼び起こし、それに基づくブーム(いざなぎ景気とよばれた)は1970年なかばまで、4年9か月の戦後最長を記録し、1966年から石油危機が勃発した1973年までの実質GNP成長率は、年平均10.8%に達した。この時期の設備投資の内容は、本格化した労働力不足に対処するための省力化と量産効果を目ざしたプラントの自動化・巨大化を特徴とし、工場立地は、旧来の三大都市圏から海岸埋立てによる太平洋ベルト地帯に広がった。これによって重化学工業は国際的にトップ・レベルの競争力を確立し、貿易・資本自由化を乗り切ったのである。1968年、日本のGNPは当時の西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ資本主義世界第2位に到達し、「経済大国」の地位を不動のものとした。
しかしながら、この第二次高度成長期は、第一次のそれと異なり、対外的にも国内でも種々の軋轢(あつれき)・摩擦を伴ったものであった。対外的には、まず、ベトナム戦争の泥沼化で疲弊し、国際収支の赤字累積でドル危機がますます深刻化したアメリカとの貿易摩擦(繊維、鉄鋼、白黒テレビ)が噴出し、1970年に入るとアメリカは、ドッジ・ラインで制定された円の対ドル為替レート(1ドル=360円)の切上げを強く迫った。これに抵抗する日本に業(ごう)を煮やしたアメリカは、1971年8月新経済政策を発してドルの金交換性を停止し(ニクソン・ショック)、主として日本を念頭に置いた為替レート調整を提起した。これは、戦後の世界経済を支えていたIMF=国際通貨制度を根本的に改変した事件であって、一度は同年12月のスミソニアン会議で円の切上げ(1ドル=308円)を含む新固定レートが設定されたものの、1973年春以降変動相場制に移行して今日に至っている。対途上国との関係でも、1965年の日韓国交正常化などもあって、日本の商品、資本のアジアへの進出が本格化し、タイ、インドネシアでは日本の「経済侵略」反対のデモが発生した。国内でもさまざまな社会問題が顕在化した。1965年の「不況下の物価高」を起点として卸売物価、消費者物価ともどもに上げ足を速め、1970年代に入ると経常収支黒字を背景とし過剰流動性がインフレを高進させた(物価問題)。農地改革の結果高成長が続いていた農業生産も、1960年代に入って若年労働力の流出や男子農民の都市への出稼ぎの結果、老人、婦人の農業(三ちゃん農業)と化し、食糧管理制度で保護された米以外の穀物生産は放棄され、食糧自給率の急低下を招いた(農業問題)。農村の僻地(へきち)では人口の高齢化、過疎化が進む一方、都市とくに大都市では人口が過密化し、土地・住宅問題、交通問題、ごみ処理問題を深刻化させた。なによりも深刻だったのは公害問題である。都市部や沿岸部に集中した工場立地、急激に進んだモータリゼーションの結果、それらの地域では空気は汚染し、水は汚濁し、騒音・振動が日常化した。三大公害(水俣(みなまた)病、四日市喘息(よっかいちぜんそく)、イタイイタイ病)は被害者の告発により裁判の対象となり、いずれも発生源である企業側の敗訴となった。
以上のような社会問題の深刻化は、国民の価値観を、それまでの経済成長至上主義から福祉・環境の重視へと、大きく変化させた。それは政治状況にも反映し、大都市圏を中心に革新自治体が簇出(そうしゅつ)し、国政選挙でも政権党である自由民主党の退潮を招いた。革新自治体が追求した福祉・環境重視の施策は、やがて国政をも動かし、1971年には環境庁(現、環境省)が発足、1973年には5万円の公的年金とその物価スライド制が実施されるなどした。しかし他方では、田中角栄首相の「日本列島改造論」が全国的な土地投機を招き、1972年から1973年にかけてインフレは過熱化の傾向を強めた。そこに石油危機が勃発した。
[柴垣和夫]
第一次石油危機とその克服
1973年秋の石油危機は、直接には第四次中東戦争でOAPEC(オアペック)(アラブ石油輸出国機構)が採用した石油戦略、続いてOPEC(オペック)(石油輸出国機構)が実施した石油価格の4倍引上げによって生じたが、その背景には、1960年代に顕在化した南北問題のもとで、自国の資源に対する主権の主張を強めていた発展途上諸国の先進諸国への反発があり、それが産油途上諸国の国際石油資本――その背後にはイスラエルに加担するアメリカが存在する――への反乱として爆発したものであった。これによって日本経済は、欧米諸国ともども激しいスタグフレーションに陥った。スタグフレーションとは、「インフレと不況の共存」というそれまでの経済学では考えられなかった事態をさす用語である。当時の日本経済はすでに景気過熱の状態にあったが、石油危機はその火に油を注ぐ役割を果たした。同年11月以降、物価は、原油高騰を利用した石油連盟の闇(やみ)カルテルによる石油製品の大幅値上げを皮切りに、買占め、売り惜しみ、便乗値上げも加わって、翌1974年春までに年率で卸売物価30%、消費者物価25%の上昇を記録した。このような「狂乱物価」に対し、1974年春闘は交通ゼネストを交えてかつてない高揚を示し、物価上昇を上回る賃上げ率35%を獲得して労働分配率を大幅に上昇させ、企業はこの賃金コスト上昇をさらに価格に転嫁する気配を示した。物価と賃金の悪循環に直面して、同年3月政府は強力な総需要抑制政策に踏み切り、その結果、原油続騰による石油消費部門の価格調整は続いたものの、投機的物価上昇はしだいに沈静していった。だが、それにかわって、総需要抑制による操業率の低下と、賃金コスト上昇によって企業利潤は大幅に低下し、一転して深刻な不況が訪れることとなった。1974年の実質GNP成長率は、第二次世界大戦後初めてマイナス(対前年比1.3%減)を記録したのである。
1973年から1974年への実質成長率10ポイントの低下という先進国中最大のショックを受けたにもかかわらず、その後の日本経済の回復過程は欧米諸国に比べて相対的に順調で、1976~1979年には5%台の実質成長率を実現した。回復を可能にした要因は、(1)アメリカのスペンディング(財政支出拡大)政策による「機関車」的役割に便乗しての輸出の急増、(2)赤字国債を含む国債大増発による財政スペンディングの拡大、(3)民間企業の省エネルギー努力をはじめとするモノ(原燃料)、ヒト(人件費)、カネ(金融費用)の全面的な減量経営の推進、であるが、(4)賃上げよりも雇用を重視し、争議を自粛して企業の減量経営に協力した日本型企業別労働組合のビヘイビアも見逃すことはできない。さらに、この過程でエネルギーの石油から天然ガス、石炭への転換、金属、石油化学、造船など資源多消費型産業の不振に対する自動車、電気・電子、精密機械など高加工型産業ならびにサービスなど第三次産業の伸張がみられ、産業構造の知識集約化・高付加価値化が進展した。とくに注目されるのは、1978年にそれまでの低迷から大幅に回復した民間設備投資が、NC工作機械やロボット・OA機器など、マイクロエレクトロニクス(ME)の進歩によるコンピュータ内蔵のいわゆるハイテクノロジー機器の導入を内容としたものであったことである。このようなひと口にME革命とよばれる新しい技術革新投資は、欧米諸国では労働組合の強い抵抗にぶつかったが、「日本的労使関係」のもとではスムーズに展開され、世界で稼動するロボットの8割が日本にあるといった状況を生み出した。このような新しい技術革新を通して、高度成長期の日本を代表した「重厚長大」型製品にかわって、「軽薄短小」型製品が世界市場を席巻(せっけん)することになったのである。
こうして日本資本主義は第一次石油危機を克服したが、そこにはさまざまな問題が伴っていたことも事実である。第一に、1976年度以降連年一般会計の30%(1979年度は40%)に及ぶ大量の国債発行は、その累積による財政危機をもたらした。1979年大平正芳(まさよし)内閣は一般消費税の導入による増税で赤字財政の一挙解決をもくろんだが、それは同年秋の総選挙中に国民の反発にあって挫折(ざせつ)した。第二に、同じく国債の大量発行は、それまでの規制低金利下の割当て消化を困難にし、発行条件の弾力化を促したが、それは同時に、既発債流通市場の自由化を通じて短期金融市場金利の自由化を実現した。またそれを背景とした自由金利預金や証券の開発は、銀行と証券の垣根を低め、金融業界の分業体制の流動化を促した。こうした動きは、高度成長期までの規制金利と分業統制による「護送船団」方式の金融秩序に風穴をあけるものであった。第三に、輸出の伸張とくに鉄鋼・機械機器を中心とした高品質の日本商品の世界市場席巻は、前期以来の貿易摩擦をいっそう深刻化し、アメリカによる鉄鋼トリガー価格制度導入(1978)や、日本の対米カラーテレビ輸出自主規制(1977)、対EC鉄鋼自主規制(1976)が実施された。石油危機後一時赤字に陥った貿易収支は1976年から大幅な黒字に転じ、その累積の結果、対米為替レートも、石油危機直後の300円台から1978年秋には史上最高(当時)の176円の円高を記録した。そこに1979年2月のイラン政変に端を発した第二次石油危機が勃発した。
[柴垣和夫]
第二次石油危機と臨調・行革路線
イランの政変による産油量低下を機に、OPECは1979年6月、1980年6月と二度にわたって原油価格を引き上げた(最高時1981年10月~1983年3月公式価格1バレル=34ドル)。これによって旧西ドイツを除く欧米諸国では、ようやく回復過程にあったスタグフレーションがふたたび深刻化したが、その日本への影響は比較的軽微だった。為替レートは250~260円台まで低落し、経常収支は1979~1980年の2年間赤字となったものの、貿易収支は黒字幅の縮小ですみ、物価の上昇は原油高騰の範囲に収まり(1980年の上昇率卸売物価18%、消費者物価8%)、「狂乱物価」は再現しなかった。GNP成長率や鉱工業生産もさほど低下せず、法人企業の経常利益率も高原状態を維持した。日本経済上出来論が内外ではやされ、E・ボーゲルの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』が国際的ベストセラーになったのも、このような背景においてであった。このような日本経済の好パフォーマンスを可能にした原因は、景気がすでに過熱状態にあった第一次石油危機の場合との初期条件の差や、経済諸主体の同じく第一次危機からの学習効果もあったといってよいが、基本的には、賃金上昇を物価上昇に連動させることなく労働生産性上昇の枠内に押さえ込み、それによって労働分配率を低下ないし横ばいに保つことに成功したためであった。日経連による生産性基準原理という名の所得政策が、同盟系労組のいわゆる経済整合性論による賃上げ自粛とも相まって、みごとに実現されたのである。しかし、日本経済がみごとに第二次石油危機を乗り切ったかにみえたとき、国際経済環境は1980~1982年の3年間に及ぶ世界同時不況に直面し、日本の経済成長率も1980年までの5%前後から1981年の4%、1982~1983年の3%台へと鈍化していった。それを規定したのが、相前後して登場したアメリカにおけるレーガン政権の新自由主義路線(レーガノミックス)と、日本の鈴木善幸(ぜんこう)、中曽根康弘(なかそねやすひろ)両内閣による臨調(臨時行政調査会)・行革(行政改革)路線であった。
この二つの路線は連動していた。レーガノミックスは、イギリスのサッチャーイズムとともに、ケインズ政策と福祉国家のシステムが生み出した政府の肥大化と社会の腐朽化――これがスタグフレーションの原因と考えられた――に対する保守的立場からの挑戦であったが、増税失敗後の深化する財政危機のなかで、肥大化する福祉財政に同様の事態の兆しをみいだした日本の為政者が、その危険を先取りして実行に移したのが臨調・行革路線であった。それは「小さな政府」「民間活力」を合いことばに「増税なき財政再建」を目ざし、具体的には「1984年度赤字国債発行ゼロ」を目標とした。この目標自体は、成長鈍化による税収不足と財政支出の硬直化のために挫折し、目標年度を1990年(平成2)に延長しての達成も困難視されて、1987年度の売上税(大型間接税)導入が浮上したのであるが、この間、一般会計概算要求枠の抑制が持続するなかで、レーガン政権の圧力による防衛費と対外公約である経済協力費だけは伸び続けたため、その「しわ」は公共事業費や社会保障費、文教費に寄せられた。こうした緊縮財政と、これもこの間持続された賃金抑制が相まって、内需は不振を極めた。既述の技術革新のうねりにのったハイテク(先端技術)産業を中心に、設備投資だけは堅調を維持したが、これも「軽薄短小」を目ざす新技術の性格からして波及効果に乏しかった。それゆえ成長要因はもっぱら外需つまり輸出に依存するほかなく、それは第二次石油危機後の円安もあって急伸し、1981年以降経常黒字はまたまた累増、貿易摩擦は工作機械、自動車、VTR、半導体等々にエスカレートしていった。貿易摩擦の深刻化は、それまで資源国への資源開発投資、途上国への製造業投資、欧米先進国への商社・銀行進出という3類型に分化していた対外直接投資のあり方にも変化をもたらし、貿易摩擦回避を目的として、欧米諸国への自動車をはじめとする製造業投資(企業進出)が本格化した。
さらに特記すべきことは、第一次石油危機後の場合とは異なり、前記のような輸出の急伸、経常黒字の累増が、この際にはただちに為替レートの円高をもたらさなかったことである。それはレーガノミックスの奇妙な帰結に基づく。レーガノミックスは、一方ではマネタリズムに基づく緊縮的なマネーサプライ(通貨供給)管理によって、大量失業と途上国債務のデフォルト(債務不履行)というコストを払いつつも、1982年にはいちおうインフレの沈静化には成功した。しかし他方では、「強いアメリカ」の再建を目ざした軍拡とサプライサイド政策(供給力強化政策)の失敗によって財政再建には失敗し、膨大な財政赤字を累積した。この財政赤字が、皮肉にもケインズ的刺激効果を発揮して、1983年以降の内需中心の景気回復をもたらしたが、同時にそれは国債増発による金融市場のクラウディング・アウト(押しのけ効果。国債に資金が吸収されるため民間企業への資金供給が抑圧されること)を誘発して高金利を持続させた。そして、この高金利が大量の資本流入をよんでドル高を持続させたのである。その際日本は1980年の外為(がいため)法改正による対外金融取引の自由化によって対米投資の主役を演ずる一方、ドル高、円安を利用して対米輸出超過を異常なまでに拡大したのであった。つまり、対米経常黒字を対米資本収支の赤字でカバーするという日米経済関係が現出したのである。しかし、その結果生じた貿易摩擦のいっそうの激化と、アメリカの債務国への転落は、世界経済の将来に大きな危惧(きぐ)をよび、1985年9月ニューヨークのプラザホテルで開催されたG5(ジーファイブ)(先進5か国財務相・中央銀行総裁会議。1986年からG7)で国際協調によるドル高是正の合意をみた(プラザ合意)。その結果事態は一変し、円・ドルレートは同年春の1ドル=260円から1988年1月の1ドル=110円にまで円高が進んだ。また、深刻化した日米経済摩擦に対しては、首相の諮問を受けた前川前日銀総裁を座長とする会議体が、1986年、1987年の二度にわたって「報告書」(いわゆる前川リポート)を発表、内需主導型の経済成長追求を打ち出した。もっとも、内需拡大といっても主役を演ずるべき財政は厳しい制約下に置かれていた。既述の臨調・行革路線は、一部省庁の統合と三公社の民営化(電電、専売、両公社1985年、国鉄1987年)、さらには何度かの挫折を繰り返したあげく1989年に大型間接税=消費税の導入を実現したものの、赤字財政の克服には至っておらず、そのため財政規模拡大の限界を日銀の公定歩合を3.5%という当時史上最低の水準に引き下げることによってカバーせざるをえなかった。
[柴垣和夫]
円高不況からバブルへ
プラザ合意による円高は日本の輸出産業に冷や水を浴びせ、1986年から1987年にかけての日本経済は「円高不況」に陥ったといわれる。確かに自動車や電気・電子機器などの輸出産業は大幅な収益の低下に見舞われたが、他方円建て輸入価格の低下で輸入産業には為替差益が生じたし、さらにその差益が後方産業に還元されて、その恩恵は輸出産業を含む全産業に及ぶ側面もあった。さらに、第二次石油危機以降OPEC(オペック)(石油輸出国機構)以外の産油国が増大した結果、軟化していた原油価格が1986年初め以来急落した。それゆえ、円高不況論は財界による1986年春闘に対する牽制(けんせい)のためのキャンペーン的性格が強かったと思われるが、実際1988年に入ると内需が大きく盛り上がり、以後1991年の春まで、1960年代後半の「いざなぎ景気」に次ぐ長期の景気が訪れたのである。内需拡大によって、NIES(ニーズ)(新興工業経済地域)やASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)諸国などからの製品輸入が増大し、全輸入に占める製品輸入の割合は、1989年に初めて過半を超えるに至った。1985年まで増加の一途をたどっていた対米貿易黒字も、以後1991年まで減少を続けた。その結果、互いに内政干渉まがいの応酬を繰り広げた、1989年から1990年にかけての「日米構造協議」も終幕した。
この大型景気で特徴的だったことは、1970年代末の国債流通市場の整備と1980年の外為(がいため)法改正によって進められた、国内・対外両面に及ぶ金融自由化と、そのもとでの既述の超低金利を背景に、株式や土地への活発な投資、後には投機が伴ったことである。東京が国際金融市場として浮上するに伴い、一方では、外資の日本進出がオフィスビルの不足をもたらすという思惑から発した東京都心の地価上昇が、やがて地方都市にも波及して、地価は上げ一方という土地神話をつくり出した。他方、地価の上昇は企業が所有する土地の含み資産価値を増大させて株価を騰貴せしめ、企業はそれを利用して内外市場で盛んにエクィティ・ファイナンス(新株発行を伴う資金調達)を行い、そこで調達した資金に金融機関から低利で調達した資金を加えて、いわゆる財テク、すなわちキャピタルゲインの獲得を狙(ねら)った外国証券や国内の株式、土地への投資を行った。それが株価と地価のさらなる騰貴をもたらし、資産インフレというバブル経済をもたらしたのである。この間、銀行をはじめとする金融機関は、かつては資金需要の主役であった製造業の設備投資の低迷によりダブついた資金を、直接に、あるいは系列のノンバンクを通じて、株や土地への財テク資金として融資した。そのなかには暴力団が絡んだいかがわしい取引もあったことが、後に明らかとなった。
1980年代後半のバブルは、日本だけでなく欧米諸国でも生じていたが、それは1987年10月の株価暴落(ブラック・マンデー)で崩壊した。日本の株価もこのときいったん下落したが、その後ふたたび上昇に転じたため、バブルはもう一回り拡大した。この間一般物価は、円高と原油安による輸入物価の低下により、卸売物価、消費者物価ともどもに安定していた。このことが、土地と株の高騰は国民生活には無関係だとして、政府、日銀を無警戒にしていた。しかし、東京通勤圏における一戸建住宅価格は、サラリーマンの年収の5倍という限度をはるかに突破して10倍を超えるに至ったのである。日銀が公定歩合を引き上げて金融引締めに転じたのは1989年(平成1)、金融機関の土地関連融資に総量規制を導入したのは、1990年に入ってからのことであった。
[柴垣和夫]
平成大不況と政治の不安定
バブルは必ず崩壊し、好況はかならず不況に転ずる。それがいつのことかは正確に予測できないが、転換がかならず起こるのは経済法則の定めである。1990年に入って株価が、ついで1991年には地価が下落を開始し、実体経済も1991年1~3月期をピークに下降に転じた。不況は1993年9月に底入れし、以後緩やかな回復過程に入ったといわれたが、同年から1995年春にかけての円高(ピークは1995年4月の史上最高の1ドル=80円)の影響もあって好況感は生まれず、1989年度に赤字国債ゼロを実現したのもつかのま、ふたたび財政金融を総動員して景気振興を図らなければならなかった。1995年4月に1%、同9月に0.5%という公定歩合は、日銀史上最低の記録である。わずかに好調なのは1995年中盤以降の円安に支えられた輸出関連の製造業ぐらいであったが、1997年4月からの消費税の5%への引き上げによる消費の冷え込みによって、同年末には景気後退に入った可能性が強い。
それゆえ、1990年代を通して平成大不況とよばれることもあるが、この不況には、それが複合不況ともよばれているように、実体経済の不振だけでなく銀行、証券をはじめとする金融機関の経営悪化という、戦後では初めての特徴が加わっている。株価と地価が高騰時の半値以下へと暴落し、既存の貸出しの担保価格を大きく引き下げ、巨額の貸出しが不良債権に転化してしまったのである。金融機関の経営破綻(はたん)はバブル時代に銀行その他が設立した住宅専門金融機関(住専)に始まり、信用組合、信用金庫、第二地方銀行などの中小金融機関の一部から、ついには都市銀行の一角を占める北海道拓殖銀行(1997年1月1日)に及んだ。その他の都市銀行や信託銀行、長期信用銀行でも、株価と地価の下落によっていわゆる含み資産が底をつき、8%の自己資本比率を必要とするBIS(国際決済銀行)規制をクリアできないおそれが生じたため、政府は1998年に入って、公的資金30兆円を用意して信用秩序維持にあたらねばならなかった。総会屋への資金提供や顧客の損失補填(ほてん)で評価を落とした証券界でも中小証券の整理が進み、やがて四大証券の一角を占める山一証券が廃業に追い込まれた(1997年11月)。1997年5月には外為法が再度改正されて、金融、証券、保険にわたる東京市場のいわゆる金融ビッグバンの条件が整ったが、弱体化したこれらの業界に外資の攻勢が激しくなっているのが昨今の特徴である。バブルの崩壊とともに人々の意識も大きく変化し、『清貧の思想』と題する書物がベストセラーとなるような状況もあって、かつては不況期の需要を下支えした個人消費も低迷した。
経済の混乱に相応じるかのように、政治も低迷した。国際政治では、この時期のソ連・東欧社会主義の崩壊による東西冷戦の終結という大転換が生じ、またその間隙(かんげき)を縫って1990年には湾岸戦争が勃発(ぼっぱつ)しているが、日本では、バブル絶頂期の1989年4月に竹下首相が退陣したあとの4年間に宇野、海部(かいふ)、宮沢の短命内閣が続き、羽田(はた)派が離党した直後の総選挙(1993年7月)で自民党が過半数割れし、細川非自民連立内閣が成立した。しかし、その後も自民、共産を除く諸政党の改名や離合集散のもとで、羽田、村山、橋本と連立政権が続いた。1996年10月の小選挙区比例代表並立制による総選挙では、自民の復調により、社民、さきがけを閣外与党とした第二次橋本自民党単独内閣が成立した。その橋本内閣も、1998年7月の参院選惨敗の責任をとって退陣、その後を小渕恵三(おぶちけいぞう)内閣が継いだ。他方では一貫して野党を貫いてきた共産党の躍進が特徴的であった。もっとも、世論調査が示すところでは、「支持政党なし」が最大多数を占め、各種選挙での投票率も低迷し、経済、政治、ともどもに混迷の度を強めている。
[柴垣和夫]
産業構造と産業組織
産業構造の高度化
W・ペティが最初に指摘し、C・クラークによって定式化された経験則によれば、いずれの国でも経済成長に伴って生産額(所得)や就業人口が、第一次産業(農林漁業)から第二次産業(鉱工業、建設業)へ、さらに第三次産業(サービス業)へとシフトしてゆく傾向をもつが、日本経済の発展過程もみごとにそれを立証している。戦前(以下「戦前」「戦後」は第二次世界大戦を境にしての時期をさす)就業人口の約半分を占めていた農林水産業人口は、最近に至るまで一貫して比重を低下し、1996年(平成8)には5.5%にまで縮小した。それに対して第二次産業と第三次産業の就業人口は、戦後の高度成長期まではともどもに比重を高めたが、石油危機を経た1970年代(昭和45~54)後半以降は、第二次産業も縮小に転じ、第三次産業のみ比重が高まるという、産業構造の高度に成熟した姿を示すに至った。ちなみに1996年の就業人口比は、第二次産業32.4%、第三次産業62.1%である。産業別の国内総生産の構成比でみると、戦争末期の空襲による都市の破壊と戦中、戦後の食糧難による人口の帰農により、いったん第一次産業の比重が高まったが、1955年の高度成長始動後は、就業人口の動きと同様の構成比のシフトが展開した。ちなみに1995年の就業人口比でみたアメリカの産業構成比は、一次2.9%、二次23.0%、三次74.1%、ドイツのそれは一次3.2%、二次34.9%、三次61.9%であるから、日本は一次産業の縮小度でなお両国に遅れているとはいえ、二次→三次へのシフトの面ではドイツを超える域に達しているといえよう。このことは、日本経済が「脱工業化」の段階に到達していることを示すものであり、近年盛んに語られる経済の「サービス化」「ソフト化」「情報化」ということばは、その内容の諸側面を表現するものである。
[柴垣和夫]
重化学工業化から知識集約化へ
上は産業構成全体の動向であるが、そのなかから製造業だけを取り出して、その内部構成の推移をみてみよう。戦前においては、綿と生糸を中心とする繊維工業が3分の1以上の比重を占め、基本的に軽工業優位の構造であったのが、戦後の高度成長過程で急速に重化学工業化が進んだ。それは、鉄鋼、造船といった古典的重工業から、家電、自動車など戦間期のアメリカで確立した耐久消費財工業、さらには石油化学、合成繊維、電子工業、原子力など戦中、戦後の新産業まで、三世代の重化学工業の同時並行的発展によるもので、1960年代末までに旧西ドイツと並ぶ国際的にトップ・レベルの重化学工業化率を実現した。1970年代以降も重化学工業化率はいっそうの高まりを示しているが、二度にわたる石油危機による資源制約ならびに価格・需要構造の変化と、新興工業国の追い上げに伴い、金属、化学など「重厚長大」型の基礎素材産業は停滞に転じ、ひとり付加価値の高い加工組立産業である機械(造船を除く電気・電子機器、自動車、工作機械、精密機械など)のみがシェアを高めている。また、この間のマイクロエレクトロニクス技術の発展とその応用は、NC(数値制御)工作機械やロボットの普及を通じて生産工程の自動化を進めるとともに、製品の軽量化、小型化(「軽薄短小」化)を促進し、ひいては工業立地についても、高度成長期の港湾に近接した臨海地帯中心から内陸・臨空(港)地帯へのシフトをもたらした。さらに1980年代は、高度技術と創造性豊かな労働力との結合によるその「創造的知識集約化」が追求され、その方法として、技術のソフトウェア化、システム化、製品のスペシャリティ化、ファッション化、技術開発と生産工程のフィードバック化、フレキシビリティ化が進んだ。
さらに1990年代に入ってからの技術革新の方向としては、すでに開花しつつあるエレクトロニクス技術の向上とその応用範囲のマルチメディアなどへの拡大とともに、生体の有する合成、代謝などの機能を産業的に応用する技術としての「バイオテクノロジー(生命工学)」(遺伝子組換え、細胞融合、細胞大量培養・組織培養、バイオリアクターの各技術とその組合せ)や、高度な機能と特性をもった「新素材」(ファインセラミックス、エンジニアリングプラスチックス、炭素繊維、アモルファス(非晶質)金属、形状記憶合金など)などが注目を集めている。また産業開発の舞台として、一方では地球最後の未開地といわれる南北両極地と海洋の開発が、他方では無限の広がりをもつ宇宙の開発が課題とされる一方、汚染や温暖化による地球環境の悪化を回避することが今後の大きな課題となっている。
[柴垣和夫]
エネルギー問題の変遷
日本のエネルギー供給は、戦前以来主として国産資源である石炭と水力に依存してきた。高度成長がスタートした1955年度の一次エネルギーの供給構成は、石炭49.2%、水力21.2%で、薪炭なども加えた国産エネルギー比率は76%を占め、ほとんどすべてを輸入に依存する石油の比率は20.2%にすぎなかった。ところが、戦後、国際石油資本(メジャーズ)による中東油田の開発とその消費地精製戦略により原油価格が大幅に低下(1バレル=2ドル前後)した結果、国産石炭から輸入原油への急激な転換が進んだ(エネルギー革命)。1960年ごろまでは、政策当局も炭鉱の合理化によってエネルギー自給率の一定の確保を図ったが、同年の三井三池炭鉱の大争議以降炭鉱の閉山が相次ぎ、電力やガスも石油を原燃料とする割合が高まった。1973年度の一次エネルギー供給構成比は水力4.6%、石炭15.5%に対して石油77.6%に達し、石炭も輸入炭の比重が高まった結果、国産エネルギー比率はわずか9%にまで低落した。またこの間の資源多消費型素材産業を中心とする重化学工業化は、日本経済のエネルギー弾性値(エネルギー消費増加率/実質国民所得増加率)を高め、1963~1973年平均のそれは1.10に達した。
1973年と1979年の二度にわたる石油危機の結果、原油価格は高騰し(最高時1981~1983年の公式価格1バレル=34ドル)、これを契機に省石油、省エネルギーと石油代替エネルギー開発の時代が開幕した。石油から石炭、天然ガスへの原燃料転換、原子力発電所の建設が急速に進められ、1996年度の一次エネルギー供給構成に占める石油の比率は55.2%に低下し、石炭16.4%、原子力12.3%、LNG11.4%、水力3.4%と変化し、自給率も1995年に20.8%にまで向上した。その結果、石油の輸入(消費)量は1973年の2億8970万キロリットルをピークに絶対量でも減少に転じた。一方、運輸・民生部門のエネルギー需要は増大しているが、産業部門では産業構造の知識集約化、省エネルギー機器の開発などによってエネルギー需要そのものが減退し、その結果国民経済としてのエネルギー弾性値は1973~1982年平均で0.27へと大幅な低下を実現した。代替エネルギー開発では当面原子力発電の拡充が進められているが、1979年のアメリカ、スリー・マイル島、1986年の旧ソ連、チェルノブイリの各原子力発電所事故もあって、その安全性が問題となり、かならずしも順調ではない。環境問題とも関連して、太陽熱、地熱、海流、風力など再生可能な自然エネルギーの利用が提起され、それは日本では「サンシャイン計画」として推進されている。
[柴垣和夫]
運輸と通信の革新
日本の運輸事業は、戦前は鉄道と海運を中核とし、昭和に入ってバス、トラックなど自動車が都市近郊輸送を補完するというシステムをとっていたが、戦後、高度成長期以降、乗用車を含めた自動車の比重が増大し、航空が新たに加わった。そのうち市街地および都市近郊私鉄を除く鉄道は、1906年の鉄道国有化以来、国(1948年以前鉄道省、運輸省、以後日本国有鉄道)が経営にあたった。戦前、世界で有数の商船隊を誇った海運は、第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けたのち、戦後「計画造船」その他の政府の保護政策によって船腹量では復興した。しかし世界的な船腹過剰のため、戦乱などによる一時的なブーム期を除くと不況基調で推移し、その対策として1964年(昭和39)には六大グループへの企業集約(海運集約)が実施された。その後も石油危機後の世界経済の停滞、途上国海運の台頭によって、斜陽化の道をたどっている。陸上では、高度成長期以降のモータリゼーションの急進展によって、旅客および貨物輸送の鉄道から自動車への大移動が生じ、鉄道の輸送分担率は、1955~1996年度の約40年間に、旅客では82.1%から28.6%へ、貨物では52.9%から4.4%へと低落した。これは、自動車の利便性に加えて、戦後、公共投資の重点が道路建設に向けられる一方、国鉄が公社として独立採算性を要求され、鉄道輸送が割高になったためでもあるが、さらに国鉄は政治家の圧力によって地方赤字路線の建設を余儀なくされ、その結果、国鉄の経営は1964年以降赤字を累積するに至った。こうした背景のもとで1987年4月、国鉄は行政改革の一環として分割(旅客部門は北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州の6旅客鉄道会社。貨物は日本貨物鉄道会社。いずれも通称JR)のうえ民営化されて今日に至っている。
一方、通信事業は、戦前には郵便、電気通信(電信、電話)とも政府の直営事業として営まれていたが、戦後は、直営が維持された郵便を除き、電気通信事業は、国内通信は公共企業体としての日本電信電話公社(1952年設立)、国際通信は国策会社としての国際電信電話株式会社(1953年設立。現、KDDI)が営むこととなった。高度成長過程ではとくに電話需要が拡大したが、1978年には加入電話の積滞の解消、1979年には全国自動即時通話化が完成し、世界有数の通信先進国となった。同時にこのころからコンピュータを中心とした技術革新により、双方向CATV(有線テレビ)やVAN(バン)(付加価値通信網)といったニューメディアが出現し、またINS(高度情報通信システム)が開発されるに及んで、1985年4月、電電公社の民営化(日本電信電話株式会社、通称NTTの設立)と内外電気通信事業の自由化が実現し、新たに複数の民間事業者が参入した。また電話機生産の自由化と電波利用の規制緩和によって携帯電話やPHSの普及が進んだ。さらに学術情報の交換から始まったインターネットが、コンピュータの小型化、高性能化、低廉化と相まって個人や企業に広汎に利用されるようになり、音声、文字、画像を含む情報通信のマルチメディア化が進展した。また、電気通信市場への新規参入の円滑化と事業者間の適正な競争を図るため、1999年7月、日本電信電話株式会社は持株会社のもとで東日本電信電話、西日本電信電話、NTTコミュニケーションズの3事業会社に分割・再編された。
[柴垣和夫]
農林水産業の諸問題
戦前以来の地主制を一掃して自作農中心の農業経営をつくりだした農地改革の結果、農民の労働意欲は高まり、農業生産は1950年代には年率4%という高成長を実現した。しかし、1960年代に入って、農村から都市への若年労働力の流出と「出稼ぎ」によって農業労働力は「三ちゃん農業」(おじいちゃん、おばあちゃん、おかあちゃんで営む農業の意)といわれる形で劣悪化し、機械化と化学肥料、農薬の多投がそれをある程度カバーしたものの農業生産は停滞した。1961年の農業基本法が打ち出した選択的拡大も成功せず、生産は食糧管理制度によって保護された米に集中し、米以外の穀物は兼業農家の増大もあって耕作が放棄され、西欧諸国とは対照的に穀物自給率は急低下した(1960年の83%から1996年の29%へ)。これは、農業経営の規模が零細で(1995年、都府県平均0.9ヘクタール)生産性が低く、国際競争力がないところで輸入制限を緩和していったことによる。その結果、農業経営は悪化し、1960年に606万戸を数えた農家数は1997年に334万戸に減少、しかも農業所得が過半を占める主業農家はその18%を占めるにすぎず、59%が農外収入が農業収入を上回る準主業ないし副業農家、残りの23%は自給農家である。こうした環境のなかで1970年代以降米の過剰生産と食管会計の赤字累積が問題となり、1978年から水田利用再編対策(いわゆる減反政策)が採用された。さらに1980年代に入ってアメリカから米の輸入自由化圧力が強まり、それに対抗するための大規模自立経営による生産性向上が図られてきたが、それに必要な土地所有の流動化にはさまざまな制約があり、農業をめぐる環境はきわめて厳しい。1993年末のガットのウルグアイ・ラウンドにおける多国間農業交渉の結果、1995年以降それまで聖域とされてきた米の輸入が始まり、他方、米価も原則自由化されるに至って、日本の農業生産は大きな転換点に当面しているようである。
林業や水産業においても、世界的な資源不足を背景に困難が増大している。林業では戦時中の乱伐がたたって内需を満たしえず、輸入材への依存が1960年の12%から1980年には56%に増加し、以後もこの水準が続いている。また日本は世界でも有数の水産国であるが、高度成長期以降、沿岸漁業は乱獲と埋立てや公害による海洋汚染によって衰退し、かわって急成長した遠洋漁業も、1970年代以降の各国の領海の拡大、「200海里漁業専管区域」の設定などの国際的潮流のなかで困難に遭遇している。戦前以来の伝統がある南氷洋の商業捕鯨も、国際的圧力のもとで1987年の出漁を最後に終焉(しゅうえん)し、以後はわずかな調査捕鯨のみが行われている。
[柴垣和夫]
企業集団と中小企業
戦前の日本経済における支配的資本は、政商から発展して家産的コンツェルンを形成した三井、三菱、住友などの財閥と、その傘下からはみだして存在した綿工業独占体とから構成されていた。このうち後者は、戦時下の企業整備と戦後の産業構造の重化学工業化の過程で斜陽化して力を失い、前者は、占領下の財閥解体による持株会社(本社)の解散と、家族および親会社による持株支配の排除によって、これも統一的な経済主体としての力を失った。さらに戦後1947年に制定された独占禁止法は、二度の緩和の方向での改正(1949、1953)後もコンツェルンの復活を禁止し、カルテルも原則として禁止していた。その結果、戦後の産業組織は、戦前と異なり競争的性格を強めたが、1950年代以降旧三大財閥系諸企業の再結集が始まり、財閥にかわる企業集団を形成するに至った。その際再結集の手段とされたのが、(1)集団構成企業社長会の結成、(2)集団構成企業相互の株式持合い、(3)集団内金融機関による系列融資、(4)総合商社を軸とした集団内取引、(5)集団構成企業の共同出資による新産業への進出などであった。1960年代に入ると三菱、住友、三井の三大集団以外にも、富士銀行、第一銀行(第一銀行はのち第一勧業銀行となり、富士銀行、第一勧業銀行は合併・再編により2002年4月からみずほ銀行、みずほコーポレート銀行となっている)、三和銀行(現、三菱UFJ銀行)などが融資系列の形成を端緒としてほぼ同様の企業集団を形成し、1970年代には、新日本製鉄(現、新日鉄住金)や電力会社などの例外を除いて、大部分の巨大企業が六大企業集団に包摂されるに至った。各企業集団はそれぞれあらゆる産業分野に構成企業をもち(集団ごとのワンセット主義)、したがって個々の業界における企業間競争は、企業集団間競争の性格をもつに至った。また各集団の構成企業は、それぞれその傘下に多数の子会社、孫会社を擁し、1975年の公正取引委員会の調査によれば、全法人企業における六大集団の社長会構成企業とその傘下企業(親会社の持株比率10%以上)のシェアは、全法人資本金の41%、総資産の31%に達した。もっとも、1980年代以降、省資源とハイテク化によって産業構造が重厚長大型から軽薄短小型にシフトしたこと、また産業資金供給における銀行融資の比重が低下したことにより、企業集団の求心力は低下し、系列を超えた企業間結合の進展を促した。さらに1990年代に入ってバブル崩壊後の平成大不況下で、益出しのための持ち合い株式の売却や金融機関の再編成を通じて、企業集団体制の流動化が進んでいる。
中小企業に目を移すと、製造業ではその中心が、戦前の問屋制下の製糸・織物業から、戦後は重化学工業、具体的には自動車や電機の下請部品メーカーや金属、石油化学などの加工業者に移った。1950年代には大企業との間の付加価値生産性格差や賃金格差が大きく、いわゆる二重構造を形成したが、1960年代以降親企業からの技術移転や金融支援が強化され、高度成長期の労働市場の逼迫(ひっぱく)による労賃騰貴もあって、二重構造は解消の方向に向かった。またソニーや松下のように、技術革新の波にのって中堅企業からさらに大企業に成長するものもみられた。しかし石油危機後の低成長期に入って、ふたたび格差拡大の傾向が生じてきた。流通面では、戦前以来複雑な流通機構のもとで膨大な零細小売商の存在が特徴的であったが、戦後の高度成長期以降、百貨店やスーパーマーケットなど大規模小売店のシェア拡大がみられ、また個人商店の後継者難からそれにコンビニエンス・ストアがとってかわるなど、流通界の再編成が進んだ。同時に、1970年代後半以降の新しい技術革新による産業構造の知識集約化、ソフト化は、いわゆるベンチャービジネスなど中小企業に新しい発展の余地を拡大するものとして注目されてきた。
[柴垣和夫]
国際収支と対外経済関係
国際収支と為替レート
戦後日本の対外経済関係は、1949年(昭和24)のドッジ・ラインにおける単一固定為替レート(1ドル=360円)の設定と中国貿易の遮断、1952年の国際通貨基金(IMF)、1954年の関税および貿易に関する一般協定(GATT(ガット))加盟によって米ドル・ブロックに編入された。貿易における国際競争力の欠如や海運の弱体から、1950年代初頭まで経常収支の赤字をアメリカの援助や朝鮮戦争による特需でカバーする時期が続いたが、高度成長期に入ってからも1960年代中盤まで経常収支の赤字基調は続き、外貨予算割当制度による輸入や技術導入の選別、経常収支改善のための金融引締めが繰り返された。しかし1960年代中盤以降、貿易と資本取引の自由化が進められたにもかかわらず、重化学工業製品の国際競争力の強まりと、それを反映した1ドル=360円レートの円安化によって輸出が急増し、貿易・経常収支は黒字を累積した。一方、長期資本収支は黒字から赤字に転じ、日本は資本輸入国から輸出国に転化した。1970年代に入って、アメリカは円レートの切上げを強く要求したが、日本がそれに抵抗したため、ニクソン大統領は1971年8月新経済政策を発表、これによって金・ドルの交換性を基礎としたIMF体制は破綻(はたん)するとともに、同年12月ワシントンのスミソニアン博物館における先進諸国の通貨調整において1ドル=308円の新固定レートが決定された。しかし金交換性を失ったドルのもとでの固定レート制は安定せず、1973年春に主要国通貨は相次いで変動レート制に移行し、円レートは一挙に1ドル=270円台に高まった。もっとも、同年秋の第一次石油危機による原油輸入価格の高騰によって、1974~1975年の貿易黒字は大幅に減少し、経常収支は赤字化、円レートも1ドル=300円前後にまで低下したが、1976年以降は貿易・経常収支ともに黒字に転じて、円レートは1978年秋の170円台にまで高まった。1979~1980年に勃発(ぼっぱつ)した第二次石油危機は、この傾向を再度逆転させ、貿易黒字の減少と経常収支の赤字化、円レートの急落をもたらした。しかし、輸出の伸張による貿易黒字の増大は1981年以降経常収支の黒字回復をもたらし、その規模は驚異的な勢いで増大した。それに伴って円レートも一時回復に向かったが、それは1981年に入って低落に転じ、経常黒字の累積にもかかわらず1985年秋まで円安・ドル高基調が続いた。この新しい事態は、アメリカのレーガノミックス下の財政赤字による高金利が日本からの対米証券投資の持続的増大を招くという資本移動に規定されたものであった。この異常事態は、1985年秋のG5(先進5か国財務相・中央銀行総裁会議。1986年からG7)以降、円高・ドル安の方向に急速に修正され、1985年春に1ドル=260円にまで下落していた円は、以後一途に上昇した。1995年(平成7)春には史上最高の1ドル=80円を記録するに至ったが、その後は平成大不況下の低金利を反映して1ドル=130円台まで反落している。なお、先に触れた対米証券投資のほか、円高や後述する貿易摩擦を回避するための対外直接投資の急増もあって、1984年以降長期資本の流出は巨額に達し、1985年にはアメリカが純債務国に転落したのに対して日本は世界最大の債権国に登りつめた。
[柴垣和夫]
貿易の構造と対外経済摩擦
第二次世界大戦前の日本貿易は、(1)対中国・アジア綿製品輸出、原料輸入、(2)対米生糸輸出、対欧米重化学工業品輸入を機軸とし、1930年代以降、(3)対アジア重工業品輸出が加わったが、戦後は産業構造と国際政治環境の変化で大きく変わった。品目別でみると、輸出では、1950年代にはなお繊維をはじめとする軽工業品が中心を占めたが、1960年代に入ると鉄鋼、機械など重工業品の比重が高まり、とくに1970年代以降は、自動車、電気・電子機器を中心とする機械類が圧倒的割合を占めるに至った。他方輸入では、原燃料および食料の占める比重が一貫して高く、とくに二度の石油危機による原油価格の高騰によって、1980年代初頭には鉱物性燃料が全輸入の約半分に達した。このような原燃料輸入・工業製品輸出という垂直分業的貿易構造は、第二次世界大戦後、欧米諸国が先進国間の水平分業による製品貿易を特徴としているのと比べて、日本貿易の大きな特徴であった。同時にそれは、輸出品は需要の所得および価格弾力性が高く、輸入品のそれが低いことを意味するため、変動為替レート制の輸出入調節機能を弱め、日本貿易の絶えざる出超基調をつくりだす要因ともなった。もっとも1980年代後半以降、アジアNIES(ニーズ)(新興工業経済地域)やASEAN(アセアン)(東南アジア諸国連合)諸国の工業化の進展に円高、原油安が加わって、主としてアジアからの製品輸入が急増し、全輸入に占める製品比率は1989年に50%を超えるに至った。次に貿易の地域別構成をみると、輸出ではアジアと北アメリカが長らくほぼ3分の1ずつを占めていたが、1990年代に入って前者の比重は45%に高まり、後者の比重が25%前後に低下した。また、ヨーロッパの比重は1950年代の10%程度から1970年代後半以降20%を占めるに至った。輸入では、1950年代中は北アメリカの比重が4割台を占め、アジアが3割程度であったが、1970年代とくにその後半以降、原油高騰による中東の比重増大と日中国交回復の影響もあってアジアの比重が5割台に達し、北アメリカの割合は2割台に低下した。輸出入とも、先の垂直分業的品目構成を反映して、開発途上国の比重が高い点に、他の先進諸国と比較しての日本の特徴がある。さらに、二国間貿易収支が、産油国である中東諸国やカナダ、オーストラリアなどの資源国に対して入超であることが、他の諸国に対する出超幅を拡大する結果となり、貿易摩擦を増幅する原因となっている。
日本の輸出は第二次世界大戦後一貫して世界貿易の伸びを上回るスピードで増大したため、各地で厳しい貿易摩擦を引き起こしてきた。そこには日本の産業構造が軽工業から重工業へ、重工業のなかでも基礎素材産業から耐久消費財、機械工業へ、さらにはハイテク産業へと高度化してきた際の主役が次々に登場してきていた。1980年代には二国間貿易における日本の出超そのものが摩擦の原因とされる傾向が強まるとともに、貿易摩擦回避のための対外企業進出が、現地資本との競合から投資摩擦を引き起こすという、対外経済摩擦の複雑化が進行している。
[柴垣和夫]
債権国化と企業の多国籍化
第二次世界大戦前の日本では、第一次世界大戦以降の綿業の中国進出(在華紡)、1930年代以降の朝鮮・中国東北部への重化学工業の進出といった対外直接投資がみられたが、他面では絶えず外債に依存し、全体としては資本輸入国であった。戦後も1960年代中盤まで、アメリカの長短外資で経常収支の赤字をカバーする資本輸入国であったが、1965年以降フローで、1968年以降ストックでも資本輸出が輸入を上回るに至り、債権国に転化した。短資を除く長期資本の流入は、1960年代は借款が中心だったが、1970年代以降証券投資が圧倒的比重を占めるようになり、直接投資の比率は一貫して小さい。長期資本の流出では1960年代中盤まで、商品輸出に伴う延払い信用が過半の割合を占めたが、1970年代以降は借款(主として開発途上国向け)、証券投資(主として先進国向け)、直接投資がともどもに増大して、この三者で大部分を占めるに至った。対外直接投資は1970年代中盤まで、安い労働力を目当てとした東南アジア向け製造業投資(繊維および中小企業)、鉱産物資源を目当てとした対資源国投資、商品輸出促進を目当てとした先進国向け商社、銀行の進出の3類型に分かれていたが、1980年代とくにその後半以降、対米欧貿易摩擦の激化に伴い、米欧先進国向けの製造業投資(電気・電子、自動車など機械中心)が急増した。商社、銀行に続く製造業大企業の米欧進出は、日本企業の多国籍企業化を意味するものであり、それは、日本企業の国際的適応能力を試すものであると同時に、法人資本主義(大株主のほとんどが法人で、経営が社員から昇進したサラリーマン重役によって営まれる企業体)と終身雇用、年功賃金、企業別組合に特徴づけられる「日本的経営」の国際的適用可能性を検証する機会となった。そこには欧米と日本との風土、文化の違いによるさまざまな摩擦が生まれているが、同時に両者の相互浸透による融合(ハイブリッド化)もみられる。製造業分野では日本企業の積極的多国籍企業化が進んでいるのに対して、銀行、証券、保険など金融面では、為替取引の自由化の進展やバブル崩壊後1990年代の業界の困難のもとで、外資の日本進出が顕著である。
[柴垣和夫]
経済協力とその問題点
開発途上諸国の経済開発を目的とした経済協力の概念には、広義には民間ベースの輸出信用や直接投資が含まれるが、厳密には政府開発援助(ODA)に限定すべきであろう。日本のそれは、1950年代に戦時中に日本が侵略したアジア諸国への賠償の形で始まったが、本格化したのは1960年にOECD(経済協力開発機構)のDAC(ダック)(開発援助委員会)に加盟し、国際収支にも余裕ができた1970年代以降のことである。とくに1976~1980年、1981~1985年の二度にわたりODA倍増計画が実施された結果、1984年には43.2億ドルとアメリカに次ぐ第2位に達したが、その対GNP比は0.35%でDAC加盟国平均(0.36%)を下回り、1971年のUNCTAD(アンクタッド)(国連貿易開発会議)第3回総会で公約した目標0.75%には、なおほど遠い状態にある。さらに、ODAは贈与と有償に分かれるが、日本の贈与比率は46%(1984)で、DAC平均の77%をはるかに下回っている。政府は1985年に新たに第三次中期目標を定め、1986年から7か年計画でODA倍増、無償協力の拡充を打ち出した。その結果1987年には「援助疲れ」のアメリカにかわって日本のODAは世界第1位となり、以後も金額ではほぼその地位を保っている。日本のODAの内容には次のような特徴が指摘されてきた。すなわち日本の位置からしてアジア向けが大きい比重を占めるのは当然としても、その割合は総額の3分の2を占め、最貧国の多いアフリカ向けは15%程度を占めるにすぎない。またフランスや北欧諸国のODAが教育、文化、衛生などにかなりの比重を置いているのに対して、日本のそれは産業基盤や鉱工業など経済関連が過半を占め、しかもしばしば独裁政権である現地政権の利害と結び付いた大型プロジェクトが多い。そのため、その建設には日本の大企業が参加し、資材も日本製品が調達されることから、汚職の舞台となりやすく、また現地民衆の目には日本資本の経済侵略とさえ映ることが多かった。さらに日本のODAは、アメリカの軍事的・政治的性格の強いODAの肩代りという性格をもつことがあり、その点で民衆レベルの不信を招くこともあった。規模はまだ小さいが好評を博している農業協力や技術協力、青年海外協力隊の活動などを拡充すべきだとの声が強い。また西欧諸国で活発なNGO(非政府組織)による民間ベースの協力拡充も、今後の課題となっている。
[柴垣和夫]
金融・財政制度とその構造
金融制度と金融市場の特徴
後発国としてスタートした日本の経済成長にとって、銀行を中心とする金融機関の役割は、戦前以来戦後の高度成長期を通じてきわめて大きかった。日本の金融制度は、中央銀行としての日本銀行を頂点として、全国銀行(都市銀行、地方銀行、信託銀行、長期信用銀行)、中小企業金融機関(第二地方銀行、信用金庫、商工組合中央金庫など)、農林水産金融機関(農林中央金庫、農協や漁協の信用事業など)、保険会社(生命保険、損害保険)などの民間金融機関と、郵便貯金や簡易保険、公的年金資金などの政府資金を原資とする各種の政府金融機関、および株式や事業債による資金調達を媒介する証券会社から成り立っている。日本では個人(家計)部門が一貫して資金過剰(貯蓄超過)で、そこでの貯蓄が前述の諸金融機関や証券会社を通じて、その他の資金不足部門に供給される構造が形成されてきた。最大の資金不足部門は、1970年代(昭和45~54)初頭までは、経済の高度成長を反映して企業部門であり、その後は、低成長への転化と財政赤字の累積によって公共(政府)部門がとってかわった。海外部門は、資本輸入国から輸出国への移行に伴い、資金過剰部門から不足部門に転化している。
企業部門への産業資金供給状況をみると、株式を通じる直接金融の比重が大幅に低下し、民間金融機関貸出による間接金融の比重が高まったことが、戦前と戦後を比較した場合の大きな変化であった。戦後は、高度成長期を通じて企業の内部資金(減価償却、内部留保)による充足度が低下し、外部資金依存度が高まったが、低成長への転化とともにその傾向は逆転した。外部資金のなかでは、1960年代中盤までの第一次高度成長期には民間金融機関貸出の比重が高まり、とくに都市銀行は貸出資金の不足からそれを日銀借入に依存するオーバーローン状態が生まれた。その結果、この時期の日銀の金融政策は、公定歩合政策と都市銀行に対する貸出の直接的な量的規制の組合せという独特な形をとり、議論の的となった。1960年代後半以降、とくに石油危機以降は、企業の資金調達ルートの多様化、内部資金の充実が相まって、産業資金供給に占める民間金融機関とりわけ都市銀行の比重は低下した。金融政策の手段も、1965年の国債発行開始もあって、売りオペ・買いオペ(銀行振出手形、長期国債、政府短期証券など金融資産の売買)などの公開市場操作など多様化した。
[柴垣和夫]
金融の自由化と国際化
高度成長期の金融市場は、臨時金利調整法(1947)による統制金利に基づく資金の統制的配分によって特徴づけられていたが、第一次石油危機後の国債増発は、その消化問題を通じて金利の自由化をもたらす契機となった。すなわち、1965年に始まった国債発行は、発行1年後の日銀買いオペの保証によって市中金利と隔離された発行条件で、都銀を中心とした引受シンジケート団によって消化されていたが、1975年以降の大増発はかかる方式での消化を困難にし、シンジケート団が引受けを拒否する事態を生み出した。そこから国債の種類の多様化、発行条件の弾力化、公社債流通市場の整備・拡大を通じて、自由金利市場が創出されることになった。既発債の現先(げんさき)(債券現先取引、債券を一定期間後に買い戻すか売り戻す条件で売買する取引)市場の拡大と関連して銀行に自由金利の譲渡性定期預金(NCD)の発行が認められ、1980年代に入るとコール・手形市場を含めて短期金融市場は完全に自由化され、同年代後半には、長期金利、長短預金金利も完全に自由化された。それに伴って証券会社による個人貯蓄を対象としての中期国債ファンドなど自由金利商品が開発され、その結果なお規制金利下にあった銀行預金などからの資金流出が生じたが、銀行側は国債の窓口販売やディーリング業務を開始して対抗した。これは、銀行と証券とを隔てていた業務の垣根の低まりを意味するものであり、ほかにも公的年金抑制の動きに対応して銀行、証券、生保が一斉に開始した年金商品の登場とともに、金融界における分業体制の流動化が進んだ。
このような金融自由化の動きは、1980年(昭和55)の外為(がいため)法改正による対外取引の原則自由化を契機として、金融の国際化へと発展し、資金調達面ではインパクト・ローンの取り入れ、外債とくに外貨建て転換社債の発行が急増した。資金運用面では、レーガノミックス下のアメリカの高金利を目当てに、外貨預金や外債(とくにアメリカ財務省証券)投資が急増した。しかも調達、運用のバランスでは圧倒的に運用超過で、そこにアメリカの債務国への転化と裏腹に、資本供給(輸出)国日本の国際金融市場での地位の高まりが認められる。金融の国際化は、1983年のレーガン訪日を機に表面化したアメリカの対日金融開放要求とも絡んで展開し、ユーロ・円市場の開放、円建てBA(銀行引受手形)市場の創設など円の国際化が進んだ。なお、以上のような金融の自由化・国際化を支える技術的要因として、コンピュータによるネットワークの形成や現金自動支払機の導入など、金融面での技術革新が急速に進んだことも見逃せない。
[柴垣和夫]
金融不祥事と金融システム改革の動き
既述のように、1980年代後半の好況期末期に生じたバブルは、一般物価が安定しているもとでの株価と地価の騰貴、つまりは資産インフレをもたらしたが、この過程で銀行は、自らないし子会社のノンバンクを通じて放漫な財テク資金の貸出し競争に狂奔し、それがバブル崩壊後には回収困難な不良債権に転化して深い痛手を負った。証券会社もまた、バブル崩壊による株価の急落に際して顧客への対応に苦しんだ。この過程で、一方では銀行や証券会社の総会屋や暴力団との関係が明るみに出るとともに、他方では接待攻勢による金融機関と大蔵省との癒着が暴露され、同省の監督責任が問われた。加えて平成大不況下で、1995年(平成7)以来3年に及ぶ公定歩合0.5%という超低金利が、公共投資等の財政手段とともに不況回復に効果が発揮できないところから、金融システムの根本改革の必要が世論となった。それには1997年6月に一斉に登場した(1)金融持株会社の設立を一つのねらいとする独占禁止法の改正、(2)日銀の独立性と透明性の向上をねらいとした日銀法の改正、(3)金融監督庁(現、金融庁)の大蔵省(当時)からの独立などがあるが、最大の目標は同じ6月に金融制度調査会、証券取引審議会、保険審議会の三者(いずれも金融審議会に統合)が共同で蔵相に提出した日本版金融ビッグバンの実現にある。しかし、その効果の当否については必ずしも楽観できないように思われる。
[柴垣和夫]
財政制度と政府部門の比重
戦前の財政制度は、明治憲法のもとで議会のコントロールが弱く、地方財政もほとんど自主性をもたなかった。戦後新憲法のもとで制定された財政法は、財政民主主義の原理にのっとり、また戦時インフレの反省から赤字国債の発行禁止や日銀の国債引受けを禁止した。財政制度は中央財政と地方財政とに分かれ、それぞれ一般会計と特別会計から成り立っている。地方財政では、特別会計のうち独立採算制をとる公営企業会計などを除いたものを一般会計とあわせて普通会計と称する。いずれの会計も年度ごとの歳入と歳出について予算と決算があり、国会または地方議会の議決事項となっている。年度途中に事情の変更で追加修正された予算を補正予算といい、年度開始前に予算が成立しない場合は、成立までの措置として暫定予算の制度がある。なお前述のほか、政府が行う金融活動の制度として財政投融資があり、郵便貯金、公的年金積立金などからなる財政投融資資金(かつては資金運用部資金とよばれていた)、簡保資金、公募債、借入金などからなる原資が、各種特別会計、政府系金融機関(銀行、公庫)、公団、地方団体などに投融資され、それぞれの事業資金をなすとともに、その一部は政府系金融機関を通じて民間に貸し出されている。
ところで、戦前の日本では後発資本主義国として政府部門の役割は量的、質的にきわめて大きかったが、戦後は経済成長が民間主導型であったこと、平和憲法の制約により軍事費が極度に抑えられたことにより、量的側面では先進国のなかで例外的な「安上りの政府」を実現した。高度成長期の中央、地方を純計した政府支出(経常支出プラス資本支出)の対GNP比、租税負担の対国民所得比はいずれも20%以下で、30ないし40%台の欧米諸国と比較するとはるかに低かった。しかし、このことは財政の果たした質的役割の大きさを否定するものではなく、政府支出の内容は経常支出と固定資本形成――その中心は道路、港湾、橋梁(きょうりょう)など産業基盤向け社会資本形成であった――がほぼ半々の割合で、後者の比率がきわめて高い点に欧米諸国との差があり、その点に資本蓄積促進的性格が表現されていた。しかし1970年代に入ると、後述の社会保障費の増大を反映して政府支出の対GNP比とくに経常支出のそれは上昇の傾向を示し、また低成長への転化を反映して国民所得に対する租税負担率も増大した。1980年代以降、政府支出の対GNP比とくに資本支出の比率が低下しているのは、財政危機打開のための臨調・行革路線を反映したものである。
[柴垣和夫]
財政危機と行革路線
戦後の財政収支は、1949年(昭和24)のドッジ・ラインで戦後インフレを克服したのち、第一次高度成長期には黒字基調で推移した。シャウプ税制改革による直接税(個人所得税、法人税)中心の租税構造のもとで、政府見通しを上回る経済成長が巨額の自然増収をもたらしたからである。1965年の不況に際し、建設国債と戦後の財政法が禁止する赤字国債が発行されたが、第二次高度成長の到来によって国債発行は漸減した。ところが第一次石油危機の勃発(ぼっぱつ)による深刻な不況下に、その克服のための公共投資と、時期を同じくして生じた社会保障費の増大をまかなうために大量の国債発行(その約半分は赤字国債)が行われ、年々の一般会計国債依存度は1970年代後半以降30%を超えるに至った。1979年、財政再建を目ざしての大平内閣による一般消費税(大型間接税)導入の試みは、世論の反発にあって頓挫(とんざ)し、1980年代初頭に政府長期債務残高は財政規模の2倍を超えるに至った。
この財政危機に遭遇して、財界の意を受けた政府は、おりから「小さな政府」のスローガンを掲げて登場したイギリス・サッチャー政権、アメリカ・レーガン政権に呼応して、第二次臨時行政調査会を設けて、行政改革による「増税なき財政再建」路線を打ち出した。1982年度予算以降、概算要求のゼロ・シーリングによる厳しい歳出抑制が図られたが、アメリカの強い圧力による防衛費と対外経済協力費の「聖域」化による突出のために、抑制の「しわ」は公共投資と福祉、文教など民生費に寄せられる結果となった。防衛費については、1976年10月三木内閣による「GNPの1%以内」とする歯止めがあったが、それは中曽根内閣による1987年度予算編成で破られた。こうして1984年度赤字国債ゼロを目ざした「増税なき財政再建」路線は失敗し、一度見送られた大型間接税の導入は1989年度予算で「消費税」という形で実現した。その税率は当初3%であったが、1997年4月に福祉財源に充当するためとして5%に引き上げられ、おりからの平成不況のもとで消費者の消費性向をいっそう低下させる効果をもたらした。人口構成の高齢化が急速に進んでいる状況のもとで、将来の社会保障費の増大は避けられず、そのための負担のあり方、財源調達方法をめぐる問題は、財政にかかわる重要な争点となっている。
[柴垣和夫]
社会・労働問題と国民生活
労働市場の特質
戦前、明治期の労働力は、婚期前の農家子女の出稼ぎ的繊維女工と鉱夫および職人によって構成され、労働市場も流動的であったが、第一次大戦後重化学工業が発展するに及んで、男子労働力を中心とする労働市場が形成され、それはしだいに大企業本工を中心とする終身雇用的労働力と、流動的な非熟練労働力とに分化し、労働市場の二重構造の原型を形成した。戦後の本格的重化学工業化は、この原型を一般化し、終身雇用を旨とする大企業本工層での年功序列賃金体系の確立とともに、この層と大企業の社外工、臨時工、中小企業就業者との間の賃金格差が定着した。もっともこの格差は、高度成長過程での労働力需要の増大、とくに新規学卒若年労働力需給の逼迫(ひっぱく)、その結果としての初任給賃金の急速な上昇を通じて縮小する傾向がみられたが、石油危機後の低成長への転化と労働力需給の緩和とともに、その傾向は鈍化している。ちなみに労働力需給は、高度成長始点の1955年(昭和30)の完全失業率2.5%、有効求人倍率0.22から逼迫のピークである1970年のそれぞれ1.1%、1.41に達したのち、1970年代後半以降はそれぞれ2%台と1倍以下で推移してきたが、1980年代後半のバブル期に求人倍率が1を超えたものの、その崩壊後はふたたび1を割り、失業率も1995年(平成7)以降3%を超え、1998年には4%を突破、2001年には5%台に突入した。
低成長期に入って以降の労働市場の顕著な特徴としては、以下の4点が指摘できる。第一は、女子の労働力率が上昇したことで、婚前のそれは高度成長期以来のことであるが、近年は子育てが終わったあとの中高年女子の労働市場へのパートとしての復帰が著しい。これは、子供の数の減少、家事労働の負担減、世帯主賃金上昇率の鈍化といった供給側の条件に加えて、産業構造の「軽薄短小」化、第三次産業の比重増大といった需要側の要因がある。第二は、上の点も一部は重なるが、企業の減量経営や経済のサービス化とともに、独立した専門技能者に対する非固定的雇用が増大していることで、1986年(昭和61)にはこうした人材の斡旋(あっせん)事業を可能にする労働者派遣法が施行された。第三は、中高年労働力の雇用問題で、一つには長寿化に伴う定年延長の動きが高まり、これは年功賃金カーブの傾斜を低め、あるいは給与ダウンと抱き合わせで広まる傾向にある。その二は新しい技術革新への中高年労働者の適応問題で、この点は職業訓練や技能再教育の問題として取り組まれつつある。
第四は、とくにバブル崩壊後の1990年代に入って、長期不況と金融業への外資の進出に影響されて、終身雇用、年功賃金といった企業内労働市場の日本的特質が流動化しつつあることである。
[柴垣和夫]
労働組合と労働運動
戦前においては、第一次大戦の戦中、戦後の重化学工業化とともに労働争議件数、参加人員が飛躍的に増大し、労働組合の組織化も進んだが、政党系列化による分裂のために大きな社会的影響力はもちえず、共産党系の労働運動が政府の弾圧によって消滅したのちは、戦時体制下の産業報国運動に吸収される結末となった。戦後改革による労働基本権の公認は、おりからの生活難を背景に労働運動の高揚をもたらしたが、その際、組合組織が産業別単一組織として再建された全日本海員組合を例外として、戦時中の産業報国会支部組織を事実上継承した事業所別・企業別組合の形態をとったことにより、終身雇用、年功賃金、企業別組合という「日本的労使関係」の三特質が出そろうことになった。運動のイニシアティブは、戦後当初は共産党に指導された産別会議がとり、生産管理闘争などのラジカルな争議を展開したが、占領軍による2.1スト(1947)中止命令やその後のレッド・パージによって衰退し、1950年(昭和25)7月に社会党系の総評(日本労働組合総評議会)が結成された。しかし朝鮮戦争の評価と講和問題をめぐって左傾した総評主流に対して右派が反発、1954年に民間単産を中心とした全労会議(全日本労働組合会議、のち1964年全日本労働総同盟に発展改組)が分離した。この間、官公労を中心とした総評は、1955年以降春闘を組織することで日本型賃金闘争のパターンを確立する一方、当時、一部の重工業や斜陽化しつつあった石炭産業で頻発した解雇・合理化に激しい反対闘争を展開した。しかし、後者の闘争は、1960年の三井三池炭鉱争議の敗北以降、高度成長による労働力需給の逼迫とともに影を潜め、財閥解体後一般化したサラリーマン経営者の開明的労務政策と、民間労組指導者の労使協調路線とが結合して、「日本的労使関係」の内実が安定した。ただ官公労は、占領下に制限された労働基本権の奪還や、勤務評定(日教組)、マル生=生産性向上運動(国労、動労)反対でストを繰り返した。
第一次石油危機後の1974年春闘で、労働側は賃上げ率35%という成果をあげたが、それ以降労働争議件数は激減、労働運動は沈滞した。低成長下の雇用不安のもとで、「賃金よりも雇用」が労使双方の重視するところとなり、欧米諸国の場合とは対照的に、合理化と減量経営に対する労働組合の協調、その結果としてのロボットの導入やME(マイクロエレクトロニクス)革命をてことする労働生産性の向上が実現した。これを推進したのが1982年12月に結成された全民労協で、その延長線上で1989年(平成1)11月には一部左派系の労組を排除して新ナショナルセンターとして日本労働組合連合会(連合)が発足、総評もそれに合流した。ところで、こうした「日本的労使関係」の安定性は、諸外国の注目するところとなった。しかし、その点を一因とする日本製品の国際競争力の強さは、諸外国との間で激しい貿易摩擦を招き、また急速な円高をもたらし、企業の海外進出を促した。それによる国内の産業空洞化は新しい雇用不安を生み出しており、その点への対応は、欧米諸国に比してはるかに長い労働時間の問題とともに、労働運動の新たな課題となった。さらにバブル崩壊後の1990年代には、企業のリストラが失業率の4%台への上昇を招き、また整理が中間管理職層にまで及んだことから、管理職組合が結成されて話題をよんだ。
[柴垣和夫]
福祉と社会保障
戦前の日本にも、救貧政策と軍人・官吏に対する恩給制度は明治期以来存在し、勤労者を対象とした健康保険と厚生年金の制度は昭和期に入って形成されたが、そのカバーする範囲は狭く、福祉対策の大部分は家族制度や企業内福利にゆだねられていた。戦後になって、新憲法が生存権規定を取り入れ、イギリスのビバリッジ報告(1942)が紹介されるに及んで、国民の権利、政府の責任としての社会保障の制度化が課題となった。しかし当初は、生活保護(公的扶助)と失業対策に追われ、社会保障の中枢をなす医療と年金について、制度としての国民皆保険が確立したのは、国民健康保険と国民年金制度が発足した1961年(昭和36)のことであった。このような立ち後れをもたらした背景には、このころまでなお社会保障を代位する農村の家族共同体が維持されていたことと、経済の高度成長により所得水準が向上したことがある。ところで、第二次高度成長過程で公害問題その他の社会問題が深刻化し、高齢化社会の到来が予測されるに及んで、それまで一途に成長を目ざした国民の関心が福祉に向けられ、大都市圏に簇生(そうせい)した革新自治体が、老人医療の無料化をはじめとする福祉に重点を置いた行政を展開した。1973年の「5万円(国民)年金」の実現とすべての年金への物価スライド制の導入、老人福祉法改正による70歳以上の医療費自己負担分の公費肩替り制度の採用は、こうした動きの帰結であり、ジャーナリズムはこの年を「福祉元年」とよんだ。
しかし1973年は石油危機が勃発した年でもあった。これを境に経済が低成長に転じたにもかかわらず、社会保障費は膨張して財政赤字拡大の一因となった。年金の成熟化、医療技術の高度化や医薬品の高額化、人口構成の高齢化による有病率の上昇などが、社会保障財政の膨張を加速した。ここにおいて「福祉国家」の建設を標榜(ひょうぼう)していた政府は、一転して「福祉見直し」に転換し、1980年代に入るとサッチャーイズムやレーガノミックスに呼応して「自助努力」を強調しての福祉政策の手直しが始まった。老人医療や被傭(ひよう)者保険本人の一部自己負担導入、年金支給開始年齢の引上げのほか、とくに公費負担軽減のために医療・年金両保険を通じて乱立している制度の調整、統一を図る施策が展開されている。さらに差し迫った超高齢化社会に備えて、1997年には介護保険法が成立し、ドイツに続いてその実施が日程に上っている。いずれにせよ、本格的高齢化社会の到来を目前にして、福祉の問題は今後も大きな政治的争点となり続けるであろうことが予想されている。
[柴垣和夫]
国民生活の諸問題
第二次世界大戦で焦土と化してから戦後50年余、国民の生活は大きく変わった。敗戦直後の飢餓線上の生活から、衣食に関してともかく充足できるようになるまでに約10年、その後約20年続いた経済の高度成長過程では、衣食の質的向上、家庭電気機器や自動車など耐久消費財の普及によって、生活内容の高度化を実現した。住宅についても量的不足は解消した。しかも、戦前には顕著であった生活水準の所得別格差、地域別格差も大幅に縮小し、先進国のなかでももっとも生活水準が平準化した社会が実現した。日本では、大衆的な「豊かな社会」が実現したのである。
しかしながら、この「豊かさ」の内容にもう少し立ち入ってみたとき、そこにある種の不均衡と問題点が潜んでいることに気がつく。それは高度成長が終焉(しゅうえん)したここ20年ぐらいの過程で徐々に自覚されてきた点であるが、以下の2点に要約することができよう。第一は、この「豊かさ」が物質面での個人的消費に集中し、その点が突出していることである。それは「飽食の時代」といわれる食生活に典型的に現れている。ダイエットが大衆的に流行する社会は、はたして健康な社会であろうか。衣料や耐久消費財についても、性能、品質を超えてデザインによる製品差別が販売戦略の焦点になる社会は、むしろ「過剰富裕化」社会というべきであろう。この点は、資源が有限な地球において、なお億を超える飢餓線上の人々が存在することを考慮するとき、深刻に考えるべき問題であろう。第二に、前記の点とは裏腹に、社会的・文化的消費の面でなお日本は立ち遅れている。その点は、下水道普及率が西欧諸国の2分の1にすぎず、大都市の1人当り公園面積が欧米の都市たとえばロンドンの10分の1であることに端的に示されている。住宅も量的には充足したものの、質的には「遠、狭、高(価)」との悪名が高い。仕事のためには残業や単身赴任もいとわないが、もともと短い有給休暇さえ消化せず、したがって余暇を趣味やスポーツ、芸術の鑑賞に費やす習慣に乏しい。
以上のような生活構造のゆがみは、戦後の日本経済の成長において、なによりも企業の成長と発展が優先され、政策的にもそれが助長されてきた結果もたらされたものといっていい。そして企業は、いまや「経済大国」日本を代表する存在として、国際舞台でも最強の存在となっている。企業社会がそのような高みにまで到達した現在、今後の日本の課題は、企業の外側の社会――それは家庭であり地域社会であり、また別の言い方をすれば、経済の外の世界すなわち広義の文化の世界であるが――の充実にあるのではなかろうか。そしてそれを国際的な広がりのなかで実現してゆくことが必要なのではなかろうか。戦後50年余をかけて達成された「経済」の「成果」は、いまや「経済」の外の世界の重要性を提起しているように思われる。
[柴垣和夫]
社会
総論
20世紀を振り返ってみると、日本人一般にとって、前半は戦争と貧困の世紀であり、後半は平和と繁栄の世紀であった。1945年(昭和20)の敗戦を契機として、日本は国家目標を軍国主義から経済主義に変えた。この結果、日本は1980年代に経済大国となり、人々の生活は豊かになった。
国際関係では、1960年代から急速に経済のグローバル化が進展し、国家間、国民間の相互浸透が進んできた。このなかで、1970年代から日本経済が急成長してきた。日本人の生活の基盤は基本的に対外経済に依存するようになった。それとあわせて、多量のモノとカネと情報、さらに人が日本に流入し、日本から出ていくようになった。1980年代からは、情報通信技術が急速に発達してきている。モノと人の輸送手段も多様となり、速度もあがった。現在、電気通信、コンピュータの発達、とりわけパソコンの普及によって、私たちの日常生活はかなり便利になり、また、国内外を問わず、各地の情報にアクセス(接続)することが非常に容易になっている。
家庭においては、核家族化がいっそう進行し、高齢化、少子化などの問題が、とりわけ1990年代から社会問題となっている。
[初瀬龍平]
国際化の進展
国際化は、1980年代後半から1990年代前半にかけて日本社会全体の流行語となり、各処で政策課題、実践問題となった。1990年代後半から現在に至っても、依然として国際化は社会的課題である。
日本人は世界経済のなかに生きている。多くの人々が海外と関係する生産、投資、流通、観光などの仕事によって生計をたてている。それ以上の人々が消費者として、海外との経済関係に関係している(商品、観光)。1995年(平成7)の貿易は、輸出40兆9442億円、輸入29兆4201億円であった。これは世界全体の貿易の15%に上る。
輸出では、1995年に輸出額の74.7%が機械機器であった。国内生産のうち、時計の88.0%、バイクの75.0%、VTRの69.8%、複写機の65.1%、カメラの60.5%、ファクシミリの54.2%、合成繊維短繊維の45.9%、乗用自動車の38.1%、テレビ受信機の38.0%、電卓の37.6%が輸出された。輸出売上額(1996年3月決算)では、トヨタ自動車2兆6276億円、松下電器産業(現、パナソニック)1兆4446億円、日産自動車1兆3100億円、本田技研1兆2750億円、ソニー1兆2506億円、東芝1兆1470億円にも上った。売上げに占める輸出の比率では、キヤノン79%、ミノルタ(現、コニカミノルタ)77%、シチズン時計71%、ソニー65%、本田技研52%、任天堂40%となっている。さらに日本企業は、海外に直接投資をして、現地生産をしている。全生産のうち、海外生産の比率(1994)は、カラーテレビ78.0%、ステレオ69.3%、電子レンジ67.8%、VTR53.3%、冷蔵庫44.6%、自動車30.5%である。海外直接投資は、1995年に4兆6402億円であり、1951年~1994年度の累計では、7万7507件で4636億ドル(うち北アメリカ43.7%、ヨーロッパ19.4%、アジア16.4%)となっている。このような経済効果は、裾野(すその)の下請企業にまで広く及んでいる。
しかし、その他の情報、サービスなどの移動については日本社会、経済の動きはかなり受動的である。1995年に貿易以外のサービス(輸送、旅行を含む)収支は5兆6469億円の赤字であった。貿易収支が黒字、貿易外(サービス)収支が赤字という国際収支の構造は、1964年(昭和39)以来続いている。技術の輸出入(1995年度)では、日銀データ(商標、使用権を含む)によると、輸出60億ドル、輸入94億ドルと34億ドルの入超である。このうち、北アメリカ、ヨーロッパに対しては大幅の赤字、アジア、アフリカ、南アメリカに対しては圧倒的黒字である。
ソフトウェアの輸出入(1995)でみると、ゲームソフトを除けば、輸出39億円、輸入3926億円と大幅赤字である。パソコンに関しても、CPU(中央演算装置)もOS(基本ソフト)もほとんどがアメリカ製である。そのなかで例外的なのが、ゲームソフトと漫画である。ゲームソフトは輸出769億円、輸入45億円と圧倒的に輸出超過である。漫画は1980年代にアジア(とくにタイ)で『ドラえもん』などが人気を博し、1990年代にはヨーロッパ(とくにフランス、ドイツ)で『AKIRA』などの人気が高まった。
現在、私たちは日常の生活用品の多くを海外からの輸入に頼っている。食品のパン、うどん用の小麦、豆腐、しょうゆ用の大豆、梅干しの梅、バナナ、グレープフルーツなどの果物、蒲焼(かばや)きのウナギ、燃料のガソリン、LNG(液化天然ガス)、LPG(プロパンガス)、住宅の木材、合板、衣料の羊毛、綿花、麻などがその例である。最近では衣類、時計、カラーテレビ、VTRなどにも輸入品が出回っている(その多くは日本企業による海外生産品の逆輸入である)。
人の国際移動も活発である。出国日本人は2000年(平成12)に1781万8590人であった。目的別では1458万2476人が観光(その他含む)、259万9173人が出張、留学・学術研究・調査等が29万4180人、永住が13万0251人、5万5119人が転勤であった。海外在留邦人数は、1996年の総数は48万1000人、うちビジネス(長期滞在)が29万人、留学・研究が11万8000人である。彼らの滞在先は、ビジネスでは北アメリカが37.4%、アジア35.7%、ヨーロッパ19.0%、研究・留学では北アメリカ53.3%、ヨーロッパ32.5%、アジア8.0%である。日本人の海外渡航の場合、短期が圧倒的に多く、長期滞在者が少ない。
国内では在日外国人の数が、1970年から1996年までの間に約2倍になっている。2001年末の外国人登録数は177万8462人である。国籍別の内訳は、韓国・朝鮮63万2405人、中国38万1225人、ブラジル26万5962人、フィリピン15万6667人、ペルー5万0052人、アメリカ4万6244人となっている。近年目だつのは、韓国・朝鮮国籍以外の外国人の増加である。いまでは彼らが在日外国人の半数以上を占めるまでになった。ブラジル国籍とペルー国籍の人の多くは、日系人であり、ある意味では日本社会へのUターン組である。また、2001年現在1万9140人登録されているベトナム国籍の人のほとんどは難民として受け入れられているから、日本社会にとって新しいタイプの外国人である。
かつて在日外国人の9割近くが韓国・朝鮮国籍の人たちであった。しかし、その比率は次第に減少し、1985年に80%、1994年に半数、1996年には50%以下となり、2001年では35.6%となっている。その減少は絶対数でも起こっている。その数は1991年に69万3000人であったが、2001年には63万2405人となっている。減少の理由は、彼らのうちから日本国籍を取得する者が出ていることである(帰化あるいは子供の国籍)。しかし、日本国籍を取得した者も、以前の生活、文化を保持しているから、彼らのコミュニティ(小社会)が消えかかっているわけではない。むしろ注目すべきことは、最近におけるそのコミュニティ構成員の変化である。
在日韓国・朝鮮系の人々は、三世、四世の時代に入りつつあり、1960年代以降生まれのものが、すでにその半数を占めている。結婚を例にとれば、1992年の結婚総数のうち、韓国・朝鮮系の女性と日本籍男性の結婚が54.4%、韓国・朝鮮系男性と日本籍女性の結婚が27.5%である。三世、四世のアイデンティティ(帰属意識)は本国の同胞と切り離れつつある。彼らは韓国系でも朝鮮系でもなく、日本人でもない、独自の文化を形成しつつある。
近年、在日外国籍住民の居住地域で偏りが目だつようになっている。都道府県別(2001)でいえば、韓国・朝鮮系は大阪、東京、兵庫に、中国系は東京、神奈川、大阪に、ブラジル系は愛知、静岡に、フィリピン系は東京、千葉、神奈川に、アメリカ人は圧倒的に東京に、ペルー人は神奈川、愛知、静岡に、ベトナム人は神奈川、兵庫に多い。このうち、ブラジル、ペルー国籍の人々が愛知、静岡、神奈川に多いのは、彼らが日系人のUターン組であり、これらの県で製造業の職を得ているからである。ベトナム系の人々が神奈川、兵庫に多いのは、大和市と姫路市に難民定住センターが置かれていたためである。長野県、山形県、徳島県では外国籍住民の増加が顕著である。これはフィリピン、スリランカ、韓国、中国などからの花嫁がこの地に住むようになったからである。場所によって、国際化は家庭の日常生活にまで及ぶ場合がある。沖縄では、アメリカ軍基地の軍人、軍属、家族がおり、基地関連の騒音、危険、暴行事件などが社会問題になっている。
このほかに、正式に外国人登録をしていない人々も、20万~30万人ほど滞在している。1980年代後半から、出入国管理および難民認定法の滞在資格では認められていない未熟練・非専門労働に従事する者が大量に現れ始める。その主要出身国は、韓国、中国、タイ、フィリピン、マレーシア(とくに1990年代前半)、イラン(とくに1980年代後半)、パキスタン(とくに1980年代後半)、バングラディシュ(とくに1980年代後半)である。男性の多くは建築、土木工事などの現場や町工場に働き、女性の多くはサービス業や風俗営業で働いている。1990年代後半の不況によって、以前ほどには社会問題として取り上げられなくなったが、断続的に流入は続いている。
このような国際化状況に対して、日本社会の対応は十分とはいえない。日本社会はこれまでその構成員を国内の日本人に限定し、そこから在日外国人と海外の日本人(中国残留婦人・孤児、帰国子女)を締め出してきた。文部科学省が日本国内の外国人学校を正規の学校と認めないので、その卒業生は国立大学の受験資格を得ることができない。地方自治体で外国籍の者を採用することも限られている。アジア系の外国人がアパートを借りるにもさまざまな障害に突きあたる。
しかし、状況は少しずつではあるが、改善されてきている。1980~1990年代にかけて、社会保障では、国民年金、国民健康保険、公営住宅、公団住宅、住宅金融公庫融資、教育では日本育英会奨学金、国民体育大会、高校総体、さらには司法試験にもその門が開かれ始め、多くの市町村で公務員の一般職の受験資格から国籍条項が削除された。1996年には関西を中心として、776人の外国籍をもつ人たちが公務員として働いている。都道府県や政令指定都市でも、1996年以降、川崎市、神戸市、大阪市、高知県、神奈川県などが、受験資格から国籍条項を撤廃した。国家公務員では、郵便外務員職が1984年から開放され、国立大学の教授、助教授にも1982年から外国人が就任できるようになった(初めは3年の任期つきであったが、最近では年限つきを解除する例も増えてきている)。1980年代に社会問題となった外国人登録時の指紋押捺(おうなつ)も、1992年以降、永住外国人の場合に限っては廃止されている。外国籍の住民の意見を取り入れるために、準審議会を設ける自治体も登場した(川崎市外国人市民会議)。このような変化は、在日外国人の運動の成果である。しかし、それを受け入れる日本政府の態度に、国際人権思想の精神の普及が影響していることも見落とせない。
日本の国際化のなかで、ひとりひとりの心も正しく国際化に対応することが必要となっている。大企業での在日外国人の採用や、外国人住民の地方参政権問題などが、当面の課題である。
[初瀬龍平]
情報化の進展
1998年(平成10)のフランス・ワールドカップ・サッカーの模様、アメリカ大リーグ・ベースボールでの日本人選手の健闘は、海外から衛星放送を通じて現場から中継、日本で放映されている。また、2002年のワールドカップ・サッカーは日本、韓国から全世界へ中継、放映された。国際情報時差ゼロの時代である。今日では情報が、電話、E-mail(電子メール)、ファクシミリ(ファックス)、衛星放送を通じて、瞬時に世界を駆け巡っている。通信手段は安価に、迅速に、正確になり、同時に多量の情報を世界各地に送れるようになっている。
情報産業は巨大である。その売上げ(1995年ないし1995年度)は、電気通信事業10兆6299億円、広告5兆4263億円、放送3兆0316億円、出版2兆5897億円、新聞2兆4529億円、情報サービス(情報のサービスと提供)6兆3622億円、CD、カセット、レコード5665億円、ビデオカセット1770億円、映画興行収入1579億円にものぼる。
メディア産業で特徴的なのは、新しい技術の開発と普及の速さである。実際、家庭ごとの保有率(1996)でみると、携帯電話24.9%、ファクシミリ20.7%、パソコン22.3%、PHS(簡易型携帯電話)7.8%、カーナビ(カー・ナビゲーション・システム)3.3%となっている。とりわけ目だつのは、携帯電話、PHS、パソコンの普及である。1980年代には、10円硬貨に変わるテレフォンカードが一世を風靡(ふうび)した。しかし1990年代に入ると、携帯電話とPHSが若者を中心に急速に普及した。1995年1月に契約数が368万台であった携帯電話は、1996年1月には867万台、同年12月には1817万台と激増した。PHSも1996年1月71万台から同年12月には494万台と、急激に浸透していった。これに伴い、街中の公衆電話は減少傾向にある。2002年6月現在の契約数は、携帯電話7071万台、PHS570万台である(電気通信事業社協会調べ)。
パソコンなどのコンピュータ関連機器は、いまでは会社や官庁のオフィス、大学の研究室などで日常的に見られるようになり、家庭でも、ゲーム機として、あるいはインターネット利用のための必須の機器として、その存在は珍しいものではなくなった。1996年にWWW(World Wide Web)にアクセスしたのは、約350万人である。これにE-mail(電子メール)ユーザーを加えると、約700万人に達する。1996年で4.6%の家庭がE-mailを利用しているが、38.4%の家庭が潜在消費層として存在しているというデータもある。
映画についていえば、映画館でみる人よりも、レンタルビデオを楽しむ人のほうが増えている。映画館は1960年の7457館をピークに減少し、1985年2137館、1995年には1776館となった。映画館の入場者数もまた1958年の11億2745万2000人をピークに、1985年1億5513万人、1995年1億2704万人と1996年まで減少した。比べて1996年のレンタルビデオ店数は1万2285店である。しかし、映画館数は1996年、入場者数は1997年より増加に転じ、2001年にはそれぞれ2585館、1億6328万人となった(映画館数はすべてスクリーン数。映画館、入場者数は日本映画製作者連盟調べ)。テレビでは地上波だけではなく、衛星放送(スカイパーフェクTVなど)がその圧倒的な情報量で浸透し始め、視聴者の選択肢が格段に増えようとしている。
しかし、問題は情報の内容である。情報のなかには、商品として売ることを第一としたものが多くなってくる。意図的につくりだされ、操作された情報も普及する。インターネットの普及によってだれでも手軽に情報を発信できるようになった反面、ネット上でのプライバシーの侵害、誹謗(ひぼう)、中傷のたぐいの問題も発生している。
情報は商品として大量に売れるようにと、内容が手軽くなっていく。読者も手短に情報を得ようとする。本でも売れるのは、雑誌であり、マンガ本であり、文庫本である。雑誌の売上げは書籍の売上げを上回っている。雑誌の販売部数(2001年度)は、マンガ雑誌『週刊少年マガジン』364万部、『週刊少年ジャンプ』350万部、女性誌『non・no』92万部、『JJ』64万部、女性週刊誌『女性自身』62万7000部、『女性セブン』68万部、情報誌『週刊ザ・テレビジョン』130万部、『東京ウォーカー』41万部、一般誌『週刊ポスト』89万部、『週刊現代』86万部である。雑誌が本の売上げの大半を占めるコンビニエンス・ストアのセブン‐イレブンが本の売上げで紀伊國屋書店の売上げを抜いてしまったことは、象徴的である。
情報化によって、私たちの心は豊かになるのか。また情報化によって、人間と人間はさらに結びつくのか。日本社会全体で、下述のように個人化が進んでいるだけに、このような方向の追求が重要である。
[初瀬龍平]
生活の標準化
1990年代前半にバブル経済がはじけて、1990年代後半の経済不況は深刻である。しかし、それまでに築きあげてきた日常生活の豊かさは基本的に続いている。人々の衣食住については、衣は華衣であり、食は飽食である。住は大きさでは好転していないが、室内の整備(自動制御ガス風呂、水洗トイレ、システム・キッチン、クーラーなど)はよくなっている。そのなかで人々の消費生活のスタイルは、都市でも農村でも画一化し、標準化してきている。
1996年(平成8)に自らを「中流」であると意識する人々の割合は、91.2%であった。同じ意識をもつ人々はすでに1986年(昭和61)の時点で87.6%に達していたから、中流意識が急速に増加したわけではない。一般的にいって、人々は生活の物的条件に満足している。電気洗濯機99.2%、カラーテレビ99.1%、電気冷蔵庫98.1%、クーラー77.2%と耐久消費財はほぼ全世帯にいきわたっている(1996年)。下水道の整備によって、市街地で水洗便所のある住宅の比率は1993年に75.6%に達している(1983年58.2%)。
農村と都市の格差も減ってきている。耐久消費財の普及率では、農村部と都市部でほとんど違いがない。同じ生活スタイル、消費生活、物的条件のもと、平均延べ面積62.05平方メートルの東京に比べて住宅の広さで優っている分だけ、地方のほうが快適であるとさえいえる。日本でいちばん住みやすいのは富山県であるとの説もある。
食文化の面でも、画一化が進んでいる。1年を通してハウス栽培のキュウリやトマトが出回っている。全面加工あるいはほぼ全面加工のレトルト食品がスーパーマーケットの棚に満載されている。出来合いの料理がパックになって売られている。形の整ったキュウリやトマトが好まれるという理由から、不格好な野菜は店で売られていない。全国至る所にファミリー・レストラン、ハンバーガー、ドーナツ、牛丼、そば、うどんなどのファストフード・チェーンが散在している。
しかし、ものの豊かさがそのまま心の豊かさにはならない。世相について「自己本位である」と考える者の割合は、1986年の44.8%から1996年の49.2%に増えている。また、「無責任」の風潮が強いと考える者も、同じ期間の42.8%から52.6%に増大している。ここでは、真の豊かさの意味が問い直されているといえよう。
[初瀬龍平]
個人化の波
家族のなかにも新しい問題が起きている。戦後の日本、とくに都市部の家族の特徴は、夫婦と子供だけの核家族化にある。この最小単位の家族構成がそのまま進むと、子供が自立したとき、年老いた夫婦が残される。しかも、最近の高齢者はますます長生きになっている。完全生命表によれば、日本人の平均寿命は1985年(昭和60)に男74.78年、女80.48年であったものが、2000年(平成12)には男77.72年、女84.60年となっている。65歳以上の人口は、2000年に男922万2116人、女1278万3036人に達した。この人口数は、1995年に男750万4253人、女1075万6569人であったから、この数年間の急増は明らかである。これに対して、出生数は2001年に117万0665人、人口1000人に対して9.3人、純再出産率は0.65である。高齢化が進む一方で少子化も進んでいる。1998年には65歳以上の人口が全人口の16.0%となり、14歳以下の人口は15.2%を割った。日本社会は減少していく労働人口をもって、増加していく高齢者を養わなければならないという問題に直面している。
この状況に対する社会的対応は遅れている。65歳以上人口10万人あたりの特別養護老人ホーム数は1985年22.8、1995年25.7、在所者数は1985年16.1人、1995年16.8人、従業員数は1990年635.4人、1996年614.9人と、10年間で実質的に増加していない。これに対してヘルパーの数は1985年の16.6人から1995年の80.9人に急増している。高齢者はホームでの介護より自宅での介護を望んでいる。その子供たち(大人)は自分の核家族を維持していくのに精一杯であって、自分の親を自分の家に引き取ろうとはしない。高齢者も自分の家にとどまろうとする。このような状況を解決するには、新しい社会制度が必要である。この面での社会制度の整備が、今後の社会全体の課題である。
女性の社会進出は目覚ましい。1996年の医師試験合格者の26.3%、司法試験合格者の23.4%、公認会計士試験合格者の20.1%は女性であった。既婚女性の約半分が働いている。その労働形態としては、時間労働(パートタイマー)が3分の1を占める。働く目的も変化した。生計維持(1983年33.5%、1997年37.7%)、家計補助(1983年37.8%、1997年37.3%)については変化はみられない。しかし、自分で自由になるお金のため(1983年28.0%、1997年40.6%)、能力、才能、資格を活かすため(1983年14.3%、1997年23.7%)、視野を広げるため、友人を得るため(1983年13.6%、1997年28.1%)という自立の目的では、10年間で大きな変化がみられる。結婚後の夫婦別姓を好む女性も増えている。
しかし、女性の自立志向を助ける家庭内外の条件は、不十分である。男女間の賃金格差は、男を100として、20~24歳で92.3であるのが、50~54歳では52.2となっている(1996)。年齢の増加とともに賃金格差が拡大している。女性管理職は全女性就労者の2.5%(1985)から4.5%(1996)であり、10年間で比率は2倍になっているが、絶対数はやはり少なく、その比率は欧米諸国と比べると極端に低い。家庭で夫が家事分担をするという比率は、掃除、洗濯、食事の支度、後かたづけ、乳幼児の世話、親の世話の各項目で、100人中1~2人にすぎない。働く女性は、家庭内外で過大な負担を背負わされている。
個人化の波のなかで、もう一つ目だつのは、人々の孤立感と、社会的連帯を求める動きである。核家族で育つ子供は、個室を与えられて当然と思っている。家族がいっしょに集まって、食事、歓談、ゲーム、あるいは勉強をすることが少なくなっている。テレビをいっしょに見ることは多いが、そこでは、会話の機会が閉ざされ気味である。彼らには祖父母というタテの系列が失われている。兄弟姉妹の数も少ないので、家庭で社会的トレーニングを積むこともむずかしい。学校でいじめられる恐れもある。偏差値の恐怖もある。そこで、孤独な子供たちは、学校から帰宅後に、電話や携帯電話のメールなどを利用して友人と接する。その中心に、自分がいることができる。
核家族以前では、子供の周囲に、兄弟姉妹、祖父母、親戚や、近所の人たちがいた。この人々が意図せずに、子供のカウンセリング役を果たしていた。この代役を期待されているのが、友人である。子供が青年になっても、頼れるのは友人であり、電話のネットワークである。彼らは、友人がいないことには耐えられない。大学の新入生が最初にすることは、友人づくりであり、彼氏、彼女探しである。サークルもクラブも、その組織の目的以上に、友人のネットワークとしての意味が大きい。この点でも携帯電話は、青年の必需品である。
さまよえる個人は、子供、青年だけではない。職場でも、人々は個人化している。労働組合の組織率は、1975年(昭和50)以来低減を続けており、厚生労働省の労働組合基礎調査によると現在の労働組合員数は1121万人、推定組織率20.7%(2001)である。その反面で、労働時間は、この10年間で大幅に改善されてきている。たとえば、製造業生産労働者の年間総労働時間は、1983年の2152時間から2001年度(平成13)の1939時間に減っている。週休2日も定着してきている。大人がこの浮いた時間をゴルフ、パチンコ、テレビ、ビデオ、ショッピング、カラオケ以外に、子供との対話を含めて、社会サービスの創造に向けるかどうかは、今後の日本社会を占ううえで見逃せない点であろう。
近代化に伴って必然的に起こる個人化の諸現象に、社会としてどのように対応していけるかが、当面の、そして最大の課題である。社会的には、各種のカウンセリングを制度化する必要性が、今後いっそう高まるだろう。それに加えて、新しい動きもある。阪神・淡路大地震(1995年1月)の直後には、全国からボランティアの青年、学生(142万人)が被災地復興のために、無償で現地に赴いた。全国で無数の青年が、種々のNGO(非政府組織)活動をしている。次世代の人々は、けっして無気力ではない。彼らは新しい型の社会的連帯を求めている。
[初瀬龍平]
文化
日本文化は、縄文・弥生(やよい)期の土器、埴輪(はにわ)にみられる古代の美をはじめとして、飛鳥(あすか)、白鳳(はくほう)、天平(てんぴょう)以来の建築や彫刻、あるいは『万葉集』の歌謡に始まる和歌と、その発展から生まれた俳句のような独特の短詩型の詩歌、世界最古の小説といわれる『源氏物語』に続く文学、世阿弥(ぜあみ)の能や近松(ちかまつ)の戯曲をもつ演劇、独特の発展を示した庭園など、豊かな有形の文化遺産がある。また、聖徳太子、最澄(さいちょう)、空海(くうかい)、そして鎌倉時代の法然(ほうねん)、一遍(いっぺん)、親鸞(しんらん)、栄西(えいさい/ようさい)、道元(どうげん)、日蓮(にちれん)ら仏教諸宗の開祖たちや、国学の本居宣長(もとおりのりなが)などの独自の哲学を残した思想家、また和算の関孝和(せきたかかず)などにみられる思想、精神的な文化伝統が、優れたものとして海外でも高く評価され、しだいに世界全体の文化遺産となりつつある。
日本文化の系譜には縄文的な荒々しい造型と、弥生的な簡素な造型に代表される二つの流れが交錯していると、谷川徹三(たにかわてつぞう)が指摘している。また各分野において海外からの影響が認められる。しかし、ここでは、個々の分野における伝統についてはそれぞれの項目に譲り、日本文化の全体について認められるその特質を、洗練された部分ばかりでなく、広く常民文化をも含めて検討しておくことにする。
[米山俊直]
同質性
現在の日本文化は、国民文化としてみると、かなり強いまとまり―文化統合を示している。これは、本来島国である日本が、一民族、一言語、一文化伝統という統合を長い歴史のなかでつくりだしてきたこと、それを背景として今日の日本文化があることは否定できない。江戸時代の250年にわたる鎖国という事態が、文化の統合を強める地盤をつくり、さらに明治以後の近代国家としての発展のために、政府が意図的に国民文化の形成を推進したことによって、この均質性は生み出された。すなわち、明治初年以来の、国語の標準化、神道(しんとう)の国教化、天皇の神格化、国歌・国旗の制定などが、国民皆兵、学校義務教育、納税の義務などとともに進められた。その結果、日本文化は世界でもまれにみる同質性の高い文化という側面をもつに至ったのである。事実、1億数千万人を超える人口を擁した一民族、一言語、一文化伝統を「たてまえ」としている国民文化は、ほかには見当たらない。そしてこの「たてまえ」が真実であると思い込まれている側面もある。近代の学校教育や、最近のマスコミの発達が同質性を促したことも見逃せない。
[米山俊直]
多様性その一―地域性
しかしその反面、日本はその文化伝統に多様性を生む条件が存在している。まず、四つの島を主とする列島は、南北に長く延びた地形をもち、亜寒帯から温帯を経て亜熱帯に及ぶ気候帯を含んでいる。さらに中央を山脈が走っていること、いくつかの火山帯が走っていることなどが、その風土の多様性をつくりだしている。日本海側の深い雪国から、黒潮の洗う太平洋に面した温暖な東海―南海地方まで、あるいは台風通過が多い沖縄から、梅雨のない北海道まで、さまざまな自然があり、それに対応した地方色豊かな文化伝統が各地に育っている。それを反映して生業も基本的には農業国としての歴史をもっているが、西南日本がイネ・ムギの二毛作など多毛作が可能なのに対して、東北日本では1年一毛作で長い冬の農閑期をもってきた。こうした生活―生業の地方差は、方言にも豊かな地方差をつくりだし、年中行事にもまた地方差が著しい。
このような地方文化は、まず日本人の民族としての形成史と関係している。すなわち、日本人は、南からの民族集団、北方からの民族集団と、中国大陸からの渡来による民族集団が、重層的に混血を続けて形成されたとされているが、それぞれの系統の文化要素が、民族の形成とともに重層的に日本文化の基盤になっている。封建体制の展開と戦国の動乱を経ての天下統一、そして江戸幕藩体制による地方の整備によって、地方文化の拠点が各地に形成され発達した。そのモデルは、四方を山々に囲まれた盆地状の地形にみることができよう。周囲七方の分水嶺(ぶんすいれい)から水を集め渓谷をつくり、盆地底で一つの川になって一方へ流れ出る。盆地底には平城(ひらじろ)があって、城下町が物資と情報と人々を集める。これが盆地を中心とした地域的まとまりの基本型であるが、現実には盆地底に湖ができたり、盆地が大きい川の流域に沿って連鎖状につながる場合もある。また海岸線ではこの「すりばち状」の形が半分になり、あと半分は海になっているとみなしてよい。日本文化にはこのような地方文化の単位(小盆地宇宙)が約100ほどもあると考えられる。
[米山俊直]
多様性その二―階層的部分文化
一つの文化はそのなかをいくつかの下位の文化に分けて考えることができ、それを亜文化(サブカルチャー)あるいは部分文化(パートカルチャー)という。日本の地方文化も日本文化全体に対してその部分文化であるが、他方、士農工商の身分階層的な部分文化がそれぞれ独自に発達して、現代の日本文化の基礎になっていることも認められる。すなわち、儒教倫理を基礎とした武家法度(はっと)や村方の掟(おきて)に拘束されている士農の農村的文化に対して、職人気質(かたぎ)や商人道に代表される都市的文化の伝統は日本の部分文化である。たとえば、武家の主家大切の観念は近代官僚の国家への献身的奉仕のなかに継承されたし、農民的な勤勉さと片隅の幸福を守ろうとする自己防衛的保守性が現代サラリーマンの行動規範として生きている。職人気質の伝統が現代に至る高度の技術を支えている技術者の精神となり、商人の倹約勤勉の精神は西洋のプロテスタンティズムに肩を並べて今日の日本の繁栄の基になっている。このような士農工商の身分階層による部分文化を備えていたのだから、日本はきわめて複雑な社会、いわゆる複合社会である。そして日本文化は、地域的な多様性に加えて、このような士農工商の部分文化の伝統の複雑な構成を背景にもっている。さらに階層性についていえば、江戸時代まではこの「四民」の別に加えて、京都の天皇家を中心とする宮廷文化の伝統と、身分的に最下層に位置づけられていた被差別民の文化を伴っていたことも見逃せない。身分制は明治維新以来の近代化の過程で「四民平等」が宣言され否定されたが、その遺制は未解放部落差別として今日もなお人権問題になっている。また皇室をめぐる文化伝統も、明治以来の天皇神格化の時期を経過したあと、新憲法の制定に伴って皇室制度も近代化されながら、国民統合の象徴として継承されている。
[米山俊直]
多様性その三―海外からの影響
複合社会である日本には、近代から100年の間にさまざまな文化要素が海外から流入した。いわゆる西欧化であるが、今日では学問・芸術においても科学技術においても、それぞれ単なる模倣の域を脱している。しかし、洋風、和風の二領域は絵画、音楽、舞踊などにみられるように、それぞれの発達を示してきた。これもまた文化の多様性に貢献している。もっとも、海外からの文化要素の流入、伝播(でんぱ)は古くから認められる。そもそも日本文化の多くの文化要素は、言語における漢字の使用や、宗教における仏教、儒教、道教の流入など、アジア大陸の先進文明に負うところが大きいことはいうまでもない。外来文化の受容は、古く4世紀より以前に、農業、鉄、馬などが日本列島に入ってきたし、7世紀までに、仏教、儒教、道教、漢字、都市計画、政治行政の制度などが伝播(でんぱ)してきた。そして16世紀にはキリスト教、鉄砲、そのほかの南蛮渡りの文物が流入した。明治以降の西洋からの文物の流入、第二次世界大戦以後のアメリカ化もその系譜を引いている。
しかし、外来文化要素の受容は、他のアジア諸国の文化の場合とはやや異なっている。漢字は用いても同時に仮名が発明されて活用され、漢字仮名交じりの独特の正字法が日本語の普通の書き方になっている。また宗教も、平安、鎌倉時代の仏教のように日本文化のなかで独自の発展を遂げて、その発生の地インドや展開の地中国のそれとは異なった日本仏教として発展し、それらの国における衰退のあとも続いて、現代にも生きている。海外からの文化要素の積極的な受容は、7世紀から8世紀にかけて隋(ずい)、唐との往来が盛んであった時期、11世紀後半の対宋(そう)貿易、15世紀前半の対明(みん)貿易の時期、16世紀後半の織豊(しょくほう)政権の時代などに繰り返し行われているが、明治維新以後の外来文物の流入が大きかったことはいうまでもない。第二次世界大戦後になると、国際性はいっそう進展して、海外に逆に日本製品が氾濫(はんらん)するまでになり、日本人の海外での活躍も活発になっている。
海外からの文化要素の積極的採用の傾向を理由に、日本文化を模倣文化、雑種文化であるとする説もある。しかしあらゆる民族文化には、伝播してきた文化要素を自己の文化の一部として採用することがある。すべての文化がその一面をもっているのだから、日本文化の模倣の面を批判し、習合を低評価するのはあたらない。
[米山俊直]
複合社会―日本文明
このようにみてくると、同質性に対する多様性が、日本文化の特色の他の一面になっていることは明らかである。そしてこの高い同質性と多様性の共存自体が、日本文化の一つの特質なのである。この矛盾をはらんだ特質は、日本の社会が未開社会のようにその構成が単純ではなく、きわめて複雑であることの反映である。事実、およそ100を数えるという地域文化があり、また士農工商の身分階層による部分文化を備えていたのだから、きわめて複雑な社会であったといえよう。このような社会のことを一般に複合社会とよぶが、日本文化はまさに複合社会の文化なのである。
このような複合社会の制度や装置を、文化ということばとは別に、文明ということばを用いて論じようという立場も生まれている。梅棹忠夫(うめさおただお)は、他のアジア諸国とは異なる生態的条件によって、日本はむしろ西ヨーロッパに近い自然条件をもち、その点で中国など大陸の文化の自然的基盤とは異なっている。それが日本の急速な近代化の道を可能にしたことを、「文明の生態史観」(1957)において明らかにした。西欧との平行現象の一つに、日本が封建制を経験していて、他のアジア諸国とは異なる体制を経験していることがある。梅棹はまた、近世という特殊な時代を、西欧のブルボン王朝に対応する徳川王朝とよんで、その平行性をあげている。
[米山俊直]
精神世界
日本には精霊信仰と祖先崇拝をもとにした固有信仰の系譜のうえに神道が発達したが、これは海外から伝播した仏教、道教の影響の下に、それ以前からの土着的な固有信仰が反応して、それら外来の教義に対抗するようにして形成されたもので、当然、仏教、道教の教義などと習合しながら発達した。のち明治の神仏分離政策によって、神道の神学として純粋化したものの、国家の保護を受けて体制化し、伝統的な民俗慣習から離れてしまった。むしろ第二次世界大戦以後になって、神道は民俗文化の伝統を取り戻したといえる。この神道にみられるような、受け身で外来の衝撃に対して対抗的に独自のものを生み出すこと、あるいは外来の事物と土着の要素を混合する「習合」ということも、日本の文化伝統の一つである。
空海に儒教・道教・仏教の比較論『三教指帰(さんごうしいき)』(797)があるように、日本にはこの三つの世界観が早くから移植されていた。仏教をほとんど国教とみなす政策が、飛鳥時代から奈良、平安の各時代を通して流れていた。しかし他方、日本独自の土着的な精霊信仰、祖先崇拝も、それぞれ仏教や道教の要素を絡ませながら生き続け、逆に外来の宗教のほうを変化させてきた。平安時代以来の日本人には独特の無常観があって、それは自然とのかかわりを明瞭(めいりょう)に示している。呪術(じゅじゅつ)的な加持祈祷(かじきとう)を伴った密教に続いて、後生を阿弥陀(あみだ)の浄土に期待する信仰がおこり、さらに自力本願の禅、法華(ほっけ)(日蓮)などの宗派が誕生する。ここで早く西洋のプロテスタンティズムに対応する思想的な動きが認められる。
さらに戦国時代を経て天下統一が実現する16世紀後半になると、人々の合理的な判断、現世に対する唯物論的な見方が生まれてくる。1571年(元亀2)の信長の比叡山(ひえいざん)焼打ちは、都の住民に神も仏もないことを示し、いわば仏教の正統的権威の崩壊を示した。その後、民衆の信仰対象は現世利益(りやく)を中心とする機能的な神仏に移ったといえる。すなわち、壮大な教義体系をもつ宗教は弱体化し、江戸時代になって寺が戸籍管理の機能を備えるに至って形骸(けいがい)化した。民衆の世直し志向などの反映は、江戸時代末期から明治初年にかけて発達した新興宗教の出現にみられる。同様の動きは第二次世界大戦後の社会にもあり、いくつかの新宗教が出現している。
しかし日本人の合理的科学的な世界観への傾斜は、明治以来の西欧的な近代科学の輸入によって圧倒的に強いものとなり、江戸時代に潜在的に育っていた合理的精神が開花をみせた。西欧の人々が抱いている日本のイメージには神秘的なものを考えられがちであるが、実はそれは大きい偏見にすぎない。むしろ日本文化のほうが、西洋ことにヘブライの伝統であるユダヤ―キリスト教につきまとう、おどろおどろしい悪魔や呪術、あるいはオカルトのような陰影はほとんど消えている。むしろ禅のような精神性を強調し、ひたすら内面に向かう瞑想(めいそう)の修行のような悟りを目ざすものになっていて、いわゆる神秘主義とは遠いものである。
[米山俊直]
都市の伝統
日本は農業国であり、日本人は農耕民族であるという先入観によって、ともすればその都市文化の伝統のことが見逃されがちであるが、日本の都市の成立は、藤原京(694)、平城京(710)、そして平安京(794)にまでさかのぼって考えるならば、けっして新しいことではない。唐の長安を模したといわれる都市計画は、都市の生活様式の早い成立を示している。中世の日本人は土地に縛り付けられていたとみなすのは、近年の研究によってかならずしも正確ではないことが明らかになってきた。定住する農民のほかに、移動する民衆が少なからず存在していて、物と情報を運んでいた。戦国の時代ごろから、政治、経済、文化の中心であった奈良、京都などに加えて、寺社の門前町、平城(ひらじろ)になった戦国大名の城下町、港町、宿場町などが発達した。そして、堺(さかい)、平野(ひらの)(大阪市)、博多(はかた)など、力のある市民を中心にした自治組織が、その町の政治を運営する所もみられるに至った。商人と職人を中心の構成者としているが、そのほかに運送業などのサービスを担当したり、芸能など文化的な創造活動をする人々も存在していた。
江戸時代に入って、都市的な生活様式はたびたび支配者の忌諱(きき)に触れ、取り締まられたが、それでも江戸、京、大坂の三都では都市的な文化が繁栄し、元禄(げんろく)・享保(きょうほう)、あるいは文化・文政(ぶんかぶんせい)の洗練された都市文化を生み出し、それが各地に伝播して、それぞれの地方文化を豊かにしていった。各地の都市に「京町」「江戸橋」などの地名が残るのは、この日本文明の中心とのかかわりを示すものである。先に、日本文化はおよそ100の地方文化の拠点をもつ、と述べたが、日本文明は、上方(かみがた)つまり京・大坂と江戸という二つの中心ないし焦点をもっているといえる。すなわち、日本文明は楕円(だえん)であるとみなすことができるのである。
[米山俊直]
高度成長以後の日本
1960年(昭和35)ごろから約10年にわたって、日本列島は大きな変貌(へんぼう)をとげてきた。まさに日本列島は改造されたともいえよう。各地に新産業都市が発達し、道路網、新幹線網、港湾が整備され、全国の海岸線の護岸工事、山地の砂防工事、あるいは多目的ダムの建設などが進み、国土そのものが変貌した。日本はその過程で1人当り国内総生産(GDP)や対外純資産額などでも有数の経済大国になった。
その後、1973年(昭和48)の第一次石油危機を契機に高度経済成長のテンポは緩んだ。いわゆるバブル経済の時代を経験して、ふたたび経済的繁栄の夢をもったが、状況は一転して経済活動は低迷し、さらに政治では55年体制のゆらぎ、あるいは戦時中の統制を引き継いだままの「40年体制」にも制度疲労が指摘された。汚職などが引き金になって規制緩和がうたわれる。
そして1990年代後半、橋本内閣は金融システム、財政構造、行政、社会保障、経済構造、教育の6つの改革課題を設定した。その背景には、経済大国となりながら国際的に立ち後れている社会経済構造、高齢化・少子社会の到来、国際化と都市化の全国への波及による価値観の多様化がある。
東京圏一極集中は、東京が日本の首都というだけでなく、世界の一つの中心としての機能をもち始めたといえるが、また東京圏の都市過密の危険性などがあることは、地震国として否定できない。この集中は、結果として、前述の日本の楕円構造が一中心の円構造に変化したともいえよう。危険回避のために、首都移転も話題になってきた。
もうひとつの楕円の極であった関西には、その「地盤沈下」を修復するために、関西国際空港、明石海峡の架橋、京阪奈文化学術研究都市の建設など、巨大プロジェクトが計画され、相次いで実現した。また、北九州では福岡を中心としての経済発展が期待されているし、東北は仙台を、北海道は札幌を中心に、また日本海側では新潟、富山、福井、金沢などの都市を中心にしてそれぞれの地方の充実が図られている。とはいえ依然として中央と地方の経済的・文化的落差は著しく、現在の円構造が楕円構造に回帰することも容易ではない。
[米山俊直]
グローバリゼーションのなかで
日本をその文化の特質、文明としての複合性、精神世界、都市の伝統から概観してきた。しかし現在では、日本が孤立して存在することが不可能なまでに交通通信が発達して、地球が狭くなり、国民の生活も国際社会、国際経済に巻き込まれている。近隣のアジア諸国ばかりではなく、南米やアフリカからの人々も日本に住むことが珍しくなくなっている。日本人の長期短期の海外への旅行も年々増加しているし、国際交流が現実に進行しているのが、日本の現状である。
そればかりではなく、環境問題のように地球全体を覆う問題が生まれていて、それは国境を越えた地球全体の問題になりつつある。そのなかで日本人自体も、他の先進諸国と同様に、高齢者人口の増加と出生率の低下による、高齢化社会としての性格を顕著に示している。
日本は依然として象徴とはいえ天皇制を備えた国家であり、その国民性は、「水に流す」ことによって過去を忘れてしまうように、長く「恨み」を持続させる国民性ではない。それに、性や年齢をもとにした差別のない個人主義と、それを前提とする民主主義、あるいは人権の尊重の理念は、なお相対的には確固としたものになっていない。現在は地球全体を視野に入れた発想が必要であり、それをもとにした行動選択が要求され、「地球市民」としての自覚が必要であるが、その場合、この日本の特殊性をどのように生かしていくかが、大きな課題になるのではないだろうか。
[米山俊直]
海外における日本研究
歴史―日本学の伝統
海外における日本研究の萌芽(ほうが)は16世紀、来日した西洋人に求められる。その代表は安土(あづち)桃山時代、イエズス会の宣教師フロイスである。江戸時代には、オランダ商館関係者のなかに、膨大な資料を収集してヨーロッパに持ち帰り、日本学(ジャパノロジー)の礎石を築いた人々が現れた。カロン、ケンペル、シーボルトなどである。シーボルトが二度の滞日中に収集した資料の整理にあたった弟子ホフマンは、オランダ、ライデン大学に1850年(嘉永3)開設された日本学の講座の初代教授となった。他方、これより1世紀以上前(1736)、ロシアでは、漂流した日本漁民を教師としてサンクト・ペテルブルグに日本語学校が設けられ、日露・露日辞典なども出版された。
明治新政府による開国は新しい日本学者のグループを生み出した。一つのグループはいわゆるお雇い外国人であって、そのなかから、日本を研究対象として取り上げたり、美術品などを広く収集して母国における日本研究の資料たらしめたりした人々が生まれた。イギリスのチェンバレン、アメリカのモース、フェノロサなどがそれである。
もう一つのグループは、とくにイギリスにみられる型であって、外交官として日本に駐在した人々、たとえばサトー、オールコックなどである。
第三のグループは、民間人として来日し、日本に魅せられた文学者、たとえばハーンやモラエスなど。このグループに入れることもできるが、宣教師、とくにアメリカの宣教師が第四のグループを形成する。一般に彼らは長期にわたって在日し、日本への理解と愛情に富んでいた。かならずしも日本を研究したわけではないが、その子供や弟子から優れた日本学者が出た例が多い。ライシャワー兄弟(ロバートと前駐日大使エドウィン)の父親(オーガスト)は日本学者でもあったが、その典型である。
こうして開国後、日本学に進んだ欧米人が増加したが、その大多数はそれまでの日本学者同様、専門的研究者としての訓練、地位、意識をもっていたわけではなく、異国趣味的、好事家(こうずか)的な興味の赴くままに日本の歴史、習俗、文学、芸術、言語などを幅広く取り上げた。人文や古典への傾斜と非専門性とを特徴とする日本学は、偶然日本に在住し感情的に日本に魅せられた個人によって担われたのであり、組織的・専門的な日本研究が制度化され、研究者が大学で体系的に養成されるまでには至らなかった。そしてこの状態は第二次世界大戦前まで続いた。
しかし、いくつかの例外がある。特筆すべきは、前述のライデン大学日本学講座のほか、1867年(慶応3)大英博物館東洋部(のちに東洋文献資料部。シーボルト、サトーのコレクションで有名)、1898年(明治31)サンクト・ペテルブルグ大学日本語文献講座に続いて、20世紀に入ってから徐々に欧米各国に設立され始めたいくつかの機関である。主要なものとして、ドイツで1914年(大正3)設立のハンブルク植民地研究所(のちにハンブルク大学に吸収。日本学の初代教授はフローレンツKarl Adolf Florenz(1865―1939))、続いて1927年(昭和2)ベルリン日本研究所、1932年ライプツィヒ大学日本学講座、オーストリアで1938年ウィーン大学日本学研究所(三井家の援助によって設立。文化人類学的伝統で有名)、フランスで1934年パリ大学日本学研究所、イギリスで1917年ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS。日本語コースは1930年設置)、アメリカで1925年太平洋問題調査会(IPR)、1928年ハーバード大学燕京(エンチン)研究所(エリセーエフSerge Elisseeff(1889―1975)、戦後はE・ライシャワーが長らく所長を務めた)などがある。なお、来日する日本学者に各種の便宜を与えた日本アジア協会(1872)、ドイツ東洋文化研究協会(OAG、1873)、東京日仏会館(1924)などが東京に設立されたことも、戦前の日本学の発達に大きく貢献した。
第二次世界大戦前の20世紀前半、指導的日本学者として活躍した人としては、ソ連のコンラドNikolai Iosifovich Konrad(1891―1970)、オーストリアのスラビークAlexander Slawik(1900―1997)、フランスのアグノエルCharles Haguenauer(1896―1976)、イギリスのサンソム、ダニエルズFrank James Daniels(1899―?)、アメリカのエリセーエフElissev Sergei Grigorievich(ロシアの人。フランスおよびアメリカの日本学を育てた。1889―1975)、ボートンHugh Borton(1903―1995)、ボールズ、E・ライシャワー、イタリアのセベリーニAntelamo Severini(1827―1909)などがいる。
[新堀通也]
現状―日本学から日本研究へ
第二次世界大戦は日本研究に決定的な変化をもたらした。最大の変化は、その中心がヨーロッパからアメリカに移ったこと、人文や歴史に傾斜し、かつ趣味的、一般的な日本学(ジャパノロジー)から、社会や現在を重視し、科学的で専門分化したいわゆる日本研究(ジャパニーズ・スタディーズ)へと移行したこと、制度化が進行したこと、全世界的に日本研究が広まったことである。
旧ソ連、ドイツ、フランスなど、それまで日本学の中心であったヨーロッパ諸国の多くと異なり、戦場となることを免れたアメリカとイギリスとは、「敵国」日本の理解、情報の解読や通訳要員の養成に努力した。なかでもアメリカでは、陸軍と海軍がそれぞれミシガン大学とコロラド大学に日本語学校を開設し、日本語が使える将校を多数養成した。イギリスでも前記SOASに日本語集中訓練コースが設けられた。この両国における戦後の指導的日本研究者の多くは、これらの学校の卒業生である。たとえばアメリカのキーン、ジャンセンMarius Berthus Jansen(1922―2000)、サイデンステッカー、パッシンHerbert Passin(1916―2003)、ケーリOtis Cary(1922―2006)、シャイブリDonald H. Shively(生没年不詳)、イギリスのドーア、オニールPatric G. O'neil(1924―2012)など。
戦後、日本の経済発展に伴う国際的地位の向上は、日本研究の制度化を大きく刺激した。なかでも戦後のアメリカは国際政治でいっそう重要な役割を担うことになったため、それまで比較的軽視していた非西欧地域の研究を推進するようになった。とくに日本は、占領行政の効率的運営のため「地域研究」の対象として重視された。すでに戦争中、軍の要請によって、ベネディクトの『菊と刀』のごとき日本研究が行われるとともに、すでに述べたとおり軍制日本語学校が戦後の指導的日本研究者を多数養成していたが、戦後、日本への関心の増大、日本研究への援助は、各種の奨学金や研究資金の増額、大学の規模の拡大などに支えられ、とくに1950年代、多くの大学に日本研究機関や日本・日本語専門の教育組織を生み出すこととなった。日本研究者は大学にポストをみつけだすことも容易であった。
[新堀通也]
アメリカ
アメリカの大学の日本研究機関は、研究所ないしセンターという名称をもつことが多いが、その場合も日本だけでなく、アジア、東アジアを含み、日本研究をその一部とするのが普通である。またその組織は普通、複数の学部の上に置かれ、プロジェクトに応じ学際的研究を調整するという形をとる。したがって、そのスタッフの多くは各学部に所属しているし、研究資金は組織自体が獲得しなくてはならない。学生は一般に大学院段階の者であり、その籍もそれぞれの学部に置かれ、博士号もそれぞれの学部から与えられる。このような特徴はアメリカの日本研究を学際的たらしめるとともに、たとえば社会学、政治学などといったディシプリン志向かつ財政的不安定という傾向をもたらす。日本の国際的地位の向上とともに、日本専門の研究所やセンターも現れるようになった。主要な研究機関、その設立年ならびに所属する(または所属した)著名なメンバーは次のとおりである。
●ハーバード大学 燕京研究所(1928、エリセーエフ、E・ライシャワー、クレイグ) 東アジア研究所(1957、ボーゲル) 日本研究所(1973、E・ライシャワー、シャイブリ) 日本法講座(1972、コーエン)
●コロンビア大学 東アジア研究所(1949、カーチス、キーン、パッシン、サイデンステッカー) ドナルド・キーン日本文化センター(1986、ルーシュ)
●シカゴ大学 極東研究センター(1937、ナジタ)
●ミシガン大学 日本研究センター(1947、キャンベル、ハケット)
●カリフォルニア大学(バークリー) アジア研究所 日本研究センター(1958、スカラピーノ、ベラー)
●スタンフォード大学 東アジア研究センター(1968、ハルミ・ベフ)
●ワシントン大学(シアトル) アジア研究委員会(1956) 国際研究学部(1978)
●エール大学 東アジア研究協議会(1969、ジョン・ホール)
●ハワイ大学 東西センター(1960、ジョージ・アキタ、ルビンジャー、ビクトル・コバヤシ)
●ジョンズ・ホプキンズ大学 エドウィン・O・ライシャワー・センター(1984、パッカード)
[新堀通也]
イギリス
日本学の伝統がいまなお残っているヨーロッパ諸国でも1960年代になると日本研究が盛んとなり、とくに新設の大学を中心に現代日本の社会科学的研究が重視されるようになった。
すでに述べたとおりロンドン大学、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学は日本学的伝統をもっているが、新設のシェフィールド大学では社会科学的研究が中心である。なお、イギリスで成果をあげている組織に、大英図書館や主要大学の図書館で日本関係図書の共同購入を行う日本図書グループがあるが、主要研究機関は次のとおりである。
●ケンブリッジ大学 東洋研究所(1963、パウエル、ストリー)
●オックスフォード大学 日産日本問題研究所(1981、ストックウィン)
●シェフィールド大学 日本研究センター(1963、ダニエルズ)
●スターリング大学 日本研究センター(1980)
●ロンドン大学 東洋アフリカ学院(SOAS。1930、ダニエルズ、ダン、オニール、ドーア) 日本研究センター(1978、ビアズレー)
[新堀通也]
フランス
アグノエルやエリセーエフによって築き上げられた長い日本学的伝統をもっているが、この二人は第二次世界大戦後もいち早くフランスの日本研究の再興に努力した。アグノエルは1945年、パリの国立東洋語学校(1968年、国立東洋語東洋文化研究所に改制)で日本語の講義を再開、1959年、日本高等研究所の設立に尽力した。エリセーエフは1957年、国立高等研究院第六学部(近代日本史)の教授となった。
1968年の大学改革以後、日本研究は整備され、パリ第三大学(新ソルボンヌ大学)の国立東洋言語文化総合研究所(1971)、パリ第七大学の東アジア言語・文化教育研究ユニテ(1968、アカマツ、ピジョー、ブリュネ)では日本文学、日本語、日本思想などを中心とした研究が行われているが、社会科学高等学院の現代日本研究センター(1973)は社会科学的研究を中心としている。そのほか、コレージュ・ド・フランスの日本学高等研究所(1973、フランク)、ギメ博物館や日仏協会(1962)は講演や資料の収集研究によって日本学の普及に大きく貢献している。
[新堀通也]
ドイツ
主要な大学に日本関係のゼミナールや講座が置かれ、日本学的伝統をもつ研究と教育が行われているが、社会科学的研究機関としては、ボン大学 日本文化研究所(1930、ツァッヘルト、クライナー)、ベルリン自由大学 東アジア研究所、とくにボッフム大学 東アジア研究部門(1964、デットマー、レビン)が有名である。
[新堀通也]
イタリア
1970年代の大学改革後、日本研究の量的拡大がみられ、国立大学ではナポリ大学 東洋学研究所、ローマ大学 インド・東アジア研究所で日本学的研究が行われているほか、ボローニャ大学、フィレンツェ大学(マライーニ)、ベネチア大学などでは日本語、日本文化の教育研究がなされている。しかしイタリアでは、大学から形式的には独立した研究機関、とくにイタリア中東・極東研究所(IsMEO、1933)および東アジア経済社会研究所(1973)が活発に社会科学的日本研究に取り組んでいる。
[新堀通也]
ヨーロッパ諸国
ヨーロッパでは、そのほかの国にも、小規模ではあるが優れた日本学的研究を継続している大学がある。すでに触れたオーストリアのウィーン大学 日本研究所(1938、スラビーク、クライナー)、オランダのライデン大学 日本学・朝鮮学研究センター(1969)、デンマークのコペンハーゲン大学 東アジア研究所(1961、リディン)、ポーランドのワルシャワ大学 東洋学研究所(1956、コタンスキー)、スウェーデンのストックホルム大学 東洋語研究所(1964)などがそれである。
[新堀通也]
ロシア
帝政ロシア時代から日本研究の長い伝統をもっており、質量ともに今日も高い水準にある。戦争中の空白を経てモスクワ国立大学 東洋諸語研究所、サンクト・ペテルブルグ国立大学 東洋学部、極東国立大学 東洋学部などのほか、ロシア科学アカデミーの極東研究所、世界経済・国際関係研究所、世界歴史研究所、哲学研究所、とくに東洋学研究所、外務省の国際研究所などが専門分野ごとの日本研究を行ってきた。
ソ連時代の日本研究には、マルクス・レーニン主義的アプローチの優越、中央集権的管理、研究者のキャリアの多様性、外国との交流の不足、専門分化と共同研究の進行、現代を中心とする研究の増加などの特徴があった。
[新堀通也]
その他の諸国
こうした傾向のなかで、その他の地域でも日本研究が盛んになった。なかでもカナダでは日本研究が本格化したのは、1956年、ブリティッシュ・コロンビア大学アジア研究プログラムの開設に伴い、ドーアを招聘(しょうへい)して以来である。アルバータ、トロント、モントリオールの諸大学のほか、研究機関としてはブリティッシュ・コロンビア大学 アジア研究所(1978)、マギル大学 東アジア研究センター(1968)が代表的である。
オーストラリアは第二次世界大戦前、すでにシドニー大学でマードックJames Murdoch(1856―1921)やサドラーArthur Lindsay Sadler(1882―1970)による日本研究の歴史をもっているが、戦後、とくに日本との関係が深まるにつれて本格的に日本研究が始まった。オーストラリア国立大学、クイーンズランド大学、グリフィス大学、シドニー大学などで日本語教育と並んで日本研究が広範に行われている。
さらにアジアや中南米でも、近代化のモデルとしての日本への関心が高まり、しだいに日本研究機関が設けられるようになった。しかし、そのレベルはいまだ高いとはいえず、日本語教育の普及、日本語文献の翻訳などが中心になっている場合も多い。インドネシア大学、フィリピン大学 アジアセンター、アテネオ・デ・マニラ大学、チュラロンコーン大学、タマサート大学、マラヤ大学、シンガポール大学、ネルー大学、デリー大学、香港中文大学 東アジア研究センターなどアジア諸国の諸大学のほか、とくに最近、急速に韓国と中国の諸大学や研究所で日本研究が盛んになった。中南米ではメキシコ、ブラジルが盛んである。
日本研究の制度化のもう一つの具体化は、研究者の組織(学会)の成立である。アメリカのアジア研究学会(1941)、ヨーロッパ日本研究学会(1973)をはじめ、イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ、オーストラリア、韓国などに国ごとの学会が存在する。
このように日本研究は世界的な広がりをみせているが、その発達を阻む条件が1970年代に顕著になり始めた。大学の拡張に歯止めがかかって研究者の就職難がおき、それを見越して日本研究を志す優秀な学生が減ったこと、また財政の逼迫(ひっぱく)のため、研究機関や研究費の淘汰(とうた)が行われるようになったこと、などの条件がそれである。
それまで外国の日本研究に対して日本自身が援助することは、1953年に設立された国際文化会館以外にほとんどなかったが、こうした状況のもとで日本政府は1972年、国際交流基金を設立して、海外の日本研究機関や研究者に対して各種の援助を行うことになった。1973年にはいわゆる「田中基金」としてアメリカの10大学に、1981~1983年度には「大平(おおひら)記念基金」としてカナダのブリティッシュ・コロンビア大学の日本研究に資金援助が行われた。また日本の企業や財団も外国の大学に日本研究のための講座を寄付するなどの活動を始めた。1985年には大蔵省(当時)がアメリカの日本研究者を援助するために研究情報基金を設立、また国立の国際日本文化研究センターの設立も正式に決定された。外国の日本研究の振興の前提となる日本語教育、留学生や研究者の招致、文化交流の拡充に対する日本の役割の重要性が広く認められるようになっている。
1961年東京に設立されたスタンフォード大学日本研究センターを前身として、1963年アメリカおよびカナダの大学の共同機関として生まれた米加11大学連合日本研究センターは、徹底的な日本語教育を行うことで有名であるが、そこで教育された日本研究者も数多い。また1983年出版された9巻からなる『Kodansha Encyclopedia of Japan』は、外国の日本研究者に対して基本的な情報を提供する。
注目すべきは、日本研究自体を研究対象とする研究が上記の国際日本文化研究センター(通称・日文研)を中心に行われたことである。日文研は1988年以来3年計画で「世界の中の日本」というテーマのもとに、国際シンポジウムの開催と専門家による共同研究を行った。国際シンポジウムの年次テーマは「日本研究のパラダイム――日本学と日本研究」「対象と方法――各専門から見た日本研究の問題点」「文化研究という視点――日本研究の総合化について」の三つであり、その成果は『世界の中の日本』Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとして公刊され、共同研究の成果は日文研の機関誌『日本研究』10集『世界の日本研究―歴史と現状』、同資料編『世界の日本研究機関・年表(海外における日本研究)』(1994年)として公刊され、もっとも包括的かつ権威ある基本文献となっている。
[新堀通也]
『【自然】』▽『寺田寅彦著『風土と文学』(1950・角川新書)』▽『水山高幸他編『風土の科学』(1982・創造社)』▽『荒巻孚・高山茂美編『地球環境へのアプローチ―自然地理学入門―』(1993・原書房)』▽『和辻哲郎著『風土―人間学的考察―』(1987・岩波書店)』▽『阪口豊編『日本の自然』(1980・岩波書店)』▽『吉井敏剋著『日本の地殻構造』(1979・東京大学出版会)』▽『勘米良亀齢・橋本光男・松田時彦編『岩波講座 地球科学15 日本の地質』(1980・岩波書店)』▽『木村敏雄著『日本列島――その形成に至るまで』全3巻6冊(1977~1985・古今書院)』▽『木村敏雄・速水格・吉田鎮男著『日本の地質』(1993・東京大学出版会)』▽『吉川虎雄・杉村新・貝塚爽平・太田陽子・阪口豊著『新編日本地形論』(1973・東京大学出版会)』▽『貝塚爽平著『日本の地形』(岩波新書)』▽『貝塚爽平著『岩波グラフィックス14 空からみる日本の地形』(1983・岩波書店)』▽『山根一郎他著『図説日本の土壌』(1978・朝倉書店)』▽『吉野正敏著『自然地理学講座2 気候学』(1978・大明堂)』▽『吉野正敏著『日本の気候・世界の気候』(1979・朝倉書店)』▽『日本海洋学会編『海と地球環境』(1991・東京大学出版会)』▽『堀越増興・永田豊・佐藤任弘著『日本の自然7 日本列島をめぐる海』(1987・岩波書店)』▽『町田貞著『自然地理学講座1 地形学』(1984・大明堂)』▽『デュショフール著、永塚鎮男・小野有五訳『世界土壌生態図鑑』(1986・古今書院)』▽『『シリーズ 日本の自然・地域編 全8巻』(1994~1997・岩波書店)』▽『町田洋他編著『第四紀学』(2003・朝倉書店)』▽『太田陽子他編『日本の地形6 近畿・中国・四国』(2004・東京大学出版会)』▽『前川文夫著『日本の植物区系』(1977・玉川大学出版部)』▽『飯泉茂・菊池多賀夫著『植物群落とその生活』(1980・東海大学出版会)』▽『堀越増興・青木淳一編『日本の生物』(1985・岩波書店)』▽『文化庁編著『植生図・主要動植物地図1~47』(1969~1978・国土地理協会)』▽『内田亨ほか編『現代生物学大系1~15巻』(1984~1986・中山書店)』▽『太田次郎ほか編『基礎生物学講座1~11巻』(1995・朝倉書店)』▽『朝日新聞社編『朝日百科植物の世界』1~15巻(1997・朝日新聞社)』▽『矢野悟道編『日本の植生――侵略と攪乱の生態学』(1988・東海大学出版会)』▽『渡邊定元著『樹木社会学』(1994・東京大学出版会)』▽『竹内均・上田誠也著『地球の科学』(1971・日本放送出版協会)』▽『倉嶋厚・青木孝著『防災担当者のための天気図の読み方』(1976・東京堂出版)』▽『宮沢清治著『防災と気象』(1982・朝倉書店)』▽『朝倉正著『気候変動と人間社会』(1985・岩波書店)』▽『中島暢太郎著『気象と災害』(1986・新潮社)』▽『環境庁編『環境白書』各年版(大蔵省印刷局)』▽『町田洋・小島圭二編『自然の猛威』(1987・岩波書店)』▽『環境保全協議会編『環境破壊の歴史』(1993・環境保全協議会)』▽『谷山哲郎著『地球環境保全論』(1991・東京大学出版会)』▽『岡崎洋編『環境要覧'92』(1992・古今書院)』▽『メディア・インターフェイス編『地球環境情報1996』(1996・ダイヤモンド社)』▽『環境情報科学センター編『自然環境アセスメント指針』(1994・朝倉書店)』▽『樽谷修編『地球環境科学』(1995・朝倉書店)』▽『新藤靜夫・大原隆編『地球環境科学序説』(1996・朝倉書店)』▽『内外アソシエーツ編『環境問題情報事典』(1992・紀伊國屋書店)』▽『荒木峻・沼田真・和田攻編『環境科学辞典』(1994・東京化学同人)』▽『内島善兵衛編『地球環境の危機』(1992・岩波書店)』▽『不破敬一郎編『地球環境ハンドブック』(1994・朝倉書店)』▽『半谷高久著『日本環境図譜』(1986・共立出版)』▽『地球環境工学ハンドブック編集委員会編『地球環境工学ハンドブック』(1995・オーム社)』▽『自然環境アセスメント研究会編『自然環境アセスメント、技術マニュアル』(1995・自然環境研究センター)』▽『市川定夫著『環境学』(1995・藤原書店)』▽『横山長之・市川淳信編『環境用語事典』(1997・オーム社)』▽『通産省環境立地局編『環境総覧』(1996・通産資料会)』▽『気象庁『平成9年版今日の気象業務』(1997・大蔵省印刷局)』▽『気象庁『異常気象レポート'94』(1994・大蔵省印刷局)』▽『和達清夫監修『新版気象の事典』(1974・東京堂出版)』▽『気象ハンドブック編集委員会編『気象ハンドブック』(1979・朝倉書店)』▽『高橋浩一郎『災害論』(1977・東京堂出版)』▽『朝倉正編著『産業と気象のABC』(1990・成山堂)』▽『宮沢清治著『防災と気象』(1982・朝倉書店)』▽『浅井冨雄著『気象変動』(1988・東京堂出版)』▽『【歴史】』▽『クローチェ著、羽仁五郎訳『歴史叙述の理論及歴史』(1926・岩波書店)』▽『遠山茂樹著「時代区分論」(『岩波講座 日本歴史 別巻1』所収・1963・岩波書店)』▽『田村圓澄他編『日本思想史の基礎知識』(1974・有斐閣)』▽『笹山晴生著『日本古代史講義』(1977・東京大学出版会)』▽『石田一良編『時代区分の思想』(1986・ぺりかん社)』▽『朝尾尚弘著「時代区分論」(『岩波講座 日本通史 別巻1』所収・1994・岩波書店)』▽『岡崎敬・平野邦雄編『古代の日本9 研究・資料』(1967・角川書店)』▽『唐木順三著『日本人の心の歴史』上(1976・筑摩書房)』▽『平野仁啓著『続古代日本人の精神構造』(1976・未来社)』▽『永藤靖著『時間の思想―古代人の生活感情―』(1979・教育社)』▽『湯浅泰雄著『古代人の精神世界』(1980・ミネルヴァ書房)』▽『赤松俊秀著「愚管抄について」「南北朝内乱と未来記」(『鎌倉仏教の研究』所収・1957・平楽寺書店)』▽『黒田俊雄著「愚管抄と神皇正統記」(『日本中世の国家と宗教』所収・1975・岩波書店)』▽『大隅和雄著『愚管抄を読む』(1986・平凡社)』▽『奈倉哲三著「幕藩制支配イデオロギーとしての神儒習合思想の成立」(『世界史における民族と民主主義』所収・1974年度歴史学研究会大会報告・青木書店)』▽『小沢栄一著『近世史学思想史研究』(1974・吉川弘文館)』▽『伊豆公夫著『新版日本史学史』(1972・校倉書房)』▽『大隅和雄編『因果と輪廻』(『大系仏教と日本人4』1986・春秋社)』▽『遠山茂樹著『戦後の歴史学と歴史意識』(1968・岩波書店)』▽『永原慶二・鹿野政直編『日本の歴史家』(1976・日本評論社)』▽『田中明・宮地正人編『歴史認識 日本近代思想体系13』(1991・岩波書店)』▽『鹿野政直著「日本文化論と歴史認識」(『岩波講座 日本通史 別巻1』所収・1994・岩波書店)』▽『吉田孝著『律令国家と古代の社会』(1983・岩波書店)』▽『都出比呂志著『日本農業社会の成立過程』(1989・岩波書店)』▽『吉村武彦著『日本古代の社会と国家』(1996・岩波書店)』▽『戸田芳実著『日本領主制成立史の研究』(1967・岩波書店)』▽『竹内理三編『土地制度史1』(1973・山川出版社)』▽『永原慶二著『日本中世の社会と国家』(1982・日本放送出版協会)』▽『永原慶二著『戦国期の政治経済構造』(1997・岩波書店)』▽『網野善彦著『日本中世土地制度史の研究』(1991・塙書房)』▽『勝山清次著『中世年貢制成立史の研究』(1995・塙書房)』▽『木村茂光著『日本古代・中世畠作史の研究』(1992・校倉書房)』▽『池亨著『大名領国制の研究』(1995・校倉書房)』▽『佐々木潤之介著『幕藩制国家論』上下(1984・東京大学出版会)』▽『『大系・日本国家史』全5巻(1975~1976・東京大学出版会)』▽『竹内誠他編『教養の日本史』(1987・東京大学出版会)』▽『義江明子著『日本古代の氏の構造』(1986・吉川弘文館)』▽『佐藤進一著『日本の中世国家』(1983・岩波書店)』▽『網野善彦著『日本中世の非農業民と天皇』(1984・岩波書店)』▽『上横手雅敬著『日本中世国家史論考』(1994・塙書房)』▽『佐藤和彦著『日本中世の内乱と民衆運動』(1996・校倉書房)』▽『藤木久志著『豊臣平和令と戦国社会』(1985・東京大学出版会)』▽『歴史学研究会編『天皇と天皇制を考える』(1986・青木書店)』▽『高木昭作著『日本近世国家史の研究』(1990・岩波書店)』▽『村上泰亮・公文俊平・佐藤誠三郎著『文明としてのイエ社会』(1979・中央公論社)』▽『明石一紀「古代・中世の家族と親族」(『歴史評論』416号所収・1984・校倉書房)』▽『飯沼賢司「「職」とイエの成立」(『歴史学研究』534号所収・1984・青木書店)』▽『服藤早苗著『家成立史の研究』(1991・校倉書房)』▽『石上英一著「古代国家と対外関係」(『講座日本歴史2 古代2』所収・1984・東京大学出版会)』▽『村井章介著『アジアのなかの中世日本』(1988・校倉書房)』▽『荒野泰典著「日本の鎖国と対外意識」(『東アジア世界の再編と民衆意識』所収・1983・青木書店)』▽『荒野泰典著「18世紀の東アジアと日本」(『講座日本歴史6 近世2』所収・1985・東京大学出版会)』▽『藤田覚著「鎖国祖法観の成立過程」(『近世日本の民衆文化と政治』所収・1922・河出書房新社)』▽『紙屋敦之著『大君外交と東アジア』(1997・吉川弘文館)』▽『【政治・国際関係・防衛】』▽『内田健三著『戦後日本の保守政治』(岩波新書)』▽『後藤基夫他著『戦後保守政治の軌跡』上下(1994・岩波書店)』▽『富森叡児著『戦後保守党史』(1977・日本評論社)』▽『日本政治学会編『政治学年報1977 55年体制の形成と崩壊』(1979・岩波書店)』▽『石川真澄著『データ・戦後政治史』(岩波新書)』▽『渡辺治著『日本国憲法「改正」史』(1987・日本評論社)』▽『神島二郎編『現代日本の政治構造』(1985・法律文化社)』▽『正村公宏著『戦後史』上下(ちくま文庫)』▽『升味準之輔著『現代政治 1955年以後』上下(1985・筑摩書房)』▽『松下圭一著『現代日本の政治的構成』(1962・東京大学出版会)』▽『渡辺昭夫編『戦後日本の対外政策』(1985・有斐閣)』▽『濱口恵俊・公文俊平編『日本的集団主義』(1982・有斐閣)』▽『佐藤紀久夫著『国際国家ニッポン』(1986・教育社)』▽『鹿島平和研究所編『日本外交史 第28、29巻』(1973・鹿島研究所出版会)』▽『牛場信彦著『経済外交への証言』(1984・ダイヤモンド社)』▽『藤原彰著『軍事史』(1964・東洋経済新報社)』▽『山口二郎著『政治改革』(1993・岩波書店)』▽『加茂利男著『日本型政治システム』(1993・有斐閣)』▽『高畠通敏著『日本政治の構造転換』(1994・三一書房)』▽『江畑謙介著『日本が軍事大国になる日』(1994・徳間書店)』▽『【経済・産業】』▽『東京大学社会科学研究所編『現代日本社会』全6巻(1991~1992・東京大学出版会)』▽『現代日本経済研究会編『日本経済の現状(各年版)』(1979~1983年版・教育社、1984~1998年版・学文社)』▽『井村喜代子著『現代日本経済論』(1993・有斐閣)』▽『中村隆英著『日本経済――その成長と構造』第3版(1993・東京大学出版会)』▽『橋本寿朗著『日本経済論』(1991・ミネルヴァ書房)』▽『小宮隆太郎著『現代日本経済』(1988・東京大学出版会)』▽『宮崎義一著『日本経済の構造と行動』上下(1985・筑摩書房)』▽『南亮進著『日本の経済発展』(1981・東洋経済新報社)』▽『同講座編集委員会編『講座・今日の日本資本主義』全10巻(1981~1982)』▽『内野達郎著『戦後日本経済史』(講談社学術文庫)』▽『安藤良雄編『近代日本経済史要覧』第2版(1979・東京大学出版会)』▽『揖西光速・大島清・加藤俊彦・大内力共著『双書・日本における資本主義の発達』(1955~1970・東京大学出版会)』▽『大内力著『日本経済論』上下(1962、1963・東京大学出版会)』▽『篠原三代平著『日本経済の成長と循環』(1962・創文社)』▽『山田盛太郎著『日本資本主義分析』(1934・岩波書店、岩波文庫所収)』▽『向坂逸郎著『日本資本主義の諸問題』(復刻版1976・社会主義協会)』▽『室山義正著『日本安保体制』上下(1992・有斐閣)』▽『山澤逸平著『日本の経済発展と国際分業』(1984・東洋経済新報社)』▽『橋本寿朗・武田晴人共編『日本経済の発展と企業集団』(1992・東京大学出版会)』▽『青木昌彦著『日本企業の組織と情報』(1989・東洋経済新報社)』▽『柴垣和夫著『日本金融資本分析』(1965・東京大学出版会)』▽『『電子立国日本の自叙伝』全4巻(1991~1992・日本放送出版協会)』▽『小宮隆太郎他編『日本の産業政策』(1984・東京大学出版会)』▽『兵藤著『労働の戦後史』上下(1997・東京大学出版会)』▽『隅谷三喜男著『日本資本主義と労働問題』(1967・東京大学出版会)』▽『佐伯尚美著『ガットと日本農業』(1990・東京大学出版会)』▽『大内力著『日本農業論』(1978・岩波書店)』▽『熊野剛雄・龍昇吉共編『現代日本の金融』(1992・大月書店)』▽『寺西重郎著『日本の経済発展と金融』(1982・岩波書店)』▽『武田隆夫・林健久編『現代日本の財政金融』全3巻(1978、1982、1986・東京大学出版会)』▽『林健久・今井勝人共編『日本財政要覧』第4版(1994・東京大学出版会)』▽『安保哲夫編『日本的経営・生産システムとアメリカ』(1994・ミネルヴァ書房)』▽『板垣博編『日本的経営・生産システムと東アジア』(1997・ミネルヴァ書房)』▽『【社会】』▽『経済企画庁編『国民生活白書』各年版(大蔵省印刷局)』▽『田中宏、江橋崇編『来日外国人人権白書』(1997・明石書店)』▽『李青若『在日韓国人三世の胸のうち』(1997・草思社)』▽『桑山紀彦『国際結婚とストレス』(1995・明石書店)』▽『福永健太郎『デジタル情報革命のキーワード』(1997・中公PC新書)』▽『立花隆『インターネットはグローバル・ブレイン』(1997・講談社)』▽『David E.Kaplan & Andrew Marshall『The Cult at the End of the World : the Incredible Story of Aum』(1997・Arrow)』▽『【文化】』▽『『日本民俗文化大系』14巻・別巻1(1983~1986・小学館)』▽『梅棹忠夫著『日本とは何か――近代日本文明の形成と発展』(1986・日本放送出版協会)』▽『長谷川如是閑著『日本的性格』(1938・岩波書店)』▽『ルース・ベネディクト著、長谷川松治訳『菊と刀――日本文化の型』(社会思想社・現代教養文庫)』▽『上山春平監修『日本文明史』全7巻(1990・角川書店)』▽『伊東俊太郎著『比較文明と日本』(1990・中央公論社)』▽『【海外における日本研究】』▽『新堀通也編『知日家の誕生』(1986・東信堂)』▽『国際交流基金の各種報告書(年報、Newsletter、地域別日本研究の現状報告書など)』▽『国立国会図書館編『世界のみた日本(日本関係翻訳図書目録)』(1989)』▽『日本アソシエーツ編集部編『文献目録 日本論・日本人論の50年 1945~1995』(1996・日本アソシエーツ)』