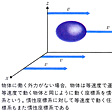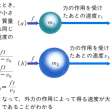精選版 日本国語大辞典 「慣性」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「慣性」の意味・わかりやすい解説
慣性
かんせい
外力の作用を受けないとき、すなわち自由運動を行っているとき、物体はその速度を変えることなく運動を保ち続ける。この性質を慣性という。すべての物体が慣性という性質をもつことを述べたのが、ニュートンの運動の第一法則である、慣性の法則である。静止状態は速度ゼロの状態であるので、慣性には、静止状態にある物体が外力の作用を受けないときに静止状態を持続する性質も含んでいる()。
物体はつねになんらかの外力を受けているので、外力の作用をできるだけ除いていくことによって慣性を実験的にみいだすことができる。自由運動を行う物体とともに移動する座標系、すなわち慣性座標系からみれば、外力の作用を受けたときの物体の速度の変化を正しくみいだすことができる。同じ大きさの外力を作用させても、得られる速度の変化は物体によって異なる。これは物体の慣性の大小によるものである。その大きさを示す物理量を定義し、これを慣性質量という()。
加速度aをもつ座標系からみれば、自由運動をしている物体は、-aの加速度で運動しているようにみえる。このように、加速度aの座標系からみたとき、物体は外力のほかに-maの力を受けているように運動する。この力を慣性力という。乗り物が急カーブをしたときに感じる力は、この力である。慣性抵抗ともいう。外力を受けた加速度aの物体に対して、外力のほかに、かりに-maの力をさらに加えるとすれば、物体は自由運動を行うか、つり合いの状態になる。このときの-maの力も慣性力という。
[田中 一]
改訂新版 世界大百科事典 「慣性」の意味・わかりやすい解説
慣性 (かんせい)
inertia
外部から力の作用を受けない物体は,初めに静止していればそのまま静止を続け,初めにある速度をもっていればその速度を保持して等速度運動を続ける。この性質を慣性と呼ぶ。このことを法則の形ではっきり述べたのがニュートンの運動の第1法則であり,それは慣性の法則とも呼ばれる。物体に力が作用すれば速度は変化する。速度変化の時間的割合は加速度で表されるが,同じ物体にいろいろな力を加えたときに生ずる加速度は力に比例し,方向も力の方向と一致する。これを運動の第2法則といい,力をF,加速度を aとしてベクトルの関係式F=maで表される。比例定数mはその物体の質量と呼ばれる。この式をa=F/mとかくと,同じ力Fによって生ずる加速度も物体の質量によって異なり,質量の大きいものほど加速度が小さいことを示す。したがって質量の大きいものは速度を保持しようとする性質が大きいと考えてよいから,物体のもつ慣性の大小を表す量が質量であるということができる(質量)。慣性があるために,飛行機や高速の電車内においても乗客はその速度を体に感ずることはなく,速度の変化のみを感ずる。そして,まったくゆれずに等速度で走る乗物内では,窓の外を見ない限り,走っているかどうかの判定ができない。これに対してゆれたり回転している場合は,力が作用しなくても加速度を生ずるように見える。この見かけの加速度を生じさせる見かけの力(座標系の加速度をaとすると-ma)のことを慣性力といい,遠心力はその一例である。
執筆者:小出 昭一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「慣性」の意味・わかりやすい解説
慣性【かんせい】
→関連項目ガリレイ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「慣性」の意味・わかりやすい解説
慣性
かんせい
inertia
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
普及版 字通 「慣性」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の慣性の言及
【質量】より
…ニュートンの考えを整理し,解析学を使って今日の形に力学を表現したL.オイラーが質量の定義も現在のものに明確化した。すなわち,すべて物体には,もっている速度をそのまま保とうとする性質があり,これを慣性というが,その大小がこの物体の〈実質の量〉の大小を表すと考えてそれを質量と呼ぶ。物体として位置の明確な質点を考えると,運動状態はそれがもつ速度で表され,それを変えるには力が必要である。…
【物理学】より
…というのも,P=WVという考え方は,運動力が増せば速さも大きくなるという常識にかなう論点をもつ反面,運動力が加わらないときは速さがない,つまり静止しているという帰結をもち,それは,手から離れたボールやこぎ終わったボートが,直接外から運動力を加えられないにもかかわらずなおしばらくは運動を続けるという経験になじまないからである。一言でいえば,近代にいう慣性的運動の説明が必要になる。これが問題の第1である。…
※「慣性」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新