精選版 日本国語大辞典 「居合」の意味・読み・例文・類語
い‐あい ゐあひ【居合】
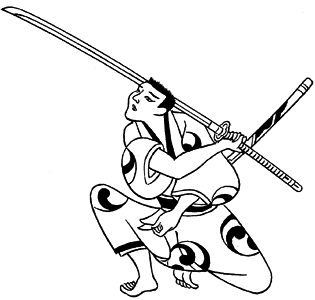
おり‐あい をりあひ【居合】
おり‐あ・う をりあふ【居合】
い‐あ・う ゐあふ【居合】
い‐あわ・せる ゐあはせる【居合】
い‐やい ゐやひ【居合】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「居合」の意味・わかりやすい解説
居合 (いあい)
現在,居合道と呼ばれるが,古くは居相,坐合,抜刀,抜剣,鞘の中(うち)などとも称した。戦国時代,戦場における急な変に対処し,すばやく腰の刀を抜いて敵の攻撃に応じ,敵を制するための武術として編み出されたものである。これが江戸時代になって治世における武術としての性格を強くし,刀の鯉口(こいぐち)の切り方,柄への手の掛け方,抜き方などの基本的所作を身につけるとともに,平生の屋内や往来における急な変に対応するための武術として武士のたしなみとなった。居合の技法は,機に応じて座位より刀を抜き出すところをその特徴とするが,立っての技(立居合,あるいは抜刀術)もあり,また,柄を取られたり,組まれたりした場合,これを投げあるいはおさえるといった柔術的な技法も少なくない。居合流派の数は多く,なかでももっとも大きな位置を占めるのは16世紀後半の人,林崎甚助重信の神明夢想流(神夢想林崎流ともいう)で,林崎は〈抜刀の始祖〉といわれる。その伝系には,無楽流(長野無楽斎),田宮流(田宮平兵衛成正)をはじめ,新田宮流(和田平助),長谷川流(長谷川主税英信)など有力な流派が多い。さらに,片山伯耆(ほうき)流(片山伯耆守久安),関口流(関口八郎右衛門氏心(うじむね))なども林崎の伝を受けたとされており,後世に与えた影響は非常に大きい。ほかに著名な流派としては,一宮流,上泉流,水野流,不伝流,影山流,制剛流,無外流,水鷗(すいおう)流などがあり,そのほか剣術や柔術に付属していたものも含めると非常に多数にのぼる。
明治初期,武道は一時衰退したが,居合もこの期に多くの流派が消滅し著しく衰微した。しかし,1895年の大日本武徳会設立を機にしだいに盛んになった。昭和に入ってからは〈居合道〉と称するようになり,中山博道(1873-1958)らの活躍などもあって広く普及していった。第2次世界大戦後一時中断されたが,やがて復活し,1954年に全日本居合道連盟が結成され,56年には全日本剣道連盟に居合道部が設けられた。66年第1回全日本居合道大会が開催され,形の演武により勝敗を競う競技化の試みがなされ,68年には〈全日本剣道連盟制定居合〉が定められ,流派を超えた統一の形ができた。それに加えて安価な居合練習刀が普及したことなどにより,子どもや女性の愛好者も加わって居合道人口は急激に増加した。
執筆者:中林 信二
居合抜き
江戸の太平期に入り,居合が見世物化した大道芸。元禄・宝永(1688-1711)のころ富山の反魂丹売(はんごんたんうり)の香具師(やし)松井一家が,人寄せに居合抜きを演じた。享保期(1716-36)にはその系統から出た松井源左衛門の名が見え,また長井兵助も歯磨売の人寄せに演じて名高い。高足駄に白だすきのいで立ちで,三宝を積み重ねた上にのり,4~5尺(1.2~1.5m)の刀を抜いて見せたといわれる。
執筆者:編集部
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「居合」の意味・わかりやすい解説
居合【いあい】
→関連項目神道流
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「居合」の意味・わかりやすい解説
居合
いあい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の居合の言及
【松井源水】より
…松井家の元祖玄長は,越中礪(砺)波(となみ)の出身で,霊薬反魂丹(はんごんたん)を創製し,2代目道三のときに富山袋町に移住して,武田信玄から売薬御免の朱印を受けた。延宝・天和(1673‐84)のころに,4代目玄水が江戸へ出て反魂丹を売りはじめたが,その宣伝,販売のために,箱枕をいろいろと扱う曲芸〈枕返し〉や居合抜きなどを演じた。享保(1716‐36)ごろには,居合抜きのほか曲独楽(きよくごま)(独楽)を演ずるようになり,将軍家重の浅草寺参詣のおりには上覧に供して御成(おなり)御用の符を拝領した。…
※「居合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
