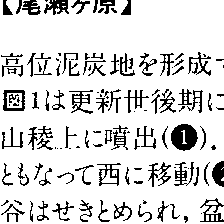改訂新版 世界大百科事典 「尾瀬ヶ原」の意味・わかりやすい解説
尾瀬ヶ原 (おぜがはら)
阿賀野川支流,只見川の源流部の小盆地に形成された日本屈指の高位泥炭地(高層湿原)。長さ6km,幅2km,面積7.6km2。原のほぼ2/3が群馬県,1/3が福島県,ごく一部が新潟県に属し,東方の尾瀬沼とともに日光国立公園の一部をなしていたが,2007年尾瀬国立公園として分割。1960年特別天然記念物に指定されている。湿原は至仏山,大白沢山,景鶴山,燧(ひうち)ヶ岳など標高2000m級の山々に囲まれて細長い三角形をしており,標高は1400m内外で,原を貫流する沼尻(ぬしり)川,只見川,ヨッピ川などの河川により東から下田代,中田代,上田代,背中アブリ田代などに分断されている。尾瀬沼から流れてきた沼尻川と,原を北東に流れるヨッピ川は合流して只見川となり,原の北東端で平滑(ひらなめ)ノ滝および三条ノ滝となって落下し,北流する。ほとんどの貫流河川沿いにハルニレ,ミズナラ,ヤチダモなどからなる拠水林(水辺にある林)が発達している。
尾瀬ヶ原は高位泥炭地という特異な景観,開花期の華麗な湿原植物,あるいは紅葉などによって知られた日本有数の観光地であるが,原の学術的価値は,北方系生物の宝庫であること,高層湿原特有の微地形が大規模に発達していること,少なくとも最終氷期後半以降の自然環境の記録の保存庫であるという3点に集約される。原には北方系湿原植物が多数見られ,本州はもとより北海道にも比類ないものである。また著しい隔離分布をしている北周極要素(北半球の高緯度に分布する要素)が多数ある。ナガバノモウセンゴケは本州唯一の確実な産地であり,オゼコウホネは北海道などにあるネムロコウホネと同じもので,氷期の遺存種とみなされている。原の特異な景観の構成に重要な役割を果たしているミズゴケは20種に及び,キダチミズゴケが広範囲に生育していることなど種構成およびその生態からみて日本では他に類例を見ない。また,動物では本州における北方系のトンボ類のほとんど全部がここに生息し,北方系のトンボの世界における事実上の南限とみなされている。
原を上空から眺めると,各所に指紋状,レース状,はしご状,墨流し様の模様が見られる。これらは泥炭でできた帯状の高まりと紡錘形の凹みからなる微地形複合体で,前者をフィンランド語でケルミ,後者をドイツ語でシュレンケという。比高がせいぜい20~30cmしかないので夏の植物の繁茂している時期にははっきりしないが,植物の枯れた時期には地上でも明確に識別できる。もう一つの顕著な微地形は総数1500余の池塘である。深さは最大で3.3m,大部分2m以下。泥炭が堆積する前にあった河跡湖から発達したものと,シュレンケから発達したものとがある。いずれの微地形も北ヨーロッパなどではよく発達するが,これほど大規模に発達した湿原は日本にはない。連続して堆積している泥炭層の最大の厚さは4.5m,その基底の年代は7000~7600年である。尾瀬ヶ原は燧ヶ岳の溶岩によって只見川河谷がせき止められてできた湖から発生したと考えられていた。しかし1972年以来中田代の3ヵ所で最深81mに及ぶ試掘が行われたが,大規模な湖の形成を裏づける証拠は得られず,原の泥炭層の基底は河成堆積物から成ることがわかった。したがって尾瀬ヶ原はよくいわれているような,湖の埋積の最終段階にできたものではなく,河川の後背湿地から発達したものである。地表下ほぼ20mの深さの盆地堆積物の年代は3万8400年であり,これらの堆積物の花粉分析によると,2万2000年前ころの尾瀬ヶ原は過去最も寒く,年平均気温が現在よりも7.5℃ほど低く,雪ははるかに少なかった。なお現在最も厚いところで4m以上の積雪が見られる。
執筆者:阪口 豊
自然保護
尾瀬に入るには群馬県側からは上越線沼田駅から戸倉を経て,(1)大清水~三平峠~沼,(2)富士見下~富士見峠~原,(3)鳩待峠~原,福島県側からは(4)第3セクター会津鉄道会津田島~檜枝岐(ひのえまた)~沼山峠~沼などのコースがある。1960年代から交通が便利になり,とくに(3)(4)のルートは比較的楽なため,多くの入山者があって(2006年度約34万人),自然環境の悪化が問題となってきた。71年の環境庁設置,〈尾瀬の自然を守る会〉の発足を契機に自然保護運動が高まり,尾瀬は日本における自然保護運動のシンボルとして注目を浴びるようになった。こうして,70年に大清水~沼山峠間で始められた尾瀬自動車道の建設は,71年大清水~岩清水間で中止され,75年には大清水からの一般車の進入も禁止された。尾瀬では通路用の木道が設けられて湿原への立入りを禁じ,生活雑排水の処理やごみ持帰り運動などの努力も続けられている。
執筆者:大沢 正敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「尾瀬ヶ原」の意味・わかりやすい解説
尾瀬ヶ原【おぜがはら】
→関連項目片品[村]|湿原|至仏山|泥炭地|檜枝岐[村]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「尾瀬ヶ原」の意味・わかりやすい解説
世界大百科事典(旧版)内の尾瀬ヶ原の言及
【湿原】より
…この段階では雨水の供給のみに依存する降水涵養型の典型的な高層湿原になる。尾瀬ヶ原はその最も代表的な例である。高層湿原がドーム状に中央がもり上がるのは,地下水面が深くやや乾燥し,かつ富栄養な水が流入する周縁部よりも中央部のミズゴケ類の生長がよくなるからと考えられている。…
※「尾瀬ヶ原」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新