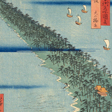精選版 日本国語大辞典 「天橋立」の意味・読み・例文・類語
あま‐の‐はしだて【天橋立】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
日本歴史地名大系 「天橋立」の解説
天橋立
あまのはしだて
- 京都府:宮津市
- 天橋立
橋立は文珠の海岸にある
「丹後国風土記」逸文には次のように記される。
天橋立はこの土地の人間にとって「神の住み給う所」とうけとられ、のちの世までも橋立を破壊から守ることともなった。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「天橋立」の意味・わかりやすい解説
天橋立
あまのはしだて
京都府北部、日本海に臨む宮津湾と阿蘇海(あそかい)を隔てる砂州(さす)。「天ノ橋立」とも記す。天橋立の名は早く『丹後国風土記(たんごのくにふどき)』にみられ、松島、宮島とともに古来日本三景の一つとして名高く、特別名勝に指定されている。天橋立は、宮津湾西岸の江尻(えじり)から対岸の文珠(もんじゅ)に向かって南西に延び、全長約3.3キロメートル、幅40~100メートル。湾内を流れる潮流と風によって運ばれた砂の堆積(たいせき)によるもので、雪舟(せっしゅう)の晩年の作『天橋立図』に描かれた白砂青松の地であり、7000本余のマツが植えられ、歌枕(うたまくら)としても知られる。砂州の先端と文珠との間は「文殊の切戸(きれと)」とよばれ、狭い水路をなし、通船に便利なように回旋橋が架けられている。文珠地区は「知恵の文珠」とよばれる智恩寺の門前町で、旅館街をなしている。また江尻の背後にある傘松公園(かさまつこうえん)は天橋立の展望に優れ、「股(また)のぞき」で知られる。北西の成相(なりあい)山には西国三十三所28番札所の成相寺がある。
[織田武雄]
『『朝日百科 日本の国宝 別冊 国宝と歴史の旅11 「天橋立図」を旅する――雪舟の記憶』(2001・朝日新聞社)』
百科事典マイペディア 「天橋立」の意味・わかりやすい解説
天橋立【あまのはしだて】
→関連項目岩滝[町]|奥丹後半島|籠神社|砂州|旋開橋|丹後天橋立大江山国定公園|智恩寺|成相寺|宮津[市]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「天橋立」の意味・わかりやすい解説
天橋立 (あまのはしだて)
京都府の日本海側宮津湾奥にある砂州。宮津市江尻から南へのびて文珠に向かう全長3km以上,幅40~110mの狭長な砂州で,東側の宮津湾と西側の阿蘇海とを仕切っている。南側に切れめがあって,北部を大天橋,南部を小天橋といい,両者は大天橋で結ばれる。小天橋は文珠の沿岸に沿って延びており,間の狭い水道は切戸(きれと)あるいは文珠ノ瀬戸などと呼ばれ,開閉式の回旋橋で結ばれている。砂州上に6000本以上の松が並ぶ景勝の地で,松島,宮島(厳(いつく)島)とともに日本三景として知られる。早くは《丹後国風土記》逸文にみえているが,後に《小倉百人一首》に加えられた小式部内侍の歌によまれたり,藤原実行宅が〈海橋立(あまのはしだて)殿〉と称されているなど平安時代にはすでに有名であった。1952年特別名勝に指定され,また若狭湾国定公園の一部となっている。
執筆者:金田 章裕
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天橋立」の意味・わかりやすい解説
天橋立
あまのはしだて
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
事典 日本の地域遺産 「天橋立」の解説
出典 日外アソシエーツ「事典 日本の地域遺産」事典 日本の地域遺産について 情報
デジタル大辞泉プラス 「天橋立」の解説
事典・日本の観光資源 「天橋立」の解説
天橋立
「日本の白砂青松100選」指定の観光名所。
天橋立
「日本の渚・百選」指定の観光名所。
天橋立
「日本十二景」指定の観光名所。
天橋立
「日本三景」指定の観光名所。
出典 日外アソシエーツ「事典・日本の観光資源」事典・日本の観光資源について 情報
世界大百科事典(旧版)内の天橋立の言及
【丹後国】より
…《和名類聚抄》に記された田数も4700町余で,これも隠岐国についで少ない。のちに日本三景の一とされる天橋立もすでに風土記にみえており,名勝として親しまれた。小式部内侍の〈大江山生野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立〉の歌は有名である。…
【智恩寺】より
…天橋山と号する。天橋立(あまのはしだて)の南岸にあってはるかに成相(なりあい)寺と相対する景勝の地にある。本尊文殊菩薩(鎌倉期,重要文化財)の霊験は,謡曲《九世戸(くせのと)》《丹後物狂(ものぐるい)》でも知られ,日本三文殊の一つとされる。…
【日本三景】より
…宮城県の松島,京都府の天橋立(あまのはしだて),広島県の厳島(いつくしま)を日本三景と称している。松島や天橋立はすでに平安時代中期までに,京都の貴族たちには広く知られた名勝地で,歌や名所絵のよき題材とされていた。…
※「天橋立」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新