精選版 日本国語大辞典 「南蛮船」の意味・読み・例文・類語
なんばん‐せん【南蛮船】
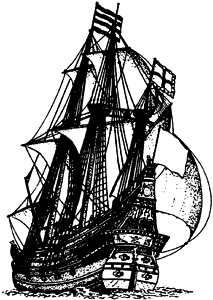
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
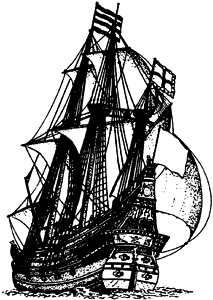
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
16世紀中頃から南方経由で日本に来航したヨーロッパ船の総称。主としてポルトガル船・スペイン船をさし,黒船ともいった。1543年(天文12)ポルトガル人の種子島漂着を契機に,薩摩国・豊後国・平戸・長崎などに来航し,貿易とともにキリスト教の布教活動を行った。ポルトガル船はインドのゴアからマカオ,スペイン船はマニラを中継地とし,季節風を利用して渡来した。船型に変遷がみられ,1639年(寛永16)の来航禁止に至るまでの期間,初期は大型のカラック,中期はガレオン,末期は小型化したガレウタに大別される。南蛮屏風には当時の南蛮船が特徴的に描かれている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…遠敷の市場は建武のころには定期市となっており,さらに1407年(応永14)には〈日市〉すなわち常設市となった。小浜の市も南北朝期にはかなりの繁栄を見せていたし,小浜港の発展も顕著で,08年,12年には南蛮船が日本国王への進物などを舶載して着岸している。このとき使臣の宿をつとめた〈問丸本阿弥〉がいたように,問丸の発達もいちじるしかった。…
※「南蛮船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新