精選版 日本国語大辞典 「加水分解酵素」の意味・読み・例文・類語
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
加水分解反応を触媒する酵素の総称で、ヒドロラーゼhydrolaseともいう。酵素を系統的に分類したときの一つのグループ名称になっている。
国際生化学連合(現在は国際生化学・分子生物学連合)では酵素の分類と命名に関する委員会を設け、1961年に同委員会の結論が報告された。それによると、酵素を、それが触媒する化学反応にしたがって六つのグループに分類しており、加水分解酵素はその第3類に与えられた名称である。この類に属する酵素は、生体内で行われているさまざまな加水分解を触媒しており、その数も多く、また重要なものも少なくない。加水分解酵素はさらに次の11の小グループに細分類されている。
(1)エステル結合に作用するもの。カルボン酸、リン酸、硫酸などのエステルを加水分解する。
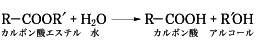
リパーゼ、コリンエステラーゼ、フォスファターゼなどがこのグループに含まれるほか、遺伝子工学の分野で非常に多く利用されている制限酵素(DNAの特定の塩基配列を識別して2本鎖を切断するエンドヌクレアーゼ)なども、このグループに含まれる。
(2)グリコシル化合物に作用するもの。糖の還元性ヒドロキシ基との間でつくられたグリコシド結合を加水分解する。α(アルファ)-およびβ(ベータ)-アミラーゼのほか、グリコシダーゼやヌクレオシダーゼなどがある。
(3)エーテル結合に作用するもの。チオエーテル結合に作用するもの(アデノシルホモシステイナーゼなど)とエーテル結合に作用するもの(エポキサイドヒドロラーゼなど)がある。
(4)ペプチド結合に作用するもの。トリプシン、キモトリプシン、カルボキシペプチダーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼなど、多くのタンパク分解酵素(プロテアーゼ)がこれに属する。
(5)ペプチド結合以外の炭素‐窒素結合に作用するもの。ウレアーゼ、アスパラギナーゼ、ペニシリナーゼのほか、ヌクレオシドやヌクレオチドのデアミナーゼがある。
(6)酸無水物に作用するもの。ATPアーゼをはじめとして、多くのピロリン酸結合を加水分解する酵素がこれに含まれる。
(7)炭素‐炭素結合に作用するもの。キヌレイナーゼなどが含まれる。
(8)ハロゲン族元素との結合に作用するもの。ジイソプロピルフルオロフォスファターゼなどがある。
(9)リン‐窒素結合に作用するもの。フォスフォアミダーゼが含まれる。
(10)硫黄(いおう)‐窒素結合に作用するもの。スルホグルコサミンスルファミダーゼがある。
(11)炭素‐リン結合に作用するもの。フォスフォノアセトアルデヒドヒドロラーゼがある。
IUBMBによって推奨されている加水分解酵素の名称は、多くの場合基質名に接尾語、アーゼ(-ase)をつけたものである。したがって基質+アーゼという名称の酵素は、その基質を加水分解する酵素と解釈してよい。たとえばウレアーゼureaseは尿素ureaの加水分解酵素。
[笠井献一]
ヒドロラーゼともいう。加水分解反応を触媒する酵素の総称。生体内では種々の化学結合が,それぞれ特異的な加水分解酵素の作用によって切断される。アミラーゼ,ペプシン,トリプシン,リパーゼなどの消化酵素は消化管内に分泌され,食餌中の高分子物質等を単糖,アミノ酸,脂肪酸など吸収可能な低分子量の構成単位に加水分解し,異化的代謝の第一段階を担う。細胞内にも高分子物質をその構成単位に分解する酵素が種々存在し,外来性の異物の分解や,細胞内で不要になったタンパク質や,核酸などからのアミノ酸やヌクレオチドの回収を行っている。細胞構成成分の無差別加水分解による細胞の自己消化が起きないように,これらの酵素はリソソームlysosomeと呼ばれる細胞器官に局在し,細胞の他の部分からは隔離されている。このような広義の栄養に関係した働きのほかに,生理機能の調節や制御に関係するものもある。例えば環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼやプロテインホスファターゼは,それぞれ基質となるリン酸エステル結合を分解する作用を通じて,環状ヌクレオチドが仲介する細胞の代謝応答の制御に寄与している。またコリンエステラーゼは,シナプス前膜から放出されるアセチルコリンを分解して興奮の後始末をする。
ある種のタンパク質加水分解酵素(プロテアーゼ)は特定のタンパク質分子の特定のペプチド結合のみに特異的に作用(限定分解)し,均一な高分子量の断片を生じさせる。このような分解様式は生体の機能にとってきわめて重要である。細胞質で合成されたタンパク質が,あるものは細胞外に分泌され,またあるものは特定の細胞器官に局在するというように,本来あるべき場へ正しく配送される過程で,最初に合成されたポリペプチドの性質は限定分解によって少しずつ変化させられていく。またトリプシンをはじめ細胞外で働くプロテアーゼの多くは不活性のチモーゲンとして分泌され,のちに限定分解を受けることによってはじめて活性型となる。血液(血清)中には一群の,このようなプロテアーゼの前駆体(血液凝固因子)がある。これらは血管の損傷(出血)が起きると限定分解を受けて連鎖的に活性化され,最終的にはフィブリノーゲンから,血餅(けつぺい)の主成分であるフィブリンを生成させることにより,血液凝固(止血)において重要な役割を果たす。一方ATPを加水分解するATPアーゼは,筋収縮や能動輸送のような,物理的仕事にエネルギーを供給する役割を担っている。このように加水分解酵素は,作用する化学結合の種類のみならず,その生理的役割においてもきわめて多彩である。
生体内の環境においては,加水分解反応の平衡は事実上不可逆的に分解の方向にかたよっている。したがって種々の生体高分子物質は加水分解の単純な逆反応によって合成されるのではなく,常に分解反応とは異なる酵素によって,別個の生化学的反応経路を通って合成される。
→環状AMP →タンパク質分解酵素
執筆者:川喜田 正夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ヒドロラーゼ,水解酵素ともいう.加水分解反応を触媒する酵素の総称.加水分解作用を受ける結合の種類によって次のように分類される.
(1)カルボン酸,チオール,リン酸,硫酸のエステル結合に作用するエステラーゼ,
(2)グリコシル結合に作用するグリコシルヒドロラーゼ(グリコシダーゼ)類,
(3)チオエーテルなどエーテル結合に作用するもの,
(4)ペプチド結合に作用するペプチダーゼ,
(5)環状,鎖状アミドならびにアミジン類のC-N結合に作用するもの,
(6)ホスホリル基の酸無水物に作用するもの(たとえば,アデノシントリホスファターゼ,
(7)ケト化合物などのC-C結合に作用するもの,
などがある.[別用語参照]酵素命名法
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…しかし酵素は高分子化合物であるため,現在の医療技術ではこれを細胞内の適当な場に押し込んで,細胞内でその作用を発揮させることには成功しておらず,現状としてはもっぱら細胞外ないし細胞表面への酵素の作用に基づく薬効に期待しているわけである。
[加水分解酵素類の消化薬としての応用]
この目的にはさまざまの動植物起源,微生物起源のデンプン,タンパク質,脂肪などに対する加水分解酵素が使われる。一般的なものとしては,ウシやブタの膵臓から抽出したパンクレアチン(デンプン,タンパク質消化を主とし,脂肪消化作用ももつ),各種のジアスターゼ類(発芽中のオオムギ,コウジカビなどからのデンプン消化酵素が主体),パパイアの果汁からのパパイン(タンパク質消化酵素)などがよく知られている。…
… 炭水化物中の糖と糖の間の結合の分解および生成はいずれも特異的な酵素によってつかさどられている。分解酵素はほとんどの場合加水分解酵素であり,これらはグリコシダーゼglycosidaseと総称されている。合成酵素は糖転移酵素(グリコシルトランスフェラーゼglycosyltransferase)と総称され,糖の活性化型である糖ヌクレオチドから単糖単位を移して糖鎖をのばす働きをする。…
※「加水分解酵素」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新