精選版 日本国語大辞典 「劇場」の意味・読み・例文・類語
げき‐じょう ‥ヂャウ【劇場】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
演劇あるいはこれに類する技芸を上演する建物で,大きく分けて演ずる場である舞台と,それを享受する観客席から成る。演劇の場としての劇場の空間構成には,屋外,室内の別を問わず,大別して二つの形態が認められる。すなわち主たる演技空間(舞台)を観客席が取り囲む形のものと,演技空間と観客席が相対するものとである。演劇は原初的には神事,祭事から発生したので,最初期の劇場は必然的に演技空間中心の前者に近い形態をとったと考えられる。そして演劇の芸能としての性格から,俳優の演技を鑑賞するのに好都合な後者の形態が発達した。古代ギリシア以来近代に至るまでの劇場空間の展開は,前者の形態から後者の形態への移行の歴史ともいえる。しかし20世紀初頭からの実験演劇の展開とともに,演技空間と観客席とを一体化した空間を求める動きが起こった。すなわち,観客席が舞台のまわりを囲む円形劇場への志向は,この空間構成に演劇の原初的な感動をよみがえらせる場を求めようとするものであった。この模索は今日も続けられている。しかし,そうした空間は歴史を通じて忘れ去られていたわけではなく,世界中の神事や祭事,民俗芸能,サーカスなどの娯楽的な催物の伝統のうちに,つねに変わらず存在していたのである。
劇場(ギリシア語theatron,ラテン語theatrum)という言葉は,古くから宇宙,世界の寓意をもって用いられてきたが,これは劇場が神と人間の運命の全様相を描く演劇の場であることに由来する。前1世紀のローマの建築家ウィトルウィウスが書いた建築書は,ヘレニズム時代の劇場の様相を知るうえで重要な資料だが,ルネサンス期の人々が劇場平面の割り出し方を,円環のうちに劇場の主部をおさめると解釈したのは,まさにこの寓意につながってのことであった。科学史家F.A.イェーツは,シェークスピア劇などを上演したエリザベス朝のロンドンの劇場(スワン座,グローブ座など)がこの原則に従って造られていたとしている。さらに劇場という言葉は中世以来,庭や鏡などの言葉とともに集成や大成の意でしばしば書物の題名に用いられてきたが,これも同じ理由によるものである。
執筆者:横山 正
1758年,ジュネーブ生れの哲学者ジャン・ジャック・ルソーは,彼の故郷の町に大きな劇場を建てるように勧める友人のダランベールに対して,私たちが必要としているのは〈陰気な顔をした少数の人を閉じ込めておく暗い洞窟〉のような劇場ではありませんと,長い反論を書き送った。
この《ダランベールへの手紙》におけるルソーの反劇場論の基礎には,古代ギリシアの哲学者プラトンの反演劇論がある。プラトンは《国家》のなかで〈悲劇〉を批判して,それは人々の涙もろい部分に集中的に働きかけて,人間はもともと劣ったみじめな存在であるというまちがった観念になれさせてしまうと論じた。同様に,ルソーも彼の理想とする小さな都市共和国にとって,〈悲劇〉に代表される演劇や,そのいれものとしての〈排他的な〉劇場はよけいなものであると考えた。その代りに〈広場のまんなかに花で飾った1本の杭を立てよう〉と彼は提案した。この杭のまわりに,すべての人々が登場人物となって顔を見せあい,愛しあうような祝祭の場をつくりだそう。それこそが私たちに必要な演劇なのだというのである。
ルソーが生きた18世紀は,ヨーロッパの各地に巨大なオペラ劇場をはじめとする常設劇場が続々と建設された時代だった。それまでの満足な屋根や壁もない中世的な劇場に代わって,厚い石の壁や天井によって外界から遮断され,その内部がさらにプロセニアム・アーチによって舞台と客席とに2分割された〈近代劇場〉が新たに登場する。それはまたたくまにヨーロッパ全土を席巻し,19世紀には,ヨーロッパ列強の帝国主義的拡張にともなってアジアやラテン・アメリカなど,非ヨーロッパ世界にまで広がっていった。イギリスの植民地だったインドでは,早くも1795年にベンガル語による演劇のための常設劇場がカルカッタに出現した。スペインの植民地だったフィリピンの主都マニラでは1820年代に,おくれて1914年に北京で最初の西洋式劇場〈第一舞台〉が建てられる。こうして20世紀初頭までには,〈近代劇場〉はほぼ全世界の都市を制覇するにいたった。日本で最初の本格的な洋式劇場といわれる帝国劇場の建設は1911年のことである。
〈近代劇場〉の特徴は空間の等質性にある。地球上のどんな土地に行っても,いったん劇場に足を踏み入れれば,そこには他の国,他の都市とまったく同一の構造をそなえた空間が用意されている。この性質によって,〈近代劇場〉は〈普遍的な人間性〉に対する信頼を世界中に広める役割を果たした。人間の心理や社会のしくみを精密に表現する装置となり,また舞台技術の発展と結びついて,それまでは存在していなかった新しい演劇的よろこびを生みだす原動力となった。
反面,それは世界のさまざまな土地に存在していた多様な劇場のかたちを画一化し,それぞれの土地に固有の演劇の楽しみ方を押しつぶしてしまう結果をもたらした。そのことによって,シェークスピアのグローブ座や江戸時代の歌舞伎劇場,インドや中国の芝居小屋にあった宇宙的な力との交感の場,演じる者と見る者との交流の場としての劇場の特質が失われた。演劇は劇場のうちに閉じこめられ,演じる者と見る者とが分断される。したがってルソーの劇場批判は,たんにプラトンの反演劇論をそのまま引き継いでいただけではない。彼は〈近代劇場〉がヨーロッパに誕生してまもない時期にあって,やがてそれがもつであろう危険性--すなわち〈大国のむなしい花やかさ〉のシンボルとしての劇場が,それぞれの土地に固有の〈質素な催しや祝祭〉をのみこんでしまう可能性について,いちはやく警告を発していたのである。
〈近代劇場〉は都市近代化の産物でもあった。ルソーの時代,パリやロンドンを皮切りにヨーロッパの諸都市では中世都市につきものの混乱--悪疫,大火災,犯罪などを一掃すべく,大がかりな都市改造計画が進められていた。迷路のような路地をつぶし,木造の家を石や煉瓦で建て替え,上下水道を設置する。この過程に並行して,都市の安全と衛生のための法規が整えられた。その際おおぜいの人間が一度に集まってくる劇場が,都市の悪の温床としてまっさきに改造の対象とされたことはいうまでもない。
イギリスにおける〈近代劇場〉の祖と見なされる第2次ドルーリー・レーン劇場(1674開場)は,1665-66年のペスト流行と大火災につづくロンドン改造計画のなかで建設されている。エリザベス朝の木造・円形の公衆劇場とは対照的な石造・長方形の建造物であった。さらに第3次ドルーリー・レーン劇場(1794開場)では,火事にそなえて屋根裏に五つの巨大な貯水タンクを設置し,〈アイアン〉と呼ばれる鉄のカーテンによって舞台と客席との間を仕切るというくふうが,同時代のフランスの劇場から導入された。日本の場合も同様である。1872年の新富座移築にはじまる明治の劇場改良運動の背景には,都市改造と衛生改良という二つの国家規模での安全運動があった。厚い壁と天井によって外界から分離され,内部空間が舞台と客席とに分割された〈近代劇場〉のかたちは,こうして都市の安全を第一の価値として守るという理念によって裏打ちされたまま今日にいたる。〈近代劇場〉とは〈安全劇場〉なのである。
都市住民の安全や健康を守るために劇場は管理される。それは誰にとっても必要な仕事であろう。だが管理の行過ぎは往々にして演劇の生命力を枯らしてしまう。1970年前後から,欧米の街頭演劇や実験的なパフォーマンス,韓国の広場劇,ラテン・アメリカやアフリカの民衆演劇運動,日本のテント劇場など,演劇を〈近代劇場〉の壁のうちから解き放って,演じる者と見る者との二分法をこわし,世界(宇宙)との生き生きした関係を回復しようとする試みが,世界の各地で見られるようになった。いずれの試みも厳しさを増しつつある管理社会の内側で,それとは別の原理に立つ相互的な人間関係をつくりだそうとする意図をもつ。〈近代劇場〉が獲得した富に基づき,さらにその先で,広場のまんなかに立てる新しい〈花で飾った1本の杭〉が求められている。
→小劇場 →前衛劇
執筆者:津野 海太郎
イギリスの演出家P.ブルックは,演劇論《なにもない空間》(1968)の冒頭で,〈なにもない空間をひとりの人間が横切り,それをもうひとりの人間が見ているだけで,演劇行為は成立する〉という趣旨のことを述べている。つまり,演劇が成り立つためには演技者と観客という,機能を異にする2種類の人間の存在が必要なのである。したがって演劇行為の場としての劇場は,この両者のそれぞれがいる場所,すなわち舞台と客席とを含むものでなければならない。そして,この二つが互いにどんな関係にあるかによって,劇場の根本的な性格,またそこで上演される劇の性格が決まる。
近代以後の劇場においては,舞台ないし演技空間と客席とは截然と分かたれるのが原則である。舞台は劇場の一方の端に設置され,その床は前方の1辺のみによって客席と接する。客席から見ると,演技空間はあたかも四角形の額縁で囲まれた1枚の絵のように感じられる。そこで,こうした構造をもった舞台を額縁舞台と呼ぶことがある。たてまえ上は,舞台は四つの壁で囲まれた空間であり,客席と舞台とを隔てる壁だけが透明であるとされる。観客はこの目に見えない〈第四の壁〉を透かして,別世界の事件をのぞき見ることになる。舞台で劇が演じられていないときには,この壁があるとされる場所に幕が下ろされ,舞台を観客の目から遮る。つまるところ,この種の舞台の前提にあるのは,舞台空間とは現実世界の空間の断片の忠実な再現であるという考え方であり,観客の存在は認めがたいものとなる。現実世界の事件の場合には,それを外部の別の世界から誰かが眺めることはありえないからである。したがって俳優は,現に観客がいるのにそれがいないかのようにふるまうことを要求される。具体的にいうと,劇中人物が観客に向かって直接に語りかけるといった演技は成立しにくい。せりふについては,独白やその一種としての傍白のように,現実生活において語られることがまれで不自然とされるものは好まれない。本質において,客席から分離した舞台は,演劇をもっぱら現実の再現と見なす考え方に根ざしており,それが戯曲や演技のあり方をも規定するのである。
これに対して舞台と客席との区別が明瞭でない劇場においては,演劇は現実に従属しない自律的な存在という性格をもつようになる。そして,近代以前の劇場はおおむねこのような構造をとっていた。たとえばエリザベス朝のイギリスの場合,舞台は客席に向かって張り出し,客席はそれを三方から囲むようになっていた。このような舞台を額縁舞台に対して張出舞台と呼ぶことができる。日本の現代の能舞台も,床が2辺において客席に接し,さらに〈橋懸り〉と呼ばれる部分でも客席に接しているから,一種の張出舞台だといえる。歌舞伎の舞台は額縁舞台にきわめて近いが,それでも花道が客席を貫いているために,演技空間と客席との区別はあいまいになっている。一般に張出舞台においては,俳優が客席に向かって直接に語りかけるという演技は抵抗なく受け入れられ,また二つの空間を幕が隔てることも原則としてはない。つまり,両者の関係は額縁舞台の場合よりも密接なのである。現代においては,客席が舞台を完全に囲むいわゆる円形劇場や,演技空間と客席とが同一の空間になっている劇場が再評価されているが,この傾向の背後にあるのは,演劇を単に現実の記号としてとらえ,現に存在している観客を無視するというやり方に反省を加えて,演劇を自律的なものとしてとらえ直そうとする考え方である。
2種類の舞台の違いは,劇の表現手段のうち俳優の演技以外のもの,特に舞台装置や舞台照明のような視覚的手段のあり方の違いにも関連がある。一般に,額縁舞台では精巧な装置が用いられるのに対して,張出舞台では装置は象徴的になったり,簡略化されたり,あるいはまったく用いられなかったりする傾向がある。もちろんこれは一般論であって,実際には額縁舞台で象徴的な装置を使った劇が演じられることも珍しくないのだが,ただ,それぞれの舞台の本来の性格からしてこうなることが多いのである。たとえば能舞台には〈作り物〉と呼ばれる簡単な装置がときどき現れるだけで,本格的な装置は組まれない。エリザベス朝のイギリスの張出舞台では,装置は事実上なかった。精巧で写実的な装置が用いられなかったのは,そうすることが不可能であったからではなく,そもそも舞台上に視覚的な意味での現実を再現するという考え方が乏しかったからであると考えるべきであろう。近代以前の舞台では,装置が果たす機能は俳優の演技,とりわけせりふによって担われた。つまり,客席に向かって開かれた舞台,客席から分離していない舞台とは,俳優中心の劇の舞台であり,そこでは現実の空間の再現は重視されないのである。
このことは舞台照明が果たす機能についてもいえる。張出舞台はその構造からして象徴性の強いものであるから,照明によって現実の月光や太陽光線などを再現するやり方にはなじまない。事実,能舞台においてはこの種の照明はまったく用いられない(一方,歌舞伎は江戸時代から高度に象徴的な照明技法が発達した演劇である)。現在のような能楽堂の出現は明治以後の現象で,それ以前には能は太陽光線の下で演じられていた。同じことはエリザベス朝のイギリス演劇にも,前5世紀のギリシア演劇にも当てはまる。これらの劇が用いたのは野外劇場であったといえる。そこで,人工的手段によって自然光線の再現を試みることはおよそ無意味である。さらにいうなら,屋内の劇場であっても事情は変わらない。エリザベス朝のイギリスには屋内の劇場もあり,そこではろうそくなどによる照明が用いられたが,これは現代の能楽堂の照明と同じく,舞台が観客によく見えるためのものであって,現実のイリュージョンを作り出そうとする照明とは根本的に異なる。後者のような照明が成立したのは,電気の使用が一般化した近代以後のことで,それ以前には照明を調節して現実らしさを生み出すことは不可能だった。しかし重要なのは,これが技術的に可能であるかどうかではなくて,演劇を現実の再現,現実の記号としてとらえるかどうかである。舞台の構造も装置や照明の使い方もすべてこの点にかかわっており,また,この点が劇場全体の構造を決定するのである。
執筆者:喜志 哲雄
近代にまでつながるヨーロッパの劇場建築の原型は,古代ギリシアにおいて完成された。前5世紀のギリシアの劇場は演技空間であるおそらく円形の平土間(オルケストラorchēstra)を斜面の観客席(テアトロン。〈劇場〉の語源)が取り囲むものであった。ヘレニズム期までには,オルケストラ背後の人工の高台にスケネskēnēと呼ばれる楽屋としての機能をもつ建物が造られ,その高台上のスケネ前の奥行きの浅い空間プロスケニオンproskēnionが俳優の演技の場として確立した。この時期の劇場のようすを知る好例はギリシアのエピダウロスの劇場の遺構(前4世紀)である。しかし古代ギリシアではこの例に見るごとく,劇場は屋外で,しかも自然の斜面を利用して観客席を造らなければならなかった。ローマ時代の劇場はギリシアのそれの発展だが,架構技術の発達によって高層の観客席の築造が可能になり,劇場は初めて建築的に自立し,祭祀からも離れて都市に不可欠の公共建築としての性格を帯びる。オルケストラは半円形になり,舞台には木造の屋根が,また観客席にも布製の日よけが架け渡されたようである。
中世においてはギリシア・ローマ以来の演劇形式が失われたために,恒久的な劇場施設の建設は行われなかったようだが,中世都市の発展に伴い,都市の広場などに仮設の舞台を築いて受難劇などの上演が盛んに行われた。それも往々にして単一の舞台でなく,広場の各所に複数の装置を配置しての上演が行われている。しかしこれは演劇空間としてはきわめて示唆に富むものの,劇場建築というよりはのちにバロック期に最盛期を迎える都市のページェント,祝祭の伝統につながる面を多く有していたと見るべきであろう。
劇場建築の再興は,ルネサンス期におけるギリシア・ローマ古典劇の復原上演とともに始まった。ウィトルウィウスの建築書の記載内容の考証からは,イタリアのビチェンツァのアカデミーが建てたテアトロ・オリンピコ(A.パラディオ設計。1584)のごとき復古的な形式のものも生まれたが,宮廷などの建物内に組み込まれる劇場の大勢は,観客席がページェントの場ともなり,また貴顕の席ともなる平土間を包みながらも,大きくは正面の奥行きのある舞台空間に相対する形態のものへと向かった。これには,この時期に開発され急速な進展を見せた透視図法が奥行きの感覚をもった舞台背景や書割をつくり出したことが大いにあずかっていると言えよう。こうして17世紀の初め,アレオッティGiovanni Battista Aleotti(1546-1636)が設計したパルマの宮廷劇場テアトロ・ファルネーゼ(1619)において,以後の劇場建築で広く用いられるプロセニアム・アーチproscenium archが登場する。これは奥行きの深い舞台の前方に額縁状の枠を配して観客席との間を仕切るものである。また同じ17世紀には,ベネチアを中心とする大衆劇場の成立も見られ,平土間の周囲を何層もの桟敷席が囲む,以後ヨーロッパで一般的となる形態も確立された。これは貴族がその収入源として営んだもので,現存する最古の例はユーゴスラビアのフバル島にあり,1612年の竣工である。一方,旅役者の仮設舞台の伝統は古代からあり,各地にそれを下敷きにした民衆劇上演の舞台形式も発達していた。イギリスのエリザベス朝の劇場では,周囲を桟敷席が取り囲む平土間部分に三方を開いた舞台(張出舞台)が突出している。こうした空間には,劇場が原初的に保持している俳優と観客が一体になった祝祭性が失われずに存在していたのである。
しかしオペラの隆盛と劇場の社交場化は,プロセニアム・アーチに限られた舞台を,平土間およびそれを取り囲む幾層にも重ねられた桟敷席から眺める形態を定着させ,さらにホアイエやラウンジなどに観客席に劣らぬ広大な空間を割くようになっていった。とくに18世紀の後半以降,ヨーロッパの大都市は競って大オペラ劇場を建設している。ミラノのスカラ座(1778),ベネチアのフェニーチェFenice劇場(1792),ロンドンのローヤル・オペラハウス(1849)などはその例であり,C.ガルニエの設計になるパリのオペラ座(1875)はその頂点を飾るものである。
こうした劇場形式の階級性,あるいは視角・音響上の非合理性を指摘し,完全に舞台と観客席が対峙するいわゆる近代の劇場の形態の先鞭をつけたのは,音楽家W.R.ワーグナーが建築家ゼンパーの協力によって建設したバイロイト祝祭劇場(1876)であった。以後,視角や音の反響を考慮したすぐれた劇場がたくさん生み出されたが,一方,観客すべてが舞台に向かうことによって,プロセニアム・アーチの採用後も,なお古いオペラ劇場などが保持していた観客席が馬蹄形に構成されることによる空間の一体化の喜びを失わしめる結果も生んだ。これへの反省と演劇の本義に立ち戻らんとする姿勢が,冒頭に述べた円形劇場の模索を生んだのである。またそれよりも早く,すでに19世紀半ばあたりから,プロセニアム・アーチを廃してエリザベス朝の劇場様式を求める実験も行われている。今日では,多様な演劇形態を反映して,劇場空間に対する,仮設,常設の別を問わない活発な実験が試みられている。
→演劇
執筆者:横山 正
芸能や舞踊が発生した時代から舞楽,延年,田楽,猿楽,能・狂言と時代が下るにしたがい,舞台は定型化の道をたどるが,観客席はなお野外であった。勧進という形式の興行がひろく行われるようになって,屋根付きの桟敷席を仮設し,一定の入場料金を徴収しはじめている。外側をむしろ・竹矢来・幕などで囲って,特定の場所を観客席として限定したのである。
常設の劇場が建てられたのは,江戸時代に入ってからである。江戸時代の初期に出雲のお国が京都四条河原で歌舞伎踊を創始し,これを模倣する女歌舞伎が盛んに催されたころは,舞台・桟敷・土間・外郭などは前代の能舞台の様式をそのままうけついでいる。外囲いも竹矢来にむしろ張りで,勧進能を模した程度のもので,観客席には屋根がなかった。慶長・元和(1596-1624)の初期歌舞伎の劇場を描いた屛風絵などから,舞台の間口と奥行きは方2間あるいは方3間で,後座に囃子方が並び,舞台上の切妻破風の屋根の下三方に水引幕をめぐらし,能舞台と同様に四本柱という構造を知りうる。江戸では,すでに興行地化していた中橋南地(現在の日本橋通3丁目付近)や,葭(吉)原の遊里が歓楽地として栄えはじめた。1624年(寛永1)2月に,初世猿若(中村)勘三郎が中橋に歌舞伎常芝居猿若座(後の中村座)を創設した。常設の歌舞伎劇場のはじめである。前年の1623年に初世勘三郎が歌舞伎興行の許可を幕府に出願し,奉行板倉四郎右衛門から免許をうけて櫓(やぐら)を上げた。
寛永期には江戸中橋南地のほかに京都四条,大坂道頓堀にも芝居町が形成され,ある程度の様式をそなえた劇場がつくられた。江戸においては中村座を嚆矢(こうし)とし,ついで1633年1月の都伝内による堺町の都座,翌年3月村山又三郎による堺町の村山座(後の市村座),42年3月山村小兵衛による木挽町5丁目の山村座,しばらくおくれて56年(明暦2)河原崎権之助による木挽町5丁目の河原崎座,60年(万治3)4月森田太郎兵衛による木挽町5丁目の森田座(後の守田座)の創業というように,次々に歌舞伎の常設劇場が建設されていった。いずれも舞台間口3間を定式とし,土間席は野天のままで,わずかに舞台部分と桟敷席に屋根が架してあった。そのため雨天には公演は行えず,晴天の日には櫓太鼓を打って興行が催されることを知らせたという。ほかに公許されない〈宮地芝居(みやちしばい)〉が,近世初期には盛んだった。神社や寺院の境内,あるいは盛場ではやった小屋がけの小芝居である。
1629年(寛永6)に女歌舞伎・女舞・女浄瑠璃が禁制され,続く若衆歌舞伎も,風俗を乱すという理由で52年(承応1)6月に禁止されると,新しく野郎歌舞伎が誕生した。芸態も,〈物真似狂言尽〉や〈島原狂言〉,さらに〈続き狂言〉へと成長した。そのことは劇場構造の上でも,ドラマ劇場としての発達を促すこととなり,64年(寛文4)ごろにはじめて用いられたといわれる引幕と,大道具の使用,また花道の出現(1668ごろ)などをみるにいたった。この過程で,徐々に能舞台の様式を離脱して,劇的な内容の進歩に相応した歌舞伎劇場へと脱皮を重ねていく。貞享から元禄初め(17世紀末葉)には,市村座の舞台間口が3間(約5.4m)から5間(約9m)に拡大したという。一方,85年(貞享2)2月には,大坂道頓堀に竹本義太夫が操芝居の櫓を上げ,次の元禄期から宝永・正徳期(17世紀末から18世紀初め)へかけて,近松門左衛門と提携して人形浄瑠璃界に新風を起こしている。このころの歌舞伎では,楽屋や桟敷にも3階建ての構造がみられ,また劇場と隣接した芝居茶屋とのあいだに,通路が設けられたりした。たび重なる江戸の大火で焼失する劇場があとをたたなかったため,幕府は1723年(享保8)に瓦屋根と塗壁を設置条件とする防火規則を義務づけた。その結果,すべての劇場が全蓋式になった。日本の劇場建築史上に画期的な転機であった。1720年1月に類焼した中村座の新築にあたって,楽屋を3層構造にしたが,公儀をはばかって2,3階をそれぞれ中二階と本二階と呼称した。市村座も森田座も,24年以降これにならい,ここから楽屋の細かい約束と制度が生みだされた。中村座が全蓋形式の劇場として改築された24年に,それまでの舞台間口3間を6間半に,花道の長さを8間に広げ,また観客席に向桟敷を1側増設し,さらに3層の桟敷を設けている。間口12間,奥行き20間程度の敷地に建てられた劇場だから,およそ600人ぐらいの観客を収容したのではないかと推定される。
宝暦年間(1751-64)には,舞台機構の上での改新的な数々の技術改革が実施された。セリ上げ(1753),狂言作者並木正三による回り舞台(1758)の発明,スッポン(1759),がんどう返し(1761),次の明和期には引割り,さらに1789年(寛政1)には田楽返しが創案されて,歌舞伎の演出上多彩な展開を可能とした。すでに歌舞伎劇場の舞台面では,1761年には舞台上の破風屋根を除去したし,目付柱・脇柱も撤去して独自の展開をすすめる条件が整えられた。文化・文政期(19世紀前半)の文化の爛熟期は,前代の劇場の様式をそのままうけついだが,4世鶴屋南北の怪談物や仕掛物が一般にうけいれられる風潮もあった。11世長谷川勘兵衛ら大道具師の活躍が,劇場建築や舞台装置を写実的なものにしていく上に果たした功績も見のがせない。1841年(天保12)の堺町,葺屋町一帯の火災で,中村座・市村座や操座が焼失した機会に,おりから天保の改革を断行しつつあった幕府は,劇場を焼跡に再築することを認めず〈芝居取払〉を決めて,浅草猿若町へ市村座・中村座・河原崎座の歌舞伎劇場と,操り人形の薩摩座・結城座の移転を命じた。1842,43年にそれぞれが新築開場し,吉原の遊里や浅草寺,また奥山に隣接した猿若町に芝居町が形成され,幕末の30年間にわたって殷賑(いんしん)をきわめる。歌舞伎大道具方の棟梁12世長谷川勘兵衛によって,安政期(1854-60)に,それまで客席にあってじゃまであった柱を除く〈亀甲梁(きつこうばり)〉が工夫された。
明治維新を迎えると,歌舞伎を拘束していた幕府の諸条例が次々に廃止されていく。座元以外の者にも興行の自由が保証され,また猿若町に限られていた劇場建築も解放されて,新たに劇場免許制がしかれた。まず1872年(明治5)に江戸三座の一つ森(守)田座の守田勘弥が,京橋区新富町6丁目へ進出して新富座を新築し,同年10月に華々しく開場した。当時の文明開化と欧化主義の影響もあって,場内の設備には新様式が用いられ,有効間口11間(約19.8m)の舞台がまちを直線状にし,外人用椅子席を設けたほか,桟敷席と土間を上中下3等級別とした。以後,中村座は86年に浅草鳥越町へ,市村座は92年に下谷二長町へ転出した。また1889年11月には,木挽町3丁目に歌舞伎座が新築開場した。外装は洋風,内部は和風の3階建てで,定員は1824,舞台間口13間,直径9間の回り舞台と,7間の蛇の目回し,さらに5尺(1.5m)幅の花道をそなえていた。歌舞伎劇場の舞台と客席が,明治期になって急に広がっていったのは,営利を求める商業ベースの反映といってよい。客席に突出していた付舞台を失い,上手に竹本の床,下手に下座を固定して定型化したのも明治以降のことである。西欧の劇場の理念の影響をうけて,プロセニアム舞台(額縁舞台)がつくられたのは,96年の川上座(神田三崎町)がはじめといわれている。オーケストラ・ボックスが設置されたのは,1908年11月に高等演芸場という名称を付して竣工した純洋風の有楽座からである。11年3月開場の本格的洋式劇場といわれた帝国劇場は,新しい釣り物の機構と,電動式回り舞台や,臨時オーケストラ・ピットを設備したのをはじめ,茶屋・出方を廃止して食堂・売店を設置し,有楽座と同様に椅子指定席とした。コメディ・フランセーズの建築様式を模した近代的な劇場である。日本における新劇の専門劇場は,関東大震災の翌24年に小山内薫・土方与志らによって創立された築地小劇場が最初である。舞台間口6間,高さ3間で,定員508席の小劇場であるが,クッペルホリゾントやプロンプター・ボックスを備え,わが国の新劇運動の歴史に大きな役割を果たした。関東大震災による劇界の被害は,東京市内で〈焼失した劇場は二十八場,活動写真館は四十三館〉(《新演芸》大正13年1月号の〈東都劇壇震災史〉)に及ぶ。
震災後に,復興または新しく建設されたおもな劇場は,24年に本郷座・演伎座・松竹座・市村座・帝国劇場・邦楽座に前記の築地小劇場,25年の歌舞伎座とつづく。25年に新たに新橋演舞場,30年に大阪四ッ橋の文楽座や東京劇場,32年に大阪歌舞伎座,33年に有楽町の日本劇場,34年に東京宝塚劇場,35年に有楽座,37年に浅草の国際劇場などが次々に竣工した。大正から昭和へかけて,歌舞伎・新派・新国劇・歌劇・バレエ・新劇・文楽や舞踊などが,上記の劇場はもとより巡業先の各地の劇場やホールで,撩乱たる多様化と繁栄の時代を迎えたのである。第2次世界大戦中,末期になるにつれ移動演劇や演劇興行も停止され,空襲の激化にともなって各地域の大部分の劇場が被災した。戦後にふたたび復興と再建の季節を迎えることとなった。再復興した劇場のほかに,54年には第1次俳優座劇場(客席401)が新劇専門の小劇場として,また文楽上演を考慮した道頓堀の朝日座(客席1000,1956),大阪の梅田コマ劇場(客席2044,1956),新宿コマ劇場(客席3000,1956),日生劇場(客席1340,1963),帝国劇場(客席1950,1966),国立劇場(客席,大劇場1746,小劇場630,1966),国立演芸場(客席300,1979),国立能楽堂(客席591,1983),国立文楽劇場(客席753,1984)などが新たに開場した。あわせて県民ホール,市・区民会館,公会堂などの多目的ホールが,全国的な規模でひろく設立されているところに,今日の特徴をみることができよう。
→芝居 →能舞台 →舞台
執筆者:藤波 隆之
舞台,客席の周辺にはその機能を支える種々の施設が設けられる。これらは表の施設と裏の施設に大別される。表の施設とは,劇場の入口から切符売場,ロビーを経て観客席へ至る,もっぱら観客のサービスに供する施設で,レストランやバー,喫茶室なども適宜設けられ,一種の社交の場を形成する。ロビーなどは一般的には観客が舞台芸術の世界に無理なく溶け込めるような雰囲気が好まれるが,特殊な演出意図のある劇場では,逆に観客に違和感を与えるような空間づくりをする場合もある。裏の施設とは,楽屋や稽古場,舞台装置や衣装の製作場,事務室など,舞台芸術をつくり上げ,上演を維持するのに必要な施設のことである。裏の施設は劇場の運用形態,所属組織,上演方式等によって大きく異なる。ヨーロッパ,特にドイツ語文化圏の劇場は,舞台芸術の制作・上演に必要なすべての職種を一つの組織体としてまるがかえする形態をとっており,したがって劇場の裏には,楽屋はもちろんのこと,各種の稽古場,倉庫,製作場などが完備され,全体として非常に大規模な施設となっている。他方,日本やアメリカの場合,劇場は必ずしも専属の劇団を持っておらず,上演の場だけを提供する貸劇場の形態をとるものが多い。この場合,稽古など制作プロセスのほとんどは劇場外にある劇団側の施設で行われ,また舞台装置や衣装などは,他社に発注される。したがって劇場には,必ずしも完備した稽古場や製作場が設けられる必要はなく,実際そうした施設を持っている劇場は少ない。
演目の上演方式も劇場の施設形態に影響を与え,レパートリー・システムのように,毎日演目が入れ替わる方式では,ストックの大量の舞台装置類,衣装類などを収納する倉庫が完備し,毎日の入替え作業に十分な作業スタッフが配備されていることが円滑な劇場運用の前提となる。反対にロングラン・システムのような場合では,舞台上に一度舞台装置を飾り込んでしまえば,公演が終了するまで舞台に放置することができるので,特別大規模な道具類の倉庫は必ずしも必要ではない。楽屋の規模や構成もそこで上演される演目によって左右される。歌手,舞踊家,オーケストラ,俳優等出演者の総数や種類によって楽屋の機能が異なるからである。このほか,市民会館のように多目的な使用が考えられる劇場では,さらにどの演目に設計条件を合わせるかあらかじめ十分な検討が必要となる。
執筆者:清水 裕之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
演劇、舞踊、オペラなどを上演し、多数の観客が集まってこれを観覧するための施設。西欧各国の劇場をさすことばのもととなったのは、古代ギリシア劇場の階段状の観客席をさすテアトロンtheatronである。英語のシアターtheatre, theater、フランス語のテアートルthéâtre、ドイツ語のテアーターTheater、イタリア語のテアトロteatroなどはすべてこのギリシア語に由来するもので、劇場という意味から、さらに演劇そのものをもさして用いられる。
[横山 正]
ヨーロッパの劇場の源流は古代ギリシアおよび古代ローマの劇場にある。いずれの文化においてもそうであったように、原初の演劇は祭祀(さいし)と分かちがたく結び付いており、古代ギリシアの劇場はディオニソス神祭祀にかかわる場として聖域に建てられた。アテナイのそれがアクロポリスの麓(ふもと)に営まれたのはその一例である。ギリシアの劇場の構成は、初め、コロス(合唱団)の演技する円形の平土間(オルケストラorchestra)を階段状の観客席(テアトロン)が囲むものであった。しかし、ドラマとしての構成が進み、コロスのなかから俳優が独立するにしたがい、舞台正面のスケネskeneとよばれる建物が楽屋となり、さらにその前の細長い歩廊のプロスケニオンproskenionが俳優の演技の場として用いられ、スケネの壁面がいわば舞台の背景を形づくるようになった。遺構の現存するもののなかでギリシア劇場の姿をもっともよく伝えるエピダウロスの劇場(前4世紀)は、すでにこの形態を示している。
古代ローマの劇場はこのギリシア劇場の形式の発展であるが、オルケストラが半円形になって観客席が舞台に相対する度合いがさらに強まったほか、舞台に木造の屋根がかけられたのが特徴であった。観客席に布製の日よけがかけられることもあったようである。しかし最大の変化は、ローマ人が連続アーチを重ねる架構を応用したことで、これによって劇場は、丘の斜面を離れて平地に自由に建てられるようになり、演劇の祭祀からの自立と相まって、古代ローマでもっともポピュラーな公共建築の一つとなった。ローマ劇場の遺跡は今日ヨーロッパの各地にみることができる。
中世における演劇活動の活発化は、おそらく10~12世紀の中世都市の勃興(ぼっこう)と軌を一にしていると思われる。しかし、固定した劇場建築の存在を裏づける資料は発見できない。中世において盛んに行われた受難劇などの上演は、木造の仮設舞台を聖堂前の広場や中央広場にいくつも並べる形か、あるいは山車(だし)式の移動舞台によって行われた。仮設の舞台は古代ギリシアの旅役者によってもすでに使用されており、ルネサンス以後も劇場建築とは別に、祝祭のページェント、旅役者の興行の場として、演劇の原初的な感動をよみがえらせる存在であり続けた。
劇場建築の再興は、ルネサンス期の古代劇上演と、それに伴う古代劇場再現への模索に始まった。人文主義者たちによるその上演は、まずは宮廷の広間や庭園に仮の舞台を設けてのものであり、やがて宮廷あるいは当時西欧各地に生まれつつあったアカデミーのための恒久的な劇場の創設へと向かった。この間の重要なできごとは、透視図法の開発とその研究の進展で、これは背景画の発達、さらには消点をすこしずつずらせた書割を幾枚も重ねて見せる技法など、舞台空間の展開に大きな影響を与えた。なかでも16世紀前半のイタリアの建築家S・セルリオが、紀元前1世紀のローマの建築家ウィトルウィウスの記述に従ってその『建築書』に載せた、喜劇・悲劇・サティロス劇3種用の舞台背景図は、とくに人々の広く知るところとなり、その影響も大きかった。前二者は王宮や神殿、あるいは町屋と、いずれも建築や市街を描くものであったが、サティロス劇用のものは自然の森を描いており、これは当時愛好された牧歌劇のかっこうの背景となるものであった。
16世紀イタリアの恒久的な劇場施設として現存する最古のものは、建築家A・パッラディオの設計になるビチェンツァのアカデミーの劇場、オリンピコ座(1584竣工)である。これは市街風景をバックにした奥行の浅い舞台に半楕円(だえん)形の観客席が相対する、古代ローマ劇場の形式に倣った構成であった。ここでは舞台背面の街路が、錯視の利用で実際よりもはるかに深く見えるように仕組まれているのが興味深いが、この種の仕掛けは多かれ少なかれこの時代の舞台構成に見られるものであった。ただ16世紀のイタリアの劇場建築の主流は、オリンピコ座のような形式のものではなく、テアトロ・ダ・サーラとよばれる、広い矩形(くけい)のホールの短辺に舞台がとられ、他の3辺に観客席のとられる形式のもので、中央の平土間が主たる演技空間であった。パラディオの弟子のスカモッツィが1588年にデザインしたサビオネタの劇場は、この形式と古代劇場風の形式とを折衷したものであり、17世紀初頭、この流れからプロセニアム・アーチproscenium archが舞台を観客席の空間からくぎり取る様式が生まれた。その最初の例は、G・B・アレオッティが1617年、パルマ公ラヌッチョ1世の命によって建造に着手したファルネーゼ座である。平土間を囲んでU字形をなす観客席に相対する舞台は奥行を増し、いまだ宮廷劇場の形式を踏襲しながらも、プロセニアム・アーチの額縁の中での演技を鑑賞する近代の劇場の形式(いわゆる額縁舞台)が生まれたのである。袖(そで)書割を両袖に幾層も重ねて奥行を強調するこの形式は、17世紀のなかばまでにアルプス北方の諸国にももたらされた。
一方この時代に、宮廷以外の場所での上演形式が固定化していく傾向もみられた。たとえばエリザベス朝イギリスのスワン座やグローブ劇場(グローブ座)は、何層にも重なる観客席に向かって突出した舞台をつくり、さらに高舞台も使用しての立体的な演出も行われたようである。これは旅籠(はたご)屋の中庭につくられた仮設舞台に遠源をもつものと思われるが、科学史家F・イェーツは、これらが円環に収まる平面構成をもっていることから、それを古代ローマの建築家ウィトルウィウスの『建築書』の影響下の創案とする説をたてている。続く17世紀の重要な動向は、ベネチアを中心とする大衆劇場の成立である。これは貴族がその収入源として営んだもので、プロセニアム・アーチの舞台に相対する平土間の観客席の周囲を数層の桟敷(さじき)席が囲む形につくられていた。このよく保存された例が、当時ベネチア領だったクロアチアのフバールに残っている(1612竣工)。これは以後のヨーロッパの劇場の主流をなす形式の先鞭(せんべん)をつけたものであった。すなわち、18世紀なかばまでには、プロセニアム・アーチに限られた奥行の深い舞台の前にオーケストラ・ボックスを置き、床勾配(こうばい)のある平土間の観客席と、それを囲む馬蹄(ばてい)形の幾層にも積み重なった桟敷席という基本形式が完成する。これはイタリアでまず開発されたが、オペラの隆盛とともに、従来の矩形や半円形の劇場にとってかわり、19世紀のなかばまでにはヨーロッパの大都市にこの形式による大オペラ・ハウスが建ちそろうようになる。ミラノのスカラ座(1778)、ベネチアのフェニーチェ座(1792)、ロンドンのロイヤル・オペラハウス(1849)、ウィーンの国立歌劇場(1869)などがその例であり、シャルル・ガルニエ設計のパリのオペラ座(1875竣工)は、時代的にはすこし遅れながらも、その豪華さによってこれらの頂点にたつ存在となった。こうしたオペラ・ハウスにおいては、ホワイエやラウンジなど、談笑や休息のための空間に観客席に劣らぬ広大な空間が割かれて、劇場は観劇と同時に社交の場ともなった。
こうした劇場構成の一般的な傾向に対して、近代的な視点から改革を図ったのが、建築家G・ゼンパーと作曲家R・ワーグナーである。彼らはバイロイトの祝祭劇場(1876竣工)の設計において、オーケストラ席を舞台前面下部の一段低いところに落とし込んで観客の視線を遮らないようにし、一方、馬蹄形の座席構成を廃して1層の観客席を半円形に並べ、観客席が舞台に相対してどの席も音響的、視覚的に不便のないようにした。これはワーグナーの楽劇上演にふさわしい空間創造の試みであったが、また一方、19世紀初め以来の演技鑑賞を十全に行える劇場構成を求めての科学的探求の流れにもつながるものであった。しかし、視線や音の届きぐあいを考慮して、どの座席からも平等に舞台が眺められるように設計されたその後の劇場では、客席のほとんどが舞台と向き合う形をとり、プロセニアムの採用後も馬蹄形、半円形の観客席の劇場にはまだ残されていた劇場空間の一体感は、しだいに失われていった。
こうした傾向への反省から、プロセニアムを廃し、舞台と観客席を単一の空間の中に包み込む原初的な劇場形式に戻ろうとする動きが現れる。もちろんこれは演劇のあり方そのもののとらえ直しに基づくもので、すでに19世紀なかばにも試みられた例があるが、20世紀に入ってさまざまな実験が盛んに試みられるようになり、そうした形式の劇場も多数つくられている。エリザベス朝の劇場形式の復原は20世紀初頭以来しばしば試みられており、これはプロセニアムを廃して演技空間が観客席の中に張り出すオープン・ステージの思想へとつながった。演技を単一方向からのみ鑑賞する形式をやめ、演技空間を観客席が取り囲むようにして、演劇本来の祝祭的な性格を復活させようとする試みも盛んに行われており、アメリカのワシントン大学のG・ヒューズの提唱した円形劇場運動(1932以降)は、矩形の演技空間を観客席が取り囲み、これに4本の花道がつく構成を生み出した。ドイツ出身の建築家グロピウスによる全体劇場のプロジェクト(1927)をはじめとして、この種の計画には、演技空間と観客席とを適宜入れ替えて、内部構成をそのつど転換できるようにしたものも多い。日本の1970年代に生まれたテント形式による上演も、こうした演劇空間の一体化を求める運動の一つに数えることができよう。
[横山 正]
インドの劇場については、3世紀ごろの編纂(へんさん)と考えられる『ナーティヤ・シャーストラ』に、古代の聖域内につくられた劇場についての記述があり、3世紀には独立した劇場建築が建てられていたことが記されている。ここでは、舞台のすぐ背後が楽屋になり、その壁面に登退場口がとられて横引きの絵幕がかかっていたという。舞台背面は絵やレリーフで飾られていたらしい。観客席は当然、カーストによって区分されていた。
中国の劇場的な空間について具体的な記述がみられる最古の例は、後漢(ごかん)(1世紀)の文献だが、すでに5世紀までには、種々の大道具、舞台装置がつくられていたらしい。隋(ずい)代(7世紀)には戯場の名が文献にみえ、そこでの演技を棚(桟敷席)から見ることが記されている。唐代にも宮廷の室内劇場はあったが、いわゆる劇場形式がとくに発達したのは、13世紀の南宋(なんそう)から元(げん)にかけてであり、宮廷および民間の常設の劇場形式が完成した。また元代から明(みん)代にかけては、道教の廟(びょう)や観の前にも戯台(舞台)がかならず設けられている。これらの戯台は原則として吹き放ちの空間で、その背後に楽屋にあたるスペースがあって、人々はその前面広場から鑑賞した。明・清(しん)の宮廷劇場においても、戯台のある戯楼の前部は中庭に面し、庭を隔てて看戯殿がある構成であった。戯楼は3層で、神仙物の上演の際などには、これを立体的に使うこともあったようである。
日本においても神事の際用いられる舞楽のための屋外舞台は早くから発達していたが、芸能のための劇場空間の確立は鎌倉後期以降ということになろう。室町初期の1349年(正平4・貞和5)田楽(でんがく)の新座と本座が京の四条河原で行った勧進(かんじん)田楽においては、観客空間に舞台が突出し、さらにその周囲を円形に桟敷席が取り巻いている。舞台背後に二つ並んだ楽屋からは反(そ)り橋状の橋掛(はしがかり)がそれぞれ斜めに出て、中央の舞台に達している。この橋掛は機能的には楽屋と舞台を結ぶ通路だが、おそらくその長さゆえに、その途上での所作が生じ、その結果、能舞台においては、これが演技空間の一部をなすまでに至った。これは歌舞伎(かぶき)劇場の花道ともども、日本の伝統的な劇場空間の一つの特徴で、西欧近代の実験的な上演などに取り入れられている。
能舞台形式の確立は安土(あづち)桃山時代と考えられるが、これに対して江戸初期には歌舞伎の常設劇場の成立をみる。その初期のものにはまだ能舞台に近い様式がみられたが、橋掛は圧縮され、通路というよりは主舞台に添った副次的な演技空間となっていた。1664年(寛文4)にはこれまで日本の舞台空間にはなかった引幕が初めて用いられ、元禄(げんろく)期(1688~1704)までにははっきりと舞台の正面性が意識されて、舞台と観客席が向かい合う形式が明確になっている。また寛文(かんぶん)年間(1661~73)には本舞台前面の付(つけ)舞台から観客席の中を突っ切って花道が延ばされて、今日の歌舞伎劇場の姿に近くなる。この花道の使用は初めは仮設のもの(花板(はないた))で、観客がひいき役者に贈り物をするための通路であった。歌舞伎劇場の特色は大道具の開発とさまざまな仕掛けの機構の発明にあり、1753年(宝暦3)のせり上げ装置、1758年の回り舞台の創始は、大坂道頓堀(どうとんぼり)の並木正三(しょうざ)の考案によると伝える。そのほかの大掛りな仕掛け機構もほとんど、続く20、30年間に開発されている。
日本にプロセニアム型の劇場形式が本格的に導入されたのは、1911年(明治44)竣工の帝国劇場であるが、これはヨーロッパの旧来の劇場を写したものであった。これに対してヨーロッパの新しい劇場の様式を移入しようとしたのが、1924年(大正13)竣工の築地(つきじ)小劇場で、曲面のクッペル・ホリゾントなど新しい設備が目だったが、いずれも現存しない。
[横山 正]

ディオニソス劇場

エピダウロスの円形劇場

ウィーン国立歌劇場

パリ・オペラ座

シェークスピアズ・グローブ劇場

中村座
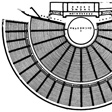
エピダウロスの円形劇場の平面図
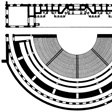
オランジュのローマ劇場の平面図
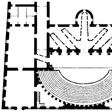
オリンピコ座の平面図
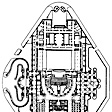
パリ・オペラ座の平面図

帝国劇場(明治時代)

帝国劇場内部(明治時代)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 演劇という語を用いるに際して,ヨーロッパ語による概念を前提としていたとすれば,そのヨーロッパ語は何であり,またどのような他の単語と対比されるのか。多くの辞典が一致して述べているように,〈演劇〉はほぼ英語theatre(シアター),フランス語théâtre(テアートル),ドイツ語Theater(テアーター)の訳語に当たる。いずれも〈見物する場所〉を意味するギリシア語theatron(テアトロン)に発して,部分で全体を表すことにより演劇の意となる。…
…シェークスピアが属していた内大臣一座Lord Chamberlain’s Men(1594発足)はその一つである。劇の上演は貴族の館や旅館の中庭でも行われたが,1576年にジェームズ・バーベッジがロンドン郊外にイギリス最初の劇場シアター座を建設し,続いてグローブ座など多くの劇場が建てられるにいたって,興行の商業化はいっそう進んだ。劇場はいずれも屋根をもたず,幕のない舞台が平土間に張り出し,数層の客席が平土間を囲むという構造をもっていた。…
…観客席が演技空間をとり囲むという構造をもった劇場。ただし,客席が舞台を完全に囲んでいなくても,近代の多くの劇場のように両者が明瞭に分離していない場合は,円形劇場に準じて考えてよい。…
…いずれも〈見物する場所〉を意味するギリシア語theatron(テアトロン)に発して,部分で全体を表すことにより演劇の意となる。しかし各国語の間で意味の広がりは異なって,〈見物席〉が〈劇場〉となるのはどの国語も同じであるが,この語が同時に〈劇場〉と〈舞台表現の総体〉と〈一作家の戯曲の総体〉を指しうるのはフランス語においてである。また,ギリシア語語源からすればテアトロンと並んで重要であり,同じく部分で全体を表すことになるギリシア語drama(ドラマ。…
…劇の進行に時間的な飛躍を示す記号としての引幕が用いられるようになり,複雑な筋の展開を可能にした。劇場が整備され,役者の数が増加し,見物の層が広がった。野郎評判記が出版されるが,当初の容色本位の野郎賛仰からしだいにその技芸をも評判するようになり,役者評判記の性格を濃くしていく。…
…ヘレニズム美術【松島 道也】
【建築】
古代ギリシア都市は上市,要塞,聖域などの機能をもつアクロポリスと,その裾にひろがる下町から成っており,下町には民会,市場,各種の催しが行われる公共広場(アゴラ)を中心に,市民の住宅が立ち並んでいた。議会,行政,司法などの公共施設はアゴラの周囲に並設されるのが普通であるが,適度な斜面を必要とする劇場や,大面積を必要とする競技場や教育・体育施設などはアゴラから離れ,ときには市外に建てられることも多かった。町全体は市城壁で囲まれていた。…
…俳優を主体にして,そのほか演劇上演に必要な人々が集まり,上演という共通目的のためにそれぞれの職能において協力しながら,組織的かつ持続的に上演活動をおこなう団体のこと。なお,〈劇場〉という言葉も,とくに〈○○劇場〉のような形で,〈劇団〉と同じ意味に用いられるが,その多くの場合は,ある演劇集団の活動が密接に特定の劇場空間と結びついていて,自然にあるいは意図的に同じ名前で呼ばれた場合である。ある意味ではそのような結びつきの強いことがむしろ当然であるから,実際,以下に述べるようにその例は数多い。…
…このような打合せを経過しながら,舞台美術家は舞台装置や舞台衣裳,小道具などをデザインしていく。舞台装置図,平面図,衣裳スケッチ,小道具製作図面,模型舞台などができ上がると,それに基づいてそれぞれの製作会社や工房で実際に仕上げられ,公演の予定に合わせて劇場に搬入される。いよいよ舞台稽古である。…
※「劇場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新