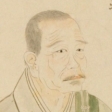日本大百科全書(ニッポニカ) 「一休宗純」の意味・わかりやすい解説
一休宗純
いっきゅうそうじゅん
(1394―1481)
室町中期の臨済(りんざい)宗の僧。宗純は諱(いみな)で、宗順とも書く。狂雲子(きょううんし)、瞎驢(かつろ)、夢閨(むけい)などと号した。後小松(ごこまつ)天皇の落胤(らくいん)ともいわれ、6歳で京都安国寺の侍童となり、周建(しゅうけん)とよばれた。17歳で西金寺(さいこんじ)の謙翁(?―1415)に参学、大徳寺の高僧で、近江(おうみ)(滋賀県)堅田(かたた)に隠栖(いんせい)する華叟宗曇(かそうそうどん)(1352―1428)の弟子となって修行、一休の号を授かった。師の没後は定住することなく各地を雲遊したが、1467年(応仁1)応仁(おうにん)の乱が起こると戦火を避けて山城薪(やましろたきぎ)(京都府京田辺(きょうたなべ)市)の酬恩庵(しゅうおんあん)に寓(ぐう)した。応仁の乱が鎮まった1474年(文明6)勅命によって大徳寺の第47代住持となり、荒廃した伽藍(がらん)の再興に尽くした。文明(ぶんめい)13年11月21日、酬恩庵で示寂。一休は、当時すでに幕府の御用哲学と化していた五山派の禅の外にあって、ひとり日本禅の正統を自任し、独自の漢詩文を駆使して禅の本質を芸術性豊かに歌い上げた。また大徳寺開山、大燈(だいとう)国師(宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう))の法流をさかのぼることによって、中国の南宋(そう)禅林に孤高の宗風を振るった虚堂智愚(きどうちぐ)に私淑し、自らその再来と称した。彼は自らを「狂雲子」と号し、形式や規律を否定して自由奔放な言動や奇行をなしたが、その姿は当時の形式化、世俗化した臨済の宗風に対する反抗、痛烈な皮肉であったといえよう。晩年には森侍者(しんじしゃ)(生没年不詳)という盲目の美女を愛し、その愛情を赤裸々に詩文に詠んでいる。しかし、その実人生と文学的虚構の間にはいまなお多くの謎(なぞ)を残している。その徹底した俗心否定と風刺の精神は後世に共感を得、『一休咄(ばなし)』『一休頓智談(とんちだん)』などが上梓(じょうし)され、子供にも親しまれるようになった。詩偈(しげ)集『狂雲集』は著名。ほかに『一休法語』や『仏鬼軍』も彼の作とされる。大徳寺真珠庵と酬恩庵に墓があり、ともに自刻等身の木像が安置されている。
[柳田聖山 2017年5月19日]
『秋月龍珉著『禅門の異流』(『日本の仏教12』所収・1967・筑摩書房)』▽『市川白弦著『一休』(1970・日本放送出版協会)』
山川 日本史小辞典 改訂新版 「一休宗純」の解説
一休宗純
いっきゅうそうじゅん
1394~1481.11.21
狂雲子とも。宗純は諱(いみな)。室町中期の大徳寺派の禅僧。後小松天皇の落胤という。幼くして山城安国寺の象外集鑑の門に入り,詩法を慕哲竜樊(ぼてつりょうはん)に,外典を清叟師仁に,禅を謙翁宗為(けんのうそうい)に学んだ。1414年(応永21)謙翁が没し,翌年華叟宗曇(かそうそうどん)のもとに参じた。18年華叟より一休の号を授けられた。求道の精神は熾烈で,法兄養叟宗頤(ようそうそうい)の偽善的な禅風を批判した。40年(永享12)大徳寺如意庵の住持となるが,即日退庵するなど反俗求道の姿勢を貫いた。56年(康正2)山城国薪の妙勝寺を復興して酬恩庵をたて,以後ここに住した。74年(文明6)大徳寺住持となり,応仁の乱で焼失した同寺の復興に尽くした。連歌師の宗長・智蘊(ちうん)・宗鑑,能の金春禅竹(こんぱるぜんちく),茶道の村田珠光(じゅこう)らとの交渉もあった。著書「狂雲集」「自戒集」。
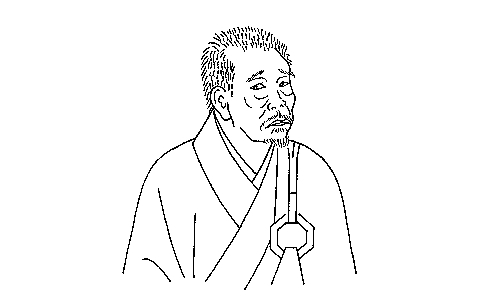
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「一休宗純」の解説
一休宗純 いっきゅう-そうじゅん
明徳5年1月1日生まれ。臨済(りんざい)宗。後小松天皇の皇子。6歳で山城(京都府)安国寺にはいり,27歳のとき華叟宗曇(かそう-そうどん)から印可をうける。各地の庵を転々とし,当時の世俗化,形式化した禅に反抗して,奇行,風狂の中に生きる。文明6年勅命によって大徳寺住持となり,入寺しなかったが,大徳寺の復興につくした。詩,書画にすぐれ,後世つくられたとんち話で知られる。文明13年11月21日死去。88歳。号は狂雲子,夢閨(むけい),瞎驢(かつろ)など。著作に「自戒集」「狂雲集」「一休骸骨」など。
【格言など】大機はすべからく酔吟の中にあるべし(「狂雲集」)
旺文社日本史事典 三訂版 「一休宗純」の解説
一休宗純
いっきゅうそうじゅん
室町中期の臨済宗大徳寺派の僧
狂雲子と号す。後小松天皇の皇子といわれる。大徳寺住持48世。反骨精神にあふれ,禅宗の腐敗を嘆き,大衆化につとめた。詩集に『狂雲集』『続狂雲集』がある。彼に参禅した文化人に村田珠光・金春禅竹らがいる。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「一休宗純」の解説
一休宗純 (いっきゅうそうじゅん)
室町時代の臨済宗の僧
1481年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の一休宗純の言及
※「一休宗純」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
脂質異常症治療薬
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新