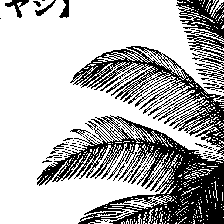翻訳|palm
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ヤシ」の意味・わかりやすい解説
ヤシ
やし / 椰子
palm
[学] Arecaceae
Palmae
ヤシ科植物の総称。ココヤシ亜科、アレカヤシ亜科、トウ亜科など11亜科29族(連)に分けられる。APG分類でもヤシ科とされ、6亜科190属に分けられる。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
分類・分布
ココヤシ亜科は約660種、アレカ亜科はヤシ全体の半数約1400種、トウ亜科は約700種で、この3グループはヤシの大部分を含める大群族である。原産は南はニュージーランド、北はヨーロッパにかけて南緯・北緯ともほぼ40度、分布は南緯43度、北緯47度に拡大し、全世界の熱帯、亜熱帯、温帯に自生し、緯度は海流、海抜、気象などの条件で一定しない。生育気温は零下10℃程度が最低である。ヤシの種類は中南米にもっとも多く、ブラジルが最大で、全品種3300余種のほぼ半数は南北アメリカ大陸に発生している。自生帯は水中、海浜、砂漠、高山などさまざまである。土質は弱酸性が多く、サンゴ礁や乾燥帯にはアルカリ性の産地もある。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
形態
ヤシは単子葉植物中もっとも発達した高等植物で、円柱状の幹茎の頂部に葉柄のある繊維質の葉脈が流線形の葉冠を形成しているスマートな容姿がヤシ独特の魅力的美観といえよう。果樹とか材料として利用される2、3の品種を除く3000余種のほとんどは装飾とか観光とか環境の美化に用いられ、葉冠の姿態が評価される。この意味において、ヤシは園芸的には観葉植物とみるべきである。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
幹
幹は普通上方に伸びるが、枝を分岐するものは少ない。単立または分株叢生(そうせい)する。幹が地上に出ない種類もある。高さ30センチメートルから100メートル、径は2ミリメートルから1.5メートルと大小の差が著しい。葉は頂生管束である葉脈が網目にならず、葉片方向に平行しているのが原則であり、かならず葉柄があるのがユリ科などとは異なる点である。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
葉
葉形は大別すると、掌状葉と羽状葉である。前者は葉柄が着葉部で中絶し、後者は上端部から中軸になって葉体中に伸びたものである。両者は基本構造においては同一で、単に小葉片が葉柄の着葉部に圧縮されたように集積したのが掌状葉で、伸長した中軸の両側に小葉片が羽状に多散配列したのが羽状葉である。小葉の形状には披針(ひしん)形と切頭(せっとう)形(歯形)があるが、後者の種子の周面は複数の溝のあるものが多い。小葉片にはV字形(内向鑷合(じょうごう)状、たとえばフェニックス、クジャクヤシ、シュロ)とΛ字形(外向鑷合状、たとえばココヤシ、アレカヤシ、テングヤシ)があり、葉芽時においてすでにV、Λいずれかに重合している。幹、葉、葉柄などに鋭刺のあるのは動物に対する保護器官である。葉の色は緑、灰、白色などがあり、若葉時には枯色でのちに緑色になるものがあるのは保護色の意味もある。ヤシの葉は幹を中心軸として幹の円周に派出伸長するが、単位の葉が幹の全周にわたり120~180度の範囲に次々とずれて旋回状をなして発生する。その角度は個体の品種固有の度数である。旋回方向には左右があり、その方向は葉の様態で観測できる。幹を軸とする回転の逆方向になびき、やや傾いて湾曲する。その旋回方向が右回り、左回りの方向を示している。120度と180度は円周が3分の1と2分の1に割り切れる特殊角なので、120度のものは幹軸の円周を3等分して葉柄が3列に垂直に条列をなして着生し、180度のものは葉柄が2列に垂直の条列状に幹軸の両側に平面的なひだ状をなして着生する。種子の幼芽の細胞分裂時に、左右いずれかに定まるものと考えられる。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
花
花は品種によって両性花、雄花、雌花、中性花など、あらゆる性別があるが、いずれも包葉内で成長した肉穂花の花柄が開いて穂状をなすこと、花弁、萼(がく)、雄しべ、子房、柱頭の数が3の倍数であるのが特徴である。雄しべは3~150本の範囲で種類が多く、6本以上のものには3で割り切れない花も混じっている。アンデス山系のヤシには雄しべも花弁も不定数の例外(アメリカゾウゲヤシ)がある。雄花に不稔(ふねん)性の雌しべのあるもの、雌花に無精(無葯(やく))の雄しべのあるものが多い。これは両性花の痕跡(こんせき)器官で、単性花が両性花に誤認されやすい。単性花で雌花と雄花が同一花軸にあるものでは、中央に雌花、その両側に1個ずつの雄花がついて3個1組の集合花になっている例が多く、花軸の先端に向かっては雄花だけが数珠(じゅず)状に列をなしてつき、包葉が割れて内蔵の花序が枝状に開くとまもなく雄花が全開し早期に落花するものと、長期間つぼみのまま閉じているものもある。いずれも雄花が散ってから雌花が開くのが普通であるが、すでに雌花の柱頭では受精が終わっている。つぼみのまま閉じたものの場合は雄花の開花までに雌花の成長が進行する。雄花は総じて小さく1~12ミリメートル程度。ヤシの性別は花だけでなく個体としての株自体にも性別があり、両性花も雌雄同株に限らず、雌雄異株に両性花のある例(シュロ)は多い。単性花でも雌花に葯のない無精の雄しべがついたものがあり、雄花でも不稔性の雌しべがあって一見両性花に似た花があるが、ともに痕跡器官になっている。同属異種の交配性には有無の2種があり、たとえばフェニックスは交配しやすく、ワシントンヤシ、ホエア、トックリヤシなどはほとんど交配しない。
花弁の色は白、黄白、桃、黄、黄緑、緑、青、紫、桃紫、褐色などじみである。花序には花柄が小枝に分岐するものと、枝のない鞭(むち)状のものとがあり、1花序に1本だけのものがある。雌雄同株でも雌雄別々の花序を発生する例(アフリカアブラヤシ、ニッパヤシ)もある。同一花序でも花軸によって両性化、雄花、雌花を別々に着生するものもある。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
果実
果実は房状に着生する例が普通で、開花と結実が間断なく連続するものと、年1回のもの、一生に1回のものがある。果実の構造は被子植物として種皮と果皮からなり、種皮は仁(じん)と種皮からなる。種皮は外種皮と内種皮からなり、木質か厚膜組織のものが多く、果皮は外果皮、中果皮、内果皮(核)からなり、内果皮は木角質の厚いものになり、種皮と区別のないものもある。普通は内果皮を種子と通称する。仁は胚(はい)と胚乳からなり、胚は子葉、幼芽、幼根からなり、胚が内種皮に内接し、種皮と内果皮に珠孔がある。中果皮には糖分を含むものがあり、種子にはタンパク質、糖分、油脂が含まれている。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
利用
熱帯民族の生活にはヤシは密接な関係がある。中近東では6000年前からナツメヤシの糖分の多い果肉(中果皮)が食料として利用され、現代でも菓子、果糖、アルコールなどの用途に供される。ココヤシやアフリカアブラヤシなどの胚乳から多量の良質な油脂(コプラ)が得られ、工業用、せっけん、マーガリンなどに利用される。また数種のサトウヤシ類からは、花柄に切り傷をつけ、切り口から出る樹液を煮つめ、乾燥して糖蜜(とうみつ)、砂糖を得る。量の多少はあるが、ヤシ全般に砂糖を含み、採集法さえ案出できれば、量的にはサトウキビの及ばないほどである。
[佐竹利彦 2019年5月21日]
工業原料としてはブラジルロウヤシやグレナダロウヤシなどの葉からロウ、サゴヤシの幹からでんぷん、ラフィアヤシの羽片やオウギヤシの葉柄から繊維、トウからは籐(とう)、キリンケツ(麒麟血)の樹脂から赤色のニスや染料がとれる。キャベツヤシ、アメリカパルミット、オウギヤシの芯葉(しんよう)はブラジルなどでは生鮮野菜であり、缶詰にもされる。サラッカヤシ、トウ、オウギヤシなどの実は果物として生食される。ボタンヤシ、アメリカゾウゲヤシ、ブラジルゾウゲヤシの固い胚乳(はいにゅう)からはボタンが製造された。クジャクヤシの種子をイスラム教徒は数珠(じゅず)に使う。ニッパヤシ、ココヤシ、オウギヤシをはじめとする葉は屋根材、壁材、団扇(うちわ)、帽子、籠(かご)、紙の代用、工芸品など利用は広い。
熱帯では観賞用に幹の美しいダイオウヤシ、アレカヤシ、トックリヤシや葉柄の赤いショウジョウヤシ、ベニウチワヤシをはじめ多数のヤシが使われる。日本でも暖地ではカナリーヤシやワシントンヤシが並木や庭園樹にされる。シュロ、シュロチク、カンノンチクはさらに耐寒性がある。
[湯浅浩史 2019年5月21日]
民俗
熱帯地域の人々と密接な関係にあるヤシは、コプラからもわかるように栄養価が非常に高く、飢饉(ききん)の際にはヤシだけでも飢えをしのげるといわれる。タミール(スリランカ)の詩には、810ものロンターヤシの使用法があげられているが、その葉だけでも屋根を葺(ふ)いたり、編んでさまざまな容器をつくったり、タバコの葉を巻くなど、いろいろに利用される。「ベテル・チューイング」といって、喫煙とよく似た習慣が熱帯地域に広く分布しているが、これはビンロウジの実とキンマの葉を石灰といっしょにかむもので、口臭を除き、一種の覚醒(かくせい)効果が得られるという。ココヤシ、ロンターヤシ、アレカヤシなどからは、やし酒もつくられる。
サンスクリット文字は最初ロンターヤシの葉に筆記されたといわれ、インドネシアのバリ島には、ロンターヤシの葉に筆記された膨大な儀礼のテキストが残されている。まっすぐに伸びたロンターヤシの幹は、『ラーマーヤナ』(古代インドのサンスクリット大叙事詩)のなかでは力と威風の象徴に例えられ、また東インドネシアのフロレス島中部では、ココヤシの実が豊饒(ほうじょう)と安全の象徴とされている。
[中川 敏 2019年5月21日]
改訂新版 世界大百科事典 「ヤシ」の意味・わかりやすい解説
ヤシ (椰子)
palm
木本性の単子葉植物。日本では従来,ココヤシを単にヤシと呼んでいたが,近年ではヤシ科の植物を総称してヤシという。
ヤシ科Palmae(palm family)
木本性の単子葉植物として,イネ科のタケ類とともに特異的な存在であるヤシ科の植物は,ほとんどの場合,幹は分枝せず二次肥大生長もしないうえに,大きな葉を幹の頂端部に群がりつけ,熱帯の景観を特徴づける。いわゆるヤシ形の生活形になる。約220属2500種を有し,それらの大部分は熱帯や亜熱帯に分布し,シュロのようなごく少数の種が暖温帯に生育する。また,この多数の属や種の多くは限定された狭い地域にのみ分布するという,固有性の強い植物群でもある。
幹(茎)は単一で直立するものが多いが,シュロチクのように株立ちになるもの,トウのようにつる性のもの,あるいはニッパヤシのように地表を横走するものもある。葉は葉鞘(ようしよう),葉柄,葉身の三つの部分に分化しており,しばしば大型となり,ニッパヤシのように10mをこえることもある。葉鞘基部はしっかりと茎を抱き,新葉と芽を包む。この葉鞘部の維管束が残ったのが,シュロのシュロ毛である。葉身は扇状の単葉から扇状あるいは羽状に切れ込んだ複葉まで,さまざまである。各小葉は,発生のときに単一の折りたたまれた葉身の折目の部分が切り離されるというヤシ科に特有の形態形成過程を経て,つくられる。またこの折りたたまれた下側の折目で切れるか,上側の折目で切れるかで,ヤシ科は大きく2群に分けられる。花は単性あるいは両性で小さく,黄色から黄緑色で目だたないが,多数が花軸の上に密集して肉穂花序を作り,それが大きな苞(仏焰苞(ぶつえんほう))に包まれ,基本的には虫媒花である。開花期には多数のハナバチ類や甲虫などが集まる。葉腋(ようえき)あるいは茎頂から出る肉穂花序は,単純な棒状からシュロのように多数分枝するもの,あるいは短縮して球形(ニッパヤシ)になるものとさまざまである。花被は内・外それぞれ3枚の花被片からなり,両者にそれほど違いはない。おしべは通常6本,めしべの子房は1室または3室で,各室に1個の胚珠がある。果実は液果,核果あるいは堅果などで,大きさはさまざまであるが,比較的大型のものが多い。種子はよく発達した胚乳を有するが,その胚乳は油脂あるいはヘミセルロースであることが多い。前者の場合は油料植物として重要になるし,後者の場合は硬質で,ゾウゲヤシのように細工物に利用されることがある。
ヤシ科は肉穂花序を有する点からサトイモ科に近縁と考えられたり,木質の幹や花序の形からタコノキ科に近いとされたりするが,すでに中生代から化石の出る古い植物群で,単子葉植物のなかでは独自に進化した系統群であろう。
ヤシはそのエキゾチックな樹形からフェニックス,シュロ,カンノンチク,シュロチク,ビロウなど暖地で観賞用に栽植されるものも多いが,熱帯ではその他に多数のヤシ類が街路,庭園,公園の植栽に利用されている。木質化した幹は硬質で割裂しやすく,耐腐性があるものは建築材をはじめ細工物に,またトウのように柔軟なつる性のものではかごやマットあるいは結束料に多用される。大きな葉も,ニッパハウス(ニッパヤシの葉を編んで屋根や壁にした家)で代表されるように,屋根ふきや壁に利用される。シュロの葉鞘やココヤシの果実の殻のように,繊維を取り出して利用することも多い。
食用植物としてのヤシの利用も多面的である。葉鞘につつまれた新芽は柔らかく,東南アジア・マレーシア地域には野菜として利用される種が多数ある。若い花序を切ると糖液を分泌する種(サトウヤシが代表的)では,糖みつを採取したり,アルコール飲料を作るのに用いられる。果実が食用あるいは油脂源とされるものは多いが,なかでもココヤシ,アブラヤシ,ナツメヤシの3種が有名で,熱帯の重要な栽培作物となっている。サゴヤシは幹からデンプンが採取され,サラッカは果実が果物になることで有名である。またつや出しワックスで有名なカルナウバ蠟(ろう)carnauba waxは南アメリカ産のカルナウバヤシCopernicia ceriferaの葉から採取される。アレカヤシ(ビンロウ)のように果実にアルカロイドを含有し,興奮性の嗜好料に使われるものもある。ヤシ類は工業社会の影響を受ける前の熱帯域では,それぞれの地方に特産するさまざまな種類が,その地域の人間の生活に深く結びついて利用されていた。現在でもアブラヤシやココヤシのように,工業原料としての油脂源植物として大規模なプランテーション栽培が行われている重要な作物を含む植物群である。
執筆者:堀田 満
ヤシ
Iaşi
ルーマニア東部の主要都市。旧モルドバ公国の首都。現在は同名県の県都で,人口30万7783(2005)。プルート川の支流バフルイBahlui川のほとりにあり,現在モルドバ共和国との国境をなしているプルート川までは8kmの位置にある。英語,ドイツ語風にヤッシーと記されることもある。鉄道分岐点としても重要で,一つはキエフを経由してモスクワへ,他はブコビナを経てリボフへ至る。
ヤシの地名が初めて文献に現れるのはロシアの史料で,1387-92年にここに市が立っていたという。国内史料ではアレクサンドル善公の治世の1408年である。当時モルドバ公国の中心は北部にあり,スチャバが首都であった。公国を隆盛に導いたシュテファン大公の治世(1457-1504)には公の館と付属教会も建てられたが,その後1565年アレクサンドル・ラプシュネヤヌ公の治世に公国の首都となった。絶えず外敵の脅威にさらされ,市は1538年オスマン帝国のスルタン,スレイマン1世の軍勢によって灰燼に帰したのをはじめ,1577年,1616年,50年,86年,1821年に,オスマン軍,クリム・ハーン国軍,ポーランド軍,コサック軍によって破壊された。市が整備され始めたのは1827年の大火以後である。また18世紀後半からいわゆる東方問題の舞台となり,1792年には,ここで露土戦争の講和条約が結ばれたが,その後も1828年,53年にはロシア軍に,54年にはオーストリア軍に占領された。このような政治的悪条件にもかかわらず,中世以降モルドバ文化は独自の性格を強めていくが,それは16世紀後半にペトル跛公の建立したガラタ修道院やとくに1639年にバシレ・ルプ公が建立し教会建築におけるモルドバ様式の傑作といわれているトレイ・イエラルヒ教会によく表されている。バシレ・ルプ公は1640年ころスラブ語とギリシア語による学校を創設し,モルドバで最初の印刷所も設立した。18世紀から19世紀初めのギリシア人ファナリオットがモルドバを支配する時代になると,ギリシア文化が優勢になり,ギリシア・アカデミーが開かれるが,このような文化的伝統の中からG.ウレケ,コスティンのような年代記作者やD.カンテミールのような文人が輩出した。1821年ヤシはエテリア蜂起の根拠地となり,そのためにイエニチェリ軍による報復的破壊を被ったが,それ以後始まるモルドバの近代化の運動の指導的人物もこの地で活躍した。教育者アサキ,1840年国民劇場の創立に貢献したV.アレクサンドリ,1848年の革命的運動と59年のワラキアとの統一の指導的人物コガルニチャーヌと,クザらである。62年ブカレストが統一ドナウ公国の首都となってからヤシの政治的重要性は減退したが,なお19世紀末まではブカレストをしのぐ文化運動の中心地であった。1860年ブカレストに先立ってヤシ大学が創立され,また文学協会〈ジュニメヤ〉の活動には評論家T.マヨレスク,国民詩人エミネスク,作家クリヤンガらが加わっていた。いまでも市内のコポウ公園はその菩提樹の下でエミネスクが詩作にふけったところとして市民に親しまれている。
19世紀後半のヤシには43のギリシア正教会の教会に対し,58のユダヤ教教会があったといわれるほど多数のユダヤ人が居住していた。彼らの多くはウクライナから18世紀以後に移住した者であったが,彼らに文化的刺激を与えたのは1876年に当地でヨーロッパ最初の常設的なユダヤ劇場(イディッシュ語)の旗上げをしたゴールドファデンAvram Goldfaden(1840-1907)であった。彼とその一座はモスクワ,ワルシャワ,オデッサなどへも巡業して成功を収めた。20世紀初め以降,ユダヤ人の間で経済的困難からアメリカをはじめとする移住が盛んになり,彼らもまたそこで活躍することになる。第1次大戦中,一時,首都がヤシに移されたが,ヤシが近代的な都市の外観を備え,薬品,化学,機械,繊維をはじめとする工業化が促進されるようになったのは第2次大戦以後である。
執筆者:萩原 直
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヤシ」の意味・わかりやすい解説
ヤシ
palm
ヤシ
Iaşi
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「ヤシ」の意味・わかりやすい解説
ヤシ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内のヤシの言及
【手】より
…手根と中手とは骨格でははっきり区別されるが,外形的には続いていて境界はない。両者合わせて軽くへこんだ皿状をなし,その凹面(前面)を〈手掌(しゆしよう)palm〉〈手のひら〉または〈たなごころ〉といい,凸面を〈手背back of the hand〉または〈手の甲〉という。指は5本あって,これを橈骨の側から尺骨の側へ順次に〈第1指,母指,親指〉〈第2指,示指,人差指〉〈第3指,中指(ちゆうし∥なかゆび)〉〈第4指,薬指(やくし∥くすりゆび)〉〈第5指,小指(しようし∥こゆび)〉と呼ぶ。…
【度量衡】より
…ただしこの単位の実体もあいまいであって,尺についていえばおよそ20~32cmにわたっていた(一般に時代が下るにつれ実長はのびた)。 (イ)の系統に属するものは,以上のほかにもいろいろあり,4本の指を並べた幅(日本のつか,イギリスのパームpalmなど),親指の幅(中国の寸,ドイツのダウメンDaumen,オランダのドイムduimなど),人差指または中指の幅(イギリスのディジットdigit,フィンガーfingerなど),げんこつの大きさ(ドイツのファウストFaust)その他,実例はきわめて多い。ただしそれらすべてが独立に基準として採用されたわけではなく,〈パームはディジットの4倍〉のように,いわゆる倍量または分量として間接的に定められた場合もあった。…
※「ヤシ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
脂質異常症治療薬
血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新