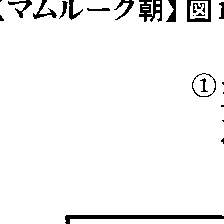精選版 日本国語大辞典 「マムルーク朝」の意味・読み・例文・類語
マムルーク‐ちょう ‥テウ【マムルーク朝】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「マムルーク朝」の意味・わかりやすい解説
マムルーク朝 (マムルークちょう)
Mamlūk
エジプト,シリア,ヒジャーズを支配したトルコ系マムルークのスンナ派王朝。1250-1517年。首都はカイロ。バフリー・マムルークBaḥrī Mamlūk朝(1250-1390)とブルジー・マムルークBurjī Mamlūk朝(1382-1517)の前後2期に分かれる。
バフリー・マムルークは軍団の兵舎がナイル川(バフル)のローダ島にあり,ブルジー・マムルークはカイロの城塞(ブルジュ)に兵舎があったことに由来する。アイユーブ朝の奴隷軍団であったバフリー・マムルーク軍は,1250年クーデタを起こして新王朝を樹立し,宮廷女奴隷出身のシャジャル・アッドゥッルを初代スルタンに推戴した。第2代スルタンのアイバクはシリアに残存するアイユーブ朝勢力をたたき,上エジプトのアラブの反乱を鎮圧したが,王朝の基礎を固めたのは第5代スルタンのバイバルス1世であった。彼はアッバース朝カリフの擁立やバリード(駅逓)網の整備によって国内体制の強化に努め,外に対してはシリアに残存する十字軍勢力と戦う一方,キプチャク・ハーン国と結んでイル・ハーン国の西進を阻止,またヌビアにも遠征して西アジアにマムルーク朝の覇権を確立した。その成果はカラーウーン家の歴代スルタンに受け継がれ,14世紀初頭のナーシル時代に王朝は最盛期を迎えた。安定した政権の下に農業生産は発展し,商品作物としてのサトウキビ栽培が普及するとともに,都市の織物業も目覚ましい繁栄ぶりを示し,これを基礎にカーリミー商人や奴隷商人がインド洋と地中海貿易に活躍した。しかし1347-48年のペストの大流行によって都市と農村の人口は激減し,ナーシル没後は幼少の息子たちが相次いで即位したために,実権を握るアミールたちの抗争によって政局は混乱を極めた。
この機に乗じてチェルケス人マムルークのバルクークが政権を握り,ブルジー・マムルーク朝を開いたが,この時代のスルタンは家系によらず,有力アミールの選挙によって選ばれるのが慣例であったから,軍閥相互の勢力争いは一段と激しくなった。またペストの流行も相次いだために経済状態はさらに悪化し,エジプト市場から金貨と銀貨が消失して,やがて銅貨の時代が始まった。バルスバイは財政補塡のために砂糖の専売政策を実施したが根本的な解決策とはならず,1498年のバスコ・ダ・ガマによるインド航路発見によって,中継貿易に基礎を置くエジプト経済は致命的な打撃を受けた。すでに16世紀初頭からオスマン帝国との間に確執を生じていたマムルーク朝は,1516年にマルジュ・ダービクMarj Dābiqの戦においてセリム1世に敗れてシリアを失い,翌年カイロを占領されて王朝は滅びた。
スルタンを頂点とするマムルーク体制を支えていたのは奴隷出身のマムルーク軍人であり,バフリー・マムルーク朝時代にはトルコ人,モンゴル人,クルドが中心であったのに対して,ブルジー・マムルーク朝時代にはカフカス出身のチェルケス人が主力を占めるに至った。彼らは奴隷商人によって購入され,カイロの軍事学校を卒業すると,やがて功績に応じて十人長,四十人長,百人長へと昇進し,非マムルーク騎士団の司令官や地方総督などの要職に抜擢された。その生活の基盤はイクター保有にあり,軍人たちはイクター授与の見返りとしてスルタンに対する軍事奉仕を義務づけられた。大イクター保有者であるアミールは農村からの富を都市に集中し,スルタンとともにモスクやマドラサの建造を競い合って,マムルーク様式と呼ばれる独自の建築様式を生み出した。このような軍人による学問の保護とバイバルス1世以降のスンナ派四法学派の公認政策とによって,ウラマーの社会的役割はさらに増大し,アズハルを中心とする学問研究は最高潮に達した。新しい学問分野の開拓はなされなかったものの,ウマリーやカルカシャンディーらの百科事典家によってイスラム諸学の集大成が行われ,またイスラム世界の危機の時代を反映してマクリージーやイブン・イヤースなど第一級の歴史家が輩出した。
執筆者:佐藤 次高
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「マムルーク朝」の意味・わかりやすい解説
マムルーク朝
まむるーくちょう
Mamlūk
エジプト、シリア、ヒジャーズを支配したトルコ系マムルークのスンニー派イスラム王朝(1250~1517)。首都はカイロ。バフリー・マムルーク朝(1250~1390)とブルジー・マムルーク朝(1382~1517)の前後2期に分けられる。1250年アイユーブ朝のトルコ系マムルークが反乱を起こし、宮廷女奴隷出身のシャジャル・アッドゥッルが実権を握り、夫のアイバクが初代スルタンとなった。第5代のバイバルス1世はシリアで、モンゴル軍、十字軍、イスマーイール派に対して活発な遠征を行うと同時に、駅逓(えきてい)制をはじめとする内政を整備し、王朝の基礎を築いた。また、モンゴル軍によりバグダードを追われたアッバース朝カリフを擁立し、スンニー派四法学派を公認した。王朝の最盛期は14世紀初頭のナーシルの時代で、安定した農業生産を背景に、インド洋と地中海を結ぶ中継貿易によって繁栄を極めた。
スルタン位は世襲制であったが、ナーシル以後は後継者争いが続き、政権は不安定であった。1382年には、カフカス出身のチェルケス人マムルークのバルクークが即位し、ブルジー・マムルーク朝(スルタンの大多数がチェルケス人であることからチェルケス〈シルカシア〉時代ともよばれる)を開いた。この時代は、スルタン位をめぐって軍閥相互の勢力争いが激化した。また、14世紀なかば過ぎから黒死病(ペスト)が蔓延(まんえん)して人口が減少し、同時に農業生産の低下、飢饉(ききん)、遊牧アラブの反乱などが加わり、経済状態が悪化した。15世紀初頭にはティームールによりシリアが一時占領された。15世紀前半のバルスバイはキプロス占領など勢力を伸長したが、1498年のバスコ・ダ・ガマのインド航路開拓によって中継貿易に大きな打撃を受けた。1516年アレッポ北方のマルジュ・ダービクの戦いで、セリム1世率いるオスマン・トルコ軍に敗れ、翌年にはカイロを占領され滅亡した。
王朝治下のカイロはバグダードにかわりイスラム世界の中心となって繁栄したが、それは当時最終的にまとめられた『アラビアン・ナイト』からもうかがわれる。優れた著作家が輩出したが、マクリージー、イブン・イヤースなどの歴史家、ヌワイリー、ウマリー、カルカシャンディーなど百科事典家のほか、近・現代のイスラム改革運動にも影響を与えたイブン・タイミーヤが現れた。カーイト・バーイ廟墓(びょうぼ)をはじめ壮麗な建造物もこの王朝の特色で、各地に残存している。
[菊池忠純]
『嶋田襄平編『イスラム帝国の遺産』(1970・平凡社)』▽『大原与一郎著『エジプト、マムルーク王朝』(1976・近藤出版社)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マムルーク朝」の意味・わかりやすい解説
マムルーク朝
マムルークちょう
Mamlūk
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「マムルーク朝」の解説
マムルーク朝
マムルークちょう
Mamlūk
アイユーブ朝のマムルーク軍団出身者がエジプトに建てたイスラーム王朝
アイユーブ朝が十字軍との抗争で衰退する中,同朝のマムルーク軍団によって宮廷女奴隷出身のシャジャル=アッドゥッルが女性スルタンに推戴され,夫アイバクとともにマムルーク朝を建国。しかし,その後もスルタン位をめぐる争いが続き,1260年パレスチナ地方のアイン−ジャールートでフラグ率いるモンゴル軍を破り,第5代スルタンとなったバイバルスが実質的な建国者である。彼は滅亡したアッバース朝カリフの一族をカイロに保護し,メッカ・メディナ両聖都の守護者であると同時に,「信徒の長」カリフの擁護者であることを内外に宣言した。内政面では,エジプト・シリアを結ぶ駅伝制(バリード)を整え,中央集権体制づくりを推進した。外交面では,キプチャク−ハン国やビザンツ帝国と結びイル−ハン国に対抗するいっぽう,十字軍から諸都市を奪回し,のちに最後の拠点アッコンを陥落させた。王朝の前期には,紅海経由の香辛料貿易でムスリム商人団のカーリミー商人が活躍し,首都カイロはイスラーム世界の経済・文化の中心として繁栄した。14世紀後半からの後期になると,度重なるペストの流行,マムルーク層による過酷なイクター経営,アミールたちによるスルタン位をめぐる権力争い,統治者の無関心による水利機構の荒廃,王朝の独占政策によるカーリミー商人の没落など,内部からの腐敗によって衰退し始めた。さらにポルトガル人によるインド航路の開拓は,東西貿易に占めるエジプトの地位喪失を決定付けた。1509年インド西北岸のディウ沖海戦でポルトガル艦隊に敗北し,アラビア海の制海権を失い,17年セリム1世のオスマン帝国によってエジプトが征服されて滅亡した。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
百科事典マイペディア 「マムルーク朝」の意味・わかりやすい解説
マムルーク朝【マムルークちょう】
→関連項目イブン・ハルドゥーン|エジプト(地域)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「マムルーク朝」の解説
マムルーク朝(マムルークちょう)
Mamlūk
1250~1517
アイユーブ朝のトルコ人やチェルケス人の奴隷軍人(マムルーク)が政権を握った王朝。エジプトに興り,シリアにも進出。都はカイロ。1382年を境に前期(バフリー・マムルーク朝)と後期(ブルジー・マムルーク朝)とに分かれる。ことに前期に英主が輩出し,十字軍を破り,モンゴル軍を阻止した。戦乱は多かったが,東西通商で市況は繁栄し,建築など見るべきものを多く残した。オスマン帝国に征服された。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のマムルーク朝の言及
【イスラム美術】より
…なおインドのイスラム建築については〈インド美術〉の項目を参照されたい。 アラブ世界のマムルーク朝(1250‐1517)の建築は,単純素朴ではあるが大規模で安定感のある様式や,モスク,墓廟,マドラサなどの複合的構成,しっくい,モザイク,特に色大理石による装飾(アブラクablaq),ムカルナスを多用した装飾などを特徴とする。代表的遺構としては,スルタン,カラーウーンの墓廟とマドラサをはじめとする建築群(1285),スルタン,ハサンのモスクとマドラサ(1359)が挙げられる。…
【インド洋】より
…彼らの運送したインド綿布(13世紀中ごろと推定される糸車の導入で生産が増加した)は,東アフリカで黒人奴隷や象牙の購入に用いられるなど,インド洋全域への最も重要な商品であったが,特に東南アジア産の丁子(クローブ),ニクズク(ナツメグ)などの香料入手に不可欠で,彼らは新興のマラッカ王国で大きな影響力をもった。 15世紀初めに経済危機に悩むエジプトのマムルーク朝が香料の国家専売制を導入したことが,結果的に15世紀末のポルトガル人のアフリカ南端迂回ルートによるインド洋への進出を招いた。船上での火器の使用技術に優れたポルトガルの香料貿易独占政策にもかかわらず,16世紀後半には紅海経由のコショウ貿易が復活した。…
【シリア】より
…しかしこの繁栄も政治的不安定のために長続きせず,エジプトおよびその首都カイロに主導権を取られてしまった。 13世紀の中ごろにアイユーブ朝に代わってマムルーク朝が成立したが,マムルーク朝(1250‐1517)時代のシリアは,モンゴルの侵入,疫病の流行,マムルーク朝諸侯間の抗争,15世紀初頭のティムールの侵入,地中海貿易での地位の低下,そして経済力の全体的衰退などにより,徐々にその重要性を失っていき,停滞の時期に入っていった。【湯川 武】
【オスマン帝国時代】
オスマン帝国(1299‐1922)は,マムルーク朝から1516年にシリアを奪い,17年には同朝を倒してエジプト,ヒジャーズの支配権を得たが,イスタンブールの中央政府にとって,シリアの重要性には時代的・地域的変化がみられる。…
※「マムルーク朝」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
今日のキーワード
焦土作戦
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
お知らせ
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新