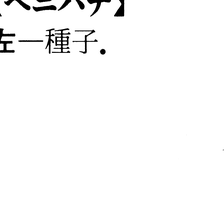改訂新版 世界大百科事典 「ベニバナ」の意味・わかりやすい解説
ベニバナ (紅花)
safflower
Carthamus tinctorius L.
西南アジア原産のキク科の二年草。サフラワーともいう。古くから南ヨーロッパ~中近東,インド,中国で栽培された。日本へは推古天皇の時代(6世紀末から7世紀初め)に朝鮮半島を経て渡来したといわれる。花から紅をとるほか,薬用にも栽培された。古くはスエツムハナ(末摘花),クレノアイ(呉の藍)とも呼ばれ,〈末摘花〉は《源氏物語》の巻名にもなっている。最近では油料作物としてアメリカやオーストラリアでも栽培が多い。
ふつう秋に,寒地では春に種子をまく。草丈0.5~1mに育ち,葉はアザミに似てとげがある。上部で枝分れし,初夏に各茎頂に橙黄色のアザミに似た花をつけ,日がたつと赤色に変わる。1花に10~100個の種子がみのる。とげが作業者の皮膚を刺すので,早朝まだ朝露のかわかないうちに花冠を摘む。これを陰干ししたものが生薬の紅花(こうか)で,漢方で婦人薬などに処方される。種子はやや堅い白色の殻に包まれ,ヒマワリの種子を小型にした形で,紅花油safflower oilを26~37%含む。リノール酸が70%を占める半乾性油で,上等の食用油となる。また血液中のコレステロールを除き,動脈硬化予防に効くとして需要が増加している。また塗料,セッケン,マーガリン,医薬品にも使われる。また,この油を燃したすすを集めて作った墨は紅花墨と呼ばれ,高級品とされる。油かすはタンパク質に富み,飼料として栄養価が高い。若い茎葉は野菜として食用にされる。切花やドライフラワーにも使われる。
執筆者:星川 清親
紅としての利用
染料と化粧料〈紅(べに)〉の原料として,ベニバナの利用の歴史は古く,前2500年のエジプトのミイラの着衣に紅花色素が認められ,朝鮮平壌郊外の墳墓出土の化粧箱の中からは,綿に浸した紅が得られた。紅の製法は夏季に花冠から紅色の色素を抽出する。紅花にはカルタミンcarthaminという紅色素とサフロールイェローsafflor yellowが含まれ,紅染にはこの水溶性のサフロールイェローを水を加えてできるだけ溶かし,アルカリで紅色素を抽出する。古代エジプトでは地中海沿岸の海藻の灰や天然ソーダで紅色素を抽出した。古代の中国,朝鮮,日本ではわら灰汁でこれを行った。褐色の抽出液を果実の酸で中和して酸性にすると,液は美しい紅色を発色し,この液を染用とする。発色用の酸はしだいに有機酸や酢に変えられた。麻や木綿,紙のような植物繊維は,サフロールイェローを吸着しないので染色は簡単である。しかし,絹は両色素を吸着して橙色に染まる。黄色素を除去した絹の紅染は,古代中国において開発されたと思われる。その後,絹の紅染は日本で改良され,紅染の前に生絹のわら灰汁による灰汁練りを行うようになる。材料としては,黄色色素を十分除き圧搾した紅餅を用いた。紅はまた,化粧料としての口紅や食紅,布や紙の染料にも用いられたほか,紅色素には駆虫性があるため,絞りかすを乾燥して夏の蚊やりに用いられた。
→臙脂(えんじ)
執筆者:新井 清
日本における生産,流通史
植物染料として江戸期に最も発達し,藍,麻と並び三草の一つに数えられた。古代の《万葉集》には〈久礼奈為(くれない)〉または〈末摘花〉として詠まれている。《延喜式》には宮中の御服や調度品の紅染法が規定され,紅花の貢納が命ぜられたが,その地域はおもに関東から中国地方であった。戦国期から近世初頭になり,その需要が上流社会だけでなく,一般庶民にも広がると,東北や九州にも発展した。17世紀末,全国に各特産物地帯が形成されると,紅花生産は出羽村山地方に集中するようになった。江戸中期に京都で刊行された《諸国産物見立相撲》によると,東関脇に最上紅花とある。最上は近世以前の村山地方の古名である。享保年間(1716-36)の全国の紅花産額は約1000駄(1駄32貫)で,そのうち出羽最上は415駄,仙台250駄,奥羽福島が120駄と次いでいる。近世末期の全国産額は約2000駄といわれたが,最上紅花は18世紀半ば以後約1000駄に達している。村山地方で紅花栽培が発達したのは,最上川中流部の山形,天童,谷地(やち)(河北町)の周辺である。この地方に紅花がとくに発達したのは,この地方の気象条件が紅花の生育にとくに適していたからで,《和漢三才図会》(1713)では,羽州最上の紅花が最もよく,伊勢,筑後がこれに次ぐとある。また紅花の需要地京都とこの地方は,最上川の河口にある酒田港を通して深い結びつきのあったことがあげられる。上方商人あるいは京都の紅花問屋は,この地方に上方物資をもたらし,紅花や青苧(あおそ)を買い付けるため,最上商人との取引が盛んであった。
最上紅花の産額が増加したのは18世紀半ばである。その背景に,それまで干し花〈花餅〉の加工は,主として山形など町方の商人によって行われていたのが,農村の上層農民のもとでも行われるようになったことがあげられる。生花(きばな)を売買する山形の花市も天明年間(1781-89)に消滅した。享保年間から続いた京都紅花14軒問屋仲間も,在方の最上紅花商人の運動によって廃止となっている。干し花の製法は,7月初旬~中旬に開花した花弁を摘み,水を加えて黄気を洗い,次にこの水花を花むしろに広げる。そのまま2~3日,日陰に寝かせて,その間水をかけて腐熟させ,手や足で踏み,粘りがでるとちぎり丸めて乾燥させる。これを紅餅ともいった。染料とするのは京都などの紅粉屋のしごとで,紅花産地では半加工品を作ったのである。京都には紅花問屋と紅染屋がおり,それらの問屋仲間のもとに多くの下請業者がいた。幕末の紅花商人をみると,京都には,紅花撰方仲間が伊勢屋源助,西村屋清左衛門など12人,紅花問屋仲間が最上屋喜八,近江屋佐助など6人であった。関東地方には,江戸の丸合組紅花荷物などを扱う問屋が,常陸,武蔵の町方に散在している。東北の紅花商人は,1851年(嘉永4)の《諸問屋再興調》によると,村山では山形が最も多く,村居清七,長谷川吉内,佐藤利兵衛など11人,ほかに谷地,天童,楯岡(村山市)の各在町,仙台地方でも各城下町,在町に1~2人がみられ,その発展が知られる。しかし,紅花は天保末年に唐紅が輸入され,開国によって化学染料が入ると急激に減少し,76年の最上紅花の産額も200駄余となっている。
執筆者:横山 昭男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報