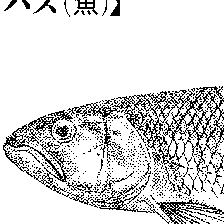改訂新版 世界大百科事典 「ハス」の意味・わかりやすい解説
ハス (蓮)
Nelumbo nucifera Gaertn.
池や水田,堀などに栽培されるハス科の多年生水草で,仏典の花として,また食用にするれんこん(蓮根)としても日本人になじみ深い植物である。日本には古く大陸から渡来したらしく,《万葉集》にハチスの名で出てくる。英名は(East)Indian lotus,Egyptian lotus,sacred lotus。なおlotusはスイレンをも含めた総称。根茎は白色で細長く泥中をはい,先端部は肥厚し,れんこんとなる。葉は長い葉柄をもち,水面に浮かぶ浮葉と抜き出る空中葉の2型がある。葉身は円形,葉柄に楯状につき,直径約30cm。葉の表に無数の小突起があり,水滴がころがる。夏に咲く花は花柄の上に単生し,花被片は多数,倒卵形,おしべは多数で,花糸は糸状。花は紅色だが,園芸品種には濃淡があり,白色のものもある。花床は逆円錐形で,多数のめしべがハチの巣状にうまる。種子は広楕円形で,長さ1cmほど。黒く堅い種皮をもつ。種子の寿命は長く,2000年前の種子が発芽している。東アジアの熱帯から温帯にかけて分布するとともに広く栽培されている。
ハス属Nelumboはしばしばスイレン科に分類されることがあるが,種子に周乳をもたない点,花粉の形態の違いなどを重視して,独立のハス科とする意見が一般的である。ハス属にはほかに黄色の花をつけるキバナバス(アメリカキバス)N.lutea Pers.(英名American lotus,water chinquapin)が北アメリカ南部や南アメリカの一部に分布している。れんこんは,中国系東南アジア人や日本人に食用にされる。またデンプンの多い種子も食べられる。
執筆者:伊藤 元己
薬用
ハスのほぼすべての部分が薬用とされる。生薬ではれんこんの節部を藕節(ぐうせつ),葉を荷葉(かよう),葉柄を荷梗(かこう),花のおしべを蓮鬚(れんしゆ),果実を石蓮子(せきれんし),種子を蓮子芯(れんししん),果托を蓮房(れんぼう)という。葉,おしべ,果実および種子にアルカロイドを含む。藕節,荷葉,蓮鬚は止血作用があり,他の生薬と配合して胃潰瘍(いかいよう),子宮出血などに用いられる。蓮子は滋養強壮薬で,他の生薬と配合して慢性の下痢,心臓病などに応用する。
執筆者:新田 あや
象徴と民俗
インド
ハスはサンスクリットではパドマpadmaと呼ばれ,この語はカマラkamala(紅いハス),プンダリーカpuṇḍarīka(白いハス),ニーロートパラnīlotpala(青いスイレン),クムダkumuda(夜開花性の白いスイレンあるいは黄色のヒツジグサ)などの総称である。〈水より生じたもの〉〈泥より生じたもの〉などの異名もある。プシュカラpuṣkaraはおもに青いスイレンを指し,バラモン教最古の文献《リグ・ベーダ》にはこの語のみが少数例みられる。《アタルバ・ベーダ》(前1000ころ)以降の文献には,ハスの実用面に関する記述,審美的描写,神話・象徴が種々みられる。れんこんはシャールーカśālūkaと呼ばれ食用とされ,そのジュース(漢訳名〈捨楼漿(しやるしよう)〉)は薬として用いられた。スイレンの茎はビサbisaといい,ジャータカの《蓮根本生》にはこれのみを食して生活する修学者が登場する。一方,医学書《チャラカ・サンヒター》はこれを消化しにくい食物とし,連日食することは避けるよう記している。この医学書はハスの果実の食用にも言及している。カーリダーサの《シャクンタラー》に描かれるように,ハスの葉はうちわとして,また,つめで葉の裏面に文字を書くために用いられ,さらに香料などを集めておく器,即席のコップ,発熱した身体に巻く冷湿布としても利用され,葉の繊維からは腕輪などが作られた。
ハスの比喩の中では〈ハスの葉と水の喩(たと)え〉が重要である。これはハスの葉が水をはじく性質に基づき,インド文化全般にみられる比喩であるが,とくに仏教においては,世間にありつつもそれに汚染されない無執着の心のたとえとしてさまざまに繰り返されている。
ハスの象徴については多くの事項の中でも次の2点が重要であろう。第1は〈生み出すもの〉としてのハスである。インダス文明のテラコッタ製地母神像の中には,頭部にハスの花の飾りをつけたものがあり,生命の母胎である水や大地の生産力の象徴とハスの花の結びつきが指摘されている。さらにこの型の母神像は後代の〈蓮女神〉ラクシュミーLakṣmī像の造形に影響を与えているともいわれる。《リグ・ベーダのキラ(補遺)》には彼女への賛歌があり,彼女は〈ハスより生まれた者〉〈蓮華(れんげ)に立つ者〉〈ハスの花輪を帯びる者〉などと呼ばれ,〈生類の母なる者,大地なり〉と賛嘆されている。このことは,ハスの象徴と生類を生み出す母神の力との結びつきが,インド文化の基層で連続していたことを示すものとされる。《マハーバーラタ》や《バーガバタ・プラーナ》にみられる創造神話によれば,ビシュヌ神は,太初の海に浮かぶシェーシャ竜を寝台として眠り,ビシュヌ神のへそが伸び蓮華を生じ,そこに梵天(ぼんてん)が生まれ世界を創造したとする。この神話は,〈産み出すもの〉の象徴としてのハスを,男性神の創造神話に組みこんだ例と考えられる。また性愛論書やタントラにおいては〈蓮華〉は女性性器を表現することばとして用いられ,一方《無量寿経》においては,極楽世界に生まれる者は〈蓮華化生〉と称し,蓮華の中に現れると説かれる。
象徴としてのハスの第2点は〈浄土〉との結びつきである。青,黄,赤,白の光を放つ4種の蓮華の生ずる蓮池は,極楽世界の描写の中心をなし,阿弥陀(あみだ)の蓮台とともによく知られている。弥勒(みろく)の浄土である兜率(とそつ)天にも七宝(しつぽう)の蓮華が説かれ,彼の大師子座の四隅からは蓮華が生じ,そこから宝女が現れると説かれる。毘盧遮那(びるしやな)仏のまします蓮華蔵世界は香水海に浮かぶ大蓮華から出生した世界とされ,先述の《マハーバーラタ》などにみられる神話との関係も指摘されている。一方,〈浄土〉とハスの結びつきは仏教に固有のものではなく,バラモン教の文献《ジャイミニーヤ・ブラーフマナ》(前9世紀ごろ)中の〈ブリグの地獄めぐり物語〉にみられるバルナ神の楽土の描写には,青蓮,白蓮の花に満ち,蜜の流れる川が登場している。
執筆者:高橋 明
中国
別字〈荷〉も蓮のことで,蓮花,荷花などと互用する。根は食用に,葉は包装用に,花は観賞用に,実は夏の食品となって捨てるところのない植物であるが,中国でこれが重視されたのは,仏教に伴ってインドの蓮花愛好の風習が伝わって以後である。蓮台,蓮花灯,《蓮花経》など,すべて仏教に縁がある。しかし中国民俗中の蓮は仏教とは関係なく,もっぱらその字音の語呂合せで吉祥の意味を表す。例えば,新年に用いる吉祥図版画で,蓮の花と鯉魚(りぎよ)を描いたものは〈蓮年有魚〉で,音通で〈連年有余〉または〈連年利余〉の意。蓮花に童子を配した図案は〈連年貴子〉で,これまた続けて聡明な男児を授かるの意。また〈荷〉は〈和〉と同音で,荷花を描いて〈和気生財〉の徴とし,蓮根の〈藕〉は〈偶〉と同音で夫婦佳偶の意とする。さらに1枝に2花をつける蓮を〈並蒂蓮〉とよぶが,比翼連理(比翼の鳥)と同じく夫婦の相和して離れない形とする結婚祝賀の文句である。
執筆者:沢田 瑞穂
エジプトと西洋
古代エジプトでは,ナイル川の増水時期に開花するエジプト・ハスEgyptian lotusを,生命と生産力の象徴とみなした。また,夕方に沈み翌朝ふたたび水面に出て開花する姿は,再生を強く連想させ,花をミイラに飾ったり,航海へ出る船や葬儀への献花とした。この花は王冠に似た形態から王位を表すものと考えられ,さらにオシリスの持物にあてられる。太陽神ホルスはハスから生まれたともいわれ,花の中央に立ちあがる姿で描かれることもある。しかしエジプト・ハスは実際はスイレンを指すと考えられている。一方,古代ギリシアにはハスを食うと記憶を失うとの伝説があり,ホメロスは《オデュッセイア》の中で,〈ハス食い人(ロトファゴイLōtophagoi)〉の国にオデュッセウスの一行が上陸した際,部下がハスを食べて故郷に帰ることを忘れたので,強引に出帆したという話を伝えている。今日では〈ハス食い人lotus eater〉といえば放蕩三昧(ほうとうざんまい)に日々を送る人を指す。このため西洋では,ハスを一種の麻薬と考える風潮が生じたが,古代ギリシアのハスもまたじつは,正体の定かでない陸生の植物を指したものといわれている。また,ハスは装飾モティーフともなり,古代エジプトの神殿では,ハスの花を図案化したロータス形(鐘形)柱頭が用いられた。ロータス文様はギリシアやイランなどでも愛用され,パルメットと組み合わされ,さらにインドにおいて蓮華文に結実し,仏教美術の主要なモティーフとなった。花言葉は〈雄弁〉〈平穏〉〈神秘と真実〉。
執筆者:荒俣 宏
ハス (鰣)
Opsariichthys uncirostris
コイ目コイ科の淡水魚。大阪では本種をケタバス,オイカワをハスと呼ぶ。原産地は琵琶湖,福井県三方湖およびこれに注ぐ鰣川(はすかわ)に限られていたが,琵琶湖のコアユに混じって国内各地に移殖,放流されて現在では関東地方などに繁殖している。水の澄んだ湖や川の中,表層を活発に泳ぎ,また水面にとびはねる。餌は小魚や昆虫などで,琵琶湖ではコアユを好んで捕食する。形はオイカワに似るが口が大きく両あごが〈ヘ〉の字状に曲がるのが特徴。成魚の全長も20~30cmでオイカワよりもひとまわり大。産卵期は琵琶湖では6~8月で,湖岸近くや湖に注ぐ小河川の砂れき底に産卵する。産卵行動は1対の雌雄によって行われる。小骨が多いが琵琶湖畔では塩焼き,刺身などにして食用にされる。しゅんは初夏。アジア大陸の温帯部には近似種コウライハスO.bidensが広く分布する。
執筆者:中村 守純
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報