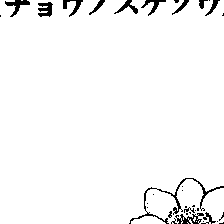チョウノスケソウ
Dryas octopetala L.var.asiatica Nakai
高山に生え,あまりふつうには見られないバラ科の小低木。茎は堅く,地面をはい,先に葉をつける。葉は密にかたまって互生し,長さ1~2cmの広楕円形または卵形,裏面には白い綿毛が密生する。7~8月に,5cmほどの花茎の先に,直径2cm内外の花を,それぞれ1個つける。花弁はふつう8枚,楕円形または卵形で白色。おしべもめしべも多数あり,めしべの花柱は,花が終わると長く伸びて3cmに達し,白く長い毛があって羽毛状になる。北半球の北部に広く分布する種であるが,日本にある変種は,アジア大陸東部からアレウト列島にかけて生じ,北海道と本州中部以北の高山帯にも見られる。日本では,岩手県人で植物採集家として著名な須川長之助によって,明治はじめに発見されたというので,この和名がある。氷河時代の寒冷期を指標する植物で,この属の化石を含む植物群は,ドリアス植物群として有名である。チョウノスケ属の常緑樹は,英名をmountain avensという。
執筆者:山中 二男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
チョウノスケソウ
ちょうのすけそう / 長之助草
[学] Dryas octopetala L. var. asiatica Nakai
バラ科(APG分類:バラ科)の常緑小低木。茎はよく分枝し、地表をはう。葉は単葉で柄がある。小葉は広楕円(こうだえん)形で革質、裏面は白綿毛が密生し、縁(へり)に鋸歯(きょし)がある。7~8月、5~10センチメートルの花柄に径約2センチメートルの白色花を1個開く。花弁は8、9枚。花期後、花柱は3~4センチメートルに伸長して尾状となり、長い毛をもつ。果実は痩果(そうか)。中部地方、北海道の高山に生え、朝鮮半島、ウスリー、樺太(からふと)(サハリン)、千島に分布する。名は、本種の発見者須川長之助(ちょうのすけ)(ロシアの植物学者マクシモビチの採集に協力した)を記念してついた。チョウノスケソウ属は北半球の高山や寒帯に2、3種あり、氷河時代の残存植物として有名である。
[鳴橋直弘 2020年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア
「チョウノスケソウ」の意味・わかりやすい解説
チョウノスケソウ
バラ科の小型の落葉小低木。北海道,本州中部のかわいた高山の草地にはえる。茎はよく分枝して地上をはい,密に葉がつく。葉は卵形で,側脈がくぼみ,下面には白綿毛が密生。夏,長さ2〜6cmの花柄に1花を上向きにつける。花は白色で径2〜2.5cm,多くは8弁。花後に長毛のある分果を結ぶ。名は発見者の須川長之助にちなむ。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内のチョウノスケソウの言及
【氷河植物群】より
…これらの植物群に代わって,氷河植物群または極地高山植物群と呼ばれる植物群が分化し,その分布域を寒冷気候が支配する地域を中心に拡大した。この植物群は,その代表的植物の[チョウノスケソウ]Dryas octopetala L.の名をかりてドリアス植物群Dryas floraと呼ばれることもある。ムカゴトラノオBistorta vivipara S.F.Gray,マルバギシギシOxyria digyna Hill,ヒメカンバBetula nana L.など,今日,北極圏やヨーロッパ・アルプス,ロッキー山脈に見られる植物が,この植物群を指標し,中緯度地方の高山植物群の主要な構成要素をなしている。…
※「チョウノスケソウ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」