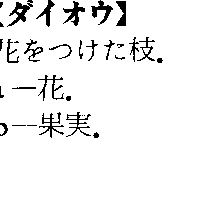ダイオウ (大黄)
rhubarb
Rheum
ダイオウ属Rheumは中国,ヒマラヤの高地とアジア内陸のステップに約50種が分布するタデ科の多年草。そのうち数種の根茎が漢方の大黄として利用されるが,種により薬効成分の含量は異なる。また葉柄を食用にするルバーブがある。それらのうちダイオウR.officinale Baill.は太い根茎をもち,根出葉は卵円形で3~7裂,幅30~90cm。葉柄は長く,叢生する。花茎は高さ1~3m,葉状の苞葉があり,分枝し壮大な円錐花序をつける。花期は夏。花は両性花,花被片は6枚,長さ3mm。おしべは9本,花柱は3本で細裂し,紅紫色。堅果は3翼があり,長さ1cm。みつ腺をもつ虫媒花で,種間交雑を起こしやすい。花の構造はタデ科の中では原始的である。中国の四川,雲南,湖北,陝西の各省の山地に生じ,栽培される。根茎を薬用にし,欧米では大型の葉と花序を観賞する。
ダイオウ属は形態的に多様で,地域的に利用される有用植物が多い。R.nobile Hook.f.et Thoms.は,根出葉の直径30~40cm,茎が太く直立し分枝せず,高さ1m。花は多くの円錐花序につき,大型の黄白色の多くの苞葉に覆われ,全草が行灯状にみえる。東部ヒマラヤに分布し,太い花軸は食用にされる。R.moorcroftiana Royleは根出葉は厚く,革質で円形,直径30cm。花茎は太く,苞葉がなく,花は疎な穂状につく。ヒマラヤに分布し,根茎は緩下剤として用いられる。ヒマラヤではこのほかにR.emodi Wall.やR.webbianum Royleの根茎が大量に薬用に採取されている。R.macrocarpum A.Los.は中央アジアに分布し,根茎からタンニンを採取する。
執筆者:土屋 和三
薬用
ダイオウ属のダイオウR.officinaleに似て葉がさらに切れこむR.palmatum L.をはじめ同属近縁植物の根茎が薬用になり,重質と軽質の2系統がある。ダイオウ属はディオスコリデスの《薬物誌》に記載されており,古来,中国からヨーロッパへと輸出された数少ない生薬の一つである。品質はさまざまで,錦紋(きんもん)star spotが散在するものが良品とされている。錦紋とは大黄特有の組織で,小さな異常維管束の髄線が放射状に見え,つむじ様を呈し,肉眼でも見ることができるものである。現在でもヨーロッパへは錦紋の重質系の最上級品が輸出されている。日本では古来,軽質品が使われ,現在,錦紋軽質系の雅黄(がおう)が輸入されている。一方,ヨーロッパ栽培種(すでに雑種になったと思われるもの)および朝鮮産のチョウセンダイオウR.coreanum Nakaiが日本においても栽培されている。アントラキノイド,センノサイドsennoside AおよびB,レインrhein,エモディンemodin,アロエエモディンaloe-emodin,タンニンなどを含む。瀉下(しやげ),抗菌,利胆作用があり,他の生薬と配合して常習の便秘,細菌性赤痢,口内炎,喉頭炎,急性肝炎,胆囊炎や胆石症,諸種の急性出血および月経調節に用いられる。また消炎,解毒作用があり,はれもの,湿疹などに外用される。
大黄は上記のほかに根を主とするものがあり(インド大黄,和大黄,トルコ大黄,ラポンティクム根),これらは品質が劣るとされている。
執筆者:新田 あや 中国産の薬用にされる大黄は10世紀以降イスラム商人により西方へ盛んに輸出された。キャフタ条約(1727)後,清とロシアとの間に盛んになったキャフタ貿易においては,大黄が中国側の重要な輸出品の一つであった。
執筆者:若松 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ダイオウ
だいおう / 大黄
rhubarb
[学] Rheum
タデ科(APG分類:タデ科)の多年草の1属。中央アジア山地、中国、シベリアに分布し、約40種からなる。このうち、薬用として重要なのは中国西部の標高3000メートル付近の高地に野生または栽培される次の3種である。(1)パルマーツム種(モミジバダイオウ)Rheum palmatum L.(陝西(せんせい)省、甘粛(かんしゅく)省南東部、青海省、四川(しせん)省西部、雲南省北西部、チベット東部に分布)。(2)タングチクム種R. tanguticum Maxim.(甘粛省、青海省、チベット北東部に分布)。(3)オフィキナーレ種R. officinale Baillon(湖北省西部、河南省南部、陝西省南部、四川省、貴州省、雲南省北西部に分布)。
前3種はいずれも花茎は高さ2.5メートルに達し、その基部に長い肉質の葉柄をもつ大形の葉を多数つける。葉身は長さ25~30センチメートル、幅60~70センチメートル(前二者は掌状に深く3~7裂し、後者は浅裂する)、基部は心形である。茎葉は小さく互生し、葉柄の基部は膜質の葉鞘(ようしょう)となる。6~7月、茎の上部に総状あるいは円錐(えんすい)花序となる小花を多数つける。小花は数個集生し、花柄は長い。花被(かひ)は内外2列におのおの3個あり、雄しべは9個、雌しべは1個で花柱は3個。痩果(そうか)は、花後に増大した3個の内花被に包まれて三稜(りょう)となるが、各片は全縁で先端はへこむ。地下部は垂直の太い根茎にゴボウ状の根が多数ついている。
[長沢元夫 2020年12月11日]
薬用として使われるのは根茎で、栽培種の場合、4年目には生(なま)の重さが3~5キログラムほどになる。通常は6~7年経過した根茎の皮と根を除去し、そのままか、あるいは横に輪切りにして乾燥する。もっとも良質のものを錦紋(きんもん)大黄といい、中国では紀元前から消炎性下剤として重用し、現在も多数の処方に配合されている。また、同品はヨーロッパ各国の薬局方にも収載されている。瀉下(しゃげ)成分はアントラキノン誘導体およびその二量体のセンノサイドである。ほかにタンニンも含有し、少量では健胃作用を現し、多量では緩下剤となり、常習便秘や消化不良などに用いる。日本では、1950年(昭和25)から錦紋大黄を得るために長野県、北海道などでダイオウが栽培されるようになっている。なお、古くから奈良県、岩手県で栽培されてきたダイオウは和(わ)大黄と称され、品質がよくないため、主として売薬に用いられてきた。
黄色染料、線香の材料とされるのはカラダイオウR. rhabarbarum L.(R. undulatum L.)で、シベリア東部、モンゴル、中国黒竜江省、華北が原産地である。ショクヨウダイオウR. rhaponticum L.はマルバダイオウ、ルバーブとも称し、シベリア南部からボルガ川下流域にかけて分布する。葉柄は長さ30センチメートル、径5センチメートルほどになり、食用とされるほか、ゼリーやパイの原料ともなる。ショクヨウダイオウには特有の香気と酸味があり、ビタミンA、B、Cを含有する。なお、カラダイオウとショクヨウダイオウの根生葉は、円形で分裂せず、辺縁は波状を呈する。
[長沢元夫 2020年12月11日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ダイオウ
中国西部,チベット原産のタデ科レウム属の多年草。根茎は黄色で肥大し,茎は高さ2m内外。初夏に小さい緑黄色花を多数つける。ダイオウおよびその近縁種の根茎を乾燥したものを大黄(だいおう)といい,中国で古くから薬用とされた。日本には奈良時代にはすでに渡来。錦紋大黄,雲南大黄などの種類がある。成分のアントラキノン誘導体やその配糖体は大腸の蠕動(ぜんどう)運動促進作用をもち,便秘や胃腸病に煎剤(せんざい)として適用される。レウム属は約50種あり,中国,ヒマラヤを中心としたアジア内陸部に分布する。食用にされるルバーブ,〈温室植物〉として知られるレウム・ノビレなどがある。
→関連項目生薬|薬用植物
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ダイオウ
タデ科のダイオウなどの根茎。瀉下(しゃげ)作用があり生薬として使用される。表記は「大黄」とも。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のダイオウの言及
【ルバーブ】より
…葉柄を食用にするタデ科の多年草。ショクヨウダイオウ(食用大黄),マルバダイオウ(丸葉大黄)ともいう。原産地はシベリア南部とされているが,ギリシア・ローマ時代にはすでに栽培されていた。イギリスには16世紀に導入されたが,市場に出るようになったのは19世紀になってからである。日本に入ったのは明治初期とされるが,普及するに至っていない。温帯の中北部に適し,暖帯にはむかない。土壌は選ばない。根生する葉は無毛で大きく,心臓形をしている。…
※「ダイオウ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」