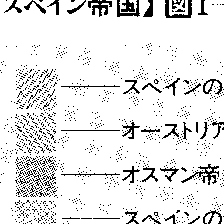改訂新版 世界大百科事典 「スペイン帝国」の意味・わかりやすい解説
スペイン帝国 (スペインていこく)
一般に16世紀から17世紀前半にかけて,ヨーロッパ,アメリカ,アジアの諸地域を支配し,かつ西ヨーロッパの列強に伍したころのスペインを指す。そして文化史の視点からは,この時代はスペインの黄金の世紀Siglo de Oroと呼ばれる。なお,〈スペイン帝国〉とは後世に造られた呼称であって,当時のスペイン王は自分の版図をカトリック王国Monarquía católicaと呼び慣らわした。さらに自国領以外の土地およびその住民に対する統治行為の意味に〈帝国〉を解するならば,〈スペイン帝国〉は1898年まで続いた。
スペインの誕生
15世紀後半,イベリア半島はカスティリャ,アラゴン連合王国(以下アラゴンと略記),ポルトガル,ナバラおよびイスラム教徒のグラナダ王国(ナスル朝)の5ヵ国に分かれ,そこにはまだスペインという国はなかった。しかし,カスティリャにイサベル1世が立ち(1474),次いでアラゴンの王位にフェルナンド2世が就くと(1479),その後40年足らずの間にポルトガルを除く4ヵ国はカトリック両王のもとに一つの王権を共有するという形で新しい政治単位を形成,周辺諸国はこれをスペインと呼び始めた。
しかし,このスペインは決してカスティリャとアラゴンの統一合体を意味するものではなかった。それはさしあたり両国が以後フェルナンドとイサベル両王の共同統治時代を迎え,また対外的にはあたかも一国のように完全に歩調をそろえて行動するというだけのことだった。それだけに,それぞれの領国の内政に臨む両王の姿勢には,おのずから著しい差異があった。
議会をはじめとする制度や法律によって伝統的に王権が大きく拘束されていたアラゴンの場合,フェルナンドは従来の体制を再確認する方向で世論の支持を取り付け,国内秩序の回復を図った。改革といえるものはわずかにカタルニャ農民を封建的慣行から解放して実質的に耕作地の所有者に変えたグアダルーペ裁断(1486)くらいだった。
これに対してカスティリャでは,積極的に王権の優位確立を目ざして一貫した努力が傾けられた。貴族が一定の条件を満たさない所領の王室返還を強要され,その城郭を取り壊され,政治の要職から遠ざけられる一方,都市は国王任命の官吏(コレヒドール)の派遣によって自治の伝統を失っていき,これに伴ってもともとその機能面で弱体だった議会(コルテス)も抵抗らしい抵抗も見せずに本来の使命を放棄していった。そしてもう一つの伝統的勢力である教会にいたっては,グラナダ征服戦,異端審問制度の発足,異教徒の追放などカトリック・スペイン樹立に向けての政策を次々と打ち出す王権にはひたむきな忠誠をもってこたえるしかなかった。こうしてカトリック両王の下でカスティリャはアラゴンとは逆に王権が大幅な行動の自由を享受する国に改造されていった。そして半島随一の人口と経済力がこれに加わるとき,新生スペインにあって王権の最大の関心はおのずからカスティリャの統治に大きく傾いた。以後,カスティリャが政治,経済,文化の諸領域のイニシアティブを握る一方,〈スペイン帝国〉の過重な負担にひとり耐えるのも,その起点はここにあった。
スペインの拡大
共同統治がいち早くしかも大きな成果を挙げたのは,いまや完全に一本化された対外政策の面においてであった。カスティリャはイサベル即位の直後これに反対するポルトガル王の武力干渉を受けて内戦状態に陥ったが,フェルナンドの才覚は短期間でこの危機を打開して世論の信望をかち取った。すると両王は長い間放置されてきたグラナダ王国の征服,すなわち中世以来の国民的課題であるレコンキスタ(国土回復戦争)の完成を目ざし,10年間の戦争の末にこれを達成した。イベリアの中世が終わり,新生スペインは拡大の一歩を踏み出した。この後,カスティリャの支配はまもなくイベリアの枠を超えてカナリア諸島やメリリャなどの北アフリカ沿岸の拠点のいくつかに及んだ。他方,13世紀以来アラゴンとフランスが覇権を争ってきたイタリア南部でも,フェルナンドはカスティリャの軍事力をてこに俄然優位に立った。
しかし,後の〈スペイン帝国〉成立を決定的にした最大の事件はなんといってもインディアスの出現だった。グラナダ征服を終えたばかりのカトリック両王が,一介の外国人船乗りコロンブスと交わした多分に投機的な性格の約定書がはからずももたらしたこの未知の土地こそは,その広さと人口と富からしてスペインに帝国としての実体を付与するものだった。発見から50年足らずの間にインディアスの主要地域はカスティリャ領となり,16世紀後半にはフィリピン諸島もこれに加えられた。そして以後300年間,この体制は実質的変化を被ることなく続いた。
カトリック・スペインへの道
中世西ヨーロッパの中でイベリア半島はキリスト教徒,イスラム教徒,ユダヤ教徒の3者が共存した唯一の地域だった。しかし中世末期には強度の社会緊張が生じ,暴動が頻発するようになった。カトリック両王はこうした状況の解決のために3者共存の伝統との決別,すなわち自国を他の西ヨーロッパ諸国のようなキリスト教徒のみの国にするという選択を行った。結局,社会,経済,文化その他さまざまな面で考えられるあらゆる犠牲をあえて無視したうえで,両王は強引に信教統一政策を実行した。異端審問制度発足(1480),ユダヤ教徒追放(1492),イスラム教徒追放(1502)の三つである。
しかしながら,過去との決別にせよ,新しい理想の実現にせよ,これらの性急かつ乱暴な施策で容易に達成されるべきものではなかった。事実,16世紀以降のカトリック・スペインは表面上の統一と平和の下に宗教対立に根ざすさまざまな危機的課題を内蔵し続けたのであり,しかもその解決の見通しはきわめて暗かった。いっとき,対抗宗教改革の覇者を自任したころのスペインのかたくなな政治姿勢と異端審問制度下の社会緊張は,ともにその裏側にこの内的もろさが指摘できよう。
ハプスブルク朝スペインの発足
政治面で多くの成功を収めたカトリック両王も後継者には恵まれなかった。ただ一人の王子には先立たれ,王族間の結婚によるポルトガルとの連合結成も当事者の死によって夢に終わった。1516年にフェルナンドが死んだとき,カスティリャとアラゴンの王位継承順位の筆頭者は,両王の次女フアナの長男カルロスだった。名門ハプスブルク家の血を引くとはいえ,この孫の登場はおそらく両王が生前予想も期待もしなかったことだった。
カルロス1世(カール5世)の即位は8世紀初頭のイスラム教徒のイベリア征服に匹敵する事件だった。それは以後スペインが歴史上初の体験としてピレネー以北のヨーロッパ情勢に深くかかわっていく,いわば歴史の転換を意味した。続くカルロスの神聖ローマ帝国皇帝選出は,この新しい関係を決定的なものにした。急転する事態に反発してカスティリャが起こした反乱(コムネロスの反乱)が失敗に終わると,事実カルロスはその汎ヨーロッパ的帝国政策の渦中にスペインを引き込んでいった。
カルロスのヨーロッパ防衛
カルロスは自己の皇帝選出を神の摂理の表れと受け止め,皇帝としての使命の遂行に生涯を賭けた。おりからヨーロッパは,ルターの抗議を契機として起こった精神界の分裂とビザンティン帝国を滅ぼして勢いに乗るオスマン・トルコの覇権主義という外圧に挟撃されて危機的局面に立っていた。この状況を前にカルロスはヨーロッパの伝統的統一を回復し,次いでヨーロッパを挙げて共通の外敵に対処することこそが自分の任務であると考えた。
しかし彼のこの考えも,視点を変えて見ればハプスブルク覇権主義としか映らず,ローマ教皇庁はこれを警戒し,フランスは激しく反発した。また急速に政治化していったプロテスタンティズムにとって,カトリックの立場を固守するカルロスは聖俗両面で最も危険な存在だった。こうして結局カルロスは外敵トルコとの対峙以前にヨーロッパで相次ぐ戦争を強いられ,しかもひとつとして決定的な勝利を得られなかった。彼が帝位を弟のフェルディナントに,カスティリャとアラゴンの王位を息子フェリペに譲って失意のうちに退位したとき(1556),問題は何ひとつ解決されていないばかりか,彼の帝国政策の最大の支えとなったカスティリャの財政は早くも危機的な赤字を負っていた。これらはむろん王位とともにフェリペが引き継がなければならない遺産となった。
カトリック信仰の防衛
カルロスはまだヨーロッパの再統一に期待をかけ,そのために汎ヨーロッパ的視点に立って行動した。しかし,フェリペ2世にはヨーロッパの分裂はもはや不可逆の事実であり,なすべきはカトリック・ヨーロッパの防衛に積極的に打って出ることだった。
即位後まもなく国内でプロテスタントの存在が発覚すると,フェリペは外国書籍の輸入禁止,国内出版の規制強化,スペイン人の国外留学禁止などで国民のカトリック信仰が〈汚染〉されるのを防止しようとした。この後のユグノー戦争下の隣国フランスへの積極干渉,カルバン派の暴動に端を発したフランドル戦争での一貫した強硬策,この過程で新たに生まれたエリザベス1世との対立とその延長であるドーバーの海戦(無敵艦隊の敗北)は,いずれもカトリック・ヨーロッパの防衛とスペインの威信を同一視した同王の対応姿勢だった。しかし,この陰で王室財政はまったく破綻し,これを支えるカスティリャ経済は確実に疲弊していった。同時に,その強大さゆえにスペインの名はカトリック諸国を含めてヨーロッパ全土で憎しみと恨みの的となっていった。
フェリペのこのヨーロッパでの失敗は,しかしながら,地中海とイベリア半島内でいくぶん補われた。つまり,レパントの海戦での勝利とポルトガル王位の継承である。前者はキリスト教諸国の反転攻勢にまではつながらなかったものの,オスマン帝国の西進を効果的に阻止した。そして後者はイベリア全土の連合というカトリック両王以来の理想の実現にほかならなかった。しかし同時にそれはアジアと南アメリカに広がるポルトガル領の防衛という新しい負担をフェリペに課するものだった。
破局への道
17世紀初め,ヨーロッパの戦局は一時の休息を必要とした。しかし,まもなく三十年戦争の火の手が上がり(1618),すでに泥沼化したフランドル戦争も再燃した(1621)。このときスペイン政治を牛耳ったのは上流貴族出身のオリバレスだった。経済的富には淡泊だった反面,その政治的野心はとどまることを知らなかった彼の目的は,ヨーロッパに号令する大国スペインの保持だった。彼の下でスペインは幾重にも戦争に関与,急上昇する軍事費の重荷にその財政と経済の崩壊はやがて陸海両軍の大敗となって露呈した。北フランドル(オランダ)の独立を承認するウェストファリア条約(1648)は〈スペイン帝国〉に大きな節目を付けるものだった。この後,スペインは隆盛期に入ったフランスの攻勢の前に南フランドルその他の領土を失う一方,1640年以来既成の事実だったポルトガルの独立も承認してその版図を大きく縮めた。
ブルボン朝の下で
政治・経済・軍事面の凋落にもかかわらず,17世紀末のスペインは依然としてヨーロッパの大国だった。病弱なカルロス2世を最後にハプスブルク朝の断絶が明らかとなると,スペインの王位継承問題はヨーロッパ最大の関心事となった。そして同王が〈スペイン帝国〉の延命をそれまでの宿敵フランスのブルボン朝にゆだねて死ぬと,列強間の利害の対立はスペイン継承戦争となって爆発,その結果スペインはフランドルやイタリア方面での最後の領土を失ったばかりか,ジブラルタルの割譲をイギリスに強いられた。それでも大西洋を隔てた広大なインディアスはほとんど無傷のままだった。
フェリペ5世に始まるスペイン・ブルボン朝はフランス的合理精神に沿ったさまざまな改革を精力的に進めて国の建直しを図った。改革はすべての領域で満足な成果は挙げえなかったものの,ヨーロッパにおけるスペインの威信は順調な経済力と軍事力の回復に支えられて著しいものがあった。しかし,これもスペイン・ブルボン朝の名君カルロス3世の没後は,フランス革命の余波と国王以下有能な政治的人材の欠如からもろくも崩れ始めた。そしてナポレオンが登場すると,その覇権主義の好餌となったスペインはブルボン改革の成果をトラファルガーの海戦で失い,次いで熾烈な独立戦争を当のナポレオンに挑まざるをえない状況に陥った。事態は大西洋を越えてインディアスにも波及,そのスペインからの独立という結果を生んだ。ナポレオンからの独立は,〈スペイン帝国〉の実質的終焉でもあった。
執筆者:小林 一宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報