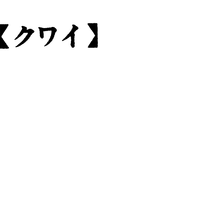クワイ (慈姑)
arrowhead
swamp potato
Sagittaria trifolia L.var.edulis(Sieb.)Ohwi
オモダカ科の水生多年草。地下の塊茎を食べるが,野菜として栽培されているのは日本と中国に限られる。クワイの名は〈鍬芋(くわいも)〉の略で,葉と葉柄の形が農具のくわに似ているところからきている。草丈は90~120cmで,葉柄は長く,葉は直立する。葉身はやじり形で特徴がある。株は全体に平滑で緑色,無毛でつやがある。地下茎から多くの匍匐(ほふく)枝を出し,先端に球形,楕円形または扁球形の塊茎をつける。塊茎の表面はうすい藍色を呈し,節輪がある。また塊茎の頂点には,くちばし状の頂芽がある。野生種オモダカはヨーロッパ,アジア,アメリカから温帯,熱帯にかけて広く分布するが,栽培は中国が始まりといわれている。日本では延長年間(923-931)の記録に〈久和為〉の名がみられるので,奈良時代には栽培が行われていたものと思われる。シロクワイとアオクワイとがあり,一般によく作られているのはアオクワイで,とくに関東に多い。湿田に栽培し,とくに泥田がよい。土壌は腐植に富む壌土が適する。砂壌土では早熟栽培に適するが,球の充実が悪くなる。塊茎は正月の煮しめや祝儀の折詰の材料としてよく使われる。そのほか,煮たものを花形に切って花クワイにしたり,きんとん,てんぷら,煮豆,砂糖漬の材料としたり,中国ではデンプンも製造する。一種のえぐ味がある。えぐ味を除くには,調理の前にあらかじめ水煮し冷水に入れておくか,米のとぎ汁でよく煮ておくとよい。主成分はデンプンである。一般家庭用の需要は少ない。また重弁花に改良されたものは観賞用として池などで栽培される。スイタ(吹田)クワイまたはマメクワイといわれる栽培型のオモダカS.trifolia L.var.trifolia Makino f.suitensis Makinoは関西で食用にされている。
執筆者:平岡 達也
料理
クワイは煮物,茶碗蒸しの具,その他いろいろに調理されるが,独特の古雅な持味を生かすには煮含めるのがいちばんである。《精進献立集》(1819-24)は10種にあまる料理を記載し,なかには現在行われているものも少なくない。おろし金でおろして使うものが多く,おろして塩を少し入れ,小さな粒にまるめて油で揚げるのが〈いちごくわい〉,おろしたものを浅草ノリに塗りつけて揚げ,それを切って煮るのが〈みなとくわい〉,おろしたものを蒸してすり,砂糖・塩で調味して卵焼鍋で焼き,ケシの実・ゴマを振って切るのが〈松風ぐわい〉,おろしたものをうすい塩味にして蒸し,それをノリ巻にして小口切りするのが〈くわい鮨〉,おろしたものに小麦粉を加えてすり合わせ,ぎんなん,クルミなどを加えて油で揚げてから煮込むのが〈くわいひりょうず〉といったぐあいである。〈くわいせんべい〉は薄切りにしたものを火であぶるとしているが,これはポテトチップ風に揚げて塩を振るのがいいようである。
執筆者:鈴木 晋一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
クワイ
くわい / 慈姑
[学] Sagittaria trifolia L. 'Caerulea'
Sagittaria trifolia L. var. edulis (Sieb.) Ohwi
オモダカ科(APG分類:オモダカ科)の多年草。オモダカの変種。中国原産で、日本や中国では塊茎を食用とするために水田で栽培される。欧米では観賞用とする。草丈は高さ1メートルに達し、葉身は三角形の矢じり形で長さ30~40センチメートル、葉柄は50~70センチメートルで、基部が広く鞘(さや)状になる。秋、まれに葉心から花茎を出し、白色の3弁花を輪生する。花茎の上部に雄花、下部に雌花をつける。泥中に地下茎を伸ばし、秋にその先端に球状の塊茎をつける。塊茎は直径1.5~4センチメートルで、オモダカより大型。春から夏に塊茎を水田に植え付け、生育に伴って追肥、消毒、除草などの管理をする。地上部が枯れた秋から翌春までの間に掘り取る。塊茎の肌は青色で肉質がよく、苦味の少ない青クワイが中心的な品種で、新田(しんでん)クワイ、京クワイなどともよばれる。日本では10世紀にすでに栽培され、現在は広島県福山市や埼玉県南部が主産地である。
中国では白クワイも栽培されるが、品質が劣り、日本では栽培されていない。
[星川清親 2018年9月19日]
塊茎には翌春伸びる芽が出ているので、「芽が出る、めでたい」にかけて、縁起物の野菜とされ、正月料理としての利用が多い。肉質がよく、甘味とほろ苦さがある。甘く煮含めたり、きんとんなどにする。あくが強いので、皮をむいて水にさらし、ゆでてから料理する。くわい煎餅(せんべい)は、皮をむいたクワイを1ミリメートルほどの厚さの輪切りにして水にさらし、水をきってしばらく陰干ししてから油で揚げたもので、塩味で食べる。また、皮をむいてすりおろし、卵と小麦粉で練り、団子にしたり、のりで包んだりして揚げるのもよい。
中国料理に使われるしゃきしゃきとしたクワイはカヤツリグサ科(APG分類:カヤツリグサ科)のオオクログワイで、本種とは別物である。
[星川清親 2018年9月19日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
クワイ
《栄養と働き&調理のポイント》
中国が原産地のクワイには、おもに3種類があります。
わが国の主要品種である直径約5cmのアイクワイ、中国で栽培されるシロクワイ、大阪吹田(すいた)で栽培されるスイタクワイの3種です。
中国料理でよく用いられる食材にオオクログワイがありますが、これはカヤツリグサ科のもので、オモダカ科のクワイとは別科のものです。
クワイは多年生の水性植物で、地下にできる塊状の茎を食用にします。旬(しゅん)は冬から初春にかけてで、芽がでていることから目出たい野菜とされ、正月料理に縁起物としてよく用いられます。
○栄養成分としての働き
栄養面での特徴は、カリウムが豊富に含まれていることがあげられます。カリウムを多くとると、塩分に含まれているナトリウムが排泄(はいせつ)され、高血圧を予防することができます。味はユリネに似ていて、ゆでるとホクホクとした食感になります。
アクが強く、すぐに色が悪くなるので、酢をたらした湯や米の研ぎ汁で下ゆでしてから調理します。「芽がでる」縁起物として正月料理に欠かせませんが、このときは、芽の部分をこわさないようにていねいに扱います。含め煮が一般的ですが、生のクワイをすりおろして小麦粉と混ぜ、揚げ衣に使ったり、うすく切って水にさらし、素揚げにするとおいしく食べられます。
購入する際は、つやがよく、芽の部分がまっすぐ伸び、しっかりしているものを選びましょう。
出典 小学館食の医学館について 情報
クワイ
中国原産のオモダカ科の野菜。各地の水田に栽培される。球茎はやや青みを帯び,球形で,先端から,葉と,地下性の匍匐(ほふく)枝をのばし,枝の先端に扁球形で頂にくちばし形の芽のある塊茎をつける。これを煮たり,きんとんなどにして食用とするが,苦みがある。なお中国料理に用いられるクログワイ(オオクログワイ)は,カヤツリグサ科の植物。
→関連項目オモダカ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
クワイ
[Sagittaria trifolia var. sinensis],[S. sagittifolia].オモダカ目オモダカ科オモダカ属の水生多年草.塊茎を食べる.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のクワイの言及
【オモダカ(沢瀉)】より
…アジアの温帯~熱帯に広く分布する。[クワイ]はオモダカから育成された作物で中国の原産,日本でも水田に栽培されている。オモダカよりも大型で,花茎の高さ1mに達するものが多い。…
※「クワイ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」