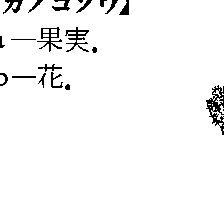カノコソウ
かのこそう / 鹿子草
[学] Valeriana fauriei Briq.
オミナエシ科(APG分類:スイカズラ科)の多年草。山地のやや湿った所に生え、栽培もされる。東アジアに広く分布し、日本では北海道から九州に生える。茎は直立し、高さ30~80センチメートル、葉は対生し、7枚の羽片に深裂し、羽片には粗い鋸歯(きょし)がある。5~7月に茎の先端に集散状に淡紅色の多数の小花を開く。花冠は細長い筒状で片側はやや膨れ、先端は5裂し、雄しべ3本は花外に突き出る。果実は披針(ひしん)形で長さ約4ミリメートル、その上部に冠毛状の萼(がく)がある。地下の根茎から走出枝を出して繁殖する。根茎は太さ約1センチメートル、長さ1.5センチメートルで、長さ約20センチメートルの細根を多数つける。この地下部を薬用とする。それをカノコソウ、纈草根(けっそうこん)、吉草根(きっそうこん)と称する。ケッソウコンと発音するのが正しいが、最近ではキッソウコンが普通になった。精油を含有し、鎮静剤として用いる。ヨーロッパではセイヨウカノコソウV. officinalis L.の地下部をワレリアナ根と称して、紀元前から利尿、鎮痛、通経剤として使用していたが、現在よく使われている神経症状、たとえば、てんかんなどの治療法は18世紀中期以後に開発され、その経験からカノコソウの利用が始まった。
カノコソウに類似したツルカノコソウV. flaccidissima Maxim.は茎の基部から細長い走出枝を出し地上をはって繁殖する。葉の羽片は卵円形で波状の鈍歯があり、雄しべは花外に突き出ない。茎の高さは20~40センチメートルで軟弱である。これは薬用にしない。本州、四国、九州の山地の木陰に生える。台湾、中国にも分布する。
[長沢元夫 2021年12月14日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
カノコソウ (鹿子草)
Valeriana fauriei Briq.
山地のやや湿った草地に生えるオミナエシ科の多年草。特有の香りがあり,観賞用や薬用として栽培される。根には8%の精油が含まれ,吉草根(きつそうこん)と呼び,日本ではヨーロッパのワレリアナ根の代用品とする。精油は種々のセスキテルペンおよびモノテルペンを含み,特有の臭気があり,精神不安定やヒステリーの鎮静薬として用いられる。しかし,このワレリアナ根をとるヨーロッパ産のセイヨウカノコソウV.officinalisL.よりカノコソウの方が薬用としては優良である。また,中国では纈草(けつそう)の名で,この仲間の数種が民間薬として利用される。セイヨウカノコソウの根にはマタタビに似た効能があるとされ,ヨーロッパではのらネコやノネズミを退治するための餌に使われた。イギリスでは魔よけの霊草で,魔女が魔物を駆るときにもこれを用いたという。細長い地下茎を出し,根はひげ状。地上茎は直立し,高さ40~80cmとなる。葉は対生し,羽状に深く切れ込む。花は小さく,茎の先に集まって散房状につき,5~7月に咲く。花冠は淡紅色,直径3mm,花筒の片側が少しふくれ蜜腺がある。おしべは3本。果実には萼が変形した白色の羽状冠毛がある。北海道から九州,サハリン,朝鮮,中国に分布する。
カノコソウ属Valeriana(英名valerian)は北半球と南アメリカに200種以上が知られている。日本にはほかにツルカノコソウV.flaccidissima Maxim.があり,細長い走出枝を出し,花は白色まれに紅色で,4~5月に咲く。
執筆者:福岡 誠行+新田 あや
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
カノコソウ
北海道〜九州,東アジアの山地に自生し,また栽培されるオミナエシ科の多年草。茎は高さ50〜100cmになり,葉は対生し,羽状複葉となる。5〜7月,茎頂に散房花序をつけ,淡紅色の花を多数つける。花冠は径約3mm。地下茎や根を乾燥したものを吉草根といい,鎮静剤とする。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
カノコソウ
オミナエシ科の多年草。根は生薬として使用され、解熱鎮痛薬などに含有。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報