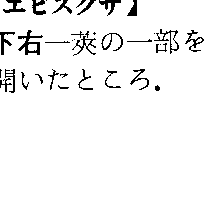改訂新版 世界大百科事典 「エビスグサ」の意味・わかりやすい解説
エビスグサ
oriental senna
sickle senna
Cassia tora L.
熱帯に広く野生状態で分布し,薬用に栽培もされるマメ科の低木性草本植物。日本では沖縄でみられる。同属のハブソウと混同され,種子ははぶ茶の原料とされる。高さ1mほどになり,全体に短毛を有する。葉は互生,通常3対の小葉からなる羽状複葉で,小葉は倒卵形,長さ2~3cm。花は黄色で放射状の5枚の花弁を有し,多くは2個が対をなして葉腋(ようえき)から出る。莢(さや)(豆果)は線形でやや扁平となり,長さ15~25cm,種子は多数で,長さ約5~8mm。種子は漢方の決明子(けつめいし)で,エモディンemodin,アロエエモディンaloeemodinなどの配糖体を含み,強壮,利尿,眼病に用いられる。また,血圧降下や抗菌作用も知られている。市販のはぶ茶の多くはハブソウではなく,エビスグサの種子である。全草は緑肥にも用いる。またC.obtusifolia L.の種子も決明子と呼ばれ,同様に利用される。
ハブソウC.occidentalis L.(英名coffee senna)はエビスグサにやや似ているが,羽状複葉は5~6対の小葉からなり,熱帯アメリカ原産の植物である。種子は漢方の望江南子(ぼうこうなんじ)で,エビスグサの種子と同様に利用される。
エビスグサが所属するカワラケツメイ属Cassiaは,熱帯を中心に約450種ほどを有するマメ科の大きな属で,薬用として有名なセンナをはじめ,ホソバセンナC.angustifolia Vahl.,ナンバンサイカチC.fistula L.,それにC.nodosa L.などの薬用植物を含むし,美しい花をつける種も多く,熱帯の公園や花壇にいくつかの種が栽植されている。高級木材として家具や細工,建築に利用されるタガヤサンも東南アジア大陸部に分布する本属の植物である。日本には一年草のカワラケツメイが分布する。
執筆者:堀田 満+新田 あや
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報