デジタル大辞泉 「アルコール」の意味・読み・例文・類語
アルコール(〈オランダ〉・〈英〉alcohol)
2 アルコール飲料。酒類。
[補説]書名別項。→アルコール
[類語](2)酒・
翻訳|alcohol
狭義では酒類の成分であるエタノール(エチルアルコール)をさすが、一般には広くアルコール類の総称として用いられる。炭化水素の水素原子をヒドロキシ基-OHで置換した化合物の総称で、一般式R-OHで示される。
[徳丸克己]
語源は、アラビア語でal-koh'l(粉状物質)に由来するが、当初は現在の意味のアルコールをさしていたものではない。その後アルコールということばの意味が変わり、酒を蒸留して燃えるものを得る操作を「アルコール化」というようになり、さらにこれから得られた留出物をアルコールとよぶようになった。これが、現在広く用いられる総称としてのアルコールとなったのは19世紀からである。
[徳丸克己]
構造から分類すると次のようになる。
(1)ヒドロキシ基の数が1個、2個、3個の場合をそれぞれ一価アルコール、二価アルコール、三価アルコールという。ヒドロキシ基が2個以上のものを多価アルコールという。また二価アルコールのうち、2個のヒドロキシ基が隣り合う炭素に結合しているものをグリコールという。
(2)ヒドロキシ基が結合している炭素原子の種類により、第一炭素原子に結合しているものを第一アルコール、第二、第三炭素原子に結合しているものを、それぞれ第二アルコール、第三アルコールという。
(3)分子内に二重結合または三重結合をもつものを不飽和アルコール、もたないものを飽和アルコールという。芳香族炭化水素の側鎖にヒドロキシ基の置換しているものは芳香族アルコールという。しかしベンゼン環に直接結合しているものはフェノールといい、アルコールとは区別している。
[徳丸克己]
骨格の炭化水素名の語尾-e(ン)を-ol(オル)に変える正式の命名法と、慣用では炭化水素基名にアルコールをつける方法とがある。たとえばCH3OHは、前者では、炭化水素名methane(メタン)からmethanol(メタノール)となり、後者では、メチル基-CH3にアルコールをつけ、メチルアルコールと名づけられる。二価および三価アルコールは、語尾を-diol(ジオール)および-triol(トリオール)と変える。
[徳丸克己]
天然には酒類に含まれるエタノールや、多価アルコールである糖や、植物の精油中に含まれるテルペン系のアルコールのようなものがあるが、多くはカルボン酸と縮合したエステルの形で存在する。
[徳丸克己]
かつて、エタノールはデンプンや糖蜜(とうみつ)などの発酵により多量に製造されていた。現在でも飲料用のエタノールは発酵法により製造されているが、工業用のアルコール、とくに炭素数の少ない、いわゆる低級アルコールは石油を原料として製造されている。
(1)メタノールの製法 一酸化炭素と水素から約300℃、200~300気圧、酸化亜鉛、酸化クロム触媒あるいはさらにこれに酸化銅を加えた触媒上の反応により製造される。原料の気体混合物は、天然ガスのメタンの部分的酸化あるいは石油の炭化水素をニッケル触媒上で水蒸気と処理して製造される合成ガスを用いる。
CO+2H2 CH3OH
CH3OH
(2)エタノールの製法 現在工業的には石油から得られるエチレンを酸の存在下で水と反応させて製造されている。
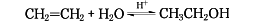
(3)2-プロパノール(イソプロピルアルコール)の製法 これもエタノールと同様に石油から得られるプロピレンを酸の存在下に水と反応させて製造している。
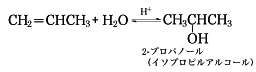
(4)1-ブタノール(n-ブチルアルコール)の製法 石油からのエチレンの酸化で得られるアセトアルデヒドあるいは石油からのプロピレンを原料として製造されている。
アセトアルデヒドを原料とするときは、これをアルカリ水溶液中でアセトアルドールとし、これを脱水してクロトンアルデヒドとし、その水素化により製造する。
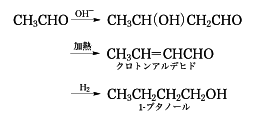
プロピレンからはまずオキソ法により一酸化炭素および水素とコバルト系の触媒上百数十℃、200~300気圧で反応させてブチルアルデヒドをつくる。
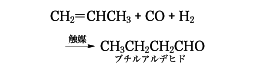
生成したブチルアルデヒドを水素化して1-ブタノールとする。
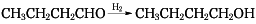
(5)多価アルコールの製法 たとえばグリコールのもっとも簡単な構造であるエチレングリコールは、エチレンを酸化して酸化エチレンとし、これを加水分解して製造する。
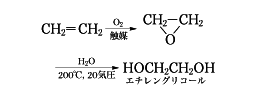
これをフタル酸と脱水縮合させてポリエチレンテレフタレート系合成繊維の製造に利用する。また不凍液としても用いられる。
また二価アルコールのプロピレングリコールCH3CH(OH)CH2OHは、(4)と同様の過程でプロピレンから製造され、ポリエステル系合成繊維や不凍液として用いられる。
(6)不飽和アルコールの製法 炭素鎖に不飽和結合を有するものを不飽和アルコールといい、アリルアルコールCH2=CHCH2OHが代表的であるが、これはプロピレンから製造され、さらにグリセリン、グリンドールなどを製造する。
このほかにもプロピレンおよびブテンを原料としたオキソ法により、アルデヒドを経由して各種のアルコールが製造されている。
[徳丸克己]
一価アルコールのうちメタノール、エタノール、プロパノールおよびブタノールは、水と任意の割合でよく混じり合う。また一般に低級アルコールは水に溶けやすいが、ペンタノールよりも炭素数が多いアルコールは水には溶けにくい。アルコールにはヒドロキシ基があり、これは水と水素結合をつくって混ざりやすい親水的な性質がある。他方、炭素鎖は水とは混ざらず疎水的である。炭素鎖の短いアルコールでは、親水性が強く現れて水によく溶けるが、炭素鎖が長くなると疎水性が強くなり、そのために水と混ざりにくくなる。また液体のアルコールでは、アルコール分子の間でヒドロキシ基が水素結合を形成して安定化するので、同じ炭素数の炭化水素に比べてはるかに沸点が高い特徴がある。
[徳丸克己]
アルコールのヒドロキシ基は、弱いが酸としての性質がある。金属ナトリウムの小片を過剰のメタノールやエタノールに加えると、激しく水素を発生して溶解し、ナトリウムメトキシドあるいはナトリウムエトキシドを生成する。
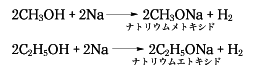
アルコールを塩酸や臭化水素酸と処理すると、アルコールのヒドロキシ基が塩素や臭素で置換されたハロゲン化アルキルが生成するが、同時にアルコールから水が脱離した形のアルケンも生成する。

アルコールから1分子の水をとる脱水反応は、アルケンの合成上重要である。たとえばエタノールでは、濃硫酸と加熱すると、140℃程度の反応ではジエチルエーテルが生成し、170℃程度の反応ではエチレン(アルケンの代表的なもの)が得られる。

アルコールを工業的に脱水するには、アルコール蒸気を加熱したアルミナ触媒上を通す。
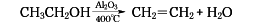
第一および第二アルコールは酸素をはじめ種々の酸化剤により容易に酸化されて、それぞれアルデヒドおよびケトンを生成し、アルデヒドはさらにカルボン酸に酸化される。
工業的には、たとえば、メタノール蒸気を加熱した銅などの触媒上を通してホルムアルデヒドに酸化し、これはフェノール樹脂などの原料として用いる。
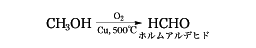
酢酸はかつては、もっぱらエチレンの酸化により生成するアセトアルデヒドの酸化により製造されてきたが、近年はメタノールをロジウム触媒の存在下、一酸化炭素と反応させて製造され、この方法は「メタノール酢酸法」とよばれる。

現在メタノールは溶剤として、また酢酸などの合成原料として多量に製造されている。
2-プロパノールの蒸気を加熱した酸化亜鉛触媒上を通すと、脱水素がおこり、アセトンが得られる。
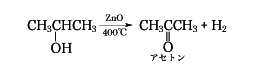
またアルコールをカルボン酸と酸触媒存在下に加熱するとエステルが得られる。
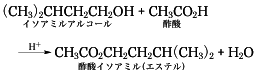
エステルは芳香性のものが多い。
[徳丸克己]
アルコールのうち炭素数の少ないものを低級アルコール、炭素数の6個以上のものを高級アルコールという。低級アルコールは現在石油を原料として製造されるが、高級アルコールは天然から得ることが多い。かつて欧米諸国は照明用の油を得るために多量のクジラを捕獲してきたが、鯨ろうの中には高級アルコールと高級カルボン酸のエステルが含まれている。したがって、このようなエステルを加水分解すると、高級カルボン酸と高級アルコールが得られる。たとえば、鯨ろう中の炭素数16のアルコール、すなわちヘキサデカノール(セチルアルコール)と炭素数16のカルボン酸、すなわちヘキサデカン酸(パルミチン酸)のエステルからは、炭素数16のカルボン酸と炭素数16のアルコールが得られる。
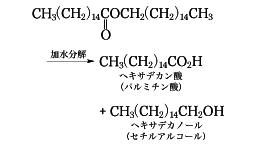
クジラの油の加水分解により炭素数18のオクタデカノール(ステアリルアルコール)も得られ、またミツバチがつくるみつろうからは炭素数30のアルコール、すなわちトリアコンタノール(ミリシルアルコール)CH3(CH2)28CH2OHが得られる。
多くの天然の油脂は高級カルボン酸のグリセリンエステルとして存在する。これを加水分解して高級カルボン酸とするかわりに、水素により接触還元すると、エステルのカルボン酸の部分がアルコールに還元される。たとえば牛脂などの接触還元により炭素数16と18のアルコールが得られる。やし油の接触水素化により炭素数8、10、12、14のアルコールが得られる。
これらの高級アルコールは天然物からだけでなく石油を原料として製造され、アルキル硫酸エステルナトリウム塩CH3(CH2)nCH2OSO2O-Na+の形の洗剤の原料とし、また可塑剤として用いられる。
[徳丸克己]
『大須賀篤弘・東田卓著『基礎 有機化学』(2004・サイエンス社)』▽『水野一彦・吉田潤一編著『有機化学』(2004・朝倉書店)』▽『日本化学会編『実験化学講座14 有機化合物の合成2』第5版(2005・丸善)』
水酸基OHを有する有機化合物の総称の一つ。すなわち,水酸基が結合している炭素が脂肪族鎖式炭化水素,脂環式炭化水素に属する場合にアルコールと呼ぶ。ベンゼン核のような芳香核に直接水酸基が結合したものはフェノールと総称され,アルコールとは区別される。エチルアルコールC2H5OHを単にアルコールと略称することが多い。アルコールという名はアラビア語に由来し,alは定冠詞,kuḥlは微粉末を意味する。古代エジプト以来,ある種の黒色微粉末が顔料として用いられ,これをアルコールと呼んでいた。この微粉末をつくるのに昇華法が用いられていたが,これから転じ,やがて酒を蒸留して得られるものもアルコールと呼ばれるようになった。アルコールの語が現在と同じ意味で用いられるようになったのは19世紀以後である。
アルコールは一般式R-OH(Rは脂肪族残基)であらわされる。分子中の炭素原子数の多いか少ないかにしたがって,少ないもの(ふつう炭素原子数5以下)を低級アルコール,多いものを高級アルコールと呼ぶ。また,水酸基が1個,2個,3個などのアルコールは,それぞれ一価アルコール,二価アルコール(グリコール),三価アルコールなどといい,2価以上のものを多価アルコールと呼ぶ。一方,水酸基が第一炭素に結合しているアルコール(RCH2OH)を第一(または一級)アルコールと呼び,第二,第三炭素に結合しているものを第二アルコール,第三アルコールという。脂肪族残基Rが炭素の二重,三重結合を含む不飽和炭化水素の基である場合には不飽和アルコールという。芳香族化合物の側鎖の飽和炭素原子に水酸基のついた化合物もアルコールで,芳香族アルコールと呼んでいる。
個々のアルコールの慣用名は,一価アルコールでは水酸基と結合しているアルキル残基の名称の後に,アルコールを付記して,たとえばメチル基の場合をメチルアルコール,エチル基ではエチルアルコールのように命名する。IUPAC命名法では,水酸基に対して〈オールol〉という語尾を用い,たとえばメタンCH4に対応するCH3OHをメタノール,エタンC2H6に対応するアルコールはエタノールと命名する。二価アルコールは語尾をジオール,三価アルコールはトリオールとする。
自然界にはエステルとして存在することが多く,遊離したアルコールは少ない。低級の一価アルコールは植物精油中に,高級の一価アルコールは動植物の蠟として産出する。三価アルコールであるグリセリンは高級脂肪酸とエステルをつくり,動植物の油脂として広く分布している。不飽和アルコールはテルペンとして広く天然に存在する。たとえば,バラ油中のゲラニオールやスズランの香りをもつリナロールなどがある。
一般に無色の液体または固体(高級アルコール)である。鎖式の1価の低級アルコールは揮発性で刺激臭があり,水とよく混じるが,炭素原子数が増すと不揮発性無臭,炭素数が6個以上になると不溶性となる。多価アルコールは水溶性で,一般に甘い。飽和一価アルコールにおいて,エチルアルコールのみが無毒で,他のものは有毒であるのはおもしろい。水を含まないアルコールに金属ナトリウムを加えると,水酸基の水素がナトリウムに置換されてアルコキシドができる。酸と反応してエステルを生ずる。酸化すると,第一アルコールRCH2OHはアルデヒドRCHOを経てカルボン酸RCOOHになり,第二アルコールRR′CHOHはケトンRR′C=Oになる。第三アルコールは一般に酸化されにくいが,強い酸化剤では分解して炭素数の少ない酸またはケトンとなる。不飽和結合に直接水酸基がついた不飽和アルコールは不安定な場合が多い。
炭素数1~6個の鎖式飽和一価アルコールは,炭水化物やタンパク質の発酵(アルコール発酵),エチレンやプロピレンなど石油製品を原料とする合成法により工業的に製造されている。アルコール一般の化学的合成は,ハロゲン化合物の加水分解,アルデヒドやケトンの還元,グリニャール反応,その他によって行われる。
執筆者:中井 武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
狭義には,エチルアルコールをさし,広義には,アルコール類を総称する.
【Ⅰ】エチルアルコールの略称.エチルアルコールは人類の酒の歴史とともに古くから知られており,その組成は,17世紀にJ.L. Gay-Lussac(ゲイ-リュサック)やJ.B.A. Dumas(デュマ)により決定された.アルコール類のうちではもっとも一般的で,もっとも広い用途をもつエチルアルコールを単にアルコールと称することが多い.【Ⅱ】炭化水素の水素原子をヒドロキシ基で置換した化合物で,一般式ROHで表される.ただし,ヒドロキシ基がベンゼン環の炭素に直接結合したフェノール類はアルコール類には入らない.ヒドロキシ基の数により,一価アルコール,二価アルコール,三価アルコールなどとよび,また,ヒドロキシ基が結合している炭素原子の種類により,第一級アルコールR1CH2OH,第二級アルコールR1 R2CHOH,第三級アルコールR1 R2 R3COHに分類される.芳香族炭化水素の側鎖にヒドロキシ基の置換しているものは芳香族アルコールという.IUPAC命名法では,炭化水素名の語尾の-eを-olにかえ,メタンに対応するCH3OHをメタノールと命名する.二価および三価アルコールは,それぞれ語尾をジオール(-diol),トリオール(-triol)にかえる.普通には慣用名が用いられ,ヒドロキシ基と結合しているR基名の後にアルコールを付記して,“メチルアルコール”のように命名する.アルコール類は,多くはエステルとして自然界に存在する.一価アルコールの低級のものは植物精油中に,高級のものは動物,植物のろう中に存在する.三価アルコールのグリセリンは高級脂肪酸エステルとして油脂中に,ペンチトールやヘキシトールのような多価アルコールも動物,植物界に存在する.また,天然有機化合物にはヒドロキシ基をもつものが多い.多数の製法が知られている.
(1)メタノールは一酸化炭素と水素の高圧接触反応によって工業的につくられる.
(2)低級の飽和一価アルコール(C2~C5)は炭水化物やタンパク質の発酵によって生成する.
(3)高級のものは天然産エステルの加水分解によっても得られる.
(4)オレフィンの水和反応によって工業的に製造できる.
(5)第一級アミンに亜硝酸を作用させる.
(6)アルデヒドやケトンの接触還元により,それぞれ第一級アルコールおよび第二級アルコールが得られる.
(7)脂肪酸エステルを水素化アルミニウムリチウムでアルコールにまで還元する.
(8)複雑な構造をもつアルコール類は,アルデヒド,ケトン,エステルあるいはオキシドとグリニャール試薬との反応によって合成することができる.
低級の一価アルコールは特有の味と香気をもつ液体で,水とよくまざるが,高級になるほど溶解度が減少し,C5 以上になるとほとんど水に溶けない.多価アルコールは水溶性の液体または固体で,多くは甘味をもつ.化学的には中性の化合物で,種々の無機塩と付加物をつくることがある.ヒドロキシ基の水素原子は金属と置換してアルコキシドを生じ,とくに低級の一価アルコールのアルコキシドは種々の反応の試薬として使われる.アルコールのヒドロキシ基は酸と脱水縮合すればエステルを,ハロゲン化水素またはハロゲン化リンと反応させればハロゲン化物を生成する.酸化すると,第一級アルコールはアルデヒドを経てカルボン酸となり,第二級アルコールはケトンを生成する.強酸の存在下に加熱脱水するとオレフィンを生じる.アルコール類の各種ヒドロキシ基は赤外線吸収スペクトルによって容易に同定できる.すなわち,3650~3200 cm-1 のO-Hの伸縮振動,1410~1050 cm-1 のC-O伸縮振動,およびO-H変角振動による特性吸収から,第一級,第二級,および第三級アルコールを区別することができる.化合物の同定は,アシル化,エステル化,ウレタン化により結晶性の誘導体に導いて行われる.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…単にアルコールとよばれることが多く,またエタノールethanolともいわれる。化学式C2H5OH。…
…一つは環境や器具器材などが汚染されたときに使用するもので,他は創傷などに際して感染を防ぐために用いられる殺菌剤である。前者のものとしては塩素や塩素化合物,石炭酸(フェノール),ヨウ素化合物が代表的であり,後者にはヨードチンキなどヨウ素化合物,アルコールが代表的であるが,両者に共通して用いられるものも少なくない。(1)塩素および塩素化合物 殺菌剤の発展は微生物学の進歩を語らずには成り立たない。…
※「アルコール」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新